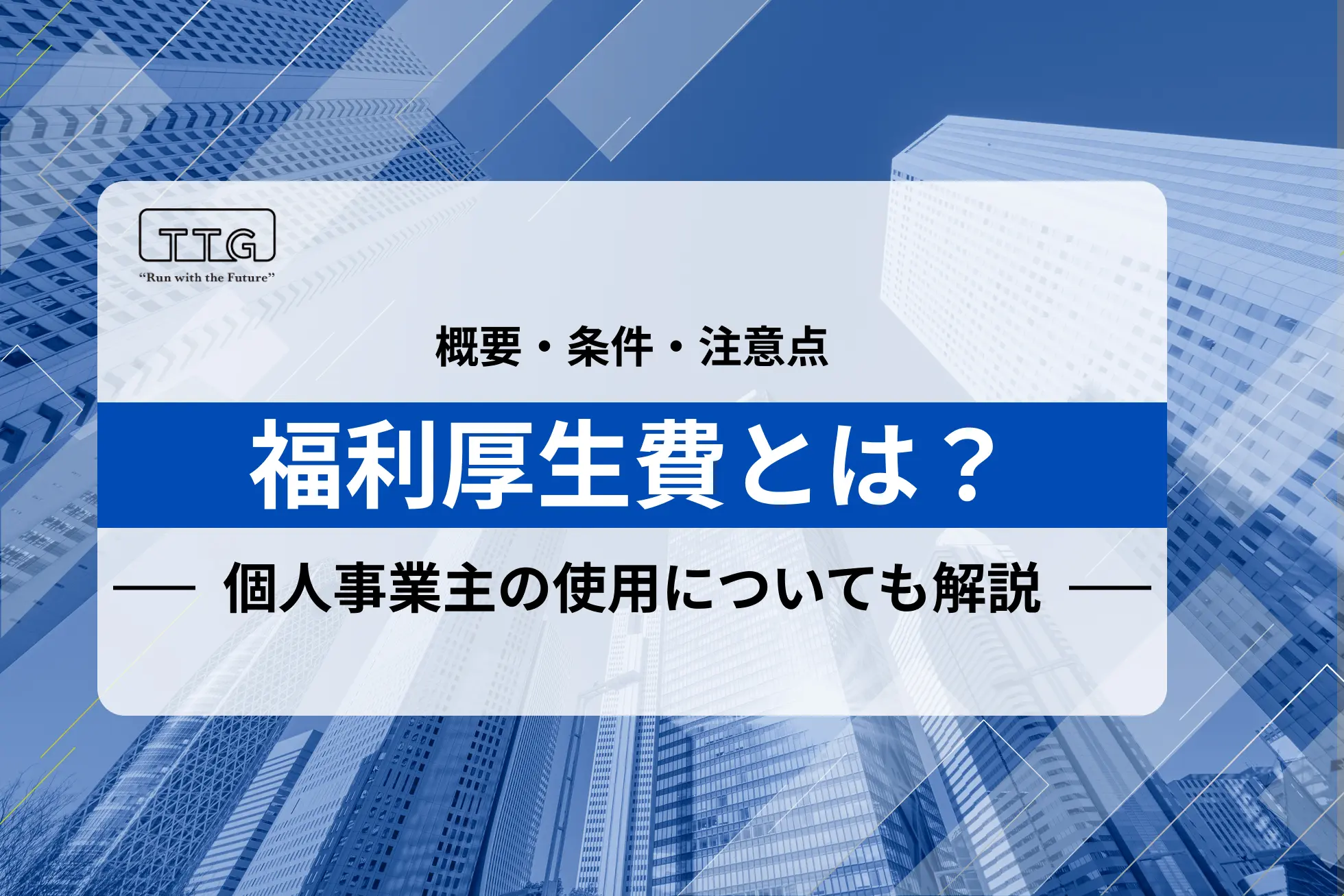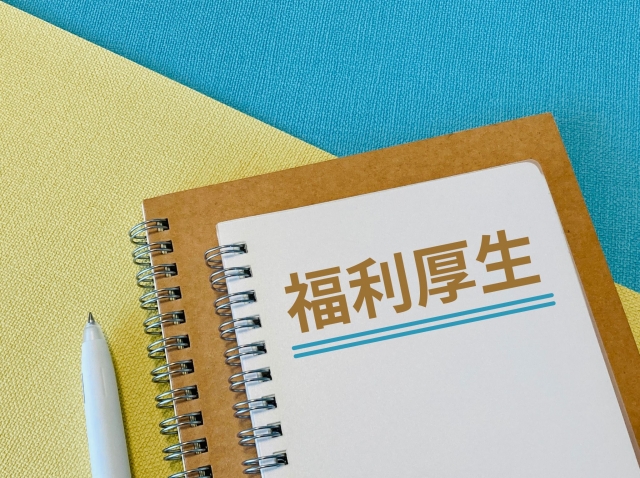Category
こんにちは。無人決済店舗システムを提供しているTOUCH TO GO 編集部です。
福利厚生費は従業員の安定した暮らしを確保するだけでなく、企業の節税にも大きく関わる重要な経費です。
本記事では、福利厚生費の概要や法定福利費と法定外福利費の違い、具体例や個人事業主での扱い方について解説しています。
福利厚生費を正しく理解すると従業員が安心して長く働けるうえ、無駄な税金を支払うリスクを防げます。
ぜひ最後までご覧ください。
監修者プロフィール

2019年に株式会社TOUCH TO GOを設立。無人決済店舗システムを提供し、次世代型小売の拡大に取り組んでいる。
目次
福利厚生費とは?
福利厚生費とは、企業が従業員に対して、給与や賞与とは別に提供するサービスや費用を指しています。
従業員の安定した生活やモチベーションの向上を目的とした施策の総称で、働き方改革に伴い、離職の防止にも効果が期待されています。
以下の点について、それぞれ解説します。
- 法定福利費と法定外福利費の違い
- 福利厚生費の主な具体例
法定福利費と法定外福利費の違い
法定福利費は、企業が従業員に提供すべきと法律で定められている保険の費用です。
具体的には以下の6つで、企業は各保険料の一部または全額を負担します。
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 介護保険
- 雇用保険
- 労災保険
- 子ども・子育て拠出金
一方、法定外福利費は企業が独自で提供する福利厚生にかかる費用で、一般的に「福利厚生費」と呼ばれるものです。
これらは企業の判断で設定できるため、住宅手当や通勤手当、慶弔見舞金、社員旅行費など多岐にわたります。
福利厚生費の主な具体例
福利厚生費となるものは幅広くあり、主な具体例は次のとおりです。
- 通勤手当
- 住宅手当
- 家族手当
- 健康診断費用
- 慶弔見舞金
- 育児・介護支援費用
- 残業時の食事代
- 外部の福利厚生サービス費
- 社員旅行の費用
- 忘年会や新年会の費用
- 従業員の食事補助
これらが福利厚生費として認められるためには、全従業員を対象としていることや、金額が社会通念上妥当であることなどの条件を満たす必要があります。
関連記事>>福利厚生にはどんな種類がある?企業が導入すべき福利厚生の種類と内容を詳しく解説
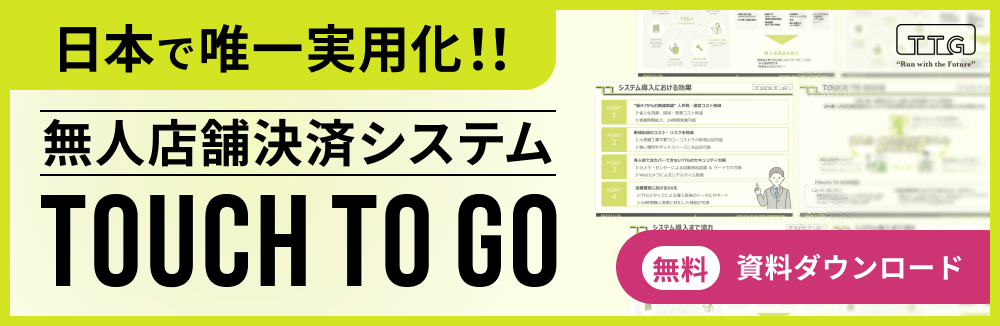
TOUCH TO GO の 無人決済店舗システムを導入すると、外出せずに必要なものをすぐ手にできるため、福利厚生として注目されています。
社内コンビニの設置をご検討中の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/福利厚生費に認められる条件と注意点
福利厚生費に認められる条件と注意点
費用が福利厚生費として認められるためには、いくつかの条件があります。
以下の点について、それぞれ解説します。
- 全従業員が対象
- 社会通念上相当とされる金額とは
- 福利厚生費と損金算入要件の関係
全従業員が対象
福利厚生費として認められるためには「機会の平等性」が必要です。
これはすべての従業員が公平に福利厚生制度を利用できることを意味しています。
そのため、一部の従業員しか利用できない食堂や、保養所の利用代金などは福利厚生費として認められないことになっています。
社会通念上相当とされる金額とは
福利厚生費の多くの項目では具体的な上限金額は定められていません。
しかし「社会通念上、著しく高額でないもの」という基準があります。
例えば、社員旅行は4泊5日以内で、参加人数が対象者全体の50%以上であることなどの条件を満たしつつ「社会通念上、妥当な金額」であることが求められます。
忘年会や新年会などのイベントも、全従業員を対象に行うこと、企業の負担が一律であることや常識的と思われる範囲の金額であることが条件です。
そのため、あまりにも高額な場合は福利厚生費として認められない可能性があります。
福利厚生費と損金算入要件の関係
福利厚生費は、一定の条件を満たせば経費として計上されて損金扱いになる場合があります。
そのため、課税対象となる所得を減らし、法人税の負担を軽減できるのが特徴です。
損金算入の主な要件は次のとおりです。
- 全従業員を対象としていること
- 現金支給でないこと
- 社会通念上妥当な金額であること
例えば、健康診断は全従業員が受診すること、全員の費用を企業が負担すること、内容が健康管理上必要と思われるものであることを条件に、福利厚生費として認められるため損金としての算入が可能です。
適切に要件を満たすと節税効果を得られます。
関連記事>>「あると嬉しい福利厚生」ランキングTOP10|男女別の傾向も解説
福利厚生費の金額基準と上限に関する知識
福利厚生費として認められるためには「金額の妥当性」が重要な要件の1つです。
例えば、数名の従業員で1泊2日の社内旅行をした場合、何百万円も支出するような場合は、金額の妥当性がないと判断されます。
福利厚生費の金額基準や上限などについて、以下のとおり解説します。
- 福利厚生費はいくらまで認められるのか
- 福利厚生費の飲食代ルールとは
福利厚生費はいくらまで認められるのか
福利厚生費としての明確な上限額は法律で定められていませんが、種類によっては非課税限度額が設定されています。
具体例は以下のとおりです。
|
通勤手当(公共交通機関を利用する場合):1ヶ月当たり最高15万円まで非課税 住宅手当:賃貸料相当額の50%未満の場合、企業負担分は非課税 社員旅行:1人あたり年間10万円程度までが目安 |
健康診断費用は一般的に7,500円〜12,000円程度で特に上限はありませんが、PET検診などの高額なオプションは経費として認められない可能性があります。
福利厚生費の飲食代ルールとは
福利厚生費における飲食代に関しては、食事補助の場合「1人あたり月額3,500円以下(税抜)」という金額が設定されています。
この金額を超える部分は「給与所得」として扱われる可能性があるのです。
また、飲食代が福利厚生費として認められるためには「従業員が食事代の50%以上を負担していること」が条件とされています。
例えば、月に5,000円の食事をして、そのうち2,500円を従業員が負担している場合、差額分は福利厚生費としての計上が可能です。
残業や宿直時の食事代について、現金で食費を支給する場合は「1食あたり300円以下(税抜)」という基準があります。
関連記事>>会社の魅力を高める福利厚生とは?ユニークな福利厚生7選も紹介!
個人事業主が福利厚生費を使う際のポイント
個人事業主が福利厚生を使う場合、一定の条件を満たせば計上できます。以下の内容について、それぞれ見ていきましょう。
- 個人事業主でも福利厚生費を計上できる条件
- 個人事業主本人や家族を対象にできるか
個人事業主でも福利厚生費を計上できる条件
個人事業主が福利厚生費で処理するためには、家族以外の従業員を雇用していることが必要です。
具体的には以下の条件を満たす必要があります。
- 賃金ではなく、換金性に欠けるものや物品などの選択ができないものであること
- 全従業員に平等に適用されること(機会の平等性)
- 社会通念上、妥当と思われる金額の範囲内であること
これらの条件を満たせば、個人事業主でも従業員向けの福利厚生費を経費として計上できます。
個人事業主本人や家族を対象にできるか
原則として、個人事業主本人や家族(専従者)に対する支出は福利厚生費として計上できません。
福利厚生費はあくまで従業員の慰安を目的としているため、1人で事業を営んでいる場合や家族を従業員としている場合は計上できない場合が多いと言われています。
ただし、家族以外の従業員が在籍している場合で、社員旅行や懇親会など従業員の慰安を目的としたイベントに個人事業主本人や家族(専従者)が参加する場合は「社会通念上、妥当」と認められる金額であれば福利厚生費として計上可能です。
まとめ
福利厚生費の概要や法定福利費と法定外福利費の違い、具体例や個人事業主での扱い方を解説しました。
福利厚生費は、従業員の安心感や働きがいを支えると同時に、企業にとっても大きなメリットをもたらす重要な経費です。
正しい知識を持って適切に運用すると、人材の定着や節税効果が期待できます。
今回紹介した内容を参考にして、自社に合った福利厚生の仕組みを見直し、より働きやすい環境づくりに役立てましょう。
TOUCH TO GO の 無人決済店舗システムを導入すると、外出せずに必要なものをすぐ手にできるため、福利厚生として注目されています。
社内コンビニの設置をご検討中の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/