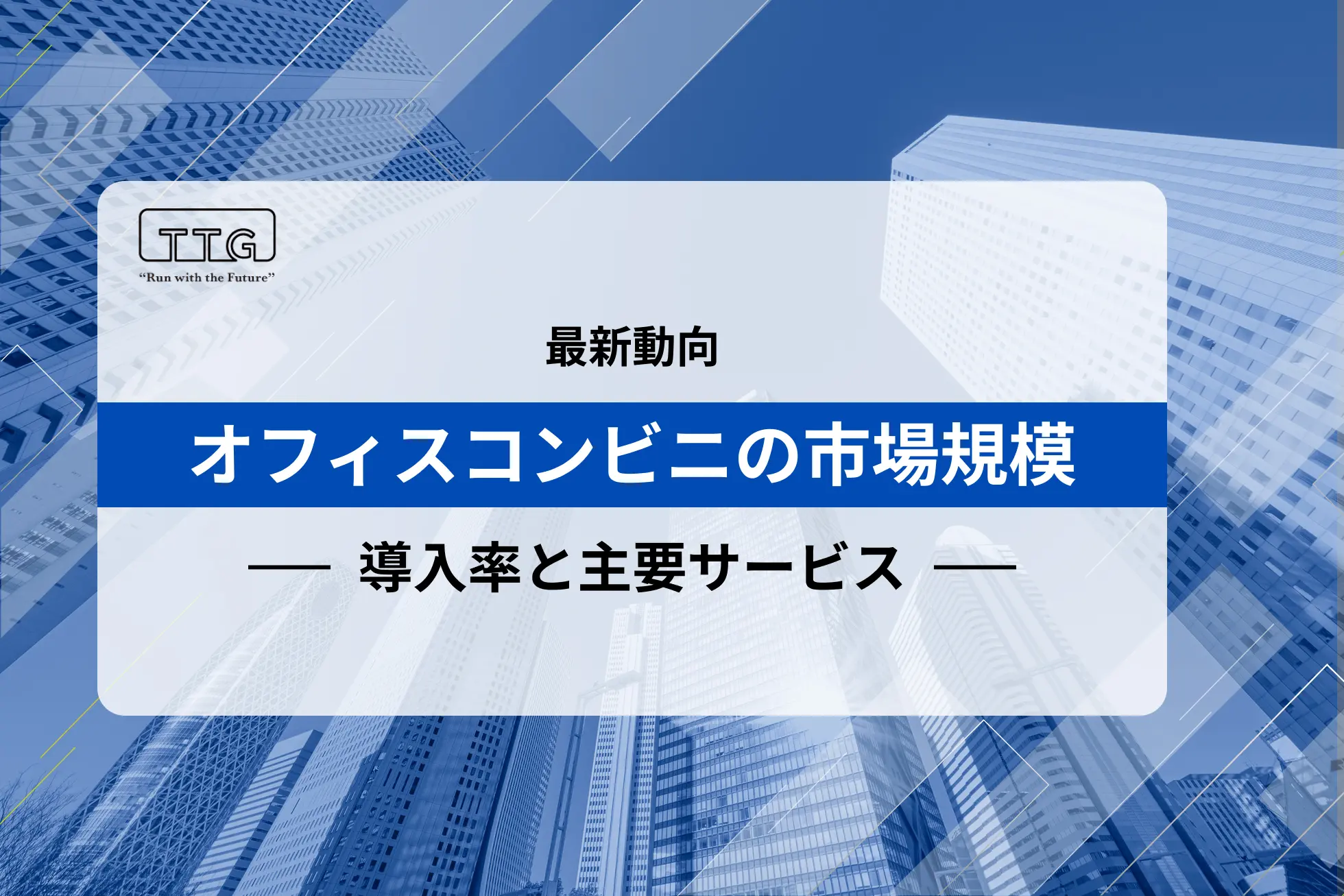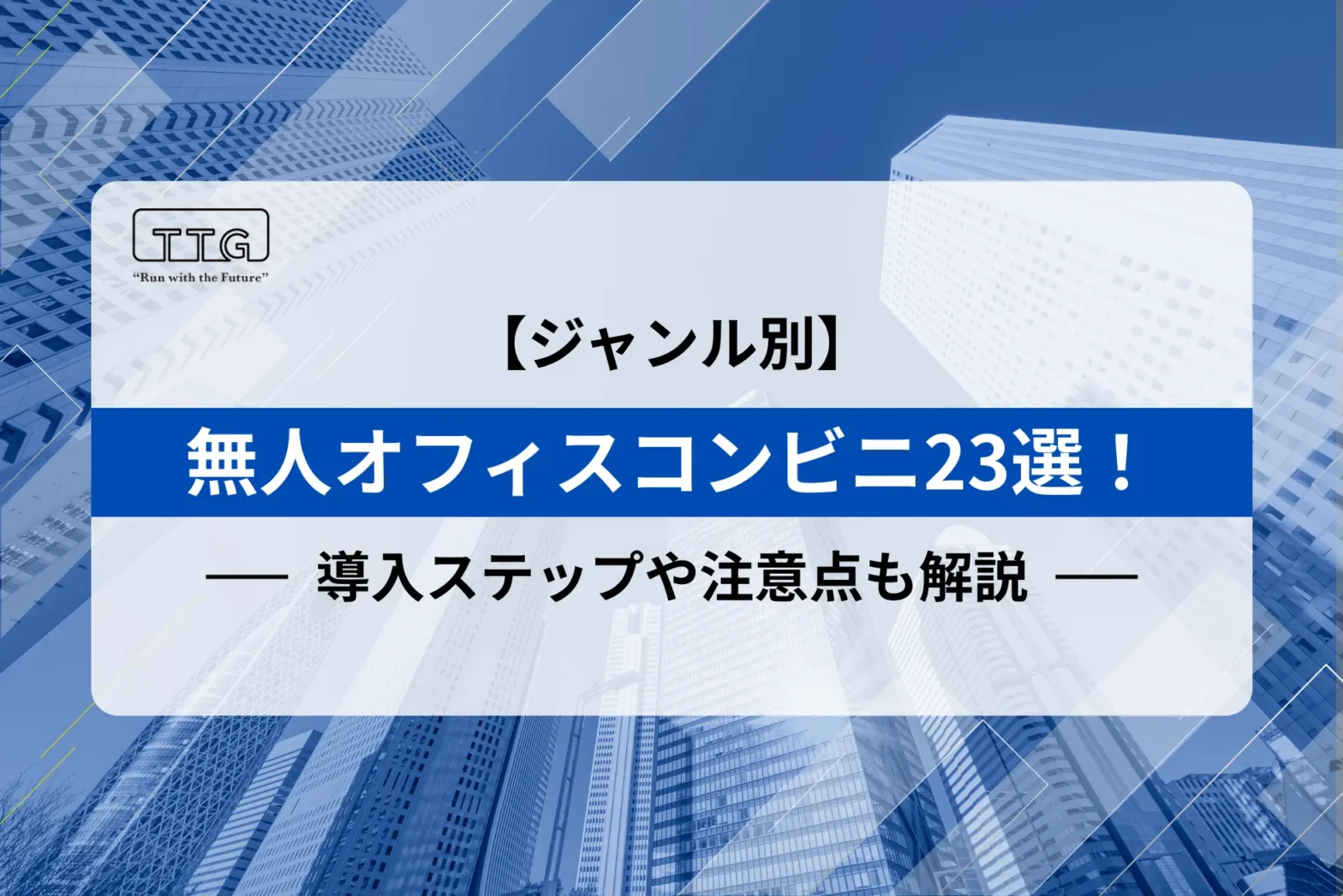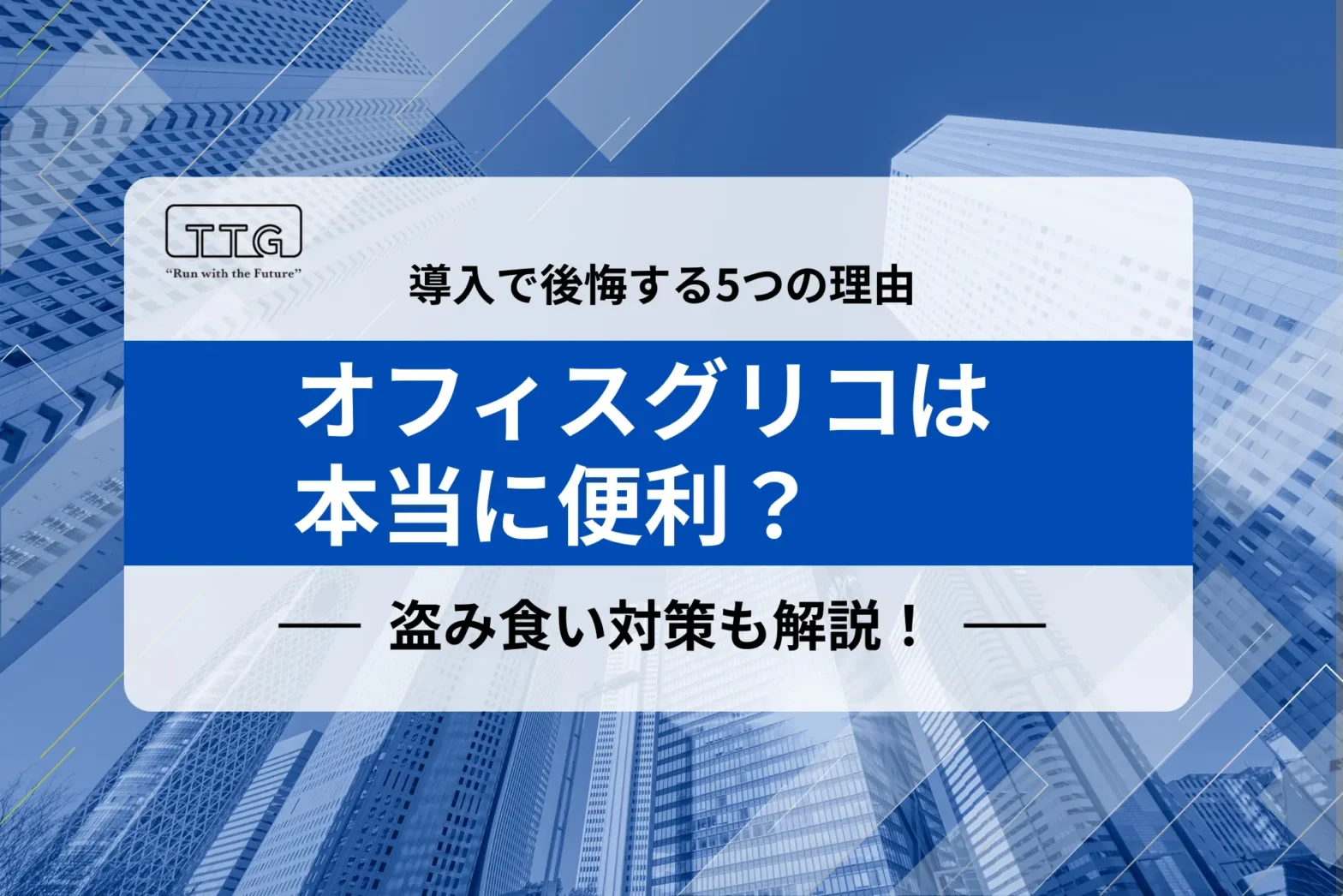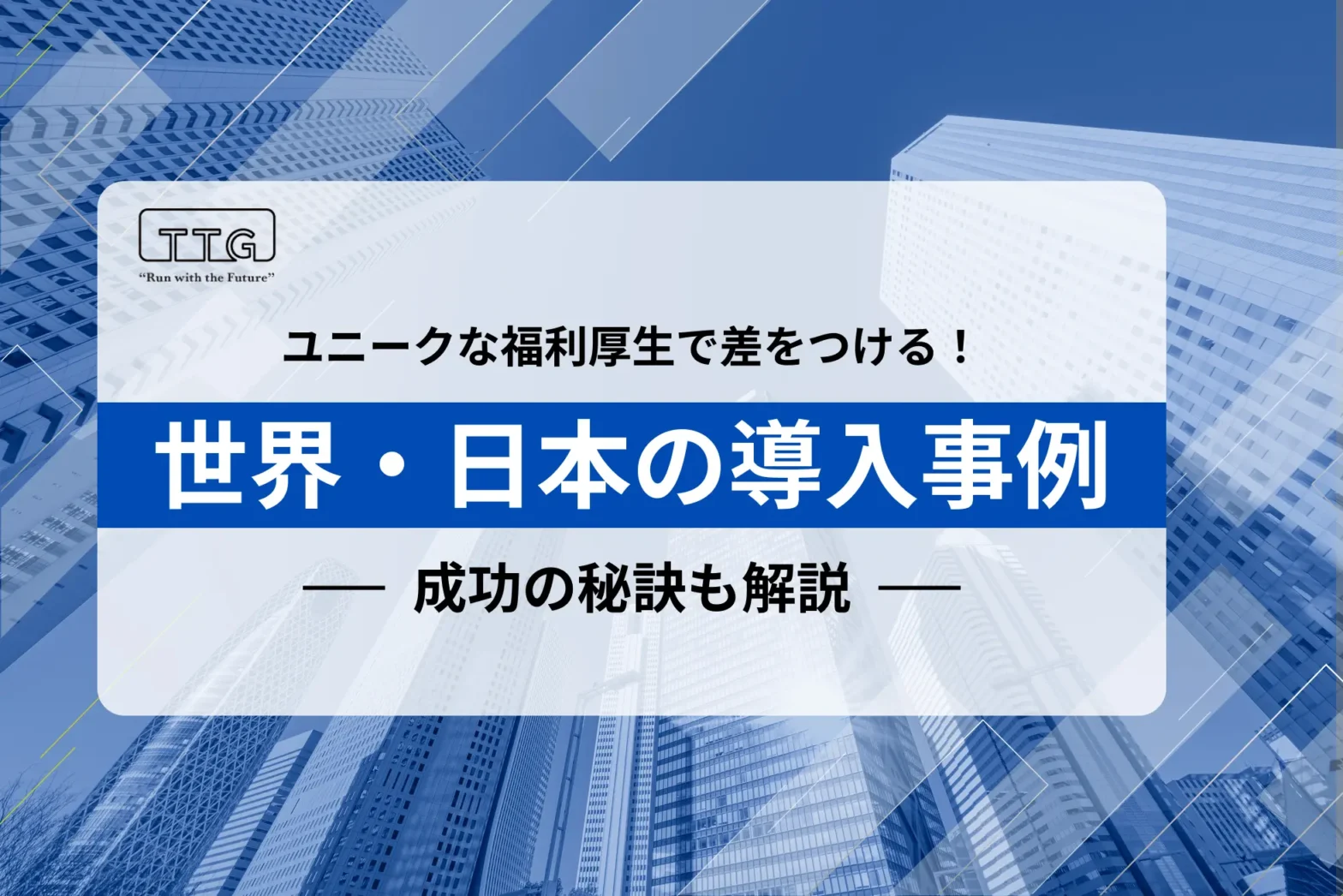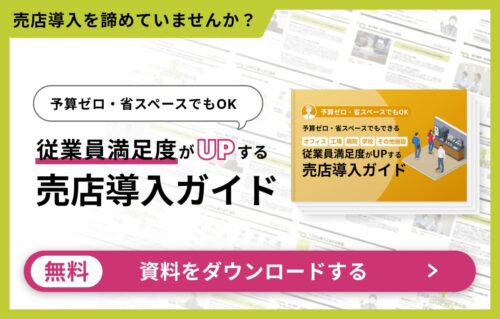Category
こんにちは。無人決済店舗システムを提供しているTOUCH TO GO 編集部です。
オフィスコンビニの市場規模は年々拡大しており、今や福利厚生の新定番と言われています。
働き方改革や社員食堂の減少、健康経営の推進などの時代背景の中で「どのくらいの規模で成長しているのか?」「導入企業はなぜ増えているのか?」と気になる方も多いはずです。
本記事では、オフィスコンビニの市場規模と成長背景、導入率と利用実績、従業員の利用状況と満足度データ、サービスの比較、導入する際の注意点について解説しています。
オフィスコンビニを導入したい方は、ぜひ最後までご覧ください。
監修者プロフィール

2019年に株式会社TOUCH TO GOを設立。無人決済店舗システムを提供し、次世代型小売の拡大に取り組んでいる。
目次
オフィスコンビニの市場規模と成長背景
オフィスコンビニ市場は着実に成長を続けており、働き方改革や健康経営への意識の高まりをきっかけに導入する企業が増えています。
以下の内容について、それぞれ解説します。
- 国内市場の規模と成長トレンド
- 注目される背景と社会的ニーズの変化
国内市場の規模と成長トレンド
コンビニ業界全体では、2024年の市場規模が13兆円弱となっており、その中でオフィスコンビニは新たな成長分野として注目されています。
参考:経済産業省 商業動態統計速報(2025年2月)P7 コンビニエンスストア販売額・前年(度、同期、同月)比増減率及び店舗数
2020年以降はコロナ禍の影響により、在宅ワークの増加でオフィス街の店舗売上は減少しました。
コロナ禍が落ち着いた現在、出社するスタイルに戻す企業が増えており、オフィスコンビニの需要も回復傾向にあります。
特に、マイクロマーケット(小さな商圏)への注目が高まっており、オフィスをはじめ学校や病院などの限定された空間での無人コンビニ展開が進んでいます。
また、社員食堂や売店の減少も市場拡大の要因となっており、厚生労働省の調査によると、2018年度に全国で5,495施設あった社員食堂が2022年度には4,958施設まで減少しているのです。
参考:
注目される背景と社会的ニーズの変化
オフィスコンビニが注目される背景には、従業員の満足度向上を目指す企業の増加があります。
近年、食に関する福利厚生に力を入れる企業が増加しており、従業員の健康促進や満足度の向上、さらに採用力の強化や離職の防止にもつながると期待されています。
社内コミュニケーションの課題を抱える企業が8割以上という調査結果もあり、オフィスコンビニは休憩時間に自然と人が集まる場として、コミュニケーション活性化の役割も担っているのです。
出典:
PR TIMES 8割以上の企業が社内コミュニケーションに課題あり。具体的な課題は「社員の参加意識の醸成」が最多。効果があった施策1位は「飲み会」
コロナ禍を経てオフィスの小規模化が進む中、省スペースで設置できるオフィスコンビニは、限られたスペースでも導入しやすい福利厚生として評価されています。
社会全体としても「モノ」から「心の豊かさ」への価値観の変化や、多様な働き方に対応したサービスへのニーズが高まっており、オフィスコンビニはこうした社会的ニーズの変化に応える形で発展しています。
関連記事>>オフィスコンビニを導入する際のポイント・注意点|おすすめ5選も紹介
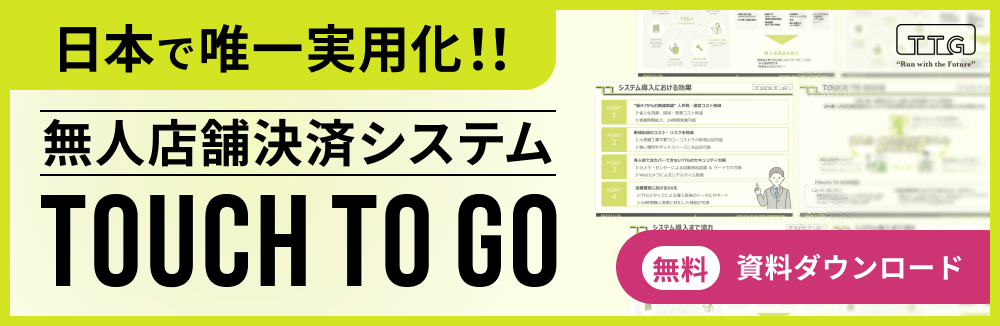
オフィスコンビニの増加に伴い、TOUCH TO GO の 無人決済店舗システムを導入する企業が増えています。
オフィスコンビニの無人店舗決済をご検討中の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/
オフィスコンビニの導入率と利用実態
株式会社リビングくらしHOW研究所と株式会社サンケイリビング新聞社が実施した調査によると、職場にオフィスコンビニが導入されていると回答した人は全体の約24%でした。
出典:PR TIMES データ&ランキング「フォーカスリサーチ」導入が進む「オフィスコンビニ」をリサーチ
導入率のトップは「オフィスグリコ」で、多くの企業に採用されています。
導入の主な理由は次のとおりです。
- 手軽にお菓子やドリンクなどを購入できる
- 設置・導入費用が無料・安い
- 設置スペースが狭くても大丈夫
- 電子マネーやキャッシュレス決済に対応
出典:PR TIMES データ&ランキング「フォーカスリサーチ」 導入が進む「オフィスコンビニ」をリサーチ
近年は福利厚生を強化する企業が増えており、その一環としてオフィスコンビニの導入が注目されています。
特にコロナ禍を経て出社率の低下に直面している企業にとって、オフィスコンビニは出社を促進するための有効な手段としても期待されています。
従業員の利用状況と満足度に関するデータ
オフィスコンビニの利用者満足度については、サービスの種類によって評価が分かれます。
ドリンク・おやつ系では「セブン自販機」が総合満足度1位で「品質」「品揃えの良さ」の観点で高い評価を得ています。
セブン自販機は近くのセブン-イレブンから商品配送されるため、オフィスにいながらコンビニ品質の商品が利用できる点が評価されているのです。
食事系では「オフィスでやさい」が総合満足度1位です。
休憩時間やランチタイムの利用が多く、外へ買いに行く手間が省けるため、ストレスの軽減にも役立っているとの報告があります。
出典:PR TIMES データ&ランキング「フォーカスリサーチ」 導入が進む「オフィスコンビニ」をリサーチ
また、オフィスコンビニは社内コミュニケーションの活性化にも貢献しており、休憩時間に自然と人が集まる場として機能しています。
厚生労働省の「令和3年雇用動向調査結果の概要」によると、従業員が辞職を決めた理由として「職場の人間関係が好ましくなかった」という理由が各年代で大きなボリュームゾーンとなっており、オフィスコンビニはこうした課題解決の一助となっているのです。
参考:
結果の概要 4:転職入職者の状況(3)転職入職者が前職を辞めた理由
従業員からは「手軽に購入できる」「時間の節約になる」といった声が多く、多忙な従業員にとって時間の有効活用につながるという評価が高くなっています。
人気のオフィスコンビニサービスの比較
オフィスコンビニサービスは福利厚生として多くの企業に導入されており、主要なサービスにはそれぞれ特徴があります。
以下の内容について、それぞれ解説します。
- オフィスグリコの特徴と導入条件
- セブン自販機やローソンのオフィス向けサービス
- オフィスおかんや冷蔵型サービスの特徴
関連記事>>オフィスコンビニのタイプを比較!おすすめ7選や注意点も紹介
オフィスグリコの特徴と導入条件
オフィスグリコは江崎グリコ株式会社の子会社が提供するオフィス向け置き菓子サービスです。
専用のボックスや冷蔵庫をオフィスに設置し、チョコレートやクッキー、アイスクリームなどのお菓子を従業員が自由に購入できます。
最大の特徴は初期費用・月額費用が無料である点で、商品代金は従業員が購入した分だけ発生する仕組みです。
支払方法は料金箱への現金投入またはQRコード決済(PayPay・d払い・auPAY)に対応しています。
従業員数に関係なく柔軟に設置できるため、小規模な企業から大企業まで対応しています。
対応地域は首都圏、中京、近畿、中国、九州の主要都市です。
設置期間についての決まりはなく、企業の事情に合わせて柔軟に対応しています。
定期的にグリコのスタッフが訪問し、商品補充や料金回収を行うため、企業側の負担は最小限です。
セブン自販機やローソンのオフィス向けサービス
セブン自販機は、セブン-イレブンの売れ筋商品を自販機形式で提供するサービスです。
最大92アイテムの商品を取り扱えるうえ、おにぎりやパンなど、店舗と同じ商品を提供しています。
支払方法は現金だけでなく、nanaco(電子マネー)や交通系電子マネーにも対応しており、利便性が高いのが特徴です。
導入条件は、1日の就業者数または施設利用者数が300人以上であること、1年以上の契約が可能であること(設置日より1年毎の自動更新)などが挙げられています。
セブン自販機は特に「品質」「品揃えの良さ」の観点で高い評価を得ており、近くのセブン-イレブンから商品が配送されるため、オフィスにいながらコンビニ品質の商品が利用できる点が魅力です。
ローソンも同様にオフィス向けサービスを展開しており、両社ともコンビニ品質の商品をオフィス内で提供することで、従業員の満足度向上に貢献しています。
関連記事>>自販機コンビニとは?導入のメリット・デメリットとおすすめも紹介
オフィスおかんや冷蔵型サービスの特徴
オフィスおかんは株式会社OKANが運営する社食サービスで、管理栄養士が監修したお惣菜を1品100円(税込)で購入できるのが最大の特徴です。
職場に設置した専用冷蔵庫に毎月約20種類のお惣菜が届き、電子レンジで温めればすぐに食べられます。
主食や主菜、副菜をバランスよく摂るためのラインナップを基本にして、定番商品や季節商品を組み合わせて提供しています。
従業員数10名未満から10万名超まで幅広い規模の企業に対応しており、累計導入実績は3,000拠点以上に達しているのです。
24時間利用できるため、昼食だけでなく朝食や残業時の食事、早朝や深夜勤務の従業員への食事補助としても活用できます。
チルド(冷蔵)商品を提供できるため、お惣菜やデザート、飲料など幅広い商品を扱えることが挙げられます。
また、省スペースで設置できるため、小規模なオフィスでも導入しやすく、従業員の健康管理や満足度の向上に貢献できるでしょう。
オフィスコンビニを導入する際の注意点
オフィスコンビニを導入する際には、いくつかの注意点があります。
以下の内容について、それぞれ解説します。
- 導入スペースやインフラ整備の確認
- 運用負担の軽減と外部委託の活用
導入スペースやインフラ整備の確認
オフィスコンビニを導入する際は、適切なスペースとインフラの整備が不可欠です。
設置場所の選定では、従業員全員が利用しやすい位置であることや、動線の妨げにならないことを考慮する必要があります。
また、電源の確保も重要なポイントです。
特に冷蔵・冷凍商品を扱う場合は、安定した電源供給が必須となります。
キャッシュレス決済に対応しているかも確認しましょう。従業員が現金を持ち歩く必要がないため、利便性が大幅に向上します。
また、現金管理の手間が省けるため、管理コストの削減にもつながるでしょう。
運用負担の軽減と外部委託の活用
オフィスコンビニを運営管理する際は、外部委託すると自社の負担を大幅に軽減できます。
多くのオフィスコンビニサービスでは、専門スタッフが商品補充や在庫管理を行うため、担当者の負担が軽減されます。
定期的に提供会社のスタッフが商品の補充や設備のメンテナンスを実施してくれるため、自社のリソースを割く必要がありません。
賞味期限の管理なども自社で行う必要がなく、常に商品が循環するので、非常時の備蓄としても活用できます。
欠品が起こるケースも考えて、商品補充の頻度もあわせてチェックしておくと安心です。
関連記事>>オフィスコンビニの導入で期待できる福利厚生の効果|今後の展望も解説
まとめ
オフィスコンビニの市場規模と成長背景、導入率と利用実績、従業員の利用状況と満足度データ、オフィスコンビニサービスの比較、導入する際の注意点について解説しました。
オフィスコンビニ市場は、働き方の多様化や福利厚生の重要性の高まりを背景に拡大しています。
社員食堂の減少や省スペースへの対応、健康経営の推進といった社会的ニーズに応える形で導入が進んでおり、職場環境の改善策として注目されています。
マイクロマーケットという新たな形態の広がりにより、オフィス以外の施設にも展開が広がる兆しを見せており、今後も成長が見込まれる分野といえるでしょう。
オフィスコンビニの増加に伴い、TOUCH TO GO の 無人決済店舗システムを導入する企業が増えています。
オフィスコンビニの無人店舗決済をご検討中の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/