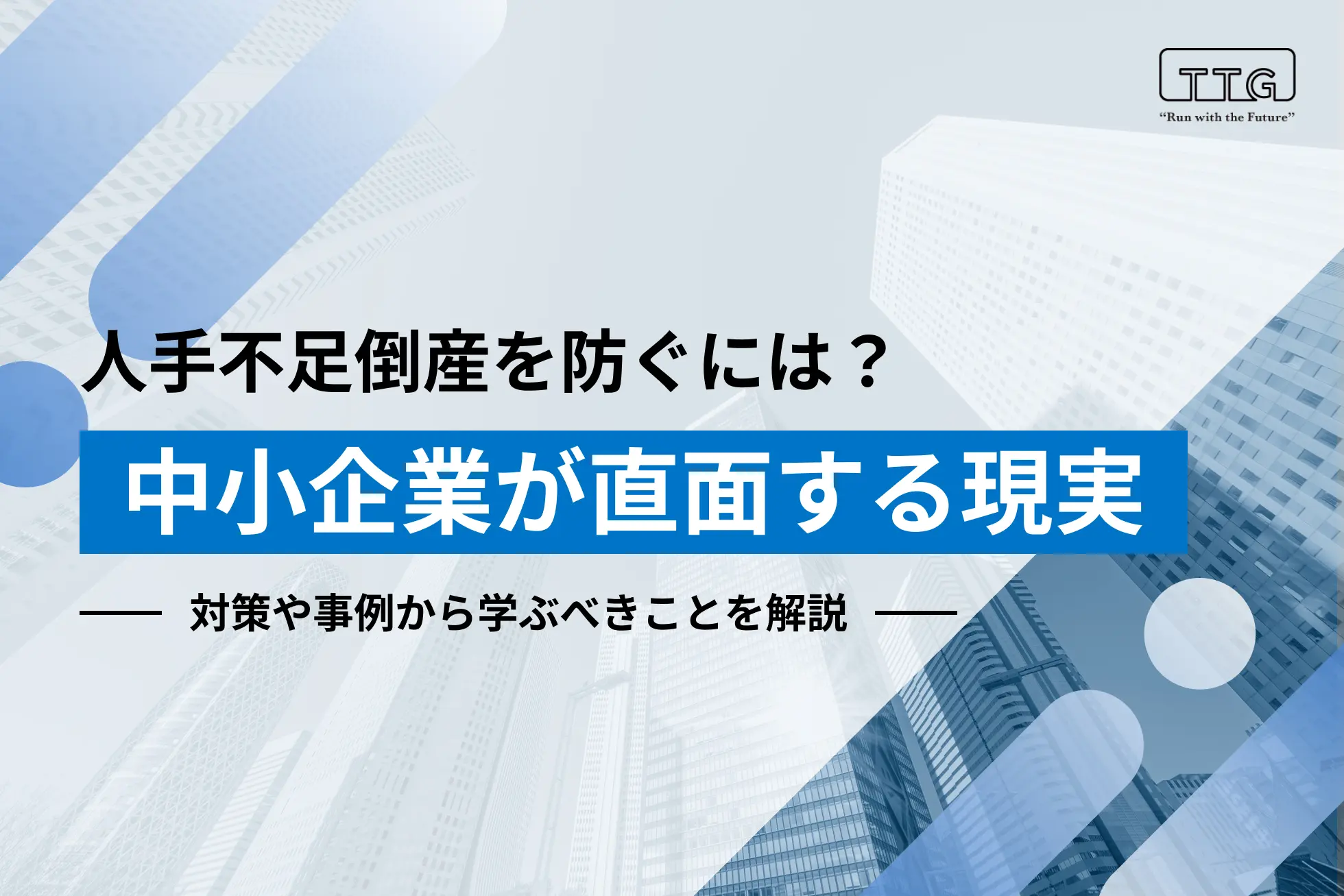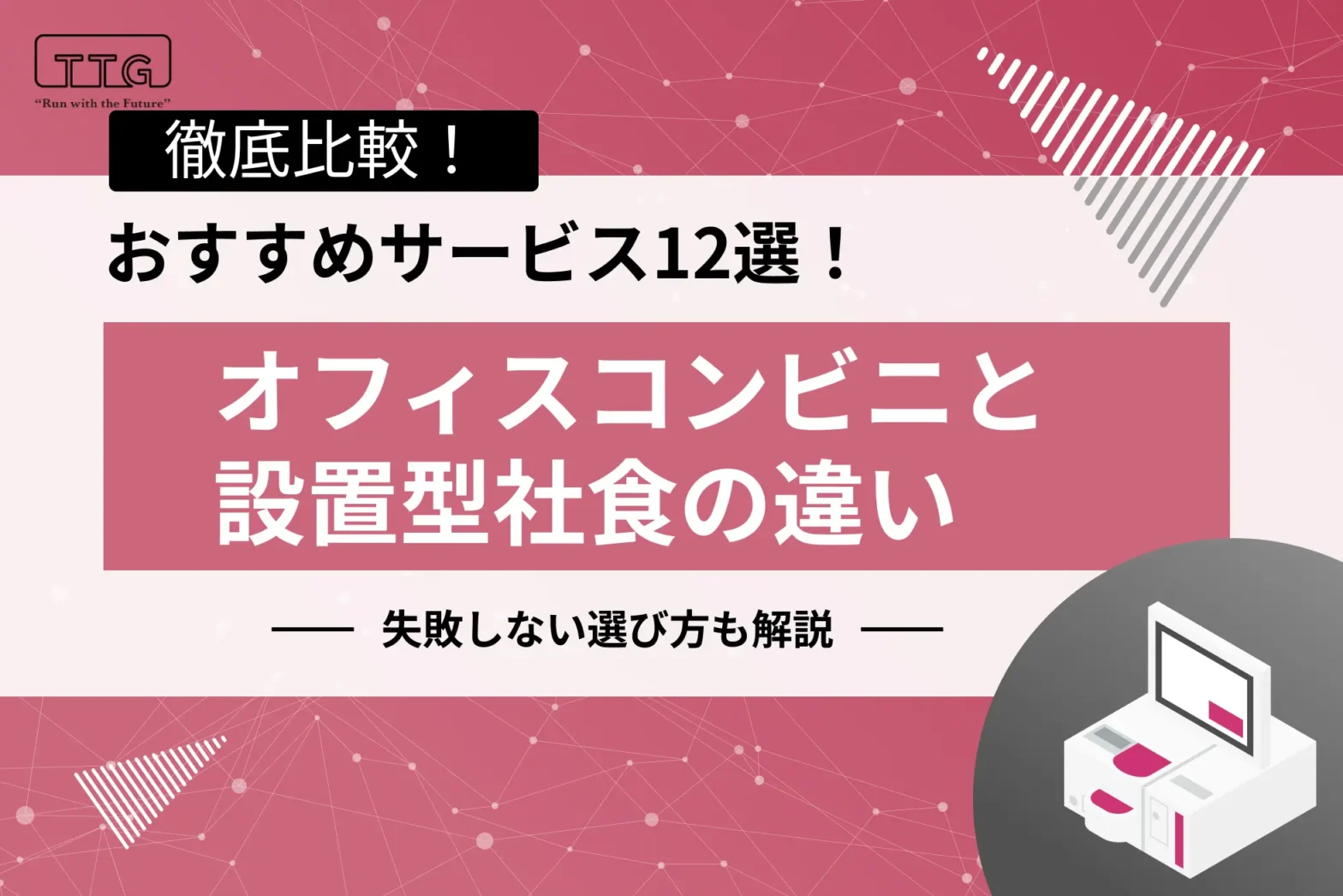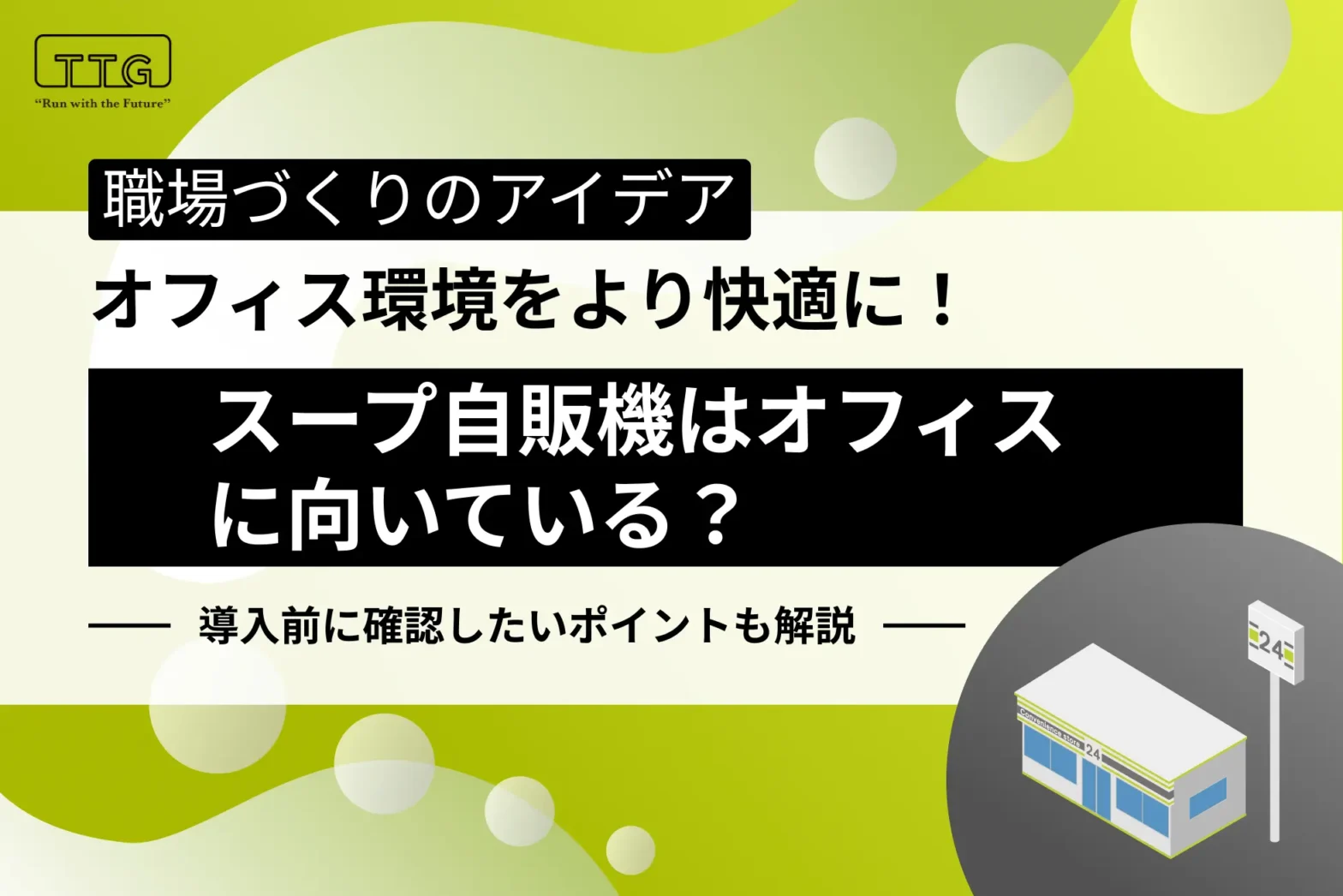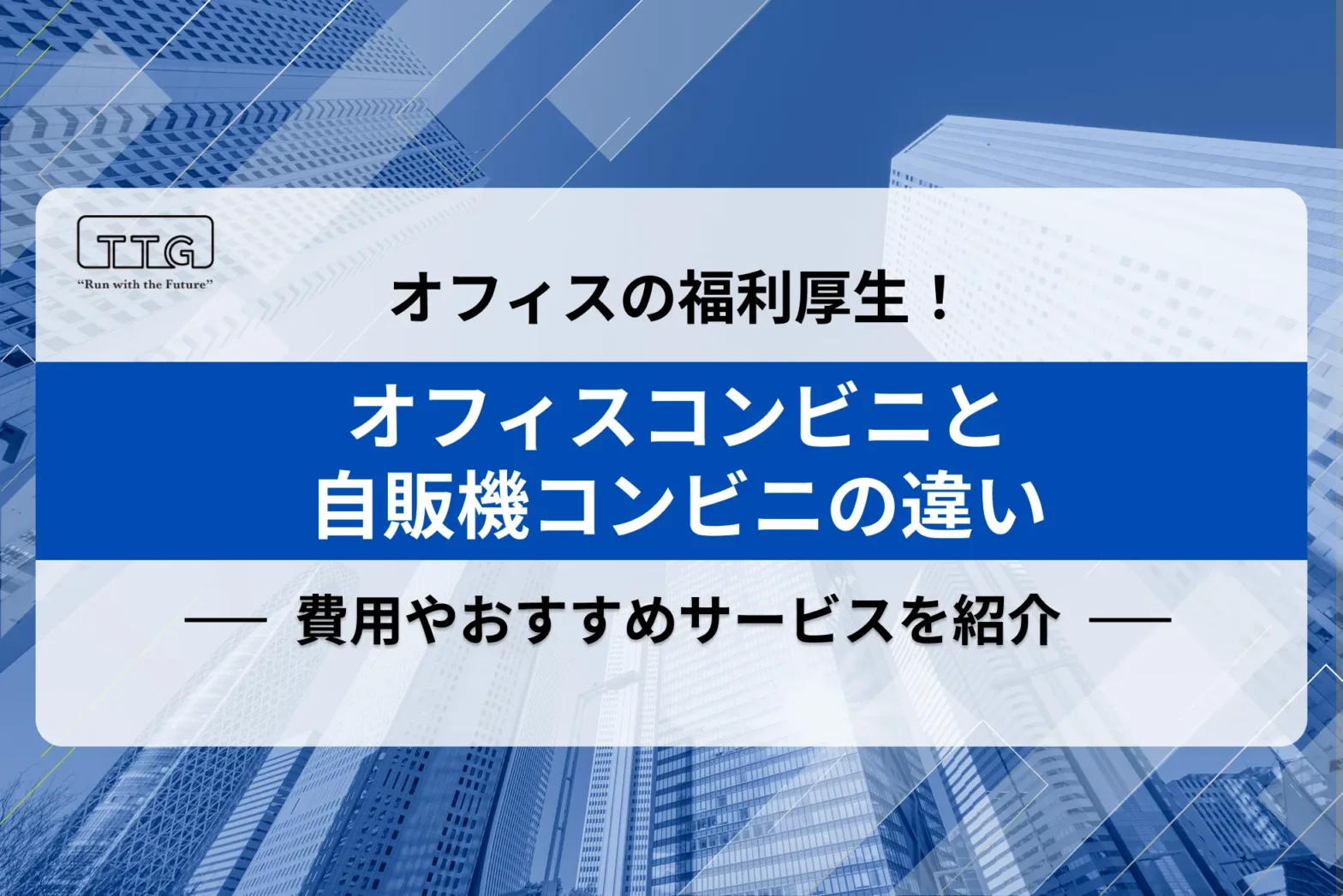Category
こんにちは。無人決済店舗システムを提供しているTOUCH TO GO 編集部です。
人手不足倒産は、必要な人材を確保できず、事業運営が困難になることで発生します。
少子高齢化による労働人口の減少や採用難、従業員の離職、そして人件費の高騰が主な理由です。
本記事では、人手不足倒産の理由や前兆、事例から学ぶべきことや対策について解説しています。
人手不足倒産を防ぎつつ、企業体質そのものを強化して持続的な成長につなげられるため、ぜひ最後までご覧ください。
監修者プロフィール

2019年に株式会社TOUCH TO GOを設立。無人決済店舗システムを提供し、次世代型小売の拡大に取り組んでいる。
目次
人手不足倒産はなぜ起きるのか
人手不足倒産とは「働き手の不足が原因で、事業の継続が困難になり倒産するケース」を指しています。以下の内容についてそれぞれ解説します。
- 帝国データバンクの統計から見る人手不足倒産の実態
- 人手不足倒産は「嘘」なのか「奴隷不足」なのか
- 「自業自得」と言われる背景にある社会構造
帝国データバンクの統計から見る人手不足倒産の実態
帝国データバンクの調査によると、2024年の人手不足倒産件数は342件に達し、過去最多を更新しました。
特に建設業や物流業が全体の約4割を占めており、労働集約型の業種で深刻化しています。背景には高齢化があり、建設業では就業者の23.9%が60歳以上という状況です。
今後も特に建設業や物流業では人手不足が見込まれることから、人手不足倒産は高水準で続くと予想されています。
(出典)帝国データバンク 人手不足倒産の動向調査(2024年)
人手不足倒産は「嘘」なのか「奴隷不足」なのか
一部では「人手不足倒産は嘘で、実際は低賃金で働く人材が集まらない『奴隷不足』だ」との批判があります。企業が賃金や労働条件を改善せず、安価な労働力を求め続ける姿勢が問題視されているのです。
特に中小企業ではコスト削減を優先し、従業員への待遇改善が後回しにされる傾向が強いと言われています。その結果、求職者とのミスマッチが生じて人材の確保が困難になっていると指摘されています。
「自業自得」と言われる背景にある社会構造
人手不足倒産が「自業自得」と言われる背景には、企業側の労働環境に対する改善の遅れや、賃金対応の不十分さがあります。
少子高齢化による労働人口減少が進む中、企業が従業員を軽視し、長時間労働や低賃金を放置してきた結果、労働者が離職する事態を招いています。
また、過去の「氷河期世代」を軽視した採用方針や、即戦力を求める選り好みの採用も問題視されているのです。これらの要因が複合的に絡み合い、倒産のリスクを高めています。
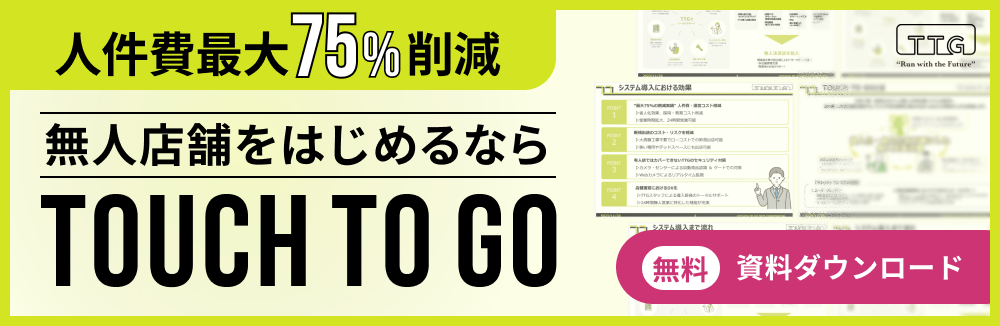
TOUCH TO GO の 無人決済店舗システムを導入すると、人手不足による営業停止やサービス品質の低下を回避できるため、事業の継続性が高まります。
店舗の省人化をご検討中の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/
中小企業で見られる人手不足倒産の前兆
中小企業における人手不足倒産には、いくつかの前兆が見られます。これらのサインに早く気づき、適切に対応することが、倒産を防ぐための第一歩です。以下の点について、それぞれ解説します。
- 若者が集まらない職場の共通点
- 退職者の増加と求人難の悪循環
- 「職場がやばい」と言われる状態とは
若者が集まらない職場の共通点
若者が集まらない職場には以下の共通点があります。
- 給与が低い
- キャリアアップの機会が少ない
- 人間関係が悪い
- 企業文化が若者の価値観と合わない
若者は生活基盤を築くために十分な収入を求める傾向があり、給与が低い会社の応募を避ける可能性が高いと言われています。
また、キャリアアップの機会が少ない職場も敬遠されます。若者は成長や達成感を重視するため、スキルアップや昇進の見込みがない環境ではモチベーションが低下するからです。
さらに、人間関係が悪い職場や企業文化が若者の価値観と合わない場合も、定着率が低くなります。これらの要因が絡み合い、若者が集まりにくい職場となるのです。
退職者の増加と求人難の悪循環
退職者の増加は、企業にとって深刻な悪循環を引き起こします。1人の退職が連鎖的に他の従業員の離職を誘発し、組織全体の士気が低下する可能性があるからです。
退職者が増えると、残った従業員の業務負担が増加して労働環境が悪化します。この結果、さらに退職者が増えるという負のスパイラルに陥るのです。
また、求人難が重なると新しい人材を確保するのが難しくなり、業務の停滞や生産性の低下につながります。
特に少子高齢化や労働市場の競争激化が背景にある場合、企業は採用活動の精度を上げるとともに、内部改善を進める必要があります。
「職場がやばい」と言われる状態とは
「職場がやばい」と言われる状態には、以下の特徴があります。
- 労働環境や職場の雰囲気が悪い
- 給与が低い
- 評価制度が不公平
長時間労働や休日出勤が常態化している場合、従業員の心身に負担がかかってストレスが増大します。
また、職場の雰囲気が悪い場合も問題です。例えば、ハラスメントやいじめが横行している環境では、従業員同士の信頼が失われ、生産性が低下します。
さらに「給与が低い」「評価制度が不公平」など、従業員が努力しても報われないと感じる職場では、モチベーションが著しく低下するでしょう。
これらの要因が重なると、職場全体が「やばい」と認識される状態になるのです。
実際の人手不足倒産の事例から学ぶべきこと
実際に起きた人手不足倒産の事例を見ると「人がいない」だけで会社が立ち行かなくなる現実が浮き彫りになります。
そこから学べるポイントは、単に人を増やすことではなく「人をどう扱い、どう守るか」が経営の核心になっているといえるでしょう。以下の内容についてそれぞれ解説します。
- 雇用環境の整備を怠った結果
- 人材戦略に課題を抱える経営者と責任の所在
- 氷河期世代と人手不足のツケ
雇用環境の整備を怠った結果
雇用環境の整備を怠った企業は、人手不足倒産のリスクを高めています。例えば、給与や福利厚生の改善を怠り、競合他社に比べて魅力的な条件を提供できない場合、必要な人材を確保するのが難しくなります。
また、長時間労働や休暇取得の制限など、労働環境が悪化すると退職者の増加が連鎖的に発生するでしょう。
さらに、職場の雰囲気や人間関係の悪化も従業員の定着率を低下させる要因です。これらの問題を放置すると、企業は生産性の低下や業務の停滞に直面し、最終的には倒産に至る可能性があります。
人材戦略に課題を抱える経営者と責任の所在
人材戦略に課題を抱える経営者の存在は、人手不足倒産の一因となる場合があります。
例えば、従業員の待遇改善や労働環境の整備を怠り、短期的な利益を優先する経営判断を繰り返すと、従業員のモチベーションが低下し、離職率が上昇します。
また、適切な採用戦略を構築せずに必要な人材を確保できない場合、企業の競争力が低下するでしょう。
さらに、経営者が従業員の声を無視して独断的な経営を行うと、職場の雰囲気が悪化して組織全体の士気が低下します。
これらの問題は経営者の責任として問われるべきであり、倒産の原因として厳しく評価される可能性があります。
氷河期世代と人手不足のツケ
氷河期世代は、1990年代から2000年代初頭の就職難の時期に正規雇用の機会を失い、非正規雇用や低賃金労働に従事せざるを得なかった世代です。
この世代が労働市場へ適切に参入できなかったことが、現在の人手不足問題の一因となっています。
企業は当時、氷河期世代を十分に活用せず、労働環境の改善を怠った結果、現在の労働力不足に直面しているのです。
さらに、氷河期世代が高齢化する中で、彼らのスキルや経験を活かす再教育や職業訓練の機会を提供しないため、労働市場の効率性を低下させています。
この問題は、過去の経営方針のツケとして社会全体に影響を及ぼしているといえるでしょう。
「潰れればいい」と思われないために企業ができる対策
「潰れればいい」「自業自得だ」と思われない企業になるためには、単に人手不足を解消するだけでは不十分で、社会や働き手から信頼される組織づくりが必要です。
そのために企業ができる対策は、次のようなポイントに集約されます。
- 定着率を高める働きやすい環境の作り方
- 外部人材やITの活用による業務効率化
- 中長期的な人材育成と採用戦略の見直し
定着率を高める働きやすい環境の作り方
定着率を高めるためには、従業員が快適に働ける環境を整えることが重要です。労働条件や福利厚生を見直し、ワークライフバランスを支援する施策を導入しましょう。
具体的にはフレックスタイム制度やリモートワークの推進、年間休日数の増加など、柔軟な勤務体制を提供すると効果的です。
また、職場のコミュニケーションを活性化し、心理的な安全を醸成すれば、従業員の帰属意識を高められます。
例えば、定期的な1on1ミーティングやフィードバックを通じて従業員の意見を尊重し、信頼関係を構築することが重要です。
さらに、キャリア支援やスキルアップの機会を提供し、従業員が成長を実感できる環境を作ることで、離職率を抑えられます。
外部人材やITの活用による業務効率化
外部人材やITの活用は、業務の効率化と人材不足の解消に有効な手段です。
外部人材を活用する際は業務範囲や目標を明確にし、進捗管理を徹底することで成果を最大化できます。
特に専門知識を持つ外部人材を活用すれば、社内で対応が難しい課題を解決できるでしょう。
ITの活用では、業務の自動化や省力化を進めると従業員の負担を軽減できるため、生産性が向上します。
例えば、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を導入して定型業務を効率化し、従業員がより付加価値の高い業務に集中できる環境を整えます。
また、DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進し、データ活用やAのI導入を通じて競争力を強化することも重要です。
中長期的な人材育成と採用戦略の見直し
中長期的な人材育成と採用戦略の見直しは、企業の持続的な成長に不可欠です。
採用戦略では、企業の中長期的な目標に基づき、必要なスキルや経験を持つ人材を明確に定義します。
新卒採用だけでなく、中途採用や外部人材の活用も視野に入れ、柔軟な採用計画を策定しましょう。
さらに、採用後の育成プランを充実させることも重要です。メンター制度や定期的な評価フィードバックを導入し、従業員の成長を支援します。
また、キャリアパスを明確化し、従業員が長期的な目標を持てる環境を整えることで、定着率を向上させます。これらの施策を通じて企業の競争力を高め、優秀な人材を確保・育成できるのです。
まとめ
人手不足倒産は単なる労働力不足ではなく、企業の体質や経営姿勢が問われる深刻な問題です。
給与や労働環境の改善を怠った結果、求職者とのミスマッチが生じ、採用や定着に失敗するケースが目立ちます。
特に中小企業では待遇の改善が後回しになりやすく、長期的な人材育成や働きやすい職場づくりの重要性が高まっています。
人材の確保だけでなく、育成や職場の魅力向上に目を向けることが、倒産リスクの軽減と企業の信頼獲得につながるでしょう。
時代の変化に適応し、働き手に選ばれる企業を目指すことが持続的な経営の鍵となります。
TOUCH TO GO の 無人決済店舗システムを導入すると、人手不足による営業停止やサービス品質の低下を回避できるため、事業の継続性が高まります。
店舗の省人化をご検討中の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/