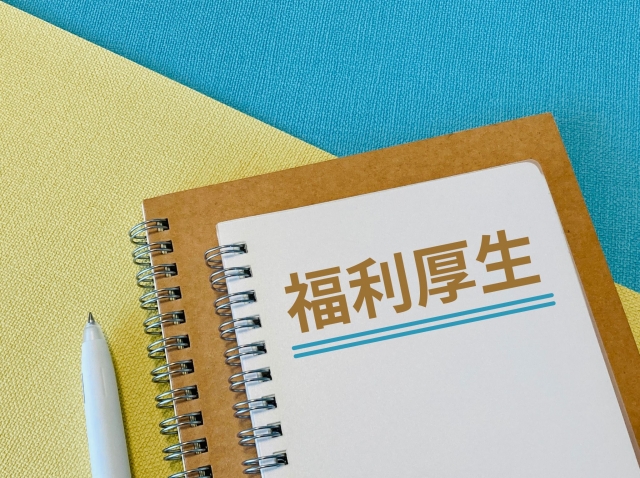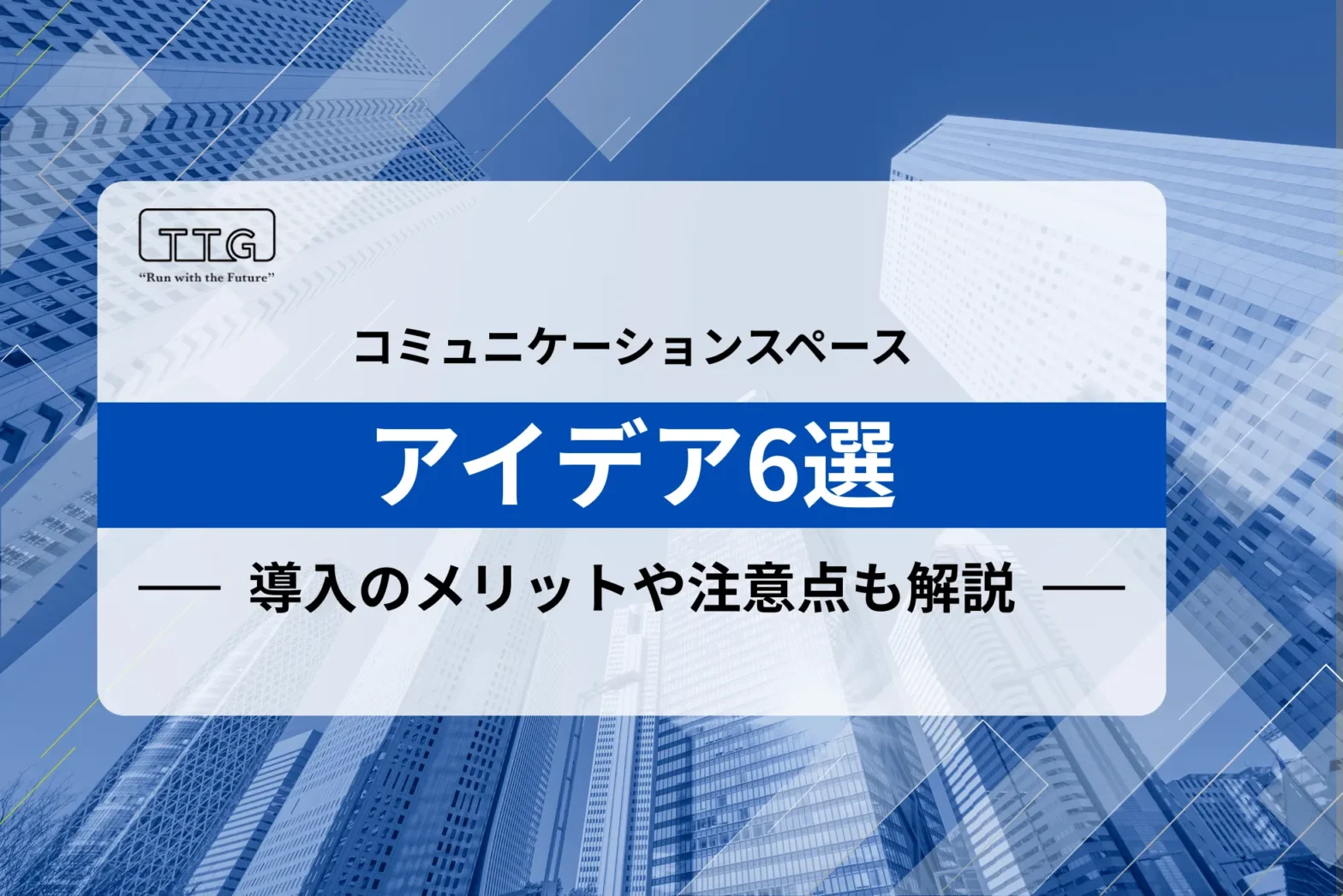Category
こんにちは。無人決済店舗システムを提供しているTOUCH TO GO 編集部です。
従業員の満足度向上や企業イメージアップに不可欠な福利厚生。法定福利厚生からユニークな法定外福利厚生まで、種類は多岐にわたります。
この記事では、福利厚生の基本的な概念から具体的な種類、導入時の注意点までを網羅的に解説します。
福利厚生の充実を検討している経営者や人事担当者はもちろん、福利厚生について詳しく知りたい従業員の方も、ぜひ参考にしてください。
関連記事>>健康経営に繋がる福利厚生サービス4選|効果的な選び方も解説
監修者プロフィール

2019年に株式会社TOUCH TO GOを設立。無人決済店舗システムを提供し、次世代型小売の拡大に取り組んでいる。
目次
福利厚生とは?
福利厚生とは、企業が従業員やその家族に対して提供する、給与や賃金以外の報酬やサービスのことです。
従業員の生活の質(QOL)向上や、企業への帰属意識を高めることを目的としています。
福利厚生には、法律で義務付けられている「法定福利厚生」と、企業が独自に設ける「法定外福利厚生」の2種類あります。
適切な福利厚生制度を導入することで、従業員の満足度やモチベーションが向上し、生産性向上や人材定着が期待できます。
また、企業イメージの向上にも貢献し、優秀な人材の確保にも繋がるでしょう。
福利厚生費の推移
近年、法律で義務付けられている「法定福利厚生」は増加傾向にあります。
これは、労働力人口の減少や人材確保の競争激化に伴い、企業が従業員の満足度や働きやすさを向上させるための施策を強化していることが一因と考えられます。
また、ワークライフバランスの重視や多様な働き方の推進により、以前より柔軟な福利厚生制度の導入が進んでいます。
今後は、従業員のニーズを的確に捉え、効果的な福利厚生制度を構築することが、企業の競争力を高めるうえでますます重要になっていくでしょう。
さらに具体的な福利厚生費の推移について、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
関連記事>>会社の魅力を高める福利厚生とは?ユニークな福利厚生7選も紹介!
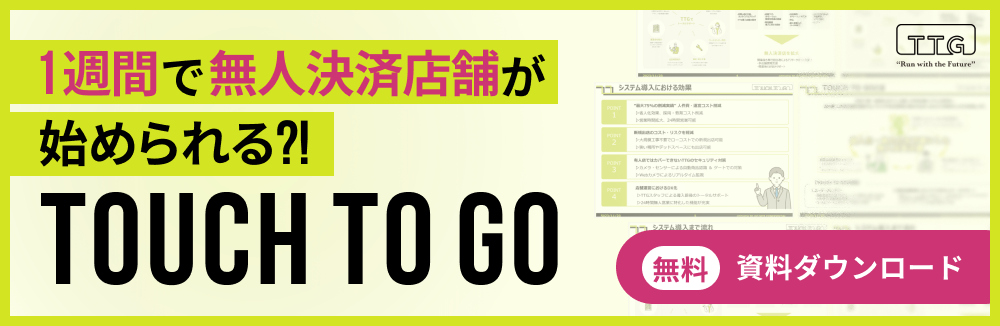
TOUCH TO GO」を導入することで、カンタンに無人のオフィスコンビニを設置できます。
福利厚生としてオフィスコンビニを導入したい方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/
法定福利厚生の特徴と種類一覧
法定福利厚生とは、法律で企業に義務付けられている福利厚生のことです。従業員の生活を保障するための重要な制度であり、社会保険料として企業と従業員が費用を一部ずつ負担します。
法定福利厚生の種類は以下のとおりです。
健康保険
健康保険は、従業員が病気やケガをした際に、医療費を補助する制度です。従業員やその家族が病院を受診した際の医療費の一部を負担し、高額な医療費がかかった場合には、自己負担額を軽減する制度もあります。
保険料は、企業と従業員が折半して負担します。なお、病気やケガによる休業期間中の収入を保障する傷病手当金も、健康保険から支給されます。
厚生年金保険
厚生年金保険は、従業員の老後の生活を保障するための年金制度です。国民年金に上乗せして給付されるもので、加入期間や給与に応じて年金額が決まります。
健康保険と同じように、企業と従業員が保険料を折半して負担します。万が一、被保険者が障害を負った場合や亡くなった場合には、障害年金や遺族年金が支給されます。
労災保険
労災保険は、業務中や通勤中の事故や病気によって従業員が負傷した場合、または疾病にかかった場合に、必要な給付を行う制度です。
治療費や休業補償などが支給され、従業員の生活を保障します。労災保険に加入することで、従業員は安心して業務に取り組めます。
なお、労災保険料は企業が全額負担します。
雇用保険
雇用保険は、従業員が失業した際に失業給付金(基本手当)を支給し、再就職活動や職業訓練の支援も行う制度です。
保険料は企業と従業員が一定割合で負担し、加入することで、失業中も一定期間生活が保障されるとともに、再就職に向けたサポートを受けることができます。
さらに、育児休業給付金や介護休業給付金なども雇用保険から支給されます。
介護保険
介護保険は、介護が必要になった従業員やその家族を支援する制度です。40歳以上の従業員が加入し、介護サービスを利用する際の費用を補助します。
保険料は企業と従業員が折半で負担し、加入することで、万が一介護が必要になった場合でも安心してサービスを受けられます。また、仕事と介護の両立を支える制度としても重要な役割を果たしています。
子ども・子育て拠出金
子ども・子育て拠出金は、子育て支援のための費用を賄うための制度で、従業員の子育て支援や保育サービスの拡充に充てられます。
企業が全額負担し、この拠出金を通じて地域の子育て支援体制が強化されることで、従業員が安心して子育てできる環境づくりに繋がります。
法定外福利厚生の特徴と種類一覧
法定外福利厚生とは、企業が独自に設ける福利厚生制度のことです。
法定福利厚生とは異なり、法律で義務付けられているものではありませんが、従業員の満足度向上や企業イメージアップに大きく貢献します。
企業は、従業員のニーズや企業の特性に合わせて、さまざまな法定外福利厚生を導入できます。
法定外福利厚生の大まかな種類は以下のとおりです。
食事関係
食事補助は、従業員の食生活をサポートする福利厚生です。社員食堂の設置・オフィスコンビニの設置・食事券の配布・弁当の支給など、さまざまな方法があります。
健康的な食事を提供することで、従業員の健康維持や集中力向上に貢献します。また、従業員間のコミュニケーション促進にも繋がります。
オフィス内で買い物できる便利なオフィスコンビニについて、以下の記事で詳しく紹介しています。あわせてご覧ください。
関連記事>>オフィスコンビニとは?特徴やメリット・デメリットを詳しく解説!
住宅関係
住宅手当や家賃補助は、従業員の住宅費負担を軽減する福利厚生です。持ち家支援制度や社宅の提供なども含まれます。
住宅費は生活費の中で大きな割合を占めるため、住宅関係の福利厚生は従業員にとって非常に魅力的です。
通勤関係
通勤手当は、従業員の通勤にかかる費用を補助する福利厚生です。交通費の支給や、通勤定期券の購入補助などがあります。
通勤は従業員にとって負担となるため、通勤関係の福利厚生は従業員の負担軽減に貢献します。
健康・医療関係
健康診断の実施や人間ドックの補助、メンタルヘルスケアの提供など、従業員の健康をサポートする福利厚生です。
健康増進のためのイベント開催や、スポーツジムの利用補助なども含まれます。従業員の健康維持は、生産性向上にも繋がります。
財産形成関係
従業員の財産形成を支援する福利厚生です。「従業員持株会制度」「財形貯蓄制度」「確定拠出年金制度(企業型)」などがあります。
将来への備えをサポートすることで、従業員の安心感を高めます。
休暇関係
有給休暇の取得促進・リフレッシュ休暇・アニバーサリー休暇など、従業員の休暇取得を支援する福利厚生です。
休暇を取得しやすい環境を整備することで、従業員の心身のリフレッシュを促し、生産性向上に繋げます。
レクリエーション関係
社員旅行・社内イベント・クラブ活動の支援など、従業員間の交流を深めるための福利厚生です。従業員同士のコミュニケーションを促進し、チームワーク向上に貢献します。
慶弔・災害関係
結婚祝い金・出産祝い金・弔慰金・災害見舞金など、従業員の慶弔時や災害時に支援する福利厚生です。
災害時に被災した従業員への特別休暇の付与や、社宅・寮の提供、低金利の貸付制度などを設ける企業もあります。
自己啓発関係
資格取得支援・セミナー参加費補助・書籍購入費の補助など、従業員のスキルアップを支援する福利厚生です。従業員の成長を促進し、企業全体のレベルアップにつなげます。
働き方関係
テレワーク制度・フレックスタイム制度・時短勤務制度など、多様な働き方を支援する福利厚生です。
従業員のワークライフバランスを支援し、働きやすい環境を整備します。
育児・介護関係
育児休業給付金の上乗せ・保育サービスの提供・介護サービスの提供など、育児や介護をしながら働く従業員を支援する福利厚生です。
仕事と育児・介護の両立を支援し、従業員の負担を軽減します。
福利厚生を充実させる際の注意点
福利厚生を充実させることは、従業員の満足度向上や企業イメージアップに繋がりますが、導入にあたってはいくつかの注意点があります。
ここでは、新しい福利厚生を導入する際の注意点を紹介します。
同一労働同一賃金ガイドラインに沿った制度にする
同一労働同一賃金ガイドラインとは、同じ仕事をしている従業員に対して、正社員と非正社員の待遇差をなくすことを目的としたものです。
福利厚生についても、正社員と非正社員で不合理な差を設けることは認められません。福利厚生制度を設計する際には、ガイドラインに沿って、全ての従業員に対して公平な制度にする必要があります。
従業員のニーズに合う制度を導入する
福利厚生制度は、従業員のニーズに合っていなければ意味がありません。そこで、導入前にアンケートやヒアリングを実施し、従業員がどのような福利厚生を求めているのかを把握しておきましょう。
従業員のニーズに合った制度を導入することで、満足度向上に繋がります。
公平な制度を導入する
福利厚生制度は、すべての従業員が公平に利用できるものでなければなりません。特定の従業員だけが得をするような制度は「不公平感」を招き、従業員の不満に繋がる可能性があります。
どの従業員も不満を感じることがないように、制度の利用条件や給付内容などを明確にし、公平性を確保することが大切です。
定期的に効果をチェックする
福利厚生制度は、導入して終わりではありません。導入した制度がどの程度の効果をもたらしているかを把握することが大切です。
そこで、従業員アンケートや利用状況の分析などを行い、「制度が十分に活用されているか」、「従業員のニーズに合っているか」などを確認しましょう。
効果が低い制度は見直し、従業員のニーズに合った制度に改善していくことで、福利厚生制度の効果の最大化を目指せます。
まとめ
福利厚生は、従業員の満足度向上や企業イメージアップに不可欠な要素です。法定福利厚生はもちろん、”法定外”福利厚生を充実させることで、従業員のモチベーションを高め、生産性向上にも繋げられます。
福利厚生制度を導入する際には、従業員のニーズを把握し、公平な制度を設計する必要があります。また、定期的に効果をチェック・改善していくことで、福利厚生制度の効果をより高められます。
本記事を参考に、自社に最適な福利厚生制度を構築し、従業員とともに成長できる企業を目指しましょう。以下の記事で、従業員に喜ばれる福利厚生を紹介しています。あわせてご覧ください。
TOUCH TO GO」を導入することで、カンタンに無人のオフィスコンビニを設置できます。
福利厚生としてオフィスコンビニを導入したい方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/