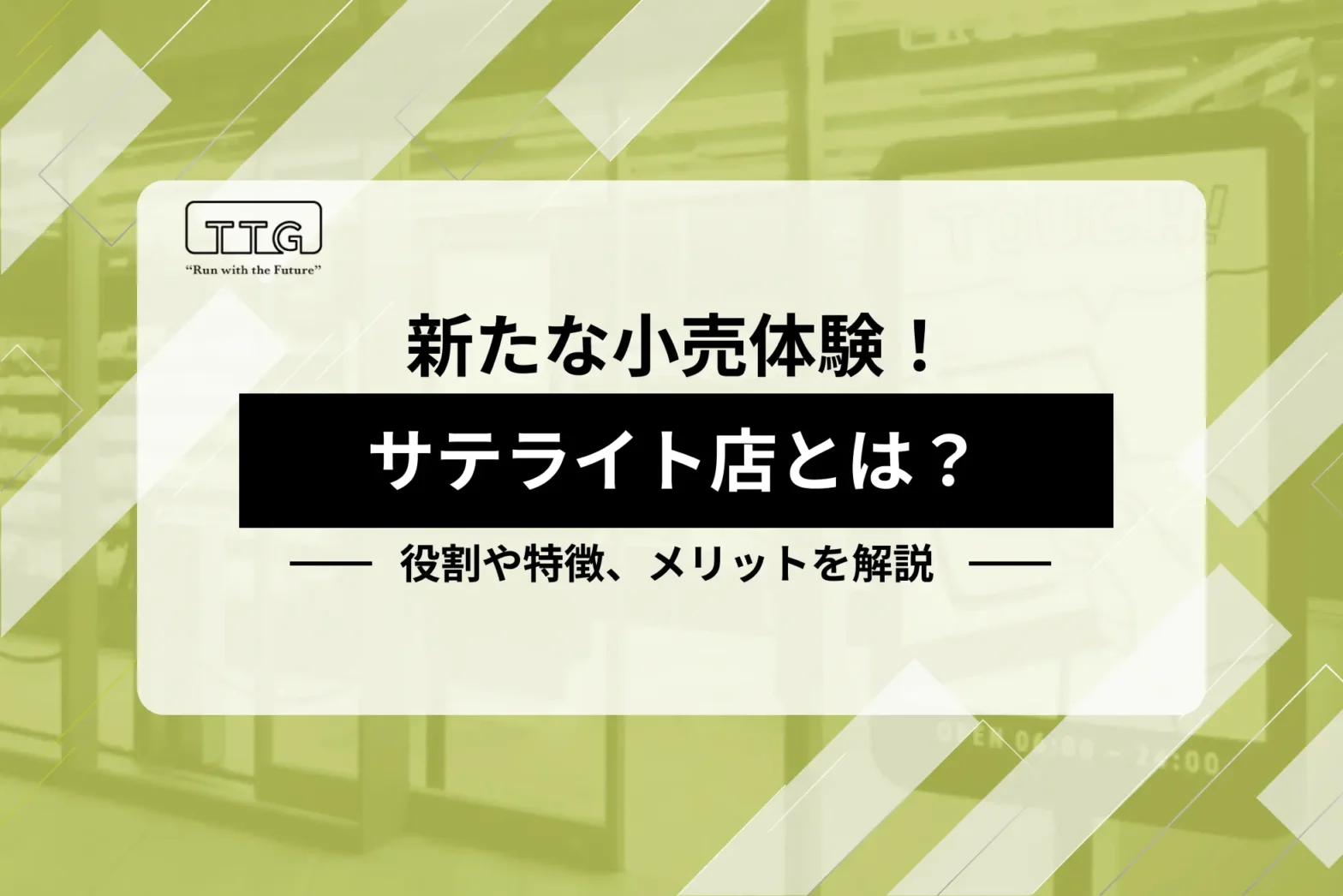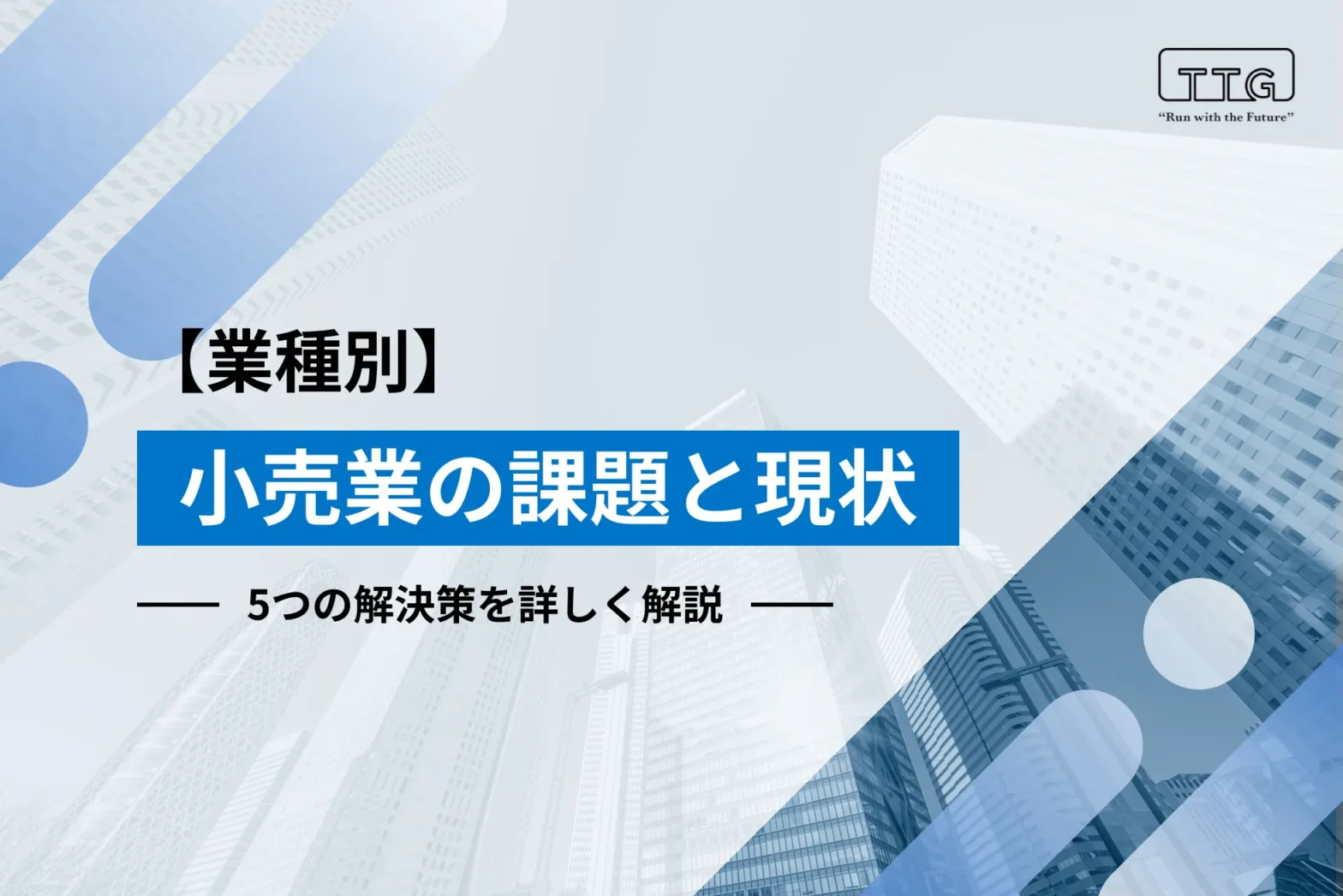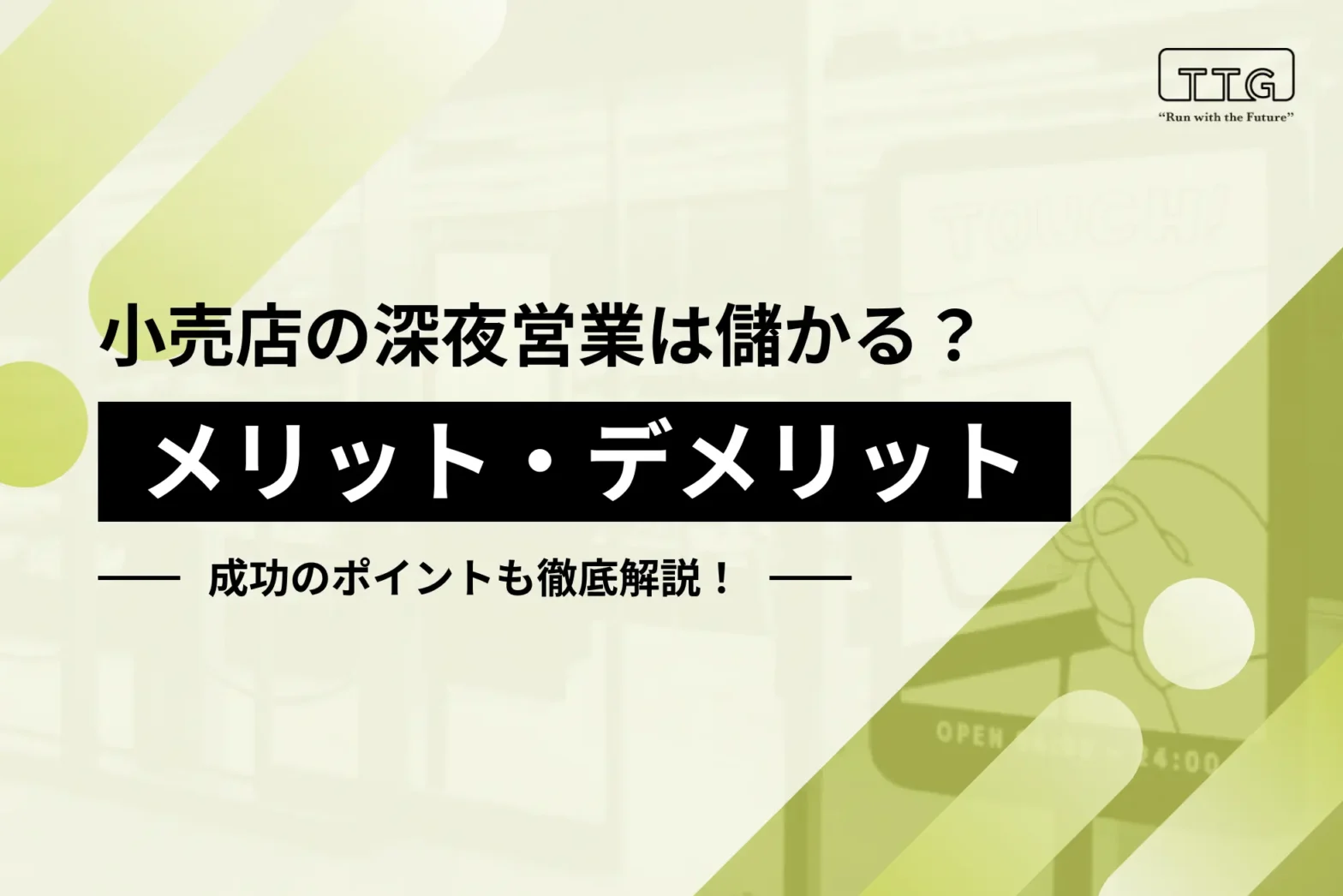Category
こんにちは。無人決済店舗システムを提供しているTOUCH TO GO 編集部です。
私たちの生活に欠かせない存在である小売業には、実にさまざまな種類があります。
業態ごとの違いや特徴を正しく理解することは、ビジネスに携わる方にとっても重要な視点です。
この記事では、小売業の概要から業態の種類を詳しく解説します。さらに、近年の小売業界の課題や売上が落ちる原因についても触れています。
小売業に興味がある方や、業界の課題について理解を深めたい方は、ぜひご活用ください。
監修者プロフィール

2019年に株式会社TOUCH TO GOを設立。無人決済店舗システムを提供し、次世代型小売の拡大に取り組んでいる。
目次
小売業とは?
小売業とは、消費者に対して商品やサービスを提供する業種を指します。
メーカーや卸売業者から商品を仕入れ、個人や法人の顧客に販売する役割を担っており、私たちの生活にもっとも身近な存在です。
具体的な小売業には、「コンビニエンスストア」「スーパーマーケット」「家電量販店」など、多様な業態が含まれます。
また、販売チャネルも実店舗だけでなく、EC(電子商取引)や移動販売、無人店舗など、多様化が進んでいます。
小売業の現状
経済産業省の「商業動態統計速報」によると、2024年上半期の日本の小売業販売額は81兆3,890億円で回復傾向にあります。
特に飲食料品や化粧品関連は伸びが大きく、消費活動が徐々に戻っていることがうかがえます。
一方で、小売業全体では依然として人手不足やコストの上昇、消費者ニーズの多様化といった構造的課題を抱えています。
これに対応するため、無人化・省力化技術の導入や、DX(デジタル化)の推進、SDGsを意識した取り組みなどが加速しています。
小売業の魅力
小売業の最大の魅力は、消費者との距離が近く、社会の変化やニーズをダイレクトに感じ取れる点にあります。
流行や季節、ライフスタイルの変化に合わせて商品を提案できる柔軟さは、小売業ならではの面白さです。
近年ではデータ分析や業務改善に活用できるテクノロジーによって、以前よりもパーソナルな販売戦略が可能になっています。
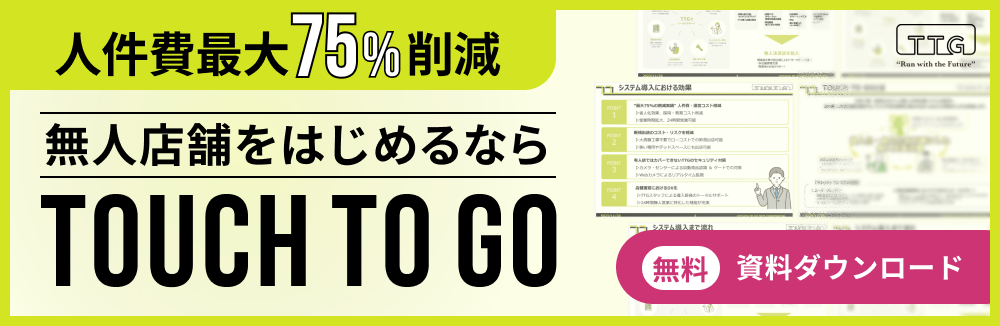
TOUCH TO GO の 無人決済店舗システムは、カメラで人物をトラッキングし、どの棚のどの商品が何個お客様の手に取られたかをセンサーで感知します。
店舗の省人化・人件費削減をご検討中の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/
小売業の主な種類と特徴
小売業にはさまざまな業態があり、それぞれに特徴や役割があります。ここでは代表的な10の小売業態について、特徴とともに紹介します。
総合スーパー
総合スーパーは、食品・衣料品・日用品など、暮らしに必要な商品を幅広く取りそろえた大型店舗です。
ワンストップで買い物ができる利便性が高く、家族層や高齢者を中心に安定した需要があります。
かつてはGMS(General Merchandise Store)として市場をけん引してきましたが、近年は消費者の多様なニーズに応えるため、テナント導入や専門売場の強化など、柔軟な売場構成が求められています。
大型スーパー
大型スーパーは、主に食品を中心に取り扱う業態で、低価格と品揃えの豊富さが特徴です。
ディスカウント志向の消費者をターゲットにしており、まとめ買いや家計節約を意識した来店に強みがあります。
多くは郊外に立地しており、駐車場の完備や広い通路設計など、ゆったりと買い物ができる環境づくりがされています。
近年ではプライベートブランド商品の強化や、地域密着型のサービスも進められています。
専門スーパー
専門スーパーは、特定のカテゴリーに特化した中〜大型の店舗で、日用品や、衣料、家電といったジャンル別に展開されるのが一般的です。
専門性の高さと品揃えの充実が特徴で、目的買いの顧客に支持されやすい傾向があります。
総合スーパーとは異なり、特定分野に集中することで、価格・品質・接客などで差別化を図りやすい点が魅力です。
コンビニエンスストア
コンビニエンスストアは、飲食物や日用品、サービス機能をコンパクトな店舗に集約した業態です。
立地の自由度が高く、都市部から地方、オフィス街や住宅街まで幅広く展開されています。
24時間営業や公共料金の支払い、宅配便の受付など多機能性が強みです。
近年は無人決済やセルフレジ、簡易イートインスペースの導入など、利便性向上と業務負担軽減の両立が進められています。
ドラッグストア
医薬品を中心に、化粧品や日用品、食品などを幅広く扱うのがドラッグストアです。
セルフ形式で効率的に買い物ができることに加え、調剤薬局を併設する店舗も増えている今、地域の“健康拠点”としての役割も担っています。
さらに、冷凍食品や簡易惣菜などの品揃えも充実し、コンビニと競合する一面もあります。
ショッピングセンター
ショッピングセンターは、複数の専門店や飲食店、サービス店舗を1つの施設内に集約した大型商業施設です。
ファッション・グルメ・エンタメなど幅広いニーズに対応できるため、買い物とともに過ごす“時間消費型”の施設として人気があります。
また、ショッピングセンターに入っているお店はテナント型が一般的で、各店舗の売上が施設全体の収益に直結するため、運営側の施設マネジメント力も重要になります。
ホームセンター
ホームセンターは、DIY用品・工具・園芸用品・日用品などを豊富に取りそろえた大型店舗です。
郊外を中心に展開されており、駐車場を備えた倉庫型のレイアウトが一般的です。近年では、ペット用品や食品などの取り扱いも拡大し、より幅広い顧客層に対応しています。
競合の増加や住宅着工数の減少により市場の成長は鈍化傾向にありますが、M&Aや業態転換などによって再編が進んでいます。
専門店
専門店は、特定のカテゴリーに特化した小規模〜中規模の店舗で、以下のような幅広いジャンルがあります。
- アパレル
- 靴
- 文具
- 家具
- アウトドア用品
商品知識や提案力を活かした接客や、独自性のある品揃えで差別化を図るのが特徴です。
最近では、ECと連携した販売やポップアップストアの活用など、柔軟な販売手法を取り入れる店舗も増えています。
百貨店
百貨店は、衣料品・食品・雑貨・ギフト・高級ブランドなどをフロアごとに展開する大型商業施設です。
豊富な品揃えと丁寧な接客が特徴で、長年にわたり高品質な買い物体験を提供してきました。
ただし、近年はネットショッピングの普及や若年層の来店減少などにより、構造的な課題に直面しています。
都心部ではインバウンド需要の回復が追い風となる一方、地方では店舗の統廃合や業態転換が進んでいます。
無店舗小売業
無店舗小売業は、実店舗を持たずに商品を販売する形態で、代表的なものにECやテレビ通販、訪問販売などがあります。
中でもECは急速に成長しており、スマートフォンの普及や物流インフラの進化により、誰もが手軽に買い物できる環境が整っています。
さらに、「サブスクリプション型サービス」や「ライブコマース」などの新たな販売手法も登場し、消費者の選択肢が広がっています。
小売業と卸売業の違い
「小売業」と「卸売業」はどちらも商品を販売する業種ですが、対象とする顧客や販売方法、流通経路などに明確な違いがあります。
ここでは、それぞれの特徴を3つの視点から比較していきます。
販売形態
小売業は、商品やサービスを最終消費者に直接販売する業態です。コンビニやスーパー、アパレルショップのように、店頭で個人に商品を販売するのが一般的です。
一方、卸売業は小売店や企業など、販売を担う事業者に向けて商品をまとめて販売します。顧客との関係性や商談のスタイルも、小売業とは異なる特徴を持っています。
取り扱い商品
小売業では、消費者のニーズに合った単品単位の商品を取り扱います。たとえば「1本のペットボトル」や「1足の靴」といったように、個人がすぐに使える形で販売される商品が中心です。
それに対して卸売業は「ロット単位」や「ケース単位」で商品を取り扱うことが一般的で、仕入先のニーズに応じて在庫管理や価格調整も行います。
商品情報やパッケージングも、販売者向けに最適化されています。
流通ルート
流通の観点から見ると、卸売業は「メーカーと小売業者をつなぐ中間的な存在」です。商品の流れは、メーカー → 卸売業者 → 小売業者 → 消費者という形が基本となります。
小売業は、卸売業者と消費者の間の立場で、商品を販売する立場にあります。
近年では、メーカーが直接ECで消費者に販売する「D2C(Direct to Consumer)」のような新しい形も登場していますが、卸売業と小売業は今なお流通を支える重要な役割を担っています。
小売業が抱える課題
現在、小売業界は以下のような複数の課題に同時に直面しています。
- 消費者ニーズの多様化
- 人手不足
- ECとの競争激化
中でも、実店舗では接客や在庫管理などの業務が増えることで、従業員への負担が大きくなっています。
また、店舗が“ショールーム化”し、来店客がその場で購入せずECに流れるケースも増加傾向にあります。
こうした状況を受け、業界全体では効率化やデジタル技術の活用による改善が求められています。
以下の記事で、業種別の小売業の課題について解説しています。解決策も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
関連記事>>【業種別】小売業の課題と現状|5つの解決策を詳しく解説
小売業で売上が落ちる理由
売上の減少にはさまざまな要因がありますが、小売業においては「顧客との関係性」や「提供価値のズレ」が大きく影響します。
ここでは、現場でよく見られる3つの原因を解説します。
顧客離れ
常連客やリピーターが離れていくと、売上に直接的なダメージを与えます。
理由としては、「近隣に競合店舗ができた」「価格・サービスに魅力を感じなくなった」などが挙げられます。
さらに、ECサイトの登場により、実店舗から顧客が離れているケースも考えられます。
一度離れた顧客を呼び戻すのは簡単ではないため、日々の接客や店舗づくりで信頼関係を築くことが重要です。
商品と顧客ニーズのミスマッチ
消費者の好みやトレンドは常に変化しています。
そうした動きに対応できず、ニーズに合わない商品ラインナップを続けていると、売場の魅力が低下して来店頻度や購買意欲の低下を招きます。
商品と顧客ニーズのミスマッチが原因で売上が落ちている場合は、市場の動向や顧客の声を定期的に見直し、柔軟な仕入れや売場展開が必要です。
顧客対応のパフォーマンス低下
人手不足や業務の属人化により、接客・レジ・品出しなど、現場対応の質が落ちると、顧客の満足度は一気に下がります。
「待たされた」「説明が不十分だった」などの不満が蓄積すれば、他店への流出は避けられません。
業務を効率化し、スタッフの教育や環境整備に力を入れることが、サービス品質の安定につながります。
小売業の売上減少の解決策
「小売業での売上がなぜ落ちるのか」を把握したうえで、的確な対策を講じることが継続的な改善につながります。
ここでは、現場で実践しやすく、成果につながりやすい3つの視点から解決策を考えてみましょう。
客数増加を目指す
売上を構成する「客数×客単価」のうち、まずは客数の増加を目指すことが基本です。
来店促進には、SNSやチラシ、アプリなどを活用した情報発信が有効です。
また、近隣住民や通勤客など、地域特性を踏まえたキャンペーンやイベントの実施も集客力を高めるポイントとなります。
新規顧客だけでなく、既存客の来店頻度を上げる工夫にも取り組んでみましょう。
商品の価値と顧客ニーズをマッチさせる
「いい商品を置いているのに売れない」という状況は、顧客ニーズとのズレが原因かもしれません。
商品の魅力を正しく伝える売場づくりやPOP、試食・試用などの体験を通じて、価値を具体的に感じてもらうことが大切です。
また、売上データや顧客の声をもとに、ニーズに合った品揃えや価格帯の見直しを行うことも、ミスマッチの解消につながります。
DX化を推進する
人手不足や業務の煩雑さを解消し、サービスの質を保つためには、デジタル技術の活用が効果的です。
たとえば、「TTG-MONSTAR」のようなセルフレジやキャッシュレス決済の導入、在庫管理の自動化、データ分析による需要予測などが挙げられます。
こうしたDXの取り組みは、業務効率を高めるだけでなく、顧客の利便性や満足度向上にもつながります。
段階的に導入し、現場で定着させていくことが成功のカギです。
まとめ
小売業は、私たちの暮らしに密接に関わる存在であり、その形態や機能も実に多様です。
今回紹介したように、スーパーや専門店、コンビニなどさまざまな業態があり、それぞれに異なる強みや課題を抱えています。
また、「顧客ニーズの変化」や「人手不足」「ECの登場による競争激化」といった業界共通の課題に直面する中で、売上の維持・向上には柔軟な戦略が欠かせません。
将来的に事業を安定させるなら、DX化への取り組みを検討しましょう。以下の記事で、小売業でのDX戦略を解説しています。ぜひご覧ください。
TOUCH TO GO の 無人決済店舗システムは、カメラで人物をトラッキングし、どの棚のどの商品が何個お客様の手に取られたかをセンサーで感知します。
店舗の省人化・人件費削減をご検討中の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/