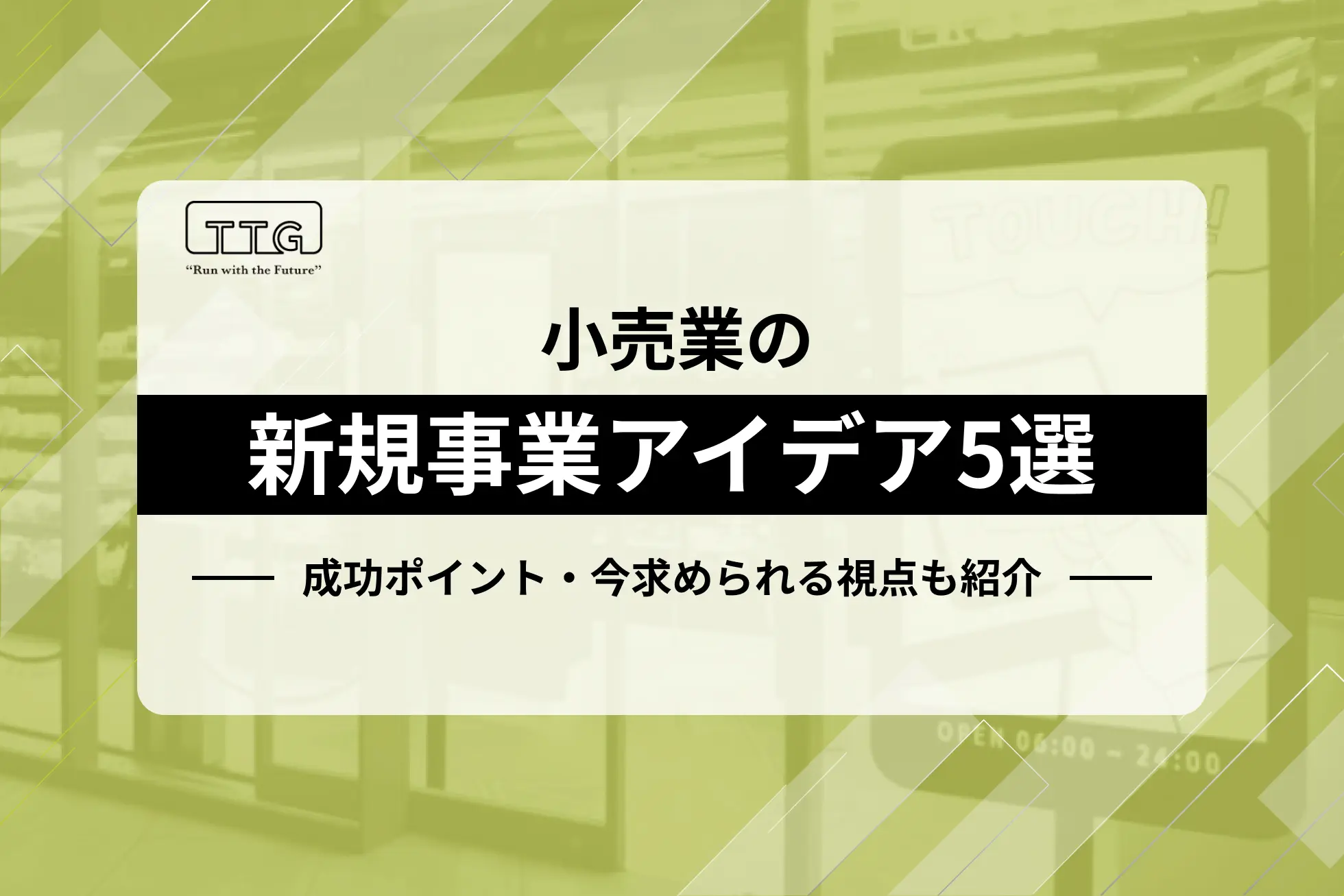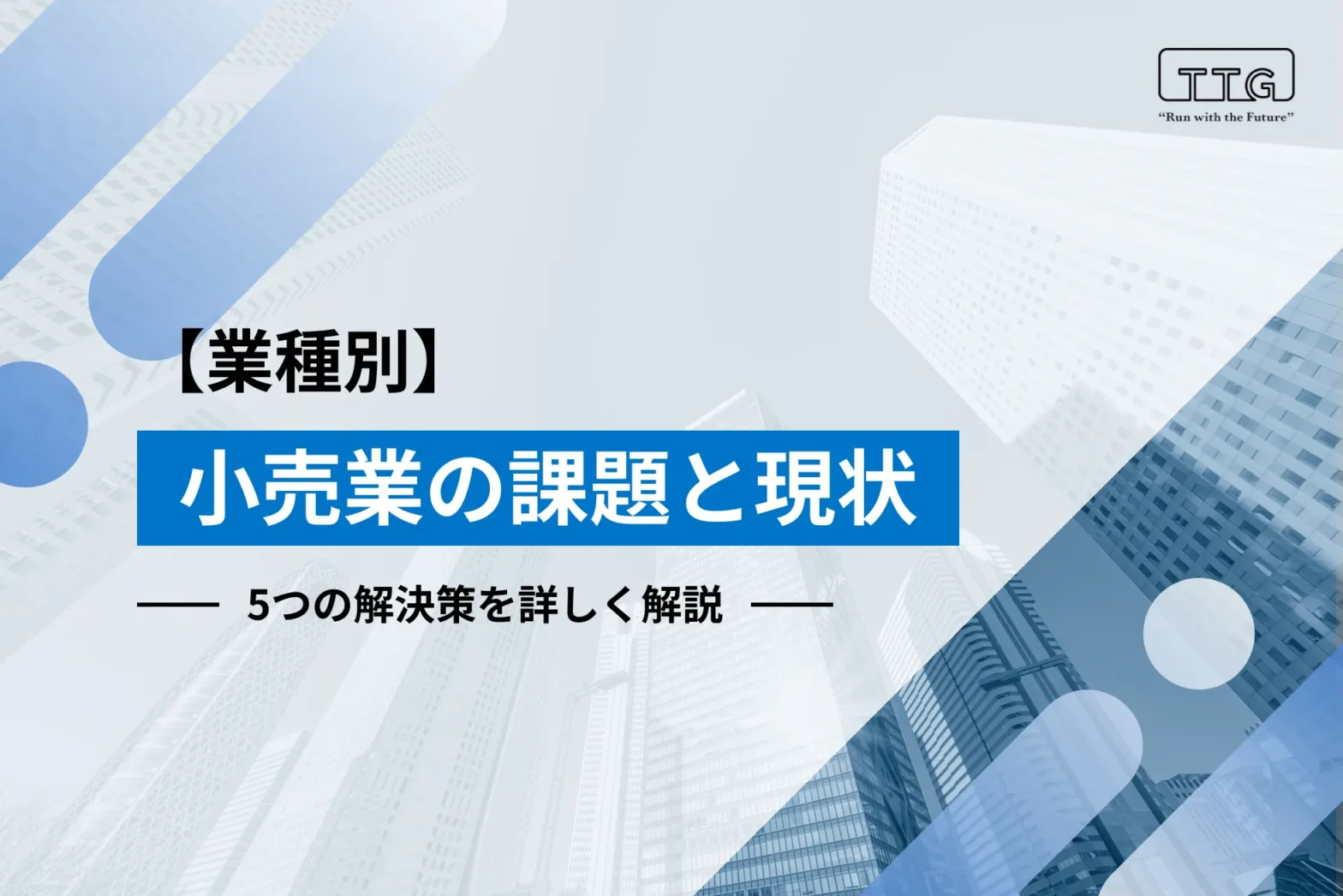Category
こんにちは。無人決済店舗システムを提供しているTOUCH TO GO 編集部です。
小売業界では近年、新たな収益源や事業モデルを求める動きが活発になっています。
これまでのやり方だけでは売上の維持が難しくなり、「そろそろ次の一手を」と考える事業者も少なくありません。
とはいえ、何を始めるべきか、どう進めるべきかは簡単には見えてこないものです。
この記事では、小売業で新規事業を検討している方向けに、既存事業との違いから注目のアイデアを紹介します。
新規事業への参入をご検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
関連記事>>無人販売は新規事業としてアリ?注目される理由やビジネスモデル・事例も紹介
監修者プロフィール

2019年に株式会社TOUCH TO GOを設立。無人決済店舗システムを提供し、次世代型小売の拡大に取り組んでいる。
目次
小売業における「新規事業」とは?
小売業における新規事業とは、これまでの販売スタイルや商品カテゴリーにとらわれず、新しい収益モデルや事業領域を切り開く取り組みのことを指します。
単に新商品を投入するだけではなく、サービスの形態を変えたり、販売チャネルを拡大したり、業種を横断してまったく新しい価値を提供することも含まれます。
変化の激しい市場環境のなかで、既存事業だけでは先行きが見通しづらくなっている今、自社の強みを活かしながら次の成長機会をつくる手段として、新規事業は注目されています。
既存事業との違い
既存事業は、これまでの成功パターンや顧客層をベースにした「守り」の側面が強いのに対し、新規事業は将来の成長や変化に対応するための「攻め」の役割を担います。
新たな売上源を生み出すだけでなく、変化する市場に柔軟に対応できる体質をつくることが大きな目的です。
また、これまでとは異なる顧客層にアプローチできる点も大きな魅力です。
たとえば店舗運営が中心だった企業が、EC参入やサブスクモデルに挑戦することで、接点のなかったユーザー層とつながることも可能になります。
なぜ今、新規事業が注目されているのか?
コロナ禍をきっかけに、人々の消費行動や価値観は大きく変化しました。
「オンライン購入の増加」「非接触へのニーズ」「働き方や暮らし方の多様化」など、小売業を取り巻く前提条件が大きく揺らいでいます。
こうした中で、既存のやり方のままでは、顧客の変化に対応しきれないリスクも高まっています。
そのため、多くの事業者が「次の時代に合ったビジネスのかたち」を模索し、新規事業に取り組むようになっています。
市場が成熟して競争が激しくなるほど、変化への柔軟性を持てる企業ほど生き残りやすいという流れが加速しているのです。
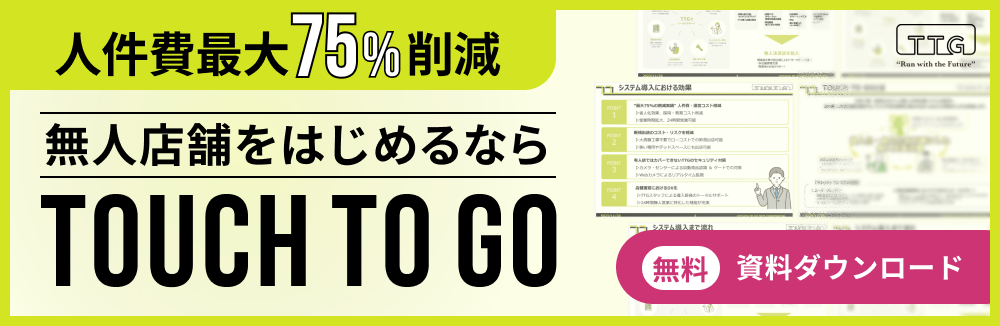
TOUCH TO GOは、人物と商品を店内カメラで認識、レジの前に立つだけで自動で商品が表示される無人決済システムです。
省人化・人件費削減が実現できる無人店舗の開業をご検討中の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/
小売業で新規事業を考える際の基本ステップ
小売業における新規事業の立ち上げは、既存の店舗運営とは異なる視点や準備が求められます。
とくに市場の変化が激しい現在では、トレンドや生活者の価値観に即した事業展開がカギとなります。
ここでは、新たな取り組みを始める際に押さえておきたい、基本的なステップを3つの視点で紹介します。
市場や顧客ニーズの変化を読み解く
まず最初に取り組むべきは、「いまの顧客が何を求めているか」「市場にどんな変化が起きているか」を把握することです。
たとえば、コロナ禍を経てECやモバイル注文が浸透したように、消費スタイルは年々大きく変わっています。
また、Z世代の台頭や高齢化の進行といった社会背景も含めて、「誰が・何に価値を感じているのか」という視点からニーズを読み取ることが、新規事業の方向性を決めるヒントになります。
単なる商品やサービスの提供ではなく、「ターゲットの課題をどう解決できるか」という発想が、現代の小売には求められています。
自社の強みと活かせるリソースを整理する
市場の状況を把握した後は、「自社がどのようなアプローチでニーズに応えられるか」を明確にすることが重要です。
すでに保有している強みやリソースを棚卸ししておきましょう。具体的に把握しておきたい内容は次のとおりです。
- 販売チャネル
- 人材
- 店舗ネットワーク
- 顧客情報
- ノウハウ
自社の強みと活かせるリソースが明確になったら、どのようなビジネスができそうかを検討しましょう。
たとえば、「地域密着の強みを活かして高齢者向けの移動販売を展開する」、または「空きスペースを活用して無人販売を導入する」など、今ある資源を起点とした新たな価値創出も十分可能です。
事業コンセプトと収益モデルを設計する
どんな価値を・誰に・どうやって届けるのかを明確にすることが、新規事業のコンセプト設計です。
売れるかどうかではなく、「なぜ選ばれるか」という視点での企画が重要です。
さらに、単発で終わらないためには、収益の仕組みもしっかり考える必要があります。
原価率や回転率、サブスクリプションなどの定期収入化など、数字の見通しが立つ形にしておくことで、継続性のある事業へとつながっていきます。
今注目されている小売系の新規事業アイデア5選
小売業を取り巻く環境が大きく変化するなか、新しい事業モデルへの関心が高まっています。ここでは、今注目されている新規事業アイデアを5つの視点から紹介します。
無人店舗・スマートストアの導入
近年、省人化や人手不足への対応策として、無人店舗やスマートストアの導入が進んでいます。
カメラやセンサー・電子決済・セルフレジなどのテクノロジーを活用することで、スタッフ不在でもスムーズに販売ができる仕組みを構築可能です。
都市部の駅ナカ、マンションの共用部、オフィスビルの一角など設置場所の柔軟性も高く、小型・省スペース型の出店にも適しています。
また、24時間営業が可能になる点も他の業態にはない強みです。
以下の記事で、無人店舗ビジネスについて詳しく紹介しています。あわせてご覧ください。
関連記事▼
移動販売・出張型店舗の展開
移動販売は、過疎地域や交通手段の限られるエリアをターゲットにした事業モデルとして再注目されています。
軽バンやトラックを活用し、食品・雑貨・衣料品などを積んで地域を巡回するスタイルが一般的です。
販売対象は高齢者世帯や在宅ワーカー、育児中の家庭など、外出が難しい層が中心となります。
販売拠点が不要で場所の制約を受けにくいため、初期投資を抑えて展開できるのも魅力のひとつです。
D2C・サブスクリプション型の仕組みづくり
D2C(ダイレクト・トゥ・コンシューマー)とは、自社で商品を企画・製造し、店舗やECサイトなどを通じて消費者に直接販売するビジネスモデルです。
従来のように卸業者や販売代理店を挟まず、企業と顧客が直接つながる点が大きな特徴です。
また、定期便型の販売手法であるサブスクリプション(定額制)モデルも、D2Cと相性が良い形として注目されています。
たとえば、日用品・コーヒー・化粧品など、リピート需要が見込める商品を一定の間隔で配送することで、安定した収益を確保できる点がメリットです。
このようなモデルは、ブランドの世界観をしっかり伝えたい場合や、顧客との継続的な関係を重視する企業に適しています。
また、顧客データを蓄積しやすいため、パーソナライズされた商品提案やサービス改善にも活用できます。
ポップアップストア・シェアスペースの活用
出店リスクを抑えつつブランドの存在を体験してもらいたい場合、ポップアップストアやシェアスペースの活用が有効です。
ポップアップストアやシェアスペースは短期出店が可能なため、新商品のお試し販売やテストマーケティングにも適しています。
また、近年では商業施設内や駅前、オフィスビルの共有スペースを活用した期間限定店舗も増えており、SNS映えやイベント性を持たせた企画で集客効果も期待できます。
リユース・サステナブル商材の専門小売
環境配慮やエシカル消費への関心が高まる中で、リユース品やアップサイクル商品を扱う小売ビジネスが注目を集めています。
使い捨てを前提としない買い物のスタイルは、消費者の価値観の変化と強くリンクしており、ブランディングや企業の社会的信用にもつながる分野です。
具体例としては、以下のような店舗が挙げられます。
- 子ども服・ベビー用品・スポーツ用品などのリユース専門店
- 廃材や古布を使ったアップサイクル雑貨店
- 賞味期限が近い商品を扱う食品ロス削減ショップ
これらの業態は単なる「物販」にとどまらず、企業の理念や社会的メッセージを発信する場としても機能します。
環境や社会課題への取り組みを可視化したい企業にとって、有力な新規事業の選択肢となるでしょう。
新規事業で失敗しないために押さえておきたいこと
小売業における新規事業は、これまでと異なるターゲットや仕組みを扱うケースも多く、思わぬつまずきが起きやすい領域です。
新規事業を成功に導くためには、立ち上げ時から事業全体を冷静に俯瞰し、リスクを最小限に抑える設計が求められます。
ここでは、新規事業の計画段階で押さえておきたい3つの重要な視点について紹介します。
初期投資と回収プランの明確化
新規事業を立ち上げる際には、以下のようなさまざまなコストが発生します。
- 商品の仕入れ
- 設備投資
- 人件費
- 販促費
- 物件の初期費用(実店舗のみ)
そのため、初期投資額だけでなく、「いつ・どのように回収していくのか」を事前に設計しておく必要があります。
月ごとの損益シミュレーションを作成し、売上見込みや固定費を踏まえた回収期間を明確にすることで、「軌道に乗るまでの体力」を判断しやすくなります。
特に小売業は”キャッシュフローが命”とも言える業態です。
投資と回収のバランスが見えていないまま進めてしまうと、思わぬ赤字や資金繰りの悪化に直結するリスクがあり、注意しなければなりません。
実験・検証のフェーズを設ける
いきなり大規模に始めるのではなく、小さな範囲で「試す」段階を設けることが、新規事業の精度を高めるうえで有効です。
たとえば、「ポップアップストア」や「クラウドファンディング」、「オンラインでのテスト販売」などを活用し、市場からの反応を確認したうえで正式な事業化に進めるのもよいでしょう。
最初の段階で「反応が良かった点」「課題となった部分」を可視化しておくことで、投入するリソースやオペレーションの最適化にもつながります。
人材・業務体制の見直しもセットで考える
事業内容が変わるということは、必要なスキルやオペレーションも変わる可能性があります。
新規事業を本格展開する前に、「現状の体制で運用できるかどうか」をあらためて見直すことが大切です。
たとえば、ECを軸にした事業を始める場合、オンライン接客やデジタルマーケティングのスキルが求められます。
既存のスタッフだけでは対応が難しい場合には、外部人材の登用や業務の一部アウトソーシングも視野に入れるとよいでしょう。
また、既存事業と新規事業を並行して運営する場合、社内の負担が一時的に大きくなる可能性があります。
そのため、「業務の分担」や「優先順位」を整理し、無理のない運営体制を設計しておくことが大切です。
まとめ
小売業を取り巻く環境は大きく変化しており、新たなニーズに応えるためには、これまでにない視点での事業展開が求められています。
「無人店舗」や「D2C」「サステナブルを意識したリユース型の事業」など、注目されている取り組みは多岐にわたります。
ただし、新規事業は立ち上げて終わりではなく、継続的に成果を上げることが求められます。
そのためには、市場や顧客の変化を的確に捉え、自社のリソースを活かした戦略設計と体制づくりが欠かせません。
事前の検証や負担の少ないスタートから着実に育てていくことが、結果として成功への近道になります。
導入時だけでなく将来を見据え、自社に合った形での新しい挑戦を進めていきましょう。
TOUCH TO GOは、人物と商品を店内カメラで認識、レジの前に立つだけで自動で商品が表示される無人決済システムです。
省人化・人件費削減が実現できる無人店舗の開業をご検討中の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/