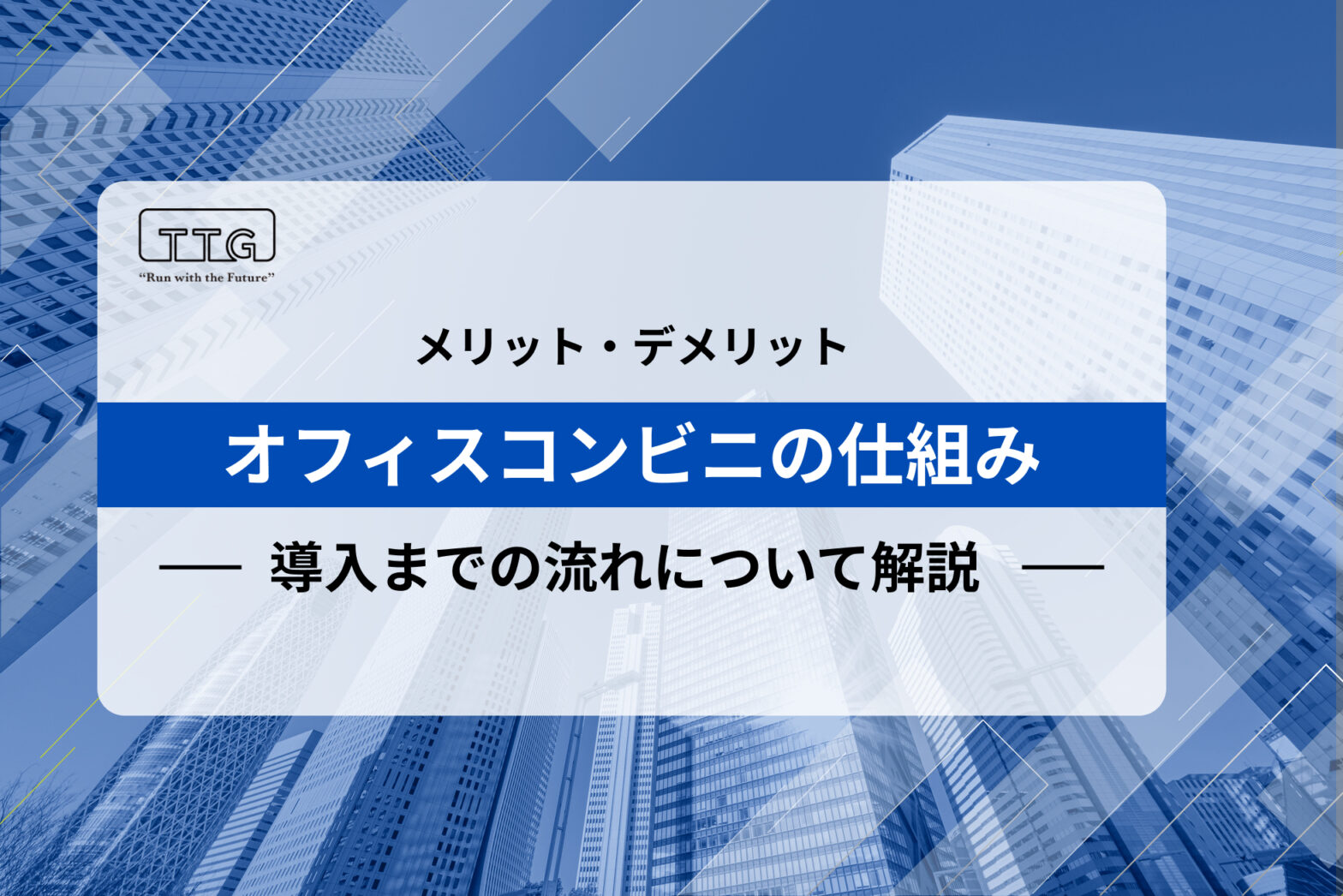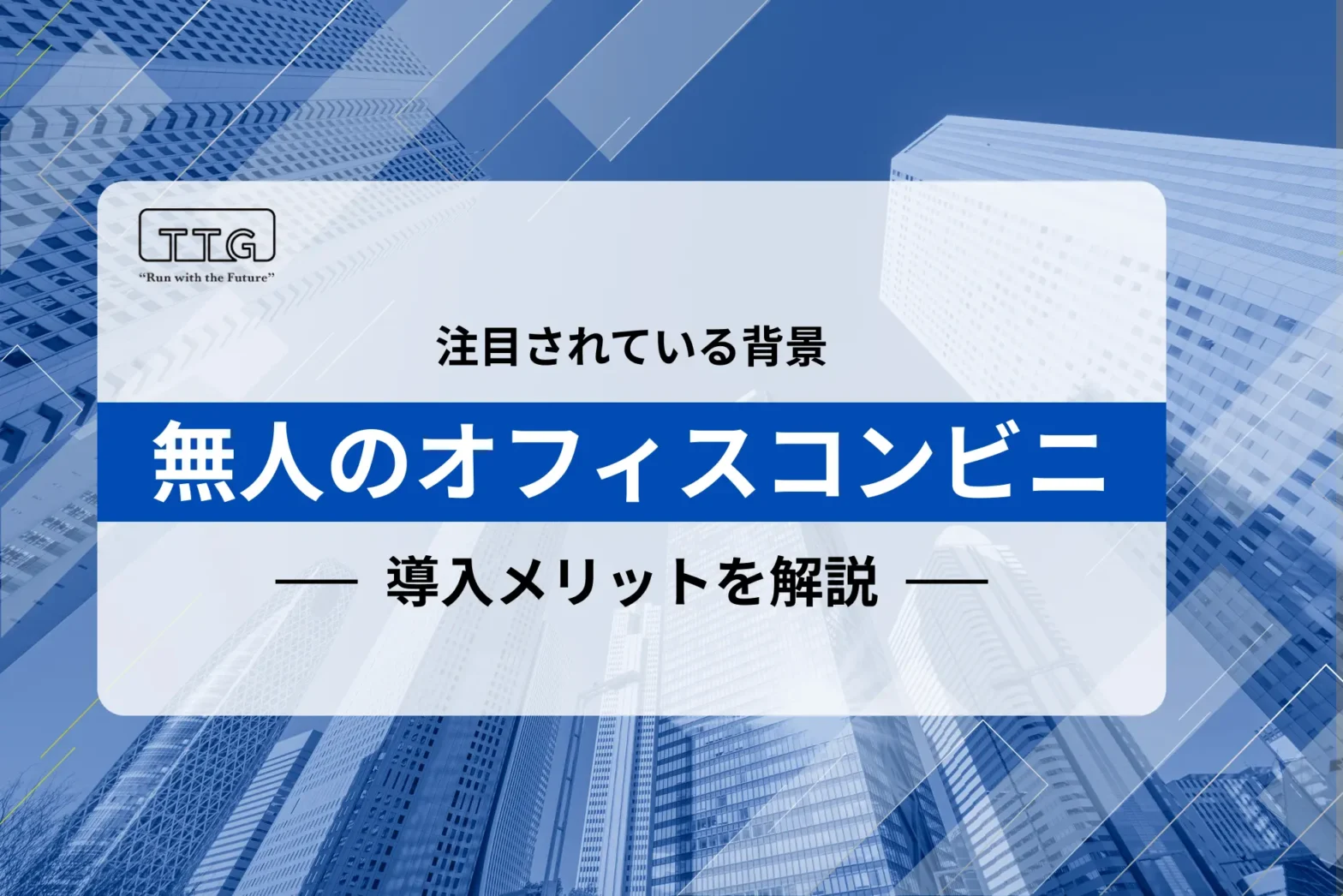Category
こんにちは。無人決済店舗システムを提供しているTOUCH TO GO 編集部です。
「福利厚生で食事補助を取り入れたいけれど、選び方が分からない」と悩んでいませんか。
本記事では、食事補助のメリットや種類、導入時の注意点や検討する際のステップを分かりやすく解説しています。
従業員の満足度アップに役立つ情報を網羅しているため、ぜひ最後までご覧ください。
監修者プロフィール

2019年に株式会社TOUCH TO GOを設立。無人決済店舗システムを提供し、次世代型小売の拡大に取り組んでいる。
目次
福利厚生で食事補助を導入するメリット
福利厚生で食事補助を導入するメリットは多くあります。
主な3つの理由をそれぞれ具体的に見ていきましょう
- 従業員の健康促進と生産性の向上
- 社内コミュニケーションの活性化
- 採用活動での企業アピール効果
従業員の健康促進と生産性の向上
食事補助の導入により、従業員は栄養バランスの整った食事が摂れます。
特に一人暮らしの従業員は節約のために食事を抜いたり、栄養バランスが偏ったりしがちですが、食事補助があれば健康的な食生活を維持できます。
健康状態が良好になると集中力が高まり、業務パフォーマンスも向上するでしょう。
健康経営の実現にもつながり、従業員の生産性向上という企業側のメリットにも直結します。
社内コミュニケーションの活性化
食事補助や社員食堂の設置は、従業員同士の交流の場を提供します。
食事の時間では、普段仕事では関わらない部署の人とも自然に会話が生まれやすくなるからです。
部署の垣根を超えたコミュニケーションが活発になるとチームワークが円滑になり、新しいアイデアも生まれやすくなるでしょう。
ランチ手当を支給すれば、従業員同士が一緒に外食する機会も増え、より親密な関係構築にもつながります。
採用活動での企業アピール効果
食事補助は求職者にとって魅力的な福利厚生の1つです。
毎日利用できる食事補助は経済的な支援として人気があり、企業が従業員の健康や生活を大切にしているというメッセージにもなります。
これにより企業イメージが向上し、優秀な人材の確保や離職率の低下にもつながる重要な採用アピールポイントとなります。
関連記事>>従業員に喜ばれるオフィスの福利厚生12選|メリット・デメリットも解説
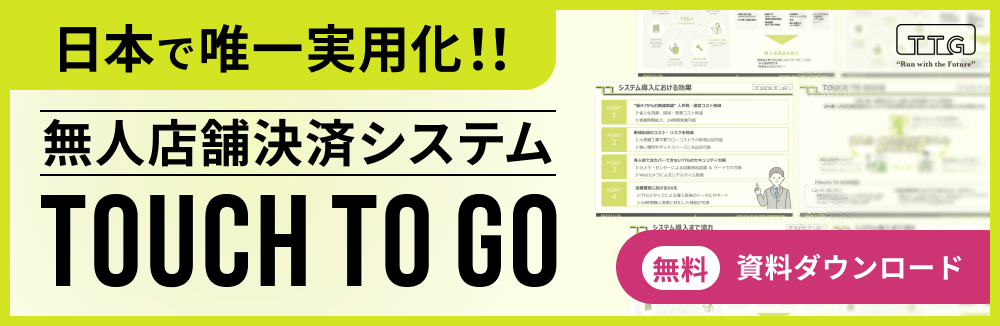
TOUCH TO GO の 無人決済店舗システムを導入すると、従業員の満足度と健康意識を一緒に高められます。
福利厚生をご検討中の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/
福利厚生で選べる食事補助の種類
福利厚生で選べる食事補助はさまざまな形態があり、企業の規模や勤務形態に合った方法を選ぶことが大切です。
主な種類をそれぞれ解説します。
- 社員食堂
- 食事チケットやチケットレストラン
- 弁当配送サービス
- オフィスコンビニ
社員食堂
社員食堂は企業内に専用の食事スペースを設けて従業員に食事を提供する、もっとも伝統的な方法です。
栄養バランスの取れた食事を提供でき、従業員の健康管理に貢献できる点が大きなメリットです。
また、食事の時間を通じて部署を超えたコミュニケーションが生まれ、一体感の醸成にも役立つでしょう。
一方で、設置費用や運営コストが高く、広いスペースの確保が必要なため、中小企業には導入のハードルが高い場合があります。
また、リモートワークや外勤の多い従業員には恩恵が少ないという課題もあります。
そのため、近年では従来型の社員食堂に代わる、より柔軟な食事補助の形態が注目されているのです。
食事チケットやチケットレストラン
チケットレストランは、全国25万店舗以上の飲食店やコンビニで利用できる食事補助サービスです。
ICカード形式で提供され、従業員は加盟店でカードをタッチするだけで簡単に利用できます。
主な特徴は次のとおりです。
- 内勤、外勤を問わず全従業員が公平に利用できる
- 24時間365日いつでも使える
また、一定条件を満たせば、非課税で福利厚生費として計上できるのも大きなメリットです。
条件は次のとおりです。
- 従業員が食事の費用の半分以上を負担していること
- 会社の負担額が3,500円(税抜)/月以下であること
さらに、Uber Eatsとの連携により、オフィス以外の場所でも購入できるため、テレワークでも利用できる柔軟性も魅力といえるでしょう。
弁当配送サービス
弁当配送サービスは、専門会社が企業に弁当を届ける食事補助の形態です。
栄養バランスに配慮した食事を提供できるため、従業員の健康促進に効果があります。
弁当配送会社が配達から回収までを行うため、企業側の負担が少ないのが特徴です。
社員食堂の設置と比べて初期投資が少なく、スペースの制約も少ないため、中小企業でも導入しやすいメリットがあります。
さらに、従業員が同じ時間に食事をとることでコミュニケーションが生まれやすく、福利厚生として導入すると社員満足度の向上にもつながります。
オフィスコンビニ
オフィスコンビニは、企業内に小規模なコンビニエンスストアを設置し、従業員が手軽に食品や飲料を購入できるようにするサービスです。
企業が商品代の一部を負担すれば、従業員は通常のコンビニよりも安く商品を購入できます。
24時間いつでも利用できるため、シフト勤務や残業の多い職場に適しています。
また、チケットレストランのようなICカード型の食事補助サービスでは、全国の大手コンビニチェーンで利用できるものもあり、外勤の多い従業員にも公平に福利厚生を提供できるのがメリットです。
コンビニ利用型の食事補助は、従業員が自分の好みや都合に合わせて食事を選べる自由度の高さが特徴で、多様な働き方に対応できる現代的な食事補助として注目されています。
関連記事>>オフィスコンビニの導入で期待できる福利厚生の効果|今後の展望も解説
食事補助制度を導入するときの注意点
食事補助制度を導入する際には、福利厚生費として認められる条件や非課税対象となる要件を正確に理解することが重要です。
以下の注意点についてそれぞれ解説します。
- 福利厚生費として認められる条件
- 食事補助の非課税対象と上限金額
- 給与課税扱いになるケースとは
- チケットレストラン利用時のデメリットと注意点
福利厚生費として認められる条件
食事補助の費用を福利厚生費で処理するためには、主に2つの要件を満たす必要があります。
- 従業員が食事代の50%以上を負担していること
- 会社負担額が1ヶ月あたり3,500円(税別)以下であること
例えば、月の食事の費用が7,000円の場合、従業員が3,500円、会社が3,500円を負担すれば非課税となります。
また、食事補助は全従業員を対象とし、社会通念上の常識の範囲内の金額である必要があります。
これらの条件を満たさない場合、給与として課税対象となるため注意が必要です。
食事補助の非課税対象と上限金額
食事補助の非課税対象と上限金額は提供方法によって異なります。
通常の勤務時間内の食事補助では、以下の条件を両方満たす場合に非課税となります。
- 会社負担額が月3,500円(税別)以下
- 従業員が食事代の50%以上を負担している場合
残業中や宿日直勤務の場合は、現物支給であれば全額が福利厚生費として非課税の処理が可能です。
また、深夜勤務(午後10時から翌日午前5時)で現物支給が困難な場合は、1食あたり300円(税抜き)以下の現金支給は非課税の扱いになります。
また、食事券や引換券の場合は、月額5,500円までが非課税となるケースもあります。
給与課税扱いになるケースとは
食事補助が給与課税扱いになるケースには、主に以下のパターンがあります。
- 現金で支給する場合(深夜勤務の例外を除く)
- 食事補助の対象が全従業員ではない場合
- 社会通念上の常識の範囲を超える金額の場合
- 従業員の負担額が50%未満の場合
- 会社の負担額が月3,500円(税別)を超える場合
多くのパターンがあるため、福利厚生として食事を提供する際は注意しましょう。
チケットレストラン利用時のデメリットと注意点
チケットレストランを導入する際の注意点は、残高に有効期限があることが挙げられます。
チャージ日から1年後の月末までが利用期限となるため、従業員への定期的な周知が必要です。
また、購入できるものは就業時間内にとる食事や飲み物に限定されるため、食品以外の商品やアルコール類、家庭用の食材は購入できません。
さらに、非課税枠を活用するためには対象となる従業員への公平な提供が前提となります。
希望者のみに提供する場合でも、後から利用を希望する従業員が参加できるよう、制度を決める際に参加条件や申請方法を明確にしておくことが重要です。
食事補助制度の導入ステップ
福利厚生で食事補助制度を検討する際は、以下のとおり実行するとよいでしょう。流れについて、それぞれ解説します。
- 現状把握と従業員ニーズの調査
- 効果的な制度設計と社内周知
- 導入コストと運用コストの最適化
現状把握と従業員ニーズの調査
食事補助制度を導入する際は、従業員のニーズを把握することが大切です。
アンケートやヒアリングを通じて、好みのメニューやジャンル、利用を希望する時間帯、現在の昼食スタイルと費用、勤務場所によるニーズの差、アレルギーなどの特別配慮事項を具体的に調査しましょう。
社内アンケートを活用すると従業員の声を反映させた制度設計が可能になり、利用率や満足度の向上につながります。
勤務形態(内勤・外勤・リモート)によってニーズが異なるため、公平性を考慮した調査が重要です。
効果的な制度設計と社内周知
効果的な食事補助制度を設計するには、明確な目的の設定が不可欠です。
人材の定着や健康経営の推進、コミュニケーションの活性化、採用力の強化など、目的によって適した形態が異なります。
制度を設計した後は、社内ポータルや説明会を活用して従業員へ周知しましょう。
申し込み方法、チケットやクーポンの配布サイクル、食事の受け取り方などの運用フローを明確に示したうえで、どのように経費処理されるかも理解してもらうと、利用率の向上やトラブルの回避につながります。
導入コストと運用コストの最適化
食事補助の導入には、形態によって大きく異なるコスト構造を理解することが重要です。
社員食堂は設置時や運用コストが高額になりがちで、弁当、食事券、設置型サービスもそれぞれサービス料や商品代の負担が発生します。
そのため、初期費用とランニングコストを正確に見積もり、予算計画を立てることが必要です。
非課税要件を満たすことによる節税効果も考慮し、トータルコストで評価しましょう。
企業の財務状況に見合った、無理なく継続可能な計画が重要です。
また、管理や運用の手間と自社の体制を比較し、必要に応じて外部委託やシステム導入による効率化を検討すると、コストの最適化が図れるでしょう。
実際に導入した企業の成功事例紹介
多くの企業が食事補助制度を導入し、成功を収めています。
ある企業では、チケットレストランを導入したところ、オフィス勤務・外勤・在宅勤務などさまざまな勤務形態の従業員が公平に利用できる環境を整備できました。
その結果、利用率99%、継続率98%、社員満足度90%という高い数字を達成しています。
また別の企業では、健康経営の一環として食事補助を導入し、栄養バランスの取れた食事を提供することで従業員の健康状態が改善し、生産性向上につながりました。
成功事例を見ると、単なる食事の提供だけではなく、柔軟な制度設計や従業員のニーズに応じたアプローチが重要であることが分かるでしょう。
関連記事>>健康経営に繋がる福利厚生サービス4選|効果的な選び方も解説
まとめ
福利厚生で食事補助を導入すると、従業員の健康促進やエンゲージメントの向上に大きな効果が期待できます。
社員食堂や食事チケット、弁当配送サービスなど、企業の規模や勤務形態に応じた柔軟な選択も可能です。
正しい制度設計と運用を行えば従業員の満足度が高まり、採用力の強化にもつながります。
自社に合った食事補助を見つけ、働きやすい職場づくりを進めていきましょう。
TOUCH TO GO の 無人決済店舗システムを導入すると、従業員の満足度と健康意識を一緒に高められます。
福利厚生をご検討中の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/