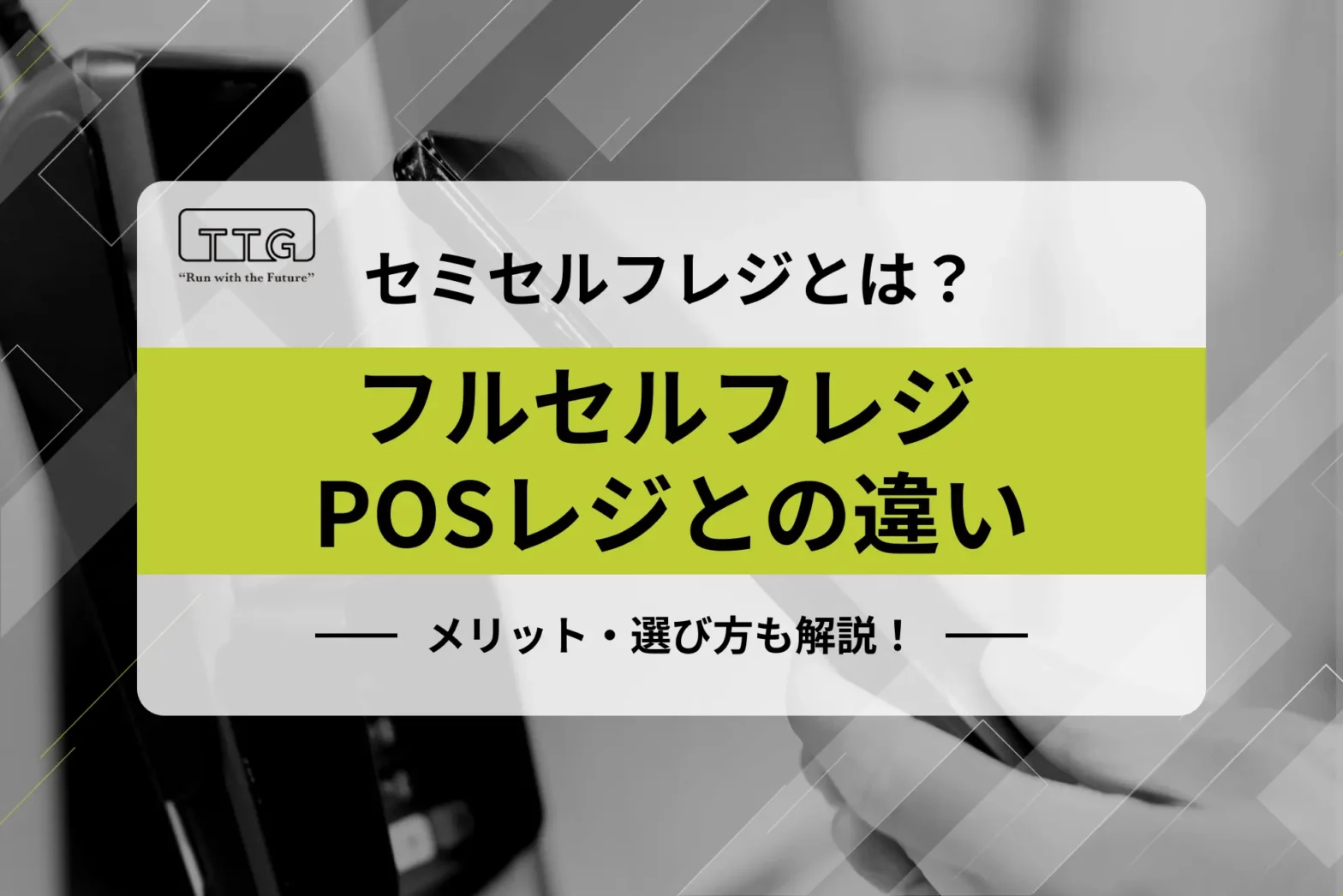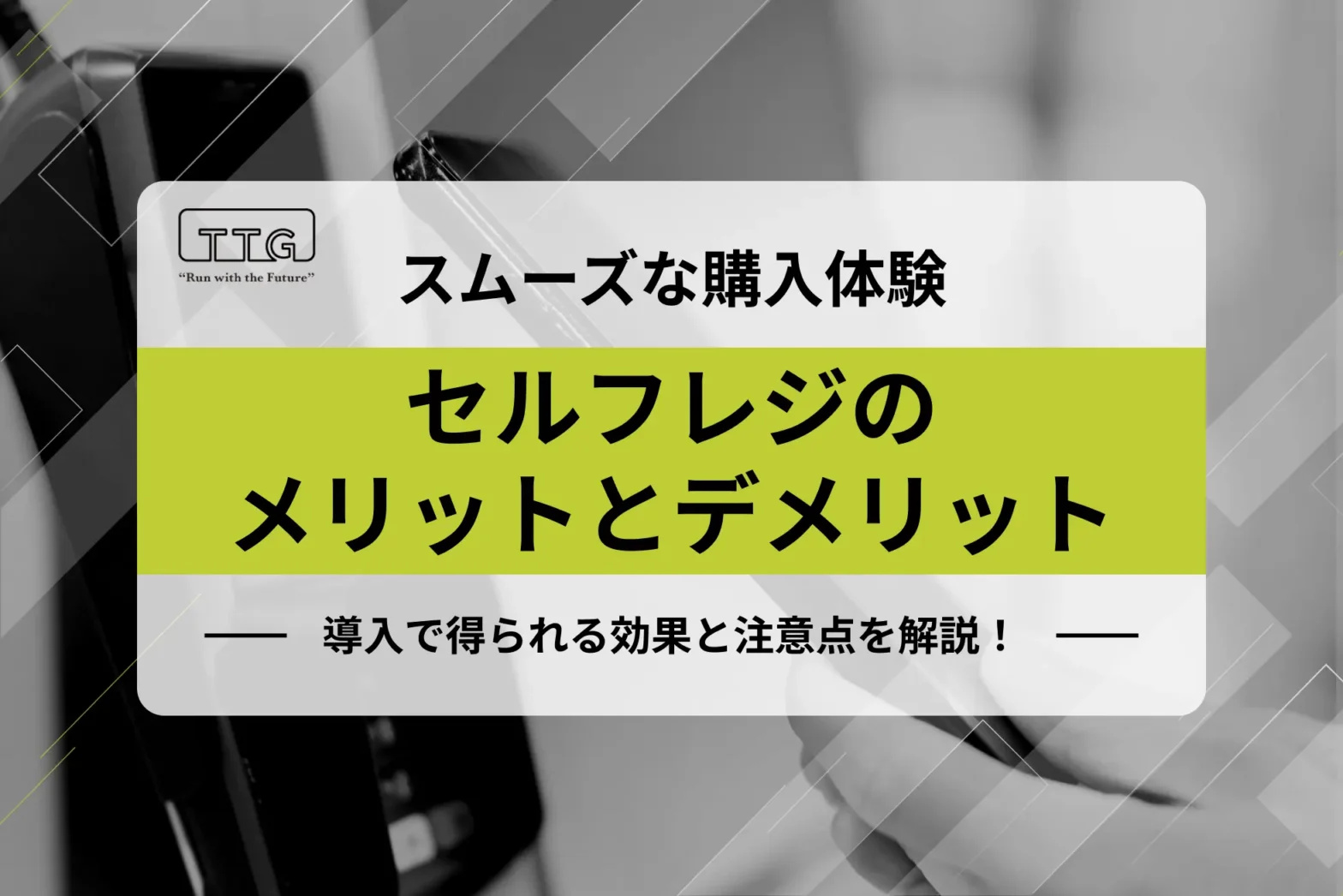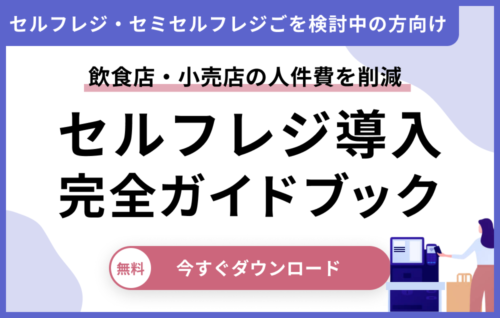Category
こんにちは。無人決済店舗システムを提供しているTOUCH TO GO 編集部です。
人手不足や業務効率化の手段として、セルフレジを導入する店舗が増えています。
一方で、導入後に「客離れが起きた」「クレームが増えた」といった声も少なくありません。
セルフレジは便利な反面、店舗側の運用ミスが原因で顧客体験を損なってしまうケースもあります。
この記事では、セルフレジによる客離れが起こる背景と具体的な対策を解説します。
これからセルフレジの導入を検討している店舗経営者・運営担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
関連記事▼
セルフレジ導入で失敗する原因7つ|対策方法や事例も紹介
セルフレジ導入のメリット・デメリットとは?選び方や導入事例も紹介!
監修者プロフィール

2019年に株式会社TOUCH TO GOを設立。無人決済店舗システムを提供し、次世代型小売の拡大に取り組んでいる。
目次
セルフレジで客離れが起こる理由
セルフレジは一見便利に思える反面、現場では「かえってストレスになる」「人を選ぶシステム」などの声も多く聞かれます。
実際、導入後に顧客の離脱が起きてしまう背景には、いくつかの共通した原因があります。ここでは、代表的な3つの理由を見ていきましょう。
操作がわかりづらい
セルフレジのインターフェースが複雑で直感的でない場合、顧客は操作に戸惑い、ストレスを感じてしまいます。
特に高齢者やデジタルデバイスに不慣れな顧客層にとっては、大きな障壁となるでしょう。
画面のレイアウトが見づらかったり、ボタンの配置がわかりにくかったりすると、操作に時間がかかり行列の発生につながります。
また、専門用語が多用されている場合や説明が不足している場合も、顧客を混乱させてしまう原因となります。
結果として、セルフレジの利用を避けて有人レジを選択したり、最悪の場合、来店自体を控えたりする可能性があります。
商品登録の負担
バーコードの読み取りにくいセルフレジや、手入力が必要な商品の登録作業は、顧客にとって大きな負担となります。
特に、生鮮食品などバーコードのない商品が多い店舗では、顧客自身が商品を探して入力する必要があるため、時間と手間がかかってしまいます。
また、商品の種類によっては個数の入力が求められるなど、操作に不慣れな顧客にとっては、大きなストレスとなるでしょう。
このような商品登録の負担は、セルフレジの利用を敬遠させるだけでなく、顧客満足度の低下にもつながる可能性があります。
サポート不足
セルフレジの操作に困ったとき、すぐにサポートを受けられない状況は顧客満足度を著しく低下させる要因となります。
特に、初めてセルフレジを利用する顧客や、操作に不慣れな顧客にとっては、近くにスタッフがいない状況では不安に感じるでしょう。
さらに、呼び出しボタンを押してもスタッフが来なかったり、質問に対する回答が曖昧だったりすると不満が募り、セルフレジの利用を避けるようになる可能性があります。
エラーの頻発
セルフレジでエラーが頻繁に発生すると、顧客は強いストレスを感じ、利用をためらうようになります。
例えば、以下のような種類のエラーが考えられます。
- バーコードが読み取れない
- 決済がうまくいかない
- システムがフリーズ
エラーが発生するたびにスタッフを呼んで対応してもらう必要があり、結果的に時間と手間がかかってしまいます。
また、エラーが原因不明な場合やスタッフによる対応が遅い場合は、顧客の不満はさらに高まるでしょう。
このようなエラーの頻発はセルフレジの信頼性を損ない、顧客離れを加速させる可能性があります。
店員の態度や対応への不満
セルフレジ導入後も、スタッフの役割は重要です。
しかし、セルフレジに不慣れな顧客へのサポートが十分でなかったり、質問に対して冷たい対応をしてしまうと、顧客満足度の低下につながります。
たとえば、「自分でやってください」といった突き放すような言い方や、操作説明が曖昧なままだと、顧客は不快に感じやすくなります。
また、セルフレジの操作に時間がかかっている顧客に対して、せかすような態度をとることも、顧客満足度を大きく損なう原因となります。
セルフレジ導入後もスタッフの教育を徹底し、顧客に寄り添った丁寧な対応を心がけることが大切です。

操作が簡単なTOUCH TO GO の セルフ/セミセルフレジ「TTG-MONSTAR」は、1台で発売機・テーブルオーダー・セルフレジの3役をこなします。
客離れを防止できるセルフ/セミセルフレジの導入をご検討中の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TTG-MONSTAR の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download1/
【セルフレジ導入前】客離れを防ぐ方法
セルフレジ導入後に後悔しないためには、事前の準備や計画が欠かせません。
ここでは、導入前に検討しておきたい客離れ対策のポイントを6つ紹介します。
業種に合わせた機種を選ぶ
セルフレジには様々な種類があり、それぞれ得意とする業種や用途が異なります。
例えば、スーパーマーケットであれば、大量の商品をスピーディーに処理できる機種が適していますし、飲食店であればテーブル会計に対応できる機種が便利です。
また、アパレルショップであれば「RFIDタグ」に対応できる機種を選ぶことで、在庫管理の効率化にもつながります。
自社の業種や店舗の規模、顧客層などを考慮して最適な機種を選択することが大切です。
“セルフ”の範囲を検討する
セルフレジを導入する際、「どこまでを顧客に任せて、どこまでをスタッフが対応するか」を明確に決めておくことも大切です。
例えば、商品登録を顧客自身に行ってもらうか、スタッフが行うかによって、顧客の負担や満足度は大きく変わります。
とくに高齢者の多い地域や複雑な会計が多い業種では、すべての工程を顧客に任せると逆に混乱を招く場合もあります。
顧客層や利用シーンに合わせて最適な“セルフの範囲”を設定することで、使いやすさと効率のバランスが取れた運用が実現できます。
読み取りやすい機種を導入する
セルフレジの「使いやすさ」は、顧客満足に直結する要素のひとつです。
とくに以下のポイントは、顧客が「使いにくい」と感じる原因になりやすい部分です。
- バーコードの読み取り精度
- タッチパネルの反応速度
- 画面の見やすさ
特にスーパーのように高頻度で使われるレジであれば、多少コストをかけてでも、直感的に操作しやすい機種を選ぶ必要があります。
また、商品スキャンの負担を軽減するために、POSレジと連動した自動登録システムや、AI搭載で商品を認識する次世代型レジを検討する動きも進んでいます。
POSレジとセルフレジの違いについて、以下の記事で紹介しています。あわせてご覧ください。
関連記事>>POSレジ・セルフレジ・無人レジの違いを徹底解説|導入時のポイントも紹介
有人レジを残す
すべての顧客がセルフレジを快適に使えるとは限りません。
特に高齢者や慣れていない顧客にとっては、有人レジの方が安心感があり、「またこの店に来たい」と感じてもらえる要素のひとつになります。
また、大量の商品を購入する場合や複雑な会計処理が必要な場合は、有人レジの方がスムーズに対応できる場合があります。
店舗の規模や顧客層などを考慮し、既存の有人レジを残すことも検討しましょう。
店舗レイアウトを工夫する
セルフレジの導入にあわせて、レジ周辺のレイアウトも見直すことが大切です。
例えば、導線が分かりづらいと混雑や操作ミスを招く原因になりますし、プライバシーが確保されていないと顧客が不安を感じることもあります。
そこで、セルフレジの近くに袋詰めを行うためのスペースを設けたり、有人レジとセルフレジの場所を明確にするための仕切りを置いたりするのも有効です。
顧客満足度を高める仕組みづくりを考える
セルフレジの導入を単なるコスト削減策と捉えるのではなく、顧客満足度を高めるための仕組みづくりを意識する必要があります。
例えば、セルフレジの利用者にポイントを付与したり、クーポンを配布したりすることで、利用を促進できるでしょう。
また、セルフレジの利用状況や顧客からのフィードバックを分析し、改善点を見つけ出すことも大切です。
さらに、顧客の意見を積極的に取り入れ、セルフレジの操作性やサービスを改善していくことで、顧客満足度の向上を目指せます。
【セルフレジ導入後】客離れを防ぐ方法
セルフレジは便利な反面、導入や運用の仕方によっては顧客に不便さを感じさせてしまうこともあります。
ここでは、セルフレジを顧客に快適に使ってもらい、客離れを防ぐために押さえておきたい2つのポイントを紹介します。
操作方法をわかりやすく書いておく
セルフレジに慣れていない人にとって、「どう操作すればいいのか分からない」というのは大きなストレスです。
特に高齢の顧客や、普段あまりセルフレジを使わない層にとっては、画面の案内だけでは不十分な場合もあります。
そうした不安を和らげるためには、セルフレジのそばに図解つきの操作案内やよくある質問とその答えを掲示するのが効果的です。
たとえば「袋の有無はどこで選ぶの?」「クーポンはいつ出すの?」など、実際によく聞かれる操作ポイントをピックアップして、簡潔にまとめておくと親切です。
お店の雰囲気に合ったデザインで掲示すれば視認性も向上し、ストレスを感じさせずに誘導できます。
スタッフの教育を強化する
セルフレジは無人でも、運営は人が支えるものです。特に導入初期は戸惑う顧客も多いため、スタッフによるサポート対応が店舗全体の印象を左右します。
「聞いてもすぐに対応してくれない」「説明がわかりにくい」といった声が出ないように、セルフレジに関する基本知識と、接客対応の両面から教育しましょう。
また、トラブル時の対応フローや言葉遣いなど、オペレーションを統一しておくこともポイントです。
セルフレジの客離れ以外の課題
セルフレジの導入によって効率化が期待される一方で、店舗運営側としては別のリスクも浮かび上がってきます。
とくに「万引き」や「意図しない不正行為」は、有人レジと比べて起きやすく、対策を怠ると損失につながりかねません。
ここでは、客離れ以外で店舗が直面しやすい2つの課題を見ていきます。
万引きの増加
セルフレジでは、レジ操作をスタッフがしないため、どうしても死角が生まれやすくなります。
人の目が届きにくいことを逆手にとって、意図的に商品をスキャンせずに持ち帰るといった不正行為が起こるケースも少なくありません。
特に、混雑時や少人数運営の時間帯などは、レジ周辺の監視が手薄になりがちです。
そこで、防犯カメラの増設やスタッフによる巡回、レジ前に「防犯中」のサインを掲示するなど、抑止力を意識した対策が必要です。
セルフレジの万引きが発生する理由について、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
関連記事>>セルフレジで万引きが発生しやすい理由|事例・手口と対策方法も解説
意図しない不正行為の増加
セルフレジに慣れていない利用者が、操作を誤ったり手順を飛ばしてしまったりすることで、結果的に会計ミスが発生してしまうケースも考えられます。
たとえば、「バーコードの読み取りを忘れて袋に入れてしまった」「割引が適用されていると思い込んでスキャンを省略した」といった“無自覚な不正”も発生するかもしれません。
こうしたケースでは、店舗側が注意喚起を怠ると、顧客とのトラブルに発展する可能性もあるため、誤操作を防ぐための案内表示や丁寧な説明が必要です。
まとめ
セルフレジの導入は、業務効率や人件費の削減といった大きなメリットがある一方で、顧客に「使いづらい」と感じられれば、客離れや不満につながる可能性もあります。
本記事では、セルフレジによって起こりやすい課題や不満の背景、さらに課題解決のための実践的な対策を紹介してきました。
導入前にしっかり準備をすることで、セルフレジの効果を最大限に活かすことができます。
以下の記事で、セルフレジの導入に必要な費用を解説しています。あわせてご覧ください。
操作が簡単なTOUCH TO GO の セルフ/セミセルフレジ「TTG-MONSTAR」は、1台で発売機・テーブルオーダー・セルフレジの3役をこなします。
客離れを防止できるセルフ/セミセルフレジの導入をご検討中の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TTG-MONSTAR の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download1/