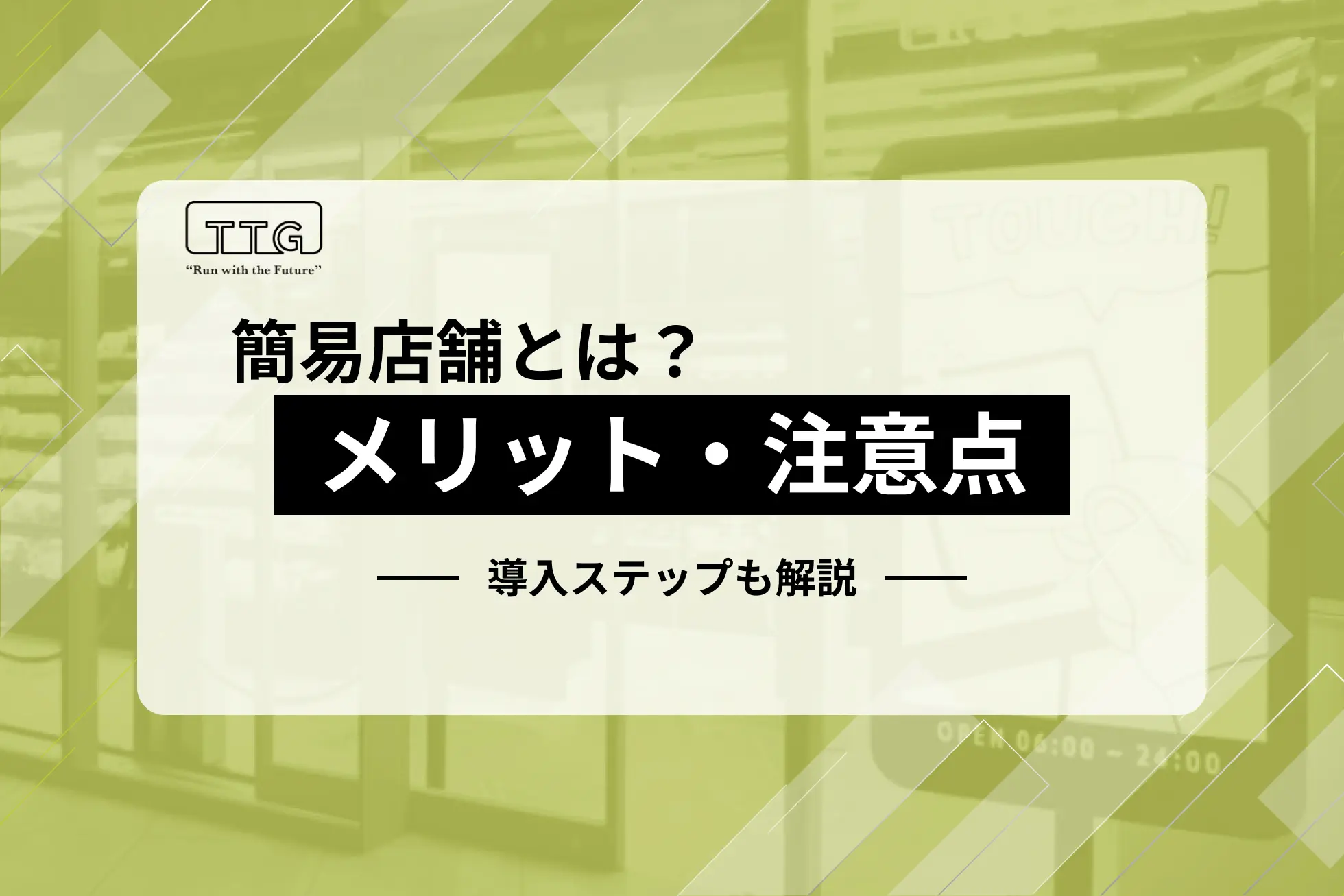Category
こんにちは。無人決済店舗システムを提供しているTOUCH TO GO 編集部です。
低コストかつ短期間で開業できる「簡易店舗」が、柔軟な出店手段として注目されています。
従来の常設店舗に比べて初期投資や運営負担を抑えやすく、省人化や移動販売などにも対応しやすいのが特徴です。
本記事では、簡易店舗の基本的な特徴から導入のメリット・注意点、実際の導入ステップまでを経営者向けに解説します。
限られたリソースでも新たな商機を生み出せる選択肢として、検討の参考にしてみてください。
監修者プロフィール

2019年に株式会社TOUCH TO GOを設立。無人決済店舗システムを提供し、次世代型小売の拡大に取り組んでいる。
目次
簡易店舗とは?
簡易店舗とは、比較的短期間で設置・撤去が可能な仮設型の店舗を指します。
常設の建物とは異なり、建築工事を必要とせずに設置できるため、開業までの時間やコストを抑えられるのが大きな特長です。
代表的なものとして、以下のような形態が挙げられます。
- ユニットハウス型
- コンテナ型
- トレーラー型の移動店舗
- 仮設ブース
これらは一時的な販売拠点として使われることも多く、設置場所の自由度が高いのもポイントです。
商業施設の一角・空き地・イベント会場・駅前スペースなど、一定の条件を満たせばさまざまな場所で展開可能です。
簡易店舗は「仮設」であることを前提として設計されているため、内装や設備は必要最低限に抑えられているケースが一般的です。
しかし、近年ではデザイン性に優れた外観や、冷暖房・給排水設備を備えた高機能なタイプも増えており、用途や業種に応じた選択肢も広がっています。
常設店舗と比べると耐久性や規模に制限はあるものの、スピード感と柔軟性に優れた営業手段として、幅広い業態にとって導入しやすい選択肢のひとつとなっています。
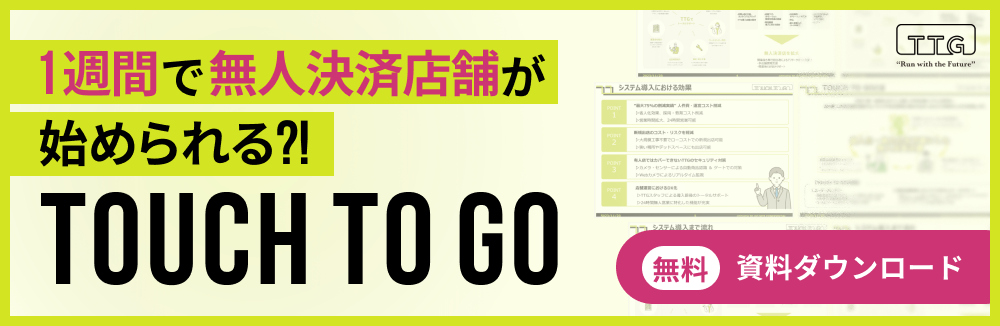
TOUCH TO GOは、人物と商品を店内カメラで認識、レジの前に立つだけで自動で商品が表示される無人決済システムです。
省人化・人件費削減が実現できる無人店舗の開業をご検討中の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/
簡易店舗のメリット
簡易店舗は、限られた資源の中でも出店を可能にする手段として、多くの経営者から注目されています。ここでは、導入によって得られる主なメリットを解説します。
低コストでの開業が可能
簡易店舗の最大の利点は、通常の店舗開業に比べて初期投資を大幅に抑えられる点にあります。
建築費や内装費が不要、もしくは最小限で済むため、資金に余裕のない段階でも比較的リスクを抑えて出店できます。
特に、テストマーケティングや期間限定の出店には適した選択肢といえるでしょう。
出店・撤退のスピードが早い
ほとんどの簡易店舗は施工期間を必要としないため、設置から営業開始までのリードタイムが短く、スピーディな開業が可能です。
また、撤退や移動も比較的容易なため、立地の見直しや季節ごとの出店にも柔軟に対応できます。出店判断のスピードが重要な業態においては、大きな武器となるでしょう。
小規模・省スペースで始められる
限られた敷地やスペースを活用できるのも、簡易店舗の特徴です。常設店舗では出店が難しいような空き地や遊休スペースでも、収益化が可能になります。
さらに、規模を抑えた運営が前提となるため、人件費や光熱費などのランニングコストも抑えやすい傾向にあります。
少人数運営・無人運用との相性が良い
近年、人手不足が深刻化する中で、「少人数体制」や「無人運営」の需要も高まっています。
簡易店舗はその性質上、省人化されたオペレーションとの相性が良く、セルフレジやキャッシュレス決済などと組み合わせることで効率的な店舗運営が可能になります。
簡易店舗のデメリットと導入時の注意点
簡易店舗は低コストかつ柔軟な出店形態である一方で、常設店舗とは異なる制約や注意点も存在します。
そのため、導入を検討する際は、以下のようなポイントを事前に把握しておくことが大切です。
法規制への対応が必要
設置場所や構造によっては、「建築基準法」や「消防法」などの法的な規制を受ける場合があります。
とくに電気・ガス・水道が必要な飲食業では、保健所や消防署への届け出が必要になるケースもあります。
また、簡易店舗といえども自治体によっては「建築物」として扱われることがあるため、設置前に行政への確認を怠らないよう注意が必要です。
許可が得られないと、設置後に撤去を命じられるリスクもあります。
設備面の制限に注意
簡易店舗は構造上、スペースや設備に制限がある場合が多く、常設店舗と同じ感覚で運営を始めるとギャップが生じやすくなります。特に注意すべきは、以下のような項目です。
- 電源容量
- 水回りの有無
- 空調・換気設備
これらを踏まえて事前に設備条件を整理し、導入可能な仕様かどうかを確認しておくことが大切です。
耐久性・快適性の課題
簡易店舗は”仮設性”を前提としているため、常設建物に比べると耐久性や断熱性、防音性に劣るケースがあります。
また、長期運営や悪天候時には、設置後の補強工事や追加装備の導入が必要になることもあります。
夏季や冬季の温度管理、雨風への備えなどを事前にしっかりと計画しておくことで、運営トラブル防止につながります。
ブランドイメージとの整合性
簡易店舗は設置のしやすさや機能面に優れる一方で、見た目の印象が仮設的になりがちです。
自社のブランドイメージや商品コンセプトと合致させるには、デザイン性の高い外装や什器の工夫が欠かせません。
外観・内装をうまく整えることで、「簡易=安っぽい」という印象を避け、限られたスペースでも十分に魅力的な店舗空間を演出することが可能です。
簡易店舗の導入ステップとポイント
簡易店舗の導入には、一般的な店舗開業とは異なる準備と判断が求められます。ここでは、簡易店舗を導入する際の流れと、それぞれの段階で押さえておきたいポイントを紹介します。
1. 目的とターゲットの明確化
まずは、「なぜ簡易店舗を導入するのか」という目的を明確にすることが重要です。というのも、目的が曖昧なまま進めると、機能面や運用面でミスマッチが起こりやすくなるからです。
そこで、以下のように目的を明確にしておきましょう。
- 新商品のテスト販売
- 繁忙期限定の営業
- 人件費削減を目的とした無人販売
このように目的とターゲット層を明確にすることで、適切な立地や設備要件が見えてきます。
さらに、短期的な活用なのか長期運営を想定するのかも含めて、初期段階で整理しておくことが大切です。
2. 設置場所の選定と事前確認
簡易店舗の利点は自由度の高い設置ですが、すべての場所に設置できるわけではありません。
目的や敷地の広さ、インフラの有無、周辺環境との調和など、立地面での制約や確認事項が多くあります。
また、地域によって自治体への届け出や使用許可が必要となることもあるため、土地所有者との契約条件とあわせて、早い段階での確認が求められます。
3. 設備・什器の準備と仕様確認
導入する簡易店舗の種類に応じて、必要な設備や什器も決まってきます。飲食であれば給排水や換気設備、物販であれば棚や照明、無人運営であればセルフレジや監視カメラの設置など、用途に合わせた仕様選定が必要です。
業者に依頼する場合は、設計・搬入・設置スケジュールに余裕を持って進めましょう。また、内外装を工夫してブランドイメージに沿った空間に出来るかどうかも、顧客の印象を左右します。
4. 許可申請と設営の段取り
飲食業や物販業を営む場合には、保健所・消防・建築の各種法令に基づく申請や検査が必要になることがあります。
特に簡易店舗は特殊な構造であるため、事前に関係機関へ相談しておくことがトラブル防止につながります。
また、設置当日の作業は天候や周囲の状況に影響されやすいため、日程の余裕や複数の対応パターンを想定して準備を進めましょう。
5. 運用後の評価と改善
営業開始後は、売上や来店状況、オペレーションの効率などを定期的に振り返ることで、次の出店や改善のヒントを得ることができます。
たとえば、以下のような項目を記録・分析することで、次回以降の計画に活かすことが可能です。
- 回転率
- 時間帯別の客数
- スタッフの配置状況
- 導線の見直し
簡易店舗は設計の自由度が高いため、PDCAを回しながら運用していく姿勢が成功に直結します。
簡易店舗と相性の良い業態・ビジネスモデル
簡易店舗は、短期間で設置できるという特性から、すべての業種に適しているわけではありません。
ただし、運営の柔軟性や省スペース性を活かせる業態においては、非常に有効な手段となります。ここでは、簡易店舗との親和性が高いビジネスモデルの傾向を解説します。
テスト販売・小規模スタート型業態
商品やサービスの市場反応を見ながら段階的に事業を拡大していくスタイルと簡易店舗は、非常に相性が良いといえます。
特に、初期投資を抑えながらブランドの立ち上げや新商品を試す場合、簡易店舗での小規模スタートはリスクを最小限に抑える方法として有効です。
ポップアップストア・期間限定ショップ
簡易店舗は、「期間限定で話題性を演出したい」といったプロモーション目的の出店にも適しています。
短期集中で集客を図るスタイルは仮設型の店舗と親和性が高く、商業施設の一角や空きスペースなどを活用しやすい点も利点です。
とくにSNSとの相乗効果を狙うような企画型ストアでは、「短期間だからこその特別感」が購買意欲を刺激する材料となります。
無人販売・省人運営型ビジネス
人件費の削減や営業時間の拡大を目的とした無人運営にも、簡易店舗は向いています。
特に、『TOUCH TO GO』のような無人決済システムや『TTG-MONSTAR』のようなセミ/セルフレジと、監視カメラなどの設備と組み合わせれば最低限の監視体制で営業が可能です。
近年では、食品や飲料の無人販売・冷凍商品の販売ブース・セルフ型カフェなど、非接触型サービスの広がりに対応する簡易店舗の活用事例も増えています。
関連記事▼
移動販売やイベント連動型ビジネス
トレーラー型や可搬型の簡易店舗は、イベント出店や観光地での短期営業などで強みを発揮します。
必要なタイミングに合わせて設置・撤去できることから、季節ごとの出店や移動販売といった機動力を活かすビジネスに適しています。
また、地方自治体や商業施設とのタイアップによる出店も検討しやすく、初期負担を抑えた事業展開に役立つケースもあります。
まとめ
簡易店舗は、低コストかつスピーディに出店できる柔軟な営業手段として、多くの企業や個人事業主にとって現実的な選択肢となりつつあります。
限られたスペースでも運営が可能で、省人化や短期出店といったニーズにも対応できる点は、今の時代に非常にマッチしているといえるでしょう。
一方で、法規制や設備の制限といった特有の注意点もあるため、導入にあたっては目的の明確化と事前準備が欠かせません。
設置場所の選定から設備の仕様、行政とのやり取りまでをしっかりと把握し、段階的に進めていくことが成功への鍵となります。
柔軟な営業スタイルを模索している方は、ぜひ選択肢のひとつとして導入を検討してみてはいかがでしょうか。
関連記事▼
TOUCH TO GOは、人物と商品を店内カメラで認識、レジの前に立つだけで自動で商品が表示される無人決済システムです。
省人化・人件費削減が実現できる無人店舗の開業をご検討中の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/