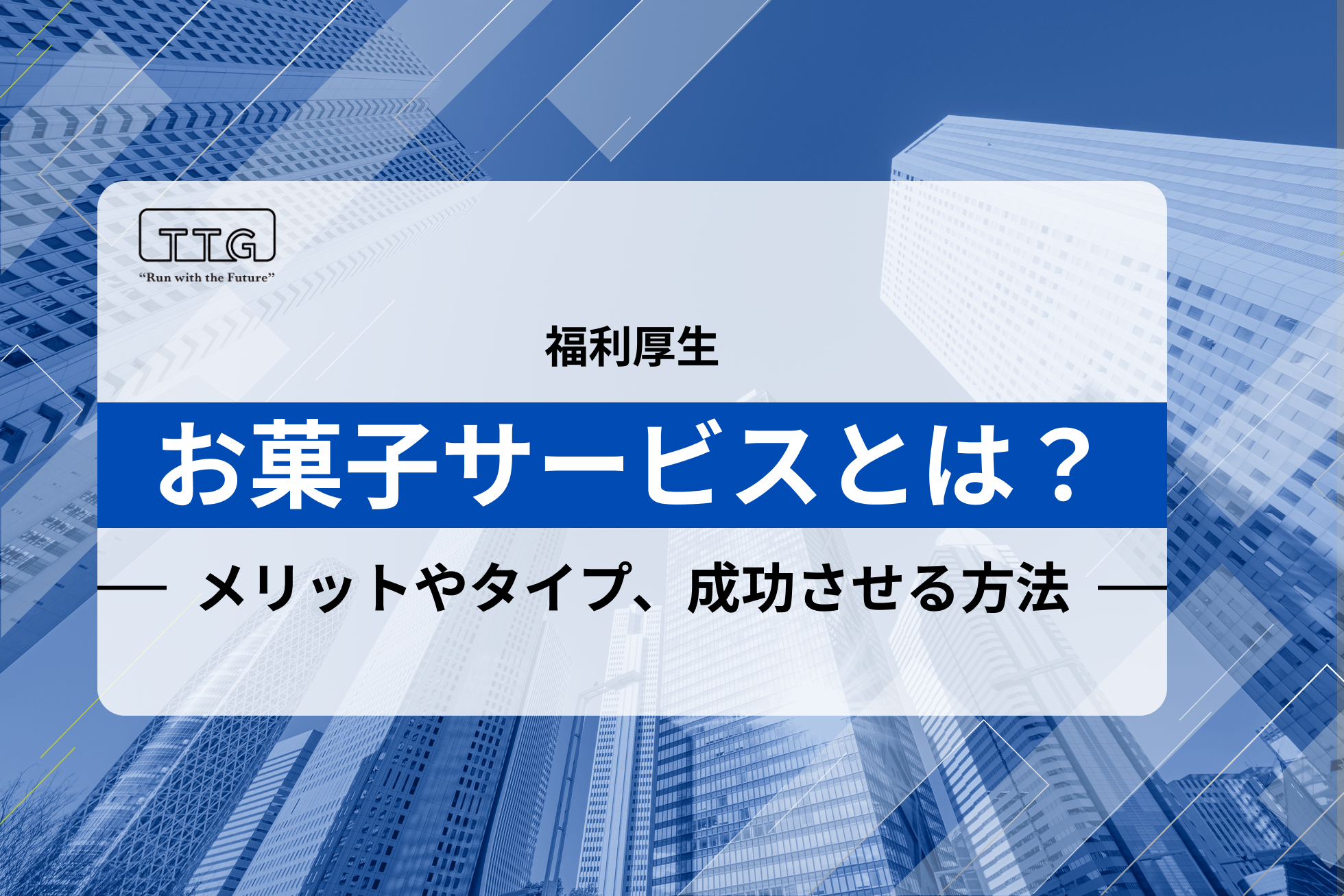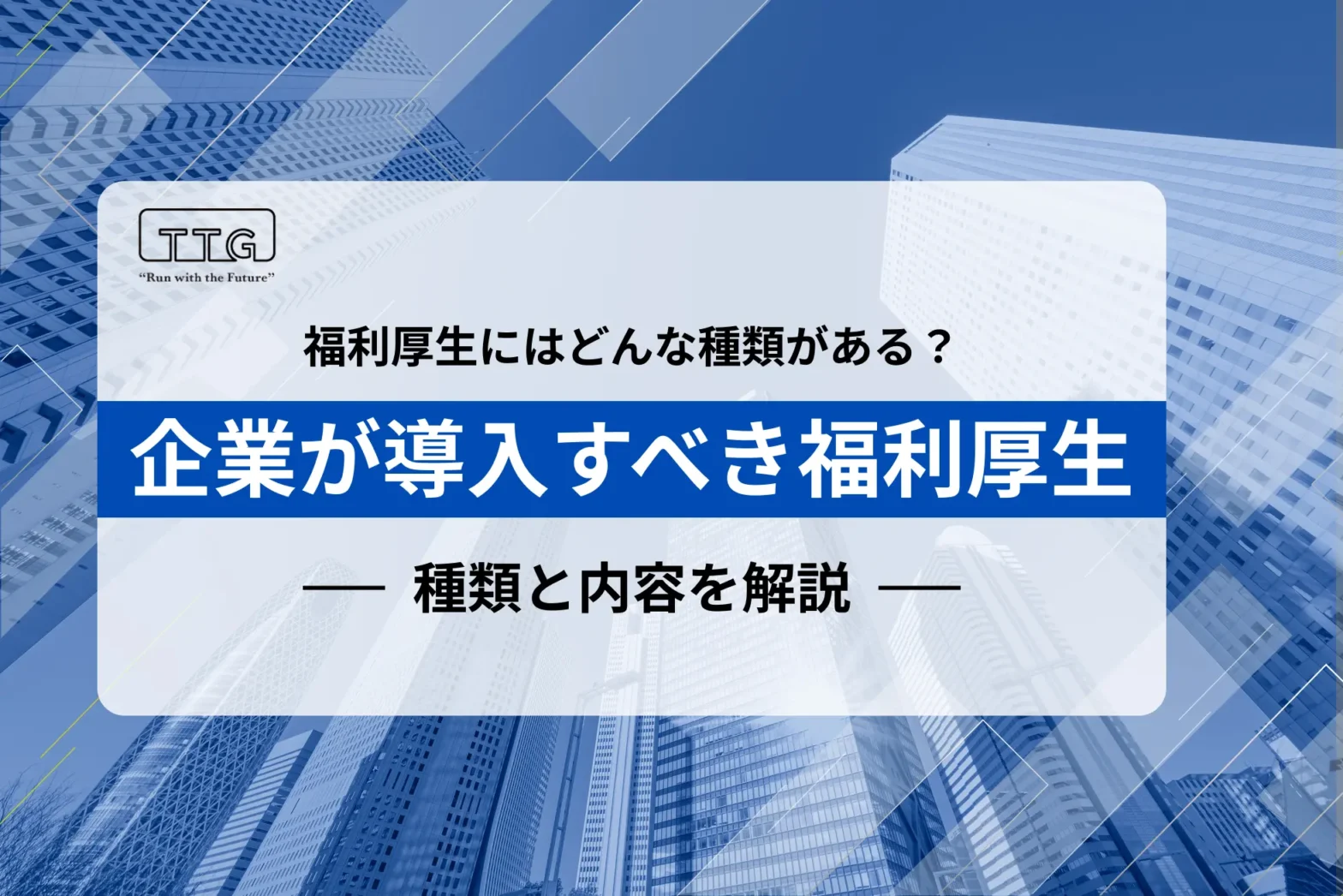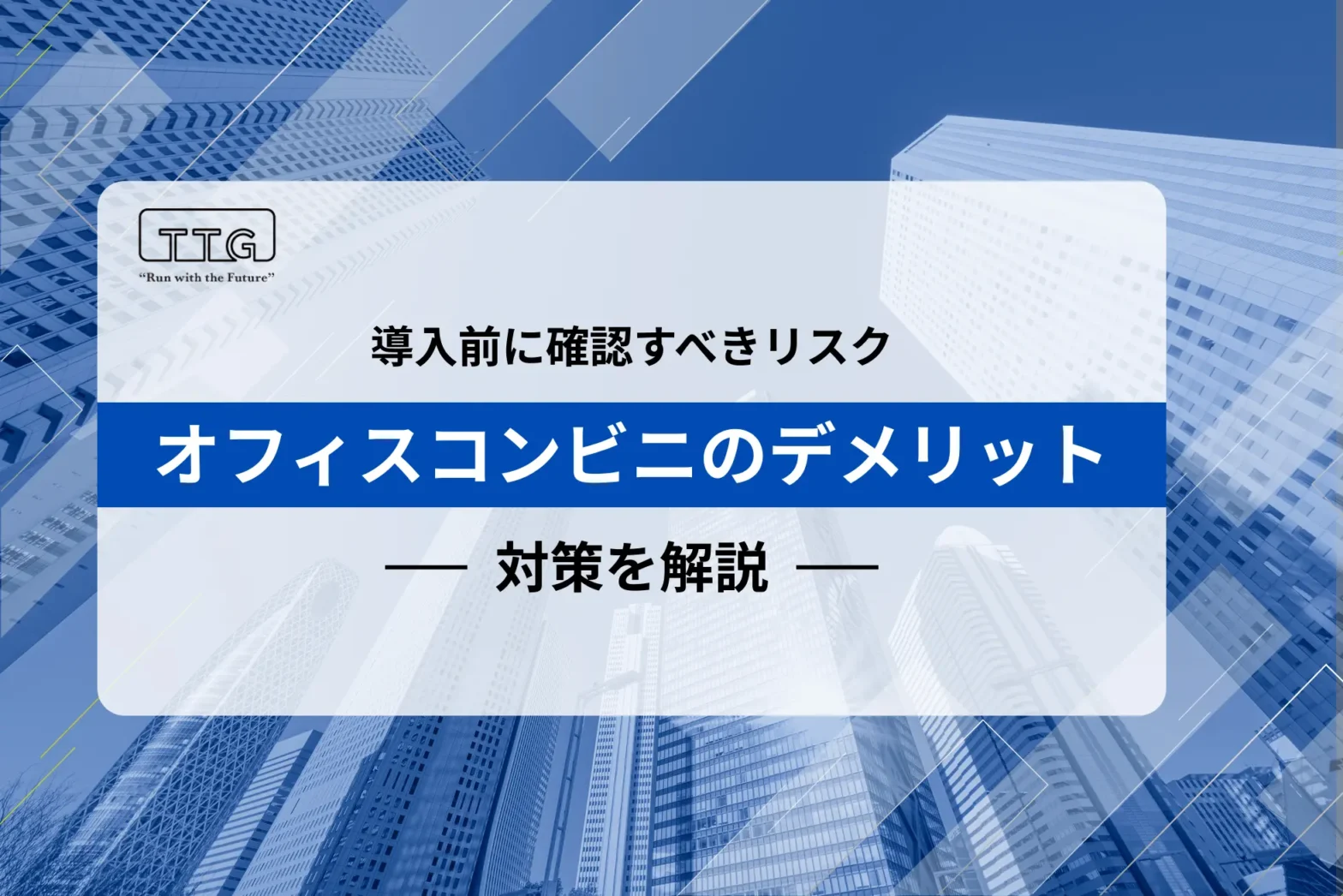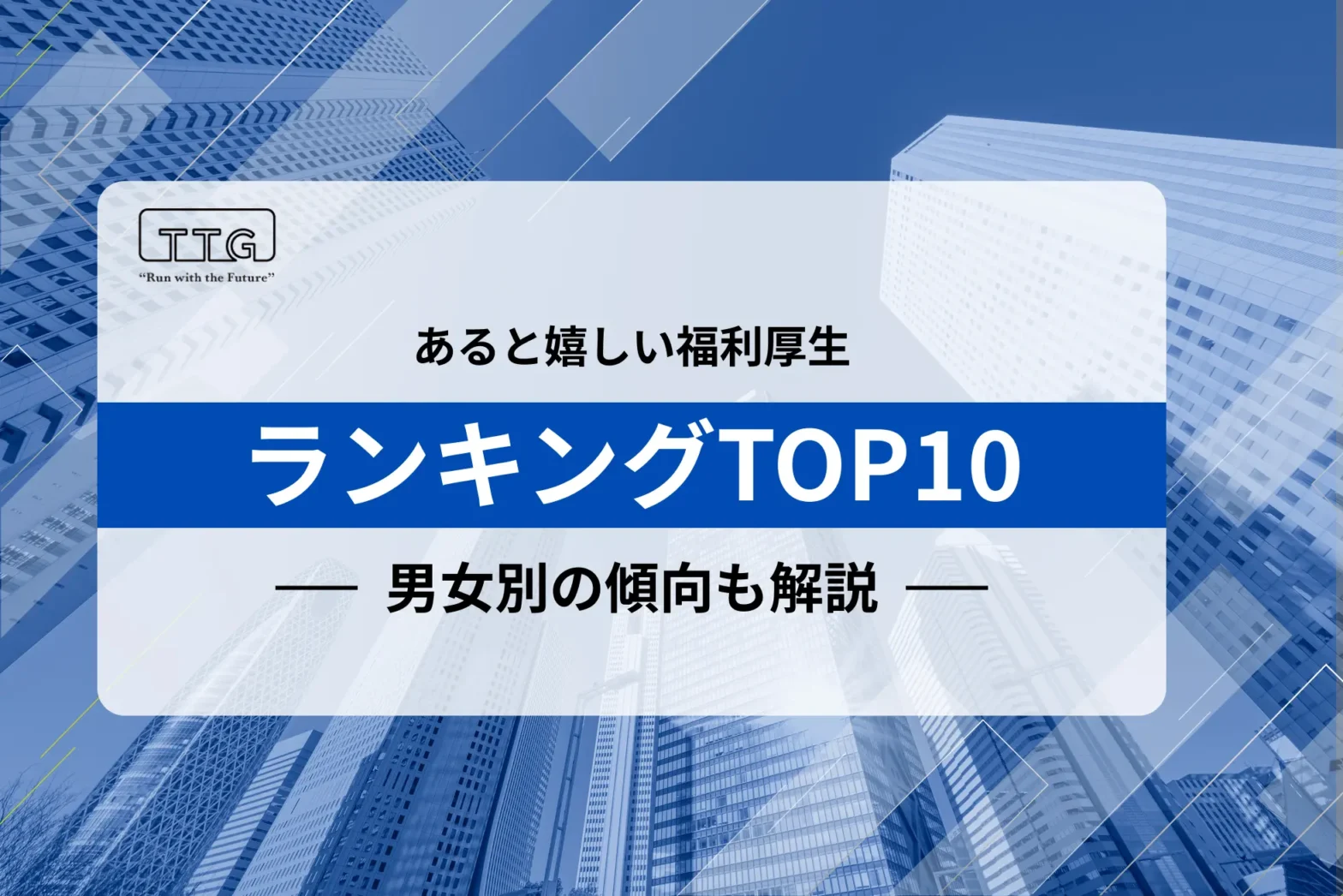Category
こんにちは。無人決済店舗システムを提供しているTOUCH TO GO 編集部です。
従業員のために働く環境をもっと良くしたいと考えたとき、福利厚生として社内にお菓子を置く方法がおすすめです。
本記事では、福利厚生としてオフィスに置き菓子を導入するメリットとサービスのタイプや特徴、導入ステップや経理処理について解説しています。
従業員の満足度を向上させつつ適切な経理処理ができるため、ぜひ最後までご覧ください。
監修者プロフィール

2019年に株式会社TOUCH TO GOを設立。無人決済店舗システムを提供し、次世代型小売の拡大に取り組んでいる。
目次
福利厚生としてオフィスに置き菓子を導入するメリット
オフィスの置き菓子は、従業員の満足度向上やコミュニケーションの活性化などにつながる福利厚生として注目されています。
主なメリット5つについて、それぞれ解説します。
- エンゲージメントの向上
- コミュニケーションの活性化
- 生産性と集中力の維持
- 低コストで始められる福利厚生
- 採用ブランディングへの寄与
エンゲージメントの向上
オフィスにお菓子を置くことにより、従業員のエンゲージメントの向上に大きく貢献します。
企業が主体となって置き菓子を提供すると、従業員は気兼ねなく休憩を取れる風潮が生まれ、会社への帰属意識が高まるからです。
「会社が自分たちのことを考えてくれている」という実感が生まれ、従業員は会社に対してより強い愛着を持つようになるでしょう。
若手社員の定着率向上や、リモートワークとオフィスワークのハイブリッド環境下での出社意欲の向上にも効果があると言われています。
コミュニケーションの活性化
従業員が集まりやすいリフレッシュコーナーにお菓子を設置すると、コミュニケーションの活性化につながるという事例も報告されています。
同じお菓子を一緒に食べると自然と会話が生まれ、チームワークが強化できるメリットがあります。
特に部署間の交流が少ない職場では、お菓子を介して異なる部署の社員同士が仲良くなるきっかけになるでしょう。
生産性と集中力の維持
オフィスにお菓子を置くと、従業員は仕事の合間にリフレッシュできるため、集中力の維持や生産性の向上につながります。
また、コンビニなどへ買いに行く時間を削減できるため、仕事を中断する時間が減って業務効率が向上する利点もあります。
特に残業中や締め切り前の忙しい時期には、オフィス内で手軽に栄養補給ができると、体力や集中力を維持したまま業務を続けられるメリットがあるのです。
健康に配慮した無添加のお菓子を提供するサービスもあり、罪悪感なく楽しめるため、心身ともにリフレッシュできる効果が高まるでしょう。
低コストで始められる福利厚生
オフィスの置き菓子サービスは、初期費用やランニングコストが比較的低く、低予算でも導入しやすい福利厚生です。主な導入形態は次のとおりです。
- 無料設置プラン(設置スペースや電気代のみ負担し、お菓子は実費で購入)
- 定額制プラン(毎月定額で、お菓子の消費量に応じて補充)
- 成果報酬型プラン(お菓子の売り上げに応じて手数料を支払う)
導入形態は自社のニーズや予算に合わせて選べます。
置き菓子サービスは設置代金が不要なケースもあり、費用対効果も高いと言われています。
従業員がお菓子を買いに行く時間を削減できるため、業務効率の向上にもつながり、経済的なメリットも大きいといえるでしょう。
採用ブランディングへの寄与
オフィスの置き菓子は、企業の採用ブランディングにも大きく貢献します。
人材獲得の競争が激しい現代において、福利厚生の充実は求職者が企業を選ぶ際の重要な判断材料となっているからです。
そのため、置き菓子のような小さな福利厚生でも「従業員を大切にする企業文化」をアピールできる効果があります。
特に若手社員や新卒採用において、オフィス環境の快適さや企業文化の魅力を伝える要素として機能するでしょう。
人材の定着率を上げる効果も期待でき、採用コストの削減にもつながります。
関連記事>>「あると嬉しい福利厚生」ランキングTOP10|男女別の傾向も解説
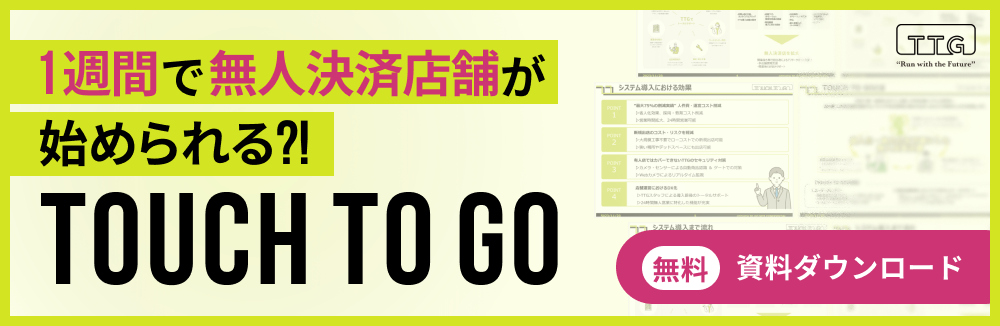
TOUCH TO GO の 無人決済店舗システムを社内に設置すると、お菓子だけでなく弁当や飲料などもすぐに購入できるため、忙しい日でもストレスなく利用できます。
無人決済店舗システムの導入をご検討中の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/
置き菓子サービスのタイプと特徴
オフィスにお菓子を置くサービスには、さまざまなサービスがあります。
タイプによって初期費用や運用コストなどが異なるため、会社の規模や従業員のニーズ、設置スペースなどを考慮して適したサービスを選びましょう。
置き菓子サービスの主なタイプと特徴をそれぞれ挙げていきます。
- 無人販売ラック
- サブスクリプション
- 社内コンビニ
- スマート自販機
無人販売ラック
無人販売ラック常設型は、オフィスの一角に専用の棚や什器を設置し、お菓子や飲料を陳列するタイプです。
「オフィスグリコ」や「スナックミーオフィス」などが代表的なサービスで、初期費用やランニングコストが不要なケースが多いのが特徴です。
従業員は欲しい商品を自由に取り、現金を入れる貯金箱方式やキャッシュレス決済、専用LINEアプリなどで支払います。
設置スペースや電源のみ確保すればすぐに導入できるため、小規模なオフィスでも手軽に始められるのがメリットです。
商品の補充はサービス会社が定期的に行うため、担当者の負担が少ないのもポイントといえるでしょう。
近年ではAIを活用して購入データを分析し、オフィスごとに適したお菓子を提案するサービスも登場しています。
サブスクリプション
サブスクリプションは、定額料金を支払うと定期的にお菓子や飲料が届くサービスです。
「snaq.me office」などが代表で、管理栄養士が監修した健康的なお菓子や、パティシエが開発した美味しいお菓子が定期的に届く場合もあります。
従業員は無料または一部負担で利用でき、企業側は福利厚生費として一括購入するケースが多いと言われています。
商品の種類や量は企業の規模や予算に応じてカスタマイズでき、健康志向のお菓子やプロテインバー、コーヒーなど多くのコースから選べる場合もあるのです。
フードロスを減らすため、消費状況に合わせて次回の配送量を調整できるサービスもあります。
そのため「賞味期限の切れたお菓子が残ってしまった」「今月は営業日が少ないので、お菓子があまり減っていない」という場合も安心して導入できるでしょう。
社内コンビニ
社内コンビニは、オフィス内にミニコンビニのような売場を設置するタイプです。
お菓子だけでなく弁当やおにぎり、パン、飲料、日用品など幅広い商品を取り揃えています。
冷蔵・冷凍設備を備えたものが多く、温かい食事や冷たい飲み物も提供できるのが利点です。
100名以上の従業員がいる大規模オフィスや工場、官公庁などが導入対象となるのが一般的です。
キャッシュレス決済に対応しており、24時間いつでも利用できるため、残業時や夜勤、休日出勤の際にも重宝します。
設置スペースが比較的大きく必要となりますが、福利厚生の一環として従業員割引を適用できるプランもあり、満足度向上に貢献するでしょう。
関連記事>>オフィスコンビニの導入で期待できる福利厚生の効果|今後の展望も解説
スマート自販機
スマート自販機は最新技術を活用した無人販売機で、従来の自販機よりも多機能かつ省スペースで設置できるタイプです。
「Store600」や「ミニストップポケット」「セブン自販機」などが代表的で、スマートロックやカメラ付きの冷蔵庫タイプのものが多くあります。
専用アプリやICカードで解錠や決済を行うため、セキュリティ面も安心です。
商品ラインナップはお菓子、飲料、食品、雑貨など多岐にわたり、冷蔵食品も取り扱えるのが特徴です。
設置費用やメンテナンス費用が不要なケースが多く、運用の手間もかからないため、中小企業でも導入しやすい利点があります。
また、商品の補充や集金の手間がなく、在庫管理もスマート自販機会社に任せられるため、社内担当者の負担が少ないのも魅力といえるでしょう。
お菓子の福利厚生を成功させる導入ステップ
福利厚生としてオフィスにお菓子を置くのは、従業員の満足度向上やコミュニケーションの活性化に効果があると言われています。
しかし、単に置くだけでは成功しないかもしれません。
設置する前に目的を明確にし、従業員のニーズを把握したうえで適切なサービスを選定することが大切です。
主な導入ステップを次のとおり解説します。
- ニーズと課題の把握
- サービスの比較と選定
- テスト導入
- 社内ルールと周知
- 本格導入と運用モニタリング
- 効果測定と改善サイクル
ニーズと課題の把握
お菓子の福利厚生を導入する前に、従業員のニーズと現状の課題を正確に把握することが大切です。
アンケートやヒアリングを通じて「どのようなお菓子が好まれるか」「どのタイミングで利用したいか」「健康志向の有無」などの情報を収集しましょう。
また、オフィス環境の課題(コミュニケーション不足、疲労感、出社意欲の低下など)も明確にし、置き菓子の導入によってどの課題を解決したいのかを特定します。
例えば、部署間の交流が少ない場合は、共有スペースに置き菓子コーナーを設けてコミュニケーションの活性化を図るなど、目的に合わせた導入計画を立てることが重要です。
導入の目的を「従業員の満足度向上」「コミュニケーションの促進」「生産性の向上」など具体的に設定すれば、後の効果測定もしやすくなるでしょう。
関連記事>>健康経営に繋がる福利厚生サービス4選|効果的な選び方も解説
サービスの比較と選定
置き菓子サービスには、無人販売ラック、サブスクリプション、社内コンビニ、スマート自販機など多くのタイプがあります。
各サービスの特徴やコスト、商品ラインナップ、決済方法などを比較検討し、自社のニーズに適した商品を選定しましょう。
選定の際は、設置スペースの確保や予算、管理の手間などを考慮します。
特に健康経営を推進したい場合は、健康志向のお菓子を提供するサービスを選ぶと良いでしょう。
また、キャッシュレス決済の有無も重要な選定ポイントです。
テスト導入
本格導入の前に小規模なテスト導入を行うと、リスクを最小限に抑えながら効果を検証できます。
テスト導入では、特定のフロアや部署に限定して置き菓子サービスを提供し、利用状況や従業員の反応を観察しましょう。
この期間中に「どのお菓子が人気か」「利用頻度はどうか」「運用上の問題点はないか」などを確認します。また、支払方法や在庫管理の仕組みが適切に機能しているかも検証します。
テスト期間は1〜3ヶ月程度設け、その結果をもとに本導入の可否や改善点を検討しましょう。テスト導入の結果を従業員にフィードバックし、意見を集めると、本格導入時の満足度向上にもつながります。
社内ルールと周知
福利厚生で置き菓子サービスを導入する際は、利用に関する明確なルールを設定し、全従業員に周知することが大切です。
ルールには、支払方法(現金・電子決済など)、利用時間、未払時の対応などを含みます。
また、お菓子の設置場所も重要です。従業員が気軽に立ち寄れる場所に設置すると、利用しやすくなるメリットがあります。
社内メールやチャット、掲示板、朝礼などを活用して、導入の目的やメリット、利用方法を丁寧に説明しましょう。
また、未払いの対策として、防犯カメラの設置や従業員への注意喚起も行い、置き菓子は皆で楽しむものであることを伝えるのも大切です。
本格導入と運用モニタリング
テスト導入の結果を踏まえて改善点を反映し、良いと思ったら本格的に導入しましょう。
設置後は定期的に運用状況をモニタリングし、問題点があれば迅速に対応します。
具体的には、商品の消費状況、支払状況、従業員の利用頻度などを確認するとよいでしょう。
置き菓子会社の担当者が定期的に訪問して商品補充や料金回収を行う場合、会社側の負担は少なくなります。
一方、自社で管理する場合は、担当者を決めて在庫管理や発注、清掃などの業務を割り当てる必要があります。
また、同じお菓子ばかりを置いていると従業員が飽きる可能性があるため、定期的に新しいお菓子を導入するなど、ラインナップを工夫することも大切です。
季節限定のお菓子や地域限定のお菓子を取り入れたり、従業員のフィードバックを基にラインナップを調整したりすると、継続的な利用を促進できるでしょう。
効果測定と改善サイクル
置き菓子サービスを導入した後は定期的に効果を測定し、継続的に改善することが重要です。効果測定の指標は次のとおりです。
- 従業員満足度調査
- 利用率
- コミュニケーション頻度の変化
- 業務効率の向上
例えば、導入前後でアンケートを実施し「職場環境の満足度」「コミュニケーションの活性度」「リフレッシュ効果」などを比較すると、置き菓子を導入した効果を定量的に把握できます。
また、売上データや利用頻度を分析すれば、人気商品や利用傾向を把握できるため、より効果的なサービス提供につなげられます。
定期的に改善サイクルを回すと、従業員のニーズに合った持続可能な福利厚生として定着できるでしょう。
福利厚生のお菓子に対する経費処理
福利厚生として会社にお菓子を置く場合、一定の条件を満たすと「福利厚生費」として費用計上できます。
これにより、企業は税務上のメリットを得られるだけでなく、従業員の満足度向上やコミュニケーションの活性化といった効果も期待できるのです。
条件について以下のとおりまとめました。
- 福利厚生費として認められる条件
- 会社負担と従業員負担のバランス
福利厚生費として認められる条件
オフィスのお菓子を福利厚生費として経費計上するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
具体的には次の条件です。
- 機会の平等性
- 金額の妥当性
- 現物支給
まず「機会の平等性」がもっとも重要です。すべての従業員が公平にお菓子を利用できる環境を整える必要があります。
特定の部署や一部の従業員だけが利用できるケースでは、福利厚生費として認められません。
「金額の妥当性」も大切です。社会通念上、妥当と認められる範囲内の支出である必要があります。
高級菓子ばかりを提供するなど、過度に豪華な内容は認められないかもしれません。
また、現物支給であることも条件の1つで、お菓子そのものを提供する形態が望ましいとされています。
商品券やギフト券など、換金性の高いものを支給した場合は、福利厚生ではなく給与として扱われる可能性があります。
これらの条件を満たすと、オフィスのお菓子は福利厚生費として適切に経費計上でき、企業の税務負担の軽減にもつながるのです。
会社負担と従業員負担のバランス
オフィスの置き菓子における会社負担と従業員負担のバランスは、福利厚生費として認められるかどうかの重要な判断基準となります。
100%会社負担でお菓子を提供する場合は、すべての従業員が平等に利用できる環境を整え、金額が社会通念上妥当であれば福利厚生費として認められます。
一方、従業員が一部負担する社内販売方式を採用する場合は、適切な価格設定が重要です。
一般的に、通常価格の70%を下回る割引率は「経済的利益が著しく大きい」と判断され、給与課税の対象となる可能性があります。
会社負担と従業員負担のバランスを適切に設計することで、従業員の満足度を高めつつ、税務上も福利厚生費として認められる仕組みを構築できます。
関連記事>>オフィスの置き菓子は福利厚生費になる?ならない?導入前に押さえたいポイント
まとめ
福利厚生としてオフィスにお菓子を置くと、エンゲージメントや生産性の向上、コミュニケーションの活性化や採用ブランディングの強化など多くのメリットがあります。
無人ラックやサブスクなど、比較的低コストで開始できるのも特徴です。
社内のニーズ把握とテスト導入を経て本格導入すれば失敗のリスクも低減できます。また、福利厚生費として経費計上すれば税務面でもメリットが得られるでしょう。
TOUCH TO GO の 無人決済店舗システムを社内に設置すると、お菓子だけでなく弁当や飲料などもすぐに購入できるため、忙しい日でもストレスなく利用できます。
無人決済店舗システムの導入をご検討中の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/