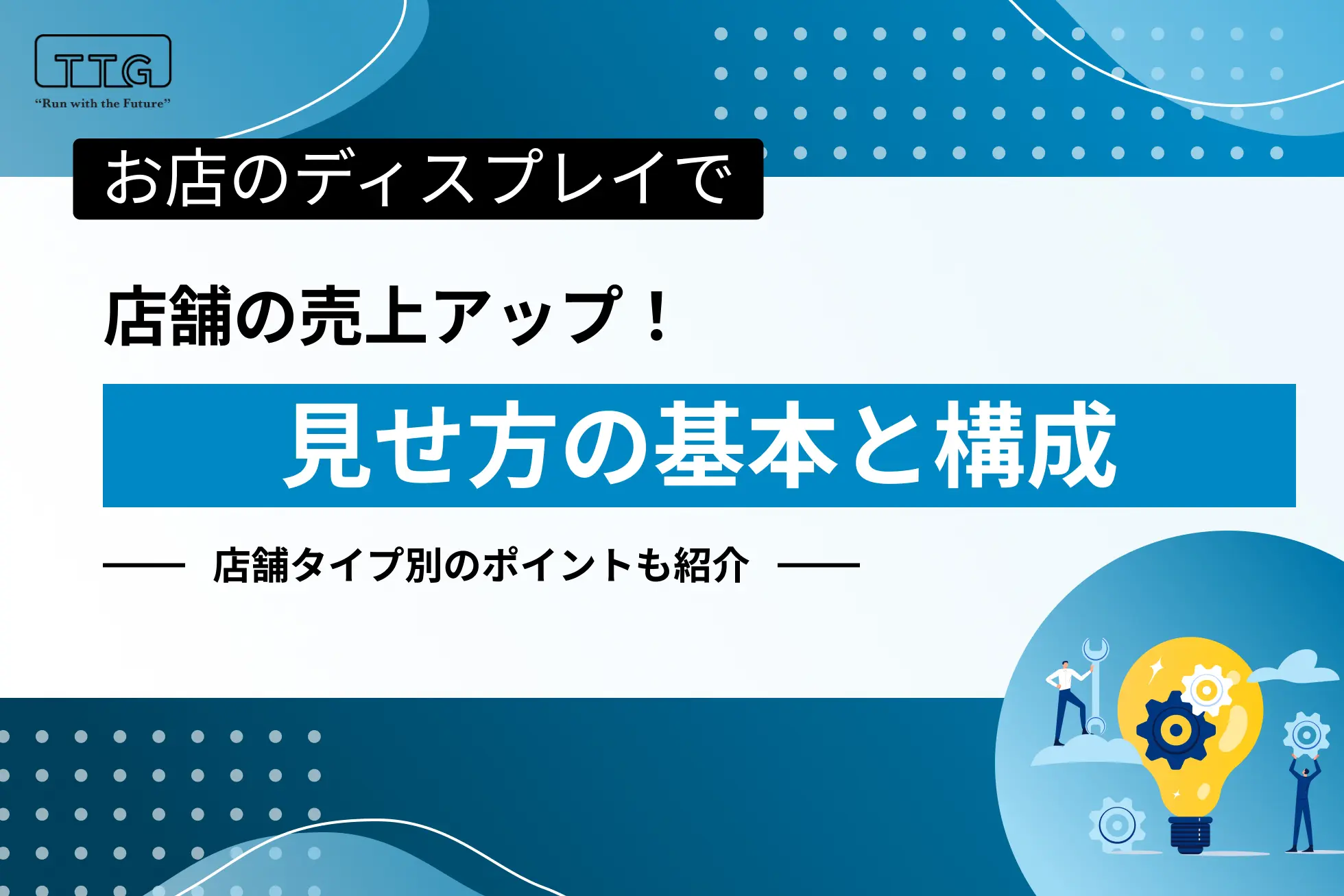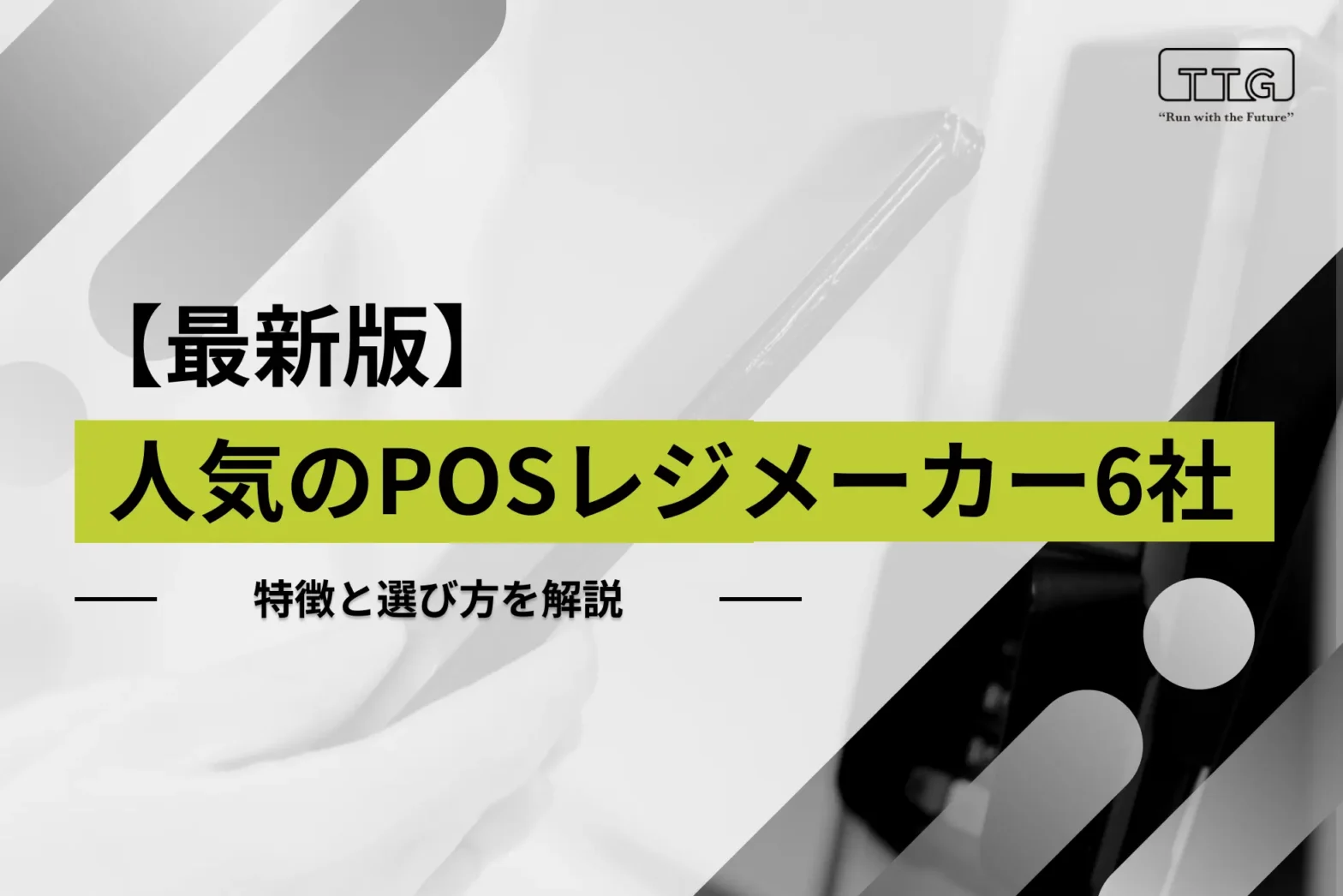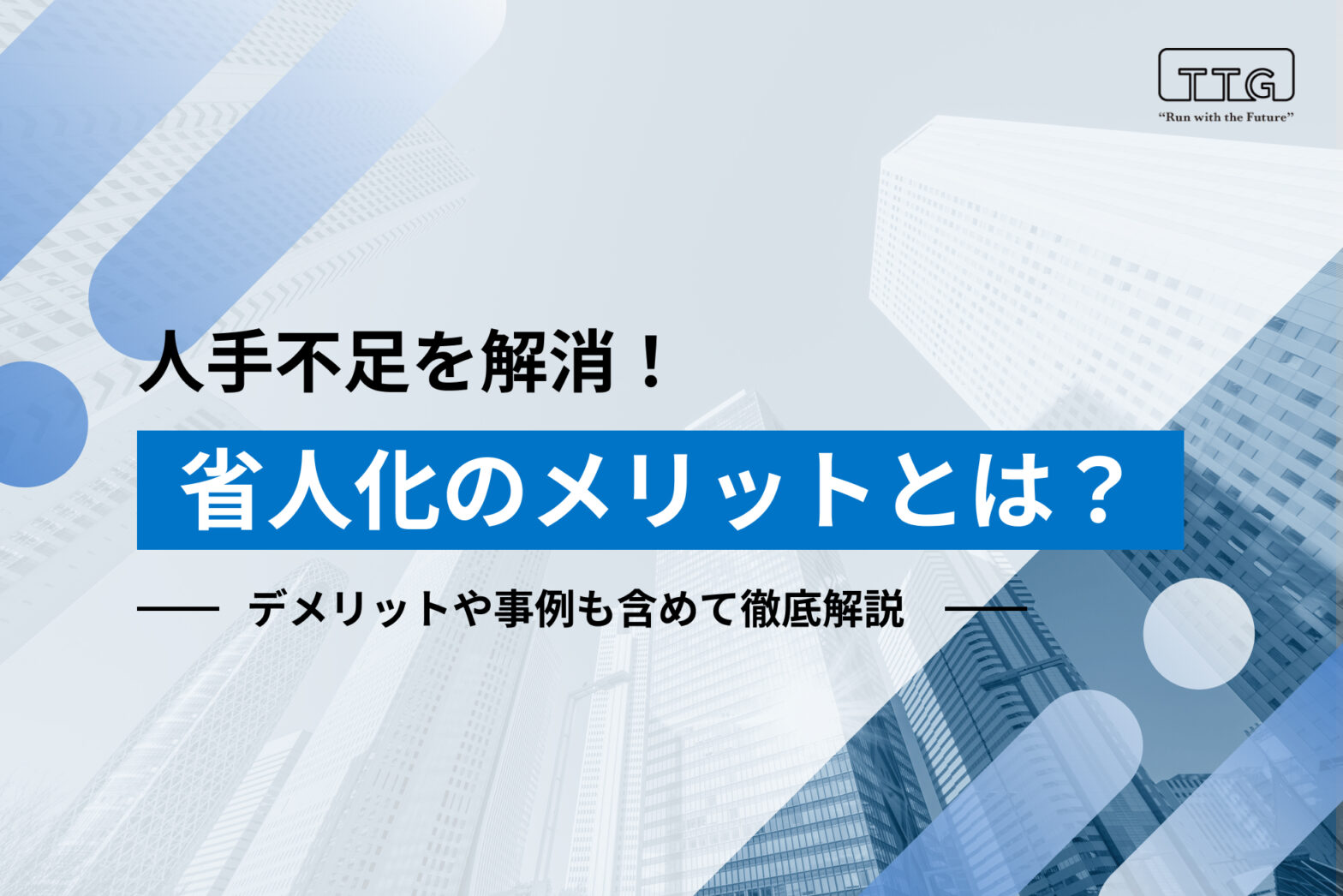Category
こんにちは。無人決済店舗システムを提供しているTOUCH TO GO 編集部です。
店舗での売上に大きく影響を与えるものの一つが、ディスプレイの工夫です。
どれだけ良い商品を揃えていても、並べ方や見せ方が悪ければ顧客の目に留まらず、せっかくの魅力が伝わらないことも少なくありません。
逆に、目を引くレイアウトや統一感のある演出によって、来店者の足を止め、購買意欲を高めることができます。
この記事では、お店の印象を左右するディスプレイの基本から、すぐに実践できる構成方法や店舗タイプ別ディスプレイのポイントまで幅広く解説します。
店舗運営に関わる方はもちろん、売上アップを目指している方は、ぜひ参考にしてください。
関連記事▼
監修者プロフィール

2019年に株式会社TOUCH TO GOを設立。無人決済店舗システムを提供し、次世代型小売の拡大に取り組んでいる。
目次
ディスプレイの役割と重要性
店頭や店内のディスプレイは、単なる「飾り」ではありません。来店客の視線を引きつけ、商品に興味を持たせ、購買という行動につなげるための重要な仕掛けです。
ここでは、ディスプレイが持つ具体的な役割と、その重要性について解説します。
視覚的な訴求力で顧客の関心を引く
人が商品に興味を持つかどうかは第一印象で決まることが多く、なかでも「見た目」が大きく影響します。
ディスプレイは、商品の良さや使い方、魅力を直感的に伝えるための最初の接点です。
たとえば、ただ棚に商品を並べるだけではスルーされてしまうこともありますが、色彩や高さ、角度を工夫して配置するだけで注目度は格段にアップします。
ブランドイメージの構築
ディスプレイには、店舗全体の印象を左右する力もあります。どのような素材を使い、どんな色味で統一するかによって、店舗の世界観やブランドイメージが伝わります。
たとえば、ナチュラルテイストの雑貨店であれば、木製什器や麻素材の装飾を用いることで「やさしさ」「自然」などの雰囲気を出せます。
逆に、スタイリッシュなセレクトショップなら、モノトーンで統一し、無駄のないディスプレイが効果的です。
こうしたビジュアルの積み重ねが、来店者の記憶に残りやすい“ブランドの顔”をつくっていきます。
購買行動への影響
効果的なディスプレイは、商品を「買いたくなる気持ち」に自然と導いてくれます。
たとえば、関連する商品を組み合わせて展示することで、「これも一緒に使いたい」と思わせるクロスセル効果が期待できますし、使用シーンを想起させる演出があれば、「自分の生活に合いそう」と感じてもらえるきっかけになります。
また、季節感を取り入れた演出や数量限定のポップなどを配置することで、来店者の購買意欲を刺激することも可能です。
単に見せるだけでなく、「手に取りたくなる」「今すぐ買っておきたい」と思わせることこそが、ディスプレイの本質的な目的と言えるでしょう。
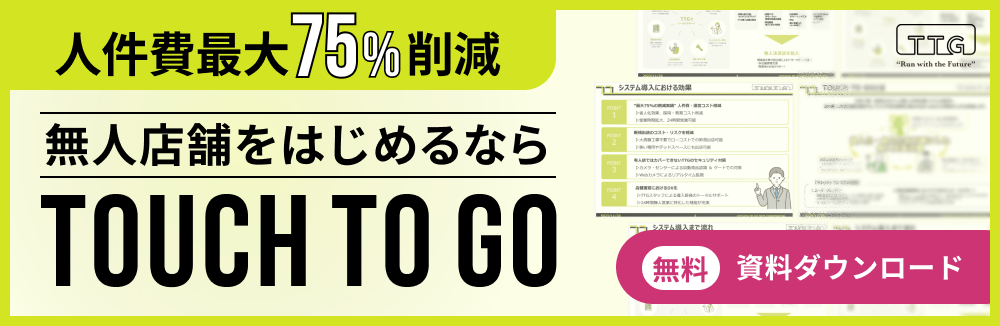
TOUCH TO GO の 無人決済店舗システムは、カメラで人物をトラッキングし、どの棚のどの商品が何個お客様の手に取られたかをセンサーで感知します。
店舗の売り場改善として無人店舗の導入をご検討中の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/
効果的なディスプレイの基本要素
魅力的なディスプレイをつくるためには、単におしゃれな装飾を施すだけでは不十分です。
どんな商品を、誰に、どのように見せたいのかという視点を持ちながら、いくつかの基本要素を押さえて設計していくことが重要です。
ここでは、ディスプレイの質を高めるために欠かせない基本要素を紹介します。
商品の見せ方と配置の工夫
顧客が商品を見つけやすい配置には、以下の視点が欠かせません。
- 目線の高さ
- 手に取りやすい位置
- 動線との関係
たとえば、最も注目させたい主力商品は、来店者の目の高さに配置すると自然と視線が集まります。逆に、低すぎる位置や高すぎる場所に置かれた商品は、存在に気づかれにくくなることも。
また、同じジャンルの商品を並べるだけでなく、「テーマ」「使用シーン」「色」などで組み合わせて陳列することで、統一感のある魅せ方が可能になります。
視覚的な流れを意識しながら配置を考えると、より自然に商品に興味を持ってもらえるでしょう。
照明や色彩の活用
照明は単なる明かりではなく、「商品の魅力を最大限に引き出す演出」です。
スポットライトを使えば、特定の商品に集中して注目を集めることができますし、温かみのある光を使えば落ち着いた雰囲気をつくることもできます。
さらに、色彩も感情に大きく影響します。たとえば、赤やオレンジは購買意欲を高める色とされ、青や緑は安心感を与える色とされています。
店舗やブランドのコンセプトに合わせて色のバランスを整えることで、空間全体の印象がより強く伝わるようになります。
季節感やテーマの取り入れ方
常に同じディスプレイでは、リピーターの新鮮さが薄れてしまいます。そこで有効なのが、季節やイベントに応じた演出の切り替えです。
例えば、以下のように季節感を反映させたデザインは来店者の感情に寄り添い、購買モチベーションを高める方法が挙げられます。
- 春:パステルカラー、桜モチーフ
- 夏:ブルー系、海のモチーフ
- 秋:暖色系、木の実モチーフ
- 冬:ホワイトやゴールド系、雪モチーフ
また、「ギフト」「母の日」「新生活」「アウトドア」など、テーマ性を持たせたディスプレイは、用途を想起させやすく、買う理由を明確にするのに効果的です。
ディスプレイ構成のテクニック
基本ができてきたら、次に取り入れたいのがディスプレイ構成のテクニックです。どのように商品を配置するかによって、視線の集まり方や印象は大きく変わります。
ここでは、代表的なレイアウト方法をいくつか紹介します。
三角構成(トライアングル構成)
三角形の形を意識して商品を配置する方法は、最も基本的で安定感のある構成とされています。
中央を一番高く、両側をやや低く配置することで自然と視線が中央に集まり、全体がまとまって見える効果があります。
三角構成は高さのある什器やPOPを使って中央に「主役」をつくるのがポイントで、視覚的にバランスが良く、複数の商品をまとめて見せたいときに有効です。
左右対称構成(シンメトリー)
左右対称の構成は、きちんと整った印象や信頼感を与えるのに適しています。
同じアイテムを左右に配置するだけでなく、異なる商品でも色やサイズを合わせることで対称性をつくることができます。
きれいに整ったディスプレイは、上品さや落ち着きを演出したい場面に向いており、ギフト商品やフォーマルな雰囲気を演出したいときに使うと効果的です。
左右非対称構成(アシンメトリー)
非対称の構成は、動きやリズムを感じさせたいときにおすすめのスタイルです。あえてバランスを崩すことで目を引き、印象に残りやすいディスプレイになります。
ただし、自由度が高い分、配置を誤ると雑多な印象を与えてしまうため注意が必要です。
商品の色や形に一定の統一感を持たせたり、視線の流れを意識して配置したりすることで、整った中にも遊び心のある表現が可能になります。
リピート構成
同じ商品やパッケージを縦や横に並べて、数のインパクトで引きつける方法です。
量感や人気感を演出したいときに効果的で、「売れている商品」「たくさんある=選びやすい」といった印象を与えることができます。
また、リピート構成は遠くから見たときにも目立ちやすく、通行人の目に留まりやすいというメリットもあります。
色を揃えたパッケージであれば、リズム感が出て見栄えも良くなります。
店舗タイプ別ディスプレイのポイント
ディスプレイの基本的な考え方は共通していますが、業種や取り扱う商品によって工夫すべきポイントは異なります。
来店客の動機や滞在時間、購買までの流れがそれぞれ異なるため、それに応じた「見せ方」の最適化が必要です。
ここでは代表的な店舗タイプごとに、効果的なディスプレイのポイントを紹介します。
アパレル店舗
アパレルショップでは、商品そのもののデザインや素材感を魅力的に見せることが大切です。
そこでよく用いられるのが、マネキンやトルソーを使ったスタイリングの提案です。
顧客に実際に着用した状態を見せることで、来店者に「自分が着たらどうなるか」をイメージさせやすくなります。
また、季節感やトレンドを強調するゾーンを設けることで、入店直後の印象を左右する効果があります。
カラーグラデーションでまとめた陳列や棚とハンガーの組み合わせなど、見やすさとおしゃれ感を両立させる配置を意識しましょう。
飲食店
飲食店のディスプレイでは、メニューの魅力を視覚的に伝える演出が鍵になります。
食品サンプルや写真パネル、POPなどを使って「どんな料理が、どんな量で、いくらなのか」を明確に伝えることが、安心感と購買意欲につながります。
また、季節限定メニューやおすすめ料理は、レジ前や入口付近に目立つように配置すると効果的です。
店内の照明やテーブルディスプレイも、料理の見た目を引き立てる工夫として重要な要素になります。
雑貨・インテリアショップ
雑貨店やインテリアショップでは、「生活のなかでの使い方」をイメージさせるような演出が効果的です。
たとえば、テーブルコーディネートを組んだり、小さな部屋の一角を再現したようなブースを設けたりすると購入後の使用シーンが明確になり、購買意欲につながります。
また、カテゴリごとにグルーピングした陳列や、「価格帯別」「贈り物シーン別」などのテーマ分けも選びやすさにつながるポイントです。
棚やボックス、カゴなどの什器選びも含めて、雰囲気づくりと実用性のバランスを考えることが大切です。
まとめ
お店のディスプレイは単なる商品陳列ではなく、来店者に商品やブランドの魅力を伝えるための大切な“言葉”のようなものです。
今回紹介したような基本のルールや構成テクニック、演出の工夫を取り入れることで、実践的なディスプレイ改善が可能になります。
日々変化する顧客の目線に寄り添いながら、伝わる売場づくりを目指していきましょう。
関連記事▼
TOUCH TO GO の 無人決済店舗システムは、カメラで人物をトラッキングし、どの棚のどの商品が何個お客様の手に取られたかをセンサーで感知します。
店舗の売り場改善として無人店舗の導入をご検討中の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/