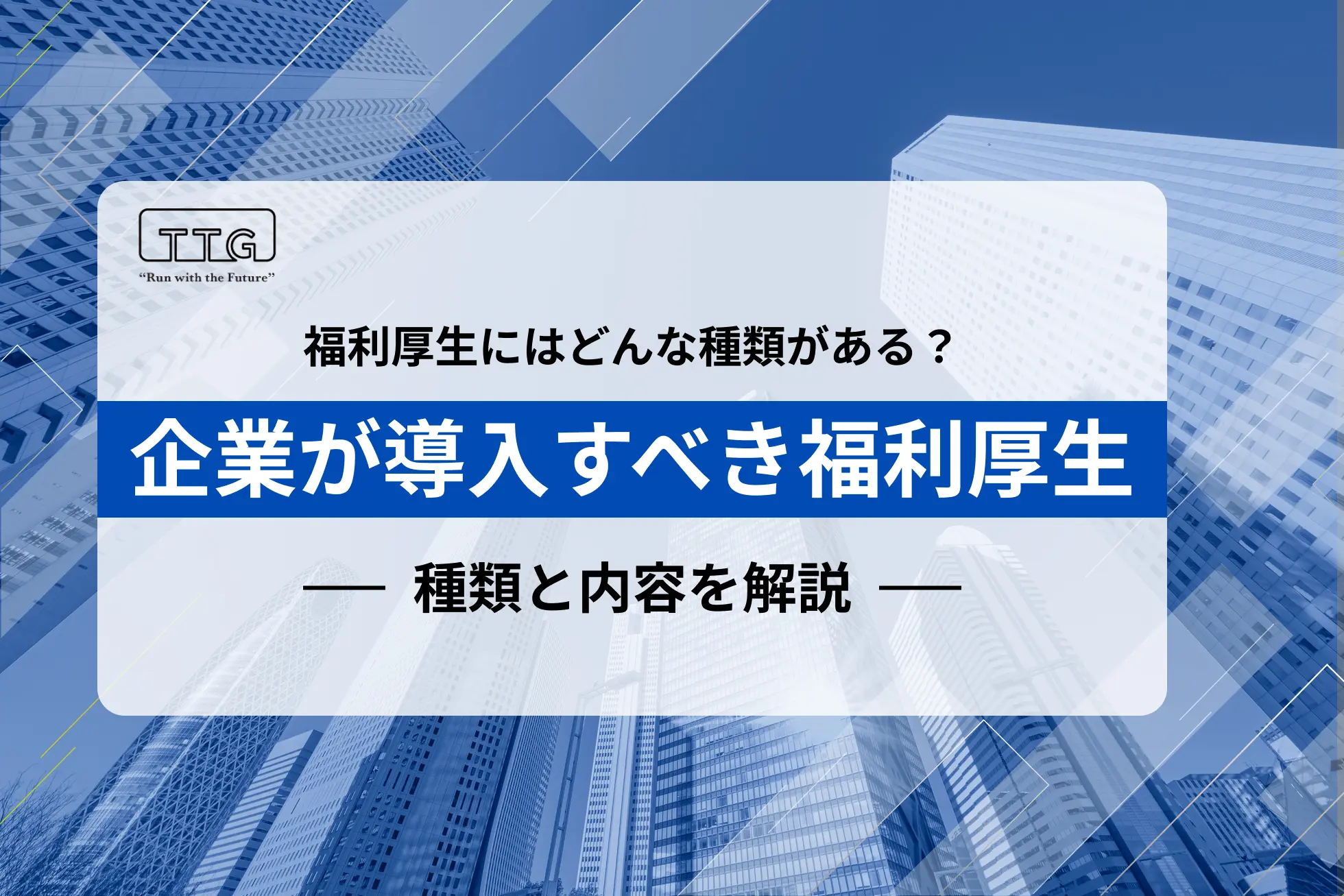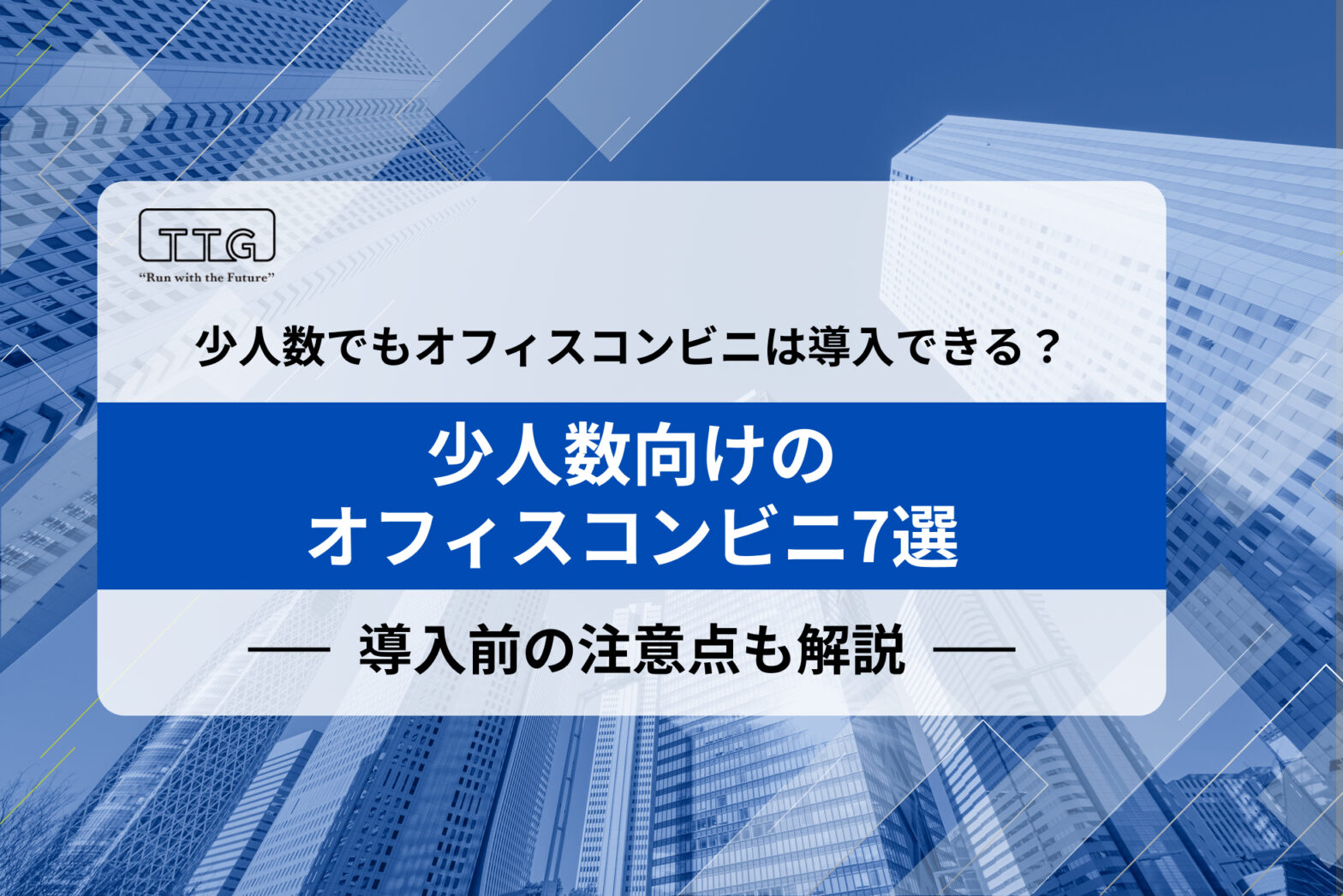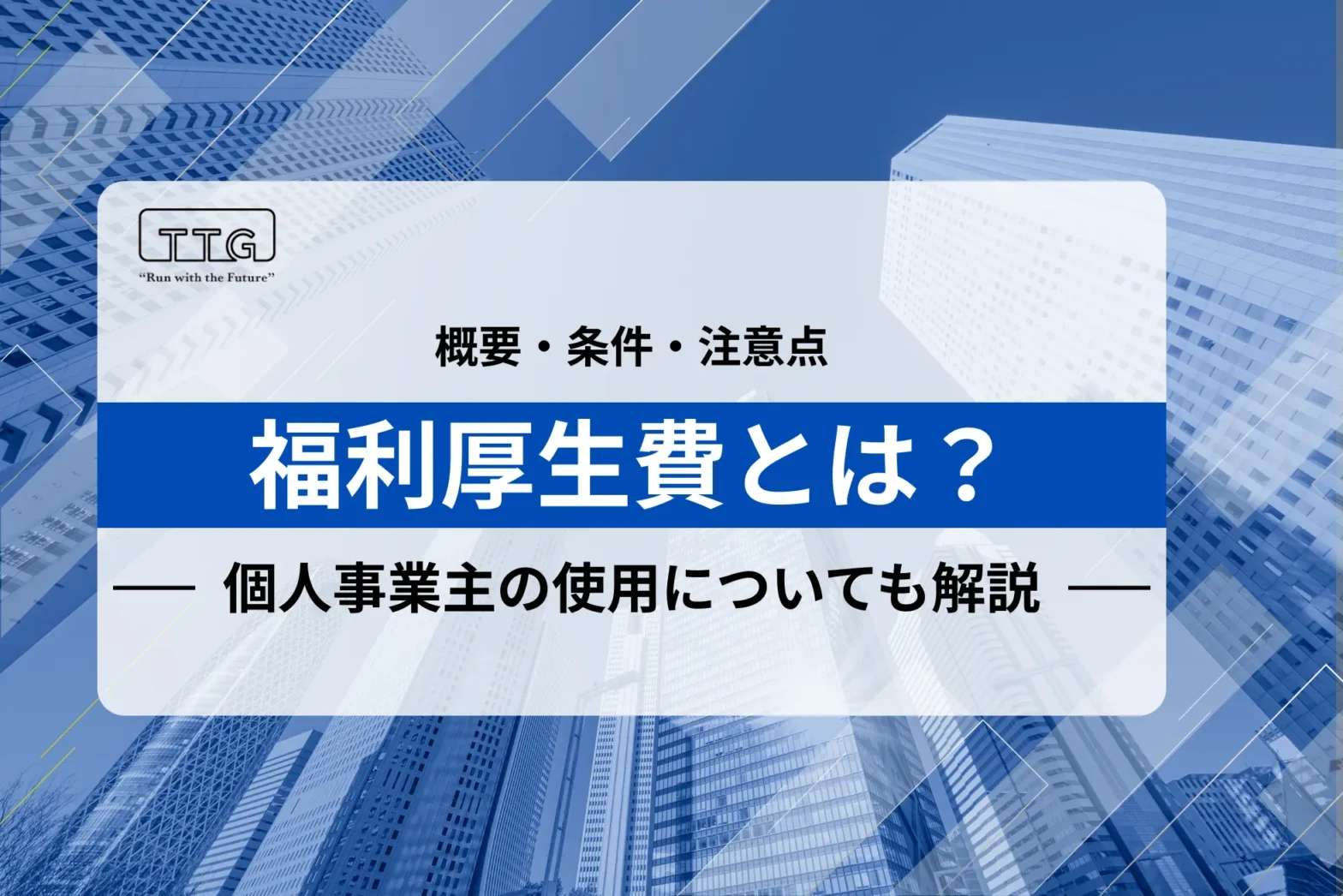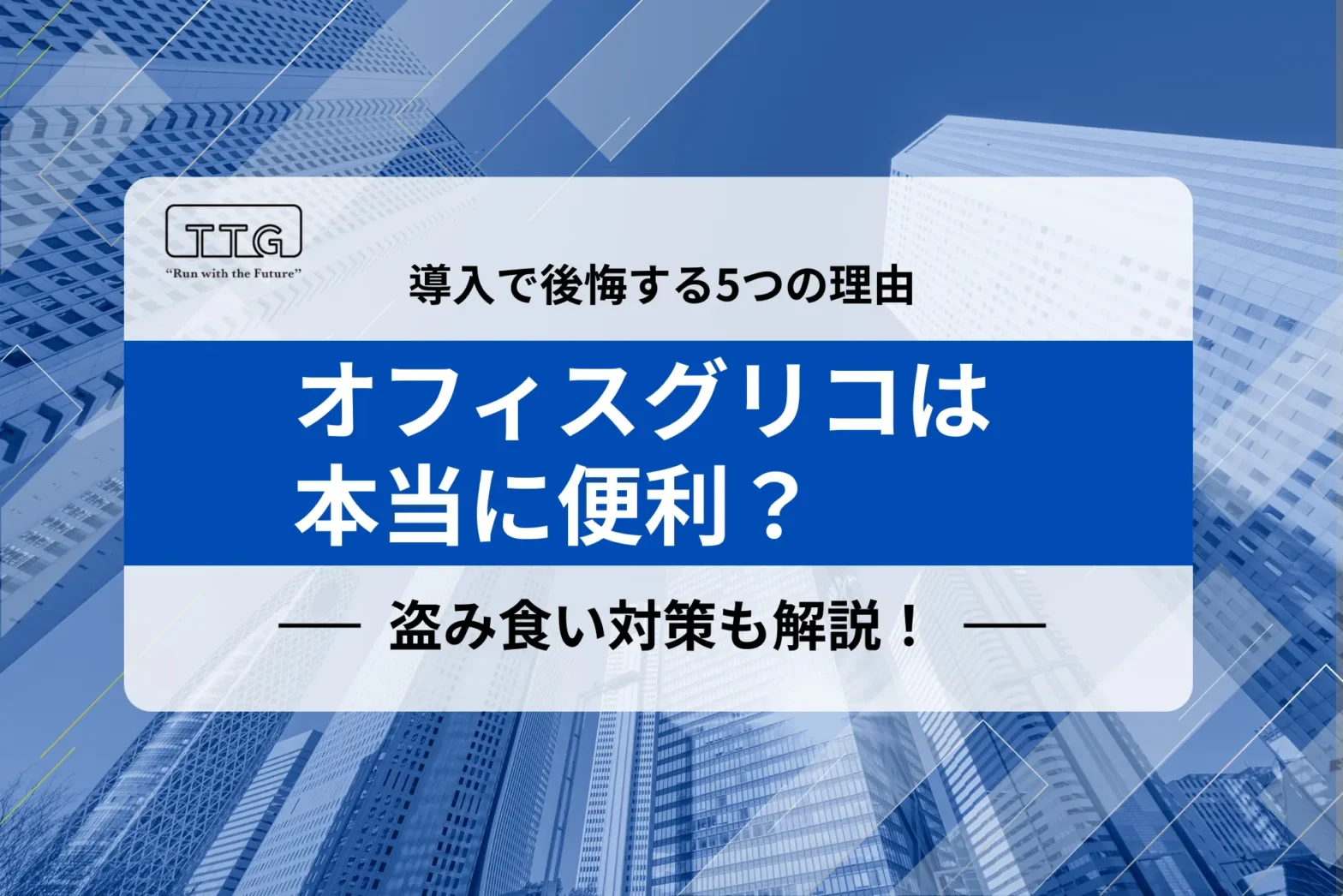Category
こんにちは。無人決済店舗システムを提供しているTOUCH TO GO 編集部です。
社員の働きやすさやモチベーションを高める手段として、多くの企業が注目しているのが「福利厚生」です。制度を整えることで、人材の確保や定着にも効果が期待できます。
福利厚生の種類が多く、どれを導入すればよいのか分からず迷っていませんか?本記事では、法定外福利厚生と法定外福利厚生の種類や内容、自社に合った福利厚生の選び方まで詳しく解説します。
監修者プロフィール

2019年に株式会社TOUCH TO GOを設立。無人決済店舗システムを提供し、次世代型小売の拡大に取り組んでいる。
目次
法定福利厚生の種類
福利厚生には大きく分けて法定福利厚生と法定外福利厚生の2種類があります。
法定福利厚生とは、企業が従業員に提供する福利厚生のうち、法律によって実施が義務づけられている制度です。法定福利厚生は、企業側に費用負担の義務があり、提供を怠ると法的な罰則の対象となることがあります。
ここでは、主な法定福利厚生の種類や内容、役割について詳しく解説します。
健康保険
健康保険は、従業員が病気やケガをした際の医療費の負担を軽減するために設けられている制度です。企業はこの保険料の半分を負担する義務があり、従業員と会社で費用を折半する仕組みになっています。
保険料は加入者の収入に応じて決まり、高額な医療費が発生した場合でも、自己負担が一定額を超えないよう調整されるため、経済的な安心感を得られるのが特徴です。
厚生年金保険
厚生年金保険は、基礎年金である国民年金に加えて給付される公的年金制度で、従業員と企業が保険料を半分ずつ負担する仕組みです。
原則として、厚生年金の対象となる企業で働く70歳未満の従業員は全員加入しなければなりません。一定の期間保険料を納めるなどの条件を満たせば、将来的に老後の年金だけでなく、万が一の際の障がい年金や遺族年金なども上乗せで受け取れます。
雇用保険
雇用保険は、失業や雇用継続が難しくなった場合に備えて、労働者の生活を支えるために設けられた公的制度です。
雇用保険は、失業手当のほか、育児に関する給付や職業スキルの習得を支援する教育訓練給付金など、状況に応じたさまざまな支援が用意されています。保険料は、従業員に支払われる賃金に所定の保険料率を掛けて算出され、事業主と労働者の双方で負担するのが一般的です。
労災保険
労災保険は、仕事中や通勤時のケガ、業務が原因となる病気などによって働けなくなった場合に、療養費や年金などを支給するための公的な補償制度です。
対象となるのは、労働基準法に基づく労働者とされており、業務に起因する事故や病気に対して必要な補償を受けられます。労災保険の保険料は他の保険と異なり、すべて事業主が負担する点が特徴で、従業員には支払い義務は発生しません。
介護保険
介護保険は、加齢などにより日常生活に支援が必要となった人に対して、金銭の給付やサービスが受けられるためのサポートする保険制度です。
対象は40歳以上の人で、保険料は健康保険料とともに徴収されます。要介護あるいは要支援と認定された場合に、必要な介護サービスを受けられるのが大きな特徴です。
介護保険は、本人の自立した生活を促すとともに、介護する家族の負担軽減が目的です。利用には自治体の窓口で申請し、審査を受ける必要があります。認定後は、前年度の所得に応じて1〜3割の自己負担でサービスが受けられます。介護保険料は会社と従業員が半分ずつ負担する仕組みです。
法定外福利厚生の種類
法定外福利厚生とは、法律で義務づけられているものではなく、企業が自主的に整備する福利厚生制度のことです。代表的な内容としては、家賃を一部支援する家賃補助や、通勤にかかる費用をカバーする通勤手当、定期健康診断の補助などがあります。
法定外福利厚生は、社員満足度の向上に直結し、働きやすい職場づくりにつながります。導入にはコストや運用の手間も伴いますが、長期的には採用力の強化や離職防止などに効果的です。
ここでは、代表的な法定外福利厚生の種類や内容、メリットについて詳しく解説します。
住宅手当
住宅手当とは、従業員の家賃や住宅ローンなど、住まいにかかる経済的な負担を軽減するために、企業が給料に上乗せして支給する制度です。企業によっては「住居手当」や「家賃手当」といった別の名称で導入されていることもありますが、基本的な目的や内容は共通しています。
住宅手当を導入することで、企業側にもいくつかの利点があります。たとえば、若年層を中心とした人材確保において有利に働く可能性があり、人手不足の解消に有効です。経済的支援を受けられる職場に留まろうとする意識が高まり、離職率の抑制にもつながります。
さらに、安定した住環境が従業員の生活基盤を整え、業務への集中力やパフォーマンス向上に寄与するケースもあります。
交通費補助
交通費補助は、従業員が通勤や出張をする際に発生する費用を、企業が「通勤手当」や「交通費」として補助する仕組みです。支給の対象には、電車・バスなどの公共交通機関の利用料金だけでなく、自家用車を使う場合のガソリン代や高速道路の料金も含まれます。
一般的に交通費は、月々の給与と合わせて支給され、従業員が事前に費用を負担する必要がなくなるため、経済的な負担を減らせます。交通費が給与とは別枠で支給されることで、実質的な収入が増え、従業員からの満足度も高まりやすい福利厚生です。
通勤コストの心配が少ない働きやすい職場として、企業の魅力を高める効果も期待されます。採用活動や社員の定着にもよい影響をもたらす制度の一つです。
休暇制度
法定外福利厚生の休暇制度は、以下のような例があげられます。
- 慶弔休暇
- 夏季休暇
- 年末年始休暇
- リフレッシュ休暇
- 病気休暇
休暇制度の一環として、結婚や出産、身内の不幸といった私的な事情に応じて特別休暇を設けたり、年末年始に合わせた長期休暇を設定する企業も少なくありません。法律で定められた有給休暇とは別に、会社が自主的に運用する休暇制度です。
休暇制度を整えることで、従業員はライフイベントや季節の節目を大切にしながら働くことができ、心身のリフレッシュにもつながります。結果として、職場全体の生産性や働きやすさが向上し、ワークライフバランスの確保にもつながります。
健康やメンタルヘルス
企業が社員の健康をサポートする施策は、重要な福利厚生の一つです。心身の健康を保ちながら働ける環境を整えることで、従業員の安心感やパフォーマンスの向上にもつながります。
具体的には、定期健康診断や人間ドックの補助制度のほか、フィットネスクラブの利用費を一部支援する企業もあります。社員の健康維持を後押しするだけでなく、職場の満足度アップにも寄与します。
また、リモートワークが広がる中で、自宅から利用できるメンタルケアプログラムや、オンライン健康相談サービスを導入する企業も増えてきました。
自己啓発
自己啓発支援制度は、社員の成長意欲を後押しするために企業が設ける福利厚生のひとつです。資格取得や専門知識の習得を目指す社員に対して、書籍の購入補助や外部講座・セミナーへの参加費の援助など、さまざまな形で学びの機会を提供しています。
自己啓発の支援制度が整っていることで、社員は業務に必要なスキルや知識を計画的に身につけることが可能です。業務効率の向上やパフォーマンスの改善にもつながります。急速に変化するビジネス環境の中でも柔軟に対応できる力をつけられます。
また、企業が社員の学習を積極的に支援する姿勢は、「自分の成長を企業が大切にしてくれている」という安心感や信頼感を社員にもたらし、仕事へのモチベーションや帰属意識の向上に効果的です。
近年では給与や休暇制度だけでなく、成長できる環境かどうかが企業選びの重要な判断基準になっています。自己啓発制度の充実は企業の魅力向上にもつながるのです。
慶弔・見舞金
慶弔見舞金制度とは、社員やその家族に人生の節目や予期せぬ出来事があった際、会社が金銭的な支援を行う福利厚生のひとつです。結婚や出産といった慶事には祝い金を、不幸があった際には弔慰金やお見舞金を支給し、社員の気持ちに寄り添ったサポートをします。
例として以下のものがあげられます。
- 結婚祝い
- 出産祝い
- 入院時のお見舞金
- 自然災害による被災支援
- 昇進祝い
ただし、支給にあたっては注意が必要です。特定の社員だけが対象となっていたり、社会通念を超えるような高額の金額が支払われている場合には、税務上「給与」とみなされる可能性があります。
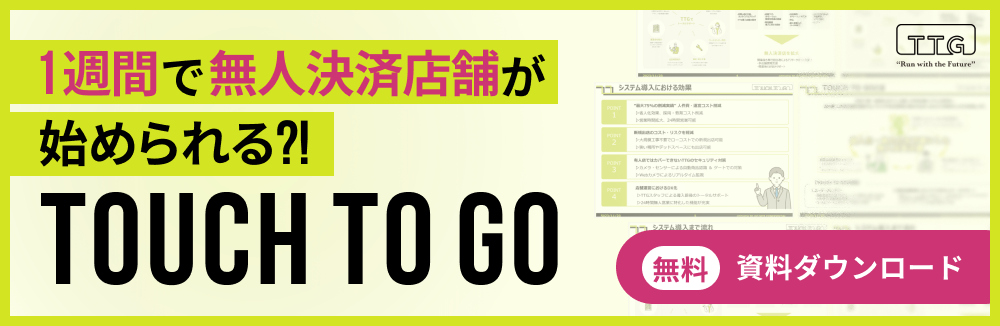
TOUCH TO GOは24時間稼働する無人店舗をオフィス内に導入できます。
福利厚生としてオフィス内に販売店舗を設置したい方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/
あると嬉しい福利厚生の具体例
基本的な制度に加えてあると嬉しいと感じられる福利厚生は、社員の定着率やモチベーション向上に大きな影響を与えます。日々の業務を支える実用的な制度から、ちょっとした驚きや楽しさを提供するユニークな施策まで、その内容は多種多様です。
ここでは、導入されていると社員に喜ばれやすい具体例をいくつか紹介します。
フレックスタイム制
時間や場所にとらわれない働き方を実現できる制度として、フレックスタイム制や在宅勤務制度は高い人気を集めています。フレックスタイム制では、業務のコアタイムを設けながらも始業・終業時間を自由に設定できるため、通勤ラッシュの回避や育児との両立が可能です。
在宅勤務制度
在宅勤務制度では、自宅で業務ができることで集中しやすい環境が整い、通勤時間の削減やプライベートの確保にもつながります。働き方の多様性を尊重する企業姿勢のアピールにもつながります。導入の際には、評価制度やセキュリティ対策なども含めた整備が必要です。
趣味に関する制度
ユニークな福利厚生は、企業のブランディングにもつながる要素として注目されています。たとえば、旅行費用の補助、社内バーやカフェの設置、推し活支援制度など、社員の趣味やリフレッシュを応援する制度は話題性があり、SNSでの拡散にもつながります。
ペット同伴出社や昼寝スペースの設置など、仕事と生活の垣根を柔軟にする工夫も取り入れられています。こうした制度は、業種や社風との相性を考慮して導入することで、定着率向上や社内のコミュニケーション活性化に効果的です。
自社に合った福利厚生の選び方と導入後のコツ
福利厚生制度は、他社の事例を参考にするだけでなく、自社の実情や社員ニーズに応じた柔軟な設計が求められます。目的に合致した制度を選定し、適切な運用と定期的な見直しを行うことで、効果的な人材定着と組織力の向上が期待できます。
ここでは、自社に合った福利厚生の選び方と導入後のコツについて解説します。
企業規模や業種に応じて選ぶ
福利厚生制度を導入する際は、自社の業種や規模に合わせた現実的なプランニングが不可欠です。
たとえば、IT系やクリエイティブ系企業ではフレックスタイム制やリモートワーク制度が定着しやすく、製造業や接客業では食事補助や作業着クリーニングなどの現場支援型制度が喜ばれます。
社員数が多い大企業では、制度の公平性や運用のしやすさが重視されます。一方で、中小企業では導入コストや即効性が重要です。全社共通の制度だけでなく、職種や部署に応じた柔軟なカスタマイズも効果的です。
社員ニーズを把握して選ぶ
社員が求めている制度を把握するには、定期的なアンケートやヒアリングが有効です。選択肢型の設問に加え、自由記述欄を設けることで、具体的な要望や不満の掘り起こしができます。アンケートは匿名形式とし、率直な意見を集めやすくする工夫も重要です。
年代やライフステージごとのニーズの違いを分析することで、多様な働き方や価値観に応える制度設計が実現できます。得られたデータは、導入の優先順位付けや、既存制度の見直し材料としても活用できます。
福利厚生導入後のコツ
福利厚生制度は、導入して終わりではありません。運用フェーズに入ってからの社内浸透、利用状況のモニタリング、効果測定が不可欠です。
まずは制度内容を分かりやすく伝える社内広報やマニュアル整備をし、利用を促進する環境づくりをしましょう。一定期間ごとに利用率や社員の声を分析し、不要な制度の廃止や新たなニーズへの対応を検討することも大切です。PDCAサイクルを活用して、制度を継続的に改善する姿勢が、社員の信頼とエンゲージメントを高めます。
まとめ
福利厚生制度は、社員のモチベーションや定着率に直結する重要な要素です。企業が提供する福利厚生は、社員の生活や働き方を支えるだけでなく、会社の魅力を高め、採用率アップにもつながります。
どのような福利厚生制度が自社に合っているかを検討し、具体的に導入を進めていきましょう。社員がよりよい環境で働けるように、福利厚生をうまく活用することが企業の成功へとつながります。
TOUCH TO GOは24時間稼働する無人店舗をオフィス内に導入できます。
福利厚生としてオフィス内に販売店舗を設置したい方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/