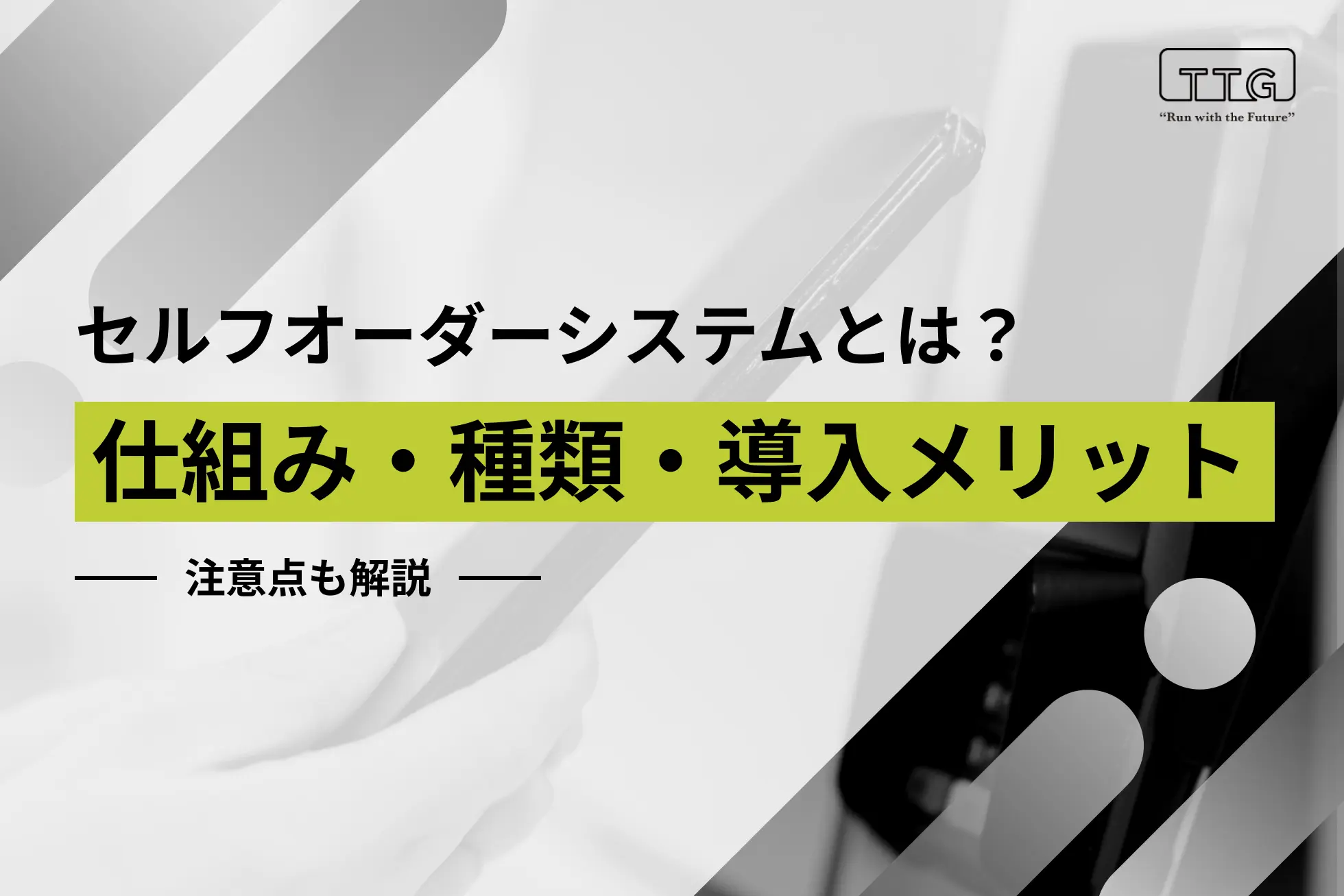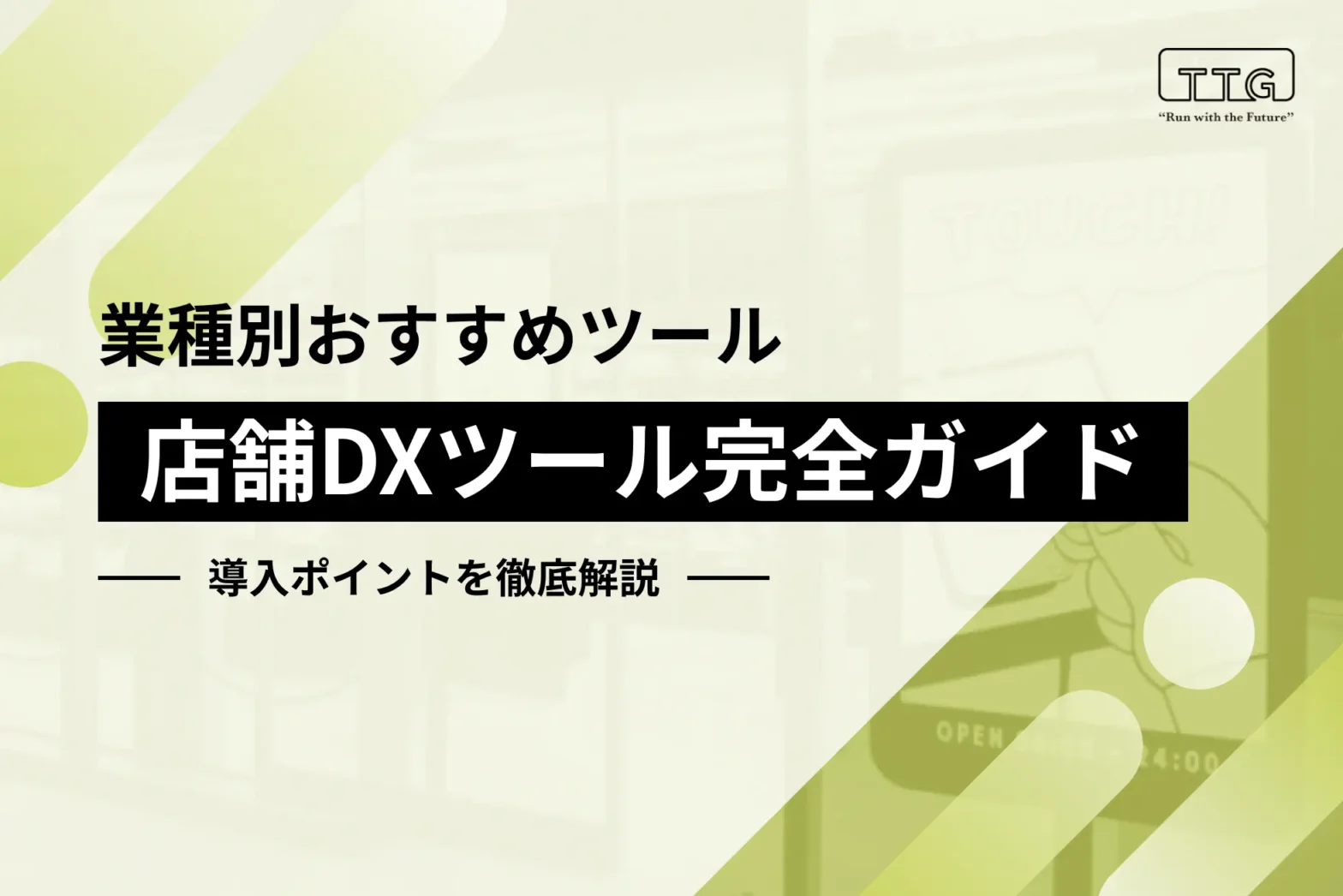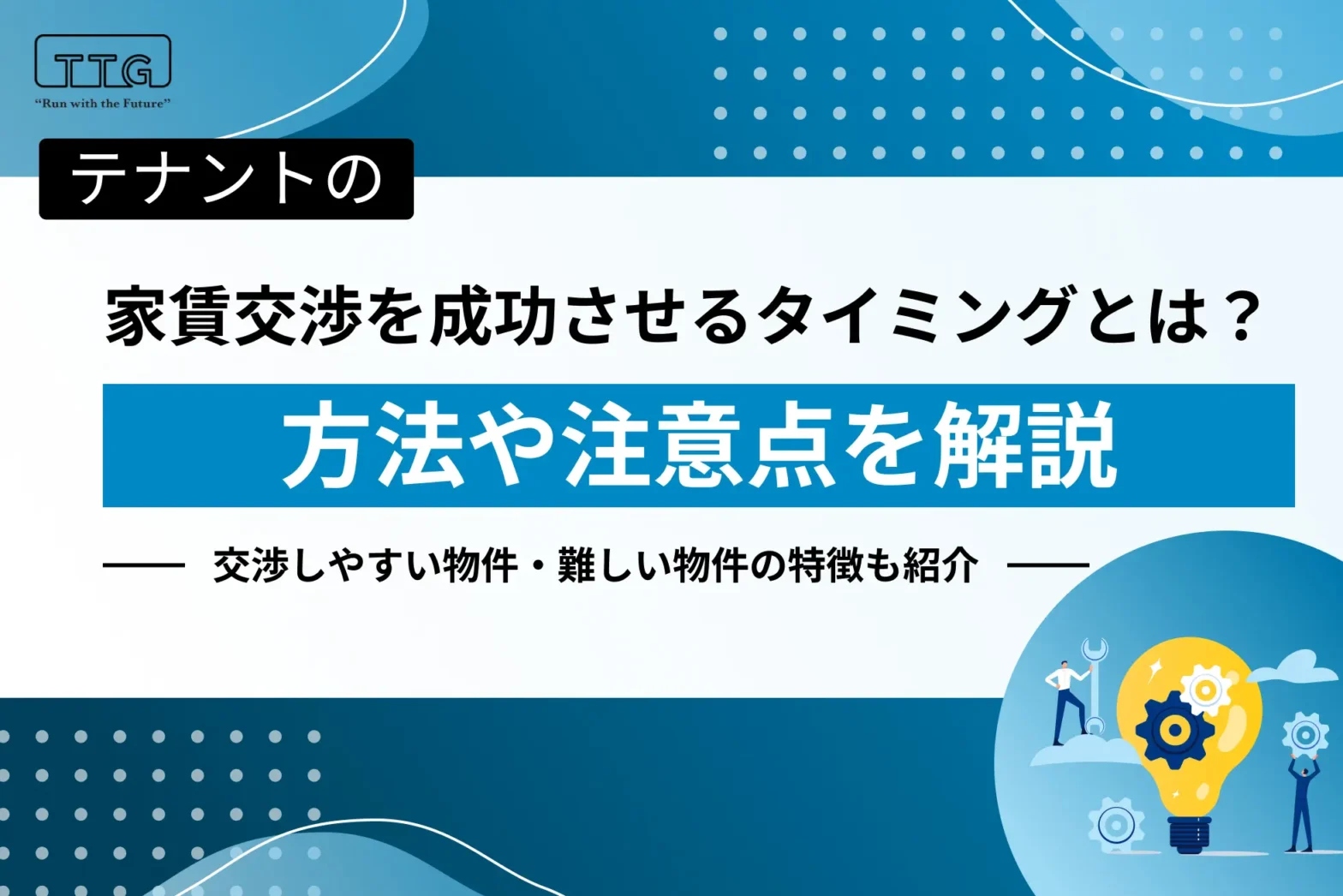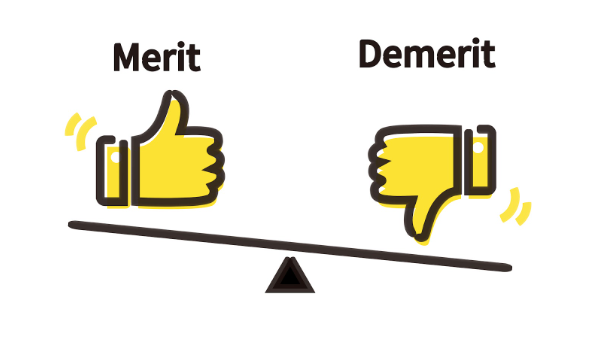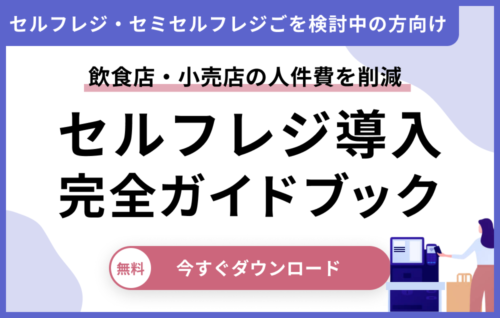Category
こんにちは。無人決済店舗システムを提供しているTOUCH TO GO 編集部です。
飲食店やカフェ、フードコートなどで、タブレットやスマートフォンを使って注文する『セルフオーダーシステム』を見かける機会が増えてきました。
人手をかけずに注文を受けられる便利な仕組みとして注目されていますが、「セルフオーダーって具体的にどういう仕組み?」「自分の店に合うか分からない」などの疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
この記事では、セルフオーダーシステムの基本的な仕組みや種類、導入によるメリットと注意点を解説します。店舗運営の効率化や人手不足の解消を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
関連記事▼
監修者プロフィール

2019年に株式会社TOUCH TO GOを設立。無人決済店舗システムを提供し、次世代型小売の拡大に取り組んでいる。
目次
セルフオーダーシステムの種類
セルフオーダーシステムとひと口にいっても、その形はひとつではありません。利用シーンや業態に応じて、さまざまなタイプが存在します。
ここでは、セルフオーダーシステムの代表的なタイプを3つ紹介します。
タブレット型
もっとも一般的な方式として挙げられるのが、各テーブルに専用のタブレット端末を設置する「タブレット型」タイプです。
ファミリーレストランや居酒屋などで多く導入されており、メニューの閲覧から注文までを来店客自身がスムーズに行える点が特長です。
タブレットは画面が大きく操作性に優れており、料理の写真や詳細な説明を見ながら選べるため、初めての利用でも迷わず注文できます。
また、注文完了時におすすめ商品を表示するなど、追加注文を促す工夫がなされている店舗も多く、売上向上にもつながります。
初期投資として端末の設置は必要になりますが、滞在時間が長くリピーターの多い店舗では、十分な費用対効果が見込めます。
モバイルオーダー型
顧客自身のスマートフォンを活用する「モバイルオーダー型」は、非接触対応のニーズが高まる中で急速に普及しています。
テーブルに設置されたQRコードを読み取ることで、専用のWebページやアプリにアクセスし、そのまま注文を完了できる仕組みです。
この形式では、店舗側が専用端末を用意する必要がなく、初期費用を抑えて導入できる点が大きなメリットです。
ただし、スマートフォンの操作に不慣れな層に対しては、簡単な説明やサポートが求められる場面もあります。
現在ではテイクアウト対応や混雑緩和の手段としても活用されており、特にカフェやカジュアルな飲食店を中心に導入されています。
券売機・キオスク端末型
主にファストフード店や牛丼チェーン、フードコートなどで多く導入されているのが、「キオスク端末型」のセルフオーダー形式です。
店頭や入口付近に大型のタッチパネル端末を設置し、来店客が注文から支払いまでを一度に完了できる仕組みとなっています。
対面でのやり取りが不要なため、業務の効率化や人手不足の解消に役立ちます。
さらに、近年では電子マネーやQRコード決済などに対応した高機能な端末も増えており、キャッシュレス化を推進したい店舗にも適した選択肢となっています。
端末設置には一定のスペースやコストが必要ですが、「セルフ注文」と「セルフ決済」を一体化できる点で、非常に効率的なオペレーションを実現できます。
以下の記事で、飲食店向けのセルフオーダーシステムのおすすめ製品を紹介しています。あわせてご覧ください。
関連記事>>【飲食店向け】セルフオーダーシステムの導入ポイント|おすすめ製品も紹介

TOUCH TO GO の セルフ/セミセルフレジ「TTG-MONSTAR」を導入することで、常駐スタッフの負担が軽減され、人件費が大幅に削減できます。
注文〜決済まで一台で完結できるセルフ/セミセルフレジの導入をご検討中の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TTG-MONSTAR の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download1/
セルフオーダーシステムの導入メリット
セルフオーダーシステムは、利便性の向上にとどまらず、店舗運営の効率化や売上向上にもつながる多くのメリットがあります。
ここでは、導入によって期待できる主な効果について紹介します。
人手不足の解消につながる
飲食業界をはじめとするサービス業では、慢性的な人手不足が大きな課題となっています。
セルフオーダーシステムを導入することで、注文業務や会計対応といったフロント業務を来店客自身が担うことになり、スタッフの業務負担が大幅に軽減されます。
とくにピークタイムにおいては、注文の取りこぼしや対応の遅れが発生しやすく、サービス品質の低下やクレームにつながる恐れもあります。
セルフオーダーによってそのリスクを回避できるだけでなく、限られた人員でのスムーズな店舗運営が実現可能になります。
関連記事>>飲食店が人手不足に陥る5つの原因|対策と新たな取り組みを紹介
注文ミスの削減とオペレーションの効率化
従来の対面注文では、「スタッフによる聞き間違い」や「オーダーの記入漏れ」など、ヒューマンエラーが発生するリスクがつきものです。
セルフオーダーシステムを導入することで、こうしたミスを大幅に削減できます。
お客様自身が画面上でメニューを選び、数量やカスタマイズを確認してから注文を確定するため、注文精度が格段に向上します。
また、注文内容は自動的に厨房へ連携されるため、オーダーの処理スピードが向上し、調理の優先順位付けや在庫の把握もよりスムーズになります。
業務全体の流れが整理され、調理スタッフ・ホールスタッフそれぞれの作業がスムーズになることで、店舗全体のオペレーション効率が高まり、回転率や顧客満足度の向上にもつながります。
客単価アップや回転率向上の可能性
セルフオーダーシステムでは、注文画面上におすすめメニューやセット商品の提案を自動で表示できる機能が搭載されています。
この機能を活用することで追加注文を自然に促し、客単価の向上を実現できます。
また、スタッフを介さずに注文できるため、気兼ねなく追加注文をしやすくなり、「ついで買い」や「もう一品」の促進にもつながります。
さらに、注文から支払いまでをセルフで完結させることで、来店から退店までの所要時間を短縮でき、テーブル回転率の向上にも役立ちます。
導入時の注意点と課題
便利で多くのメリットがあるセルフオーダーシステムですが、導入する際には事前に把握しておきたい注意点や課題も存在します。
導入後にトラブルが起きないよう、以下のポイントをしっかり押さえておきましょう。
導入コストとROIの見極め
セルフオーダーシステムの導入にあたっては、初期費用とランニングコストのバランスを事前に把握しておくことが重要です。
初期投資としては、タブレットやキオスク端末などの機器代に加えて、ソフトウェア使用料や保守・サポート費用も発生します。
そのため、単なる導入価格だけで判断するのではなく、総コストと見込まれる効果の両面から、ROI(投資対効果)を検討することが重要です。
スタッフや顧客のリテラシー対応
システムの利便性が高くても、利用する側が操作に不慣れであれば、スムーズな運用にはつながりません。
とくに高齢者やデジタルデバイスに慣れていない層に対しては、簡単な使い方の案内やスタッフによるサポートが求められる場面もあります。
また、店舗スタッフに対しても、新しい業務フローやトラブル時の対応方法などを事前に教育しておくことが欠かせません。
導入当初は有人サポートを併用するなど、段階的な定着を図ることがスムーズな運用につながります。
店舗環境に合った運用設計
セルフオーダーシステムは、店舗の規模や業態、客層によって適切な設置方法や運用スタイルが異なります。
たとえば、キオスク端末を設置するには一定のスペースが必要となり、入口の動線や混雑状況を考慮した配置計画が求められます。
また、「回転率を重視する店舗」と、「長時間の滞在を前提とした店舗」では、求められる機能や表示方法にも違いが出てくるため、自店の特性に応じた最適な運用設計が不可欠です。
システムトラブル時の対応体制
IT機器を活用する以上、通信エラーやハードウェアの故障など、トラブルの発生はゼロではありません。システムが停止すれば注文業務が滞り、営業に大きな支障をきたす恐れもあります。
こうしたリスクを最小限に抑えるためには、導入前にベンダーのサポート体制を確認し、トラブル時の対応フローを整えておくことが大切です。
安定した運用を支えるためには、技術面だけでなく、スタッフの対応体制やマニュアル整備など、運営面での備えも重要なポイントとなります。
セルフオーダーシステムの導入ステップと準備事項
セルフオーダーシステムは、導入するだけで効果が得られるものではありません。自店舗の業態や課題に合ったシステムを選び、運用を円滑にスタートさせるためには、事前の準備が必須です。
ここでは、導入までに押さえておきたい基本的なステップと、現場で混乱を招かないための準備事項について解説します。
導入の目的を整理し、最適なシステムを選定する
まず重要なのは、「なぜセルフオーダーを導入するのか」という目的を明確にすることです。
人手不足の解消・回転率の向上・非接触対応の強化など、目的によって求められる機能や運用スタイルは大きく異なります。
たとえば、以下のように店舗ごとに適している型式は異なります。
- テーブル単位での注文回数が多い店舗:タブレット型
- 回転率重視の店舗:キオスク端末型
- テイクアウト店:モバイルオーダー型
現場のオペレーションとの相性を見極めながら、必要な機能・導入コスト・拡張性などを比較し、自店舗に合ったシステムを選定することが成功の第一歩となります。
ネットワーク・端末の環境整備も重要
システムを安定的に運用するためには、インターネット環境や端末設置に関する事前準備も不可欠です。
特にWi-Fiを利用するタイプのシステムでは、通信の安定性が注文処理や決済のスムーズさを左右します。
「電波の届きにくい場所がないか」や、「複数台の端末に対応できるか」を事前に確認しておきましょう。
また、タブレットやキオスク端末などのハードウェアも、操作性や視認性、設置スペースとのバランスを考慮する必要があります。
デバイスの設置場所が混雑や導線を妨げないように、店舗レイアウトとの整合性も踏まえて計画することが大切です。
スタッフへの教育とテスト運用で現場を慣らす
システムを円滑に運用するためには、スタッフ全体が仕組みを理解し、実際の業務に慣れておくことが重要です。
そのためには、導入前の研修を通じて、基本的な操作や対応方法をあらかじめ身につけておく必要があります。
たとえば、次のような内容を事前に共有しておくと安心です。
- 注文データの確認や処理の流れ
- 機器の不具合や通信エラーなど、トラブル発生時の対応方法
- 操作に不慣れなお客様へのサポート対応
また、本格運用に入る前には、実際の営業に近い形でテスト導入を行い、システムの動作や業務フローに問題がないかを確認しておくと効果的です。
現場からの意見をもとに必要な修正を加えておけば、導入後の混乱を最小限に抑え、スムーズな定着につながります。
まとめ
セルフオーダーシステムは、人手不足や注文ミスといった現場の課題を解消しながら、顧客にとってもスムーズで快適な注文体験を提供できる仕組みです。
タブレット型やモバイルオーダー型など、店舗の業態や目的に応じて最適な形式を選ぶことで、業務効率とサービス品質の向上を同時に図ることができます。
自店舗に合ったセルフオーダーシステムを選定し、スタッフの教育環境を整え、売上アップや店舗業務の効率化につなげていきましょう。
関連記事▼
TOUCH TO GO の セルフ/セミセルフレジ「TTG-MONSTAR」を導入することで、常駐スタッフの負担が軽減され、人件費が大幅に削減できます。
注文〜決済まで一台で完結できるセルフ/セミセルフレジの導入をご検討中の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TTG-MONSTAR の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download1/
RECOMMEND / この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます
-

-

デパ地下の惣菜事情について
デパ地下の惣菜市場は、日本の食文化において重要な役割を果たしています。そこでは和洋を問わず、幅広い惣菜が取り揃えられ、忙しい現代人にとって便利で美味しい食事の提供をしています。一方...
-

テナントの家賃交渉を成功させるタイミングとは?|方法や注意点も解説
こんにちは。無人決済店舗システムを提供しているTOUCH TO GO 編集部です。 テナントを借りて店舗を運営している方にとって、毎月発生する家賃は大きな固定費のひとつです。 そこ...
-

免税事業者のメリットとデメリット:企業にとっての選択肢
こんにちは。無人決済店舗システムを提供しているTOUCH TO GO 編集部です。 企業が持つ重要な戦略の一つは、税制優遇を利用することで負担を軽減し、経済的な競争力を向上させるこ...