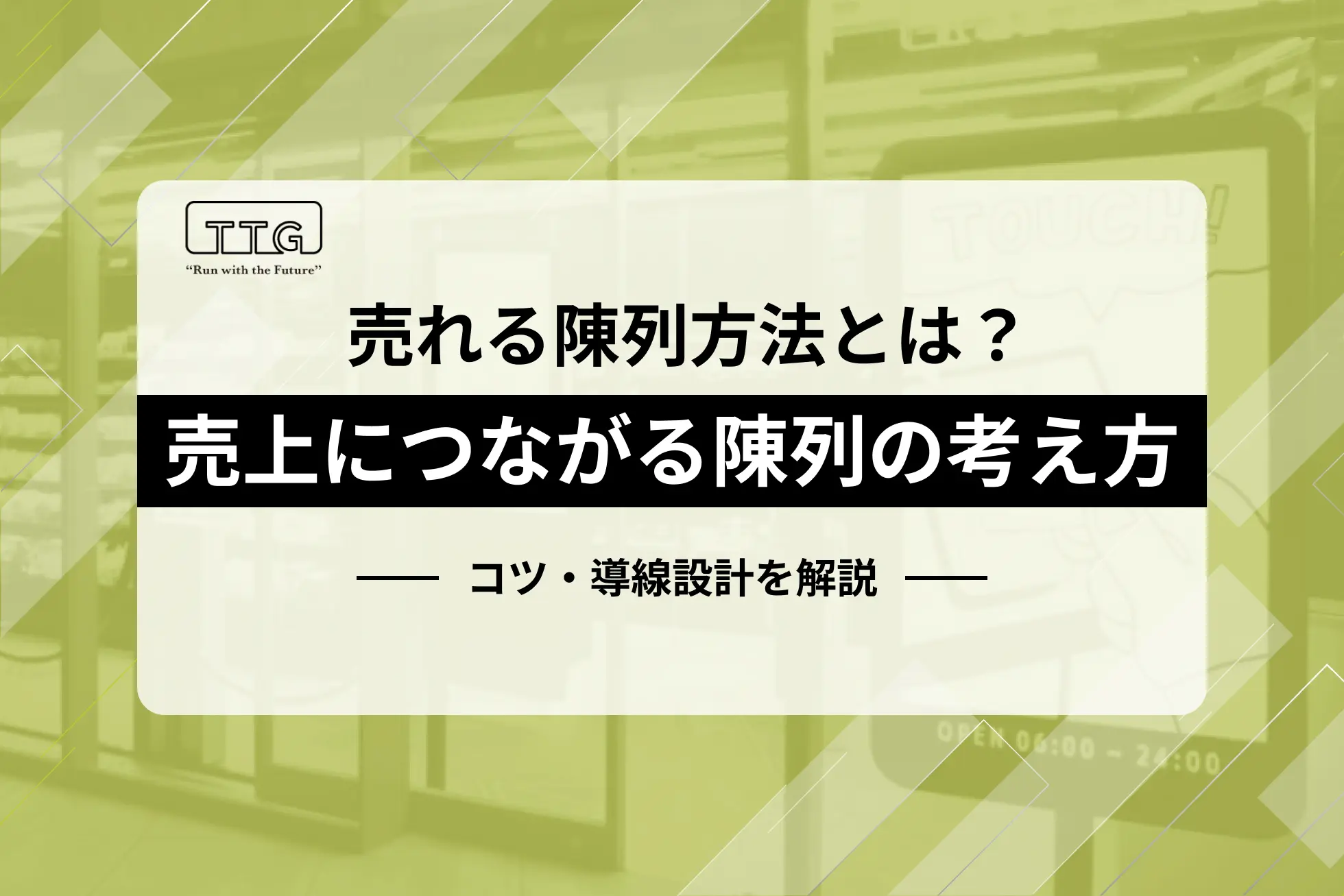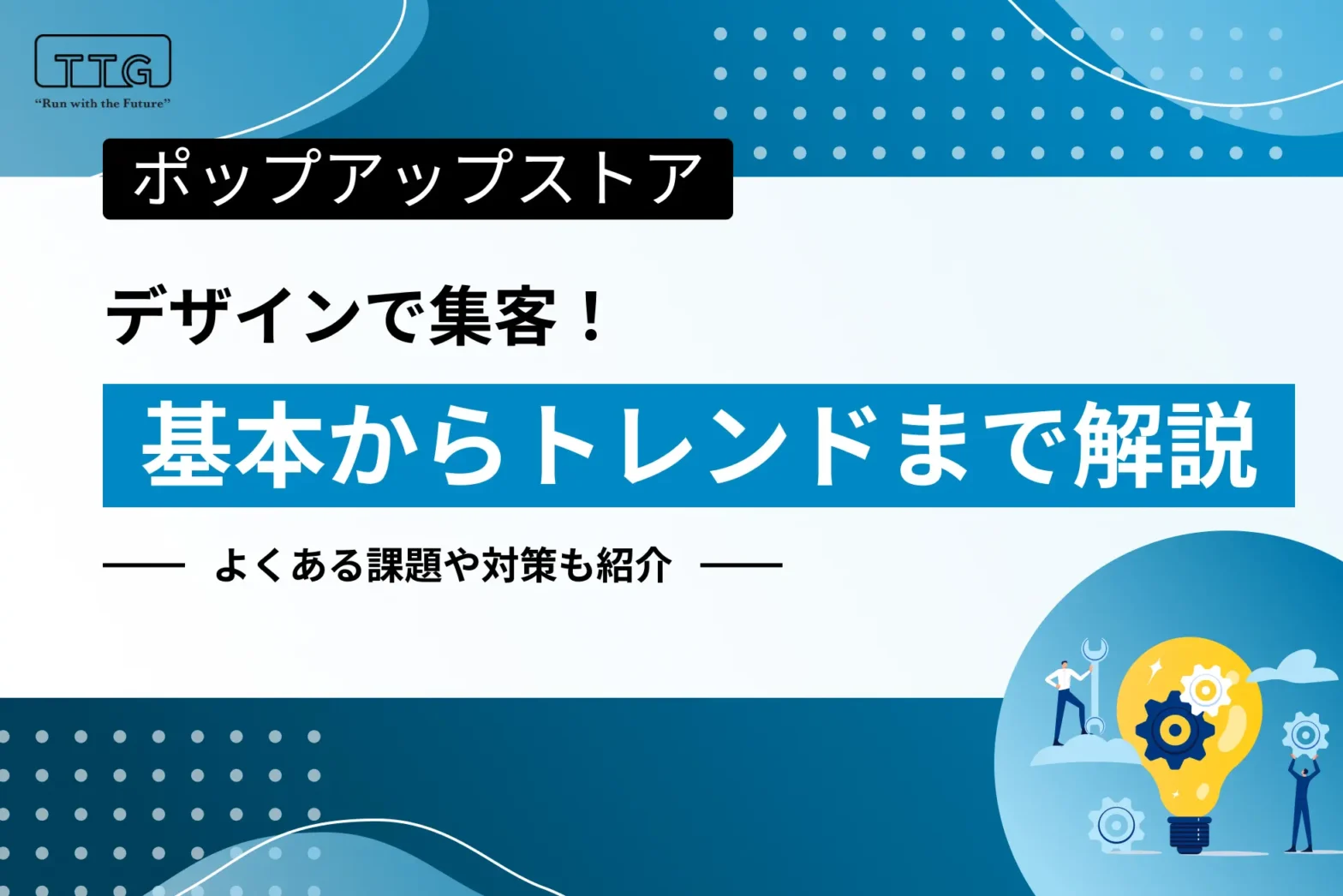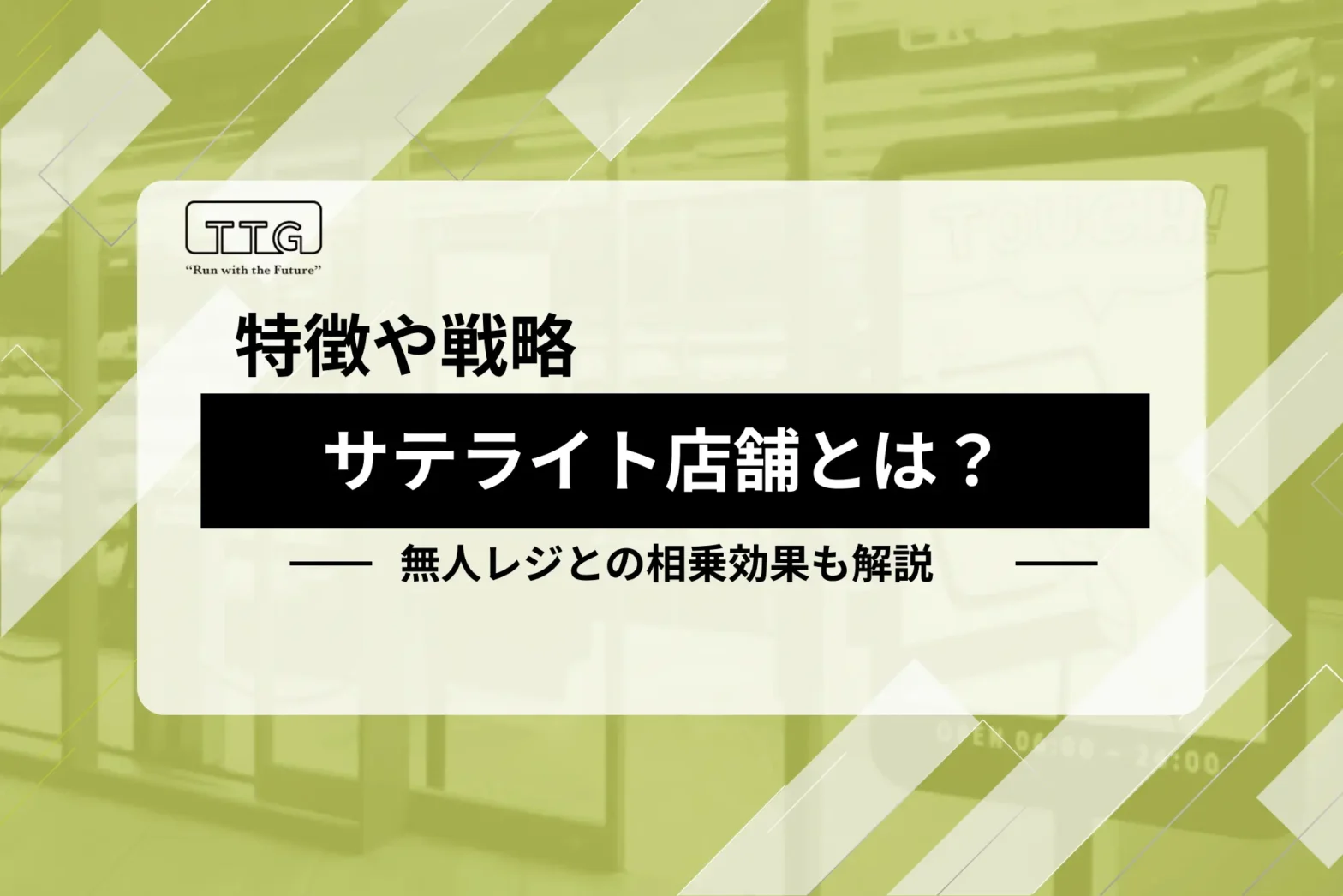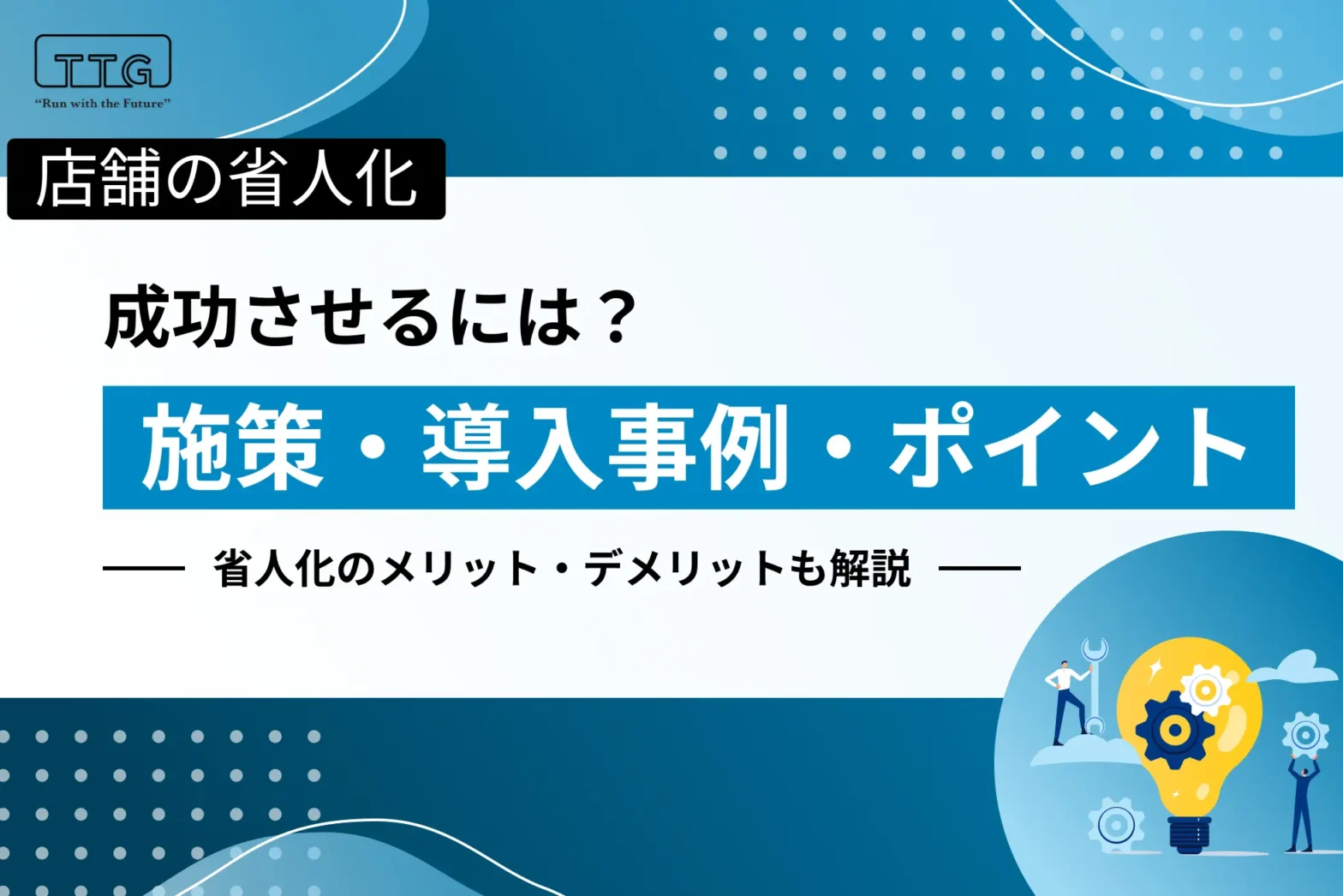Category
こんにちは。無人決済店舗システムを提供しているTOUCH TO GO 編集部です。
店舗の売上を左右する要素として、「商品の並べ方」は非常に重要です。
どれだけ良い商品でも、陳列やレイアウトが工夫されていなければ、手に取られずに終わってしまうこともあります。
一方で、視線の誘導や動線の工夫、POPや什器の使い方を見直すだけで、購買率が大きく変わることも少なくありません。
この記事では、売れる陳列の基本から実践的な配置のコツ、店舗設計の考え方まで詳しく解説します。
店舗の売場改善に取り組みたい方は、ぜひ参考にしてください。
関連記事▼
監修者プロフィール

2019年に株式会社TOUCH TO GOを設立。無人決済店舗システムを提供し、次世代型小売の拡大に取り組んでいる。
目次
売れる陳列とは何か?
商品の並べ方ひとつで売上が変わる背景には、「陳列」が単なる整頓作業ではなく、売れる仕組みの一部として機能しているという考え方があります。
ここでは、売れる陳列の基本的な捉え方を確認していきましょう。
陳列の目的は「商品を見せること」だけではない
商品を見える位置に並べるだけでは、売上に結びつくとは限りません。
売れる陳列とは、顧客の目に留まって足を止め、手に取ってもらい購入へと進む一連の行動を自然に導く配置設計を意味します。
そのためには、「どの商品を・どこに・どのような順序や流れで配置するか」といった視点が必要です。
見た目の整然さだけでなく、顧客の動きと視線を想定した売場づくりが、陳列の効果を最大限に発揮する鍵となります。
リアル店舗ならではの「視覚・感覚への訴求」が売上を左右する
リアル店舗には、オンライン販売にはない特徴があります。それは、視覚・嗅覚・触覚など、五感に直接訴える空間演出ができることです。
特に重要なのが視覚への訴求です。顧客の視線を自然に誘導し、商品に注目させる工夫があるかどうかで、購買行動の確率は大きく変わります。
高さ・色・光・角度など、目に入りやすい工夫がなされた陳列は、商品価値の印象そのものを高める効果があります。
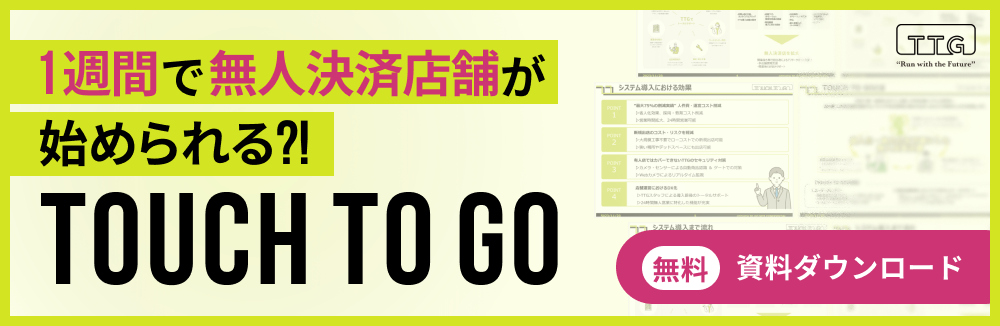
TOUCH TO GO の 無人決済店舗システムは、カメラで人物をトラッキングし、どの棚のどの商品が何個お客様の手に取られたかをセンサーで感知します。
店舗の売り場改善として無人店舗の導入をご検討中の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/
売れる陳列の基本原則
売上につながる陳列には、基本的な考え方があります。ここでは、どの業種・業態でも参考にできる、汎用性の高い陳列の原則について解説します。
ゴールデンゾーンを意識する
もっとも購買につながりやすいのが「ゴールデンゾーン」と呼ばれるエリアです。
これは、顧客の目の高さから腰の位置あたりまでの範囲を指し、視認性と手の届きやすさが両立することから、”最も注目されやすい場所”とされています。
以下のような商品は、このゾーンに優先的に配置することで、手に取られる可能性が高まります。
- 主力商品
- 利益率の高い商品
- 初見で魅力を伝えたい商品
逆に、ゴールデンゾーンを軽視した陳列では、目立たせたい商品が埋もれてしまうこともあるため注意が必要です。
フェイシング(面出し)の工夫で印象を整える
フェイシングとは、棚に陳列する際に、商品が正面を向いて整列されている状態を指します。
視認性や統一感を高めるだけでなく、商品の存在感を強調するうえでも効果的です。
たとえば、同じ商品を横並びに3面以上見せることで、数量感や人気感を演出することも可能です。
フェイシングの最適化は、商品棚全体の“見やすさ”や“選びやすさ”を高める要素として、基本の取り組みといえます。
カテゴリー分けと関連性のある配置
陳列する際は、商品同士の「意味的なつながり」を意識することが大切です。
カテゴリーごとにまとまりをつくることで、顧客が目的の商品を見つけやすくなり、比較や選択もしやすくなります。
さらに、使用シーンや用途が共通する商品同士を隣接させることで、自然な“ついで買い”の導線が生まれます。
関連性をもたせた配置は顧客の購買ストレスを軽減し、満足度の向上にもつながります。
第一印象を左右する「入口付近」の陳列
店舗の入口付近は、来店者が最初に目にする重要なエリアです。
ここでは、季節の注目商品やプロモーション対象商品など、初見で印象に残したい商品を配置するのが効果的です。
また、店舗の世界観や取扱ジャンルを伝える役割も担っており、入口の陳列が与える印象は、そのまま購買意欲や滞在時間にも影響する可能性があります。
最初の5秒で期待を持ってもらえるような構成を意識しましょう。
購買意欲を高める陳列テクニック
基本を押さえたうえで、さらに売上を伸ばすためには、視線の動きや心理的な効果を意識した応用的なテクニックも取り入れることが効果的です。
ここでは、実践に活かしやすい陳列手法を紹介します。
トライアングル陳列・Z陳列など視線誘導の手法
視線の流れをコントロールする陳列技術として、「トライアングル陳列」や「Z陳列」が挙げられます。
トライアングル陳列は、商品を三角形を描くように高低差をつけて配置する方法で、自然と中央に視線が集まる効果があります。
一方、Z陳列は、左から右・右から左へとジグザグに目線を動かす配置で、棚全体をしっかりと見てもらいたい場合に有効です。
これらの手法は単調な棚に動きや立体感を加え、興味を引きやすくする視覚的演出として役立ちます。
クロスMDで「ついで買い」を引き出す
クロスMD(クロスマーチャンダイジング)は、異なるカテゴリの商品をあえて組み合わせて陳列する手法です。
たとえば、パスタソースの近くに乾麺を配置したり、靴売場で靴下や中敷きを並べたりといった例が挙げられます。
これにより、関連性に気づかなかった顧客に新たな購買動機を提供できるとともに、「まとめて買う」行動を自然に誘発できます。
クロスMDは、単価アップや在庫回転の促進にもつながる柔軟な販促手段です。
数量感の演出
同じ商品でも、数個だけ陳列されている場合と大量に陳列されている場合では、受け取られ方が異なります。
陳列数をあえて多めに見せることで、「人気がある」「売れている」「今が買い時」といった印象を与えることができます。
また、ボリューム陳列によって目を引きやすくなり、購買の勢いを生む効果も期待できます。
ただし、整理されていない印象を与えると逆効果になるため、整然とした配置を意識することが大切です。
期間限定・季節感のある演出で即決を促す
「今しか買えない」「季節に合っている」といった要素は、購買行動を後押しする大きな要因になります。
季節商品や期間限定アイテムを明確に打ち出すことで、即時購入を促す心理的な刺激を与えられます。
さらに、装飾やPOP、色づかいなどを季節に合わせて変えることで、店舗全体の印象にもメリハリが出ます。
購買意欲のピークを逃さないよう、タイミングと見せ方を戦略的に組み立てることが重要です。
動線とレイアウトの設計ポイント
どれだけ陳列に工夫を凝らしても、お客様が売場に足を運ばなければ商品は見られません。
売れる陳列を実現するうえでは、店舗全体の動線設計とレイアウトの考え方も欠かせない要素です。
ここでは、店内の動線とレイアウト設計のポイントを解説します。
顧客の「回遊行動」を想定した陳列とは
店舗では、以下のような「回遊行動」を想定した設計が重要になります。
- 来店者がどのルートを通り
- どこで足を止め
- 何を手に取るか
具体的には、一方通行にならずに店内を自然に回ってもらえるようなレイアウトを意識することで、接触機会が増えて購買率が向上します。
陳列を考える際も顧客の目線や歩くスピードに合わせて、視認性の高い場所や「つい立ち寄ってしまう」構造を取り入れることが効果的です。
滞留しやすい場所と回遊しやすい通路の考え方
店舗内には、「滞留ポイント」と呼ばれる、人が立ち止まりやすい場所が自然と生まれます。
たとえば、以下は視界に入りやすく動線がぶつかるため、陳列の効果が出やすい場所となります。
- 入口すぐのスペース
- 柱の周囲
- コーナー部分
一方で、店内が狭すぎたり商品が過密に並べられていたりすると、動きづらさが不快感につながり、早々に退店されてしまうリスクもあります。
回遊性を確保するためには、通路幅や導線の“抜け感”を意識した設計が必要です。
「視線が集まる場所」の活用方法
売場の中でも、自然と視線が集まりやすいスポットを「視認性の高いゾーン」として活用することが売上に直結します。
具体的には、入口付近・レジ待ちの列ができやすい場所・棚の端などが該当します。
これらの場所に、目玉商品や季節のプロモーション商品を配置することで、高い確率で「目に触れる」→「手に取られる」という流れを生み出しやすくなります。
店内全体の売上バランスを考慮しつつ、最も効果の出やすい場所をどの商品に割り当てるかは、戦略的に判断することが大切です。
売れる陳列に必要な販促ツールと演出
商品をただ並べるだけでは、顧客の興味・関心を十分に引き出すことはできません。
視覚や感覚に訴える「演出」や「販促ツール」の活用によって、陳列の効果をさらに高めることが可能です。
そこで、ここからは、商品を売りやすくなる販促ツールや演出方法を紹介します。
POPの役割と効果的な見せ方
POPは、商品の魅力や特徴を補足する情報ツールです。価格だけでなく以下の情報を提示することで商品への理解を深め、購買意欲を高める効果があります。
- 使用方法
- ターゲット
- 効果
- スタッフのおすすめ
特に多くの人が初めて見る商品や説明が必要な商材では、“言葉による補足”が意思決定を後押しする要因になります。
目立たせたい商品には、視認性の高い位置・サイズ・配色で配置し、文字数は簡潔にまとめるのが基本です。
照明・什器・カラー設計による視覚的印象の強化
照明や什器(ディスプレイ用の棚・台)などの売場設備も、陳列の印象を大きく左右します。
たとえば、スポットライトで一部の商品を強調したり、什器の素材や高さを統一することで、高級感や統一感を演出できます。
また、売場全体やコーナーごとの色のバランスを意識することで、見やすく落ち着いた印象を与えたり、季節感やコンセプトを伝えたりできます。
五感を活用する売場演出
陳列と演出をより深く連動させるためには、視覚だけでなく五感に訴える工夫も効果的です。
たとえば、香りを活用して空間の雰囲気を演出したり、BGMで購買心理を刺激したりといった施策が挙げられます。
これらの要素は、「この商品を実際に使ってみたい」「印象に残る」といった感情的な接点を生み、ブランド理解や購買決定を後押しする役割を担います。
物理的な並べ方に加えて空間自体の演出も、売れる陳列には欠かせない視点です。
まとめ
売れる陳列をつくるには、商品をただ並べるのではなく”顧客心理”を意識した設計が欠かせません。
基本原則に加えて、視覚演出や導線設計、販促ツールをうまく活用することで、売場の魅力は大きく変わります。
日々の売上を左右する要素として、陳列は改善の余地が大きい部分といえます。
商品力と見せ方の両面から売場を見直し、購買につながる環境を整えていきましょう。
近年、増加傾向にある『無人店舗』に興味がある方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
関連記事▼
TOUCH TO GO の 無人決済店舗システムは、カメラで人物をトラッキングし、どの棚のどの商品が何個お客様の手に取られたかをセンサーで感知します。
店舗の売り場改善として無人店舗の導入をご検討中の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/