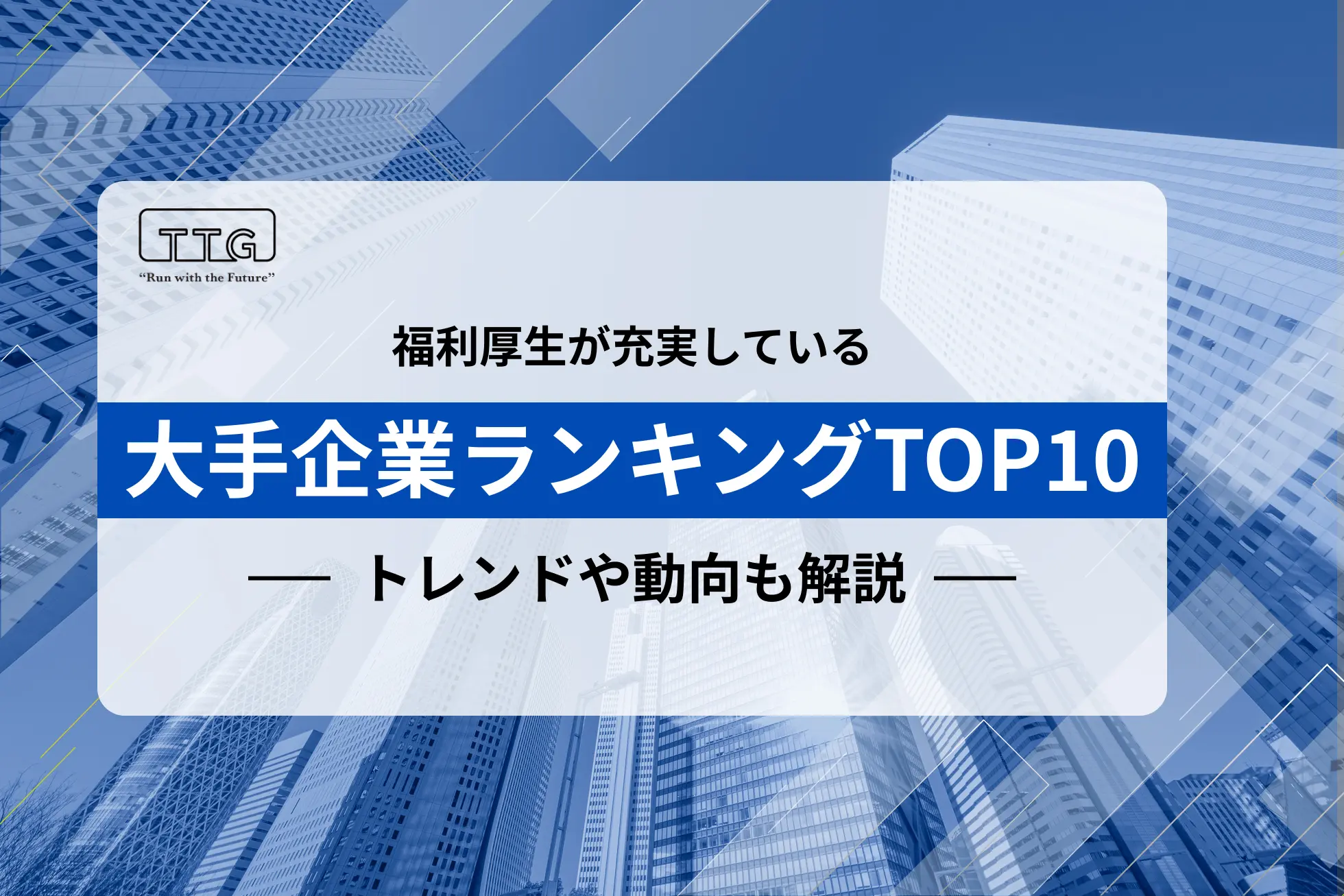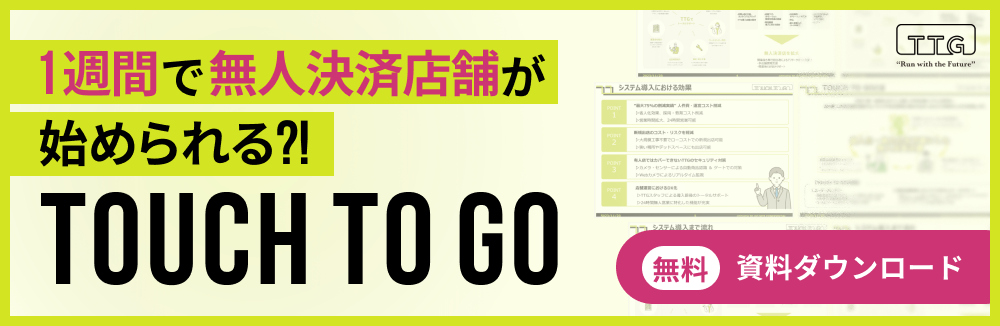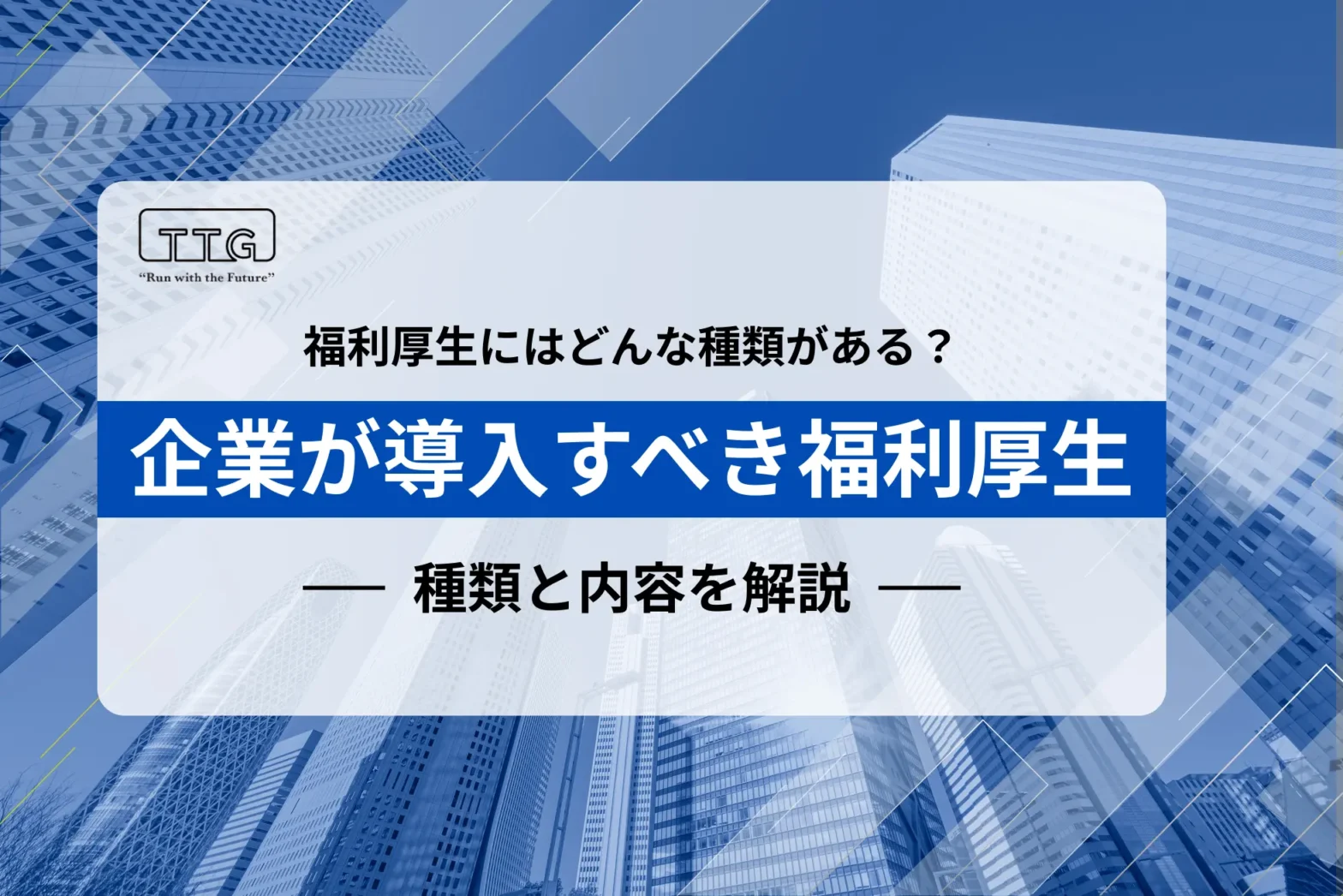Category
こんにちは。無人決済店舗システムを提供しているTOUCH TO GO 編集部です。
働き方やライフスタイルが多様化する中で、企業の「福利厚生」に注目が集まっています。
特に大手企業は、従業員満足度の向上や優秀な人材の確保を目的に、他社と差がつくような独自の制度を次々と導入しています。
そこで本記事では、福利厚生が充実している大手企業をランキング形式で紹介します。
さらに、近年の福利厚生のトレンドや、企業がどのような視点で制度を整えているのかについても解説しています。
自社制度の見直しを検討している方は、ぜひチェックしてみてください。
関連記事▼
「あると嬉しい福利厚生」ランキングTOP10|男女別の傾向も解説
【最新版】従業員幸福度ランキング|幸福度が高い企業の特徴とは?
監修者プロフィール

2019年に株式会社TOUCH TO GOを設立。無人決済店舗システムを提供し、次世代型小売の拡大に取り組んでいる。
目次
有給休暇の取得率が高い大手企業ランキング
福利厚生が手厚い企業は、従業員の働きやすさを支える土台として、就職・転職市場でも高く評価されています。
中でも「有給休暇の取得率」は、制度がしっかり運用されているかどうかを示す一つの指標として注目されています。
そこで今回は、東洋経済オンラインが公表した「有給休暇の取得率が高い200社ランキング」を参考に、福利厚生が充実している大手企業をランキング形式でご紹介します。
※掲載している福利厚生の内容は変更されている可能性もあるため、実際の制度については各企業の最新情報をご確認ください。
1位DMG森精機(有給取得率 109.4%)
1位にランクインしたのは、NC旋盤やマシニングセンタで知られるDMG森精機です。直近3年間の有給取得率は109.4%に達し、昨年の2位から順位を一つ上げてトップとなりました。
同社は「よく遊び、よく学び、よく働く」というスローガンを掲げ、有給休暇の取得を積極的に促進しています。
さらに、「遊び」「学び」「仕事」の各分野で優れた取り組みを行った従業員を毎月表彰し、奨励金を支給する制度も実施。
こうした取り組みにより、仕事とプライベートの両面から従業員の充実を支援している点が大きな特徴です。
2位トヨタ車体(有給取得率 101.3%)
2位には、トヨタグループの完成車メーカーであるトヨタ車体がランクイン。3年平均の有給取得率は101.3%と高水準を維持しています。
同社では、有給休暇を翌年度以降に繰り越せる制度を整備しているほか、取得忘れによる失効を防ぐために「年休カットゼロ」を掲げた取り組みを行っています。
この取り組みの成果として、1994年度から現在に至るまで、有給休暇の失効ゼロを28年連続で実現しているのが大きな特徴です。
3位クボタ(有給取得率 100.8%)
3位には、農業機械などを手がける大手メーカーのクボタが入りました。3年平均の有給取得率は100.8%と高い数値を記録しています。
同社では、年次有給休暇の一部を時間単位で取得できる制度を導入しており、年間で最大5日分までを細かく使える仕組みが整っています。
ちょっとした私用や急な用事にも対応しやすく、柔軟な働き方をサポートしています。
4位ホンダ(有給取得率 100.4%)
4位は、日本を代表する自動車メーカー・ホンダです。3年間の平均有給取得率は100.4%と非常に高く、制度面・文化面の両方で有給取得を後押ししています。
入社後わずか2ヶ月で所定の勤務日数を満たせば、一律で10日間の有給休暇が付与されるという、法定よりも早い対応が特徴的です。
その後も勤続年数に応じて日数が加算され、半日単位での取得や、3日・5日間といった連続取得も推奨されています。
5位エイチワン(有給取得率 99.3%)
5位には、自動車用プレス部品を製造するエイチワンがランクイン。取得率は99.3%と高く、すべての有給休暇を半日単位で利用できる柔軟な制度を導入しています。
また、フレックスタイム制度も取り入れており、従業員一人ひとりの生活リズムや都合に合わせた働き方を実現できる点が特徴です。
6位〜10位の企業
6位は建設機械メーカーのコマツ(99.2%)。続いて、7位には豊田自動織機とテイ・エス テックが同率で並び(98.5%)、それに関西電力(96.6%)、デンソー(96.5%)が続きます。
いずれの企業も、休暇制度を積極的に活用できる環境づくりに取り組んでおり、福利厚生面でも高い評価を得ています。
「TOUCH TO GO」では、お弁当や飲料などを購入できるオフィスコンビニをカンタンに導入できます。
従業員の多様なニーズに対応できるオフィスコンビニを導入したい方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/
福利厚生のトレンドと今後の動向
時代の変化とともに、企業が提供する福利厚生のあり方も大きく変わってきました。
かつては一律の手当や施設利用といった“画一的”な制度が中心でしたが、近年では従業員のライフスタイルや価値観に応じた“柔軟性”が求められるようになっています。
ここでは、最近注目されている福利厚生の傾向と、今後の方向性について見ていきましょう。
多様性を重視した新しい福利厚生の導入
従業員一人ひとりの価値観やライフステージが異なる中で、多様性を前提とした福利厚生が広がりを見せています。
たとえば、LGBTQ+フレンドリーな制度、選択的週休3日制、不妊治療や卵子凍結への支援制度などがその代表例です。
また、「推し活休暇」「誕生日休暇」など個人の趣味や生活を尊重するユニークな取り組みも増えてきました。
こうした制度は、企業の柔軟性や包容力を示すものとして、若い世代からの評価も高まりつつあります。
関連記事>>ユニークな福利厚生で差をつける!世界・日本の導入事例と成功の秘訣
リモートワーク対応の福利厚生制度
働く場所の自由度が広がる中で、リモートワークを前提とした福利厚生の整備も進んでいます。
リモートワーク対応の福利厚生の代表的な例は、次のとおりです。
- 在宅勤務用の備品購入補助
- 通信費の支給
- リモート環境に配慮した健康支援
また、出社を前提としない社内コミュニケーションの活性化を目的に、オンライン懇親会の費用補助や、バーチャルオフィスを導入している企業もあります。
キャリア形成を支援する制度の拡充
従業員の成長をサポートする「キャリア支援型」の福利厚生も、重要性が増しています。
具体的には、以下のような制度が挙げられます。
- 資格取得支援
- eラーニングの無償提供
- 副業・兼業を後押しする制度
- 社内公募・キャリアチャレンジ制度
企業が個々のキャリア形成に関心を持ち、機会を与えることで、従業員のモチベーション向上と定着率の向上にもつながります。
今後は「会社にとって必要な人材」ではなく、「従業員自身が望むキャリア」を応援する制度設計が求められていくでしょう。
福利厚生の見直しで企業が得られるメリット
福利厚生は従業員のためだけの制度と思われがちですが、実は企業側にとっても多くのメリットがあります。
制度の設計や運用を見直すことで、さまざまな面に良い影響をもたらします。ここでは、特に注目される6つのメリットについて見ていきましょう。
優秀な人材の確保
福利厚生が充実している企業は、求職者にとって「働きやすさ」や「安心感」が感じられる存在となり、応募の動機づけにつながります。
特にスキルや経験のある人材ほど、給与だけでなくライフスタイルへの配慮や成長機会なども重視する傾向が強く、福利厚生は差別化の重要な要素となります。
採用競争が激しくなる中で、魅力的な福利厚生制度は優秀な人材を引き寄せる大きな武器になります。
定着率向上
入社後に「長く働きたい」と感じてもらえるかどうかは、福利厚生の質と運用にも左右されます。
たとえば、次のような環境や制度が整っていると、従業員の満足度やエンゲージメントが自然と高まりやすくなります。
- 仕事と私生活を両立できる環境
- 成長を応援してくれる制度
- 自分に合った働き方を選べる柔軟性
このような職場環境を整えることで、従業員の定着意欲が高まり、離職率の低下や中長期的な定着率の向上につながるでしょう。
企業イメージの向上
働きやすさを重視する制度が整っている企業は、外部からの評価も高まりやすくなります。
就職・転職サイトの口コミやSNS、採用説明会などでも「福利厚生の充実」は強みとして伝えられることが多く、ブランディングの一部としても活躍します。
また、従業員が実際に制度を活用して満足している様子は、企業の信頼性や透明性を感じさせる材料にもなります。
従業員のモチベーション向上
福利厚生は、単なる“お得な制度”にとどまらず、「自分は会社に大切にされている」と感じるきっかけになります。
そうした安心感や信頼感があると、日々の業務にも前向きに取り組めるようになり、結果としてやる気の向上につながります。
特に、「表彰制度」や「インセンティブ」、「キャリア支援」など、努力がきちんと評価される環境が整っていると、目標に向かって頑張ろうという意欲が生まれやすくなります。
モチベーションが安定している従業員は、チーム内の雰囲気づくりにも良い影響を与えるため、組織全体にもプラスの効果が広がります。
生産性の向上
従業員の働きやすさを重視した福利厚生は、業務の効率アップにもつながります。
たとえば、フレックスタイム制度やリモートワークの導入によって通勤ストレスが減ると、集中力の高い時間帯に仕事をこなせるようになります。
また、食事補助や休憩スペースの充実といった取り組みも、日々のパフォーマンスを支える重要な要素です。
体調不良時に無理をさせない仕組みや、メンタルヘルスケアの制度などがあることで、長期的な視点でも安定した稼働が見込めるようになるでしょう。
このような取り組みを導入し、個人のパフォーマンスが上がれば、チームや部門全体の生産性向上にもつながります。
まとめ
本記事では、有給休暇の取得率を指標に、福利厚生が充実している大手企業をランキング形式でご紹介しました。
上位にランクインした企業には、取得しやすい制度設計だけでなく、従業員一人ひとりが働きやすさを実感できるような柔軟で多様な取り組みが見られます。
近年では、福利厚生の内容も大きく変化しています。
制度を充実させることは、従業員にとってのメリットだけでなく、企業イメージの向上にもつながる重要な施策といえます。
福利厚生の見直しを検討している担当者様は、ぜひ以下も参考にしてみてください。
関連記事▼
従業員に喜ばれるオフィスの福利厚生12選|メリット・デメリットも解説
会社の魅力を高める福利厚生とは?ユニークな福利厚生7選も紹介!
「TOUCH TO GO」では、お弁当や飲料などを購入できるオフィスコンビニをカンタンに導入できます。
従業員の多様なニーズに対応できるオフィスコンビニを導入したい方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/