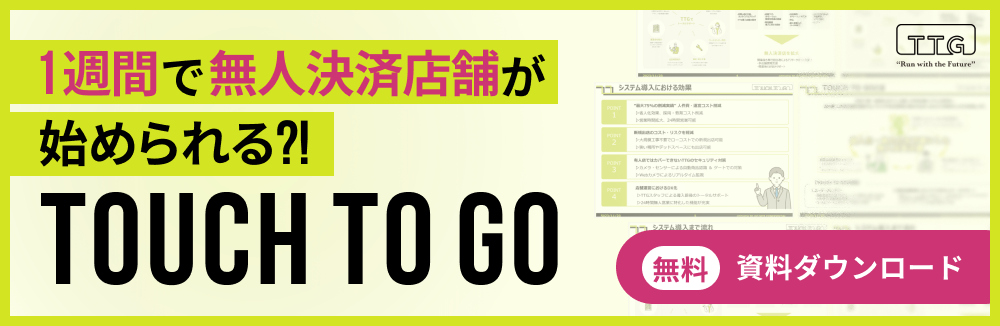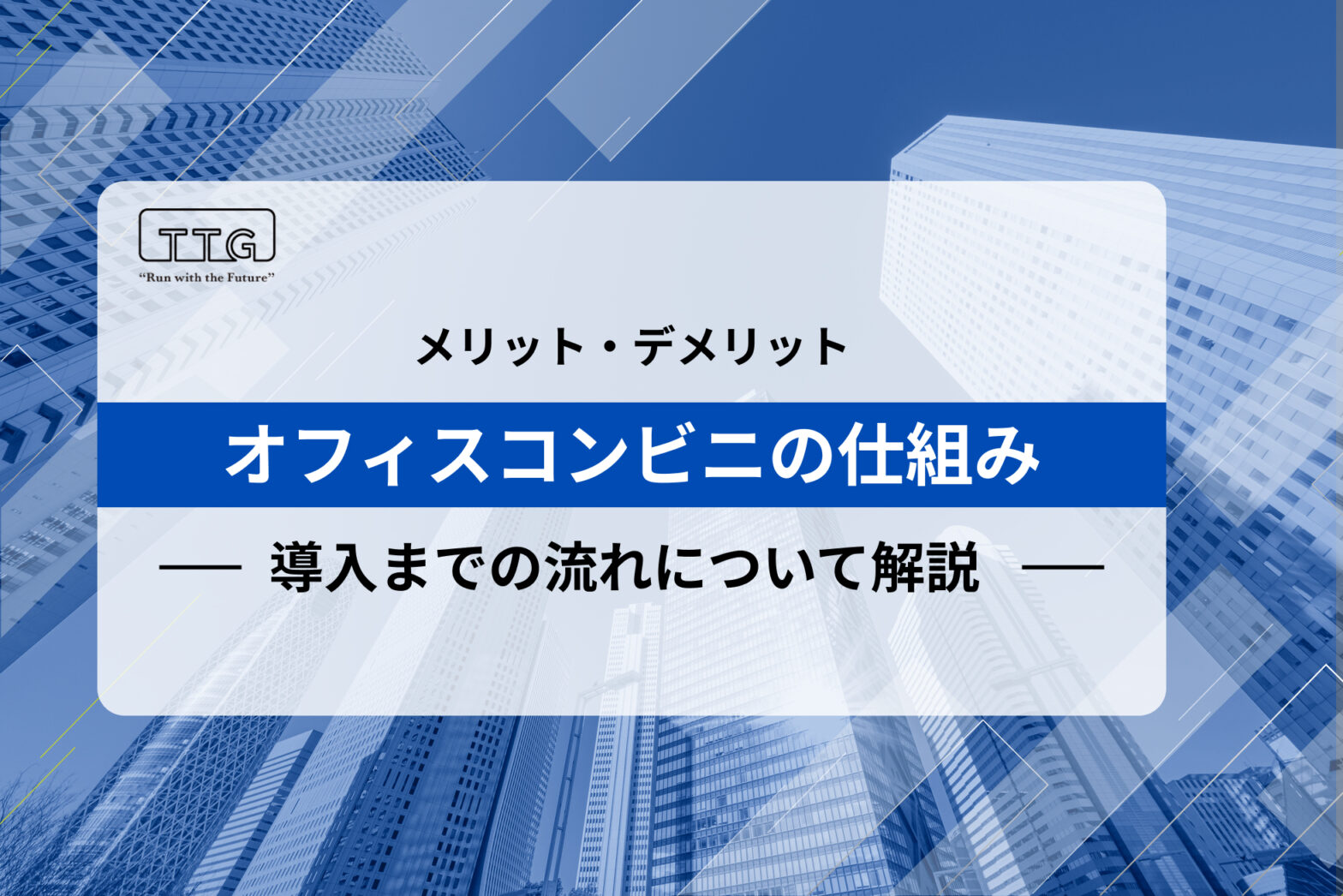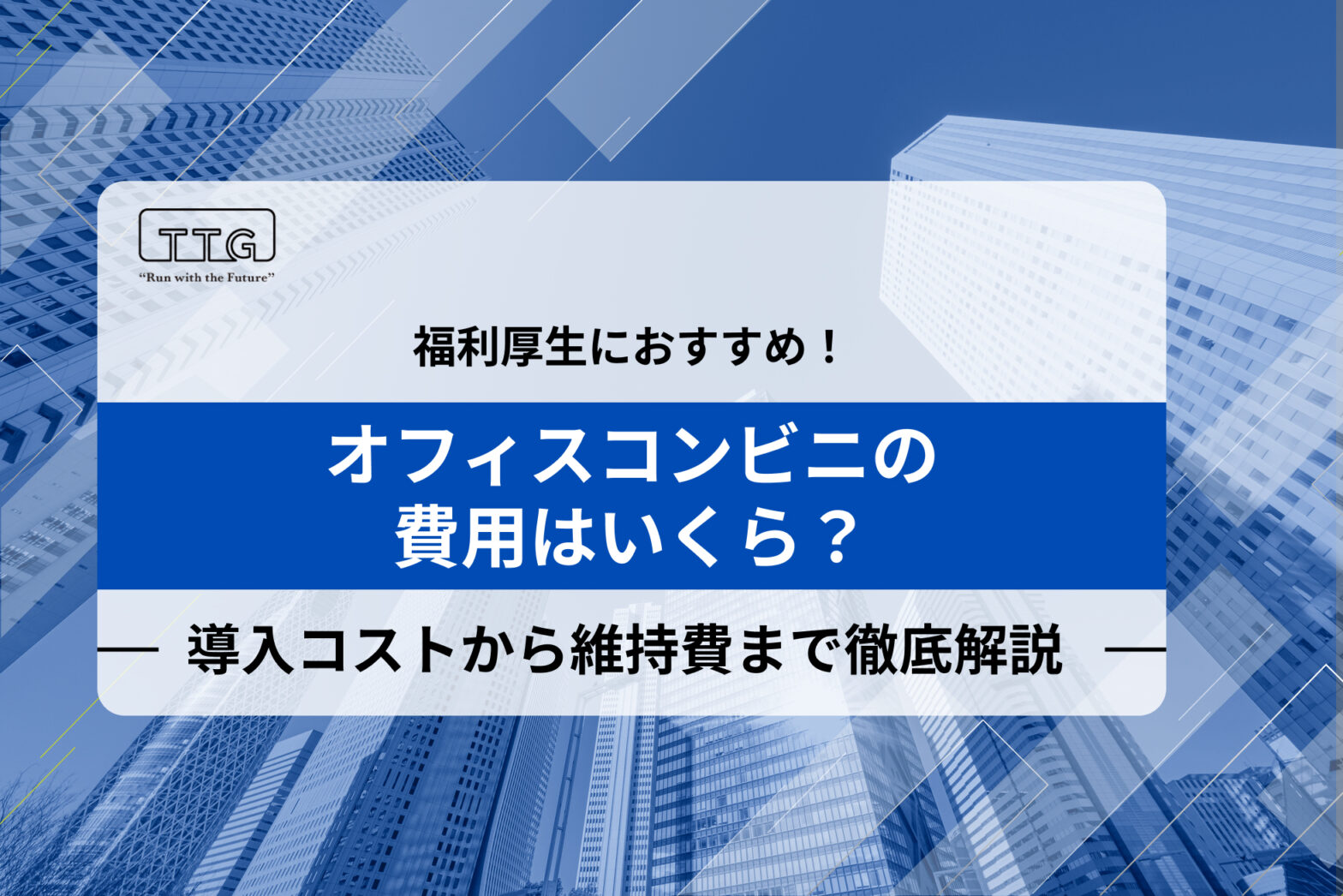Category
こんにちは。無人決済店舗システムを提供しているTOUCH TO GO 編集部です。
オフィスに置き菓子を導入することで、社員のリフレッシュやコミュニケーション促進が期待できる一方で、福利厚生費として計上できるかどうかが気になるところです。
実際、どんなお菓子が福利厚生費に該当するのか、また導入にあたって注意すべきポイントは何か、気になる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、オフィスの置き菓子が福利厚生費として、認められるケースと認められないケースを解説します。
導入前に知っておくべきポイントもまとめているので、ぜひ参考にしてください。
関連記事>>オフィス向け置き菓子サービスを導入するメリット|おすすめサービスも紹介
監修者プロフィール

2019年に株式会社TOUCH TO GOを設立。無人決済店舗システムを提供し、次世代型小売の拡大に取り組んでいる。
目次
置き型の福利厚生でお菓子は人気!
『おやつ体験BOX』などの置き菓子サービスを提供する「株式会社スナックミー」の調査では、職場にあったら利用したい置き型の福利厚生の食品ジャンルとして、お菓子が最も人気だったことが分かりました。
次いで、飲み物・パン・おにぎり・弁当・プロテインバー・フルーツなどが選ばれましたが、中でもお菓子と飲み物の人気が際立つ結果となりました。
職場で気軽に楽しめる点や、リフレッシュにつながることが支持された理由として考えられます。
「TOUCH TO GO」では、お弁当や飲料などを購入できるオフィスコンビニをカンタンに導入できます。
お菓子以外のニーズにも対応できるオフィスコンビニを導入したい方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/
オフィスの置き菓子の種類
オフィスの置き菓子には、大きく分けて2つの種類があります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、自社の状況に合わせて最適な方法を選びましょう。
自社で購入して置いておく
自社でスーパーやコンビニエンスストア、ECサイトなどでお菓子を購入し、オフィスに設置する方法です。
メリットとしては、まず、自由度が高い点が挙げられます。お菓子の種類を自由に選べるため、社員の好みに合わせたり、予算に応じて調整することができます。
また、業者との契約が不要なので、導入が非常に簡単で、すぐに始められるのも大きなポイントです。
デメリットとしては、管理の手間がかかることです。在庫管理や補充、賞味期限のチェックなど、すべて自社で行う必要があります。
さらに、従業員の好みに偏りが出ると、売れ残りが多くなり無駄な費用が発生する可能性もあります。
また、人数が多い場合はお菓子の量も増えるため、購入担当者の負担が大きくなることも考慮しなければなりません。
置き菓子サービスを利用する
置き菓子サービスとは、専門の業者がオフィスにお菓子を定期的に配送・補充してくれるサービスです。
置き書サービスを利用する大きなメリットとしては、管理の手間が省ける点が挙げられます。
在庫管理や補充、賞味期限のチェックなどを業者に任せることで、担当者の負担が軽減されます。
また、業者によっては、健康志向のお菓子や地域限定のお菓子など、さまざまな種類のお菓子を楽しめるのも魅力です。
一方、デメリットとしては、費用が自社で購入するより高くなる傾向があることが挙げられます。
さらに、提供されるお菓子の種類や量が業者によって決められているため、自由に選べない可能性もあります。
業者によってはサービス提供エリアが限定されていることもあるので、事前に確認が必要です。
オフィスの置き菓子が福利厚生費になるもの
オフィスの置き菓子にかかる費用が福利厚生費として認められるかどうかは、税務上の取り扱いによって決まります。
会社が代金を負担した場合
会社が置き菓子の代金を負担した場合、どのような条件を満たせば福利厚生費として認められるのでしょうか。
従業員の誰もが食べられる場合
置き菓子が福利厚生費として認められるためには、従業員全員が利用できる状態であることが重要です。
特定の部署や役職の人だけが利用できる場合は、福利厚生費として認められません。
具体的には、以下のような条件を満たす必要があります。
- 従業員全員に利用機会が与えられていること
- 常識的な範囲の金額
- 現金支給ではないこと
これらの条件を満たしていれば、置き菓子にかかる費用は福利厚生費として計上でき、法人税の節税につながります。
取引先など外部向けに出す場合
置き菓子を従業員だけでなく、取引先や顧客など外部の人にも提供する場合は、接待交際費として扱われます。
接待交際費は、税法上の取り扱いが福利厚生費とは異なり、一定の金額までしか損金として認められません。
役員など一部の人しか食べられない場合
置き菓子が役員や特定の従業員しか利用できない場合は、福利厚生費として認められず、役員報酬または給与手当として扱われます。
役員報酬や給与手当は、所得税や住民税の課税対象となるため、注意が必要です。
オフィスの置き菓子が福利厚生費にならないもの
会社が代金を負担していない場合、つまり、従業員が自ら代金を支払って利用する置き菓子は、福利厚生費として認められません。
具体的には、オフィスグリコのように、設置や運用費用は無料ですが、お菓子の代金は従業員が各自で支払うようなケースが該当します。
この場合、会社は費用を負担していないため、税務上の取り扱いは発生しません。
オフィスにお菓子を置く前にチェックすべきポイント
オフィスに置き菓子を導入する前に、以下のポイントをチェックしておきましょう。
導入の条件
置き菓子を導入する目的や予算、運用方法を明確にしておくことが大切です。
従業員の満足度向上や福利厚生の一環として導入するのか、来客向けに用意するのかなど、目的によって選ぶサービスや運用方法が変わります。
また、毎月の予算を決め、自社に合った方法を選ぶことで無理なく継続しやすくなります。
なお、置き菓子サービスを利用する場合は、業者ごとに導入条件が決まっていることがあるため、事前の確認が必要です。
最低注文金額や契約期間など、自社に合うかチェックしておきましょう。
お菓子の内容
置くお菓子の種類も事前に検討しましょう。定番のスナック菓子やチョコレートだけでなく、健康志向のお菓子やアレルギー対応の商品を取り入れることで、より多くの従業員に喜ばれます。
従業員の好みやニーズをアンケートなどで確認し、適したラインナップを選ぶのもおすすめです。
対応している支払い方法
置き菓子を導入する際に、どのような支払い方法に対応しているかもチェックが必要です。
無料で提供する場合は会社負担となりますが、有料で運用する場合は、現金・キャッシュレス決済・電子マネーなど、従業員が利用しやすい支払い方法を選ぶとスムーズです。
特に、キャッシュレス決済に対応していると、お金の管理の手間が省けて便利です。
設置場所
オフィスのどこに置くかも重要なポイントです。従業員が気軽に立ち寄れる場所に設置することで、利用しやすくなります。
ただし、通路の邪魔にならないように配置したり、清潔に保てる場所を選ぶことも大切です。
スペースに余裕があれば、ちょっとした休憩スペースを作るのも良いでしょう。
オフィスの福利厚生として置き菓子を提供する場合の注意点
福利厚生として置き菓子を提供する際には、いくつかの注意点があります。
ここでは、オフィスの福利厚生として、き菓子を提供する場合の注意点を紹介します。
従業員のニーズを確認する
従業員がどのようなお菓子を求めているのか、アンケートなどを通じて定期的に確認しましょう。
ニーズに合わないお菓子ばかりを置いていても、利用されずに無駄になってしまう可能性があります。
そのため、まずは「福利厚生として置き菓子で良いのか?」や「どのようなジャンルのお菓子が良いのか?」を明確にしておくことが大切です。
セキュリティ面の対策をとる
置き菓子は誰でも自由に利用できるため、盗難やいたずらなどのリスクがあります。
防犯カメラを設置したり、従業員に注意喚起を行ったりするなど、セキュリティ面の対策を講じましょう。
また、定期的に従業員へ注意喚起を行い、置き菓子は皆で楽しむものであることを伝えることも大切です。
適切なマナーを守ることを意識させることで、無用なトラブルを防げます。
導入後もラインナップを工夫する
同じお菓子ばかりを置いていると、従業員が飽きる可能性があります。そのため、定期的に新しいお菓子を導入するなど、ラインナップを工夫しましょう。
季節限定のお菓子や、地域限定のお菓子などを取り入れるのもおすすめです。
また、従業員のフィードバックを取り入れることも検討してみましょう。
定期的にアンケートを実施し、どのようなお菓子や飲み物が好まれているのかを調べ、その結果に基づいてラインナップを調整することで、従業員のニーズに合った商品を提供できます。
導入後もラインナップを工夫することで、導入後も飽きずに楽しめるオフィス環境を維持でき、従業員満足度の向上にも繋がります。
従業員の健康を損なわないお菓子を揃える
スナック菓子やチョコレートなど、カロリーの高いお菓子ばかりを置いていると、従業員の健康を損なうかもしれません。
健康志向のお菓子や、野菜チップス、ナッツ類なども用意するなど、バランスの取れたラインナップを心がけましょう。
なお、お菓子以外の食べ物も福利厚生として提供するのであれば、「オフィスコンビニ」の導入がおすすめです。
オフィスコンビニとは、職場内に設置された小規模な無人販売システムのことで、社員が手軽に飲み物や軽食、お菓子などを購入できるサービスです。
通常、専用の棚や冷蔵庫に商品が陳列されており、現金やキャッシュレス決済で支払いができます。
代表的なサービスには、「オフィスグリコ」や「オフィスファミマ」などがあり、企業が導入することで、社員の利便性向上や業務効率の向上、リフレッシュ効果が期待できます。
以下の記事で、オフィスグリコの類似サービスを紹介しています。あわせてご覧ください。
関連記事>>オフィスグリコの類似サービス10選|福利厚生に最適な選び方も解説
まとめ
オフィスの置き菓子は、従業員の満足度向上やコミュニケーション活性化に貢献するだけでなく、条件を満たせば福利厚生費として計上できます。
導入を検討する際は、この記事で解説したポイントを踏まえ、自社に合った方法を選びましょう。
また、お菓子以外の食べ物も提供したい場合は、オフィスコンビニの導入も検討してみてください。
オフィスコンビニを導入することで、オフィス内で手軽に食べ物や飲み物を購入でき、外出の手間を省き、短時間で飲食を済ませられるという魅力があります。
以下の記事で、オフィスコンビニについて詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
「TOUCH TO GO」では、お弁当や飲料などを購入できるオフィスコンビニをカンタンに導入できます。
お菓子以外のニーズにも対応できるオフィスコンビニを導入したい方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/