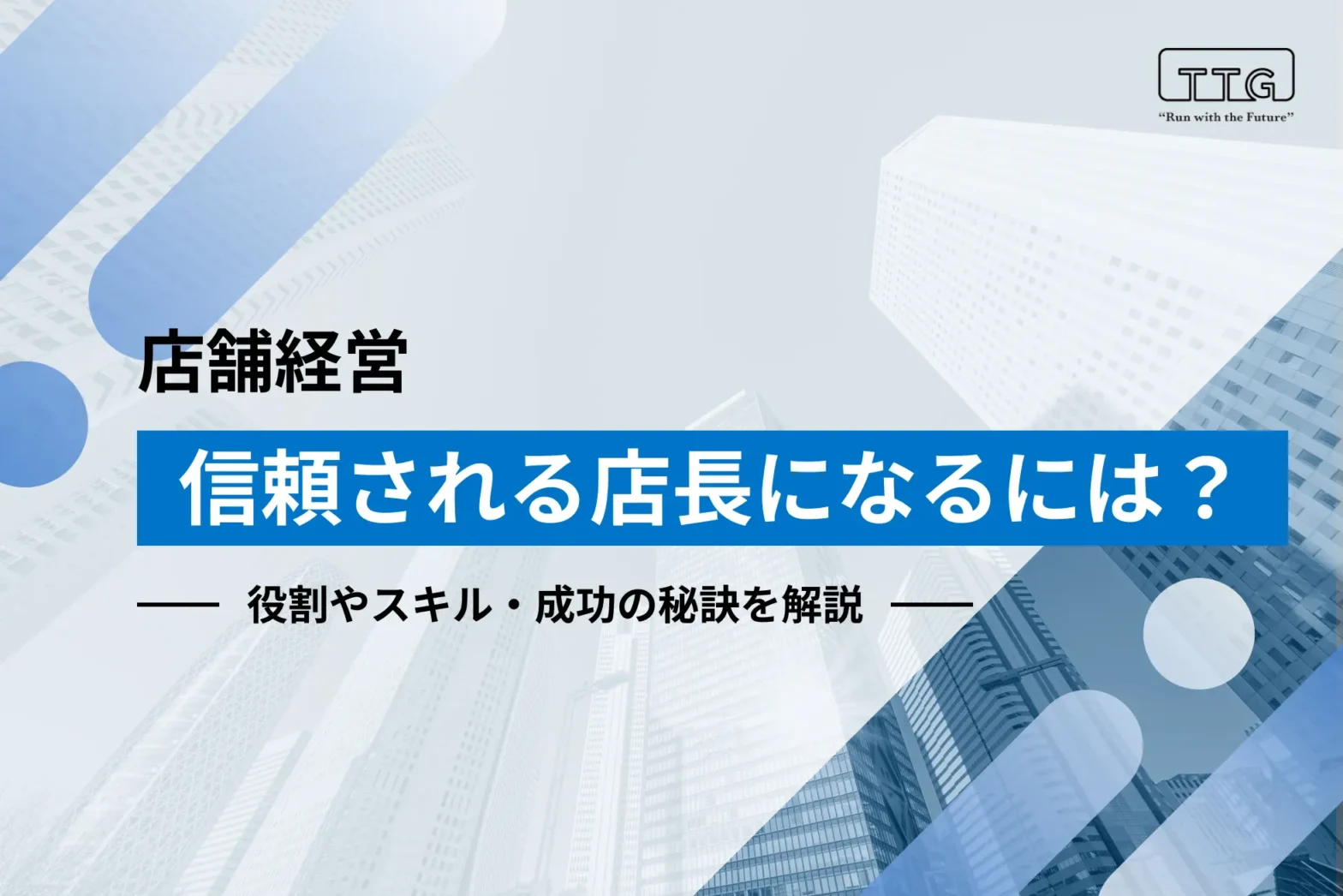Category
こんにちは。無人決済店舗システムを提供しているTOUCH TO GO 編集部です。
「人手不足なのに、企業はなぜ雇わないのか」そんな疑問を持っていませんか。
本記事では、採用コストや人材のミスマッチ、経営リスクの回避など、企業が採用をためらう理由を解説しています。
さらに、今後の人手不足に向けた対応策も紹介しています。現代の採用現場のリアルが分かるため、ぜひ最後までご覧ください。
監修者プロフィール

2019年に株式会社TOUCH TO GOを設立。無人決済店舗システムを提供し、次世代型小売の拡大に取り組んでいる。
目次
人手不足なのになぜ雇わないのか?理由を解説
人手不足にもかかわらず企業が採用を見送る理由はさまざまです。
主な3つの理由をそれぞれ解説します。
- 採用コストや教育負担の重さ
- ミスマッチによる適切な人材不足
- 経営リスク回避のための採用見送り
採用コストや教育負担の重さ
採用活動には多額のコストがかかります。
マイナビの調査によると、中途採用の平均コストは629.7万円、年間の採用人数は21.8人(2023年実績)と、過去最高の数字でした。
引用:株式会社マイナビ 中途採用状況調査2024年度版(2023年実績)
さらに、採用後の教育コストや研修費用も必要です。早期離職があれば採用コストが再度発生するため、企業にとって大きな負担となります。
特に中小企業では、限られた予算の中でこれらのコストを捻出するのが難しく、採用に踏み切れない要因となっています。
ミスマッチによる適切な人材不足
採用のミスマッチは人手不足の大きな原因の1つです。
企業が求める人材像と応募者のスキルや期待が合致しないと、入社後に「思っていたのと違う」と感じ、早期離職につながります。
ミスマッチが発生すると、社員は職務や職場の文化に不満を抱き、生産性が低下するため、チーム全体のパフォーマンスにも悪影響を及ぼします。
また、企業の評判にも悪影響を与え、さらなる採用難を招く悪循環に陥るのです。
適切な人材を確保するためには、企業の魅力を正確に伝え、具体的な業務内容や求められる役割を明確にすることが大切です。
経営リスク回避のための採用見送り
企業は経営リスクを回避するために採用を見送る場合があります。
人材を雇用すると固定費が増加し、業績が悪化した際の負担となるからです。
特に中小企業では景気変動に対する耐性が低く、人件費の増加が経営を圧迫するリスクがあります。
また、採用のミスマッチによる早期離職は、採用や教育コストの無駄遣いとなるだけでなく、企業のノウハウの蓄積を妨げ、長期的な競争力低下にもつながります。
さらに、離職率の高さは企業イメージを損ない、優秀な人材の確保をさらに困難にするのです。
これらのリスクを考慮し、企業は採用判断を慎重に行なっています。
関連記事>>飲食店が人手不足に陥る5つの原因|対策と新たな取り組みを紹介
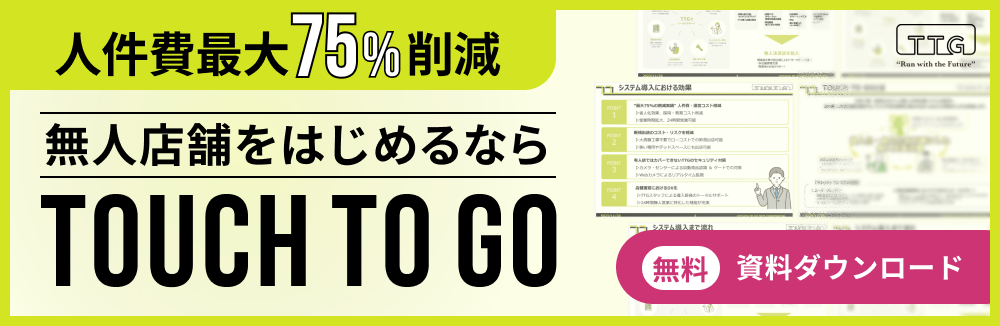
TOUCH TO GO の 無人決済店舗システムを導入すると、深刻な人手不足も解決できます。
人手不足に負けない運営を検討されている方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/
人手不足の職場で起きている問題
人手不足の職場では多くの問題が連鎖的に発生します。これらの問題は生産性の低下や不安定な品質を引き起こし、長期的には企業の競争力を損なう要因となるのです。
主な問題を3つ挙げていきます。
- 業務の属人化
- しわ寄せによる社員の疲弊とストレス
- 離職率の上昇と職場崩壊のリスク
業務の属人化
業務の属人化とは、特定の従業員のみが業務を把握している状態を指しています。
人手不足の環境では、1人の従業員が多くの業務を抱え込み、その詳しい手順やノウハウ、進捗状況などを他の従業員に共有する時間がなくなります。
属人化が進むと、担当者が休暇や病気で不在の際に業務が停滞し、サービスの品質が安定せず、業務改善も進みにくくなるのです。
その担当者が退職した際は、同じレベルで業務を継続するのが困難となり、組織全体の業務効率と品質が低下するリスクが高まります。
特に専門性の高い業務は知識の共有が難しく、属人化しやすい傾向があります。
しわ寄せによる社員の疲弊とストレス
人手不足の職場では、欠員分の業務が残された社員にしわ寄せされ、1人あたりの業務量が増加します。
属人化が進んだ環境では、特定の従業員に業務が集中し、過重な負担がかかります。
この状況が続くと、社員は慢性的な疲労やストレスを抱え、心身の健康を損なうリスクが高まるのです。
また、業務量の増加により残業や休日出勤が常態化し、ワークライフバランスが崩れると、さらなるストレスや不満が蓄積されます。
社員の疲弊は集中力や判断力の低下を招き、ミスの増加や業務品質の低下につながり、組織全体の生産性を低下させる要因となります。
離職率の上昇と職場崩壊のリスク
人手不足と業務の属人化、社員の疲弊が進むと、離職率が上昇するリスクが高まります。
離職率が高まれば、さらなる人手不足に陥り、残された社員の負担がさらに増加するという悪循環が生じるのです。
特に中核となる人材が離職すると、属人化した業務の引き継ぎが難しくなり、業務の停滞や品質の低下を招きます。
また、離職率の上昇は社内の雰囲気を悪化させ、内部対立やいじめなどの問題を引き起こすかもしれません。
このような状況が続くと、企業の信用失墜や顧客離れを招き、最終的には組織崩壊につながるリスクがあります。
そのため、人材の確保と定着のための環境整備や、業務の標準化による属人化の解消が重要な対策となります。
関連記事>>人手不足はなぜ起こる?原因と企業に与える影響・対策も紹介
人手不足でも企業が選り好みを続ける理由
人手不足が深刻化する中でも、多くの企業が採用において選り好みを続けていると言われています。以下の理由について、それぞれ解説します。
- 優秀な人材への過度な期待
- 日本企業特有の採用文化と現実
優秀な人材への過度な期待
企業は人手不足の中でも「優秀な人材」を常に求め続けています。
これは単に選り好みをしているのではなく、企業の競争力を維持するためです。
優秀な人材を獲得するには高い待遇が必要ですが、人件費を上げる原因にもなるため、企業は人材の確保と競争力維持の間で苦戦しているのです。
また、企業は表向きには人手不足を訴えながらも採用基準を高く設定して、優秀な人材だけを厳選して採用する戦略を取っています。
これにより、短期的には人手不足が解消されなくても、長期的に企業の価値を守ろうとしているのです。
しかし、この過度な期待が求職者とのミスマッチを生み、結果的に人手不足の解消を遅らせる一因となっています。
日本企業特有の採用文化と現実
日本企業の採用文化には特有の傾向があります。
従来の日本では「1つの会社に長く勤めてキャリアアップを目指す」という価値観が主流でした。
しかし現在は「キャリアアップのために積極的に転職し、自分の希望を最優先する」という価値観に変化しています。
この価値観の変化により、どの企業でも人材の定着率が低下しており、企業はより慎重に採用を行うようになっています。
また、日本企業は「上から目線」で採用活動を行っているという批判もあり、これがZ世代の就活生との間に溝を生んでいるのです。
現実には、企業が求める人材像と求職者のニーズとの間にミスマッチが生じており、これが「人手不足なのに選り好み」という状況を作り出しています。
企業の人手不足を解消するためには、採用基準の見直しだけでなく、働きやすい環境づくりや適切な報酬体系の整備など、総合的な取り組みが必要です。
関連記事>>人手不足が顕著な業界(業種)ランキングTOP10|原因も解説
これからの人手不足問題に向き合う方法
人手不足の問題は今後さらに深刻化すると予測されています。
この課題に対応するためには、単に人員を増やすだけでなく、多角的なアプローチが必要です。以下の方法をそれぞれ解説します。
- 属人化の解消と業務効率化の推進
- 外部リソースや柔軟な採用戦略
- 働き方改革と社員定着率向上への取り組み
属人化の解消と業務効率化の推進
属人化を解消するには、ワークフローの可視化が重要です。
業務プロセスを明確にしてマニュアルを作成することで、誰でも同じ品質で業務を遂行できる環境を整えます。
また、ノウハウの可視化と蓄積も不可欠です。
データベースやクラウド上に知識を蓄積すれば、社員間の情報共有を促進できます。
ITツールの導入も効果的で、業務の自動化や情報共有、進捗の可視化などにより、属人化の原因となる要因を解消できます。
さらに、継続的な評価や改善を行うと、標準化された業務をさらに効率化できるため、人手不足の影響を最小限に抑えられるのです。
外部リソースや柔軟な採用戦略
人手不足に対応するためには、外部リソースの活用や柔軟な採用戦略の導入が効果的です。
外部リソースの活用例としては、特定の業務をアウトソーシングしたり、繁忙期のみ派遣社員を活用したりする方法があります。
これにより、適正な量の業務を社員へ割り当てられるため、過重労働を防止できます。
採用戦略においては、ダイバーシティの採用が有効です。
年齢や性別、国籍などにとらわれず多様な人材にアプローチすると、人材確保の可能性が高まります。
また、ダイレクトリクルーティングやリファラル採用など、コストを抑えつつ効果的な採用手法も検討するとよいでしょう。
特に中小企業では自社の魅力を効果的に発信し、求職者に直接アプローチする戦略が重要です。
働き方改革と社員定着率向上への取り組み
働き方改革は人手不足解消の重要な鍵となります。
フレックスタイム制やリモートワークの導入、業務プロセスのデジタル化など、従業員が最大限の能力を発揮できる環境整備を進めることが重要です。
また、副業や兼業の解禁も検討すべきで、これにより社員の収入アップや多様なキャリア形成を支援できます。
社員の定着率を向上させるためには、労働条件の改善や福利厚生の充実が不可欠です。
特に若手の求職者は働きやすい環境やワークライフバランスを重視する傾向があるため、これらに配慮した制度設計が求められます。
さらに、地域限定社員制度の導入など、転勤に伴う離職を防ぐ工夫も効果的です。社員のエンゲージメント向上や適切な評価制度の構築も、長期的な定着率向上につながるでしょう。
関連記事>>人手不足の対策7つ|人材採用のポイントや長期的な視点についても解説
まとめ
人手不足が叫ばれる中、企業はなぜ雇わないのか。その背景には採用コストや人材のミスマッチ、経営リスクの回避など、複雑な事情があります。
本記事ではその実態を詳しく解説し、今後の人手不足対策に向けた具体策も紹介しました。企業も個人もこの現実を正しく理解し、未来への一歩を踏み出すために、今こそ行動が求められているのです。
TOUCH TO GO の 無人決済店舗システムを導入すると、深刻な人手不足も解決できます。
人手不足に負けない運営を検討されている方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/