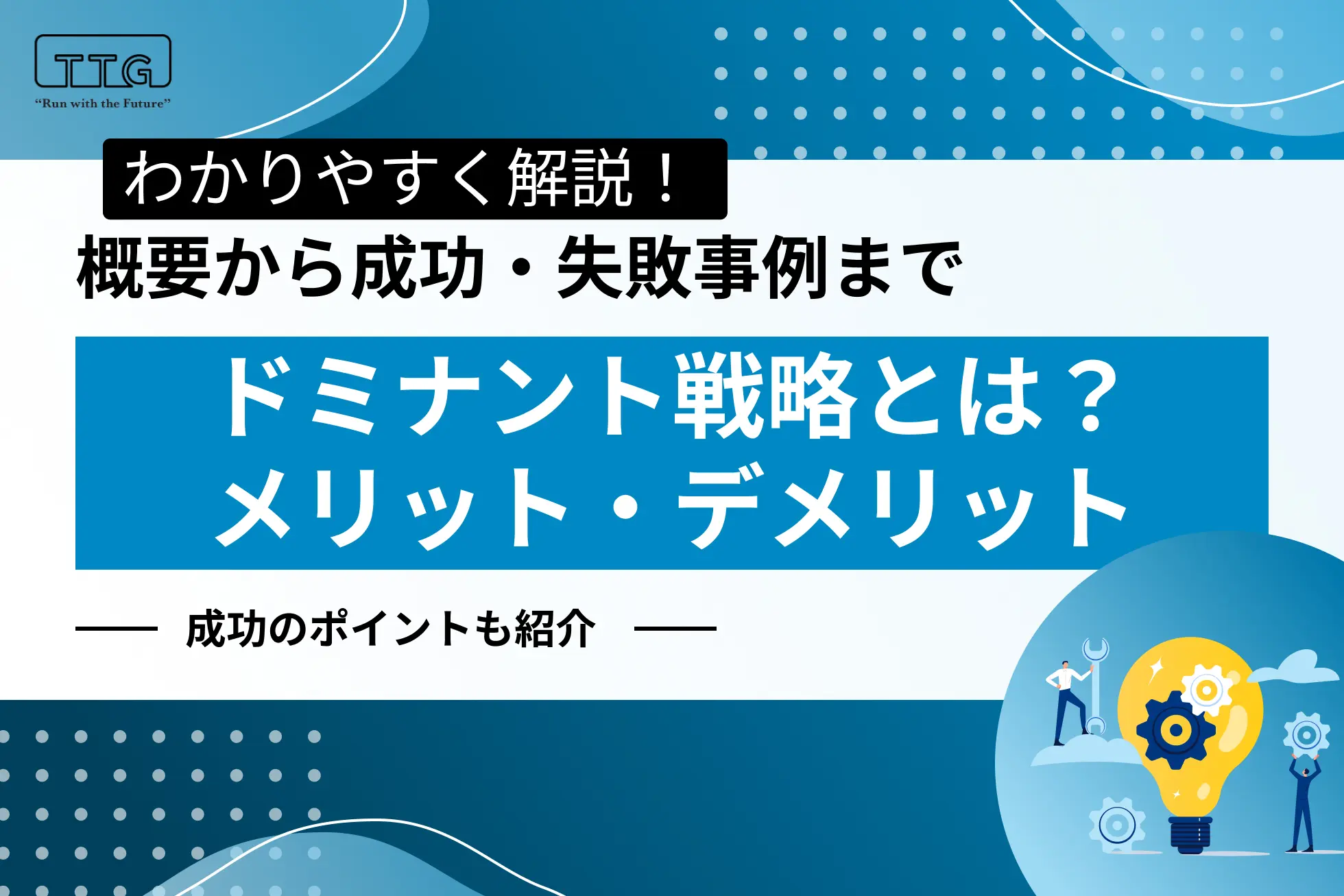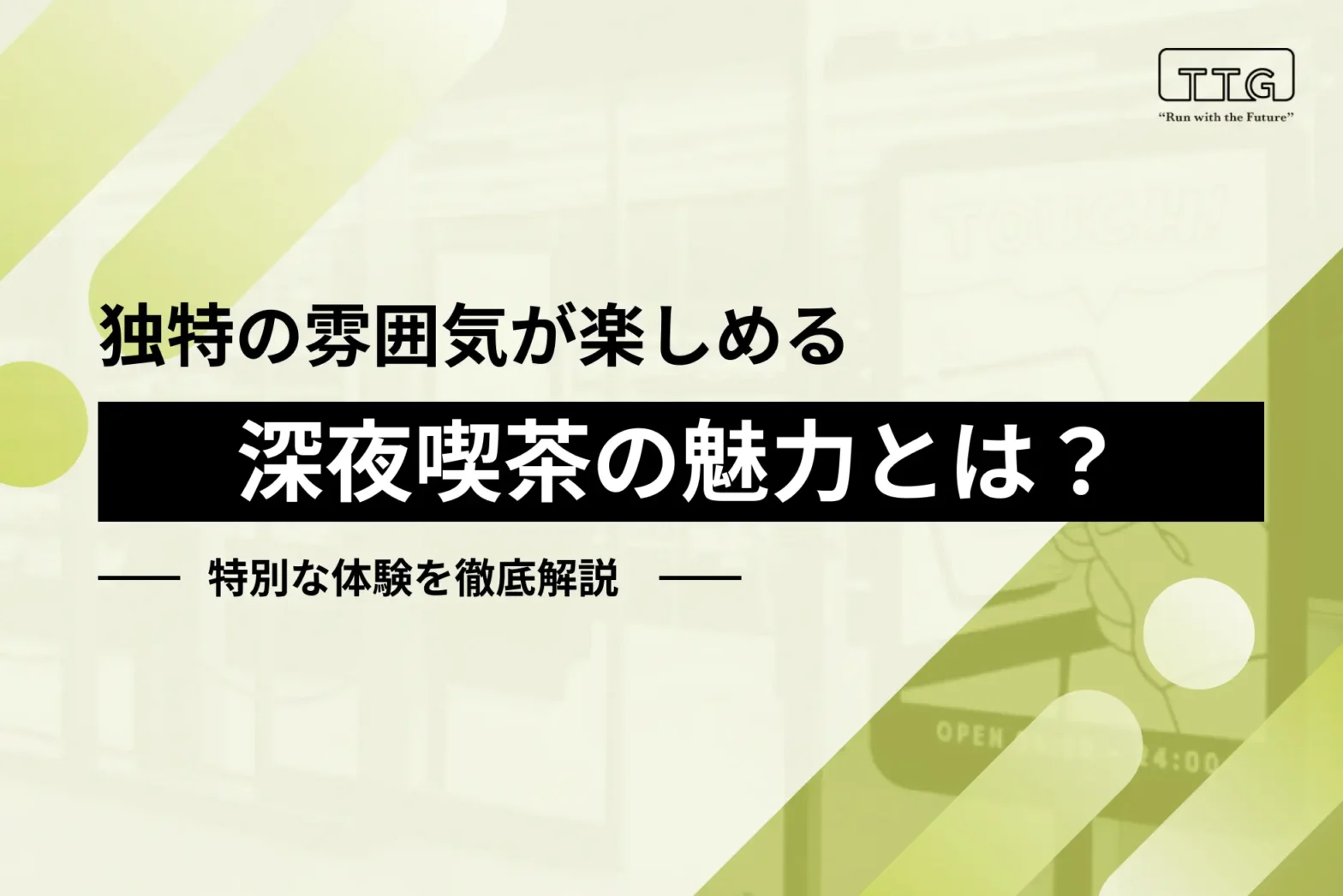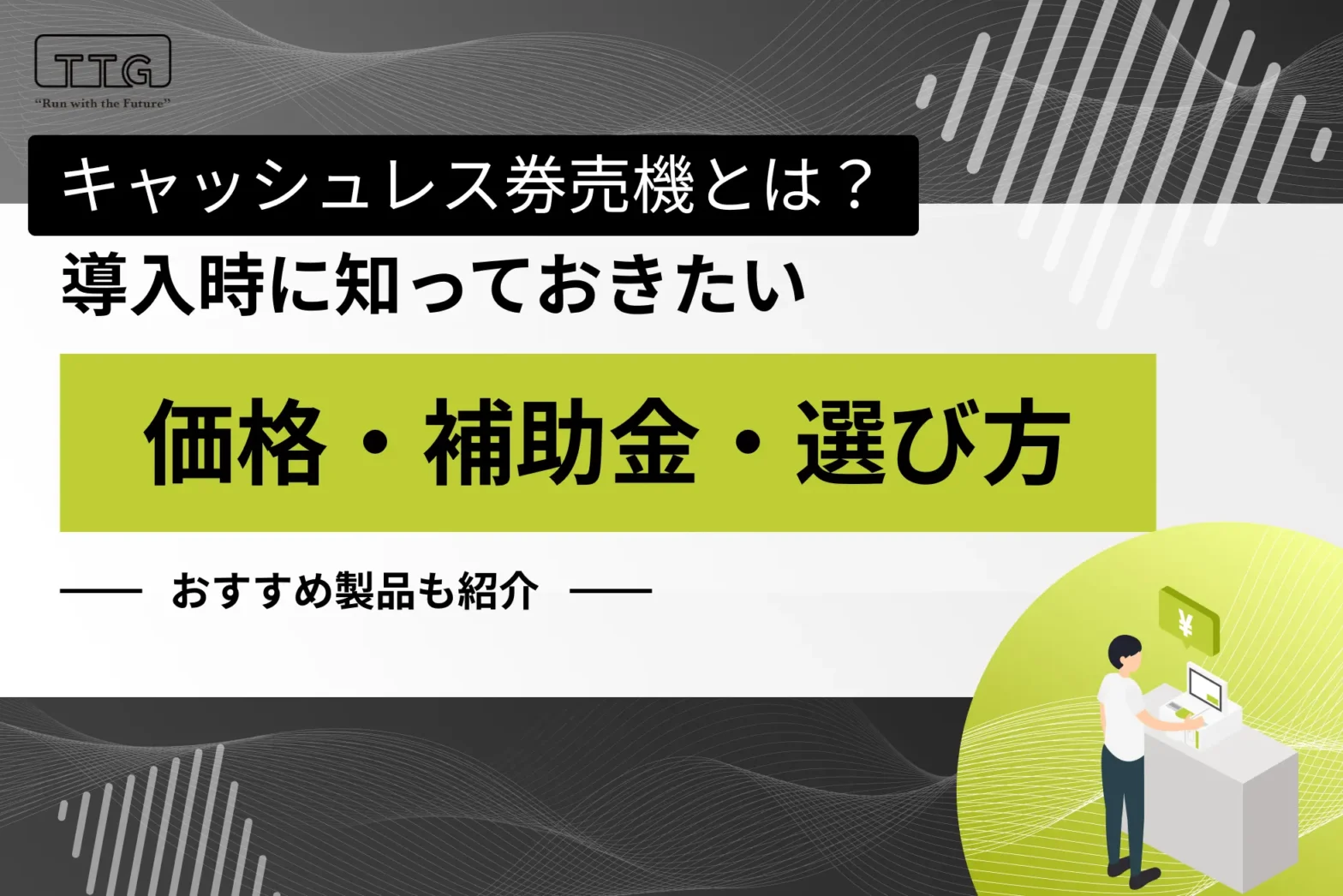Category
こんにちは。無人決済店舗システムを提供しているTOUCH TO GO 編集部です。
特定の地域に、同じコンビニや飲食店などのチェーン店が展開されているのをみたことがある方も多いのではないでしょうか。
これは、あえて同じエリアに店舗を出店する「ドミナント戦略」と呼ばれる競争戦略です。
しかし、「なぜ同じお店を出すのだろう?」「どのような意味があるの?」と疑問を感じる方もいると思います。
そこで今回の記事では、ドミナント戦略の概要からメリット・デメリット、成功事例を紹介します。
失敗事例と成功のポイントも解説しているので、ぜひ参考にしてください。
関連記事▼
監修者プロフィール

2019年に株式会社TOUCH TO GOを設立。無人決済店舗システムを提供し、次世代型小売の拡大に取り組んでいる。
目次
ドミナント戦略とは?
ドミナント戦略とは、コンビニや飲食店、ドラッグストアなどの多店舗展開している企業が取り入れている競争戦略です。
そもそも「ドミナント(dominant)」は英語で「支配的な」「優勢な」という意味があります。
ビジネスにおいては、特定エリアに集中して自社店舗を展開することで、競合の参入余地をなくし、より有利な立場を築く手法として活用されています。
たとえば、あるコンビニチェーンが都内の一部の区に10店舗出したとします。
すると、その区内では「この区にはこのコンビニがある」と認知度が高まり、利用頻度の向上につながります。
このように、あえて店舗を近距離で展開することで、特定エリアの顧客を囲い込みやすくなり、他社が入り込む余地を小さくできるのがドミナント戦略の特徴です。
また、ドミナント戦略はフランチャイズでも活用されており、店舗数を増やしながら地域密着型のビジネスを実現したい企業にとって有効な出店手法の一つです。
ドミナント戦略とランチェスター戦略の違い
| 項目 | ドミナント戦略 | ランチェスター戦略 |
| 特徴 | 特定地域に複数店舗を展開し、そのエリアのシェアの獲得を目指す | 特定の市場に特化することで、その市場のシェアの獲得を目指す |
| 取り入れている企業 |
|
|
| 業種例 |
など |
など |
ランチェスター戦略は、競合と異なる市場に特化することで、その市場のシェアを獲得する戦略手法です。
特定地域に集中して出店するドミナント戦略とは根本的な考え方が異なり、リソースを一点に集中させ、競合の少ない領域で優位性を獲得することを目的としています。
ランチェスター戦略はおもに中小企業や新規参入企業など、リソースが限定される企業が活用する手法で、比較的小さな市場を狙うことで競争を回避します。
大手企業と戦う場所を変えることで、ニッチな市場で独自のポジションを確立し、市場の主導権を握れる状態を築くのが大きな特徴です。
このように、ランチェスター戦略は市場の特定分野でのシェアの獲得、ドミナント戦略は特定地域でのシェア獲得を目指す手法という違いがあります。
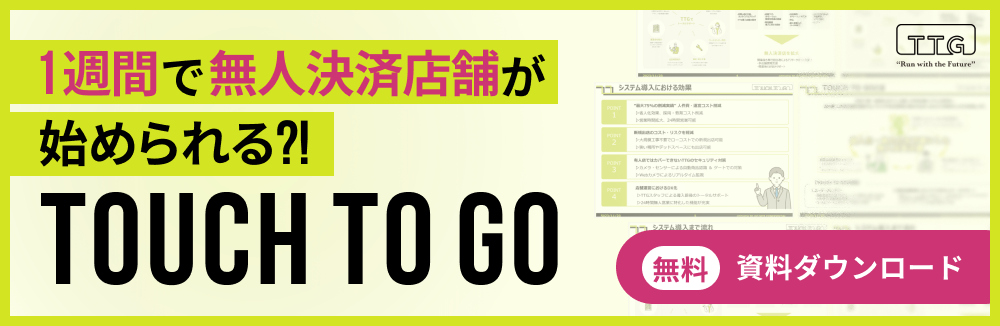
TOUCH TO GOの無人決済システムは、カメラとセンサーの高度な商品認識技術を活用し、省人化を実現。狭小スペースにも対応した柔軟な設計で、ドミナント戦略による出店にも最適です。
人手不足や運営コストの課題を抱える店舗運営者の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/
ドミナント戦略のメリット
では、ドミナント戦略にはどのようなメリットがあるのでしょうか。
ここでは、ドミナント戦略の代表的なメリットを5つ紹介します。
特定地域での認知度が高まりやすい
ドミナント戦略では特定の地域に複数店舗を出店するため、認知度が高まりやすいというメリットがあります。
その地域に住む人や通勤・通学で日常的に通行する人にとって「身近な店」として認知されやすくなり、自然と記憶に残りやすくなります。
また、特定の地域での認知度や知名度を高めたあと、地域を拡大するケースもあります。
すでに一定の認知度・知名度を獲得していることから信頼を得やすく、新しく出店するエリアでも顧客を確保しやすい傾向があります。
エリアマーケティングを最適化できる
エリアマーケティングとは、地域ごとの特性にあわせたマーケティングのことです。
そもそも、出店エリアは広いほど顧客の年齢層やライフスタイルが多様化し、マーケティングを最適化するのは困難になります。
しかし、ドミナント戦略では特定エリアに限定することでターゲット層を絞りやすく、ニーズを正確に捉えやすくなります。
店舗を出店する前に分析することで、販売する商品やサービスの内容、価格、販促手法などを最適な形に設定しやすくなるのです。
なお、調査すべき地域特性としては、以下のような項目が挙げられます。
- 地理的な条件
- 人口規模・世帯数・人口密度
- 交通網の発達状況
- 歴史・文化・伝統
- 教育機関・医療機関・公共施設
このような地域特性を事前に調査・把握することで、より的確な店舗戦略を立てることができ、結果として集客力や売上の向上にもつながります。
競合他社の参入を抑制できる
競合他社の参入を抑制できる点も、ドミナント戦略の大きなメリットです。
特定地域に同じ企業の店舗が複数展開している場合、多くの顧客は既存の店舗に信頼感や安心感を抱いており、競合他社が新たに出店しても集客が難しい状況に陥りやすくなります。
このような状況は競合他社にとって「リスクの高い地域」と認識されやすく、参入を見送る判断につながりやすくなります。
他の企業よりも先に特定地域に店舗を集中的に出店することで、地域内でのブランドの存在感が高まり、結果的にそのエリアでの顧客を囲い込みやすくなります。
物流を効率化しやすい
店舗同士が近いことにより、物流の効率化も可能になります。
店舗同士が離れていれば、各店舗への配送用のトラックをそれぞれ用意する必要があり、時間もコストも大きくなります。
しかし、店舗同士が近くにあれば一つのトラックでまとめて配送できるため、コスト削減につながります。
飲食店であれば、食材を鮮度の高い状態で複数店舗に配送できるというメリットもあります。
経営リソースを無駄なく有効活用できる
物流面の効率化に加えて、ドミナント戦略は人材や在庫、販促などの経営資源をより効果的に使いやすくなります。
具体的には、以下のような活用方法が挙げられます。
- スタッフ不足時に他の店舗に応援を依頼
- 余剰在庫を近くの店舗へ移動させてロス削減
- キャンペーンの同時開催で宣伝コスト削減
- まとまった仕入れでコスト削減
さらに、特定のエリアに店舗を集中させることで、地域の顧客ニーズをより深く理解できるようになります。
その結果、無駄な投資を抑えながら、顧客ニーズにあわせた商品やサービスの開発にもつなげやすくなります。
ドミナント戦略のデメリット
次に、ドミナント戦略のデメリットといえる部分を4つ紹介します。
自店舗間で顧客の奪い合いが起きる可能性がある
ドミナント戦略では、「カニバリゼーション=自店舗間での顧客の奪い合い」が生じる可能性があります。
というのも、特定の地域にいる顧客数はある程度限られているため、同じ企業やチェーン店内で集客の競争が起きてしまうのです。
とくに売上にノルマがある場合、各店舗では数字を伸ばそうと競い合うことになります。
本来はエリア全体での売上を最大化することが目的であるにもかかわらず、自店舗間で顧客の取り合いが激しくなると、全体の売上が伸びづらくなるケースもあります。
地域ニーズの変化による影響が強い
特定の地域に最適なマーケティングができるメリットの一方で、出店地域のニーズが変化したときの影響が強いというデメリットもあります。
たとえば、以下のような例が挙げられます。
- 人口の減少
- 高齢化の進行
- 住民のライフスタイルの変化
- 近隣への大型商業施設の出店
- 競合店の出店
- 地域産業の弱体化
他の地域への分散が少ないドミナント戦略では、特定地域への依存度が高くなりがちです。
場合によっては、経営戦略の根本的な見直しや大掛かりな変更、コストの投入が必要になるかもしれません。
複数店舗が同時に影響を受けると、売上の低下による撤退などのリスクも高まります。
地域のニーズの変化をいち早く察知し、対策を検討してリスクを回避することが重要なポイントとなります。
災害における売上減少リスクが高い
地震や台風などの自然災害が起こったとき、その地域全体の売上が減少するリスクもあります。
たとえば、停電したり物流が滞ったりすると通常営業が難しく、複数店舗で一斉に売上がゼロになるケースも考えられます。
被災地域の復旧が長引くほど営業再開の見通しを立てづらく、売上に与えるダメージも大きくなるでしょう。
さらに、建物や設備が被害を受けている場合、売上の見込みがない状態で修繕しなければならず、経営に深刻な影響を及ぼす可能性もあります。
他地域にノウハウを活かせない可能性がある
一つの地域でのドミナント戦略に成功したあと、新しいエリアへの展開を検討するケースも少なくありません。
しかし、ドミナント戦略は地域ごとの特性にあわせてデータやノウハウを蓄積していく手法のため、他の地域ではそのノウハウが通用しない可能性があります。
この場合、新しいエリアの特性にあわせたマーケティング戦略を検討したり、ドミナント戦略からランチェスター戦略に切り替えたりと、柔軟性が必要になります。
ドミナント戦略を採用する企業の成功例
ここからは、ドミナント戦略を採用している企業の成功例を紹介します。
コンビニ|セブン-イレブン
ドミナント戦略の代表的な成功事例として挙げられるのが、セブン-イレブンです。
セブン-イレブンは、1974年5月に第1号店を東京都江東区に出店。「江東区から出るな」という新規店舗開発の方針をもとに、一定の地域内のみで顧客の目に触れる機会を増やしました。
ドミナント戦略を採用し店舗同士を近い場所に展開するとともに、「独自の専用工場の設置」「販売時間帯にあわせた配送」を実施することで、品質の良いサービスの提供が可能になりました。
さらに、出店エリアを絞ることで、販売促進に必要な広告や、店舗経営を支援する相談員のサポート活動などの効率化にも成功しています。
2025年6月時点の総店舗数は21,756店で、国内のコンビニ業界におけるシェアNo.1となるまでに成長しています。
(出典)
コンビニ|ファミリーマート
ファミリーマートは、am/pmやサークルK、サンクスなどの他ブランドを統合し、一気に店舗網を拡充しました。
この買収・統合により、短期間でドミナントエリアの構築に成功。2025年5月時点での国内店舗数は16,306店と、業界第2位の規模を誇るコンビニチェーンとなっています。
中期経営計画でも「強いドミナントを確立できたことは、今後のコンビニ事業の成長にとって大きな優位性となる」と位置付けられており、企業戦略の柱のひとつとなっています。
(出典)
ドラッグストア|ツルハグループ
ツルハグループは、創業地の北海道をはじめとした特定エリアに複数店舗を構えるドラッグストアです。
「ツルハドラッグ」のほか、「くすりの福太郎」など複数のブランドを展開することで、地域の特性や顧客層にあわせた店舗を展開。
ブランドを分けることで同一エリア内でのカニバリゼーションを抑えながら、地域のニーズに応えることに成功しています。
また、地域に根付いたドラッグストア運営会社を買収することで、スピーディかつ低コストでエリアを拡大してきた点も、ツルハグループの戦略的な強みとなっています。
スーパー|ヤオコー
埼玉県発祥のスーパーマーケット ヤオコーは、都心から20〜40kmのドーナッツ状にドミナントを形成し、出店する戦略を採用しています。
埼玉県のほかに東京都・千葉県・神奈川県を最重要エリアと位置付け、店舗を中心とした半径1〜3kmを商圏と設定しています。
各エリアでは、地域特性にあわせた店舗フォーマットやレイアウト・内装を設計し、買い物客の固定化と顧客満足度の向上を図っています。
飲食店|スターバックスコーヒー
アメリカ・シアトルで誕生したスターバックスコーヒーも、複数店舗を密集させるドミナント戦略で成功している企業例です。
東京都では、千代田区に48店舗、港区港区に44店舗、渋谷区に42店舗、大阪府でも大阪市北区に32店舗、中央区25店舗と、狭い範囲内に多数の店舗を展開していることがわかります。(2025年7月時点)
スターバックスはテレビコマーシャルなどを大々的におこなっていませんが、街のあちこちで見かける店舗やテイクアウト用のカップのデザインなどが広告として機能しており、自然と認知度を高めています。
さらに、SNSの活用や顧客の口コミによる拡散なども、集客力向上やブランド認知度向上に大きくつながっています。
飲食店|炭焼きレストランさわやか
静岡県内に34店舗を展開するハンバーグレストラン 炭火焼きレストランさわやか。浜松市だけで12店舗を出店しており、地域に根ざした店舗網を構築しています。(2025年7月時点)
ローカルチェーン店ながら県外からの人気も高く、連休や休日には数時間の待ち時間が発生することも。
炭焼きレストランさわやかが静岡県にこだわる理由は、品質へのこだわりによるものです。
各店舗には、当日中に消費する分だけの肉を直送しており、この鮮度重視のサプライチェーンが最大の強みです。
この「静岡でしか味わえない」という限定性によって、ブランドの特別感と高い付加価値を実現しています。
出典:炭焼きレストランさわやか
ホテル|アパホテル
アパホテルは、日本のほぼ全都道府県に進出し、ホテル数は2025年7月時点で981棟、総客室数138,054室と国内最大規模のホテルチェーンです。
なかでも、主要駅には駅の出口ごとに複数棟を出店するなど、エリア内での店舗密度を高め、「このエリアに泊まるならAPAホテル」というイメージを根付かせています。
さらに、ホテル同士が近いことでオーバーブッキングにも対応でき、「一つのホテルが満室でも、近くのホテルで予約が取れる」という状況を作り出しています。
出典:APA GROUP
ドミナント戦略に失敗した企業
ドミナント戦略には多くのメリットがある一方で、進め方を間違えると大きなリスクを負うことになります。
実際に、ドミナント戦略で店舗を展開したものの、思うような結果が得られず撤退した企業も存在します。
ここでは、ドミナント戦略に失敗した企業の一例を紹介します。
飲食店|いきなり!ステーキ
2013年東京に1号店を開店した「いきなり!ステーキ」は、ドミナント戦略を採用し、わずか3年で店舗数を5倍に拡大。
「フランチャイズチェーン史上最速」と言われるほどの急成長を遂げた飲食店チェーンです。
しかし、店舗数が増えるごとに利益がマイナスになる店舗が増え、さらに店舗間で顧客を奪い合うカニバリゼーションが深刻化。
また、アメリカ・ニューヨークでの出店でも、短期間に11店舗を構えたものの、立ち食いスタイルが現地に受け入れられず9店舗を閉鎖する結果となりました。
日本国内における地域需要に対する供給過多だけでなく、現地ニーズへの理解不足も影響したものと考えられます。
いきなり!ステーキの事例から、ただ出店数を増やすだけでは地域密着型の運営は成立しないことが伺い知れます。
(出典)
元トップが語る「ドミナント」の失敗
The Aftermath of Failed Ikinari Steak Expansion In New York City
ドミナント戦略の成功のポイント
ここからは、ドミナント戦略の成功のポイントを紹介します。
商圏調査を徹底する
ドミナント戦略でもっとも重要といえるのが「どのエリアに出店するか」という点です。
集客や商売の対象となる地理的な範囲を「商圏」と呼びますが、その広さは業種や立地などによって異なり、出店前の調査が不可欠となります。
エリアの人口や世帯数、交通量、周辺施設、地域特性などを細かく調査・分析することで、出店予定の店舗がどのくらい集客できそうかを把握できるようになります。
なお、商圏調査や店舗開発の精度を高めるために、GIS(地理情報システム)などのツールを活用した「商圏分析」の実施が効果的です。
商圏分析の方法やツールについて、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
関連記事>>商圏分析とは?新規店舗出店時に知っておくべき活用例や進め方を解説!
競合の調査・分析と差別化を徹底する
新規店舗を出店するにあたり、競合店の調査・分析は欠かせません。
競合調査によって、強みや弱みを把握し、自社ならどのように打ち出すかを考えましょう。
価格帯やメニュー構成、取扱商品、サービス内容など、店舗を構成するどの部分で差別化を図るかが、重要なポイントとなります。
なお、競合店がない場合は「その地域に需要がない」とも考えられるため、一概に競合がいない=シェアを独占できるわけではない点に注意が必要です。
リスク管理体制を整えておく
特定エリアに経営資源を集中するドミナント戦略では、リスクへの管理体制を整えておくことも大切です。
自然災害はもちろん、地域需要の変化や人口減少にともなう経済の悪化など、自社ではコントロールできない要因によって売上が落ち込む可能性も想定しておく必要があります。
なかでも、「早めに地域情報をキャッチできる体制づくり」や、「非常時に対応できる資源の確保」は必須といえます。
店舗を利用する顧客の声にもしっかりと耳を傾け、リスクに備えながら地域に根付く店舗づくりを目指しましょう。
TOUCH TO GOの無人決済システムなら多店舗展開がスムーズに
特定エリアにスピード感をもって多店舗展開を進めたい方には、TOUCH TO GOの無人決済システム「TTG-SENSE」の導入がおすすめです。
一般的な店舗出店では、商業ビル内の空きテナントを探したり、空き地の用途や規制を調べたりと、準備に多くの時間とコストがかかります。
しかし、狭小スペースにも店舗を出店できるTTG-SENSEなら、準備の手間を最小限に抑えられます。
TTG-SENSEは、商品棚と決済エリアだけで構成されたシンプルな設計のため、設置場所の自由度が高くスピーディーな展開が可能です。
さらに、スタッフ不在で店舗を運営できることから、スタッフの育成にかかる手間やコストの削減にもつながります。
コストを抑えながら、効率よくスムーズな多店舗展開を目指したい方は、ぜひTOUCH TO GOのTTG-SENSEの導入を検討してみてください。
プロダクトの詳細はこちらから>>TOUCH TO GO
まとめ
ドミナント戦略は、特定の地域に店舗を出店する競争戦略です。
店舗同士を近づけることで経営資源を集中させ、効率的な運営やブランドの認知度を高める効果に期待できます。
ただ、同じ地域にたくさん店舗を出店すればよいわけではなく、事前にエリアや競合の調査・分析は必須となります。
さらに、万が一に備えたリスク管理体制の整備も欠かせません。
地域に根ざした店舗網を構築するためにも、自社にあった戦略と手法を見極め、選択していきましょう。
関連記事▼
TOUCH TO GOの無人決済システムは、カメラとセンサーの高度な商品認識技術を活用し、省人化を実現。狭小スペースにも対応した柔軟な設計で、ドミナント戦略による出店にも最適です。
人手不足や運営コストの課題を抱える店舗運営者の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/