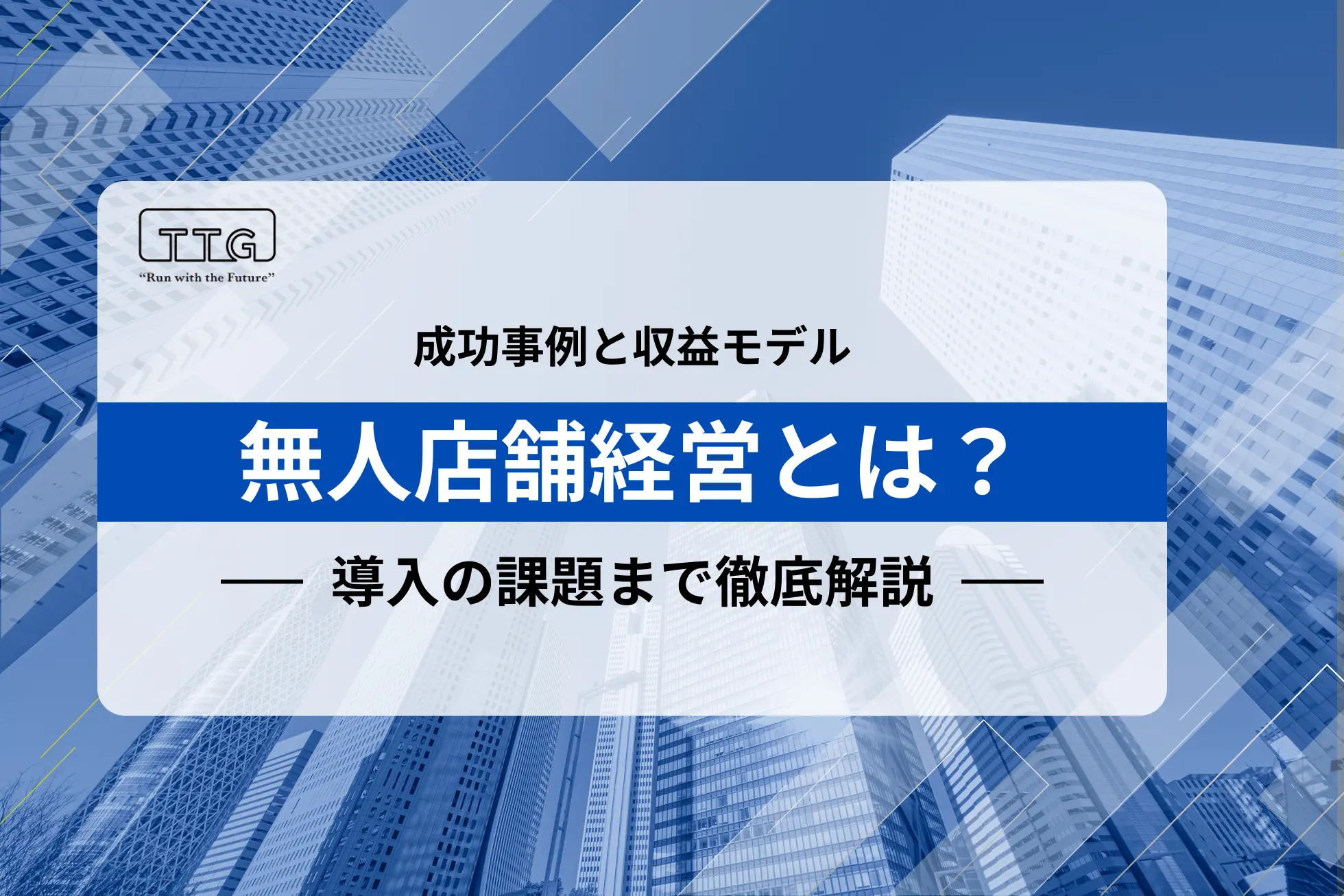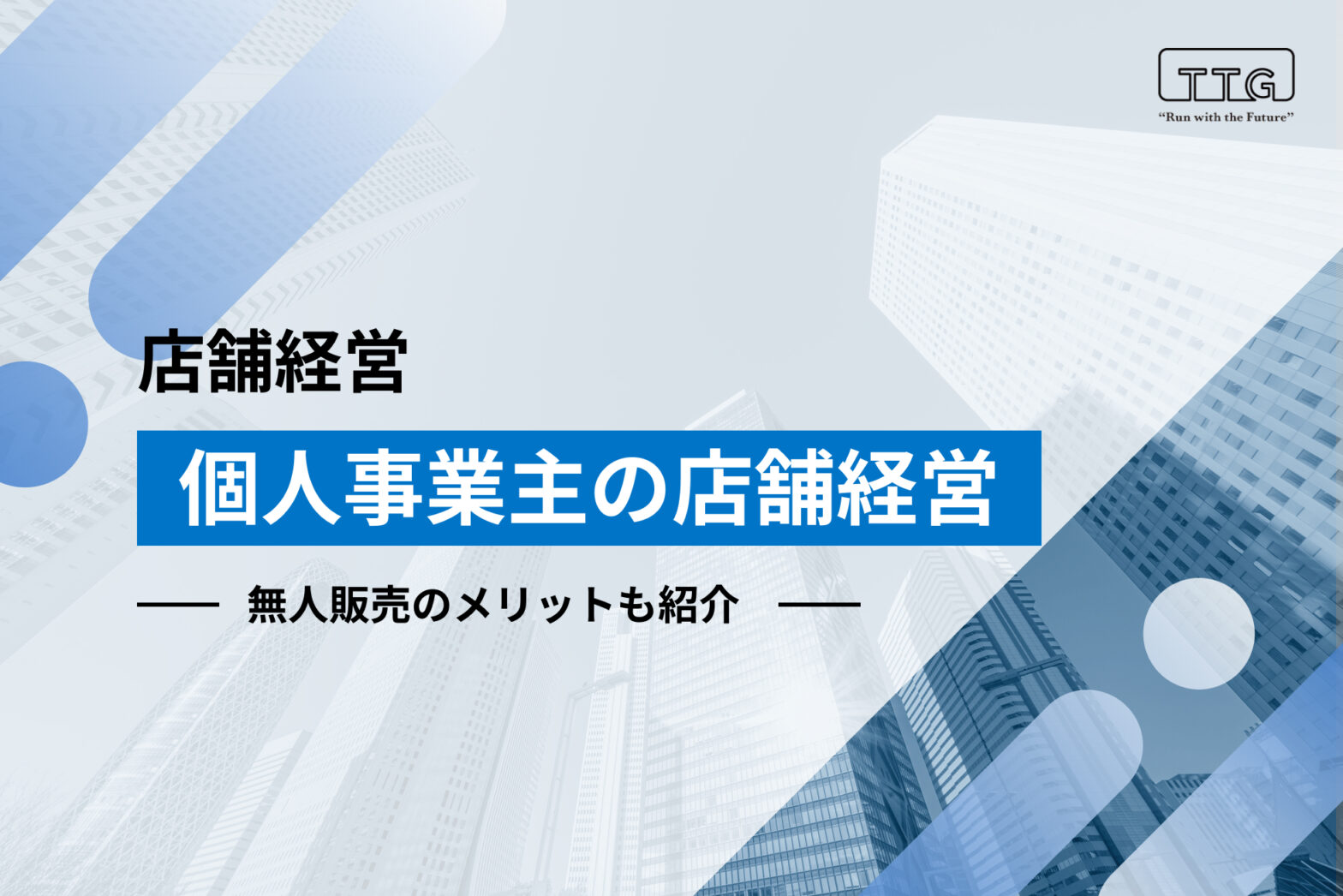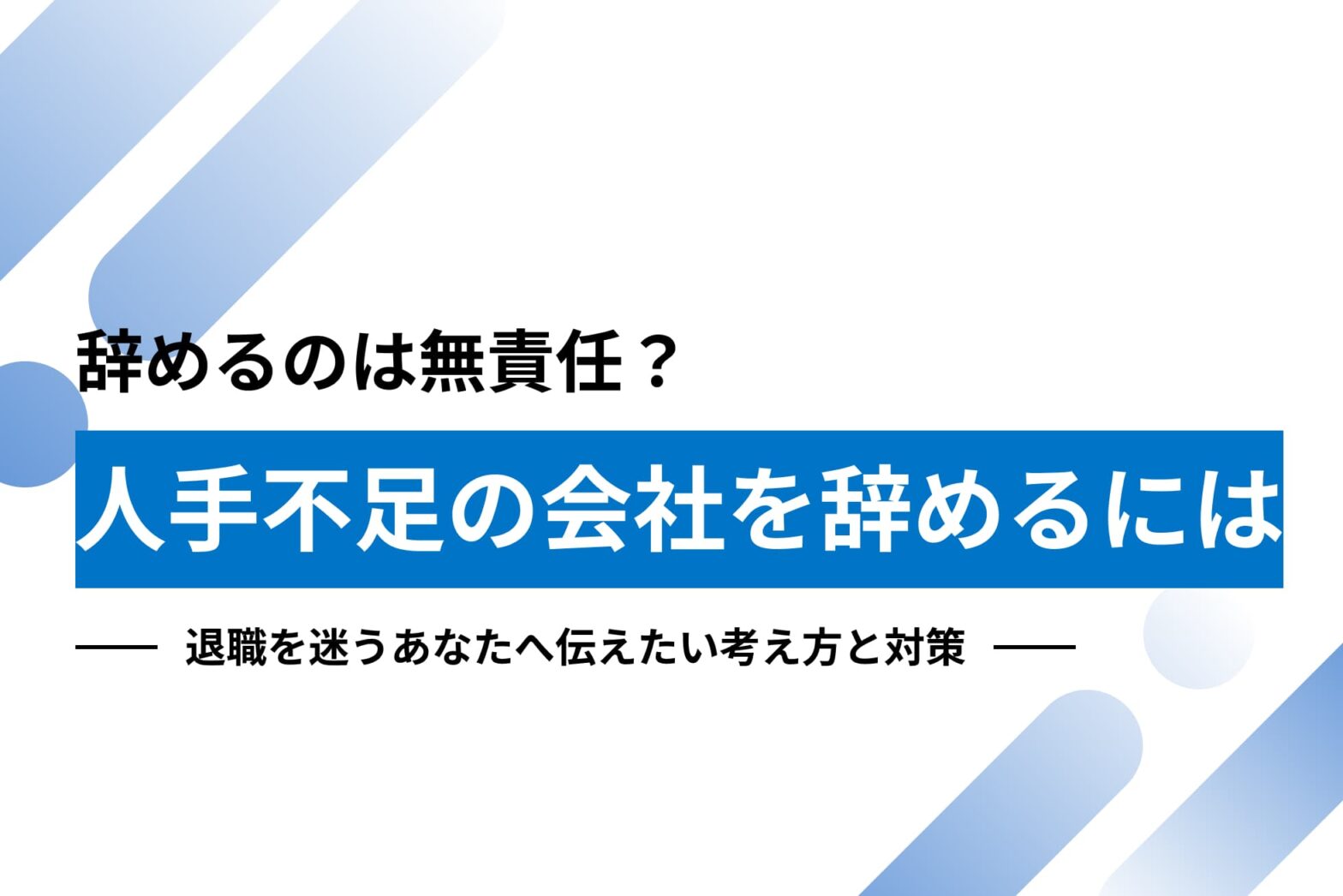Category
こんにちは。無人決済店舗システムを提供しているTOUCH TO GO 編集部です。
無人店舗経営は、人手不足や非接触ニーズに応える革新的なビジネスモデルとして急拡大しています。
「店舗を無人化して本当にうまくいくの?」そんな疑問や不安を抱える方も多いでしょう。
本記事では、無人店舗の市場動向から導入ステップ、収益モデルについて解説しています。
無人店舗経営の成功につながるため、ぜひ最後までご覧ください。
監修者プロフィール

2019年に株式会社TOUCH TO GOを設立。無人決済店舗システムを提供し、次世代型小売の拡大に取り組んでいる。
目次
無人店舗経営とは?注目される背景と市場の動き
無人店舗とは、店員を常駐させずにAIやIoT、センサー、セルフレジなどを活用して自動で運営する店舗形態です。
人手不足や感染症対策、24時間営業への対応など、多くの社会的ニーズに応える仕組みとして注目を集めています。
以下では、無人店舗の背景と市場の動きを3つの観点から解説します。
- 人手不足と人件費削減のニーズ
- 非対面・非接触ニーズの拡大
- 無人店舗の市場規模と今後の成長性
人手不足と人件費削減のニーズ
日本の深刻な人手不足は無人店舗の需要を押し上げる要因です。
少子高齢化により飲食や小売業では慢性的な人材不足が続いており、採用コストや労働時間の確保が課題となっています。
無人店舗では、セルフレジや自動精算機などを導入することで人手を介さずに運営でき、人件費の大幅な削減が可能です。
特に深夜営業やピーク時間外など、従来なら採算が合わなかった時間帯にも対応できる点が経営上の大きなメリットとなっています。
非対面・非接触ニーズの拡大
新型コロナウイルスの流行を契機に、非対面・非接触でのサービス提供が求められるようになり、無人店舗はそのニーズにマッチする形で急成長しています。
入店から決済まで他人と接触せずに完結できる仕組みは、感染リスクを軽減し、衛生面での安心感を提供できるのが特徴です。
これにより消費者の購買心理を後押しし、購買率の向上にも寄与しています。
近年では、このような需要がコロナ後も継続しており、無人化技術は今後も日常的な利便性の向上に資する要素として評価されているのです。
無人店舗の市場規模と今後の成長性
無人店舗市場は国内外で急成長しています。
日本国内では、無人店舗のビジネス市場が2022年に約606億円規模、2027年には技術やサービス市場などの関連技術分野も含めて97億円に達すると予測されており、年間の平均成長率は驚異の94.5%とされています。
また、アメリカ市場では2023年に約1兆円規模だったものが、2031年には4兆円を超えると予測されています。
これらの背景には、IoTやAIなどの技術進化や、消費者の購買行動における変化があります。
無人店舗は一過性のトレンドではなく、今後の小売業を変える中核技術となる可能性が高いといえるでしょう。
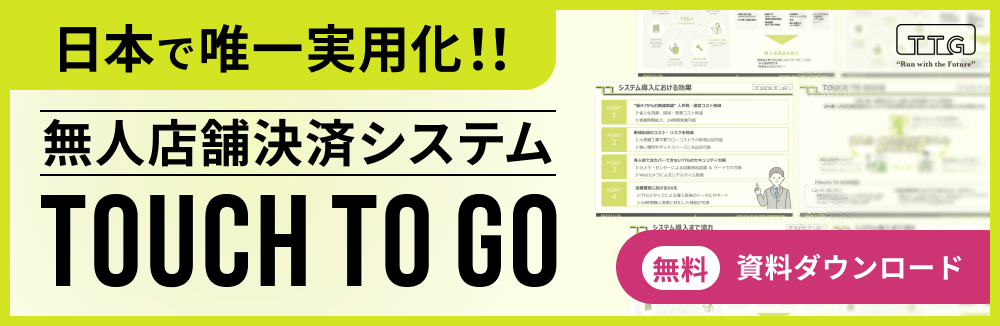
TOUCH TO GO の 無人決済店舗システムなら、人手不足でも効率的な運営が可能。コストを抑えながら安定した経営を実現できます。
無人店舗での利用を検討されている方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/
無人店舗経営の代表的なビジネスモデル
無人店舗には「無人コンビニや販売所」「コインランドリー・無人ホテル」「海外展開」の3つの主要モデルがあります。
業種ごとの特徴や技術導入の動向から、どの業種でも顧客ニーズと運営コストのバランスをどのように取るかがポイントです。
以下の内容について、それぞれ解説します。
- 無人コンビニや無人販売所の特徴
- コインランドリー・無人ホテルなど業種別事例
- 海外における無人店舗の展開と反応
無人コンビニや無人販売所の特徴
無人コンビニは、AIカメラやセンサーによって来店者の行動を認識し、レジなしで自動決済が完了する次世代型店舗です。
TOUCH TO GOのように、入店から退店までスムーズな購買体験を実現します。
また、飲料や食品などを販売する簡易型の無人販売所は省スペースで運営可能なため、オフィスや駅構内などへの設置が進んでいます。
キャッシュレス決済を前提とすることでセキュリティ面でも利便性が向上し、導入のハードルが下がっているのです。
コインランドリー・無人ホテルなど業種別事例
コインランドリーは無人店舗の中でも定着している業態で、最近ではスマートフォンで予約や決済ができるシステムや遠隔監視カメラなどが導入されています。
ふとん対応や猫ギャラリーの併設など、付加価値型の店舗も登場しており、差別化が進んでいるのが特徴です。
また、無人ホテルやカラオケボックス、ジムなども無人化が進み、予約や顔認証を活用したチェックインシステムが普及しています。
これによりスタッフの常駐が不要となり、運営コストの大幅な削減が実現しています。
海外における無人店舗の展開と反応
海外ではAmazon Goが代表格で、米国や英国で数十店舗を展開しています。
中国ではAIの無人店舗が広く普及し、顔認証や自動決済技術を用いたコンビニが都市部を中心に増加しています。
中東やヨーロッパでも24時間の無人店舗が登場し、スピーディでストレスのない買い物体験が評価されているのです。
また、アメリカのRobomartのような無人移動販売車や香港のWatsons、7-Elevenによる無人店舗も注目を集めています。
グローバルでは「手間がかからず清潔」「現金不要」などのニーズに応える形で無人店舗が急拡大しています。
関連記事>>無人店舗ビジネスと相性がよい業種とは?課題やビジネスモデル例も紹介
導入に必要な設備とシステム
無人店舗を成功させるためには、AIやIoTを活用した技術基盤、セルフレジや入退室管理などの基本装備、そして顧客データの収集・分析の仕組みが不可欠です。
以下に、それぞれの役割と導入メリットを解説します。
- AIやIoT技術の活用(顔認証・センサーなど)
- セルフレジ・入退室管理などの基本装備
- 顧客データの収集と分析の仕組み
AIやIoT技術の活用(顔認証・センサーなど)
AIカメラやセンサー技術は、無人店舗の運営を支える中核システムです。
顔認証システムは、入退店の本人確認に役立ちます。
また、重量センサーや行動認識AIにより、商品を手に取っただけで自動的に認識し、レジなしで決済が可能です。
これらの仕組みにより、人手が不要でも万引き防止やスムーズな買い物が期待できます。
さらに、IoT連携によってリアルタイムで商品棚の状況や顧客動線を把握でき、店内オペレーションの最適化が進みます。
セルフレジ・入退室管理などの基本装備
セルフレジはバーコードやQRコード、RFIDによる自動スキャン、精算機能を備え、スタッフを配置せずともスムーズに会計を完了できるシステムです。
最近では、スマホ連動や非接触型のレジも普及しています。
入退室管理では、スマートロックや顔認証付きゲート、ICカードリーダーが活用されており、不正入場の防止や利用時間の記録も可能です。
そのため、防犯や安全面を確保しながら、営業時間の拡大や深夜営業も実現できます。
これらの設備は無人化運営の基盤となるでしょう。
顧客データの収集と分析の仕組み
無人店舗では、顧客の入店時間や購買行動、商品選択などの行動データをシステムが自動収集し、AIが解析する仕組みが整備されています。
そのため「いつ・誰が・何を買ったか」「どの商品が手に取られたが買われなかったか」などを可視化できるのが特徴です。
蓄積されたデータは人気商品の分析や在庫調整、販促キャンペーンの最適化に活用でき、リピート率の向上や売上アップにつながります。
POSやCRMと連携すれば、より精度の高いパーソナライズ施策が展開可能です。
関連記事>>無人店舗の事例7選|市場規模やメリット・課題も詳しく解説
無人店舗のメリットとデメリット
無人店舗は省人化による収益性や24時間営業といった利点がある一方で、高額な初期投資や防犯・顧客対応などの課題も存在します。
以下では、無人店舗の導入を検討するうえで重要な3つの視点から整理します。
- 24時間営業や省人化による収益性
- 初期投資やシステム導入コスト
- 防犯・万引き・顧客対応の課題
24時間営業や省人化による収益性
無人店舗の最大の魅力は、人的コストを大幅に削減できる点です。
従来の有人運営では難しかった深夜営業や長時間営業が可能になり、売上の最大化が図れます。
また、セルフレジやキャッシュレス決済によって回転率が向上し、レジ対応の待ち時間も解消されます。
特に人手不足に悩む中小企業や飲食・小売業にとって、省人化は利益改善に大きく貢献できるでしょう。
実際に無人化を導入した企業の多くが、運営効率の向上とコスト削減を実感しています。
初期投資やシステム導入コスト
無人店舗の立ち上げには、センサーやカメラ、ゲートなどの初期設備やAI・IoTシステムの導入が必要なため、まとまった初期投資が発生します。
また、導入後もシステムの保守や管理費用が継続的に必要となり、運営規模によっては数百万円以上のコストがかかる場合もあるのです。
小規模店舗では、リースやレンタルを活用してコストを分散する事例も増えています。
導入前には事業計画をしっかり立て、費用対効果を見極めることが重要です。
防犯・万引き・顧客対応の課題
無人運営では、万引きや不正侵入などの防犯リスクへの対策が必要です。
監視カメラやセンサー、ゲートなどの設備を組み合わせて多重防御を行うことが基本ですが、完全にリスクをゼロにするのは難しいでしょう。
また、顧客がシステムトラブルに遭遇した場合、即時対応できないケースがあり、顧客満足度に影響する場合もあります。
これらの課題に対しては、遠隔サポートや簡易マニュアルの設置、段階的な無人化の導入などが現実的な対処法です。
関連記事>>無人店舗のメリットや課題とは?事例と開業準備のポイント
無人店舗経営の成功事例と収益モデル
無人店舗経営を成功させるためには、フランチャイズの活用による低リスク開業や、立地に応じた店舗戦略、投資回収を見据えた収益モデルの設計が重要です。以下に3つの代表的な観点から解説します。
- フランチャイズ活用による低リスク開業
- 地方での小規模店舗と都市型高収益モデル
- 投資回収シミュレーションと収益の考え方
フランチャイズ活用による低リスク開業
無人店舗の導入ハードルを下げる手段として、フランチャイズ(FC)展開が注目されています。
例えば、無人セルフ脱毛サロン「ONESELF」や「ハイジ」は、RemoteLOCKなどの入退室管理技術とセットで提供され、運営ノウハウも共有されるため、未経験でも参入しやすいモデルです。
ブランドの認知や集客支援、設備一式のパッケージ提供などにより、初期のマーケティングやトラブル対応の負担を軽減でき、安定したスタートが可能になります。
地方での小規模店舗と都市型高収益モデル
無人店舗は立地に応じて戦略が異なります。
地方は家賃や人件費が比較的低いため、小規模な店舗でも利益を出しやすく、静岡のMaxマートや長野のデリシアなど、地元密着型の展開が進んでいます。
一方、都市型モデルでは、駅構内やホテル内に設置される無人店舗が高い集客力を発揮し、TOUCH TO GOなどの例が好調です。
都市型は客単価や回転率が高く、初期投資はやや高額ですが、高収益が期待できます。
投資回収シミュレーションと収益の考え方
無人店舗の初期費用は、設備やシステムによって異なりますが、セルフ型で100〜300万円、AI自動決済型では1,000万円以上かかる場合もあります。
しかし、省人化によって月間数十万円の人件費が不要となるため、8か月〜2年程度で投資回収できる事例があります。
重要なのは、売上や経費、運営効率などを数値で試算し、感度分析を行うことです。
補助金の活用やリースの導入による資金分散も、有効な戦略といえるでしょう。
関連記事>>無人店舗の課題を徹底解説|成功のためのポイントと事例も紹介
無人店舗導入のステップと注意点
無人店舗を円滑に導入・運営するには「物件選びと立地条件」「設備と業者の選定」「セキュリティとトラブル対応」の3つのステップを計画的に進める必要があります。
各段階での注意点を以下にまとめます。
- 物件選びと立地条件の検討
- 設備導入と業者選定のポイント
- セキュリティ対策とトラブル時の対応策
物件選びと立地条件の検討
無人店舗の立地は、想定ターゲットや商品構成に直結する最重要項目です。
例えば、ビジネスパーソンをターゲットにするならオフィスや駅近の立地、ファミリー層なら住宅地が適しています。
また、人通りの多さや近隣店舗との競合状況、駐車場の有無なども重要な判断材料です。
さらに、無人運営では夜間営業も多いため、セキュリティ面や照明環境も確認が必要です。
物件選びは運営に直結するため、現地調査と家賃収支のバランスを確認しましょう。
設備導入と業者選定のポイント
無人店舗に必要な主な設備には、セルフレジ、AIカメラ、センサー、入退室管理装置、キャッシュレス決済システムなどがあります。
導入コストは店舗規模や機能により異なりますが、100万〜300万円程度が一般的です。
業者選定は価格だけでなく、導入後のサポート体制やトラブル対応のスピード、システムの拡張性なども考慮する必要があります。
また、複数の見積もりを取り、導入機器が補助金の対象となるかを確認することも重要です。
セキュリティ対策とトラブル時の対応策
無人店舗ではスタッフ不在の時間帯が多いため、防犯対策が極めて重要です。
監視カメラの設置だけでなく、顔認証による入退室管理、警備会社との契約など、複数のセキュリティ対策を組み合わせることで安心感が高まります。
さらに、トラブル時の対応として、遠隔からの操作やモニタリング、非常ボタンの設置、24時間体制のサポートセンターとの連携体制を整えることが求められます。
顧客が安心して利用できる環境づくりが成功のポイントです。
関連記事>>無人店舗の万引きが深刻化?対策と万引防止のための店舗運営について解説
無人店舗経営の今後と将来性
無人店舗は、技術の進化と消費者ニーズの変化により、今後さらに拡大が見込まれる分野です。
特にサービスの拡張や補助金制度の整備、副業・起業ニーズの高まりが今後の成長を後押ししています。以下に、将来性を示す3つの視点を解説します。
- 無人化が進む分野とサービスの拡張
- 自治体支援や補助金制度の活用方法
- 副業・スタートアップとしての可能性
無人化が進む分野とサービスの拡張
近年では、無人コンビニだけでなく、セルフエステや無人カフェ、無人貸し会議室、冷凍食品販売機、無人レンタルスペースなど、さまざまな業態で無人化が進行しています。
非対面・非接触のニーズが続く中、利便性と安全性を兼ね備えた業態が求められています。
さらに医療や介護、交通、物流などの分野でも、無人窓口や自動運転システムなどの導入が検討されているのです。
今後は、無人技術を活かした複合型サービスや地域連携型の運営モデルが普及する可能性も高いといえるでしょう。
自治体支援や補助金制度の活用方法
無人店舗を導入する際は、複数の補助金制度を活用すると初期費用を大きく軽減できます。
例えば「小規模事業者持続化補助金」は、店舗設備や広告費の2/3を補助(最大250万円)します。
「事業再構築補助金」では最大1億円の支援を受けられる可能性もあるのです。
また「中小企業省力化投資補助金」や「IT導入補助金」では、セルフレジや予約システムの導入費用に対応しています。
申請には事業計画書や見積書が必要ですが、支援機関や税理士によるサポートも整っています。
副業・スタートアップとしての可能性
無人店舗は、低コストかつ省人力で運営できる点から、副業や小規模起業にも最適なビジネスモデルです。
例えば、冷凍自販機や無人アイス販売所などは個人でも導入可能で、月収20万円以上の実績例もあります。
また、フランチャイズモデルであれば、開業支援や集客サポートが整っており、未経験者でも安心して始められるのがメリットです。
さらに、店舗数を増やすスケーラビリティが高く、成功すれば複数拠点展開も可能です。
これにより、副業から本業へのステップアップも視野に入るでしょう。
まとめ
無人店舗経営とは何か、その背景や市場動向、主要なビジネスモデル、導入に必要な設備、収益モデルについて解説しました。
無人店舗は、人手不足や非接触ニーズの高まりを受け、急速に普及している業態です。
無人コンビニやコインランドリー、無人ホテルなど、業種別にさまざまなモデルが展開されており、AI・IoT技術の進化により導入のハードルも下がっています。
導入時には、物件選定からセキュリティ対策、投資回収の見通しまで綿密な計画が求められますが、補助金制度の活用やフランチャイズ展開によって低リスクでの開業も可能です。
今後はさらなるサービスの多様化が進み、副業や小規模起業の手段としても有望な選択肢となるでしょう。
無人店舗は、これからの小売業やサービス業の在り方を変える可能性を秘めています。
TOUCH TO GO の 無人決済店舗システムなら、人手不足でも効率的な運営が可能。コストを抑えながら安定した経営を実現できます。
無人店舗での利用を検討されている方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/