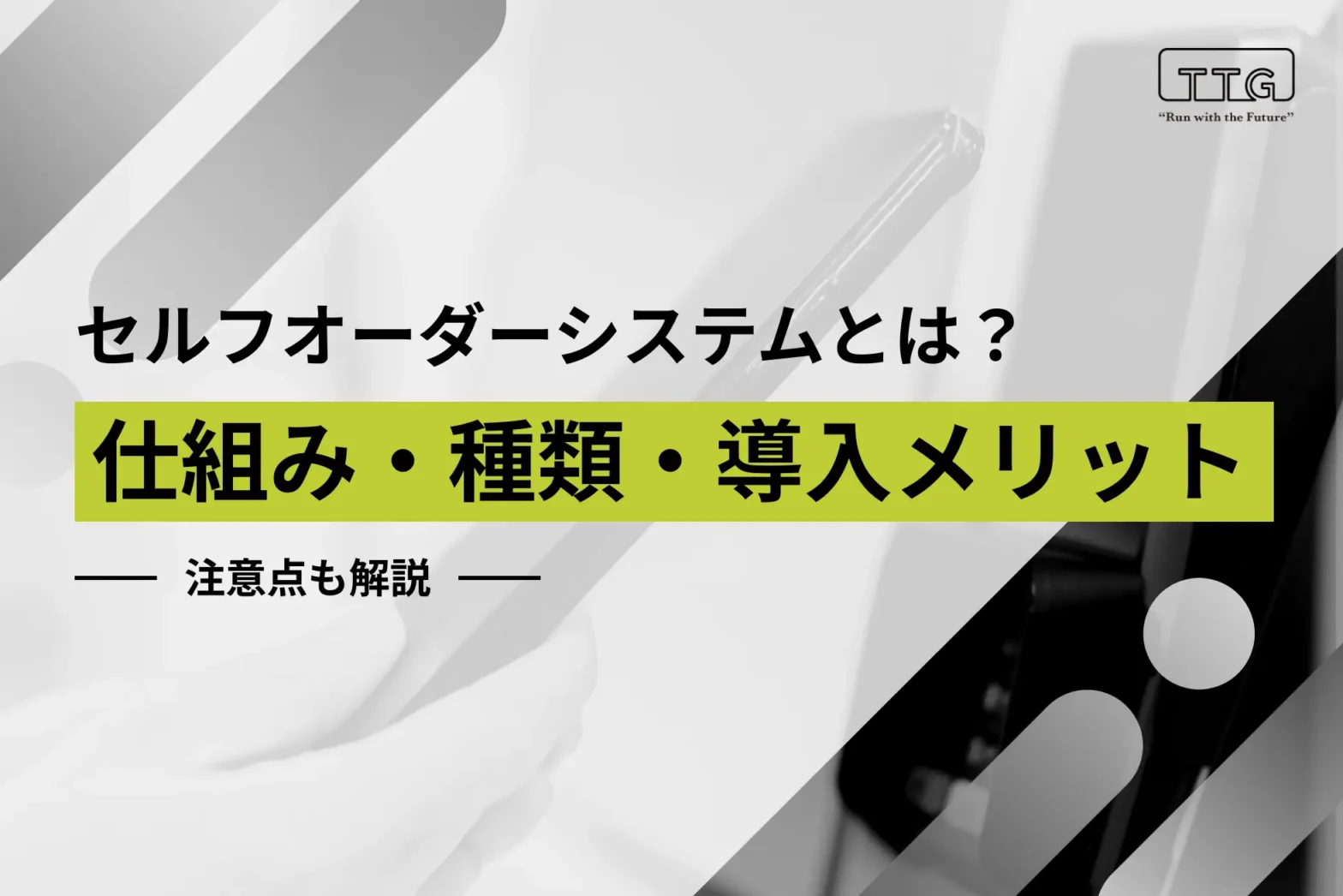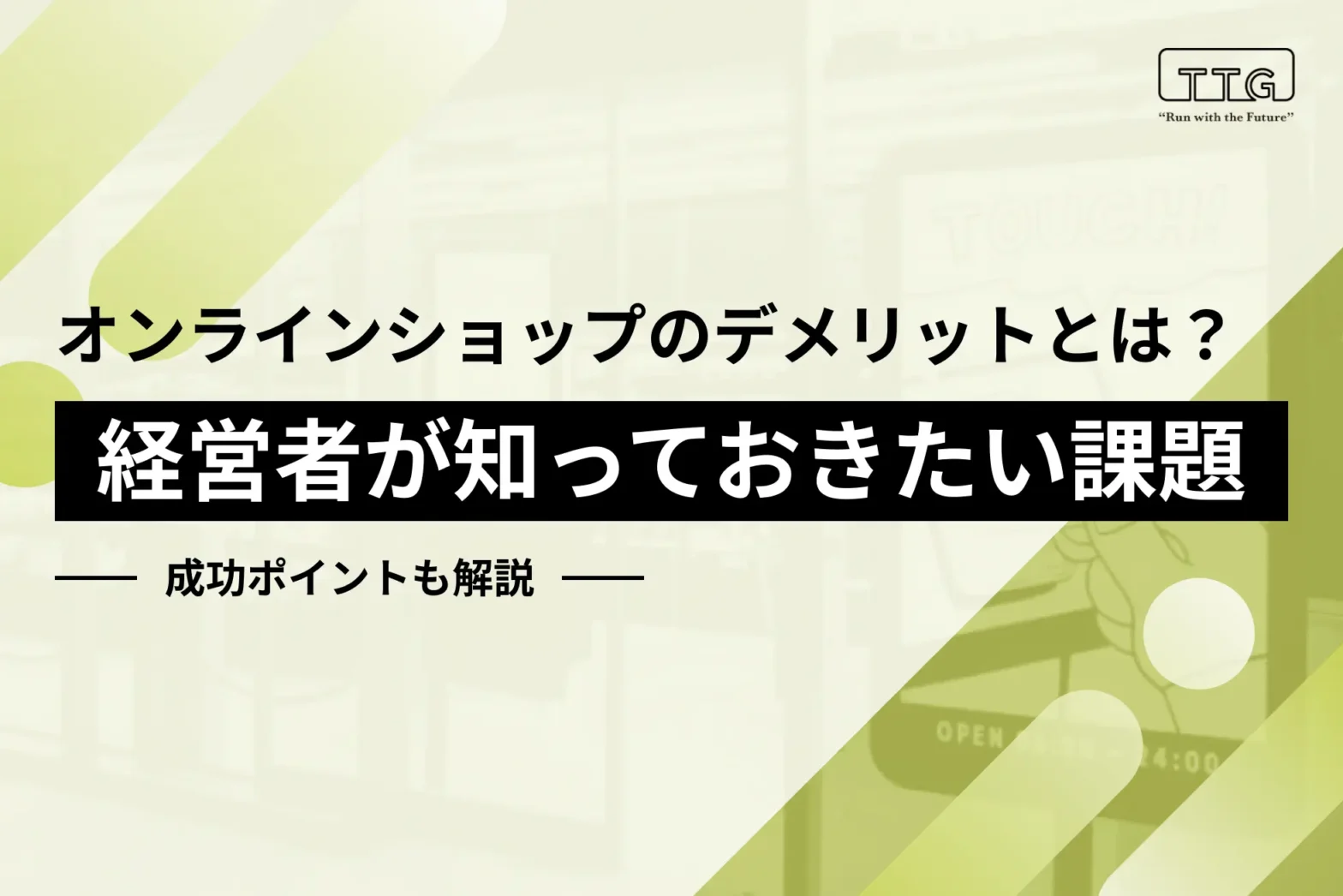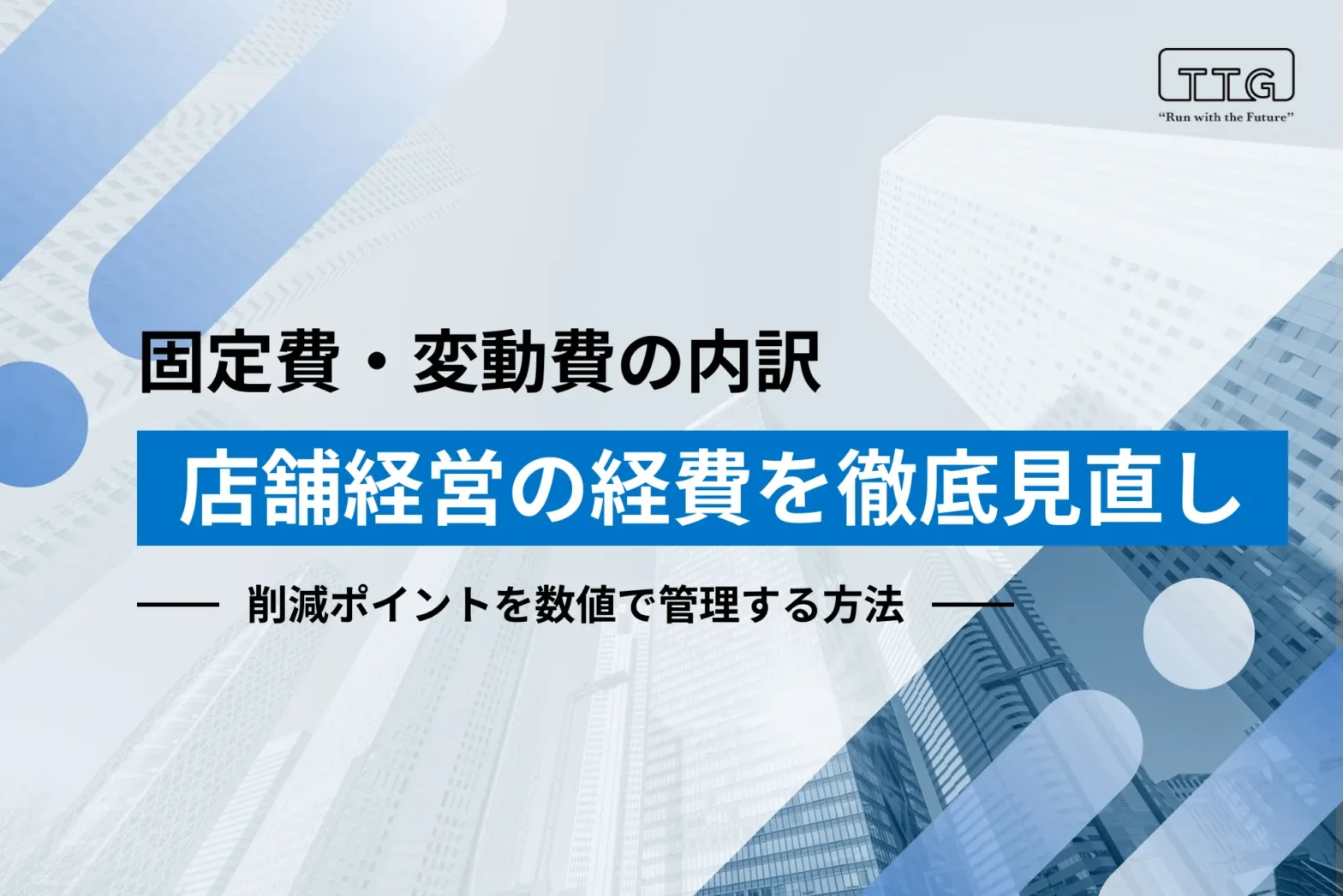Category
こんにちは。無人決済店舗システムを提供しているTOUCH TO GO 編集部です。
コンビニ業界では今、人件費の見直しが避けられない課題となっています。人手不足と最低賃金の上昇により、人件費の増加は店舗運営のコスト構造を大きく変えつつあります。
一方で、接客品質や顧客満足度を維持することも、これまで以上に重要になってきました。
こうした背景の中、「人件費をどう抑えるか」ではなく「どう整えるか」という考え方が求められています。
そこで本記事では、コンビニの人件費の割合や内訳、人件費削減のための具体的な施策を紹介します。
コンビニオーナーが知っておきたい、人件費との向き合い方のポイントも解説しているので、ぜひ参考にしてください。
関連記事▼
監修者プロフィール

2019年に株式会社TOUCH TO GOを設立。無人決済店舗システムを提供し、次世代型小売の拡大に取り組んでいる。
目次
コンビニの人件費が増加する背景
人件費の高騰は、多くのコンビニオーナーにとって頭の痛い課題となっています。 単に雇用コストが上がっているだけでなく、シフト確保の難しさも重なり、人件費の“質”も“量”もコントロールしづらくなっているのが現状です。
ここでは、人件費が増え続けている背景についてみていきましょう。
人手不足と最低賃金の上昇がもたらす影響
日本全体で労働人口が減少しているなか、コンビニ業界も深刻な人手不足に直面しています。
特に都市部では競合店が多く、アルバイトの確保には時給アップが避けられない状況です。
さらに、最低賃金の引き上げも人件費を押し上げる大きな要因です。
経済産業省が公表する資料でも、最低賃金の上昇が小規模事業者の経営に与える影響が指摘されています。
出典:中小企業庁|「2024年版 小規模企業白書」第1部第4章第1節「人手不足対応と持続的な賃上げ」
さらに、さらに、新人スタッフの育成には時間とコストがかかり、「人が集まりにくい」「教育に時間がかかる」「賃金が上がる」という三重苦が、コンビニ経営を圧迫していると考えられます。
深夜営業と人件費の関係性
深夜の勤務は一般的に時給が25%以上増しになるため、同じ業務時間でも昼間に比べて人件費がかさみやすい傾向があります。
しかし、深夜の売上がそれに見合っているとは限りません。むしろ客数が少ない時間帯でも「開けておくこと」が前提となっていたこれまでの24時間営業体制は、今見直しの時期にきているともいえます。
実際、一部のコンビニチェーンでは深夜営業の縮小や無人営業への切り替えを試験的に進めており、コストと売上のバランスを改めて見直す動きが出始めています。
今後のコンビニ運営では、「どの時間帯にどれだけの人員を置くか」という視点が、さらに重要になっていくでしょう。
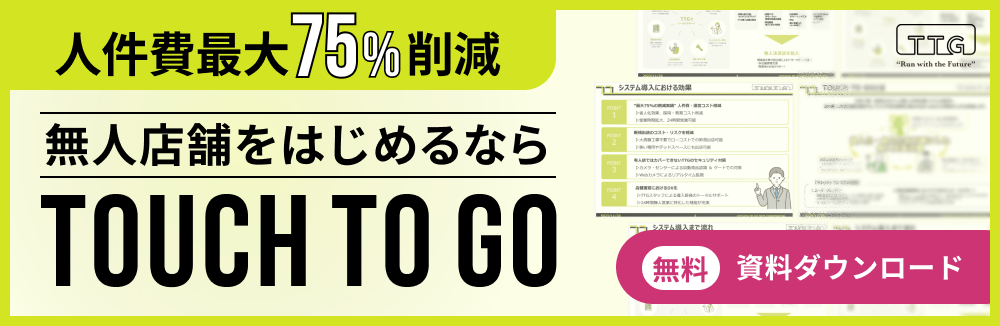
「TOUCH TO GO」の無人決済システムを導入し、無人店舗にすることで、人手不足の解消と人件費の削減を同時に実現できます。
店舗の省人化・人件費削減をご検討中の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/
コンビニの人件費の割合と内訳
人件費が店舗経営に大きな影響を与えるのは言うまでもありませんが、その実態や内訳をしっかり把握している店長・オーナーは意外と少ないかもしれません。
感覚だけで「高い」「厳しい」と感じているのではなく、何にどれくらいかかっているのかを具体的に知ることが、改善への第一歩になります。
ここでは、コンビニの人件費の現状と内訳について詳しく解説します。
平均的な人件費の割合
一般的に、コンビニエンスストアの人件費は売上高の10%程度を占めるとされています。
ただし、この数値はコンビニ業界全体の平均であり、地域や店舗規模、営業時間帯などによって実際の人件費率は異なります。
特に、最低賃金の上昇や人手不足による時給の高騰、深夜の割増賃金などを考慮すると、さらに高くなります。
また、オーナー自身が現場に立たない店舗では、より人件費が利益を圧迫しやすくなります。
人件費の内訳
コンビニにおける人件費は、主に以下のような業務に割り当てられています。
- レジ・接客対応
- 商品陳列・補充
- 清掃・衛生管理
- 発注業務・返品対応
- 店舗運営業務(教育・指導・事務)
時間帯別に見ると、朝・昼のピーク時にはレジ業務の負担が大きく、夜間や深夜には商品の補充や清掃業務が中心となります。
また、新人教育にかかる人件費も見落とせないポイントです。
ベテランスタッフが新人の指導に時間を割くことで、実質的に「ダブルで人件費が発生する」状態になることも珍しくありません。
人件費削減のための具体的な施策
人件費の負担が大きくなっている今、単に人員を減らすという方法だけでは、店舗の運営やサービスに支障が出る恐れがあります。
そこで大切なのは、業務の効率化や働きやすい環境づくりを通じて、「ムリなく削減する」工夫を取り入れていくことです。
ここでは、人件費削減のために取り組みたい施策を紹介します。
セルフレジ導入による業務効率化
セルフレジは、人件費削減の代表的な手段のひとつです。特に、ピーク時のレジ対応にかかる人手を減らせることが大きなメリットとなります。
お客様自身が支払いを行うことで、スタッフは品出しや清掃といった他の業務に集中できるようになります。
初期コストは発生しますが、長期的には人件費の圧縮に効果が見込めるケースも多く、導入を検討する価値は十分にあるといえます。
シフト最適化と労働時間の見直し
シフトの組み方を見直すだけでも、人件費削減に繋げることができます。
たとえば、混雑する時間帯にピンポイントで人を多く配置し、閑散時間帯は最低限の人員で回すような設計にするだけで、無駄な人件費を抑えられる可能性があります。
また、「1日のうちの1時間だけ人が足りない」といったケースも多いため、柔軟な短時間シフトの活用や、学生アルバイトとの時間調整も有効です。
最近では、AIやPOSデータを活用した自動シフト作成ツールを導入する店舗も増えています。
データを活用することで、売上や来店数の傾向をもとに人員配置を最適化できるため、無駄なシフトを減らし、効率的な人件費管理がしやすくなります。
業務の簡素化とスタッフ教育の充実
人件費を抑えるには、業務自体の見直しも欠かせません。
具体的には、以下のような「覚えやすく・こなしやすい現場」づくりが効果的です。
- 商品の補充ルールを統一して迷いをなくす
- レジ操作を簡素化する
- マニュアルを動画化する
あわせて、スタッフ教育やフォロー体制の整備も重要です。新人が早期に戦力になれば、そのぶん教育にかかる時間やコストが削減され、人件費全体の抑制にもつながります。
無駄を減らし、「やるべきことに集中できる環境」を店舗全体で整えることが、無理なく人件費を見直す第一歩となるでしょう。
無人店舗という選択肢も視野に
近年では、セルフレジをさらに発展させた「無人店舗」の導入を検討する動きも広がりつつあります。
スタッフが常駐せずとも店舗を運営できる仕組みは、人件費の大幅な見直しにつながる可能性を秘めています。
たとえば、TOUCH TO GOが提供する無人決済システムでは、入店から会計までをスムーズに完了できる設計により、顧客にとってのストレスを抑えながら、省人化を実現することが可能です。
深夜帯や閑散時間帯のみ無人運用に切り替えるといった部分的な導入でも、コスト削減効果は期待できます。
また、TOUCH TO GOの無人決済システムは、コールセンターとの連携によって、リモートでの接客サポートにも対応しています。
そのため、店内にスタッフがいなくても、「困ったときに誰かが対応してくれる」という安心感を提供できます。
コンビニの無人化を検討している方は、ぜひ以下のリンクからTOUCH TO GOのプロダクトをチェックしてみてください。
製品詳細>>TOUCH TO GO
人件費削減と接客品質のバランスを取る方法
人件費を削減するとなれば、どうしても「サービスの質が下がるのでは」と不安になるかもしれません。
実際に、人数を減らせば手が回らなくなる場面も出てきます。そこで考えておきたいのが、人件費削減と接客品質のバランスを取る方法です。
ここでは、スタッフの人数を減らしても接客の質を落とさない方法を紹介します。
顧客満足度を維持する
スタッフ数を減らす場合、お客様が不便を感じない店舗オペレーションの設計が重要になります。
たとえば、見やすいPOPや案内表示、分かりやすい商品配置を工夫することで、お客様が迷わずスムーズに買い物できる環境を整えられます。
また、レジ周辺でのひとことの声かけや挨拶など、短時間でも“気持ちの良い接客”を感じてもらえるような工夫が、接客品質を大きく左右します。
スタッフの人数が少なくても顧客満足度を維持することができれば、「感じがよかった」「また来たい」と思ってもらえるはずです。
クレームや緊急時における体制の整備
少ない人員でコンビニを運営する際、クレームやトラブルへの対応の懸念もあります。
万が一、誰も対応できない状況が発生すれば、「接客の質が悪い店」という印象に直結しかねません。
そのため、クレーム対応のフローや、緊急時における判断をマニュアル化しておくことです。
「誰が・どのタイミングで・どう対応するか」を明確にしておけば、経験の浅いスタッフでも安心して対応できます。
さらに、バックヤードや本部との連携体制を強化しておくことで、現場の人数が少ないときでも補助的な対応が可能になります。
緊急時でも落ち着いて対応できる仕組みがあれば、少人数体制でも接客品質を大きく損なうことなく運営できるでしょう。
人件費との向き合い方のポイント
人件費の見直しというと、「とにかく人員を減らす」と考えがちですが、本来は店舗の持続性やスタッフのモチベーションと合わせて考えるべきテーマです。
ここでは、経営者として人件費とどう向き合うかについて、意識しておきたいポイントを紹介します。
人を減らすことだけがコスト削減ではない
「人件費の削減=スタッフの数を減らす」という発想は、短期的には効果があるかもしれません。
しかし、スタッフの人数を減らしたことで業務が回らなくなったり、接客の質が落ちたりすれば、売上の低下や顧客離れにつながる可能性もあります。
本当に目指すべきは、必要な業務に人員を配置し、“ムダをなくす”ことで最適なコストに整えていくことです。
業務の効率化や自動化も含めて、店舗運営全体を見渡した視点で改善を進めることが大切です。
働きやすい環境を作り定着率を高める
「採用してもすぐ人が辞めてしまう」というサイクルが続くと、採用費や研修コストがかかるわりに人件費がかさみます。
一方、働きやすい環境が整えばスタッフは定着し、教育にかかる時間やコストも抑えられ、安定した戦力として店舗を支えてくれるようになります。
たとえば、柔軟なシフト対応、明確な評価制度、小さな成果を認め合う社風など、「日々の満足度を高める工夫」が定着率アップに繋がります。
こうした取り組みが、結果的に人件費全体の見直しにもつながっていくのです。
長く続けられる店舗運営のあり方を考える
人件費の見直しは、あくまで経営改善の“手段”のひとつです。本当に大切なことは、利益を確保しながら、無理なく続けられる運営スタイルを築くことです。
そのため、目先の削減ばかりを追うのではなく、「これからも必要とされるお店であり続けるには、どんな体制が必要か?」という視点で取り組むことが、スタッフにもお客様にも心地よい店舗作りにつながります。
まとめ
最低賃金の上昇や人手不足が続くなかで、人件費の見直しはコンビニ経営における重要なテーマとなっています。
しかし、単に人を減らすだけでは店舗の運営に支障をきたしたり、顧客満足度の低下を招いてしまう恐れもあります。
だからこそ重要なのが、必要な業務に必要な人を配置し、無駄を減らす“最適化”の視点です。
「セルフレジの導入」や「シフトの見直し」など、さまざまな手段を組み合わせることで、接客品質を保ちながら効率的な運営が可能になります。
人件費を最小限に抑えながら、自店舗で働くスタッフにとって良い環境を整えて、店舗運営の安定を目指しましょう。
無人コンビニの運営に興味がある方は、以下の記事も参考にしてください。
関連記事▼
「TOUCH TO GO」の無人決済システムを導入し、無人店舗にすることで、人手不足の解消と人件費の削減を同時に実現できます。
店舗の省人化・人件費削減をご検討中の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/