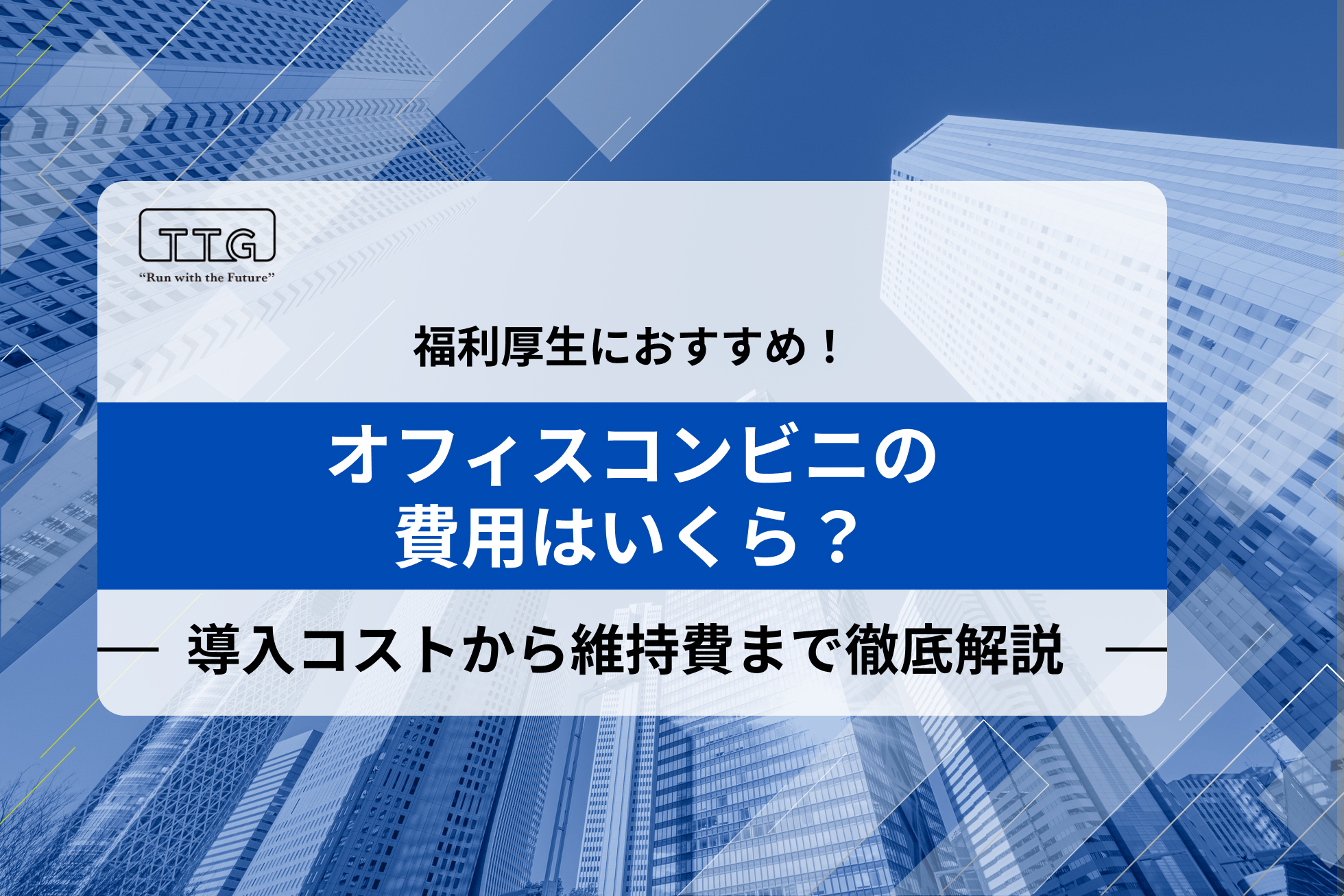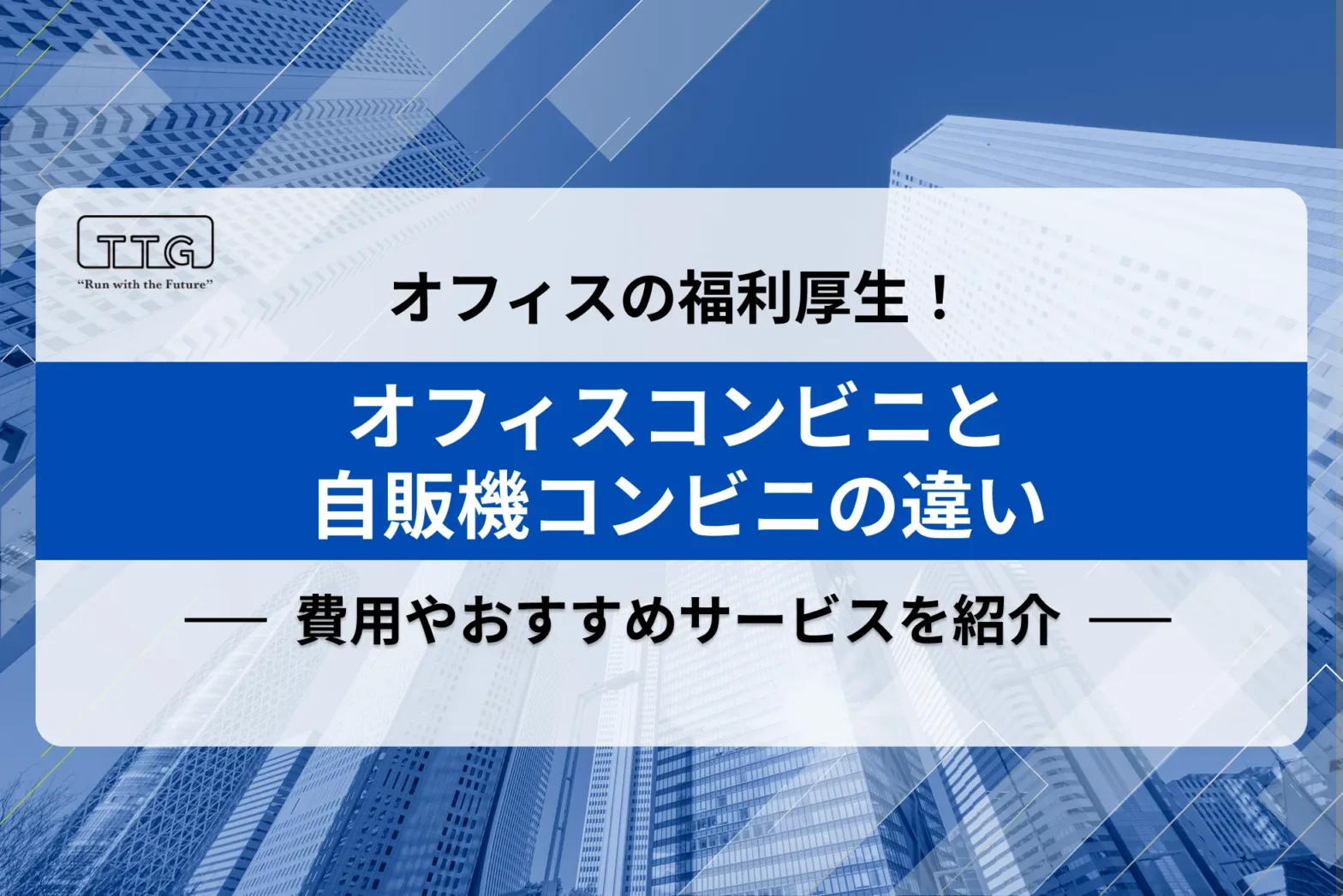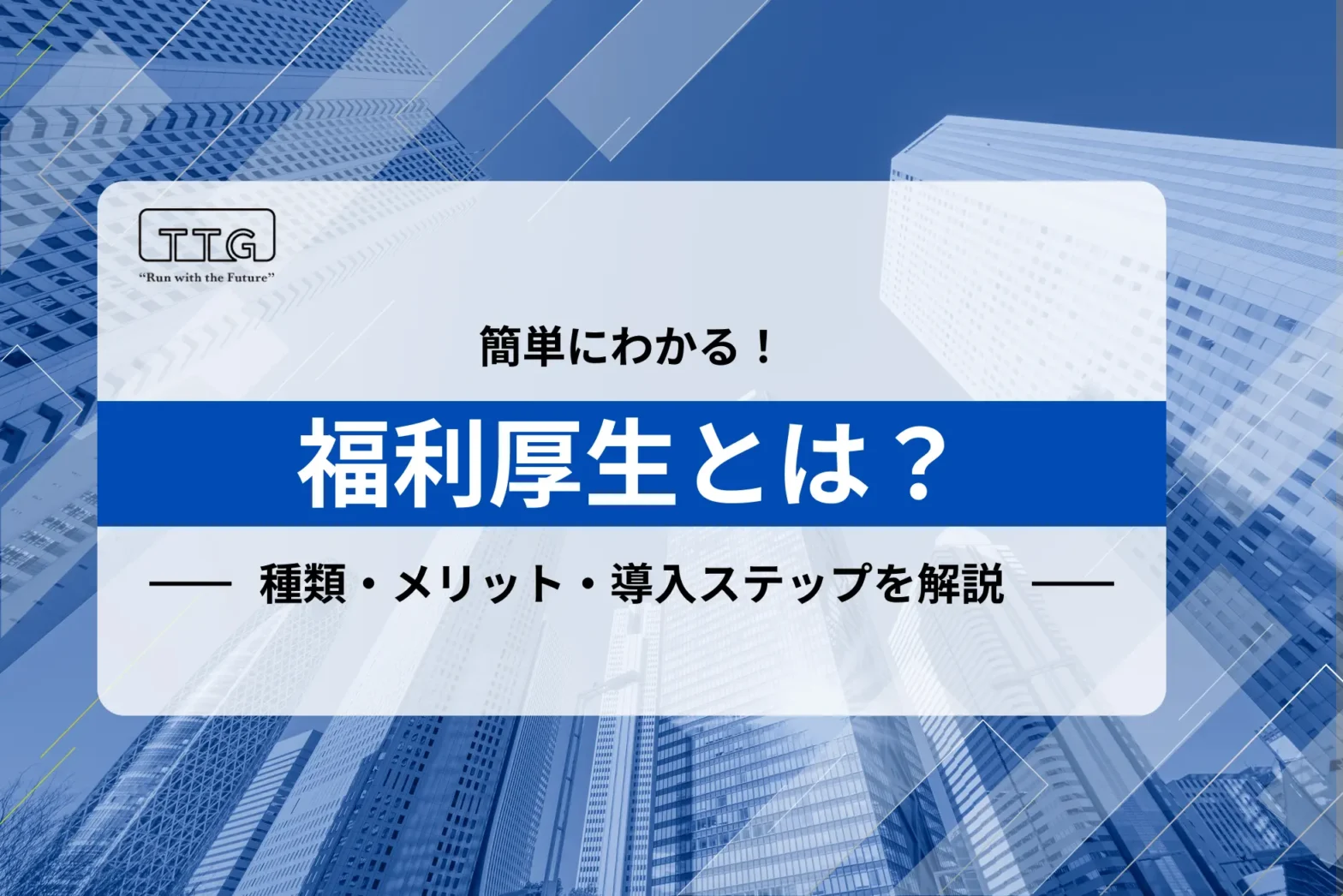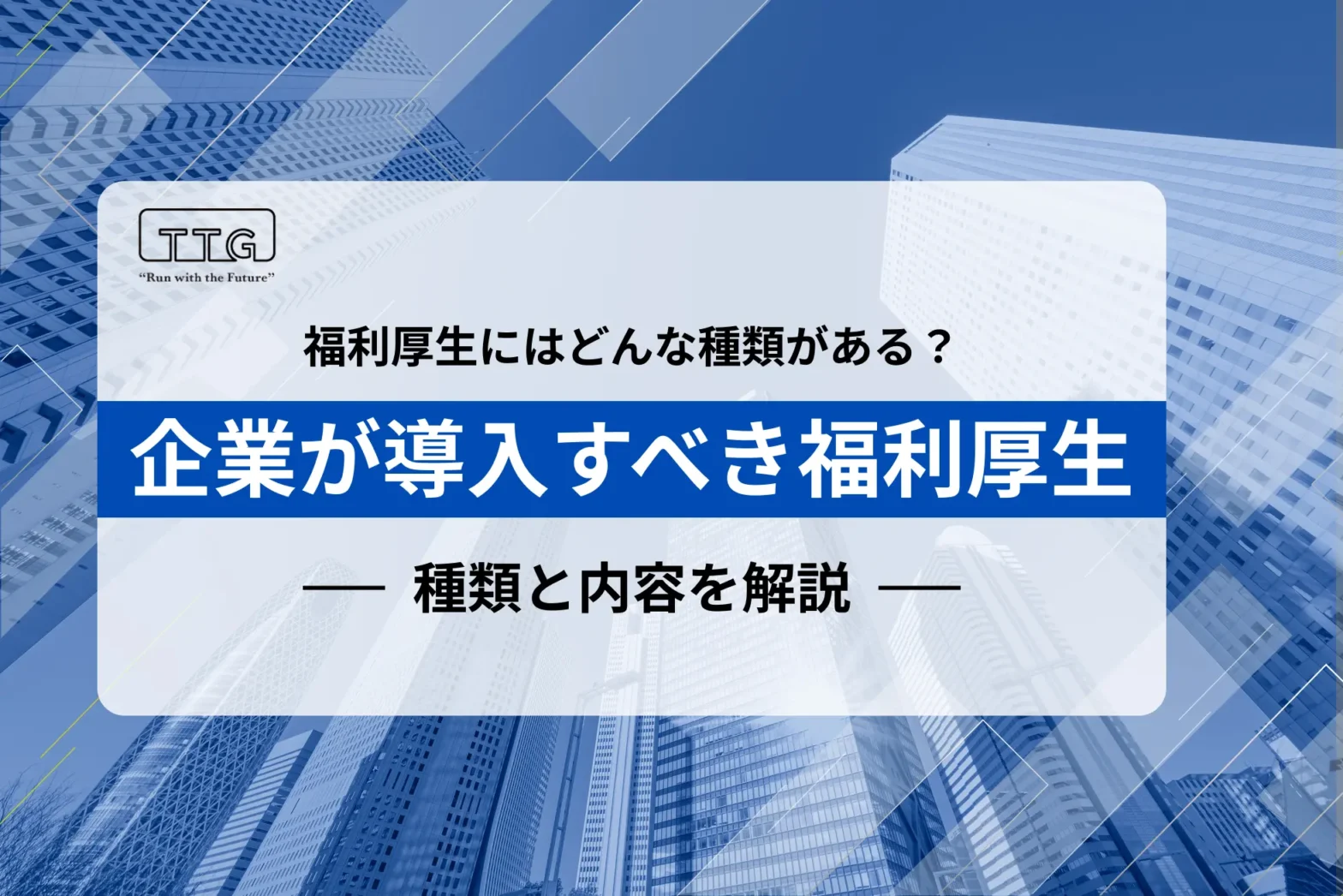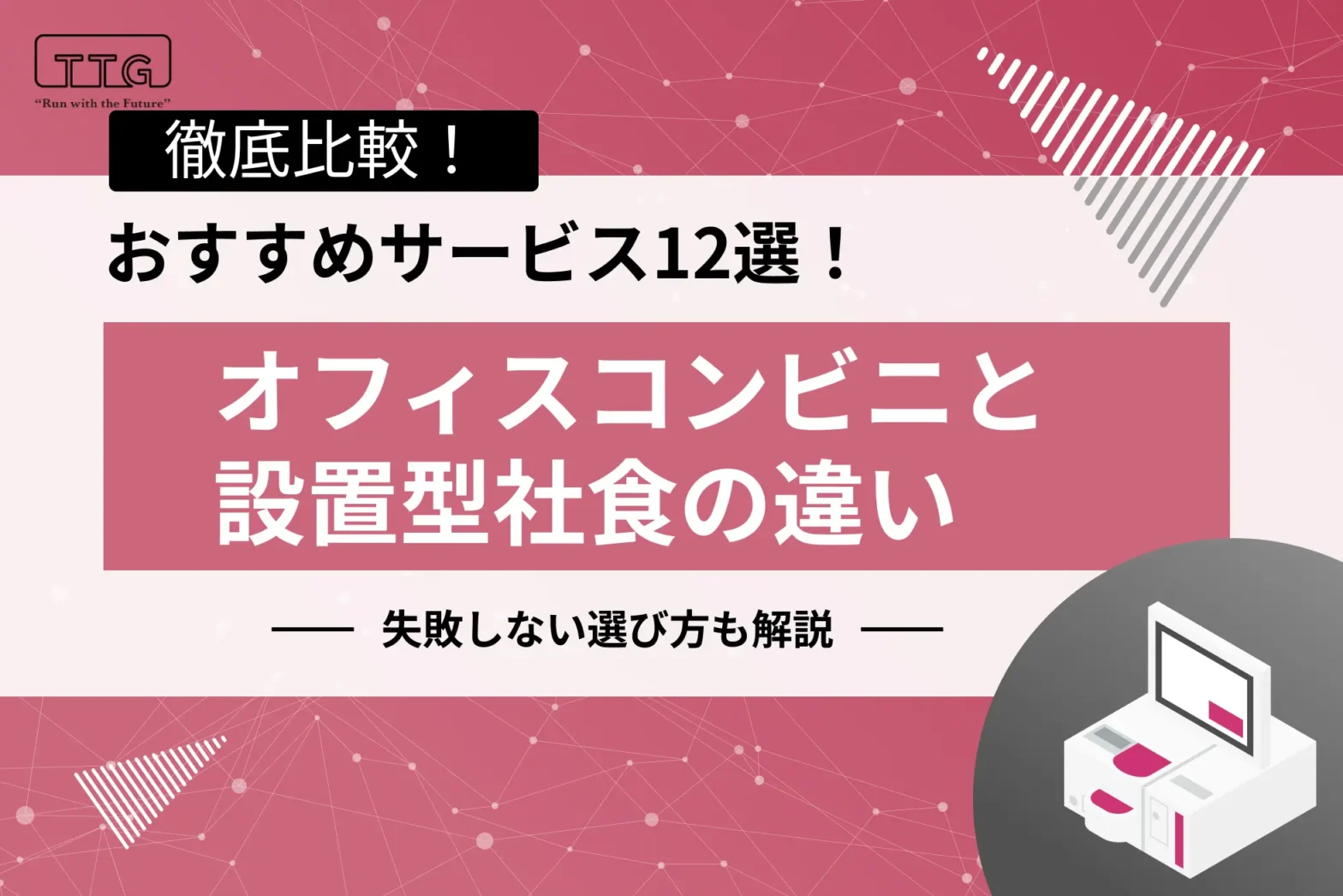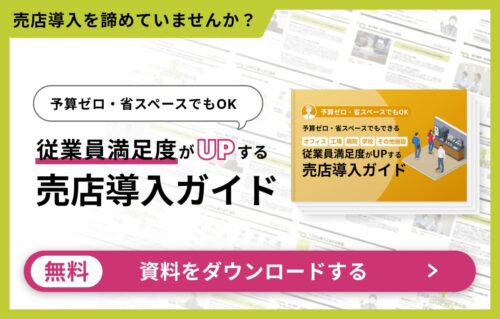Category
こんにちは。無人決済店舗システムを提供しているTOUCH TO GO 編集部です。
従業員の満足度や健康意識を高めつつ、採用力や定着率の向上も狙えるオフィスコンビニ。福利厚生として導入を検討する企業も増えています。オフィスコンビニの導入費用やランニングコストが気になっていませんか?
本記事では、オフィスコンビニの仕組みや導入費用の内訳、オフィスコンビニの費用を抑えるポイントについて解説します。
監修者プロフィール

2019年に株式会社TOUCH TO GOを設立。無人決済店舗システムを提供し、次世代型小売の拡大に取り組んでいる。
目次
オフィスコンビニとは
オフィスコンビニは、オフィス内に設置された小型の無人販売スペースで、従業員が飲料や軽食をいつでも購入できる仕組みです。有人レジを必要としないものも多く、セルフレジやQRコード決済などを活用することで運用が可能です。
設置形式は、冷蔵庫・ラック・冷凍庫などを組み合わせたものが主流で、電源を確保できれば設置場所も柔軟に選べます。補充や商品管理は提供事業者がするサービスもあるため、運営側の手間も少なく済みます。
オフィスコンビニで必要な費用
オフィスコンビニの導入を検討する際、どれくらいの費用がかかるのかは非常に気になるポイントです。費用構造を理解しておかないと、導入後にギャップが生まれる可能性もあります。
主に発生するのは、設置に関する初期費用、定期的な月額料金、商品そのものの代金です。以下では、それぞれの費用項目について解説します。
設置にかかる初期費用
オフィスコンビニを導入する際の初期費用は、サービスによって異なるものの、多くの場合で冷蔵庫の設置に関する費用はかかりません。冷蔵庫自体は業者が提供し、設置や立ち上げの作業もあわせて対応してくれることが一般的です。
商品の補充や設備のメンテナンスもベンダー側の管理下で行われるため、企業側が初期対応に追われることはほとんどありません。
ただし、電源の確保は必要であり、冷蔵庫を稼働させるための電気代は企業側が負担します。一部のサービスでは設置にあたって数万円程度の初期費用が発生するケースもあり、具体的には3万円程度が相場です。サービス内容や契約条件によって費用体系が異なるため、導入前には詳細な確認が欠かせません。
月額利用料金
オフィスコンビニの月額利用料金は、導入するサービスの内容によって大きく異なります。
たとえば、ペットボトル飲料やスナック菓子などの軽い商品を中心に取り扱う場合は、基本的に月額費用がかからないプランを選べることもあります。こうしたライトな構成は、導入のハードルが低く、まずはお試しで始めたい企業にぴったりです。
一方で、サラダやお惣菜、冷凍食品などをラインナップに含む本格的なサービスになると、一定の月額料金が必要になることもあります。目安としては3万円から5万円程度で、商品管理や補充、衛生面での対応なども含まれていることが多いため、金額の内訳を確認しておくと安心です。
商品自体の費用
オフィスコンビニを利用する際に発生する商品代金は、利用した分だけ支払う仕組みが基本です。取り扱うベンダーや商品の種類によって価格帯は異なりますが、ペットボトルの飲み物であれば50円前後、簡単なお惣菜であれば100円程度から購入できるケースもあります。
一般のコンビニと同等か、それよりも少しお得な価格設定のものが多いです。ただし、すべてのサービスが安価なわけではなく、一部では店舗よりも高めに価格が設定されていることもあります。そのため、月額費用や初期導入費とあわせて、全体としてのコストバランスを見ながら、サービスを選ぶことが大切です。どのような商品をどれくらいの頻度で社員が利用するのかを想定したうえで、費用対効果をしっかりと見極めるようにしましょう。
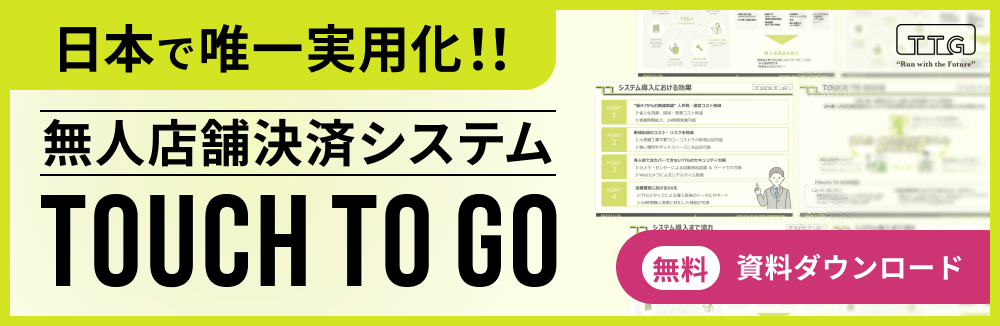
TOUCH TO GOの無人決済システムは、来店者の動きと商品を自動で検知。スキャンレスでスムーズな会計が可能なうえ、リモート管理によって人件費を約半分まで削減できます。
店舗の省人化・人件費削減をご検討中の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/
オフィスコンビニのメリット
オフィスコンビニの導入は、企業にも従業員にも多くのメリットがあります。ここでは、主なオフィスコンビニのメリットについて解説します。
コストをかけずに福利厚生を従業員に提供できる
オフィスコンビニは、企業が大きなコストをかけずに従業員の福利厚生を充実させられる仕組みです。
自動販売機感覚で軽食や飲み物を提供できるため、社内に食堂を設けるよりも圧倒的に導入コストを抑えられます。従業員にとっては「職場で小腹を満たせる便利な場所」があるという満足感を得られるため、福利厚生として十分に機能します。
商品の管理に手間がかからない
無人で運営されるオフィスコンビニは、商品の在庫補充や管理を外部業者が担うことが多く、社内スタッフが品出しや発注の手間に追われることはありません。運営に人手を割かずに済む点も、多忙な総務担当者にとっては、メリットです。
従業員が時間を問わずに利用できる
24時間いつでも利用できる点も、オフィスコンビニならではの魅力です。たとえば、夜遅くまで残業が続いた日や早朝出勤のタイミングでも、近くにコンビニがない状況でも、すぐにドリンクや軽食を手に取れる環境があるため、従業員のストレスは軽減されます。
企業イメージのアップにつながる
オフィスに無人コンビニを設置している企業は、社員を大切にしている会社という印象を与えやすく、採用活動や取引先とのイメージアップにもつながります。訪問者の目にも触れやすいため、社内の工夫として評価されるケースも少なくありません。
災害時に非常食にもなる
オフィスコンビニに備えられている飲料やスナック類は、災害時における非常食としても活用できます。物流が止まった際に備え、ある程度の在庫を維持しておけば、いざというときにも社員の安全と安心を守る備えになります。日常の利便性に加え、万が一のリスク管理にも役立つ点は、オフィスコンビニの隠れたメリットです。
オフィスコンビニの費用を抑えるポイント
コストをできるだけ抑えながらオフィスコンビニを活用したい企業にとって、最適なサービスを見極める力と、運用方法を見直す工夫が重要です。特に、小規模オフィスや少人数の職場では、無理のないプラン選びと実情に合った利用ルールがコスト削減に直結します。ここでは、オフィスコンビニの費用を抑えるポイントについて解説します。
自社に合ったサービス選定
数あるオフィスコンビニサービスの中から、自社に適したものを選ぶことが大切です。たとえば、管理の手間が少なくキャッシュレス対応に優れたサービスを選べば、運用にかかる人件費や工数を減らせます。
取り扱う商品の種類や補充頻度、冷蔵設備の要否などもサービスごとに異なります。オフィスの規模や社員の勤務形態、業務フローに応じて最適なプランを選定すれば、使わない機能に費用を払うといった無駄も避けられます。初期費用や月額料金の安さだけで判断せず、トータルコストで比較することが重要です。
少人数でも導入できるかをチェック
少人数のオフィスであっても導入可能なサービスを選べば、無理のないコストで運用が継続できます。従業員数が10人未満の事業所では、販売実績が安定しにくいため、在庫のロスや補充対応のコストがネックになるケースがあります。
小規模利用向けの低価格プランを選ぶことが効果的です。最低注文数の制限や、配送エリアの条件を事前に確認しておけば、導入後に想定外の出費が発生するリスクを回避できます。
利用実態に応じた運用ルールを設定する
オフィスコンビニを効果的に活用するには、サービスを導入しただけで満足するのではなく、実際の利用実態に応じたルール設定が大切です。
たとえば、補充タイミングを毎週から隔週に変更したり、人気のない商品の注文頻度を見直したりするだけでも、月々のコストは大きく変わります。社員に利用状況のフィードバックを促す仕組みを取り入れれば、実際に求められている商品に絞ったラインナップができ、無駄な在庫や賞味期限切れによるロスを減らせます。運用ルールを一度決めたままにせず、状況に応じて柔軟に調整する姿勢が、コスト管理の精度を高めるポイントです。
まとめ
オフィスコンビニは、従業員の満足度を高めながら、職場の利便性や健康意識の向上にもつながる便利なサービスです。ただし、導入や運用にあたっては、初期費用や月額料金、商品代金といったコストが発生します。そのため、必要な機能や規模を見極めたうえで、自社の予算や人数に適したサービスを選ぶことが欠かせません。
少人数向けプランの活用や運用ルールの見直しによって、無理なくコストを抑える工夫も可能です。導入を検討する際は、価格だけでなく、継続性と活用度を見据えて判断しましょう。
TOUCH TO GOの無人決済システムは、来店者の動きと商品を自動で検知。スキャンレスでスムーズな会計が可能なうえ、リモート管理によって人件費を約半分まで削減できます。
店舗の省人化・人件費削減をご検討中の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/