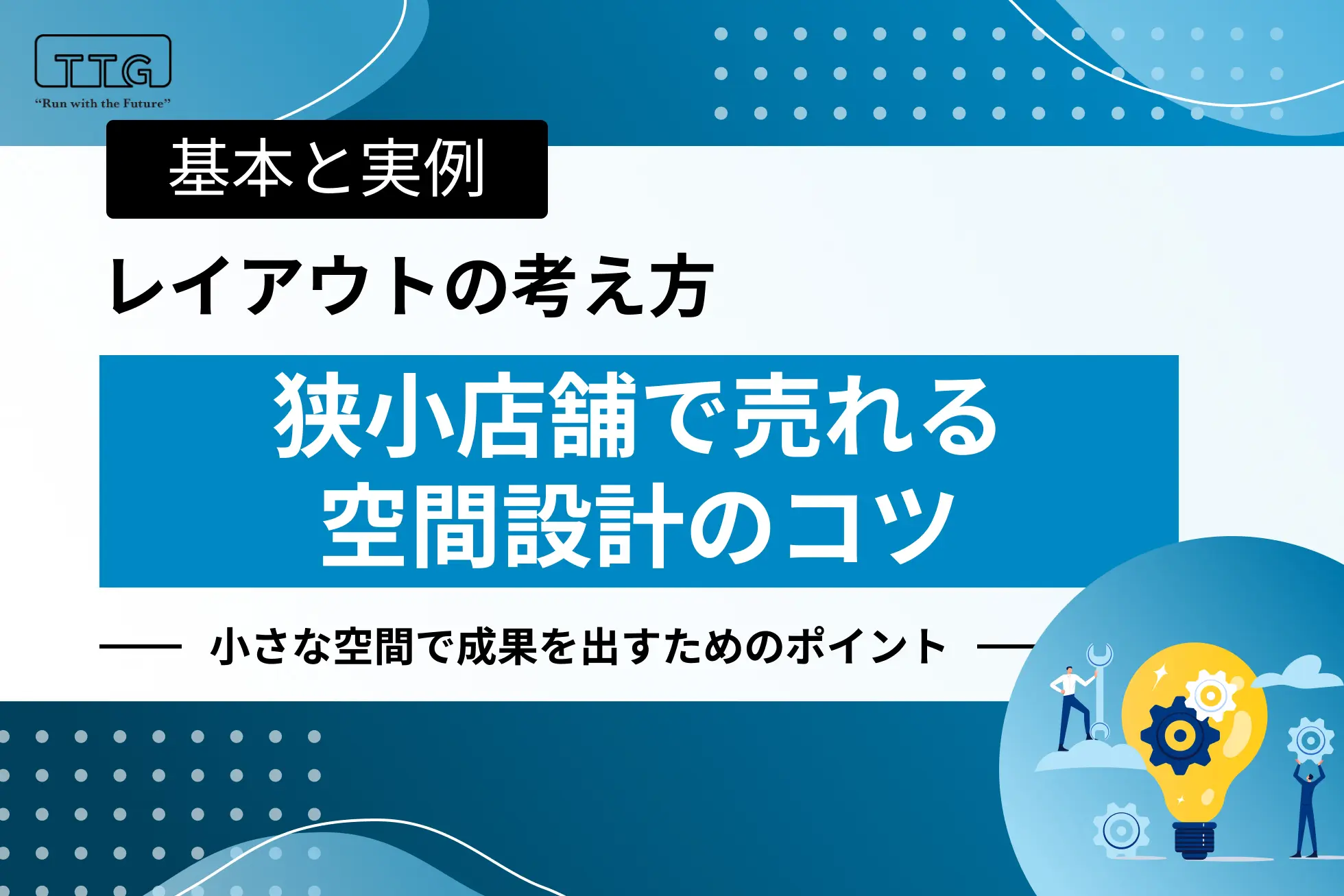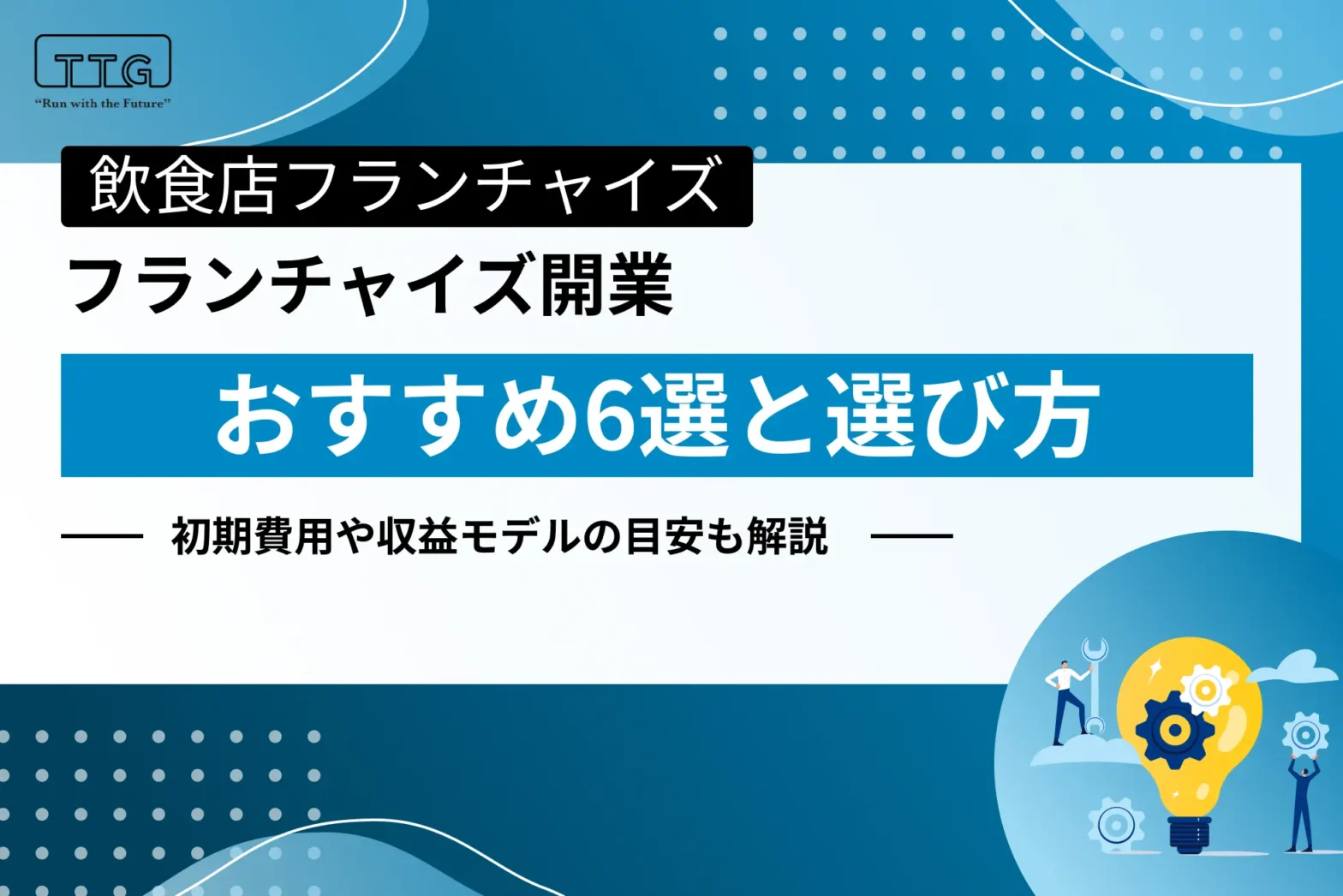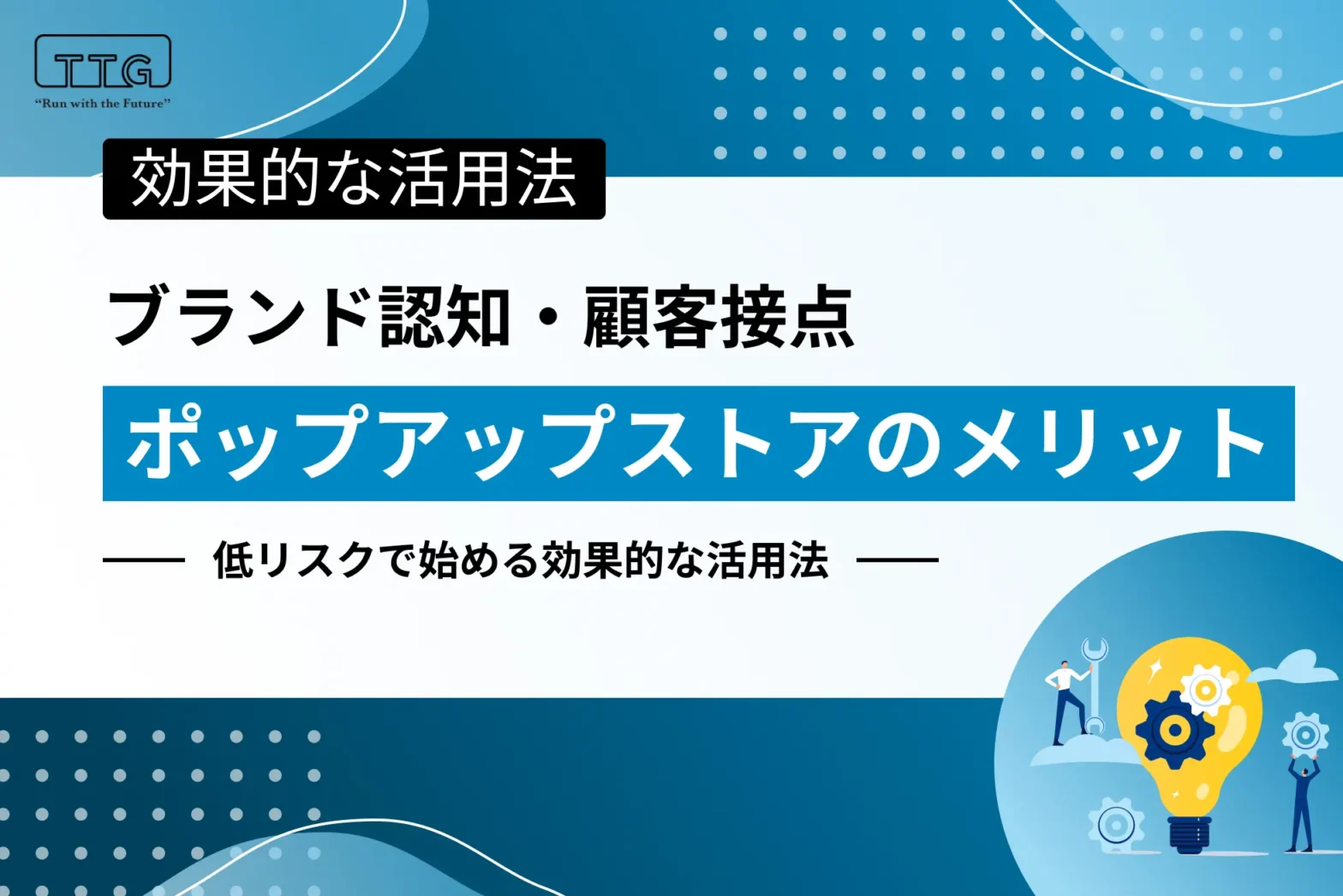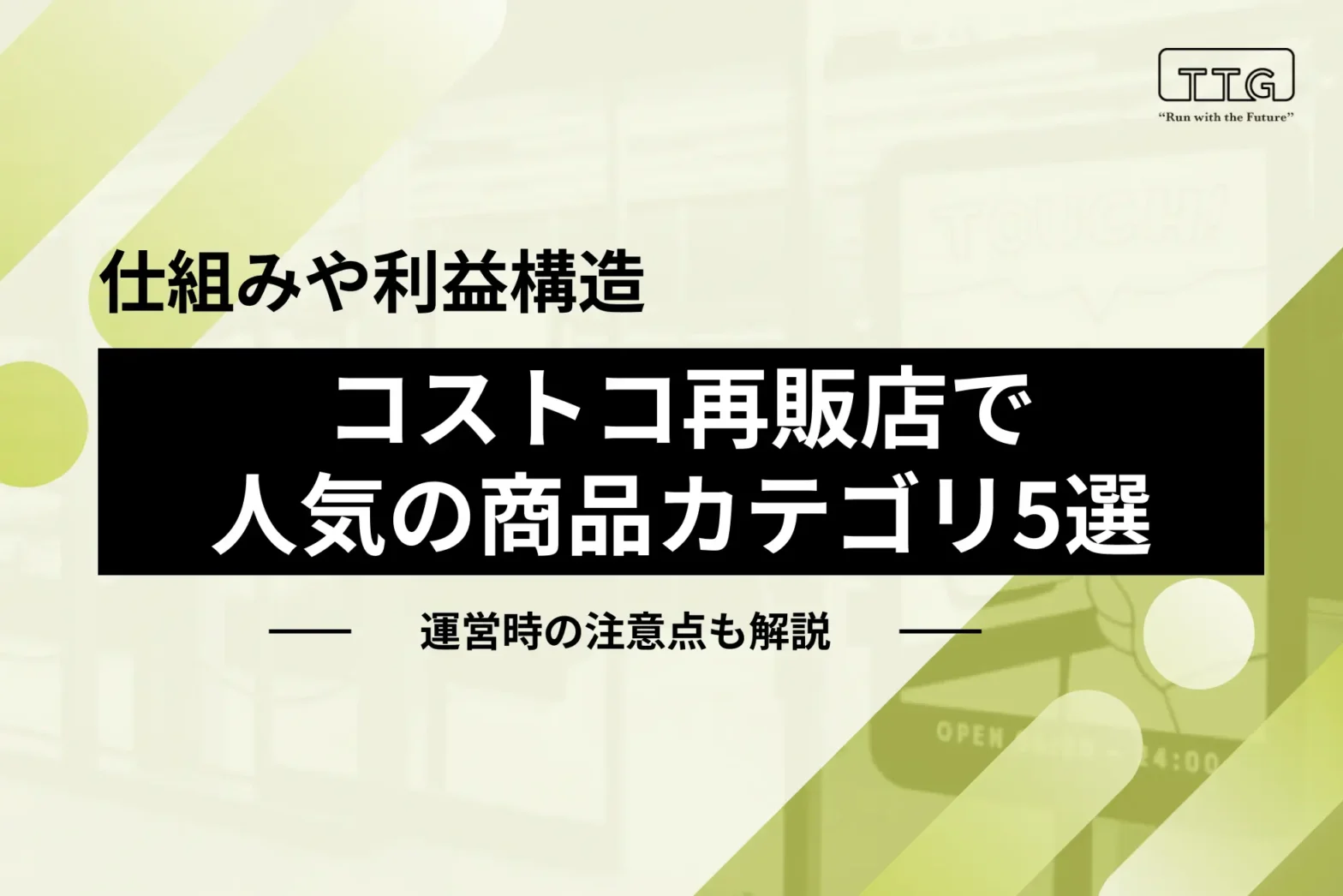Category
こんにちは。無人決済店舗システムを提供しているTOUCH TO GO 編集部です。
店舗の広さに限りがあっても、レイアウト次第で売上や来店時の印象は大きく変わります。
特に、10坪程度の狭小店舗では、限られたスペースを最大限に活かす工夫が欠かせません。
什器の配置や動線設計、内装デザインなど、ちょっとした工夫が「狭さを感じさせない、売れる店舗」につながります。
この記事では、狭小店舗に適したレイアウトの考え方や設計のコツを紹介します。
実例や業種別の視点も交えながら、限られた空間でも成果を出すためのポイントをわかりやすく解説していきます。
関連記事▼
監修者プロフィール

2019年に株式会社TOUCH TO GOを設立。無人決済店舗システムを提供し、次世代型小売の拡大に取り組んでいる。
目次
狭小店舗レイアウトの基本
狭小店舗では、限られた面積に複数の要素をバランスよく詰め込む必要があります。
そのため、なんとなくで配置を決めてしまうと使い勝手が悪くなり、顧客満足や売上に悪影響を及ぼすこともあります。
まずは、狭小店舗のレイアウト設計を始めるにあたって押さえておきたい、基本の考え方を見ていきましょう。
5W2Hで考えるコンセプト設計
店舗のレイアウトを考える前に、「誰に・何を・どのように届けるのか」を明確にしておくことが大切です。
5W2H(Who・What・When・Where・Why・How・How much)のフレームワークを使えば、狭小空間でもブレない設計軸を持つことができます。
たとえば、このフレームワークに当てはめて以下の要素を要素を整理することで、必要な什器の数やサイズ、客動線の流れも明確になります。
- どんな客層が
- どんな商品を
- どんな時間帯に
- どこで買うのか
狭小店舗では、とにかく情報を削ぎ落とし「目的に合った空間だけをつくる」ことが重要です。
レイアウト設計の基本ルール
狭小スペースのレイアウト設計で基本となるのは、「最短距離で機能がつながる配置」を意識することです。
レジ・陳列棚・ストック・作業スペースがスムーズに連動することで、限られた面積でも快適な店舗運営が可能になります。
また、陳列棚や什器が高すぎたり圧迫感を与えたりすると、店内がより狭く感じられてしまいます。
なるべく高さを抑えて視界を抜けさせる、あるいは縦の空間を上手に活用した収納設計を取り入れることがポイントです。
よくあるレイアウトの失敗例
狭小店舗でよく見られるのが、「とにかく商品を詰め込みすぎてしまう」パターンです。
商品数が多いと選択肢は増える一方で、見づらくなったり、動きにくくなったりするリスクもあります。
その結果、お客様が商品を手に取らず、そのまま離れてしまうことも。
また、スタッフと来店客の動線が交差してしまうような配置にも注意が必要です。
補充作業やレジ対応で通路がふさがってしまうと、滞在時間や購買率に影響を及ぼしかねません。
狭小店舗では「商品数を絞る」「動きやすさを確保する」ことが、売れる店舗づくりの基本です。
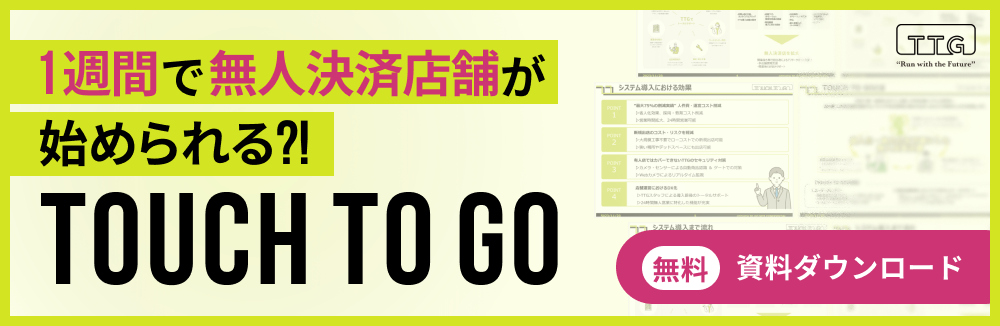
狭小店舗でも導入しやすいTOUCH TO GOの無人決済システムは、カメラとセンサーで購買行動を把握し、限られたスペースでも快適な買い物環境を実現します。
狭小店舗での無人販売をご検討中の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/
狭小空間の動線設計の考え方
店舗の使いやすさや居心地の良さは、動線設計に大きく左右されます。
スムーズな動線があるだけで、スタッフの作業効率が向上し、来店客にも快適な買い物体験を提供できます。
ここからで、狭小空間でも無理なく動ける動線設計の考え方を解説します。
スタッフと来客の動線を分ける
狭い店舗では、スタッフとお客様の動線がぶつかりやすくなります。
補充中のカゴや掃除用具が通路をふさいでしまうと、それだけでお客様にストレスを与えてしまいます。
動線設計の基本は、「スタッフ用」と「顧客用」をできるだけ分けることです。
陳列棚の裏側や壁際に作業スペースをまとめたり、補充・清掃の時間を営業ピークからずらしたりするなど、物理的に空間を分ける工夫が効果的です。
どうしても動線が交差してしまう場合は、通路幅や什器の配置を調整して、すれ違いやすいスペースを確保しましょう。
入口から奥へ自然に誘導する方法
来店客にとって動きやすい店舗とは、「入口から出口まで迷わず歩ける」空間です。
狭小店舗では特に、「入ってすぐに全体が見渡せる」レイアウトが好まれます。
そのうえで、視線の先に目を引く商品や什器を配置し、自然と店の奥へと誘導する導線をつくるのが理想です。
通路が一方通行になりやすい狭小空間では、「U字型」や「L字型」に回遊させるような設計を意識すると、滞在時間が延び、購買にもつながりやすくなります。
関連記事▼
レジ・厨房・トイレの配置バランス
飲食店をはじめとする狭小店舗では、レジや厨房、トイレといった設備の配置も動線に大きく影響します。
たとえば、レジを出入口付近に設置すれば会計の導線が短くなり、回転もスムーズになりますが、入口が混雑しやすくなる点には注意が必要です。
厨房やストック場所は、できるだけ裏側や死角にまとめ、客動線を妨げないように設計するのが理想です。
トイレについても、客席や売場から距離を取ることで、狭いながらも快適な空間に感じてもらえます。
空間を広く見せるテクニック
狭小店舗では、実際の面積以上に「広く感じさせる工夫」が売場づくりの大きな鍵となります。
色や素材の使い方、光の取り入れ方によって圧迫感を和らげ、快適で開放感のある空間を演出できます。
ここからは、視覚的な広がりを生み出すためのテクニックをご紹介します。
色使いと素材で広さを演出
色には、空間の印象を大きく左右する力があります。
たとえば、壁や天井に白やベージュなどの明るく柔らかい色を使うと、光を反射して空間を広く見せる効果が期待できます。
床材には明るめのウッド調やグレー系を選ぶことで、すっきりとした印象に仕上がります。
一方、暗い色や強い色は、アクセントとして部分的に取り入れると空間にメリハリが生まれます。
ただし、全面に濃い色を使うと圧迫感が出やすいため、バランスには注意が必要です。
什器や棚も、軽やかな素材や抜け感のあるフレームデザインを選ぶことで、視線が通りやすくなります。
照明と鏡の効果的な使い方
照明の工夫も、空間演出に大きな影響を与えます。
全体を均等に照らすだけでなく、スポットライトで商品に光を当てたり、間接照明で天井や壁をやわらかく照らしたりすることで、奥行きと立体感が生まれます。
また、鏡を活用することで、反射によって実際の空間が広く感じられることもあります。
たとえば奥の壁に大きめのミラーを設置するだけでも、店舗を広く見せる効果が期待できます。
ただし、映り込む景色や照明の位置によっては落ち着かない印象になることもあるため、設置場所は慎重に選びましょう。
ガラス素材で抜け感をつくる
ガラスやアクリルなどの透明素材を取り入れると、視線が抜けて空間に開放感が生まれます。
たとえば、間仕切りや棚の一部にガラスを使うだけでも、圧迫感を和らげる効果があります。
入口をガラス扉にすれば外からの視認性も高まり、通行人に店舗の雰囲気が伝わりやすくなります。
什器は重たい印象の木製や金属製より、軽やかな素材感のあるものを選ぶと、見た目にゆとりのある店舗づくりが可能です。
狭小店舗における什器と収納の工夫
狭小店舗においては、什器や収納を“置く”だけでなく、“活かす”発想が求められます。
限られたスペースを最大限に使うには、什器そのものが収納や動線の一部として機能するように工夫することが重要です。
ここからは、狭い店舗で役立つ什器や収納の工夫について紹介していきます。
可動式什器で柔軟なレイアウトに
レイアウトを柔軟に調整したいときに便利なのが、キャスター付きの可動式什器です。
日によって配置を変えたり、売れ筋商品の位置を調整したりすることで、限られたスペースでも臨機応変に対応できます。
イベントや季節商品の展開にも柔軟に対応でき、店舗運営の幅が広がります。
さらに、閉店後の清掃やメンテナンスもスムーズに行えるため、スタッフの負担軽減にもつながります。
コンパクトな空間では、「移動できる」「使い回せる」什器が想像以上に役立ちます。
収納付き什器でスペース活用
収納付きの什器は、表側のディスプレイと裏側の在庫管理を同時にこなせる頼れるアイテムです。
たとえば、以下のような工夫をすることで、物が散らからず、すっきりとした売場を維持できます。
- レジ台やカウンターに引き出しを備える
- 陳列棚の下部にストックを収納できるスペースを設ける
狭小店舗ではバックヤードの確保が難しいため、什器自体を収納と一体化させることで、スペースのムダを省くことが大切です。
関連記事▼
視線と通行を考えた配置のコツ
什器の配置で意識したいのが、「人の視線」と「通行のしやすさ」です。
高さのある棚を入口付近に置いてしまうと、視界が遮られ、店舗全体が暗く感じられてしまうことがあります。
入口付近には低めの什器を配置し、奥へと視線を誘導できるようにしましょう。
また、什器同士の間隔は、すれ違いや立ち止まりがスムーズにできるよう、最低でも80〜90cmを目安に確保するのが理想です。
人の動きやすさを意識することで、狭い店舗でもストレスの少ない空間づくりが可能になります。
業種別レイアウト実例
狭小店舗といっても、業種によって必要な設備や理想的な動線は異なります。
ここでは、飲食店・カフェ・小売店など、代表的な業種ごとに実際のレイアウト例や考え方を紹介します。
自分の業態に近い事例を参考にすることで、より現実的な設計イメージが描きやすくなるはずです。
7〜10坪の飲食店レイアウトのポイント
7坪〜10坪ほどの飲食店では、席数と厨房スペースのバランスが重要になります。
たとえば、カウンター中心の構成にして厨房と客席を一体化させると、コンパクトながらライブ感のある店舗をつくることができます。
動線も最小限で済むため、少人数でのオペレーションにも適しています。
また、回転率を高めるために、テーブル席ではなく立ち飲みスタイルやスツール席を取り入れている店舗も多く見られます。
狭小カフェに適したレイアウト
狭小カフェでは、「雰囲気づくり」と「回転率の両立」がカギとなります。
2~3名用のコンパクトなテーブルを間隔広めに配置し、窓際を活かした席やスタンディングスペースを設けることで、開放感を演出できます。
また、什器を極力減らし、壁面収納や縦型ディスプレイを活用することで、ゆったりとした印象を与えられます。
さらに、レジ横にテイクアウト用の棚を設けるなど、滞在と持ち帰りのどちらにも対応できる工夫が成功のポイントになります。
小売店に向く基本レイアウト
小売店では、回遊性と視認性が売上に大きく影響します。
狭い店内でも、通路を一方通行にする、またはU字型やL字型に配置することで、お客様が自然に商品を見て回れる流れをつくることができます。
入口から目につきやすい位置には、季節商品や新商品を配置しましょう。
一方で、定番商品はあえて奥に配置し、動線の途中でしっかり見てもらえるように計画することで、店内全体の滞在時間が伸び、購買率アップにもつながります。
また、在庫管理のスペースが限られるため、売場の什器にストック機能を持たせたり、バックヤードを兼ねた壁面収納を取り入れたりすることで、オペレーション効率を保てます。
まとめ
狭小店舗はスペースに制限があるからこそ、レイアウトの工夫が売上や印象に大きく影響します。
コンセプトに基づいた設計や什器・収納の活用など、複数の要素をバランスよく組み合わせることで、小さな店舗でも快適で魅力ある空間をつくれます。
業種や業態によって最適なレイアウトは異なりますが、共通して大切なのは「限られた面積をどう活かすか」という視点です。
今回紹介した考え方や実例を参考に、狭小でも成果の出る店舗づくりに取り組んでみましょう。
関連記事▼
狭小店舗でも導入しやすいTOUCH TO GOの無人決済システムは、カメラとセンサーで購買行動を把握し、限られたスペースでも快適な買い物環境を実現します。
狭小店舗での無人販売をご検討中の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/