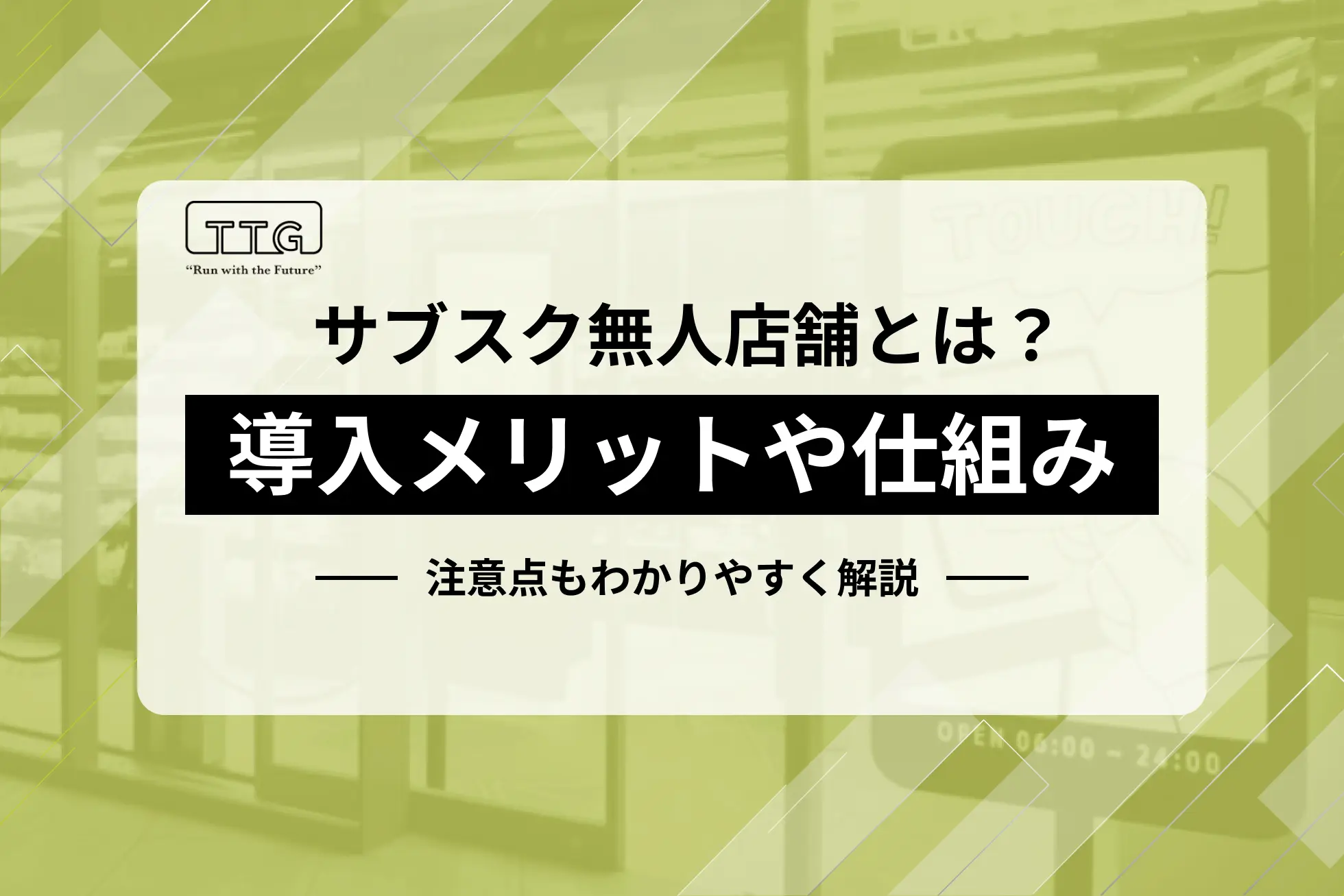Category
こんにちは。無人決済店舗システムを提供しているTOUCH TO GO 編集部です。
無人店舗の導入を検討する事業者のあいだで、「サブスク無人店舗」という新しい導入スタイルが注目されています。
サブスクの無人店舗は、セルフレジや店舗システムを月額課金で利用できるサービスで、初期投資を抑えながら低リスクで店舗を無人化できるのが特徴です。
本記事では、サブスク無人店舗の概要や、導入メリット、注意点を紹介します。
導入の流れも解説しているので、低コスト・低リスクで無人店舗を始めたい方は、ぜひ参考にしてください。
関連記事▼
監修者プロフィール

2019年に株式会社TOUCH TO GOを設立。無人決済店舗システムを提供し、次世代型小売の拡大に取り組んでいる。
目次
サブスク無人店舗とは?
「サブスク無人店舗」とは、無人店舗に必要な機器やシステムを月額制(サブスクリプション)で導入・運用できるサービスのことです。
従来、無人店舗を始める場合、以下のようなシステムをすべて最初に揃える必要があり、初期費用だけで数百万円にのぼることもありました。
- セルフレジ
- 入退店管理システム
- 監視カメラ
- キャッシュレス決済端末
それに対し、サブスク型では、必要な設備・システムを月額定額で利用できるため、導入のハードルがぐっと下がります。
特に、短期の試験運用や小規模な出店を検討している事業者にとっては、非常に相性の良い選択肢といえるでしょう。
提供される内容はサービスによって異なりますが、一般的には以下のような機能が提供されています。
- セルフレジ/無人レジシステム
- 入退店の認証管理(ICカード、QRコードなど)
- 店内の監視カメラと遠隔モニタリング
- 売上管理・在庫管理などのクラウド連携
- キャッシュレス決済端末
上記のシステムをすべてサブスク形式で利用できるため、「できるだけ初期費用を抑えて無人店舗を試したい」というニーズに最適なサービスとなっています。
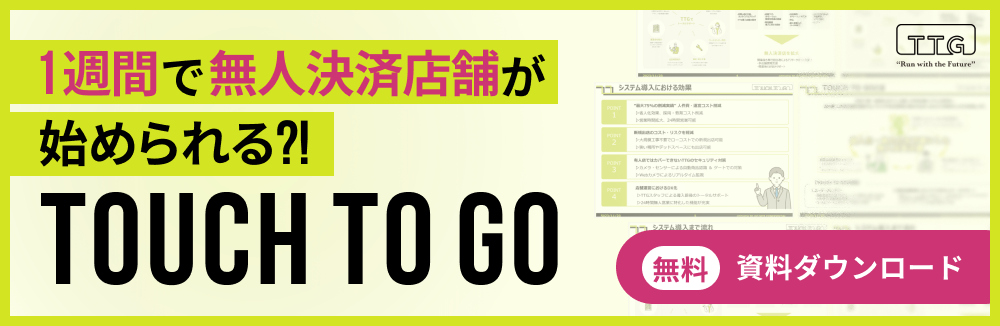
TOUCH TO GO の 無人決済店舗システムは、カメラで人物をトラッキングし、どの棚のどの商品が何個お客様の手に取られたかをセンサーで感知します。
低リスク・低コストで無人店舗を始めたい方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/
なぜ今サブスク無人店舗が注目されているのか?
サブスク型の無人店舗が注目を集めている背景には、いくつかの社会的な変化があります。
中でも特に大きな要因は、「人手不足の深刻化」と「初期費用の高さに対するハードル」です。
近年、飲食業や小売業では慢性的な人手不足が続いており、「人が確保できないなら、無人化で補いたい」と考える事業者が増えています。
しかし、無人店舗の導入には通常多額の設備投資が必要になるため、そう簡単に踏み切れるものではありませんでした。
こうした課題を解消する画期的な方法が、サブスク型の無人店舗です。
店舗を運営するためのシステムが月額制であれば、高額な機器を一括購入せずに済むため、開店までのスピードも速くなります。
また、保守やサポート、アップデート対応が含まれているサブスク無人店舗であれば、専門知識がない事業者でも安心して導入できます。
無人店舗を短期的に試してみたい人や、将来的に多店舗展開を見据えている企業にとって、「まずサブスクで始めてみる」という選択肢は、今の時代に合った導入スタイルだといえるでしょう。
サブスク無人店舗のメリット
ここからは、サブスク無人店舗の主なメリットを3つ紹介します。
初期コストを抑えられる
通常、無人店舗の導入には数百万円単位の費用がかかることもあります。というのも、無人店舗を運営するには、さまざまな設備が必要になるからです。
一方、サブスク型であれば、店舗運営に必要な機器やシステムを月額定額で利用できるため、大きな資金を用意せずに導入が可能になります。
初期投資を抑えられることは、資金に限りがある小規模事業者や、新規事業をスタートする際のリスク軽減にもつながります。
スピーディな導入が可能
サブスク型の無人店舗には、あらかじめパッケージ化されたサービスもあるため、導入までのスピードも早いのが特徴です。
例えば、TTG-SENSE MICROのようなパッケージタイプの無人店舗なら、一からシステムを構築する必要がなく、最短3ヶ月で運用を開始できます。
スピーディに導入できるサブスク型無人店舗は、ポップアップ店舗や短期の実証実験などにも向いており、柔軟な店舗展開が可能になります。
メンテナンスやサポートが含まれていることもある
サブスク形式で提供される無人店舗システムには、以下のようなサービスが月額料金に含まれていることもあります。
- システム保守
- 障害時のサポート
- ソフトウェアのアップデート
ITや無人店舗の知識がないオーナーでも安心して運営ができるほか、トラブル発生時も専門のサポート体制が整っている点は大きなメリットとなります。
サブスク無人店舗の導入に向いている事業者の例
サブスク無人店舗の仕組みは、すべての業界に向いているわけではありません。ただし、以下のような事業者にとっては、非常に相性の良い導入スタイルといえます。
ここでは、サブスク無人店舗が向いている事業者の例をご紹介します。
新規事業として無人店舗を始めたい人
無人店舗は今後の成長が見込まれる分野のひとつですが、いきなり大きな初期投資をかけるのはリスクがともないます。
しかし、サブスク型であれば月額制で導入できるため、初めて無人店舗を試してみたい人にとって安心感があります。
「どの立地でどの程度売上が立つのか知りたい」「業務オペレーションに無理がないか検証したい」といった段階でも導入しやすく、新規事業のテストとして最適な方法と言えるでしょう。
小規模・個人事業の小売業者
限られた資金で事業を運営している小規模事業者にとって、設備投資は慎重にならざるを得ない部分です。
サブスク無人店舗であれば、大型機器の購入や複雑なシステム構築は不要で、導入時のハードルを大幅に下げられます。
たとえば、「農産物の直売所」や「地元のお菓子店」、「雑貨店」なども、無人販売を通じて営業時間を拡大したり、人手をかけずに販路を増やすことが可能になります。
ショールームや店舗の省人化を進めたい企業
すでにリアル店舗を展開している企業にとっても、サブスク型無人店舗は省人化・効率化の手段として有効です。
たとえば、営業時間外でも商品を見てもらえるショールームや、既存店舗の一部を無人対応に切り替える運用も可能です。
サブスク無人店舗の注意点
サブスク型で無人店舗を導入するスタイルは手軽にスタートできる反面、いくつか注意しておきたいポイントもあります。
ここでは、特に気をつけたいポイントを3つ紹介します。
月額費用がかかる
サブスク導入の最大の特徴は、月額制で設備やシステムを利用できる点です。
しかし、当然ながら毎月固定費が発生します。店舗の売上が安定しないうちは、この固定費が負担に感じることもあるかもしれません。
そのため、特に初期段階では、収益と支出のバランスをしっかり見極めておく必要があります。
契約内容によっては最低利用期間や解約金が発生する場合もあるため、事前に月額費用の内訳や契約条件を確認しておきましょう。
カスタマイズに制限がある
サブスク型の無人店舗サービスでは、あらかじめパッケージ化された設備や運用システムを利用するケースが多く、自由にカスタマイズできる範囲が限られていることがあります。
たとえば、内装のデザイン変更や機能追加などを希望しても、提供元の仕様に依存するため、自分の思い通りに反映できない場合もあります。
独自性を出したいブランド運営や、特殊な商品の取り扱いを考えている場合は、慎重に検討する必要があります。
運用ノウハウやサポート体制の確認が必要
無人店舗の運営には、通常の有人店舗とは異なるノウハウが求められます。事前に、以下のような運営体制を把握しておく必要があります。
- 商品補充
- トラブル時の対応
- 遠隔管理の仕組み
なお、導入前には「どこまでサポートしてくれるのか」「マニュアルやトレーニングはあるか」「トラブル時の連絡手段は整っているか」などを確認しておくことが大切です。
サブスク無人店舗を導入する流れ
サブスク無人店舗を始めるには、機器やサービスを申し込むだけで完了というわけではありません。
実際には「何を売るのか」「どこで営業するのか」といった事業設計や、設置に向けた準備も必要です。
ここでは、一般的な導入の流れを順番に解説します。
1. 導入目的・必要なシステムの決定
まずは「なぜ無人店舗を導入したいのか?」を明確にすることが大切です。たとえば、
- 人手不足の解消
- 販売機会の拡大
- 新しい販売チャネルの構築
など、目的によって必要な設備やサポートも変わってきます。また、食品販売・物販・レンタルなど業態によっても適したシステムは異なるため、自社に合うプランを検討しましょう。
2. 事業者の選定
無人店舗のサブスクサービスを提供する企業は複数あり、それぞれ取り扱う機器やサポート内容が異なります。
複数の事業者に問い合わせを行い、以下のポイントを比較検討しましょう。
- 月額費用
- 導入までの期間
- 対応エリア
- 運用支援の有無
特に、導入実績のある業者や、販売したい商品に精通した事業者を選ぶとスムーズです。
3. 設置場所の確保・契約
設置予定地が自社敷地内でない場合は、オーナーとの賃貸契約や電源の使用許可が必要になります。
コンセントの容量や、インターネット回線の有無も事前に確認しておきましょう。とくに冷蔵・冷凍設備を使用する場合は、電源環境や温度管理を徹底しましょう。
4. 設備の搬入・設置・テスト
機器の搬入・設置後には、実際に商品を並べてテスト販売を行うのが一般的です。
操作性や来客動線、決済トラブルの有無などを確認し、必要に応じてレイアウトや表示を調整します。
また、セキュリティカメラやリモート監視システムの稼働確認も忘れずに実施しましょう。
5. 運用開始・定期的な見直し
無人店舗は“設置して終わり”ではなく、稼働後の運用がとても重要です。
販売データを確認しながら商品構成や価格の見直し、在庫管理体制を調整し、効率的で継続可能な運営を目指しましょう。
また、清掃や補充、故障時の対応ルールもあらかじめ明確にしておくことが、スムーズな継続につながります。
まとめ
サブスク無人店舗は、初期費用を抑えて無人店舗を導入できる新しい選択肢として、近年注目が高まっています。
特に「小規模から始めたい」「まずは試してみたい」という事業者にとって、月額制で必要な機器やシステムを使えるこの仕組みは、導入のハードルを下げてくれます。
一方で、毎月の固定費やカスタマイズの制限など、あらかじめ知っておくべきポイントもあります。
導入を検討する際は、事業の目的や販売する商品、設置場所との相性などを踏まえた上で、最適なサービスを選ぶことが大切です。
無人店舗ビジネスに向いている業種や、ビジネスモデル例を以下の記事で紹介しています。あわせてご覧ください。
TOUCH TO GO の 無人決済店舗システムは、カメラで人物をトラッキングし、どの棚のどの商品が何個お客様の手に取られたかをセンサーで感知します。
低リスク・低コストで無人店舗を始めたい方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/