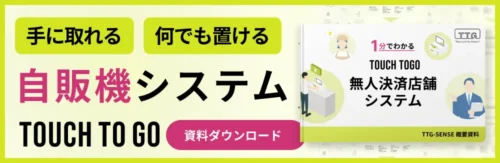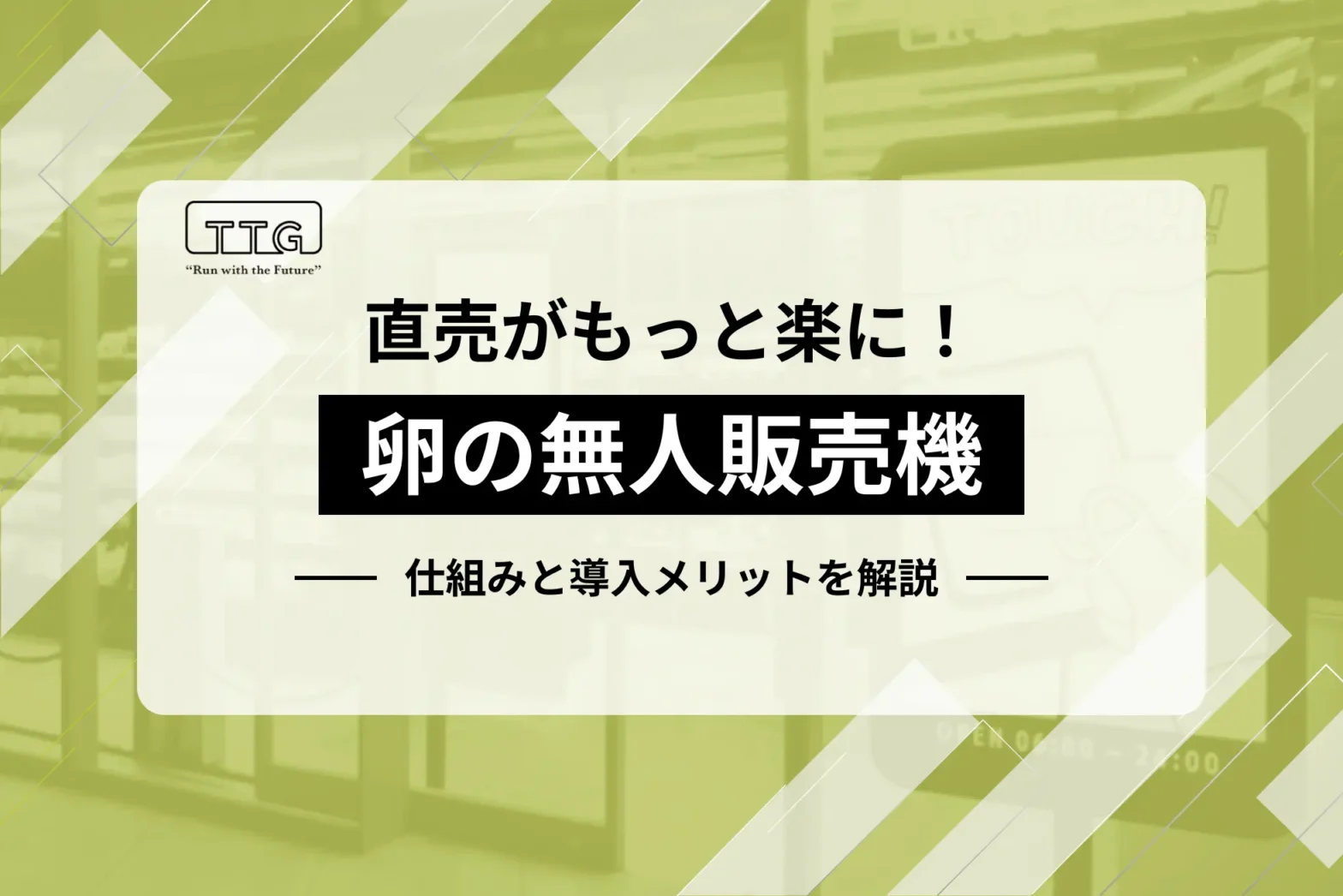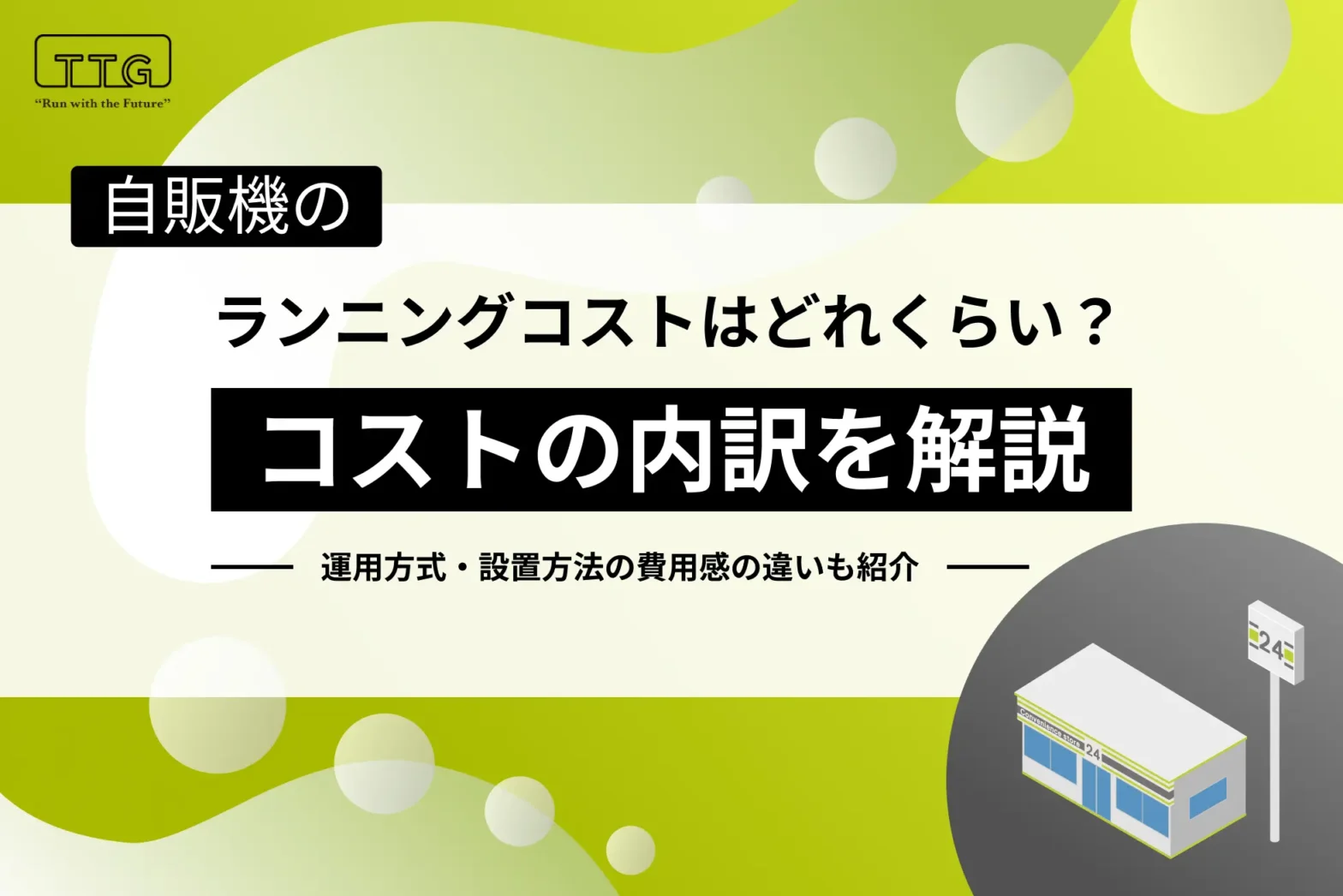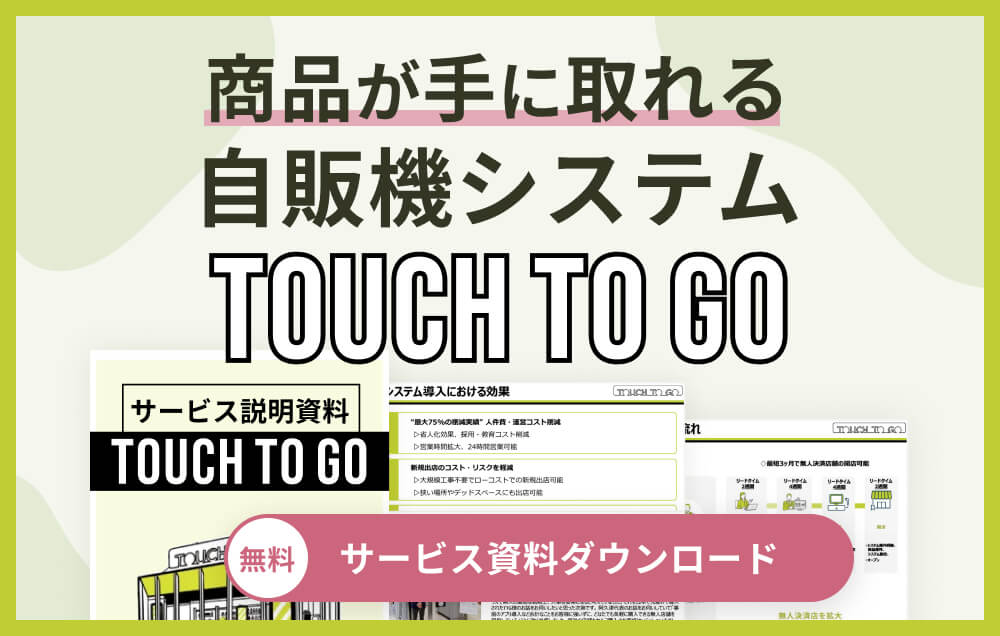Category
自販機システムの導入なら、無人決済店舗システムTOUCH TO GOにお任せください!プロダクト概要資料を下記のフォームよりダウンロードできます。
こんにちは。無人決済店舗システムを提供しているTOUCH TO GO 編集部です。
最近、街中やサービスエリアで見かけることが増えた「食べ物の自動販売機」。
食べ物系自販機は比較的少ない初期投資で始められる、新しい販売手法として注目されています。
とはいえ、設置には費用やスペース、メンテナンスの手間なども関わるため、「本当に利益が出るのか?」「どんな商品が売れるのか?」といった不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
今回の記事では、食べ物の自販機の概要や人気商品例、設置方法を紹介します。
屋外に設置する際のポイントも解説しているので、食べ物の自販機の設置を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
関連記事▼
監修者プロフィール

2019年に株式会社TOUCH TO GOを設立。無人決済店舗システムを提供し、次世代型小売の拡大に取り組んでいる。
目次
食べ物の自動販売機とは?
最初に、食べ物系自販機の特徴や、どんな商品が販売されているのかについて見ていきましょう。
一般的な飲料自販機との違い
食べ物の自販機とは、その名のとおり「飲料以外の食品を販売する自動販売機」です。
近年では、ラーメンやスープ、おにぎり、冷凍弁当、パン、スナックなど、軽食や冷凍食品を中心に多彩な商品を取り扱う機種が増えています。
一般的な飲料自販機との大きな違いは、温度管理や保存方法の幅広さにあります。
食べ物系の自販機では、冷蔵・冷凍・常温など複数の温度帯に対応していたり、電子レンジ機能を備えてその場で温められたりと、機種によっては特殊な構造となっています。
販売されている主な商品ジャンル
現在流通している食べ物自販機の多くは、「冷凍食品」や「レトルト食品」など賞味期限が比較的長いものを中心に構成されています。 代表的なジャンルは以下のようなものです。
- ラーメン、餃子、カレーなどの冷凍調理品
- スープ、シチュー、おでんなどのレトルト系
- おにぎり、パン、ホットスナックなどの軽食
- 地元の特産品やご当地グルメ
- アイスクリームや冷凍スイーツ
近年では、手作りパンなどの個人店が参入しやすい“個性重視”の商品展開も増えており、単なる販売機ではなく「店舗の代わり」としての活用も進んでいます。
設置する地域やターゲットに合わせて商品を選べば、自販機でもファンをつくることが可能です。
「TOUCH TO GO」のプロダクトは、自販機を設置するように、工事不要でコンビニ区画を導入できます。
店舗の省人化・人件費削減をご検討中の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/
なぜ今「食べ物系自販機」が注目されているのか?
近年、飲料ではなく食べ物を扱う自動販売機が各地で急増しています。
これは単なる流行ではなく、「社会の変化」や「消費者のニーズに合わせた販売形態」として注目されていることが背景にあります。
ここでは、なぜ今、食べ物系の自販機が支持を集めているのかを詳しく見ていきましょう。
コロナ以降の非接触ニーズ
新型コロナウイルスの影響により、非接触・非対面での買い物が一気に広まりました。
その流れのなかで、人と接することなく商品を購入できる自販機が再評価されており、特に食品系の自販機は「手軽さ」と「安心感」を兼ね備えた販売方法として注目されています。
飲食店の時短営業や休業が相次いだ時期には、自販機による24時間営業の利便性が改めて認識されました。
営業時間を気にせず購入できる便利さ
食べ物の自販機は、24時間いつでも利用できるのが大きな魅力です。
早朝や深夜など、飲食店が閉まっている時間帯でも軽食を手に入れられるため、仕事や生活スタイルが不規則な人にも重宝されます。
特にコンビニやスーパーが近くにないエリアでは、ちょっとした空腹を満たせる手段として、住民や利用者の強い味方になっています。
「時間を気にせずに買える安心感」は、食べ物の自販機が支持される理由のひとつといえるでしょう。
SNS映えや話題性による集客効果
ユニークな食べ物を扱う自販機は、それ自体がちょっとした話題になります。
たとえばラーメンの冷凍自販機や、ご当地グルメが買える自販機、スイーツ専門の自販機など、見た目にも珍しく、つい写真を撮って投稿したくなるようなデザインや商品が増えています。
こうした自販機は、SNSでの拡散や口コミにつながりやすく、自然と集客につながるのも魅力のひとつです。
「この自販機でこんなものが買えるらしい」といった情報が広まることで、新しい顧客を呼び込むきっかけにもなります。
飲食店や施設の一角に設置することで、既存のサービスにプラスアルファの話題性を加えることも可能です。
食べ物の自販機で売られている人気商品
食べ物の自販機と一口にいっても、販売されている商品はさまざまです。ここでは、食べ物系自販機で人気の商品例を紹介します。
おにぎり・パン・冷凍食品などの軽食系
忙しい朝や仕事の合間など、手軽に食べられる商品はやはり根強い人気があります。
コンビニで買うような感覚で利用できるため、気軽に立ち寄れるオフィス街や駅周辺などで特に売れやすい傾向があります。
また、電子レンジで温めるだけの簡単な冷凍食品などは、保存が利くため、自販機との相性が良い商品といえます。
ラーメン・スープ・グルメ系の冷凍商品
最近では、有名ラーメン店やご当地グルメとコラボした商品も多く登場しています。
本格的な味を家庭で楽しめるという手軽さが好まれ、週末や夜の「ちょっと贅沢したい時間」に利用されることもあります。
特にラーメンやスープは、冷凍のまま持ち帰って調理するスタイルが主流で、幅広い年代から支持を集めています。
地域の特産品や限定商品
観光地や高速道路のサービスエリアでは、その地域ならではの名物商品を扱う自販機も増えています。
たとえばご当地バーガー、郷土料理をベースにしたレトルト食品、地元のベーカリーが作るパンなど、限定性のある商品は話題性もあり、観光客からの需要も見込めます。
地元の小さな店舗が自販機を通じて販路を広げるケースも多く、地域活性化の一環として導入するのもよいでしょう。
以下の記事で、フード自販機(食べ物自販機)の人気ジャンルを紹介しています。あわせてご覧ください。
関連記事>>フード自販機の人気ジャンルや費用・補助金について解説!
珍しい・話題の食べ物自販機を紹介
食べ物の自動販売機は、単なる販売設備ではなく「観光スポット」や「話題づくりのコンテンツ」としての役割も果たしています。
ここからは、話題性・独自性の高い自販機の事例を2つのタイプに分けて紹介します。
レトロ自販機が人気を集める理由
日本では、昭和時代の雰囲気をそのまま残した“レトロ自販機”が再び注目されています。
1970〜80年代に設置された自販機が今も現役で稼働しており、うどん・そば・トーストサンドなどを数分で提供する懐かしいタイプが代表例です。
こうした自販機は、旧ドライブインやサービスエリアを中心に全国で稼働しており、「昭和レトロを体験できるスポット」として若い世代や観光客から人気を集めています。
自販機そのものに歴史的価値があることから、写真を撮ってSNSに投稿する人も多く、地域の観光資源としても注目されています。
関連記事▼
SNSで話題の“変わり種”自販機
近年、「こんな食べ物が自販機で買えるの?」と驚くような“変わり種自販機”も急増しています。
ラインナップは、冷凍ステーキ・高級寿司・クラフトビールなど多彩で、「自販機で買えるとは思えない商品」がSNSを中心に話題を集めています。
また、ショートケーキ缶やティラミスなどのスイーツ特化型自販機も若年層に人気です。
このような自販機は「珍しさ」だけでなく、販促ツールとして活用されるケースも見られます。
実店舗では扱いにくい限定商品や、非対面で購入できる仕組みとして注目されており、新しい販売手法の一つとなっています。
関連記事▼
- ケーキの自動販売機を導入するには?費用・メリット・補助金や設置の流れも解説!
- パン自販機の導入は難しくない?費用・商品例・補助金をわかりやすく解説
- スープの自販機とは?導入メリットや種類、設置の流れをわかりやすく解説
食べ物自販機を設置するメリット
食べ物の自動販売機は、少ない人員で運営できるうえ、営業時間に縛られずに商品を販売できる点が大きな魅力です。
飲食店や小売店が導入するケースも増えており、コスト削減や販路拡大、さらには話題づくりの手段としても注目されています。
ここからは、食べ物自販機を設置することで得られる具体的なメリットを紹介します。
人件費削減につながる
食べ物自販機は、販売スタッフを常駐させる必要がないため、人件費を抑えられる点が大きなメリットです。
商品の補充や清掃など、定期的なメンテナンスは必要ですが、日々の販売対応に人手を割く必要がありません。
特に人材確保が難しい飲食業や、深夜帯の販売を避けたい小規模店舗にとって、効率的な運営方法といえます。
24時間販売が可能になる
自販機を設置すれば、営業時間に関係なく商品を販売できます。
たとえば、夜間や早朝に利用したい人、仕事帰りに立ち寄る人など、従来の営業時間外のニーズにも対応可能です。
スタッフを増やさずに販売時間を拡大できるため、売上のチャンスを広げることができます。
新たな販路をつくれる
自販機は、既存店舗とは別の場所で販売を行うことができるため、新しい販路の開拓にも役立ちます。
たとえば、オフィス街や駅前、商業施設などに設置すれば、これまで店舗に来店しなかった層にも商品を届けられます。
実店舗の補完的な役割として、自社商品の知名度を高めるきっかけにもなります。
話題性によるPR効果が期待できる
珍しい商品や限定メニューを自販機で販売することで、SNSなどで話題になるケースもあります。
とくに「無人販売」「非接触購入」などのキーワードは、時代のニーズとも重なり、注目を集めやすい傾向があります。
販売実績だけでなく、店舗やブランドの認知拡大につながる点も、自販機導入の魅力といえます。
食べ物自販機を設置する際の注意点
食べ物の自動販売機を導入する際には、メリットだけでなく運用上の注意点も把握しておくことが大切です。
ここでは、設置前に知っておきたい代表的な注意点を解説します。
保存・衛生管理を徹底する
食品を販売する自販機では、保存温度の管理が最も重要です。冷凍食品であれば−18℃以下、冷蔵品なら10℃以下など、商品に応じた温度帯を維持する必要があります。
設定温度を守らないと、食品の品質が劣化したり、安全性に問題が生じるおそれがあります。
また、定期的な清掃も欠かせません。自販機の庫内や取り出し口は人の手が触れやすく、衛生環境を保つためにはアルコール消毒などの清掃を習慣化することが大切です。
衛生管理の徹底が、信頼性の高い販売運営につながります。
食品衛生法などの届出・許可を確認する
食べ物の自動販売機を運営する際は、販売する商品の種類や保存方法、加工内容によって、食品衛生法に基づく営業許可や届出が必要となる場合があります。
たとえば、店舗で調理した食品や、加熱機能付き自販機で提供する商品などは、自治体によって「営業許可」が求められるケースがあります。
一方で、冷凍食品や常温で長期保存できる食品を扱う自販機の場合は、届出が不要とされることもあります。
判断は自治体や販売形態によって異なるため、設置前に所轄の保健所へ相談し、必要な手続きを確認しておくことが重要です。
法令を順守することで、安心して継続的に運営できる環境を整えられます。
トラブルを防ぐためのメンテナンスを行う
自販機を長く安定して運用するためには、定期的なメンテナンスが欠かせません。
販売機の故障や商品の詰まり、電源トラブルなどが発生すると、売上機会の損失や顧客からの苦情につながります。
機器の状態を定期的にチェックし、冷却装置やセンサーの動作確認を行うことが重要です。
また、異常があった場合に迅速に対応できるよう、メーカーや販売代理店と保守契約を結んでおくと安心です。
食べ物の自販機を設置する方法
食べ物の自販機を運営してみたいと思っても、「何から始めればいいのか分からない」という方は多いのではないでしょうか。
ここでは、自販機の設置方法や流れ、必要な設備についてわかりやすく解説します。
1. メーカーや専門業者に「委託」する
もっとも手軽に始められるのが、自販機メーカーや代理店に設置・運営を委託する方法です。
自販機の設置・補充・管理をすべて業者側が担当するため、オーナーはスペースと電源を提供するだけでOKというケースが多く、ほとんど手間がかかりません。
【メリット】
- 初期投資がほとんど不要(業者側が機器を用意)
- 商品補充やトラブル対応も任せられる
- 売上の一部が収入になる(歩合制)
【注意点】
- 売る商品や価格は業者により決定される
- 自由度は低め(オリジナル商品などは扱えない)
2. 自販機を「リースまたはレンタル」して自分で運営する
自販機本体をレンタル・リースし、自分で商品の仕入れや補充を行う方法です。
自社商品を販売したい事業者や、小規模飲食店などに人気のスタイルで、自由度の高い運用が可能になります。
【メリット】
- 販売する商品を自由に決められる
- 利益率が高く、工夫次第で収益も大きくなる
- 自社ブランド商品の販売にも使える
【注意点】
- 仕入れ、在庫管理、補充などの手間がかかる
- 食品衛生法や保健所への届け出が必要な場合がある
- 冷凍・冷蔵機能付きは初期費用が高めになりやすい
3. 自販機を「購入」して完全に自営で運用する
完全に自前で運営したい場合は、自販機本体を購入する方法もあります。初期費用はかかりますが、長期的に見ると運用コストは抑えやすく、収益もすべて自分のものになります。
【メリット】
- 100%自由な運営が可能
- 設置期間が長いほどコストパフォーマンスが良い
- 中古自販機を利用すれば初期投資を抑えられる
【注意点】
- メンテナンス・修理対応を自分で管理する必要がある
- トラブル発生時の対応体制も自分で構築しなければならない
「TOUCH TO GO」のプロダクトは、自販機を設置するように、工事不要でコンビニ区画を導入できます。
店舗の省人化・人件費削減をご検討中の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/
食べ物自販機を設置する手順と費用
食べ物の自動販売機を導入するには、設置場所の選定から機器の手配、電源確保まで、いくつかのステップを踏む必要があります。
初期費用や運用コストも販売形態によって異なるため、あらかじめ全体の流れと費用感を把握しておくことが重要です。
ここでは、設置の基本的な手順と費用の目安を解説します。
導入までの流れ
設置場所を決める
人通りや滞在時間が長いエリアほど販売数が期待できます。駅前、病院、オフィス街などが代表的な設置候補地です。屋外に設置する場合は、防水・防塵性能を備えた屋外対応機を選びましょう。
販売する商品を選ぶ
冷凍食品や軽食など、ターゲット層や立地に合った商品選びが重要です。商品を自社で仕入れる場合は、販売許可や保存管理などの条件を確認しておく必要があります。
機器を選定する
販売したい商品の温度帯やサイズに合わせて機種を選びます。最新モデルではキャッシュレス決済や遠隔在庫管理にも対応しており、運営効率を高めることができます。
電源・設置工事を行う
冷凍・冷蔵機能付きの自販機には、一般的に100Vまたは200Vの電源が必要です。屋外設置では、電気工事業者による専用電源の引き込みが求められる場合もあります。
販売を開始する
商品の補充、清掃、売上管理などの運営体制を整えたうえで販売をスタートします。導入後は販売データをもとに商品の入れ替えや価格調整を行うことで、収益性を高めやすくなります。
食品自販機の設置費用と運営コストの目安
設置費用は運営方法によって大きく異なります。メーカーに設置を委託する場合は本体費用が不要なケースもありますが、自社で運営する場合は機器購入や電気工事費が必要です。
本体価格は新品で100〜200万円程度、中古で20〜70万円前後が目安です。設置工事費は屋外で5〜15万円ほど、電気代は飲料自販機よりも高くなりやすく、冷凍自販機であれば月8,500円前後となります。
なお、これらの数値はいずれも目安であり、実際の費用や利益率は機種や設置条件によって変動します。
関連記事▼
食べ物の自販機を屋外に設置する際のポイント
食べ物の自販機を運用するうえで、「屋外に設置できるかどうか」は多くの方が気になるポイントではないでしょうか。
もちろん屋外設置は可能ですが、飲料の自販機とは違って、食品を扱う自販機ならではの注意点があります。
ここでは、屋外設置の際に確認しておきたいポイントを紹介します。
屋外用の食べ物自販機を選ぶ
食べ物の自販機を屋外に設置する場合は、防水や耐熱・耐寒性能を備えた「屋外対応型」の自販機を選ぶ必要があります。
特に冷凍・冷蔵商品を扱う場合、温度管理機能の安定性が売上や衛生面に直結します。
最近の機種はキャッシュレス決済や遠隔管理に対応しているものも多く、運営の手間も軽減できます。
設置環境や扱う商品の特性に合わせて、専門業者に相談しながら機種を選びましょう。
雨風や直射日光を防ぐ工夫が必要
屋外用の自販機には防水性・耐候性が備わっていますが、食べ物を扱う場合は温度管理がより繊細になるため、設置場所にはひと工夫が必要です。
そのため、できるだけ軒下や屋根のある場所、または日差しが直接当たらない方角への設置を検討しましょう。
特に夏場は機械の内部が高温になりやすく、商品への影響や故障の原因になりやすいため、直射日光を避けることが大切です。
また、強風や台風などの災害時に備えて、転倒防止措置も検討しておきましょう。
電源の確保は必須条件
冷凍・冷蔵機能を備えた食べ物の自販機は、常に安定した電力が必要になります。
一般的には100Vまたは200Vの電源を使用しますが、屋外にコンセントがない場合は電気工事が必要になることもあります。
設置を検討する際には、事前に電源の有無と設置可能な容量を確認しておきましょう。
また、電力の容量に余裕がないと、他の電気機器と併用したときに電源が落ちるリスクもあるため、電力会社との契約内容の見直しも視野に入れておくと安心です。
防犯・安全面の対策も忘れずに
屋外に食べ物自販機を設置する場合は、防犯や安全面の対策も欠かせません。以下のような、防犯面や安全面の対策を検討し、トラブルを未然に防ぐ工夫が必要です。
- 人目につく場所に設置する
- 夜間でも明るく照らされる位置に設置する
- 防犯カメラを設置する
また、冬場の凍結や落雪、夏場の虫の侵入など、季節による環境変化にも注意が必要です。
食べ物の自販機の最新トレンド
食べ物の自動販売機は、技術の進歩によって利便性や販売手法の幅が広がり、従来の「無人販売機」とは異なる存在になりつつあります。
ここでは、導入を検討する事業者が注目すべき最新動向を3つ紹介します。
キャッシュレス決済への対応
自販機業界では、現金に加えて電子マネーやQRコードなどのキャッシュレス決済に対応する機種が導入されています。
非接触決済を利用できる環境を整えることで、小銭を持たない利用者や訪日観光客にも対応しやすくなります。
また、キャッシュレス決済を導入すると、売上データや利用傾向をデジタルで把握できるため、商品補充や価格設定の見直しを効率的に行うことが可能です。
関連記事▼
IoT・データ連携による運用効率化
近年では、在庫状況や販売データを遠隔で確認できるIoT対応型の自販機が登場しています。
センサーや通信機能を活用し、商品の温度管理や稼働状況をリアルタイムでモニタリングできるのが特徴です。
これにより、無駄な補充作業の削減や、人気商品の販売機会損失を防ぐ運用が実現しやすくなっています。
通信コストなどの課題はありますが、効率的な運営を目指すうえで有効な手段のひとつです。
地域性やコラボレーションを重視した展開
食べ物の自販機では、地域の特産品や飲食店と連携した商品展開が各地で見られます。
たとえば、地元の人気ラーメン店が監修した冷凍メニューや、観光地のスイーツブランドが手掛ける限定商品など、立地の特性を生かした販売が行われています。
このような商品は「話題性」や「限定感」が購買意欲を高める要素となり、自販機の差別化につながっています。
よくある質問(FAQ)
食べ物の自動販売機を導入する際には、商品の選び方や設置条件、費用などについて多くの疑問が生まれます。ここでは、導入を検討する際によく確認されるポイントをまとめました。
Q1:自動販売機で売れる食べ物は?
立地や利用者層によって売れ筋は変わりますが、軽食系が安定した人気です。
また、スイーツやパンなどの冷凍商品を扱うケースも増えており、24時間いつでも購入できる利便性が支持されています。ターゲット層に合わせて商品ラインナップを調整することが、売上向上のポイントになります。
Q2:飲料以外の自販機も設置できる?
飲料以外の自販機も設置できます。冷凍・冷蔵・常温などの温度帯に対応した自販機を選ぶことで、弁当や惣菜、菓子類などさまざまな食品の販売が可能になります。
最近では遠隔で在庫や売上を確認できるIoT型の自販機も登場しており、管理の効率化が進んでいます。
Q3:設置に許可や届出は必要?
自動販売機の設置自体に特別な許可は不要です。ただし、販売する商品によっては食品衛生法に基づく届出や管理が必要になる場合があります。
特に、自社で調理・包装した食品を販売する場合は、所轄の保健所に相談して条件を確認しましょう。また、屋外に設置する際は土地の管理者や所有者からの承諾を得ることが求められます。
Q4:導入費用はいくら?
費用は運営方法や設置環境によって異なります。自社で機器を購入する場合、新品は100〜200万円程度、中古は20〜70万円前後が目安です。
メーカー委託型を選ぶと初期費用を抑えられますが、売上の一部を手数料として支払う仕組みになる場合があります。
まとめ
一見ハードルが高く感じられる「食べ物の自販機」ですが、設置方法や運営スタイルの選び方次第で、小規模なビジネスでも十分に取り入れることができます。
特に最近は、冷凍食品や軽食、スイーツなど、商品ラインナップも多様化しており、ちょっとした買い物ニーズや“話題性”を生かした集客にもつながる点が魅力です。
もちろん「電源の確保」や「設置場所の選定」、「衛生管理」といった準備は必要ですが、専門業者によるサポートを活用することで、導入ハードルを下げることも可能です。
無人運営や非対面サービスが求められる今、食べ物の自販機は新しい収益源としても注目されています。
将来を見据えた販路のひとつとして、前向きに検討してみてはいかがでしょうか。
関連記事▼
「TOUCH TO GO」のプロダクトは、自販機を設置するように、工事不要でコンビニ区画を導入できます。
店舗の省人化・人件費削減をご検討中の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/