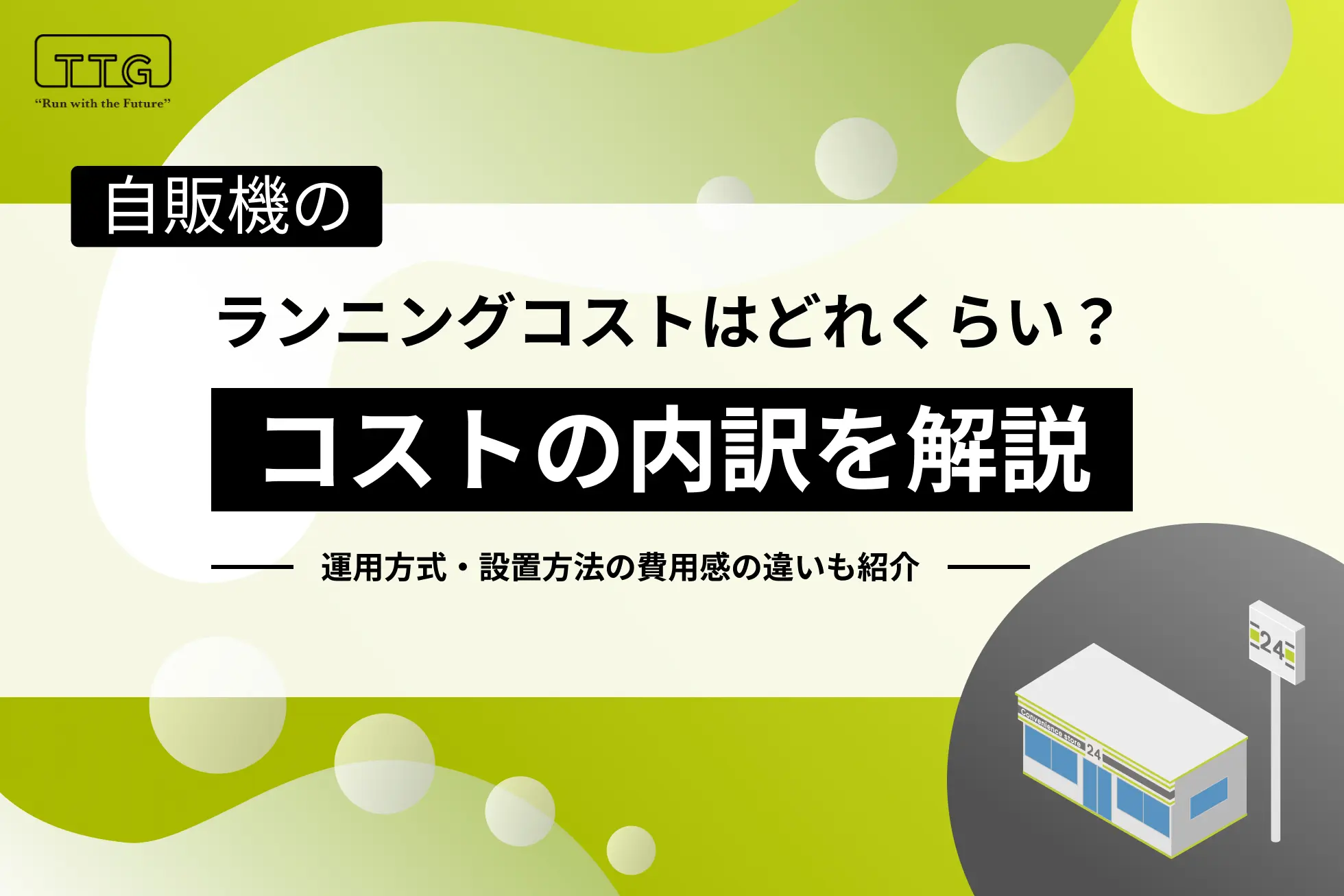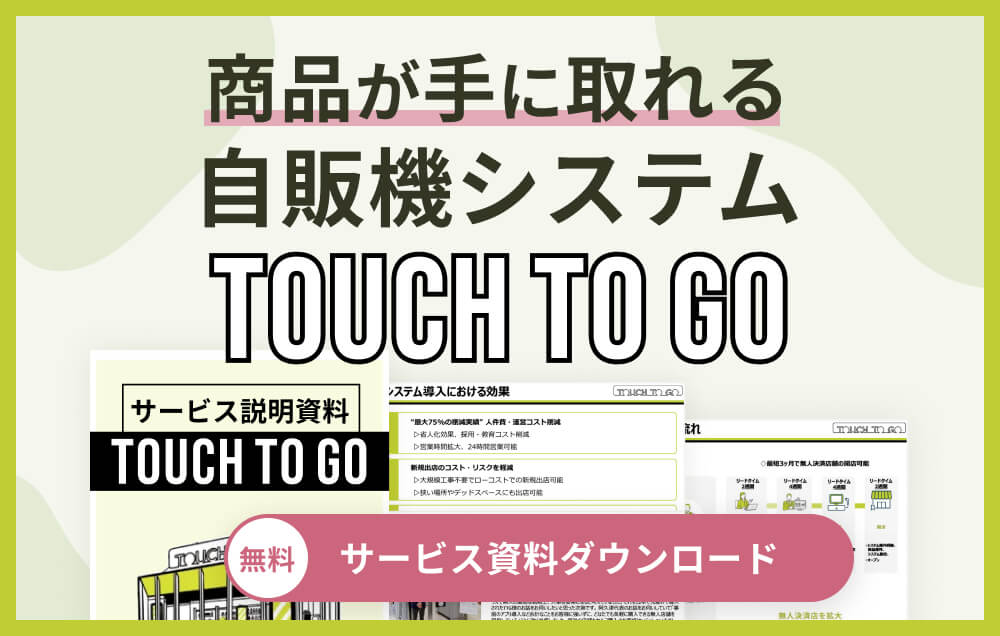Category
こんにちは。無人決済店舗システムを提供しているTOUCH TO GO 編集部です。
ちょっとしたスペースに設置でき、24時間いつでも販売ができる自動販売機。人手もかからず、上手く運用すれば副収入の手段としても魅力的です。
しかし、気になるのが「運営にかかるコスト」ではないでしょうか。
毎月発生する電気代や補充の手間、設置方法による費用の違いなど、始める前に知っておきたいポイントはたくさんあります。
この記事では、自販機のランニングコストの内訳や、運用方式・設置方法の費用感の違いを紹介します。
また、省エネ型自販機の機能や設置場所についても解説しているので、ぜひ参考にしてください。
関連記事▼
監修者プロフィール

2019年に株式会社TOUCH TO GOを設立。無人決済店舗システムを提供し、次世代型小売の拡大に取り組んでいる。
目次
自販機のランニングコストの内訳
自販機は一見、省スペースで効率的な販売手段に思えますが、設置したあとも継続的にコストがかかります。
運営を長く続けるには、月々の固定的な出費をあらかじめ把握しておくことが大切です。
ここでは、自販機の代表的なランニングコストである、電気代やメンテナンス費について見ていきましょう。
毎月かかる電気代
自販機の運用で、最も分かりやすく、かつ継続的に発生するのが電気代です。
庫内の温度を一定に保つために、飲料を冷やしたり温めたりする必要があり、基本的に24時間電力を消費し続けます。
そのため、電気代は年間を通じて無視できないコストとなります。
金額は、機種や季節、設定温度などによって異なりますが、一般的な清涼飲料水の自販機であれば、月に1,000円〜8,000円程度が目安です。
特にホット・コールド両対応の機種は電力消費が増えやすく、コストが高くなる傾向があります。
一方、省エネ性能に優れた最新機種では、消費電力を抑える工夫がされており、古い機種に比べて電気代を抑えられます。
補充・メンテナンスにかかる費用
自販機は自動で商品を販売するとはいえ、以下のような日常的な管理作業が必要です。
- 商品の補充
- 売上金の回収
- 清掃
- 故障対応
このような業務を誰が行うかによって、かかる費用は大きく変わります。
たとえば、自分で補充や清掃を行う場合は人件費がかかりませんが、業者に委託する場合は定期的な訪問コストや手数料が発生します。
また、冷却機能の故障や支払い機能のトラブルに備えて、保守契約や修理費用の積み立ても必要になります。
メンテナンスの頻度や管理の手間は、設置場所の環境や利用頻度によっても異なるため、自販機導入前に、どの程度の維持管理が必要かを見積もっておくことが大切です。
【補足】季節によって電気代は変動する
意外と見落としがちなのが、電気代は季節によって変動するという点です。
特に冬場は、ホット商品を提供する自販機にとって最も電力を消費する時期です。庫内を温め続ける必要があるため、夏よりも電気代が高くなりがちです。
逆に、冷却にかかる負担が少なくなる秋〜春先にかけては、電力消費が抑えられる傾向にあります。
月によって出費に差が出ることを前提に、年間を通した運営プランを立てておくと、資金繰りにも余裕をもって対応できます。
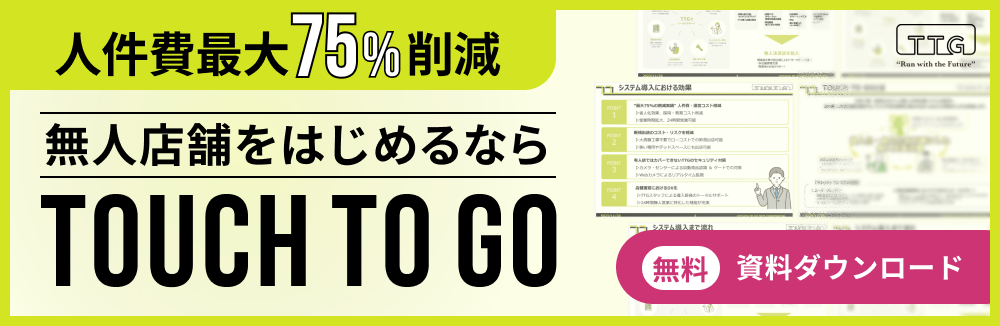
「TOUCH TO GO」のプロダクトは、自販機を設置するように、工事不要でコンビニ区画を導入できます。
店舗の省人化・人件費削減をご検討中の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/
運用方式・設置方法で変わる費用感
自販機の運営コストは、本体価格や電気代だけで決まるわけではありません。
実は、どの運用方式を選ぶかや、どのように自販機を設置するかによって、毎月かかる費用にも大きな違いが生まれます。
ここでは、主な運用スタイルと設置方法の違い、それぞれの費用感について紹介します。
フルオペレーション・セミオペレーション方式の違い
自販機の運用には主に「フルオペレーション方式」と「セミオペレーション方式」の2つあります。
フルオペレーション方式は、商品の補充やメンテナンス、売上金の回収など、すべてを業者に任せる運用方法です。
この場合、手間はほとんどかかりませんが、設置スペースの提供のみで収益は売上の一部に限られるため、利益はやや少なめです。
一方でセミオペレーション方式は、自販機本体は業者から提供されるものの、商品の仕入れ・補充・清掃などは自分で対応することになります。
そのぶん収益率は高くなるため、多少手間がかかっても売上をしっかり確保したいオーナーに向いています。
どちらを選ぶかで必要な手間と収益のバランスが大きく変わるため、自分の事業スタイルや目的に合った方式を選ぶことが大切です。。
購入・リース・レンタルの違い
自販機の導入方法にもいくつかの選択肢があります。
まず、購入の場合は、初期費用が最も高くなるものの、以降の月々の支払いがないためランニングコストは抑えられます。
リースは月額で支払いながら一定期間使い続ける方法で、初期負担を軽減しつつ、安定した設備を持ちたい人に適しています。
レンタルは短期イベントやお試し導入などに向いており、初期費用が抑えられる反面、月々のレンタル料はやや高めです。
なお、レンタルは短期運用には便利ですが、長期的にはコストがかさむ傾向があります。
どの方法にもメリット・デメリットがあるため、運用期間や資金状況をふまえて最適な導入スタイルを選ぶことが大切です。
省エネ型自販機でコストを抑えるには
電気代がランニングコストの中でも大きな割合を占める自販機において、省エネ性能の高い機種を選ぶことは、年間の運営費に大きな影響を与えるポイントになります。
ここでは、最新の省エネ機能の特徴と、導入のタイミングについて見ていきましょう。
最新機種の節電機能
最新の自販機には、以下のような省エネ技術が搭載されています。
- ヒートポンプ機能:冷却時の熱を加温に再利用して省エネ化
- ピークカット機能:電力使用が多い時間帯の消費を自動で抑える機能
- 真空断熱材:外気の影響を受けにくい素材で保冷・保温効率を向上
- LED照明:蛍光灯より消費電力を大幅に削減
- 照度センサー:周囲の明るさに合わせて照明を自動調整
上記のような技術を搭載した機種を導入することで、旧型機種に比べて電気代を大幅に削減することが可能です。
省エネ型自販機の導入タイミング
省エネ型自販機は、初期費用がやや高めになる傾向があります。ただし、毎月の電気代が確実に下がるため、中長期的に見ればトータルコストを抑えることが可能です。
たとえば、月々の電気代が1,000円安くなる場合、年間で12,000円、5年間で60,000円の削減になります。
省エネ機の本体価格が10〜15万円高くても、数年で差額を回収できる計算になります。
現在使用している自販機の製造年や消費電力を確認し、電気代やメンテナンスコストが高くなっている場合は、早めの買い替えを検討するとよいでしょう。
売上にも影響する設置場所と商品選定について
自販機の運営では、コストを抑える工夫と同じくらい、「しっかり売れる環境を整えること」も重要です。
電気代や管理コストをかけても、売上が伸びなければ収益は確保できません。
ここでは、売上にも影響する設置場所と商品選定について解説していきます。
売上が見込める場所と見込めない場所がある
自販機の売上は、設置する場所によって大きく変わります。
たとえば、オフィスビルや工場敷地内、学校の近くなど、人の流れがあり、休憩ニーズが高い場所では、比較的安定した売上が見込めます。
反対に、住宅街の裏通りや交通量の少ない場所など、目につきにくい立地では利用されづらく、電気代などのランニングコストを回収するのが難しくなります。
また、屋外設置の場合は天候や時間帯によって利用状況が変わるため、「人通りの多さ」だけでなく、「日当たり」や「足元の安全性」なども含めて検討する必要があります。
自販機の設置前に、周辺の人の動きや他の自販機の有無など、立地条件をしっかりチェックしておくことが成功の鍵になります。
設置場所によって商品のニーズは異なる
自販機で売上を伸ばすには、商品の選び方がとても重要です。特に見落とされがちなのが、「設置する場所によって、求められる商品が大きく異なる」という点です。
たとえば、オフィスビルや駅構内に置かれた自販機では、仕事中のリフレッシュや移動中の手軽な水分補給が目的になるため、コーヒーやエナジードリンク、ミネラルウォーターなどが好まれます。
一方、住宅街の一角やマンション前などでは、日常的に飲まれるお茶・ジュース・乳飲料といった定番商品がよいでしょう。
また、学校やオフィスの建物内に設置されている自販機では、小腹を満たせるようなスナック菓子やパン、アイスといった軽食系商品が人気になることもあります。
このように、「誰が・どのタイミングで・どんな目的で買うのか」をイメージすることで、売上につながる商品構成を組み立てることができます。
立地を考慮せずに商品を選ぶよりも、ターゲットに合った品ぞろえを意識することが、自販機運営成功への近道です。
自動販売機の設置に向いている場所
自動販売機の売上は、「どこに設置するか」で大きく変わります。 設置場所によっては、特別な宣伝をしなくても安定した利用が見込めることもあります。
ここでは、実際に自販機の設置に向いている代表的な場所を4つ紹介します。
小売店が少ない地域
周辺にコンビニやスーパーなどの小売店が少ないエリアは、自販機にとって好立地です。
「ちょっと飲み物がほしい」と思っても、すぐに買える場所がない状況では、自販機の利便性が際立ちます。
特に、郊外の住宅地や山間部、深夜営業をしていないエリアなどでは、生活インフラとしての役割にもなり、地域住民に重宝されやすくなります。
公園やレジャー施設の近く
公園や観光地、スポーツ施設の近くなど、人の出入りが多く、屋外で過ごす時間が長い場所では飲料のニーズが高まります。
散歩やレジャー、運動の合間に「手軽に水分補給できる」場所があると便利なため、自販機の設置にはぴったりです。
また、ベンチや広場がある場所では、飲み物だけでなくスナックやアイスの需要も見込めます。
オフィス街・オフィスビル
オフィス街やビジネスビルの一角も、自販機の好立地です。特に、昼休みや午後の休憩時間には、コーヒーやエナジードリンク、軽食系の需要が高まります。
建物内の共有スペースや駐車場の端など、わずかなスペースでも稼働できるため、限られた土地でも設置しやすいのが特徴です。
マンションやアパートの近く
マンションやアパートといった集合住宅の近くも、安定した利用が見込める設置場所です。
帰宅途中や夜間など、ちょっとしたタイミングでの利用が多く、特にコンビニが遠い場所では自販機の存在が生活の一部になります。
ファミリー層が多い地域では、お茶やジュース、子ども向けの飲料やお菓子などを取り揃えることでリピート率が上がりやすくなります。
まとめ
自販機の運営では、毎月かかる電気代などのランニングコストを把握し、それに見合う収益をどう確保するかがポイントになります。
近年は省エネ性能に優れた自販機も増えており、電気代を抑えながら運用することも可能です。
その一方で、コストを削減するだけでは十分とは言えません。
「どこに設置するか」「誰に向けて何を売るか」といった視点を持ち、設置場所と商品構成を工夫することも大切です。
まずは現状のコストと見込める売上のバランスを見直し、無理なく・ムダなく収益を生み出せる自販機運営を目指していきましょう。
関連記事▼
「TOUCH TO GO」のプロダクトは、自販機を設置するように、工事不要でコンビニ区画を導入できます。
店舗の省人化・人件費削減をご検討中の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/