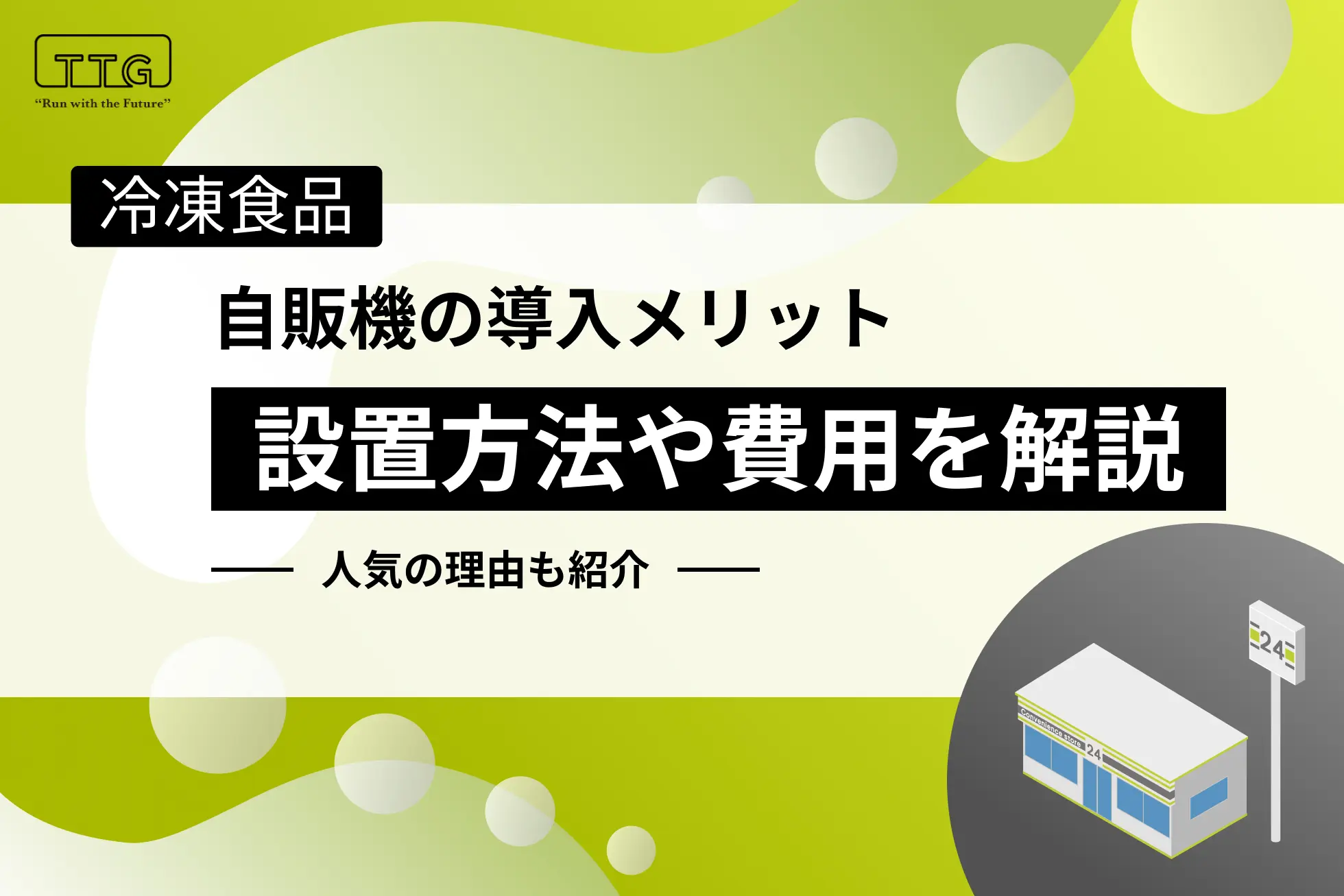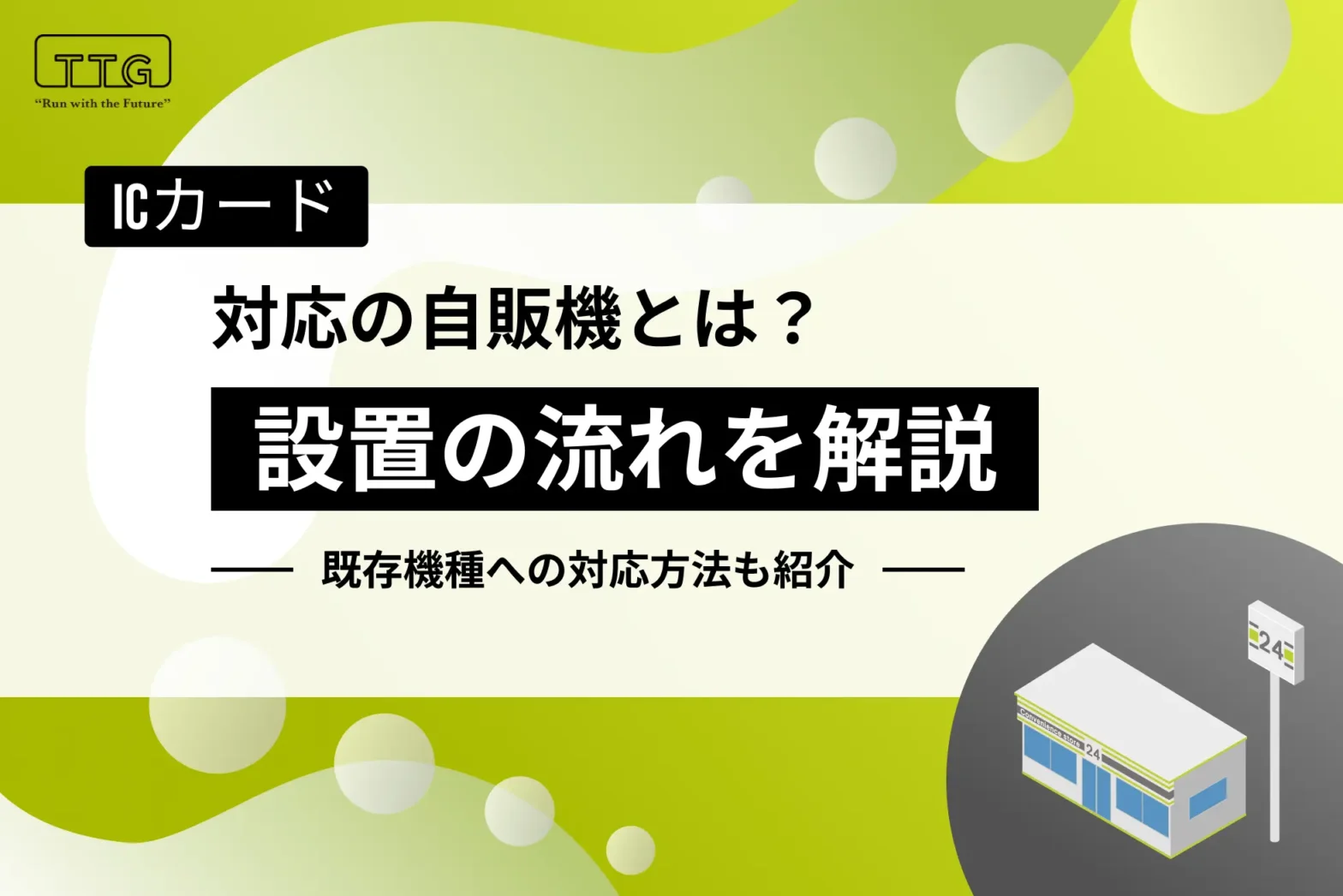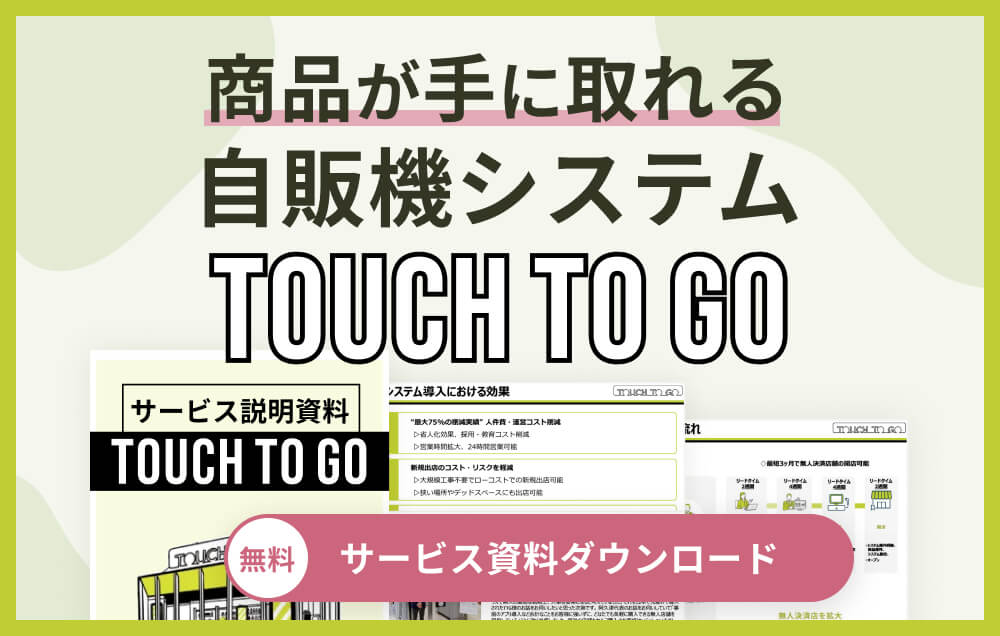Category
こんにちは。無人決済店舗システムを提供しているTOUCH TO GO 編集部です。
飲食業界や小売業を中心に、近年注目を集めているのが「冷凍食品自販機」の導入です。
ラーメンやスイーツ、ご当地グルメなど、多彩な商品を非対面・非接触で24時間販売できるスタイルは、時代のニーズにもマッチしており、導入する店舗や事業者が年々増えています。
とはいえ、設置には初期費用やランニングコストがかかるほか、「本当に採算が取れるのか?」「どこに置けば売れるのか?」といった不安を感じる方も多いかもしれません。
この記事では、冷凍食品自販機の導入メリットや人気の理由、設置方法や費用を詳しく紹介します。冷凍自販機の導入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
関連記事▼
監修者プロフィール

2019年に株式会社TOUCH TO GOを設立。無人決済店舗システムを提供し、次世代型小売の拡大に取り組んでいる。
目次
冷凍食品自販機とは
冷凍食品自販機は、その名の通り冷凍された食品を販売するための自動販売機です。
通常の飲料用自販機とは異なり、庫内の温度がマイナス18度以下に保たれるよう設計されており、冷凍保存されたまま商品を販売できるのが特徴です。
自動販売機の扉を開けると、冷凍ラーメンやスープ、冷凍弁当、スイーツなどの商品が並んでおり、購入者は好きな商品を選んで購入後、家庭で温めて食べるというスタイルです。
設置場所は店舗の軒先や駐車場、商業施設の一角などさまざまで、近年では飲食店が自社メニューを冷凍販売するケースも増えています。
冷凍食品自販機が人気の理由
冷凍食品自販機が注目されている背景には、いくつかの社会的なニーズの変化があります。
まず大きいのは、「非接触で商品を購入できる」という安心感です。
コロナ禍をきっかけに、対面接客を避けたいという声が高まったことで、自販機ビジネス全体が見直されました。
さらに、冷凍食品の品質向上も、冷凍食品自販機の広まりの後押しとなっています。
近年の冷凍技術の進歩により、調理済みのラーメンやカレー、スープなども「お店で食べる味」に近いクオリティで提供できるようになっています。
こうした背景から、飲食店や個人事業者だけでなく、商業施設などでも冷凍食品自販機が導入されるケースが増えています。
売れやすい人気商品
冷凍食品自販機では、調理が簡単で、日持ちしやすい商品が人気です。
なかでも安定して売れているのは、冷凍ラーメンや冷凍餃子、蕎麦、カレーなどの調理済み食品です。
店舗やブランドとコラボした「有名店の味を自宅で楽しめる商品」も根強い人気があります。
また、個包装の冷凍スイーツ・冷凍フルーツ・おにぎり・パンといった軽食系の自販機の設置も増えています。
以下の記事で、食べ物の自販機の人気商品を紹介しています。あわせてご覧ください。
関連記事>>食べ物の自販機を設置したい方必見|人気商品や設置方法を詳しく解説
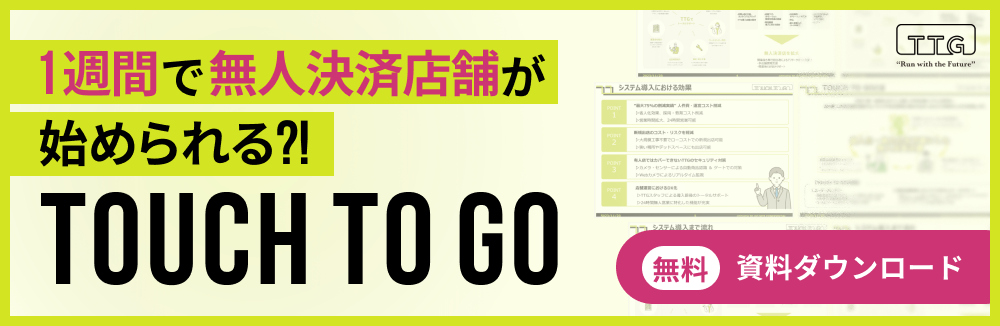
「TOUCH TO GO」のプロダクトは、自販機を設置するように、工事不要でコンビニ区画を導入できます。
店舗の省人化・人件費削減をご検討中の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/
冷凍食品自販機のメリット
冷凍食品自販機の導入には、多くのメリットがあります。ここでは、冷凍食品自販機のメリットを5つ紹介します。
24時間販売できる
冷凍食品自販機の最大のメリットのひとつが、時間に縛られず24時間販売できることです。
深夜や早朝など、通常の店舗営業では対応しにくい時間帯にも対応できるため、忙しい人や夜勤明けの人など、幅広い生活スタイルのニーズに応えられます。
人手をかけずに「いつでも買える環境」を提供できるのは、サービスの満足度を高めるうえで大きな強みです。
特に、店舗の閉店後や休業日でも売上を生み出せる点は、収益機会の拡大にもつながります。
人件費を最小限にできる
人件費を大幅に削減できるところも、冷凍食品自販機の大きなメリットです。
店舗を構える場合、スタッフの確保やシフト調整、教育コストなどがかかりますが、自販機であればそれらのコストはかかりません。
定期的な商品の補充やメンテナンスは必要ですが、基本的には無人で運用できるため、スモールスタートをしたい方や、人材確保が難しい地域でも導入しやすい仕組みといえます。
空きスペースで利益が得られる
冷凍食品自販機は、スペースを有効活用できる点でも注目されています。以下のような、ちょっとした場所に設置するだけで、新たな収益源になります。
- 店舗前の空き地
- 商業施設の共用部
- マンションのエントランス横
特に、営業時間外は活用されていない店舗の屋外スペースや、使い道のない敷地を所有しているオーナーにとっては、「遊休スペースの収益化」として有効です。
広告としても活用できる
冷凍食品自販機は、ただの販売手段としてだけでなく、自社商品のPRツールとしての役割も果たします。
たとえば飲食店がオリジナルメニューを自販機で販売すれば、営業時間外にもお店の味を周知でき、リピーター獲得やファンづくりにもつながります。
また、デザイン性のあるラッピングや看板を活用すれば、道行く人の目に留まりやすく、話題性のある“動かない広告媒体”としての効果も発揮します。
SNS映えするような自販機は、写真を撮ってシェアされる機会も多く、口コミでの集客にもつながりやすくなります。
非対面・非接触で販売できる
冷凍食品自販機は、非対面・非接触での販売が可能なため、衛生面や感染症対策の観点でも安心して利用できるのが強みです。
とくにコロナ禍以降、「人と接することなく商品を購入したい」というニーズが高まり、この販売スタイルに大きな価値が見出されるようになりました。
顧客にとっても、気軽に立ち寄って自分のペースで購入できる環境は、ストレスなく利用できる便利なサービスとなるでしょう。
冷凍食品自販機のデメリット
多くのメリットがある冷凍食品自販機ですが、当然ながら注意すべきデメリットも存在します。
ここでは、代表的なデメリット3つについて詳しく解説していきます。
赤字になる可能性がある
冷凍食品自販機はうまく運用すれば収益化が可能ですが、すべてのケースで利益が出るとは限りません。
売れる立地を選ばなかったり、ターゲットに合わない商品構成だった場合、思うように売上が上がらず赤字になってしまうこともあります。
また、自販機本体の購入費や設置費、冷凍商品の仕入れコストを回収するには、ある程度の販売数が必要です。
特に初期投資が大きくなりやすい冷凍機種では、事前の計画と見通しが不十分だと、長期的に負担が残ってしまう可能性もあります。
導入前に、事業モデルの収支バランスや立地調査、競合分析を実施して、無理のない運用を心がけることが大切です。
電気代がかかる
冷凍食品自販機は、常に一定の温度を保つために稼働し続ける必要があり、他の自販機に比べて電気代が高くなりがちです。
とくに冷凍タイプの場合、庫内温度をマイナス18度以下に保つ仕様が一般的で、季節や気温、設置場所の環境によってはさらに電力を消費します。
月々の電気代は機種によって異なりますが、目安として5,000〜8,000円前後が目安となります。
設置台数が増えればそれだけランニングコストもかさむため、導入前に想定される電気代をきちんと計算しておくことが大切です。
なお、省エネタイプの自販機を選ぶことで、電気代をある程度抑えることも可能です。
商品が売れ残る可能性がある
冷凍食品は賞味期限が比較的長いため在庫管理がしやすい反面、「売れ残るリスク」もゼロではありません。
とくに新しい立地や顧客層を狙う場合は、売れ行きが安定するまで試行錯誤が必要です。
また、商品ごとの人気に差が出やすく、ある一部の商品だけが残ってしまうと在庫の偏りにつながり、全体の売上が鈍ることもあります。
売れ残った商品は廃棄や値引き対応が必要になるため、ロスを抑えるためのラインナップや補充頻度の調整が欠かせません。
冷凍食品自販機の設置方法
冷凍食品自販機を導入するには、いくつかの方法があります。
ここでは「購入」「リース」「レンタル」の3つの選択肢について、それぞれの特徴を紹介していきます。
購入
冷凍食品自販機を購入する方法は、完全に自社の所有物として運用できる点が大きな特徴です。
初期費用は高くなりますが、長期的に見ればリースやレンタルよりもコストを抑えられるケースも多く、利益の全額を手元に残せます。
また、購入すれば設置場所やデザイン、販売商品などを自由に決められるため、ブランディングや自社商品の販売にこだわりたい事業者にも適しています。
一方で、メンテナンスや修理、故障時の対応も自己責任となるため、初めての導入で不安がある場合は、専門業者のサポート体制もあらかじめ確認しておくと安心です。
リース
リースは、自販機を一定期間借りる形式で導入する方法です。初期費用を抑えつつ、自社商品の販売やデザインの自由度を持ちながら運営できる点が魅力です。
多くの場合、リース契約には保守・メンテナンスが含まれているため、トラブル時の対応もスムーズに進みやすいというメリットがあります。
特に、数年以上の中期的な運用を検討している事業者にとっては、予算計画を立てやすい選択肢といえるでしょう。
ただし、契約期間内の解約には違約金が発生するケースもあるため、導入前に契約内容をよく確認しておく必要があります。
レンタル
レンタルは、短期的に冷凍食品自販機を導入したい場合に向いている方法です。
イベント出店や期間限定の販促企画として活用されることが多く、1日〜数ヶ月単位で借りられるプランもあります。
初期費用を最小限に抑えられるうえ、契約期間が短いため、導入リスクを低く抑えられるのが大きなメリットです。
冷凍食品自販機ビジネスを試してみたい、という人にとっては、テスト導入としても活用しやすい方法といえるでしょう。
ただし、機種や台数に限りがあることや、長期的に見るとコストが割高になる場合もあるため、運営期間に応じた費用対効果をよく検討することが大切です。
冷凍食品自販機の設置にかかる費用
冷凍食品自販機を導入する際には、本体代だけでなく、設置や運営にかかるさまざまな費用も考慮する必要があります。
ここでは、初期費用と継続的な運営費用の目安について、具体的に見ていきましょう。
初期費用
冷凍食品自販機の初期費用は、主に自販機本体の購入・設置・電気工事にかかる費用で構成されます。
一般的な冷凍自販機の相場は200万円程度ですが、機種や機能によって差があります。
このほかに、以下のような費用が発生することもあります。
- 設置費用:地面の整備や固定工事など
- 電源工事費:専用コンセントが必要な場合
- 初回の商品仕入れ代
購入する場合はすべて自己負担となりますが、リースやレンタルを活用すれば、購入費用や設置費用を抑えることも可能です。
運営費用
冷凍食品自販機の運営にかかるランニングコストとしては、主に以下の費用があります。
- 電気代:月5,000円〜8,000円程度
- 商品の仕入れ代:仕入れ数に応じて変動
- メンテナンス費用:リース・レンタル契約であれば月額費用に含まれることもある
- 消耗品費用:レジ袋や保冷バッグなど(必要な場合のみ)
とくに電気代は、自販機の稼働において継続的にかかる代表的なコストです。
また、売上に応じて在庫補充の頻度が増えれば、配送コストや人的コストも追加で必要になることがあります。
安定した利益を得るためには、これらの固定・変動費を把握したうえで、販売価格や商品構成を調整していくことが大切です。
まとめ
冷凍食品自販機は、24時間稼働・非対面販売・人件費削減といったメリットを持つ、新しい販売スタイルのひとつとして注目を集めています。
飲食店の販路拡大や副業としての活用、小規模スペースの有効活用など、導入目的も多様化しています。
一方で、設置費用や電気代、売れ行きによっては赤字のリスクもあるため、事前のリサーチや立地選定、商品構成の工夫が重要になります。
購入・リース・レンタルの3つの導入方法を比較しながら、自分に合ったスタイルで無理のない運営を目指しましょう。
以下の記事で、食べ物の自販機の人気ジャンルや費用について解説しています。あわせてご覧ください。
「TOUCH TO GO」のプロダクトは、自販機を設置するように、工事不要でコンビニ区画を導入できます。
店舗の省人化・人件費削減をご検討中の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/