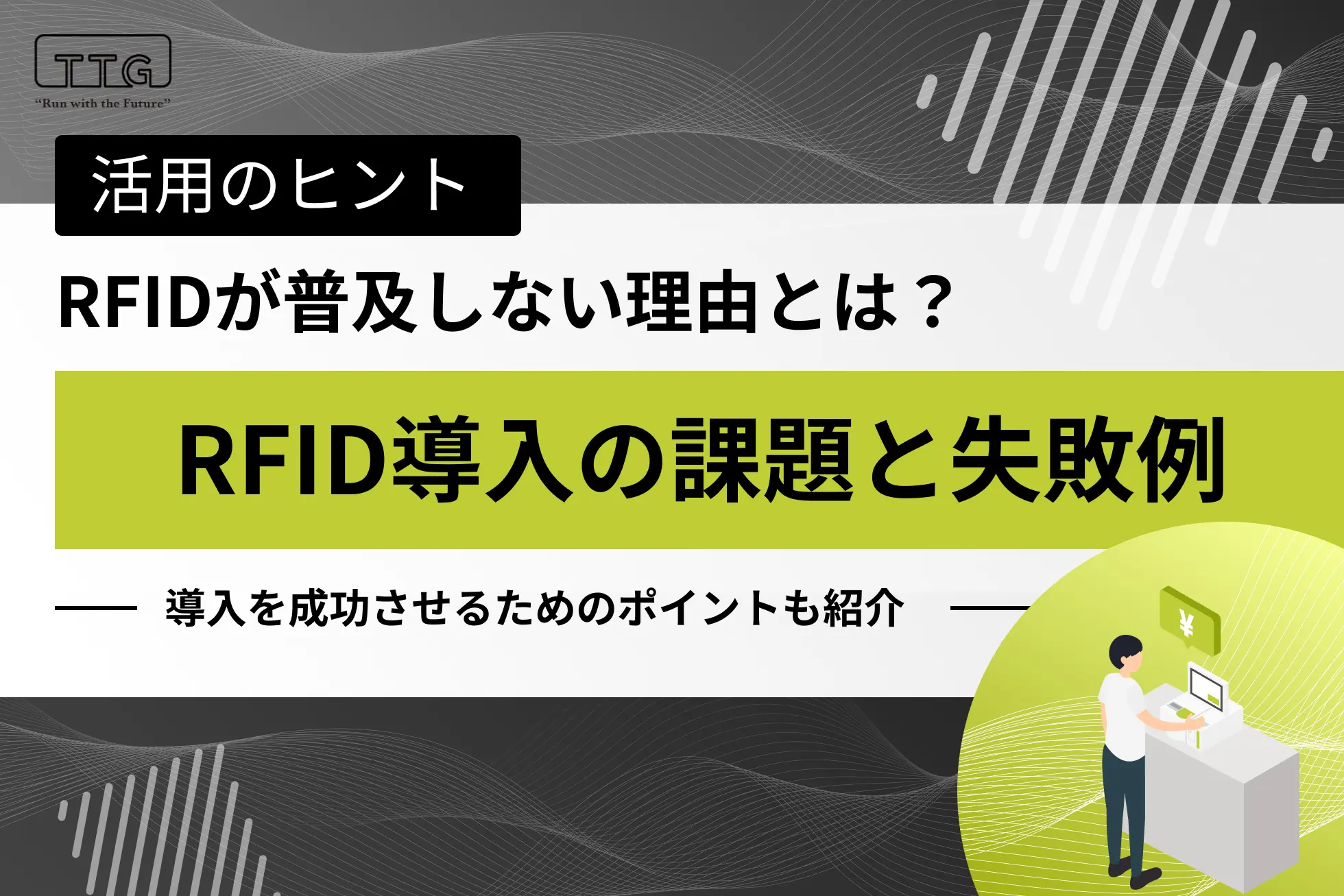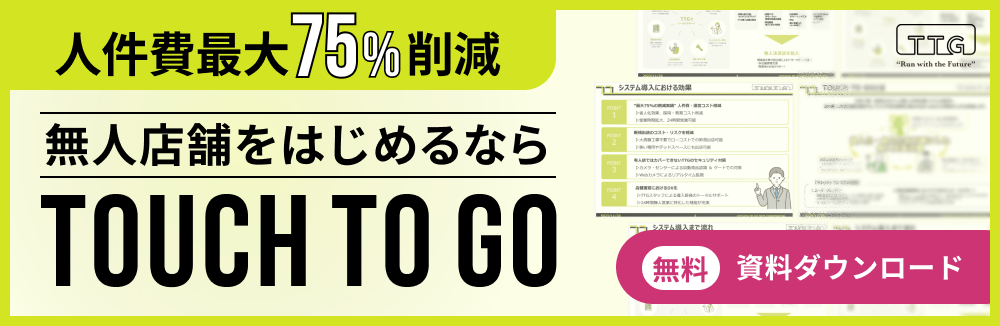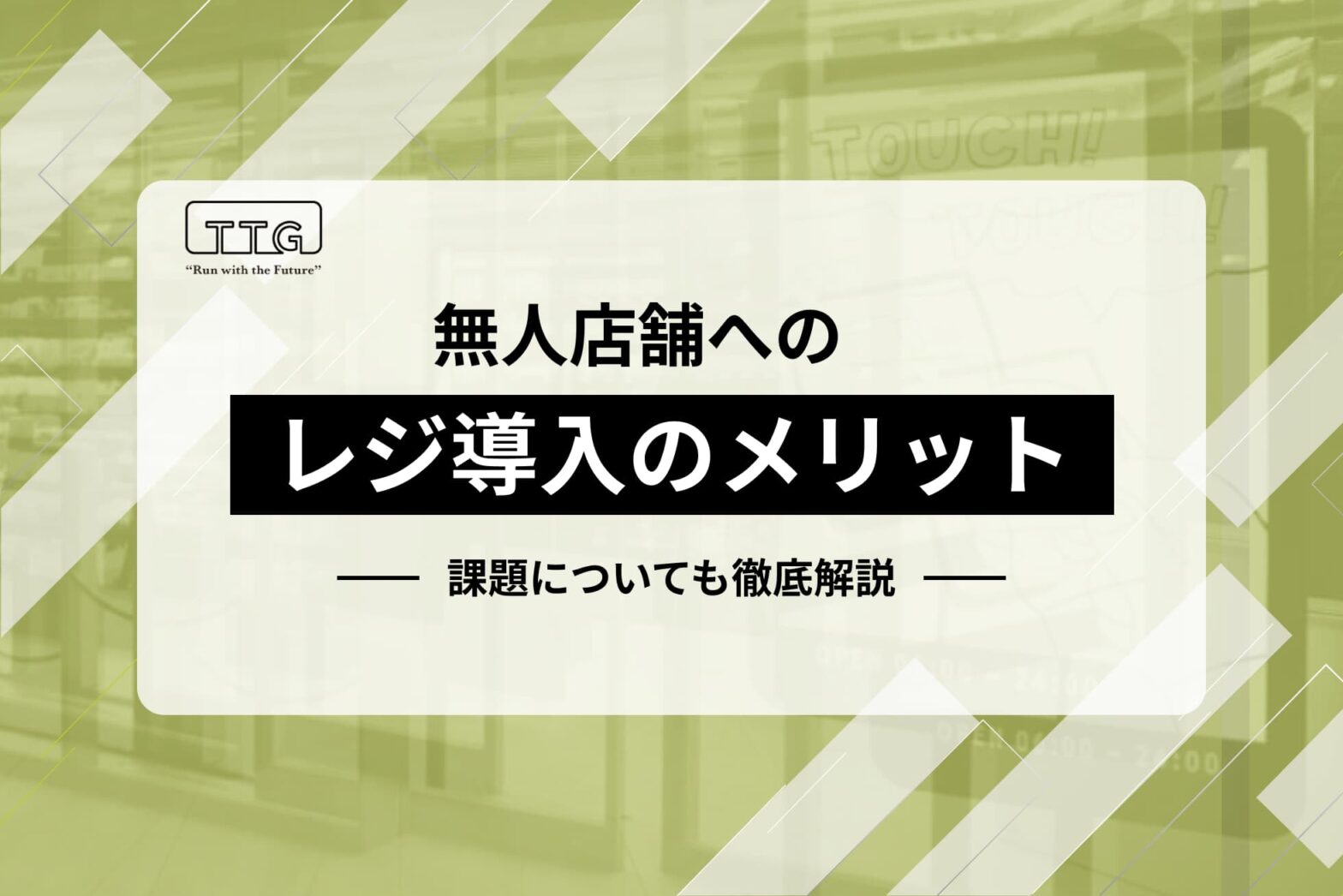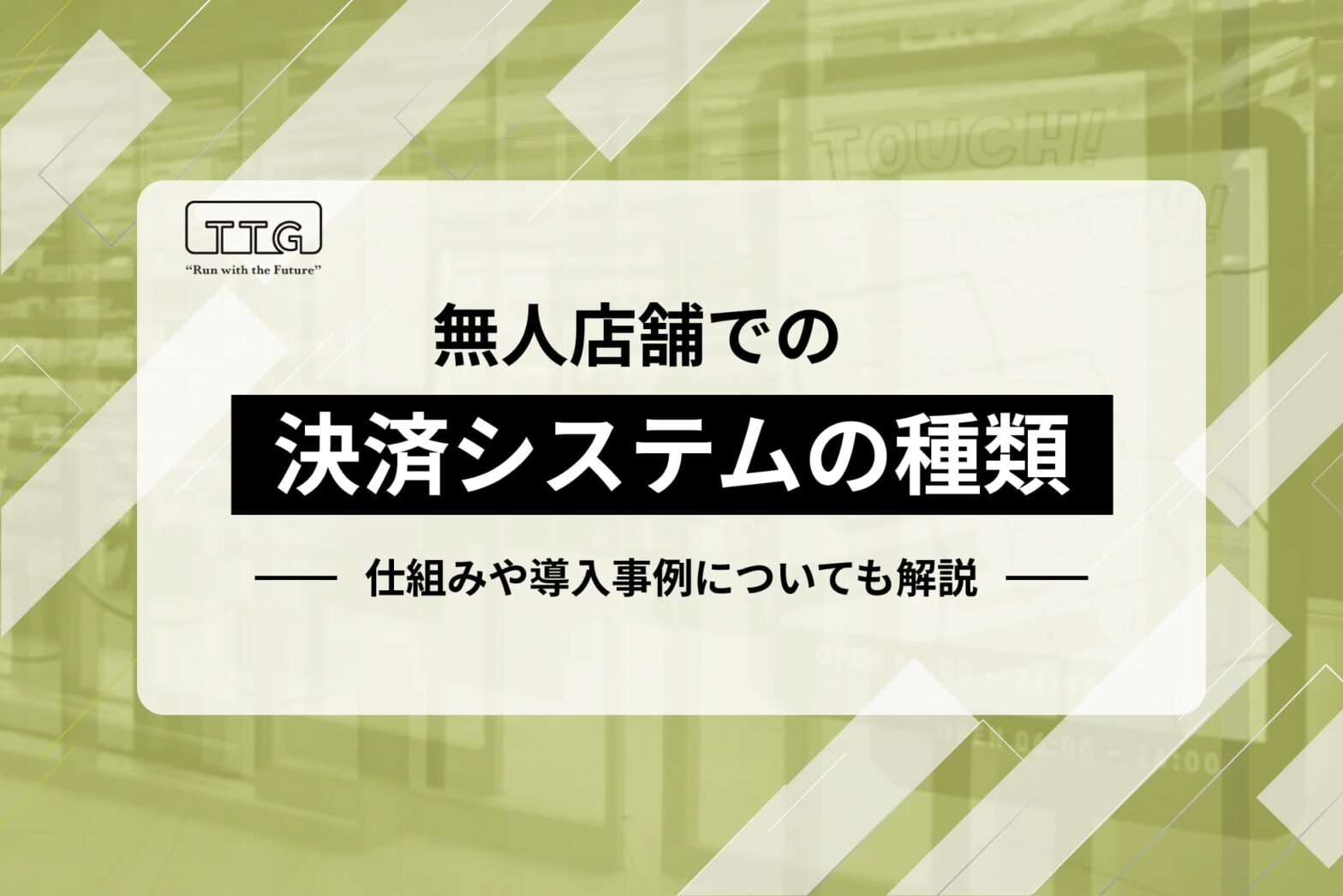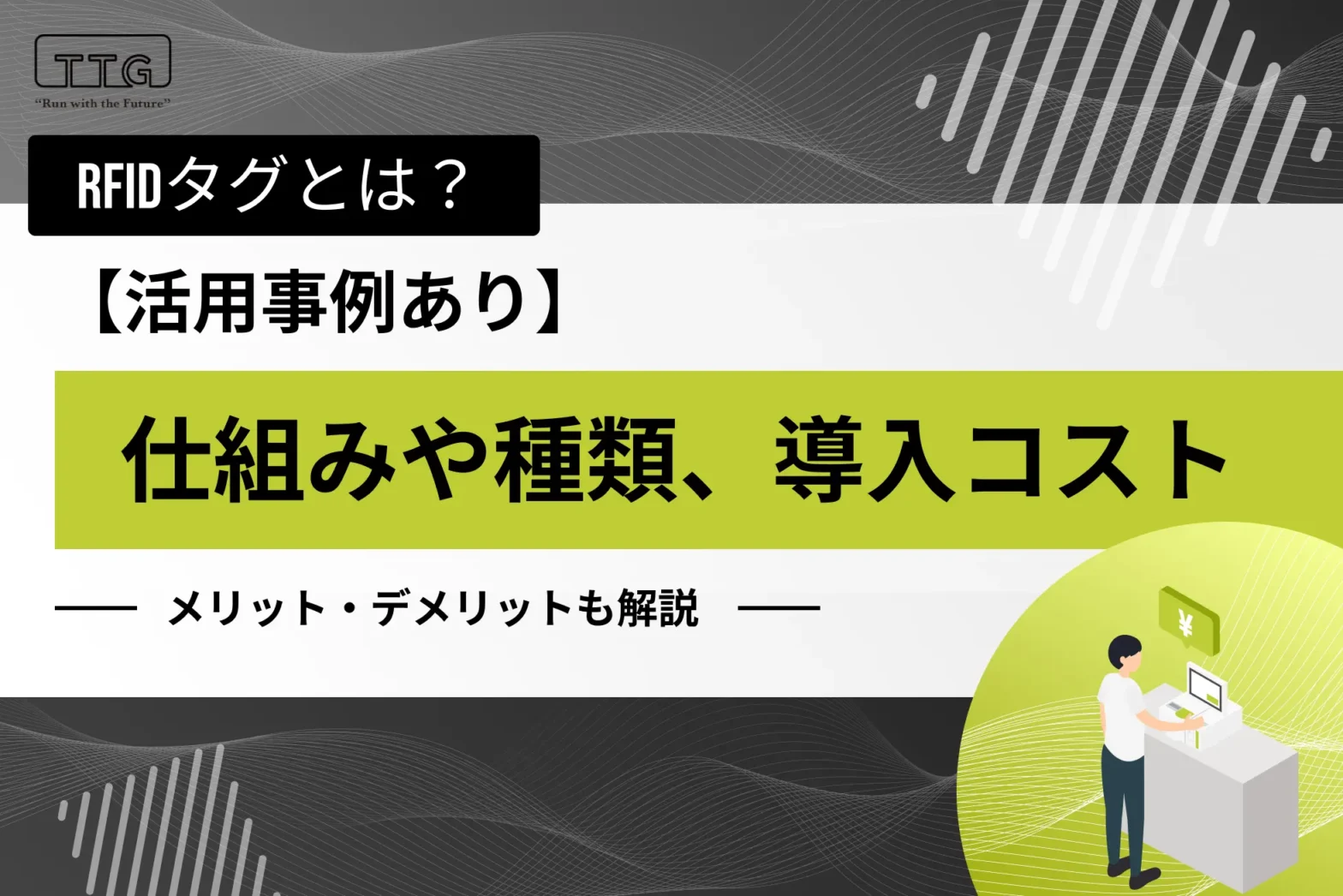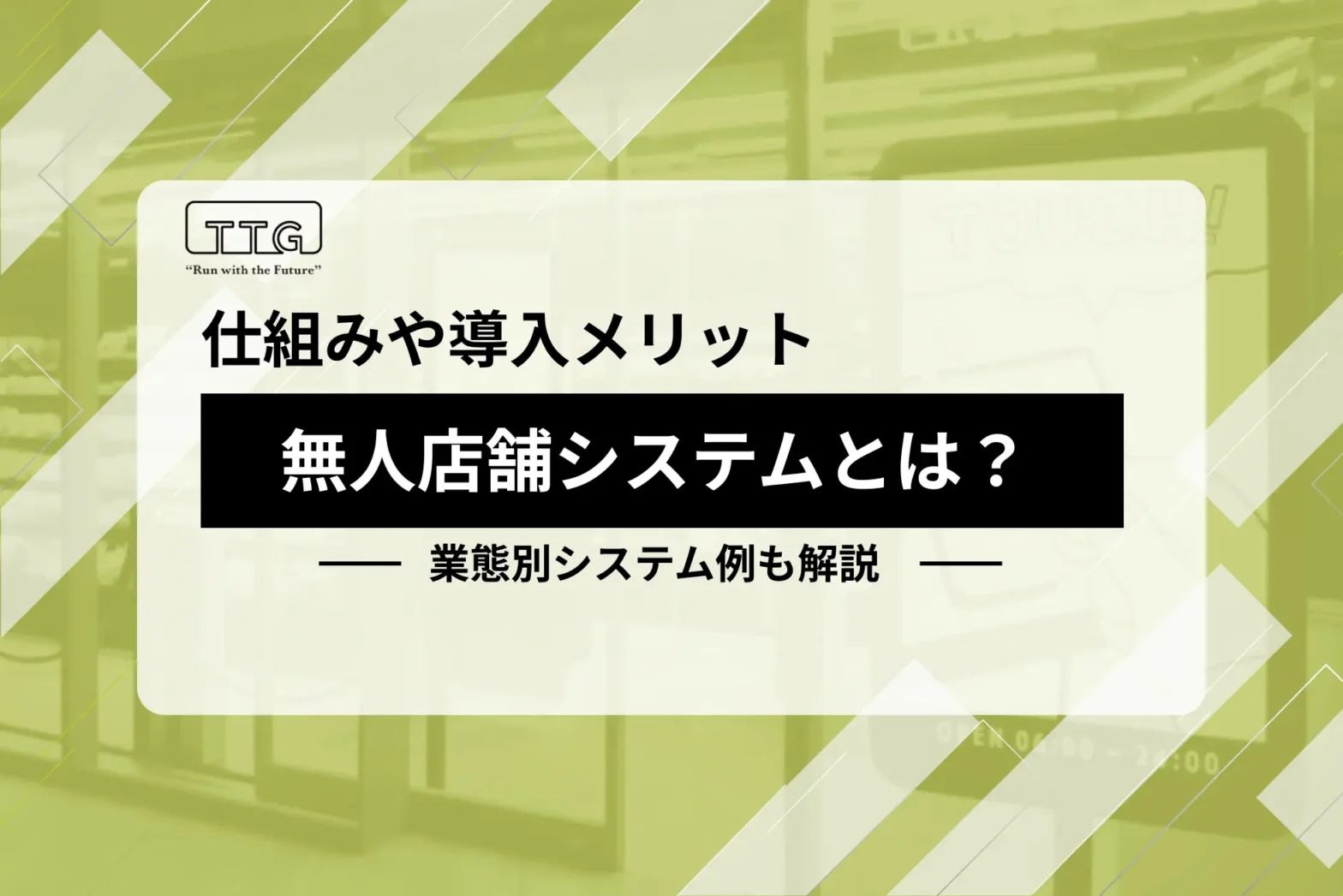Category
こんにちは。無人決済店舗システムを提供しているTOUCH TO GO 編集部です。
非接触で複数のタグを一括読み取りできるRFIDは、小売や物流をはじめ、さまざまな業界で注目を集めています。
しかし一方で、「思ったほど普及していないのはなぜだろう」と疑問に感じる方も少なくありません。
本記事では、RFIDの基本的な仕組みや普及状況、導入を妨げる要因や技術的な課題を解説します。
さらに、導入を成功させるためのポイントも紹介するので、RFIDを検討している事業者の方はぜひ参考にしてください。
関連記事▼
監修者プロフィール

2019年に株式会社TOUCH TO GOを設立。無人決済店舗システムを提供し、次世代型小売の拡大に取り組んでいる。
目次
RFIDとは
RFID(Radio Frequency Identification)とは、アンテナ付きのタグとリーダーが電波で非接触通信し、物品を識別・追跡する技術です。
一度に複数のタグを読み取れるため、バーコードでは難しかった一括処理や効率的な資産管理を可能にします。
タグには「パッシブ型」や「アクティブ型」などの種類があり、用途や環境に合わせて最適な方式を選択できます。
導入の仕組みや具体的な選び方については、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事>>【事例あり】RFIDタグとは?仕組みや種類、導入コストやメリットを解説
RFIDの普及率
近年、RFID技術は世界的に導入が進み、市場規模も着実に拡大しています。
民間の市場調査会社「矢野経済研究所」の調査によると、2024年のグローバルRFIDソリューション市場は約1兆6,431億円に達し、前年比110.8%という力強い成長を遂げました。2027年には、2兆3,000億円規模まで成長すると予想されています。
特に流通や小売分野を中心に活用が広がり、製造業や医療、物流など幅広い業界へも普及が進んでいます。
国内においても同様に、IoTやデジタル化の流れと相まってRFIDの導入が加速しており、在庫管理や業務効率化を目的とした需要の高まりがうかがえます。
出典:RFIDソリューション世界市場に関する調査を実施(2025年)|株式会社矢野経済研究所
RFIDが普及しない理由
RFIDは効率的な在庫管理や業務の自動化に大きな効果を発揮する一方で、まだ広く普及しているとは言い切れません。
その背景には、導入や運用に関わるいくつかの課題が存在します。ここでは主な理由を解説します。
初期導入コストが高い
RFIDを導入するには、タグだけでなくリーダー機器やシステムの構築も必要です。小売や物流の現場では数万〜数十万点のアイテムを扱うため、タグ単価が数十円でも全体では大きな費用になります。
さらに、リーダー機器やアンテナの設置費用や、システム連携のための開発コストも発生します。こうした初期投資の高さが、RFID普及の大きな壁となっています。
こうした課題に対応するのであれば、『TOUCH TO GO』の無人決済店舗システムがおすすめです。TOUCH TO GOのシステムはカメラとセンサーによる自動認識を活用しているため、RFIDタグの購入や貼付作業は不要です。
そのため、導入に伴う負担を抑えながら在庫管理やレジ業務の効率化を実現できます。コンビニやスーパーなど、スピードと利便性が求められる店舗運営においても、現場に馴染む形で導入を進められるのが大きな魅力です。
関連記事▼
TOUCH TO GO の無人決済店舗システムは、カメラとセンサーでお客様と商品を自動で認識。商品の読み取りなどのレジ操作は不要で、待ち時間ゼロの快適な購買体験を提供できます。
人手不足対策・コスト削減に強いシステムの導入を検討している方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/
導入による費用対効果が見えにくい
RFIDは効率化や省人化に役立つ技術ですが、短期間で数値として投資回収効果を示すのは容易ではありません。
在庫管理や棚卸作業がスムーズになるといった定性的なメリットは理解されやすい一方で、導入前にROI(投資対効果)を明確に算出するのは難しく、経営層の判断をためらわせる要因となっています。
環境による読み取り精度の低下
RFIDは電波を利用するため、金属や水の影響を受けやすいという特性があります。
そのため、飲料や化粧品など液体を含む商品や、金属棚・コンテナに入った物品では読み取りエラーが発生する場合があります。
こうした環境要因によって、導入しても期待どおりの精度が得られず、普及の妨げとなっています。
既存システムとの連携や標準化の問題
RFIDを活用するには、POSやERP、倉庫管理システムなど、既存の業務システムとのデータ連携が欠かせません。
しかし企業ごとにシステムの仕様や規格が異なるため、スムーズに統合できないケースも少なくありません。
国際規格(ISOやEPCglobal)は整備が進んでいるものの、現場レベルでの標準化はまだ十分とはいえず、システム開発の手間やコストが大きな障壁となっています。
関連記事▼
セキュリティやプライバシーへの不安
RFIDタグは電波で情報を読み取れるため、正規のリーダー以外からも読み取られる可能性があります。
その結果、個人情報や商品情報が不正に取得されるリスクが指摘されています。
特に小売や医療の分野では、消費者や患者のデータ保護が重視されるため、セキュリティ対策が普及のカギとなります。
こうした懸念から、導入をためらう企業も少なくありません。
RFIDの課題
RFIDは幅広い分野での活用が期待されていますが、導入にあたってはいくつかの課題も指摘されています。ここでは代表的な3つのポイントを見ていきましょう。
情報漏えいや不正利用のリスク
RFIDは非接触で情報を読み取れるため利便性は高いものの、正規のリーダー以外からも読み取られる可能性があります。
もし悪意のある第三者に不正スキャンされれば、商品の流通状況や個人情報が漏えいするリスクが生じます。
特に医療現場で患者情報を扱う場合や、小売で購買履歴と結びついた情報を管理する場合には、プライバシー侵害の懸念が強まります。
そのため、暗号化や認証技術を取り入れたセキュリティ対策が不可欠です。
関連記事▼
導入コストと運用のハードル
RFIDシステムの導入には、タグやリーダー機器だけでなく、システム開発や既存業務との統合が欠かせません。
これらを一から構築するには多額の初期投資が必要で、運用開始後も保守費用やランニングコストが発生します。
特に中小企業にとっては、このコストが大きなハードルとなり、普及を妨げる要因の一つとなっています。
規格のばらつきとシステム互換性の問題
RFIDには複数の周波数帯や規格が存在し、必ずしもすべての機器やタグが相互運用できるわけではありません。
国際的には「ISO」や「EPCglobal」といった標準規格が整備されていますが、現場では企業ごとにシステム仕様が異なるケースが多く、互換性の欠如が障害となることがあります。
その結果、異なるサプライチェーン間でデータを共有したり統合管理を行ったりする際に、追加の調整やカスタマイズが必要となるのです。
RFID導入による失敗例
現場でのRFID導入は大きなメリットをもたらしますが、十分な準備や知識がないまま進めてしまうと、期待した効果が得られないケースもあります。ここでは、実際に起きがちな失敗例を紹介します。
素材の影響でデータが読み取れない
金属や液体は電波を反射・吸収する性質があるため、缶やペットボトルに入った商品ではタグを正しく読み取れないケースがあります。
実際、棚卸時に飲料ケースの在庫数がシステム上の数値と一致しなかったり、金属ラックに並べた商品の読み取り漏れが発生したりするケースも指摘されています。
こうした特性を考慮せずにタグを貼り付けると、導入したシステムの精度が低下し、業務効率化どころか手作業による確認作業が増えるといった問題につながるおそれがあります。
アンテナ配置と電波干渉による読み取り不良
RFIDリーダーのアンテナとタグの位置関係は、読み取り精度に大きな影響を与えます。
アンテナの角度や設置場所が適切でないと、本来読み取れるはずのタグが反応せず、データが欠落することがあります。
さらに、アンテナ同士の電波干渉や周辺機器からのノイズによっても読み取りが不安定になり、一部の商品だけ読み取れないといったトラブルにつながります。
周波数の選定ミスによる読み取り不良
RFIDにはLF帯・HF帯・UHF帯・マイクロ波帯と複数の周波数帯があり、それぞれ得意とする用途や環境が異なります。
周波数の選定を誤ると、現場環境に適さず読み取りが安定しなくなります。
例えば物流倉庫で短距離向きのHF帯を採用してしまうと、広範囲での一括読み取りが難しくなり、結果的に作業効率の低下につながります。
運用・管理体制の不備
RFIDを導入しても、現場スタッフが正しく運用できなければ十分な効果は得られません。
リーダーの操作方法やエラー時の対応が教育されていないと、読み取り不良が放置される可能性があります。
また、導入後のメンテナンスやシステム更新が不十分だと、不具合が少しずつ積み重なり、結果的に現場で使いづらい仕組みになってしまいます。
RFID導入で失敗する原因
RFID導入で失敗する背景には、導入前の準備やシステム設計の不十分さが隠れているケースが多く見られます。ここでは、失敗を引き起こす主な原因を解説します。
導入目的や要件定義の不足
「最新技術だから」「他社が導入しているから」といった理由だけでRFIDを導入すると、目的が曖昧なまま進んでしまいます。
その結果、どの業務を効率化したいのか、どんな成果を期待しているのかが不明確となり、導入後に費用対効果を実感できないケースも少なくありません。
現場フローとのミスマッチ
RFIDを導入する際は、現場の作業手順やオペレーションに沿った設計が欠かせません。
もし従来の検品手順を大幅に変更しなければならないシステムを導入すれば、現場スタッフに余計な負担がかかり、結果として効率が低下してしまいます。
最悪の場合、現場ではRFIDが使われず従来の手作業に戻ってしまい、投資が無駄になるリスクもあります。
ベンダーやシステム選定の誤り
RFIDには周波数帯やタグの種類など多くの選択肢があり、それぞれに得意不得意があります。
こうした特性を十分に理解せずにベンダーやシステムを選んでしまうと、自社の環境や目的に適さない仕組みを導入してしまうリスクがあります。
失敗を防ぐためには、「信頼できるベンダー選び」と「要件に基づいた事前の比較検討」が欠かせません。
教育不足による運用トラブル
どれだけ優れたシステムを導入しても、現場で使いこなせなければ意味がありません。
スタッフがリーダーの操作方法を理解していなかったり、エラー発生時の対応手順が共有されていなかったりすると、教育不足が原因で日常的にトラブルが生じることがあります。
こうした問題を防ぐには、導入時の教育プログラムやマニュアル整備など、運用体制の構築が不可欠です。
TOUCH TO GO の無人決済店舗システムは、カメラとセンサーでお客様と商品を自動で認識。商品の読み取りなどのレジ操作は不要で、待ち時間ゼロの快適な購買体験を提供できます。
人手不足対策・コスト削減に強いシステムの導入を検討している方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/
RFIDの今後の展望
RFIDはまだ課題を抱える技術ではありますが、今後の技術革新や社会的なニーズの変化によって普及が一層進むと考えられています。ここでは、今後の展望を「技術」「標準化」「活用分野」「社会的要因」の4つの視点から解説します。
技術面の進化による普及加速
今後は、RFIDタグの低コスト化がさらに進み、大口の注文であれば1枚あたり5円程度まで価格を下げられます。コスト面のハードルが下がれば、これまで導入をためらっていた中小規模の事業者にも普及が広がるでしょう。
また、高耐久・小型化も進展し、高温環境や水分・金属の影響を受けにくい特殊タグが普及することで、これまで導入が難しかった現場でも活用が可能になります。
さらに、長距離かつ高速での読み取り技術の開発が進めば、物流や工場など広いエリアでの効率的な管理が実現します。
標準化とシステム連携の進展
RFIDの課題のひとつである「規格のばらつき」は、国際的な標準規格の整備によって解消が進んでいます。標準化が進むことで、異なるベンダーの機器同士でも互換性が高まり、導入のハードルが下がります。
さらに、ERPやPOSなど既存システムとの連携がスムーズになることで、導入効果はより大きくなります。将来的には、サプライチェーン全体をRFIDで一元的に管理する仕組みも現実味を帯びてきています。
導入分野の拡大
これまでRFIDは小売や物流の分野での活用が中心でしたが、今後は医療、製造、建設といった幅広い産業に応用が広がると予測されています。
医療では医薬品や医療機器のトレーサビリティ、製造業では工程管理や偽造防止、建設業では資材や工具の管理に役立ちます。
さらに、IoTやAIとの組み合わせにより、スマートファクトリーやスマートリテールといった次世代の仕組みが実現しつつあります。
RFIDは今後さらに、データ収集の基盤技術として重要性を高めていくと考えられます。
普及を後押しする社会的要因
技術やシステム面だけでなく、社会的な要因もRFID普及を後押ししています。
政府によるDX推進政策や補助金制度の拡充は、企業の導入を加速させる大きな要素です。
また、慢性的な人手不足に対応するための自動化ニーズも高まっており、RFIDはその解決策として注目されています。
さらに、ESGやサステナビリティの観点からもRFID導入は評価されています。食品ロス削減や循環型社会の実現に貢献できることから、環境配慮型の取り組みとしても今後の需要は拡大すると考えられます。
関連記事▼
RFIDの主な活用シーン
RFIDは、単に商品を識別するだけでなく、さまざまな業務の効率化や精度向上に役立つ技術です。
特に小売業や物流業を中心に導入が進んでおり、近年では医療やオフィス管理など利用分野も広がりを見せています。ここでは、代表的な活用シーンを紹介します。
在庫管理
工場や倉庫、小売店舗における在庫管理は、RFIDが最も効果を発揮する分野のひとつです。
商品や部品にRFIDタグを取り付けることで、入庫・出庫時に一括で読み取れるため、リアルタイムで正確な在庫数を把握できます。
これにより、欠品や過剰在庫のリスクを抑え、在庫コストの削減につながります。
棚卸管理
定期的な棚卸作業は、多くの人手と時間を必要とする負担の大きい業務です。
RFIDを導入すれば、ハンディリーダーやゲート式リーダーで商品を一括して読み取れるため、従来の目視確認やバーコードスキャンと比べて大幅に効率化できます。
その結果、作業時間を短縮できるだけでなく、カウントミスの削減にもつながります。
会計・レジ業務の効率化
小売業では、RFIDタグを使った無人レジやセルフレジの導入が進んでいます。
商品を一つずつスキャンする必要がなく、袋に入ったままでも一括で読み取れるため、会計のスピードが格段に上がります。
そのため、待ち時間の削減やレジ人員の削減など、店舗運営の効率化が可能になります。
関連記事▼
備品管理
工具や事務用品、計測器など、社内の備品管理にもRFIDは有効です。
タグを取り付けることで、貸出状況や返却履歴を自動で記録でき、紛失や不正利用を防止できます。
特に工場や医療機関など、多数の備品を扱う現場では、管理工数の削減や安全性の向上に貢献します。
トレーサビリティ(流通経路の把握)
RFIDは商品の流通経路を追跡する「トレーサビリティ」にも活用されています。
製品がどの工程を経て消費者に届いたのかを可視化できるため、品質保証やリコール対応の迅速化に役立ちます。
特に食品や医薬品など、安全性が重視される分野ではその有用性が高く、導入の動きが広がっています。
RFID導入を成功させるポイント
RFIDは正しく設計・導入すれば大きな効果を発揮しますが、準備不足や選定ミスがあると期待通りの成果につながらないこともあります。
ここでは、導入を成功に導くために押さえておきたいポイントを解説します。
導入目的を明確にする
RFIDを導入する際には、まず「どの課題を解決したいのか」を明確にすることが欠かせません。
たとえば「在庫管理の効率化」「会計のスピード化」など、具体的な目標を定めることで、投資効果を正しく測定でき、システム設計もぶれなくなります。
利用環境に適したタグを選定する
RFIDタグには多様な種類があり、利用環境に合わないタグを選んでしまうと性能を十分に発揮できません。
特に金属や水が多い環境では、通常のタグでは読み取りが難しいため、「防水タグ」や「金属対応タグ」などの特殊タイプが必要です。
現場環境に応じた適切なタグ選びは、運用の安定性を大きく左右します。
周波数帯とリーダー機器の相性を確認する
RFIDは周波数帯ごとに特徴が異なり、それに対応するリーダー機器も使い分ける必要があります。
HF帯は交通系ICカードやスマートフォンで利用されることが多く、近距離での安定した読み取りに適しています。
一方、UHF帯は物流や在庫管理など広い範囲をカバーする場面でよく使われます。
導入目的に合った周波数帯と、それに対応するリーダーの組み合わせを確認することが重要です。
コストと効果のバランスを見極める
RFID導入では、タグ単価やリーダー機器の費用だけでなく、システム開発費やランニングコストも考慮する必要があります。
初期投資が大きくても、長期的に業務効率化や人件費削減につながるのであれば費用対効果は十分に見込めます。
逆に、目的が不明確だとコストばかりかかり、効果が見えづらくなるリスクがあります。投資回収のシミュレーションを事前に行うことが大切です。
システム連携と標準化を意識する
RFIDを単独で導入しても、既存のPOSやERPと連携できなければ、現場で二重入力やデータの分断が発生する可能性があります。
また、国際規格への準拠や将来的な拡張性を意識しておかないと、後に互換性の問題が出てくる場合もあります。
システム全体を俯瞰して、スムーズに連携できる設計が欠かせません。
運用体制と教育を整える
RFIDを導入しただけでは十分な効果は得られません。現場で活用するには、以下のような基本動作の教育が欠かせません。
- リーダーの操作手順
- タグの正しい貼付位置・向き
また、棚卸や入出庫時の読み取りフローを標準化したマニュアルを作成し、「読み取り漏れがあった場合の確認方法」「タグが破損した際の交換手順」などの対応ルールも整備しておく必要があります。
この仕組みを現場に浸透させることで、安定した運用と効果的な活用が可能になります。
RFIDを使わない無人決済店舗システム『TOUCH TO GO』
RFIDは便利な技術ですが、導入にはタグの貼付やリーダー機器の設置といった負担が避けられません。
一方で、TOUCH TO GOの無人決済店舗システムは、カメラとセンサーを用いてお客様と商品を自動で認識する仕組みを採用しています。
そのため、商品一つひとつにタグを取り付ける必要がなく、日々のオペレーションに余計な工程を加えずに導入可能です。
特にコンビニやスーパーなどの「取扱商品が多い」「商品が頻繁に入れ替わる」業態にとって、運用面の負担を大きく軽減できます。
RFIDの導入に迷っている方や、別の選択肢を探している方は、ぜひTOUCH TO GOの無人決済システムをチェックしてみてください。
TOUCH TO GO の無人決済店舗システムは、カメラとセンサーでお客様と商品を自動で認識。商品の読み取りなどのレジ操作は不要で、待ち時間ゼロの快適な購買体験を提供できます。
人手不足対策・コスト削減に強いシステムの導入を検討している方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/
まとめ
RFIDは非接触で情報を読み取れる技術として、在庫管理やトレーサビリティなど幅広い分野で活用が進んでいます。
導入にはコストや環境要因といった課題もありますが、タグの低価格化や規格整備により普及の環境は整いつつあります。
導入にあたっては「目的の明確化」「適切なタグや周波数帯の選定」「システム連携」が成功のカギです。
適切に活用すれば、業務効率化やDX推進を支える有力な技術となるでしょう。
関連記事▼
TOUCH TO GO の無人決済店舗システムは、カメラとセンサーでお客様と商品を自動で認識。商品の読み取りなどのレジ操作は不要で、待ち時間ゼロの快適な購買体験を提供できます。
人手不足対策・コスト削減に強いシステムの導入を検討している方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/