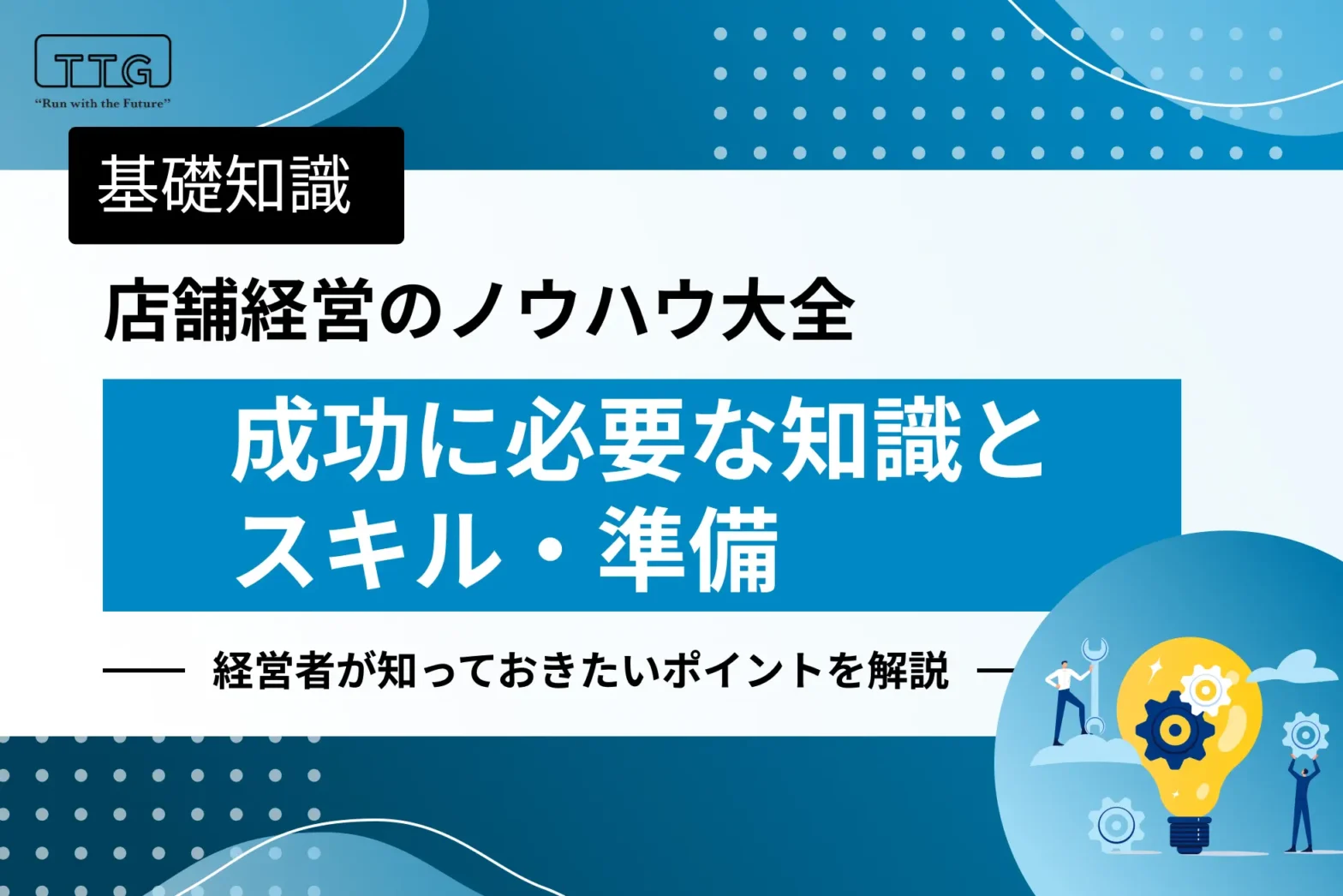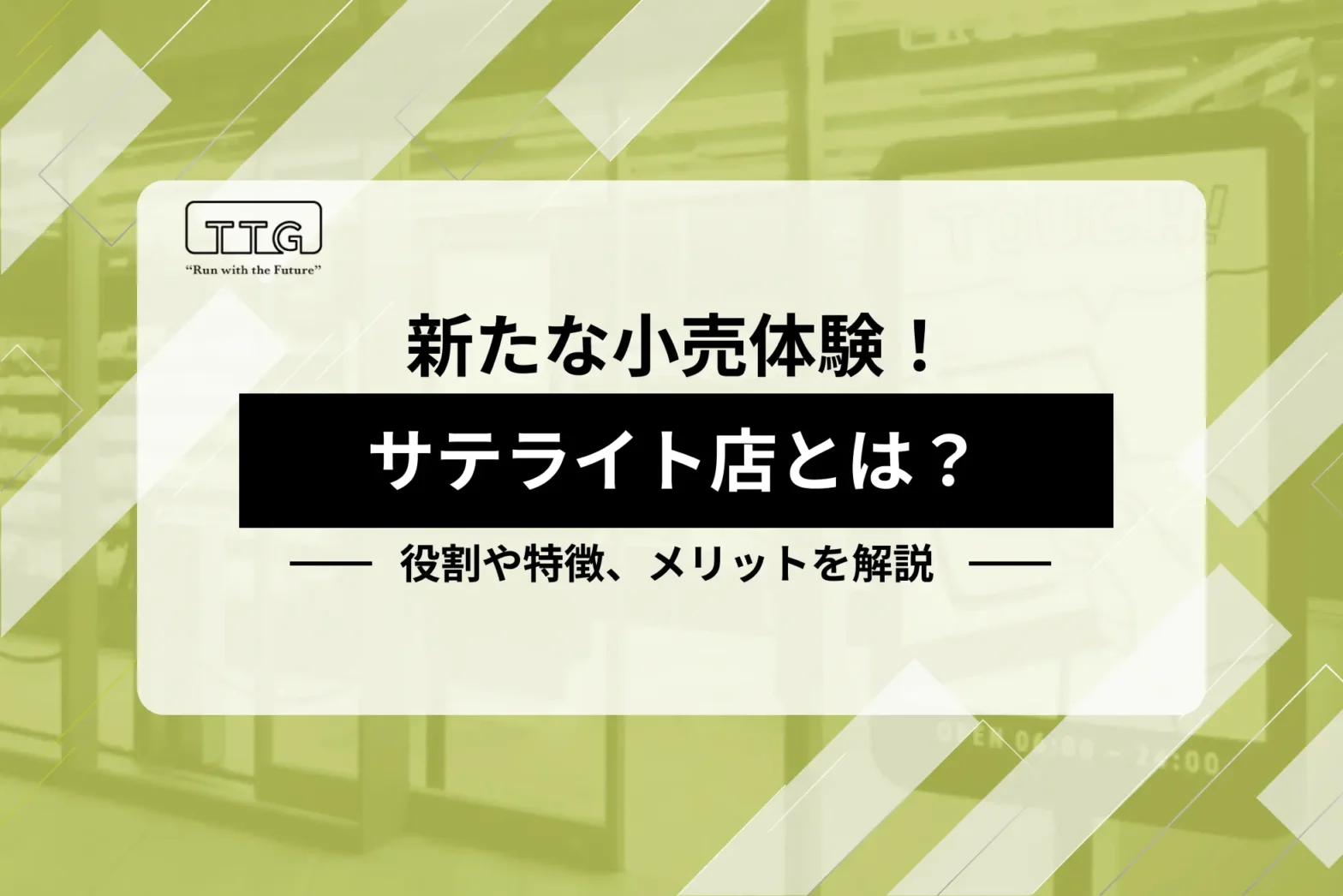Category
こんにちは。無人決済店舗システムを提供しているTOUCH TO GO 編集部です。
「求人を出しても応募が集まらない」、「採用してもすぐに離職してしまう」といった課題に直面している企業は少なくありません。
特に中小企業においては、人材確保そのものが事業の成長を左右する重要な経営課題となっています。
背景には、労働人口の減少や若年層の働き方に対する意識の変化など、従来の採用活動では対応しきれない構造的な要因があります。
そのため、単に募集を強化するだけでなく、採用手法や企業としての姿勢自体を見直すことが求められています。
本記事では、採用難の現状を踏まえたうえで、経営者が実践できる具体的な対策を紹介します。
関連記事▼
監修者プロフィール

2019年に株式会社TOUCH TO GOを設立。無人決済店舗システムを提供し、次世代型小売の拡大に取り組んでいる。
目次
採用難の現状とその背景
企業の成長を支える人材確保は、今や最も大きな経営課題のひとつです。
とくに地方や中小企業においては、慢性的な人手不足が続いており、「人がいない」「採用できない」状態に悩む企業は少なくありません。
なぜこれほどまでに採用が難しくなっているのか、その背景をみていきましょう。
労働人口の減少と少子高齢化
総務省の調査によると、日本の生産年齢人口(15〜64歳)は、1995年をピークに年々減少傾向にあります。
日本の総人口は2050年には2020年より約2,000万人以上減少するとも言われており、そもそも働ける人の数が足りないという構造的な問題が存在します。
その結果、働き手の総数が縮小し、企業間での人材獲得競争はますます激しくなっています。
特に中小企業は、大手に比べて条件や知名度で不利になりやすく、採用が難航しやすい傾向があります。
(出典)
総務省|生産年齢人口の減少
2050年までに「プラス5歳活躍社会」実現を
若年層の就業意識の変化
かつては「安定した会社」「長く勤められる環境」が重視されていましたが、近年では若年層を中心に、働きがいや柔軟な働き方、プライベートとの両立を重視する人が増えています。
大手企業であっても、職場環境に不満を持てばすぐに転職を選ぶ人も多く、「条件がいいだけでは続かない」時代になってきました。
特にZ世代(1990年代後半〜2000年代生まれ)の求職者は、以下のような目に見えない部分に価値を感じる傾向があります。
- 企業理念に共感できるかどうか
- 自己成長の機会があるかどうか
- 風通しが良いかどうか
こうした価値観の多様化に対応できなければ、採用はますます難しくなるでしょう。
中小企業特有の課題
中小企業は、大手に比べて知名度・待遇・福利厚生の面で不利とされることが多く、同じ条件で人材を奪い合えばどうしても後手に回りがちです。
とくに地方企業では、「そもそも自社の存在を知られていない」「魅力を伝える場がない」といった課題が顕在化しやすくなっています。
また、人事部門が小規模で採用専任担当がいないケースも多く、求人広告を出しただけで終わってしまうなど、戦略的な採用活動を行いにくい土壌があることも採用難の一因となります。
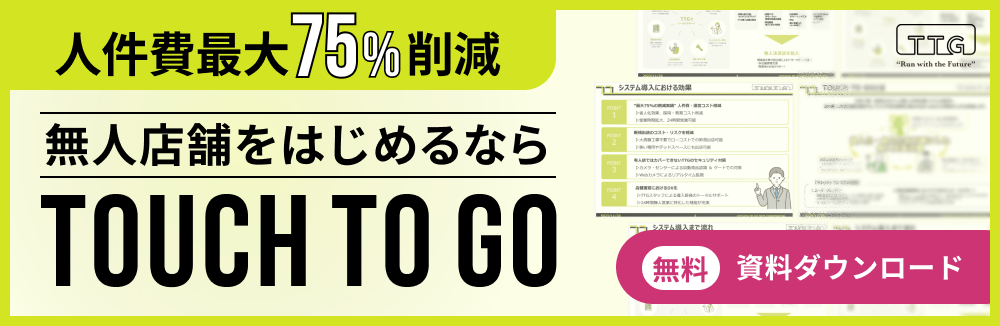
TOUCH TO GO の 無人決済店舗システムは、カメラで人物をトラッキングし、どの棚のどの商品が何個お客様の手に取られたかをセンサーで感知します。
店舗の省人化・人件費削減をご検討中の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/
採用難を乗り越えるための具体的な対策
採用が難しいとされる時代でも、人材を安定的に確保できている企業は存在します。
そうした企業に共通するのは、採用活動を「人を集める作業」ではなく、「企業の価値を伝え、選ばれる仕組みづくり」として捉えている点です。
ここでは、限られた採用資源でも効果を出すために、企業が取り組める実践的な対策を紹介します。
採用手法の多様化
従来の求人媒体への掲載やハローワーク頼みの採用活動では、十分な応募が得られないケースが増えています。そのため、採用チャネルを広げる取り組みが必要です。
具体的には、以下のような手法が挙げられます。
- ダイレクトリクルーティング(候補者に直接アプローチする方法)
- 社員からの紹介によるリファラル採用
- SNSや動画を活用した情報発信型の採用活動
このような多様な手段を組み合わせることで、求職者との接点を増やすことが可能になります。
求人票を出すだけで終わらせるのではなく、候補者と接点を持つ仕組みを複数持つことが、今後の採用活動では重要になります。
採用ブランディングの強化
求職者は企業を選ぶ際、「何をしている会社か」だけでなく、「どのような価値観で運営されているか」「社内の雰囲気はどうか」といった情報にも注目しています。
そのため、企業側にも「選ばれるための情報発信」が求められるようになっています。
自社のホームページに採用専用ページを設け、社員の声や働く環境、キャリアのイメージを伝えるコンテンツを整備することは、応募率やマッチングの精度を高める効果があります。
知名度の高くない中小企業こそ、「内部の様子が見える情報」を積極的に発信することで、他社との差別化を図ることができます。
労働環境と待遇の見直し
採用において、給与や福利厚生といった条件面の整備は依然として大きな要素です。ただし、現代の求職者はそれだけで企業を選んでいるわけではありません。
働き方の柔軟性や休暇制度の取りやすさ、キャリア形成の支援など、長期的に働き続けられる環境を重視する傾向が強まっています。
そこで、「テレワーク」や「時短勤務」、「資格取得支援制度の導入」など、自社の体制に合った範囲で改善できるポイントを洗い出し、実行に移すことが採用力の底上げにつながります。
経営者自身の発信
採用活動において経営者が自ら関わることは、企業規模に関わらず大きな意味を持ちます。
求職者にとって、企業のトップがどのような考えを持ち、どんなビジョンを描いているかを知ることは、応募動機や入社後の定着意欲に影響を与える要素のひとつです。
たとえば、以下のような取り組みは、企業への信頼感を高める効果があります。
- 採用面接に経営者が一部同席する
- 求職者向けにメッセージ動画を用意する
- ブログやSNSを通じて企業の姿勢を発信する
とくに中小企業やスタートアップでは、経営者の発信が求職者の共感を呼びやすく、応募や入社のハードルを下げるきっかけにもなります。
採用活動を継続的に改善するための視点
市場環境や求職者のニーズは常に変化しており、それに合わせて採用活動も柔軟にアップデートしていく必要があります。
ここでは、採用力を長期的に維持・向上させるための基本的な考え方を紹介します。
数値をもとに改善サイクルをつくる
採用活動は感覚ではなく、データをもとに振り返ることで精度が高まります。特に、以下のような数値を記録・分析することで、ボトルネックとなっている部分を客観的に把握できます。
- 応募数
- 面接通過率
- 内定承諾率
- 定着率
たとえば、応募は集まっているのに内定につながらない場合は、「面接の進め方」や「選考基準」に改善の余地があるかもしれません。
こうした仮説と検証を繰り返しながら、小さな改善を重ねていくことが安定的な採用につながります。
社内の採用意識を共有する
採用は人事や経営層だけの仕事ではなく、現場の社員も含めた組織全体で取り組むべき課題です。
社員一人ひとりが「自分たちの仲間を迎える」という意識を持つことで、紹介の協力や受け入れ体制の整備が進み、定着率の向上にもつながります。
そのためには、社内ミーティングや社内報などを通じて、採用活動の目的や状況を共有し、全社的な関心を高めることが重要です。
採用活動を支える環境づくりも重要
採用の成果は、単に応募数や選考プロセスだけで決まるものではありません。求職者が「この会社で働きたい」と思えるかどうかは、職場環境や社内文化にも大きく左右されます。
たとえば、柔軟な勤務制度や風通しのよいコミュニケーション体制があると、それだけで安心感を与える要素になります。
また、オンボーディング(入社初期の受け入れ支援)が整っている企業は、早期離職を防ぎやすく、紹介や口コミによる応募にもつながりやすくなります。
採用に力を入れると同時に、「入社後に活躍できる環境」があるかを見直すことも、長期的な採用成功のカギとなります。
採用の外部リソース活用も視野に入れる
すべての採用活動を社内だけで完結させることが難しい場合、外部の力をうまく活用することも有効です。
特に中小企業では、「人事の専任担当者がいない」もしくは「兼務で十分な時間が割けない」という状況も珍しくありません。
そこで、採用支援を行う民間のエージェントや採用代行(RPO)などのサービスを活用することで、以下のような業務を効率化することが可能になります。
- 求人票の作成
- 応募者対応
- 面接日程の調整
外注により自社の手間を減らすだけでなく、求職者とのコミュニケーションの質を保つ効果も期待できます。
また、自治体や商工会などが提供する無料または低コストの人材支援制度もあります。
採用活動に関する相談窓口やセミナー、助成金制度の紹介など、利用できる外部資源は少なくありません。
情報収集を継続して自社に合うものを選んで取り入れていく姿勢が、採用難を乗り越える助けになります。
まとめ
労働人口の減少や働き方の多様化が進むなかで、従来のやり方だけでは人材を安定的に確保することが難しくなっています。
そのためには、採用チャネルの見直しや採用ブランディング、労働環境の改善など、企業側の在り方を問い直す取り組みが必要です。
また、採用後を見据えた体制づくりや、採用活動そのものを継続的に改善していく仕組みづくりも欠かせません。
中小企業であっても、工夫次第で採用力を高めることは十分に可能です。現場に合った現実的な対策を取り入れ、自社に合った形で採用活動を見直していきましょう。
関連記事▼
TOUCH TO GO の 無人決済店舗システムは、カメラで人物をトラッキングし、どの棚のどの商品が何個お客様の手に取られたかをセンサーで感知します。
店舗の省人化・人件費削減をご検討中の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/