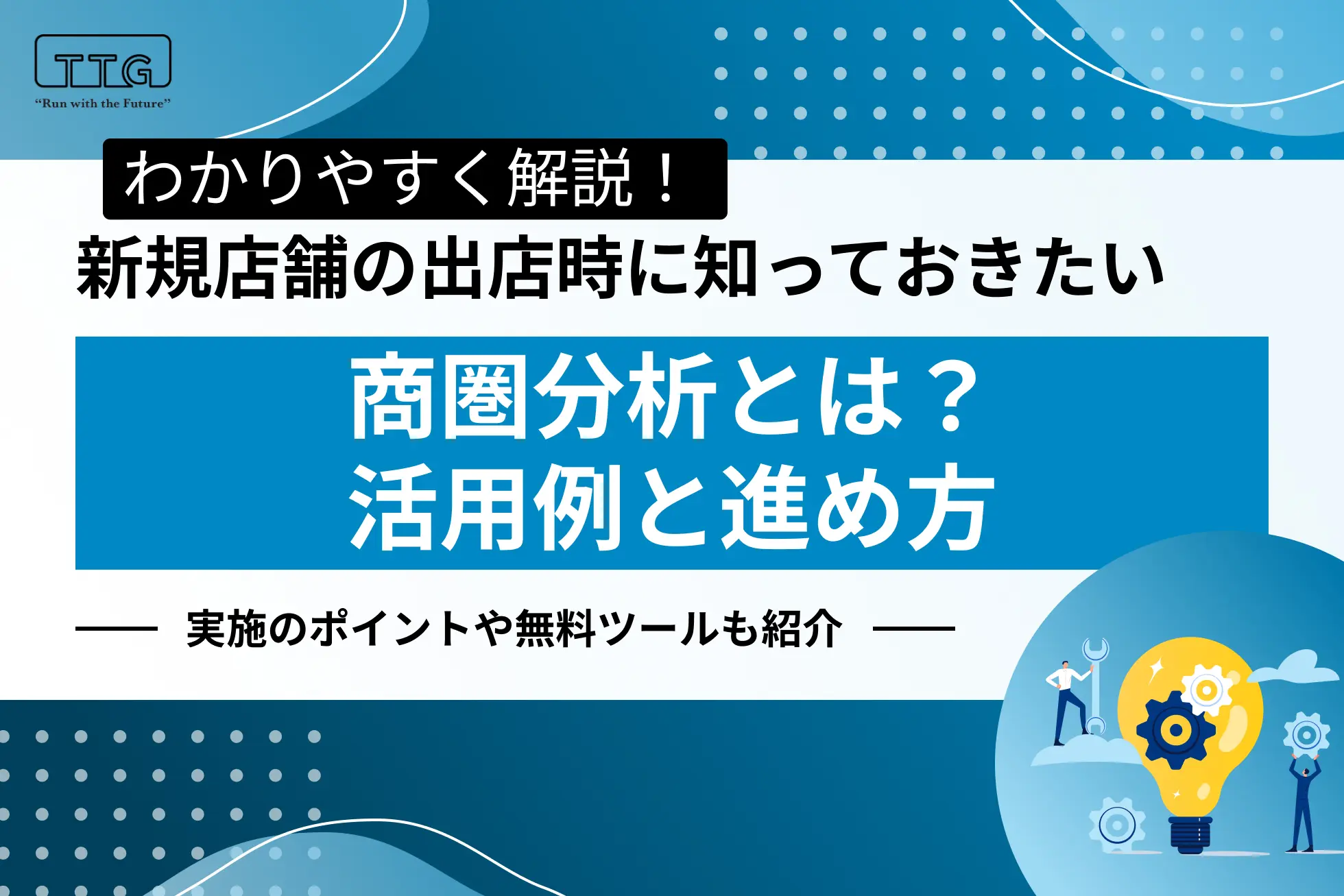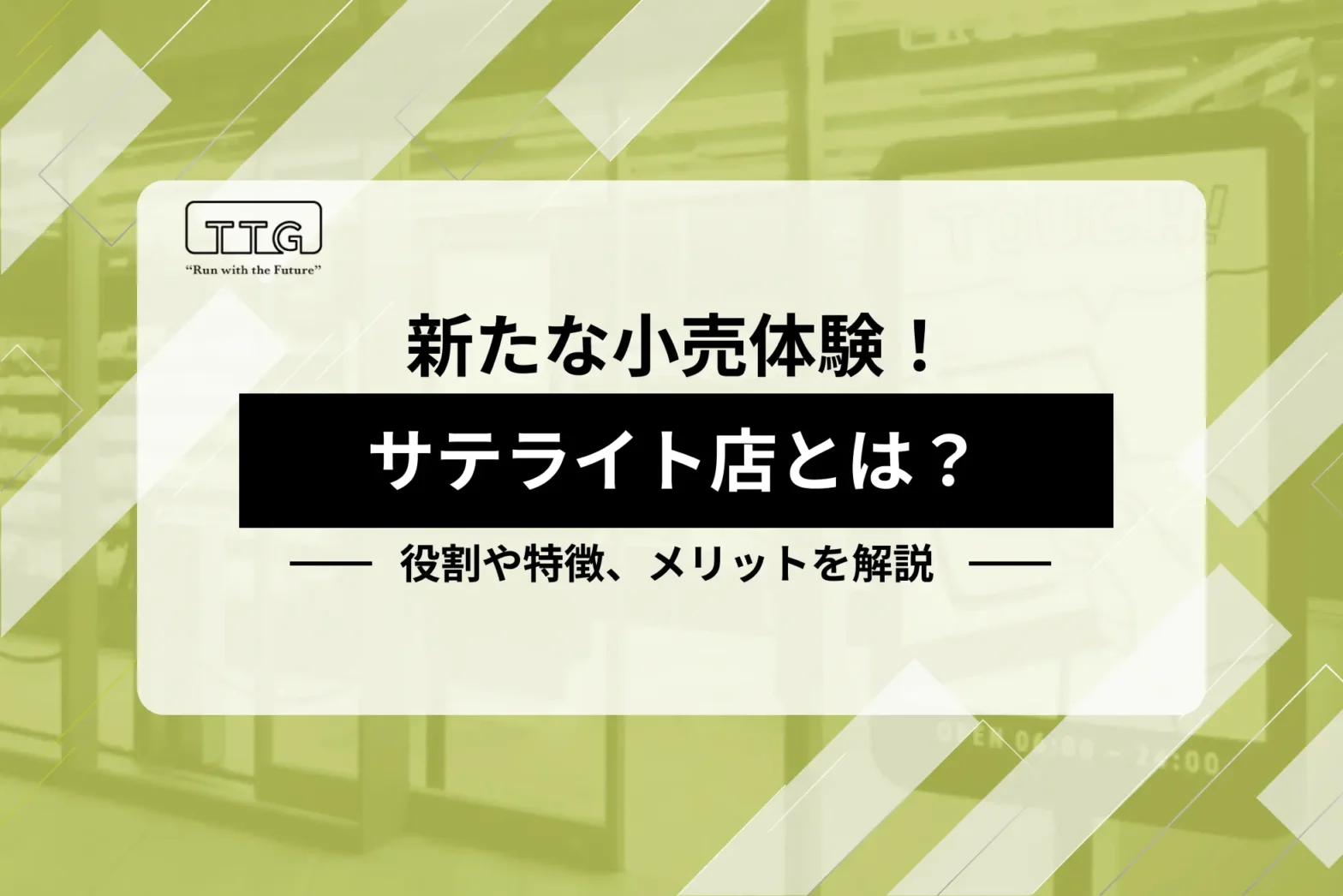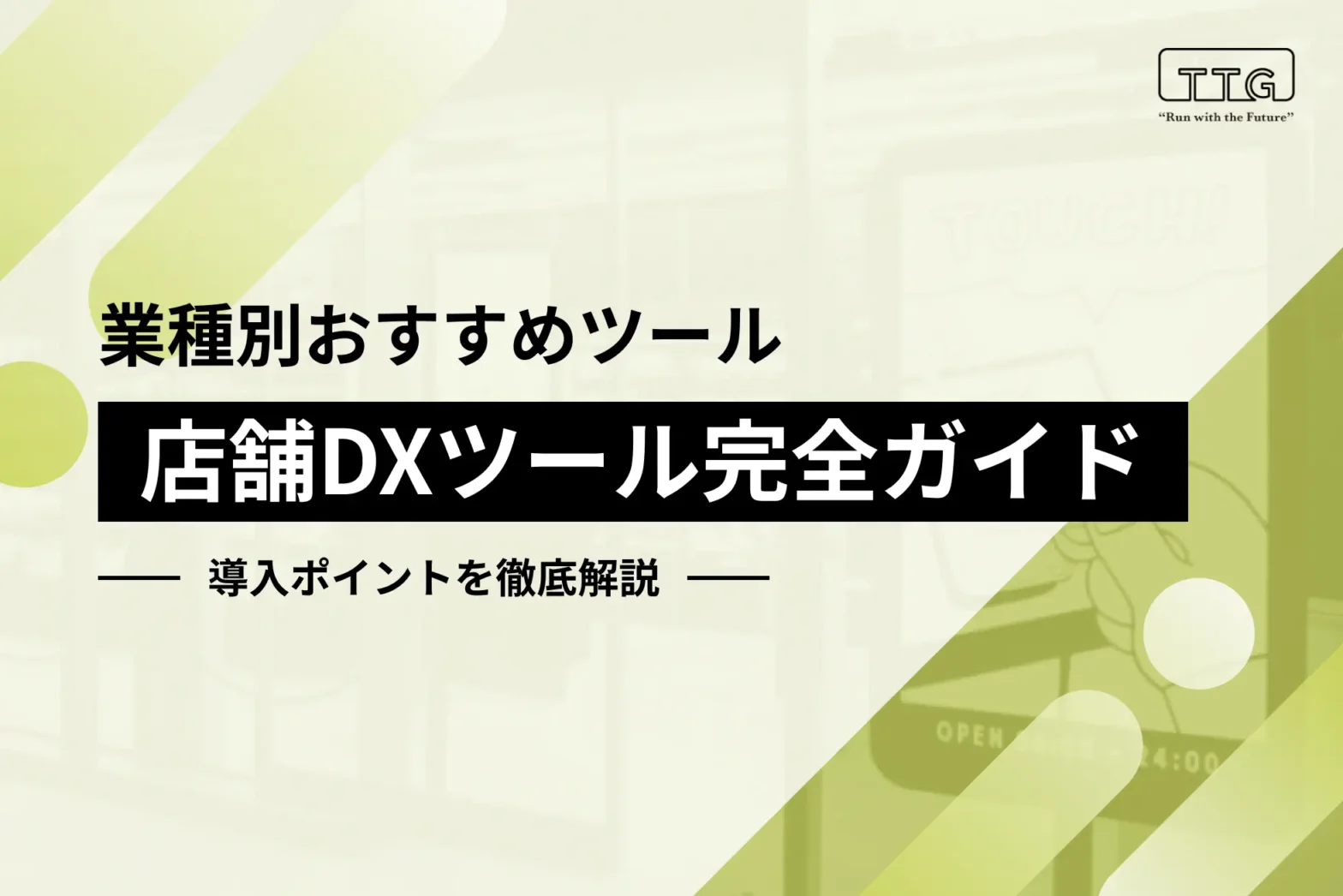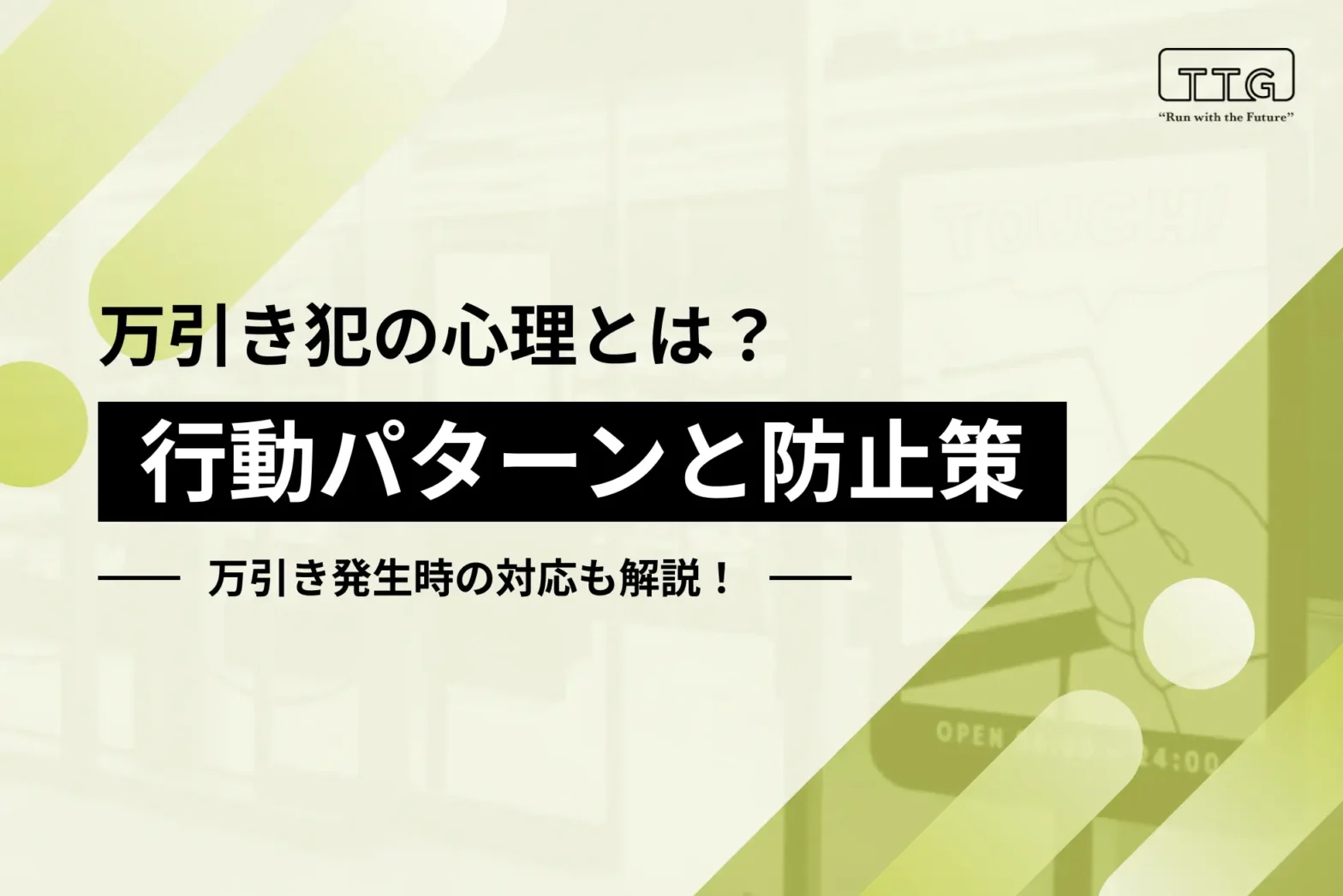Category
こんにちは。無人決済店舗システムを提供しているTOUCH TO GO 編集部です。
新店舗の出店時に欠かせない「商圏分析」。
ターゲットとなる顧客層の生活圏やニーズ、地域の特性をデータで把握することで、正しく戦略的な判断が可能になります。
今回の記事では、商圏分析の概要や進め方、活用シーンを解説します。
商圏分析を実施する際のポイントや無料ツールも紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
関連記事▼
監修者プロフィール

2019年に株式会社TOUCH TO GOを設立。無人決済店舗システムを提供し、次世代型小売の拡大に取り組んでいる。
目次
商圏分析とは
商圏分析(しょうけんぶんせき)とは、販売や営業において以下の3つを目的におこなわれるマーケティング戦略の手法の一つです。
- 出店候補地や既存店舗の売上予測
- ターゲットとなる顧客層や分布の可視化
- 効果的な販促エリアの設定
そもそも「商圏」とは、ある店舗への来店の可能性がある地理的な範囲、もしくは日常的に行動しているエリアのことを指します。
商圏分析では、出店を予定する地域に「どのような人が住み」「どれくらいの消費が見込めるか」をデータに基づいて把握します。
感覚や経験ではなく数値をもとに判断することで、出店リスクを最小限に抑え、より効果的な集客戦略を立てることが可能になります。
商圏分析でわかること
商圏分析を行うことで、出店戦略や販促計画に必要なさまざまな情報をデータで把握できるようになります。具体的にわかることは、以下のとおりです。
| 分析項目 | わかること |
| 市場規模の把握 | 人口・世帯数・購買力・年収などの市場ポテンシャル |
| 消費支出・購買傾向 | 商品別の支出額や購買頻度・時間帯などの動向 |
| 顧客分布・来店エリア | 来店者の居住地・年齢・性別などの属性と分布 |
| 競合状況・立地特性 | 競合店舗の位置・数・業種や周辺エリアの特徴 |
| 売上予測・収益シミュレーション | 来店数・売上予測、ハフモデルなどによる推定 |
| 販促・マーケティング活用 | ターゲティング広告や販促施策の精度向上 |
| 出店・事業戦略判断 | 新規出店可否、既存店改善、設備投資判断 |
| 継続的な効果検証 | 人口や競合の変化把握とPDCAの支援 |
上記のような情報を活用することで、「どこに・何を・どのように」出店・販売していくべきかという判断を、客観的に導き出せるようになります。
とくに新規出店の際には、競合店舗の状況や地域住民の属性、購買傾向などを踏まえることで、立地や店舗規模の選定に有効な材料となります。
エリアマーケティングとの違い
商圏分析と似ている手法に「エリアマーケティング」があります。この2つは一見似ているものの、目的と活用範囲が異なります。
商圏分析は、おもに出店や営業戦略の判断材料として地域特性を調査・分析し、データで把握することです。
一方、エリアマーケティングは、商圏分析で得られた結果を活かしたマーケティングを指します。
つまり、商圏分析は「判断のための前工程」、エリアマーケティングは「商圏分析の結果を活かした実践フェーズ」となります。
商圏分析に用いられるGISとは
高精度な商圏分析の実施に欠かせないのが、「GIS(地理情報システム)」と呼ばれるツールです。
GISは、デジタルの地図上に人口統計などの付加情報を重ねて、視覚的に表示・分析できるのが大きな特徴です。
GISを商圏分析に用いることで、以下のような分析が可能になります。
- 移動手段ごとの商圏の可視化
- 地域ごとの予測モデルの構築
- ターゲット層が集中するエリアの特定
なお、GISは商圏分析以外にも、科学的調査や土地、道路などの地理情報の管理、都市計画などにも活用されています。
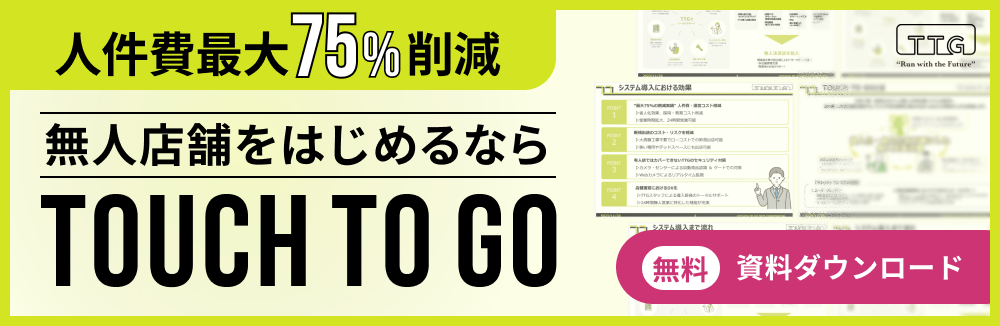
無人決済店舗システム「TOUCH TO GO」なら、限られたスペースにも出店が可能です。来店者の動きはカメラで自動的にトラッキングされ、手に取られた商品は棚のセンサーが検知。最小人数での店舗運営を実現できます。
店舗の省人化・人件費削減をご検討中の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/
商圏分析の重要性
商圏分析は、新規出店やマーケティング施策の決定に欠かせない要素です。
というのも、商圏内の人口や競合状況は常に変化しており、以前は良い立地だった場所が、今でもその条件であるとは言い切れないからです。
そのため、最新のデータによる正確な情報・分析結果がなければ、「立地が良さそう」というだけの理由で出店すると、失敗するかもしれません。
たとえ人通りが多いエリアでも、ターゲット層にあわなければ、経営不振に落ちいる可能性は高くなります。
また、商圏分析は出店候補地の選定だけではなく、既存店の販促強化や売上改善、設備投資の判断にも役立ちます。
このように、商圏分析は店舗開発や販促施策、経営判断など幅広く活用できる大切なプロセスなのです。
商圏分析に活用できるデータ
商圏分析に活用できるデータには、次のようなものがあります。
【公的統計データ一覧】
| データ種別 | 内容・用途 |
| 人口統計データ | 国勢調査に基づく、総人口・年齢・性別・世帯情報 |
| 年収別世帯数推計 | 住宅・土地・賃金統計等を元に推計された世帯の購買力指標 |
| 将来人口推計/未来人口データ | 国勢調査+社会保障研究所データ等により将来の地域人口予測を把握できる |
| 家計・消費行動データ | 総務省家計調査や推計消費額データにより、商品・サービス別支出傾向を分析可能 |
| 商業統計・商業人口データ | 小売業の事業所数、従業員数、売上額など商圏内の業況を把握 |
| 昼間人口/メッシュ統計 | 昼間の働く人や通行人の人数を時間帯別・エリア別に分析 |
上記の国勢調査や家計調査などの公的統計は、地域全体の基本構造を把握するのに適しており、信頼性の高いベースデータとなります。
また、近年ではIT技術の発達により位置情報やPOSデータを取得することが可能になり、より実践的な分析に役立てることも可能です。
自社もしくは外部で活用できるデータの一覧は以下のとおりです。
【自社・外部データ一覧】
| データ種別 | 内容・用途 |
| 競合店舗データ | 出店件数・業種・位置情報を地図上で可視化し競合環境を評価 |
| 自社POS・顧客データ | 実際の来店者属性・購買履歴と統計を重ねて地域特徴を深化 |
| 位置情報ビッグデータ | GPS・Wi‑Fiなどの実際の人流を把握し、商圏内での行動パターンの可視化 |
| 地理・交通ネットワークデータ | 道路網や公共交通など移動経路に影響する要素を考慮 |
| 文化・ライフスタイルデータ | 地域の生活習慣、風習、商習慣など定性要素の分析で施策精度向上 |
なお、必ずしもすべてのデータを使う必要はありません。どのデータを使うかは目的次第で異なり、目的に応じて組み合わせることで、精度の高い商圏分析が可能になります。
商圏分析のやり方を7ステップで解説
ここからは、商圏分析の具体的なやり方を7ステップで解説します。
①自社データのマッピング
自店舗の位置や顧客分布などのデータを地図上に展開します。
地図上にデータを落とし込むことで、顧客がどこから来ているかやどのエリアが強いかなどの傾向を可視化できます。
また、競合店の場所も地図に落とし込み、位置関係やエリア状況を俯瞰します。
②商圏エリアの把握・設定
ステップ①の状況を踏まえて、自店舗の商圏エリアを把握します。
たとえば、売上の65%が2km以内の顧客からの発生であれば、商圏エリアを2kmと設定します。
なお、アンケート調査や実地調査、商圏シミュレーションなどの情報があれば、それらも活用します。
③商圏エリアのデータを取得
次に、設定した商圏エリアの特性を調査し、データを取得していきます。
人口統計・世帯年収・年齢構成・消費支出などの公的統計や、競合データ・POSデータなどを組み合わせて、仮説検証を繰り返しながら分析します。
④自店舗の強み・弱みを数値化
競合店舗との比較や、商圏内の需要に対する自店舗のカバー率、売上構成などから、自社の強みや弱みを分析します。
ここでは、以下のようにできるだけ具体的に検証することが大切です。
【例】
3km圏内に30〜40代が多い人口エリアでは、客単価が高く売上も安定する一方、同じ商圏人口でも30〜40代が少ない地域では売上が伸びにくい傾向がある。
⑤エリア別の商圏レポートを作成
必要なデータが揃ったら、エリア別に商圏レポートを作成します。
地図やグラフなどを活用し、視覚的にわかりやすく表現するのがポイントです。
他のエリアとの商圏分析結果もあわせて確認し、自店舗の全体の平均との比較なども検証してみましょう。
⑥マーケティング戦略の実施
商圏レポートを活用して、チラシ配布エリアの決定、Web広告のターゲティング設定、商品構成の最適化など、具体的な施策を実施していきます。
⑦PDCAの継続
マーケティング戦略の方向性が決まり実施したあとは、成果や課題点を定期的に見直して精度を高めていきましょう。
一度分析して終わりではなく、PDCAを回しながら継続的にデータを収集・検証していくことが大切です。
関連記事>>店舗開業の流れ完全ガイド|初めてでも安心のステップと必要な手続き
商圏分析の活用例・活用シーン
次に、商圏分析の活用例と活用シーンを紹介します。どのように活用できるのか、具体的にみていきましょう。
新規店舗開発
商圏分析の代表的な活用シーンといえるのが、新規店舗開発と新規出店時です。
新たに出店を検討する際、候補地をどこにするかという判断は売上を左右する重要な要素となります。
たとえば、同じ市内にある2つの候補地を比較する場合、商圏分析によって以下のような判断が可能になります。
| 比較項目 | A地点(駅前) | B地点(郊外) |
| 人通り・昼間人口 | 多い | 少なめ |
| 周辺環境 | オフィス街 ビジネス層中心 |
住宅地 30〜40代ファミリー層中心 |
| 競合の数 | 多い(競合店が集中) | 少ない(商圏内に競合が少ない) |
| 単価・購買傾向 | 単価はやや低く、回転率重視 | 単価が安定し、リピートにつながりやすい |
| 商品との相性 | 一部適合するが差別化が難しい可能性 | 商品ラインナップと親和性が高い |
上記の結果であれば、中長期的に安定した売上が見込めるのはB地点と判断される可能性が高いと考えられます。
このように、商圏ごとの人口構成や競合状況、生活スタイルを数値で把握することで、より確度の高い出店判断が可能になります。
販促戦略
販促エリアの選定やアプローチ方法の最適化にも、商圏分析が役立ちます。
たとえば、過去のキャンペーン結果と地域属性を照らし合わせることで、「どのエリアやターゲット層で反応が高かったか」を把握できます。
ここでは、例としてチラシ配布エリアの最適化についてみていきましょう。
以下の表に、あるエリアで実施した「クーポン付きチラシキャンペーン」の分析結果をまとめました。
| エリア特性 | クーポン反応率 | 備考 |
| 20代単身世帯が多い住宅街 | 高い(約8%) | 若年層の来店率が高く、SNS拡散効果も見られた |
| 高齢者比率が高い地域 | 低い(約2%) | チラシの内容や配布媒体がターゲットと合っていなかった |
| 近隣に大学のある学生街 | 中程度(約5%) | 学生向け割引を明記した内容では一定の効果あり |
この分析結果では、若年層の比率が高い地域ほどクーポンへの反応が良いという傾向が把握でき、ターゲットの絞り込みや媒体選びの参考になります。
このように、商圏分析を販促戦略に活用すれば、属性に合ったエリアに販促を集中でき、無駄なコストを抑えつつ成果を最大化できます。
エリアごとの売上分析
同じ商品を取り扱っていても、商品のターゲットと商圏内のターゲット層があわない場合、売上は伸びにくくなります。
さらに、多店舗展開している場合、店舗ごとに売上の差が出るケースもめずらしくなく、原因の特定に悩む経営者も多いでしょう。
商圏分析は、エリアごとの売上分析を可視化する手段としても役立ちます。
たとえば、売場面積や商品構成は同じでも、商圏の違いによって売上に差が生じるケースがあります。
以下に2つの店舗の比較例を挙げてみます。
| 比較項目 | A店舗 | B店舗 |
| エリア属性 | 30〜40代の働き盛りの層が多いエリア | 高齢化が進んでいるエリア |
| 購買力 | 高い傾向 | やや低め |
| 商品との相性 | 働く世代向けの商品ラインナップと合致 | 高齢層にはややミスマッチ |
| 売上傾向 | 安定して高水準 | 伸び悩んでいる |
| 改善の方向性 | 現行戦略を継続・強化 | 商品構成や販促手法の見直しが必要 |
このように、エリアごとの属性やニーズを把握することで、売上差の背景にある要因を可視化でき、店舗ごとに最適な戦略を立てる手がかりになります。
商圏分析をおこなう際のポイント
商圏分析をおこなう際は、次の3つのポイントをおさえておきましょう。
- 定期的に実施する
- 常に仮説を立てて分析する
- 必要なデータを収集して活用する
以下で、それぞれ詳しく説明します。
定期的に実施する
商圏はずっと一定なものではなく、人口流動や競合の出店、都市開発などによって変化します。
そのため、商圏分析は一度おこなって終わりではなく、定期的に実施して戦略を見直すことが大切です。
その際、過去に作成したレポートと比較する内容にすると、そのエリアでどのような部分にどのような変化が生じたのかを把握しやすくなります。
常に仮説を立てて分析する
商圏分析を効果的なものにするには、まず「何のために分析するのか?」という目的を明確にすることが重要です。
たとえば、「新商品のターゲットにあうエリアを見つけたい」「売上が伸びない原因が知りたい」など、目指すべきゴールを設定します。
そのうえで、「20〜30代のファミリー層が多いエリアほど売上が良いのでは?」といった仮説を立てることで、重要なデータが明確になり、検証しやすくなります。
仮説がない状態で分析を進めると「何を明らかにしたいのか」が曖昧になり、集めたデータを活かしきれない可能性があります。
必ず目的を設定したうえで仮説を立て、分析に取り組むようにしましょう。
必要なデータを収集して活用する
商圏分析は、さまざまな角度から仮説・検証します。そのためにも、目的に応じたデータを幅広く収集して活用することが重要なポイントとなります。
まず、国勢調査や家計調査などの公的統計データは、地域の人口構成や世帯年収など、地域の基本的な特性を把握するのに役立ちます。
一方、地域のリアルタイムな動きや変化を捉えるには、自社のPOSデータやGPSを活用した位置情報データなども欠かせません。
商圏分析をおこなう目的に応じて、必要だと考えられるデータをすべて集めて活用することで、より実践的なものになります。
無料で使える商圏分析ツール3選
ここからは、商圏分析ツールを3つ紹介します。
商圏分析ツールには有料のものと無料のものがありますが、ここでは無料で提供されているツールに限定しました。
ツールによって機能や特長が異なるため、自社の課題解決につながるものを選びましょう。
jSTAT MAP
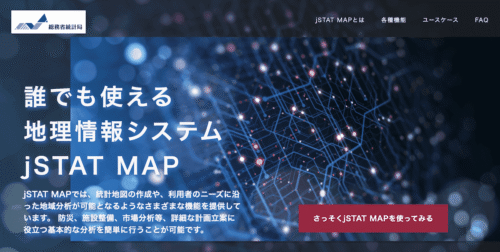
画像出典:jSTAT MAP
jSTAT MAPは、総務省統計局が提供するGIS(地理情報システム)で、国勢調査などの統計データを地図上に重ねて表示できます。
「エリア作成機能」「統計グラフ作成機能」など、直感的に使える便利な機能が用意されており、初心者でも操作しやすい設計です。
さらに、「レポート作成機能」では、分析結果をレポート形式で作成し出力までできるため、効率よく商圏分析レポートを作成できます。
RESAS

画像出典:RESAS
地域経済分析システム RESASは、経済産業省と内閣官房が提供している地域分析ツールです。
「マーケティングマップ」や「観光マップ」「人口マップ」などの分析メニューがあらかじめ用意されており、初めて利用する人でも直感で操作できるようになっています。
分析メニューの選択後に表示されたページで地域や表示年数、分類などの検索条件を指定すると、分析結果が表示されます。
完全無料で登録も不要なため、手軽に商圏分析ツールを使いたい方に便利なツールです。
MANDARA
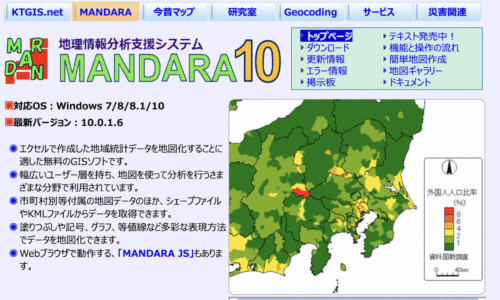
画像出典:MANDARA
MANDARAは無料で使える地理情報分析システムで、Excelで作成した地域統計データを地図化できます。
地図データのほか、シェープファイルやKMLファイルからデータを取得することも可能。
jSTAT MAPやRESASよりもカスタマイズ性が高いため、地理情報に詳しい方におすすめです。
TOUCH TO GOの無人決済システムなら狭小スペースでも店舗出店可能
新規店舗の出店には、物件探しから契約まで時間と費用がかかるのが一般的です。
とくに立地条件が良い場所は競争が激しく、希望通りのスペースを確保できない可能性もあります。
そこで、TOUCH TO GOが提供する無人決済システム「TTG-SENSE」なら、省スペースでもスムーズに出店できます。
たとえば、駅ナカやオフィスビルの一角など、これまで店舗展開が困難だった狭小エリアにも対応可能です。
商圏分析をおこなったうえで、「まずはミニマムな形でビジネスを始めたい」という方にもTOUCH TO GOの無人店舗がおすすめです。
省コストで立地を有効活用した出店を目指したい方は、ぜひ以下のリンクからプロダクトの詳細をチェックしてみてください。
プロダクトの詳細はこちらから>>TOUCH TO GO
まとめ
商圏分析は、新規出店や販促計画などのビジネスにおける重要な判断をデータに基づいておこなう手段です。
公的統計データや、自社もしくは外部で収集したデータを組み合わせることで、地域の特性やニーズを具体的に把握できるようになります。
感覚や経験に頼らず、より精度の高い戦略を立案し、店舗運営の成功を目指しましょう。
関連記事▼
無人決済店舗システム「TOUCH TO GO」なら、限られたスペースにも出店が可能です。来店者の動きはカメラで自動的にトラッキングされ、手に取られた商品は棚のセンサーが検知。最小人数での店舗運営を実現できます。
店舗の省人化・人件費削減をご検討中の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/