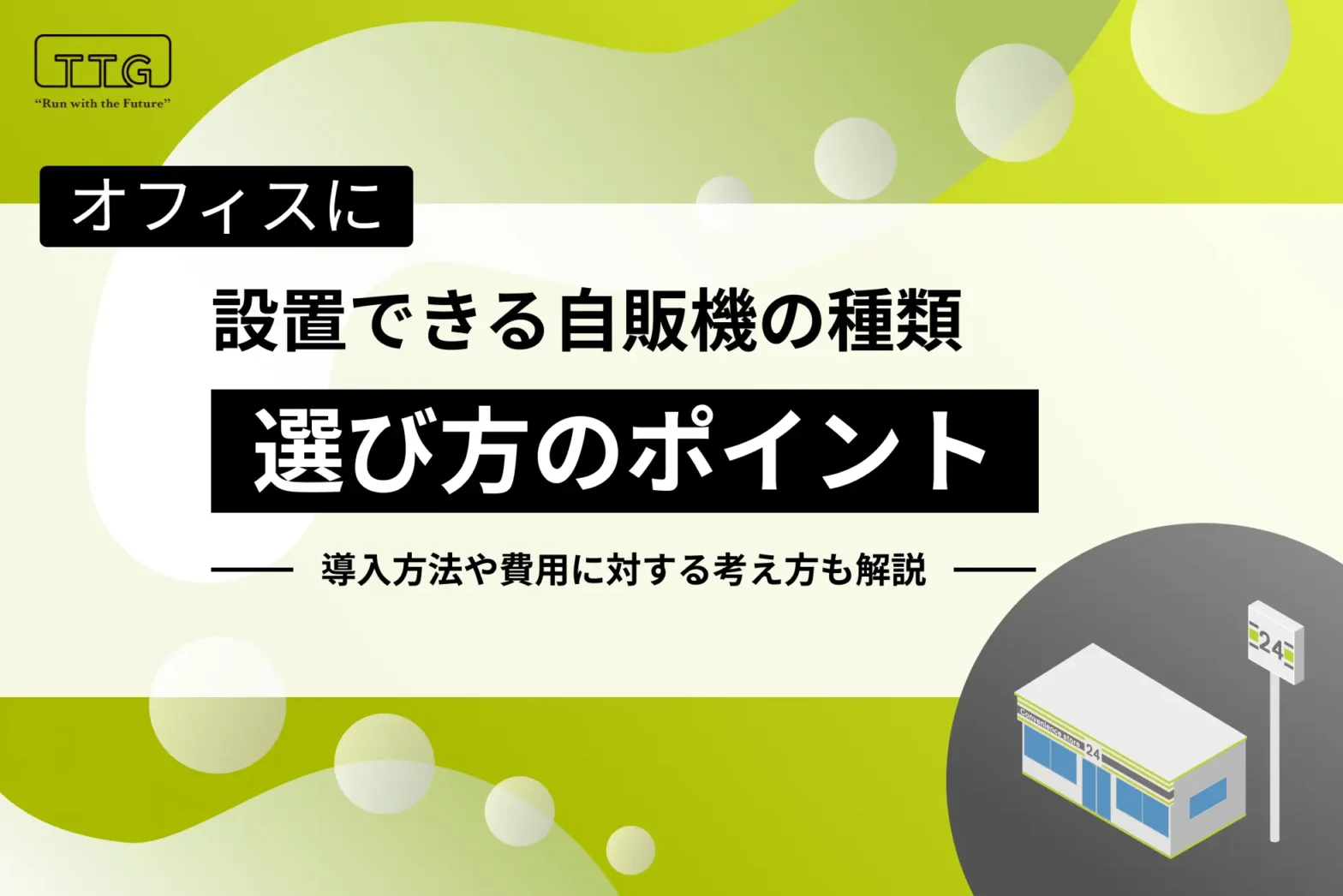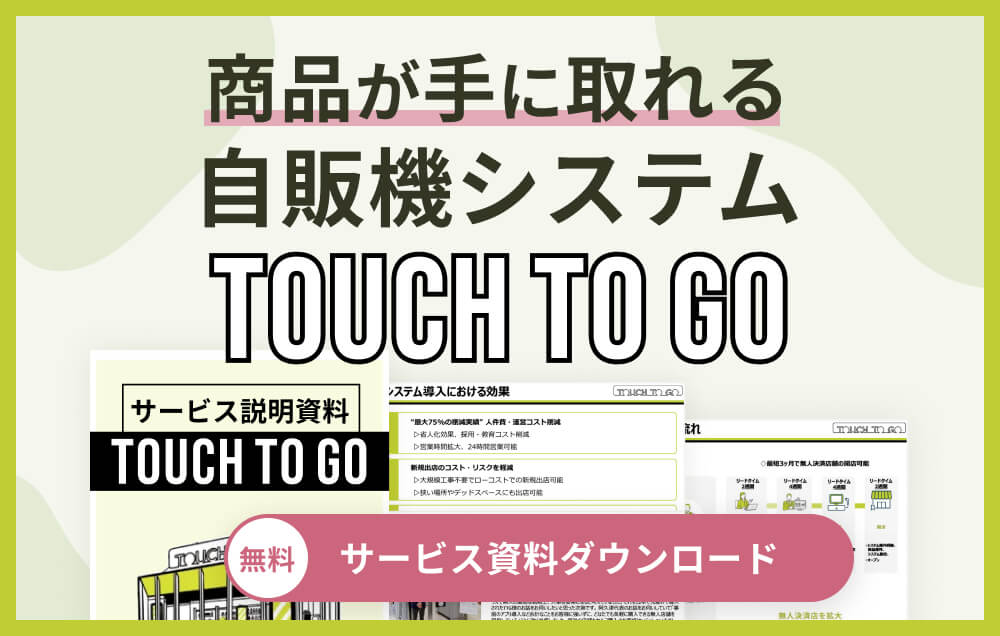Category
こんにちは。無人決済店舗システムを提供しているTOUCH TO GO 編集部です。
人手不足や運営コストの高騰が続くなか、「省力化しながら安定した収益を得られるビジネスモデル」として注目を集めているのが、自販機ビジネスです。
自販機ビジネスは、わずかなスペースさえあれば始められ、24時間365日無人で稼働するのが大きな特徴。
設置場所と商品選びさえ間違えなければ、大きな人件費をかけずに新たな収益源を築くことも可能です。
本記事では、自販機ビジネスの仕組みや運営モデル、始める前に確認すべきポイントを詳しく解説します。
関連記事▼
監修者プロフィール

2019年に株式会社TOUCH TO GOを設立。無人決済店舗システムを提供し、次世代型小売の拡大に取り組んでいる。
目次
自販機ビジネスとは?
自販機ビジネスとは、自販機を活用して商品を無人で販売し、利益を得るビジネスモデルです。
小さなスペースで始められ、24時間休みなく営業できる点から、店舗経営や人材確保が難しい現代において注目が集まっています。
運営スタイルによって、利益の出し方やオーナーの関与度合いは大きく変わってきます。
ここではまず、自販機ビジネスの基本的な仕組みと、主な運営形態を紹介します。
フルオペレーション方式
自販機の導入にあたって最も手間がかからないのが「フルオペレーション方式」です。
フルオペレーション方式は、自販機ビジネスに必要な以下の項目を専門業者に委託するスタイルです。
- 自販機の設置
- 商品補充
- 売上管理
- 清掃・メンテナンス
オーナーは自販機を置くための土地やスペースを提供し、代わりに売上の一部を歩合で受け取ります。
自販機に関する業務は一切不要なため、空きスペースの有効活用や、完全な副収入としての活用に向いています。
ただし、自由度は低く、取り扱う商品や販売価格は業者側の方針に従うのが一般的です。
セミオペレーション方式
一方、自販機オーナー自らが仕入れや補充、運用を担うスタイルが「セミオペレーション方式」です。
自販機本体の所有者となり、何を売るか・どのように価格を設定するかなどを自由に決められるため、収益性を高めたい方にとって魅力的な選択肢です。
ただし、この方式では定期的な補充作業や商品管理、メンテナンスといった実務が発生するため、ある程度の運用リソースの確保が必要です。
関連記事>>自販機設置の費用と収入の仕組みを徹底解説
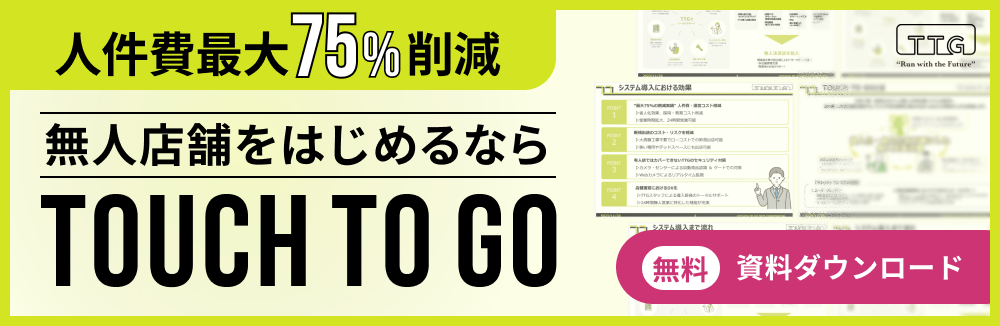
「TOUCH TO GO」のプロダクトは、自販機を設置するように、工事不要でコンビニ区画を導入できます。
店舗の省人化・人件費削減をご検討中の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/
自販機ビジネスのメリット・デメリット
自販機ビジネスは小規模から始めやすく、無人での収益化が可能という点で魅力的なモデルです。
とはいえ、当然ながらメリットだけでなく、運用上の注意点やリスクも存在します。
ここでは、事前に理解しておきたいメリットとデメリットを紹介します。
メリット
まずは、メリットからみていきましょう。
初期投資が比較的少ない
自販機ビジネスは、店舗のような建物を構える必要がなく、設置スペースさえ確保できればスタートできます。
中古自販機を活用すれば、数十万円程度で導入できるケースもあり、他の事業と比べても初期投資が抑えられるのは大きな魅力です。
無人・省人化が実現できる
自販機は基本的に人を介さずに販売が完結する仕組みであるため、営業時間中にスタッフが常駐する必要がありません。
そのため。人手不足に悩む業種や、人的コストを極力抑えたい経営者にとっては非常に有効な選択肢といえます。
24時間営業による売上機会の最大化
自販機は常時稼働が前提のため、営業時間に縛られることなく商品を販売し続けられます。
特に、夜間や早朝のように通常の小売店が閉まっている時間帯でも収益チャンスがある点は、自販機ならではの強みです。
商品展開の柔軟性が高い
自販機ビジネスでは、ターゲットや立地に応じて販売商品を柔軟に切り替えられます。
たとえば、「夏場には冷たい飲料」、「冬場には温かいスープ」といった形で、需要に合わせてラインナップを調整できます。
セミオペレーション方式であれば、オーナーのアイデアで独自の差別化も図れます。
デメリット
次に、デメリットをみていきましょう。
売上は設置場所に大きく依存する
自販機は「人が通る場所」に設置されてこそ収益が見込めるビジネスです。立地が悪ければ、どれほど良い商品を揃えても売上は伸びません。
実際、同じ商品でも駅前と裏通りでは販売数に大きな差が出るケースもあり、設置場所は慎重に選ぶことが大切です。
電気代やメンテナンスなどの固定費が発生する
自販機は24時間稼働しているため、電気代がかかります。特に、冷蔵・冷凍機能付きの場合は消費電力が高くなる傾向にあります。
また、故障時の修理や定期的な清掃・消耗品の交換など、運用コストも見込んでおく必要があります。
商品ロスや盗難リスクもゼロではない
食品系の自販機では、賞味期限切れや季節変動による売れ残りが発生することもあります。
さらに、設置場所によっては盗難などのトラブルも起こり得るため、必要に応じて防犯カメラの設置も必要です。
扱える商品の種類と特徴
自販機ビジネスの魅力の一つは、取り扱える商品の幅広さにあります。
従来の自販機では飲料の販売が主流でしたが、近年では冷凍食品やスイーツ・雑貨・地域限定商品など、さまざまな商品展開が可能です。
ここでは、自販機ビジネスの代表的な商品ジャンルを紹介します。
飲料・軽食類
もっとも一般的なのは、ペットボトル飲料や缶コーヒー、お茶などを販売する飲料自販機です。
安定した需要が見込める反面、競合も多く、価格競争に巻き込まれる可能性があります。
軽食系では、お菓子やカップ麺、おにぎりなどの常温食品が比較的取り扱いやすく、駅構内や学校周辺などの立地で安定した売上に期待できます。
冷凍食品・スイーツ
近年注目されているのが、冷凍自販機を活用した自販機です。
たとえば、以下のように冷凍でも品質を保ちやすい商品は、飲食店の味をそのまま届けられるという点で人気が高まっています。
- 冷凍餃子
- ラーメン
- 蕎麦
- パスタ
- ケーキ
- クレープ
なかには、有名店が監修した冷凍食品や地域の人気スイーツを自販機で販売する事例もあり、商品単価を高く設定することも可能です。
関連記事>>冷凍自販機導入ガイド|最適な機種選びから設置費用まで完全解説
地域特産品・雑貨
地元産の野菜、味噌、海産物といった地域性の高い商品を扱う自販機や、以下のような食べ物以外を扱う自販機ジャンルもあります。
- キャラクターグッズ
- マスク
- 釣り具
- 文房具
これらは大量販売よりも「話題性」か「物珍しさ」を活かしており、観光地や商業施設内での設置が向いています。
季節商品やイベント限定グッズを販売する手段としても、自販機は非常に相性が良いといえます。
自販機ビジネス成功のポイント
自販機ビジネスは誰でも参入しやすい分、収益を安定させるには独自の工夫が欠かせません。
ここでは、ビジネスとして成功させるために押さえておきたい3つのポイントを解説します。
立地選定の重要性
自販機の売上は、設置場所によって大きく左右されます。人通りが多く、立ち止まりやすい場所であるかどうかが最大のポイントです。
具体例は以下のとおりです。
- 駅前
- オフィス街
- 住宅地
- 病院の待合室
- 学校近くの歩道
また、自社の敷地や駐車場などを活用する場合でも、どの位置に設置するかで売れ行きは変わります。
自販機にとっての「好立地」を客観的に判断することが重要です。
商品ラインナップは“想定客層”から考える
販売する商品の選定は、自販機の設置場所を通る人の属性をイメージすることが大切です。
たとえば、学生が多い場所であれば手頃な価格の軽食や甘い飲料、高齢者が多ければ健康志向の飲み物など、ターゲットに合わせて内容を調整することが成功のカギです。
また、商品数は多すぎても少なすぎても失敗しやすいため、「選びやすさ」と「魅力的な選択肢の幅」を意識しながら構成を考えましょう。
定期的なメンテナンスと補充体制の確保
どんなに良い商品を並べても、補充されていなければ売上にはつながりません。
自販機は”常に動いている店舗”という意識で、定期的に在庫補充・ゴミの回収・清掃を行う必要があります。
また、販売データを定期的にチェックし、売れ筋・死に筋商品の入れ替えも大切です。
最近では遠隔で売上や在庫を確認できるシステムもあるため、少人数でも安定した運営が可能になります。
自販機ビジネスを始める前に確認しておくべきこと
自販機ビジネスは小規模でも始めやすい一方で、始めてから「思っていたより大変だった」と感じるケースも少なくありません。
安定的に収益を得るためには、事前の準備や確認が欠かせません。ここでは、スタート前に押さえておきたいポイントを解説します。
設置場所の許可と契約条件
まず重要なのが、「どこに自販機を置くか」と「そのスペースをどう確保するか」です。
自己所有の敷地であれば問題ありませんが、他人の敷地を借りて設置する場合には、事前に契約を交わす必要があります。
特に商業施設や駅構内、駐車場などは、運営会社との交渉が必要になるケースが多いため、条件を細かく確認しておきましょう。
また、公道や公共スペースへの設置は原則として認められておらず、自治体によっては制限が設けられているため注意が必要です。
初期費用とランニングコストの試算
自販機本体の購入・設置には数十万円〜100万円以上の初期費用がかかります。
また、月々のコストとして、電気代や補充・清掃・保守メンテナンスの費用がかかることも想定しておきましょう。
フルオペレーション式では、初期費用がかからない代わりに、売上の一部を業者に支払う形になります。
事業として採算が取れるかどうかを判断するために、事前に利益をシミュレーションしておくことが大切です。
関連記事>>自販機のランニングコストはどれくらい?省エネ型自販機についても解説!
補充・清掃・トラブル対応の体制
自販機は無人で商品を販売できますが、「完全放置」でよいわけではありません。
商品が売り切れたままになっていたり、汚れていたりすると、売上だけでなく店舗やブランドのイメージにも影響します。
自己管理・運営の場合は、週に何回補充に行くかや、誰が清掃や点検を行うかを事前に決めておきましょう。
故障時の対応をスムーズにするためにも、業者に連絡すればすぐ修理してもらえるのか、予備パーツがあるのかなどを確認しておくと安心です。
まとめ
自販機ビジネスは、初期投資が少なく、無人で収益を生み出せる手軽さから、経営者にとって魅力的な選択肢のひとつです。
近年では、飲料だけでなく冷凍食品や特産品など商品の幅も広がっており、運用次第で安定収益が見込めます。
一方で、立地や商品選定、補充・清掃などの管理体制が不十分だと売上は伸び悩みます。
始める前に準備すべきポイントを整理し、自社に合った運営スタイルを選ぶことが成功のカギとなるでしょう。
関連記事▼
「TOUCH TO GO」のプロダクトは、自販機を設置するように、工事不要でコンビニ区画を導入できます。
店舗の省人化・人件費削減をご検討中の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/