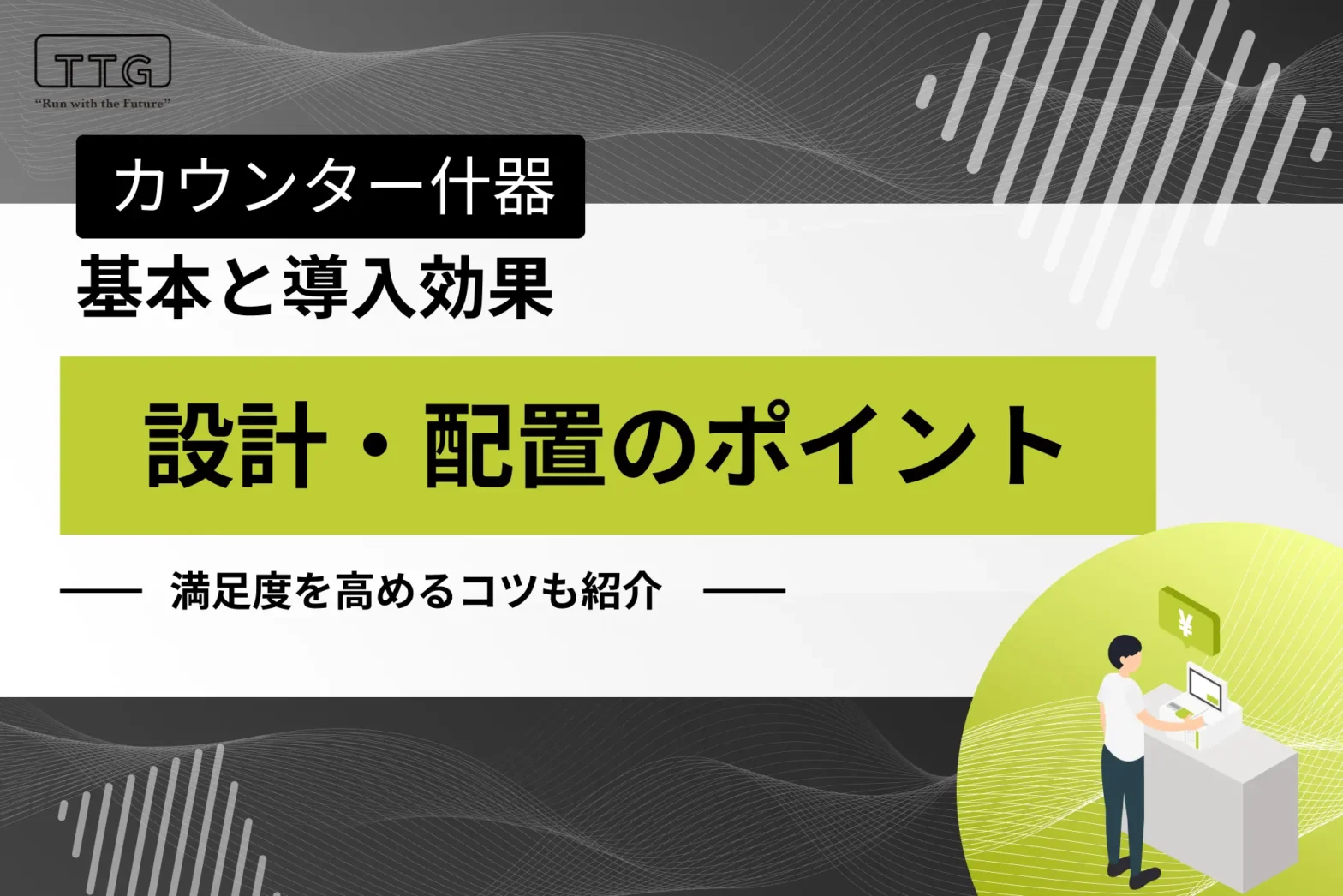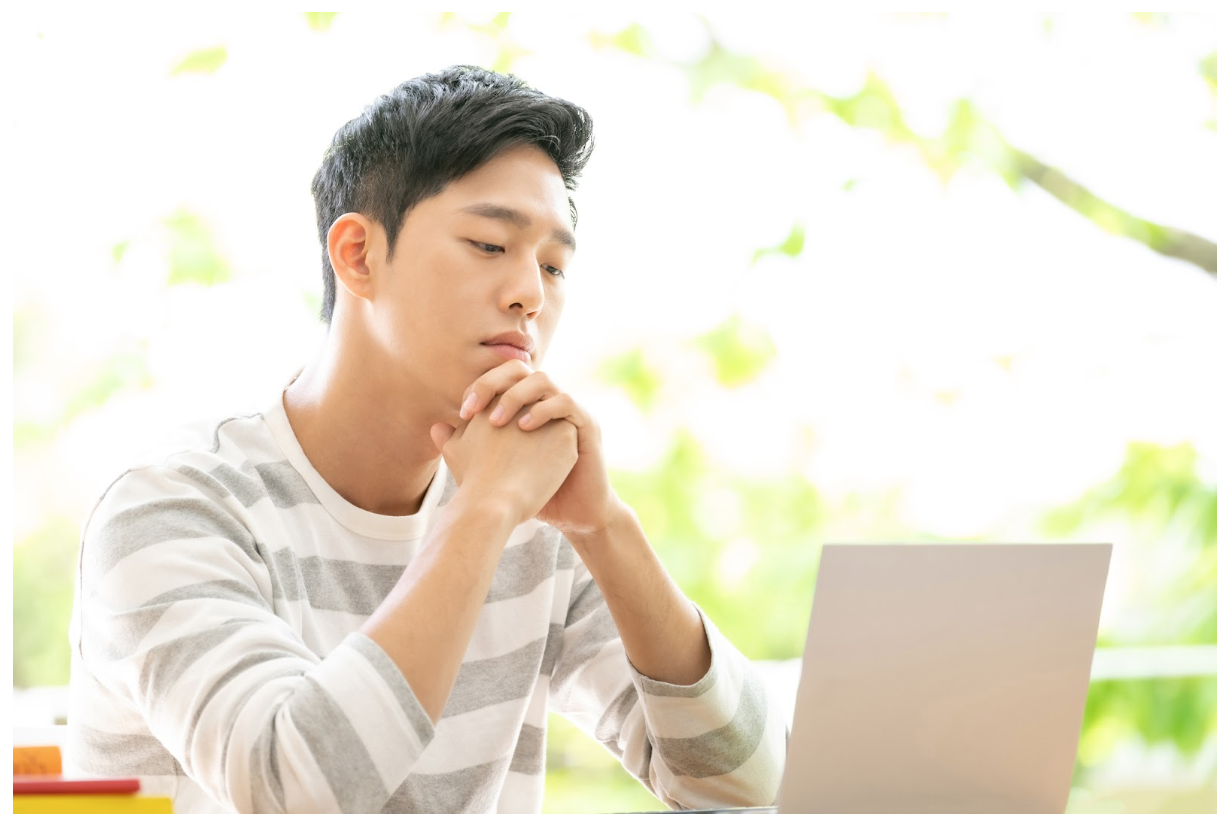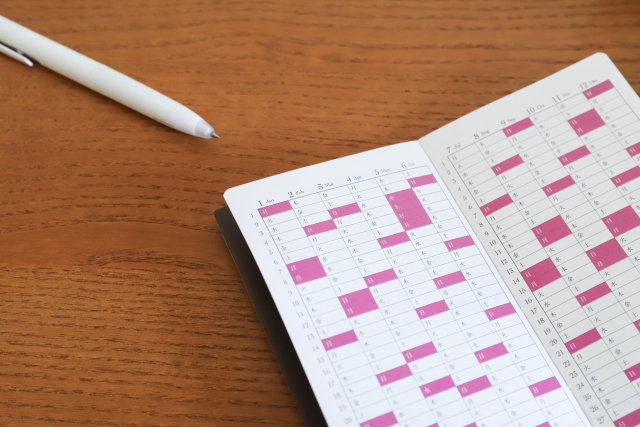Category
こんにちは。無人決済店舗システムを提供しているTOUCH TO GO 編集部です。
ホテル・宿泊業界では、慢性的な人手不足が深刻な課題となっています。十分な人材を確保できなければ、サービスの質を維持・向上させることも難しくなります。
では、なぜ人手不足が生じているのでしょうか。本記事では、その原因と具体的な対策について解説します。
人材確保に悩むホテル・宿泊施設の経営者や人事担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
関連記事>>人手不足が顕著な業界(業種)ランキングTOP10|原因も解説
監修者プロフィール

2019年に株式会社TOUCH TO GOを設立。無人決済店舗システムを提供し、次世代型小売の拡大に取り組んでいる。
目次
ホテル・宿泊業界の人手不足が起こる原因
ホテル・宿泊業界の人手不足には、いくつかの根本的な原因が存在します。ここでは、人手不足が生じる原因について詳しく解説します。
賃金が低い
ホテル・宿泊業界の賃金水準は、他の産業と比較して低い傾向にあります。もちろん、職種や経験によって給与は異なりますが、全体的に見て賃金が低いことが、人材が集まりにくい要因の一つと考えられます。
特に、若い世代はより高い収入を求めて他の業界へ流れる傾向があり、人手不足を加速させる要因となっています。
また、昇給制度やキャリアアップの機会が少ない場合、従業員のモチベーション低下につながり、離職率を高める可能性もあります。
有給取得日数が少ない
ホテル・宿泊業界は、繁忙期と閑散期の差が激しい傾向があります。そのため、慢性的な人手不足の状況下では、従業員が有給休暇を取得しにくい状況に陥りがちです。
有給休暇を取得しにくい環境は、「従業員の疲労蓄積」や「ストレス増加」につながり、結果として離職率を高める要因となります。
また、ワークライフバランスを重視する若い世代にとって、有給休暇の取得しやすさは就職先を選ぶ上で重要なポイントとなるため、人材確保の面でも不利になりやすいです。
拘束時間が長い・労働時間が不規則
ホテル・宿泊業界は、24時間体制でサービスを提供する必要があるため、拘束時間が長くなる傾向があります。
特に、宿泊部門や料飲部門はシフト制勤が一般的なため、早朝や深夜勤務、土日祝日の出勤も発生します。
また、繁忙期には残業時間が増えることも珍しくありません。このような不規則な勤務形態は、従業員の生活リズムを崩し、心身の負担を増大させる要因となります。
さらに、労働時間が長時間化すると、従業員の集中力やモチベーションが低下し、サービスの質の低下にもつながる可能性があります。
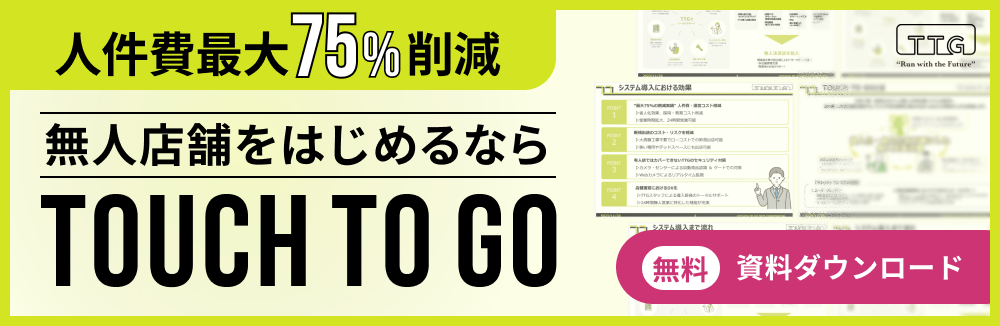
「TOUCH TO GO」の無人決済システムを導入し、ホテルや宿泊施設内のお土産やコンビニを無人化することで、人手不足の課題を解決できます。
ホテル・宿泊施設の人手不足にお悩みの方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/
ホテル・宿泊業界の人手不足が深刻化した背景
ホテル・宿泊業界の人手不足は、近年ますます深刻化しています。その背景には、以下のような要因が考えられます。
ホテルの開業数の増加
近年、外国人観光客の増加に伴い、全国各地でホテルや宿泊施設の開業ラッシュが続いています。
特に、都市部や観光地では、外資系ホテルやリゾートホテルの進出が目立っています。
ホテルの開業数が増加すれば、当然ながら人材の需要も高まりますが、供給が追いつかず、人材の獲得競争が激化しています。
新規開業のホテルは、既存のホテルから人材を引き抜くことも多いため、業界全体の人手不足をさらに深刻化させる要因となっています。
離職率が高い
ホテル・宿泊業界は、他の産業と比較して離職率が高い傾向にあります。
その理由としては、前述したような「賃金の低さ」や「有給休暇の取得しにくさ」、「拘束時間の長さ」などが挙げられます。
また、人間関係の悩みやキャリアアップの機会の少なさも、離職につながる要因となります。
せっかく採用した人材がすぐに辞めてしまうと、採用コストや教育コストが無駄になるだけでなく、現場の負担も増大します。
離職率を下げるためには、従業員が働きやすい環境を整備することが不可欠です。
コロナ禍での人材の流出
新型コロナウイルス感染症の拡大は、ホテル・宿泊業界に大きな打撃を与えました。
緊急事態宣言や移動制限が発令され、観光客の数は激減。その結果、多くのホテルや宿泊施設は休業や営業縮小を余儀なくされました。
この影響で、「従業員の解雇」や「雇止め」、「減給」が相次ぎ、他業種に転職した人も少なくありません。
コロナ禍の収束により観光需要は回復していますが、一度業界を離れた人材が戻らないケースが多く、現在も深刻な状況が続いています。
インバウンド需要の高まり
近年、日本を訪れる外国人観光客(インバウンド)が急増しています。
政府は、2030年に訪日外国人旅行者数6,000万人・消費額15兆円を目指しており、今後もインバウンド需要は拡大することが予想されます。
インバウンド需要の高まりは、ホテル・宿泊業界にとって大きなビジネスチャンスである一方、人材不足をさらに深刻化させる要因ともなっています。
というのも、外国人観光客に対応するためには、語学力のある人材や異文化理解に長けた人材が必要となりますが、そのような人材の確保は容易ではありません。
そのため、インバウンド需要に対応するための適切な経営戦略が求められます。
今後のインバウンド需要の動向や戦略について、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
関連記事>>インバウンド需要は今後どうなる?対応するための経営戦略とは
ホテル・宿泊業界の人手不足への対策
ホテル・宿泊業界の人手不足を解消するためには、業界全体で様々な対策を講じる必要があります。
賃金の見直し
ホテル・宿泊業界の人手不足への対策として、賃金の見直しは重要な取り組みの一つです。賃金の見直しは、単に基本給を上げることを指すのではありません。
例えば、年齢や経験に応じた給与体系の整備や、労働環境に応じたインセンティブを導入することが有効です。
これにより、従業員のモチベーションが向上し、業界全体での人手不足の解消が期待できます。
また、賃金アップだけでなく、福利厚生の充実や働きやすい環境を提供することも、従業員の満足度を高め、離職率の低下に繋がります。
従業員に喜ばれる福利厚生を以下の記事で紹介しています。あわせてご覧ください。
関連記事>>従業員に喜ばれるオフィスの福利厚生12選|メリット・デメリットも解説
業務の効率化
ホテル・宿泊業界での人手不足を解消するためには、業務の効率化が不可欠です。
限られた人数で多くの業務をこなす必要があるため、作業の無駄を省き、業務の流れをスムーズにすることが大切です。
例えば、デジタルツールやIT技術を活用することで、業務の効率化が進みます。
「予約管理システムの自動化」や、「顧客データを活用したマーケティングの最適化」なども、従業員の手間を減らし、サービスの質を維持しつつ効率的に運営する手段となります。
このように業務の効率化に取り組むことで、限られた人員でも高い生産性を維持しつつ、業務負担を軽減できます。
勤務形態の見直し
従業員が働きやすい勤務形態を導入することも、人手不足対策として有効です。例えば、以下のような勤務形態が考えられます。
- 短時間勤務制度
- フレックスタイム制度
- テレワーク制度
- シフト制の見直し
これらの制度を導入することで、従業員のワークライフバランスを改善し、離職率の低下や人材獲得に期待できます。
出戻り採用
また、過去に自社で働いていた従業員を再雇用する「出戻り採用」も、有効な人手不足対策の一つです。
出戻り採用には、即戦力となる人材を比較的容易に確保できるという大きなメリットがあります。さらに、企業の文化や業務内容を理解しているため、教育コストを抑えられる点も魅力的です。
出戻り採用の可能性を高めるためには、退職した従業員との良好な関係を維持し、常に連絡を取り合うことが大切です。
福利厚生の充実
ホテル・宿泊業界の人手不足を解消するためには、福利厚生の充実も重要な対策の一つです。
従業員が長期的に働き続けるためには、給与だけでなく、働きやすい環境や生活面でのサポートが必要不可欠です。具体的には、以下のような福利厚生が考えられます。
- 住宅手当や家賃補助
- 社員食堂やオフィスコンビニの導入
- 育児支援制度
- 介護支援制度
- リフレッシュ休暇制度
- 資格取得支援制度
- 社員旅行やレクリエーション
福利厚生を充実することで従業員の定着率が向上し、結果的に人手不足の解消に貢献します。
以下の記事で、ホテルや宿泊業界にも導入できる福利厚生の種類を紹介しています。あわせてご覧ください。
関連記事>>福利厚生の種類一覧|特徴や導入時の注意点も詳しく解説!
教育制度の充実
従業員のスキルアップや、キャリアアップを支援するための教育制度を充実させることも、人手不足対策として有効です。例えば、以下のような教育制度が考えられます。
- OJT(On-the-Job Training)
- Off-JT(Off-the-Job Training)
- 外部研修への参加支援
- 資格取得支援制度
- 語学研修
これらの教育制度を通じて従業員の能力開発を促進し、モチベーション向上を図ることで、定着率向上に繋がります。
ITシステムやロボットの導入
ITシステムやロボットの導入は、業務効率化や省人化に貢献し、人手不足を解消するための有効な手段です。
例えば、「セルフチェックイン精算機」を導入することで、チェックイン・チェックアウトにおけるフロント業務の負担を軽減できます。
また、予約管理や顧客情報の一元化を図るITシステムを導入することで、スタッフの手間を減らし、業務の効率化が進みます。
さらに、ホテルや宿泊施設内のお土産やコンビニを無人化することで、従業員の配置が不要になり、人手不足の解消と人件費削減を両立できます。
このような無人化・省力化を進めるために、無人決済システム「TOUCH TO GO」の導入も効果的です。
「TOUCH TO GO」は、店内に設置されたセンサーやカメラが顧客の動きを追跡し、手に持っている商品を自動的に認識します。
さらに、セルフ決済機を使って、タッチパネルで簡単に支払いを完了させる仕組みのため、従業員が常駐する必要はなく、人件費を最小限に抑えて店舗を運営できます。
ホテルや宿泊施設内にお土産・コンビニを導入したいと考えている方は、ぜひ以下のリンクから詳細をチェックしてみてください。
製品詳細>>TOUCH TO GO
派遣従業員の活用
必要な時に必要なスキルを持った人材を確保できる派遣従業員の活用も、人手不足対策の一つです。
繁忙期やイベント時など、一時的に人手が必要な場合に、派遣従業員を活用することで人員不足の解消に繋げられます。
ただし、派遣従業員に業務を依頼する際は、事前に十分な研修を行い、スムーズに業務を遂行できるよう配慮する必要があります。
まとめ
ホテル・宿泊業界の人手不足は、さまざまな要因が絡み合って発生しています。深刻な人手不足を解決するためには、多方面からの対策を検討しなければなりません。
近年では、ITシステムやロボットを活用した無人化・省力化に取り組む企業が増えており、これらの導入によって人手不足の解消が期待されています。
今後、ホテル・宿泊業界が持続的に発展していくためには、働きやすい環境を整え、限られた人材で高いサービス品質を維持できる仕組みづくりが不可欠です。
最新の技術を活用しながら、業界全体で人手不足の課題に取り組んでいきましょう。
「人手不足でありながら人件費削減が必要」という複雑な課題を抱えている場合は、以下の記事も参考にしてください。
「TOUCH TO GO」の無人決済システムを導入し、ホテルや宿泊施設内のお土産やコンビニを無人化することで、人手不足の課題を解決できます。
ホテル・宿泊施設の人手不足にお悩みの方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/