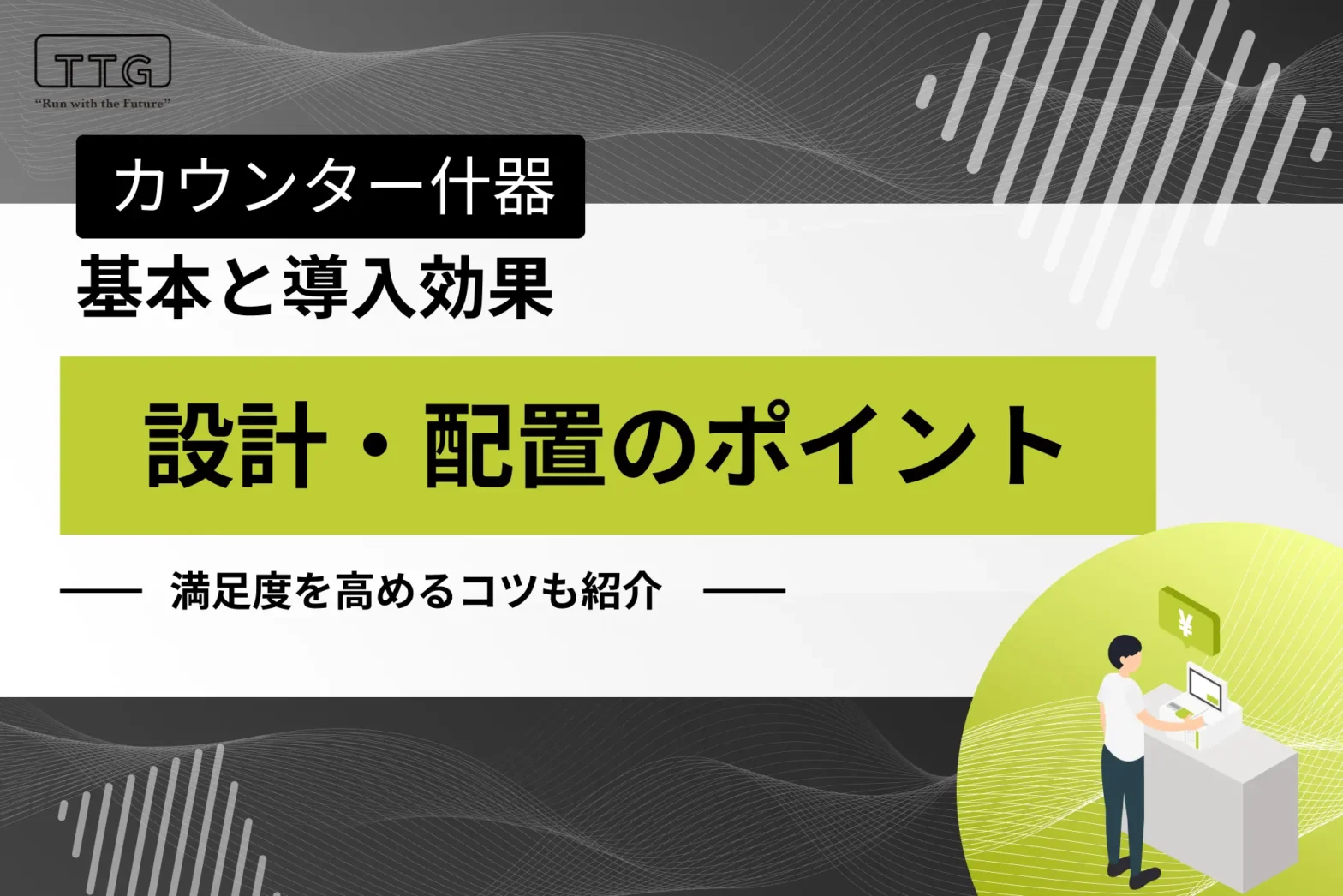Category
こんにちは。無人決済店舗システムを提供しているTOUCH TO GO 編集部です。
現金を使わないスムーズな決済方法として、急速に普及しているキャッシュレス決済。
便利でお得なイメージが強い一方で、「本当にキャッシュレス決済はメリットばかりなの?」と疑問を抱いている方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、キャッシュレス決済のデメリットを「店舗側」と「顧客側」の両方の視点から解説します。
キャッシュレス決済導入に伴う課題への対策も紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
関連記事▼
目次
【店舗側】キャッシュレス決済のデメリット
最初に、店舗側のデメリットを紹介します。
初期費用・運用コストがかかる
キャッシュレス決済の導入には、初期費用や運用コストがかかるというデメリットがあります。
初期費用には、以下の項目が含まれます。
- 決済端末の購入
- 設置費用
- 必要なシステム
特に、複数の決済手段に対応する場合、それぞれに対応した端末やソフトウェアを準備する必要があり、コストがかさみやすくなります。
また、運用コストとして、決済手数料が発生する点も注意が必要です。
クレジットカードやスマートフォン決済の利用に対して、売上の一定割合が手数料として差し引かれます。
導入前に準備が必要
キャッシュレス決済をスムーズに導入するには、事前の準備が大切です。
最初に、店舗に合った決済方法や決済端末の選定が必要です。決済手段にはクレジットカード、スマートフォン決済、電子マネーなどがあり、それぞれに対応する端末やシステムを選ぶ必要があります。
また、店舗スタッフへのトレーニングも欠かせません。スタッフがスムーズに操作できるように、キャッシュレス決済の操作方法や、トラブル対応についてしっかり教育しておくことが求められます。
場合によっては、店舗のオペレーションの見直しが必要になります。変更点を事前に洗い出し、スムーズに移行できるよう計画を立てておくことも重要なポイントです。
キャッシュレスのみに絞るのは難しい
キャッシュレス決済の普及が進んでも、現金決済の需要は完全にはなくなりません。
顧客によっては現金払いを希望するケースもありますし、小額の買い物や特定のシーンでは現金が選ばれることもあります。
そのため、店舗側としてはキャッシュレス決済を導入しても、現金管理を完全に廃止することは難しいのが現状です。
ある程度は軽減されますが、キャッシュレス決済の導入後も以下のような現金を扱う業務は発生します。
- 売上金の回収
- 釣銭の準備
- 現金出納帳の管理
キャッシュレスと現金の両方を扱うことになれば、二重での管理が必要になり、いかに効率化できるかが重要なポイントとなります。
会計業務がシステムに依存する
キャッシュレス決済の導入により、会計業務はシステムに大きく依存することになります。
決済端末やシステムに障害が発生した場合、決済処理ができなくなり、店舗運営に支障をきたす可能性があります。
特に、売上のピークタイムにシステム障害が発生すると、顧客への影響は大きくなります。
また、システムの不具合や誤操作によって、売上データの不整合や損失が発生するリスクも想定しておかなければなりません。
現金を受け取るまでに時間がかかる
キャッシュレス決済で得た売上は、即座に店舗の口座に入金されるわけではありません。
決済サービスを提供する事業者や、決済代行会社をつうじて入金処理されるため、現金を受け取るまでに一定の時間を要します。
入金サイクルは利用する決済サービスや代行業者によって異なりますが、「月末時めの翌月末払い」などの方法が採用されています。
入金までの期間が長い場合、店舗の資金繰りに影響を及ぼす可能性があるので注意が必要です。
店舗負担を軽減する工夫と解決策
キャッシュレス決済の導入には一定のコストや運用上の課題が伴いますが、工夫次第でその負担を軽減することも可能です。
ここでは、導入にかかるコストや手間を抑えるための具体的な解決策を紹介します。
マルチ決済端末や一括導入パッケージの活用
複数の決済手段に対応しようとすると、それぞれのブランドに応じた端末やシステムの導入が必要になり、コストがかさみやすくなります。そこで有効なのが、マルチ決済に対応した統合端末の活用です。
たとえば1台でクレジットカード、QRコード決済、電子マネーなどに対応できる端末を導入すれば、設置スペースも抑えられ、端末ごとの管理やメンテナンスの手間も軽減されます。
また、初期費用を抑えたい場合には、決済代行会社が提供する一括導入パッケージも検討する価値があります。
一括導入パッケージには、端末の貸与やサポート、決済システムの導入支援が含まれており、中小規模の事業者でも導入しやすいのが特長です。
決済手数料と入金タイミングの目安
キャッシュレス決済を導入するうえで、決済手数料と入金サイクルも重要な検討ポイントです。
手数料は決済手段や契約先によって異なりますが、手数料が3〜5%の場合、1ヶ月の売上が100万円であれば3万〜5万円程度が差し引かれる計算になります。
また、入金のタイミングとしては、以下のようなサイクルが多く見られます。
- 週1回入金(例:毎週金曜日に振込)
- 月2回入金(例:15日締め・末日締め)
- 月末締め翌月末払い
資金繰りに余裕がない店舗では、入金サイクルが遅いと現金不足に陥るおそれもあるため、入金スピードが早いサービスを選ぶことも選定基準の一つになります。
キャッシュレス決済の種類ごとの手数料の相場について、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
関連記事>>キャッシュレス決済の手数料とは?決済方法別の手数料相場・安く抑える方法を徹底解説!
現金管理にかかる具体的な手間とコスト
キャッシュレス決済の導入により現金管理の手間を軽減できますが、完全に現金をなくすのが難しい店舗も多いのが現状です。そこで、現金管理にかかる実際の負担を改めて整理しておきましょう。
現金対応にかかる作業には、以下のようなものがあります。
- 釣銭準備のための銀行往復や両替手数料
- 売上金の回収と保管・金庫管理
- 帳簿への記帳や締め作業の手間
- 現金過不足による精算業務・トラブル対応
さらに、現金は盗難や紛失のリスクも伴うため、監視カメラの設置、防犯金庫など防犯対策のコストもかかります。

TTG-MONSTARは、クレジットカード決済や交通系IC、QR決済など幅広い決済方法に対応するセルフレジです。
キャッシュレス決済に対応する端末の導入をご検討中の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TTG-MONSTAR の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download1/
【顧客側】キャッシュレス決済のデメリット
ここからは、顧客側のキャッシュレス決済のデメリットを紹介します。
対応していない店舗もある
近年キャッシュレス決済の普及は着実に進んでいますが、全ての店舗で利用できるわけではありません。
特に、個人経営の小規模店舗や地方の商店などでは、キャッシュレス決済に対応していない店舗もめずらしくありません。
そのため、事前に店舗の対応状況を確認したり、現金を持ち歩いたりなどの対策が必要です。
不正利用のリスクがある
キャッシュレス決済には、不正利用のリスクも考えられます。例えば、カード情報や決済情報が漏洩すると、第三者によって不正に利用される可能性があります。
不正利用の被害に遭った場合、金銭的な損失だけでなく個人情報の漏洩にもつながりかねません。
キャッシュレス決済の不正利用のリスクを軽減するには、利用者自身がセキュリティ意識を高めることが大切です。
例えば、パスワードの適切な管理や不審なメールやWebサイトへの注意、利用明細の定期的な確認などが有効な対策となります。
端末の故障など利用できない可能性がある
キャッシュレス決済は、端末の故障やバッテリー切れ、通信障害などの理由で利用できなくなることがあります。
特に、スマートフォンを決済手段として利用する場合、端末への依存度は高くなりがちです。
万が一、決済時に端末が使用できない状況に陥ると支払いができず、お店で困ることになります。
このようなトラブルを避けるためにも、複数の決済手段を用意しておくとよいでしょう。
例えば、クレジットカードや電子マネーなど、複数の決済方法を組み合わせて利用することで、リスク分散が図れます。
キャッシュレス決済が使えない場面とは
キャッシュレス決済の利用者が増える一方で、すべての場所でスムーズに使えるわけではありません。
とくに地域や店舗の規模によっては、キャッシュレス非対応のケースも少なくなく、現金が必要になる場面もあります。
ここでは、キャッシュレス決済が使えない場面やその背景について解説します。
小規模店舗や個人経営店では未導入なケースも多い
キャッシュレス決済は都市部のチェーン店では当たり前のように導入されていますが、個人経営の小規模店舗では対応していないケースも依然として多く見られます。その主な理由として、次のような事情が挙げられます。
- 導入コストへの懸念
- ITリテラシーの課題
- 現金管理に慣れている
また、売上規模が小さい店舗では「キャッシュレス決済にしても売上が伸びるとは限らない」という判断から、導入に消極的である可能性も考えられます。
このような背景から、小さな飲食店や個人経営の小売店などでは、キャッシュレス非対応のまま営業を続けている店舗も一定数存在しています。
地方や観光地では非対応な場合もある
都市部ではキャッシュレス決済の普及が進んでいますが、地方の商店街や観光地では現金が主流という場所も未だ多く見られます。
特にローカルイベントや露店、農産物直売所などでは、現金しか扱っていないこともあります。
キャッシュレス非対応の観光客向け施設では、以下のような場面で不便を感じることがあります。
- ローカルバスやタクシーが現金のみ
- 寺社仏閣の入場料や御朱印が現金のみ
- 地域限定の小規模土産物店が現金のみ
このような状況では、観光客がキャッシュレス決済だけを前提に行動すると、支払いに困るケースもあるため注意が必要です。
特に海外からの旅行者にとっては、言葉の壁に加えて現金対応の手間が負担になることもあります。
関連記事▼
キャッシュレス普及率と国の支援制度
キャッシュレス決済にはさまざまな課題がある一方で、国全体としてはその普及を強く後押ししています。
ここでは、日本におけるキャッシュレス決済の普及状況や政府の目標、さらに導入を検討している事業者向けの支援制度について紹介します。
キャッシュレス決済の普及状況と政府目標
日本におけるキャッシュレス決済の比率は、ここ数年で大きく伸びています。
経済産業省の発表によると、2024年のキャッシュレス決済比率は42.8%に達し、2010年代前半と比べて2倍以上に拡大しました。
政府は「キャッシュレス・ビジョン」に基づき、2025年までにキャッシュレス決済比率を40%程度に、将来的には80%まで引き上げることを目標としていますが、前倒しで普及している状況となっています。
政府がキャッシュレス決済を推進する背景には、以下のような理由があります。
- 消費者の利便性向上
- 店舗の業務効率化
- 防犯性の向上
- インバウンド対応の強化
- マクロ経済のデータ活用促進
特にコロナ禍以降、非接触での支払いニーズが高まり、クレジットカードやQRコード決済などの利用が一気に浸透しました。
ただし、現金主義が根強く残る業種や地域もあり、「全国一律の普及」にはまだ課題があるのが実情です。
こうした中で、政府はさまざまな支援策を講じることで、事業者の導入を後押ししています。
(出典)
2024年のキャッシュレス決済比率を算出しました
キャッシュレス・ビジョン|経済産業省
導入時に使える補助金・支援制度
キャッシュレス決済を導入する際には、中小企業や個人事業主でも活用できる補助金制度がいくつか用意されています。以下は代表的な支援例です。
IT導入補助金
- 対象:中小企業・小規模事業者
- 内容:デジタル化を目的としたITツール導入支援
- 補助額:最大350万円(類型によって異なる)
- 対象経費:POSシステム、キャッシュレス連携ツール、セキュリティ強化ツールなど
小規模事業者持続化補助金
- 対象:小規模事業者・個人事業主
- 内容:販路開拓や業務効率化のための費用を補助
- 補助額:最大50万円〜200万円(枠により異なる)
- 対象経費:キャッシュレス決済端末の導入費用、関連システムの購入なども対象になるケースあり
これらの補助金は年度によって条件が変動するため、導入を検討するタイミングで最新の公募要領を確認することが大切です。
また、申請には事前準備が必要なため、商工会議所や地域の中小企業支援窓口に早めに相談しておくと安心です。
関連記事▼
キャッシュレス決済導入に伴う課題への対策
キャッシュレス決済の導入と運用には、様々な課題が伴います。しかし、適切な対策を講じることで、これらの課題を克服し、キャッシュレス決済のメリットを最大限に活用できるのです。
ここでは、キャッシュレス決済導入に伴う課題への4つの対策について解説します。」
費用対効果を検証する
キャッシュレス決済の導入を検討する際には、費用対効果を慎重に検証する必要があります。
導入初期費用や運用コストだけでなく、決済手数料や現金管理コストの削減効果なども、総合的に考慮しなければなりません。
店舗の規模・業種・顧客層・取り扱う決済方法の種類などによって、費用対効果は大きく異なります。
そのため、自店舗の状況に合わせた最適なシステム選定が重要です。
導入前にシミュレーションを行い、費用対効果を検証しておきましょう。また、導入後も定期的に効果を測定し、必要に応じて運用方法を見直すことが大切です。
セキュリティ対策を強化する
キャッシュレス決済の普及に伴い、セキュリティ対策の重要性が高まっています。
不正利用や情報漏洩のリスクを軽減するために、店舗と顧客双方が適切な対策を講じなければなりません。
店舗側には、決済端末やシステムのセキュリティ強化が求められます。
例えば、POSシステムの定期的なアップデートや、不正アクセスを検知するシステムの導入などが有効です。
また、従業員に対するセキュリティ教育を徹底し、個人情報の取り扱いに関する意識を高めることも大切です。
不正利用や情報漏洩は店舗の信頼性に大きく影響するため、万全なセキュリティ対策を実施しましょう。
災害時に備える
地震や台風などの自然災害により停電や通信障害が発生すると、決済端末やシステムが使用不能となるリスクがあります。
キャッシュレス決済に絞ることで管理が容易になり、コスト削減も可能ですが、万が一の場合に対応できなくなるかもしれません。
そのため、非常時に備えて、現金決済との併用体制を維持することも検討しましょう。
また、災害発生時の対応マニュアルを作成し、従業員に周知徹底することも欠かせません。
非常用電源の確保や、オフライン決済の導入なども検討しておくことをおすすめします。
スタッフ教育を実施する
キャッシュレス決済の導入において、スタッフ教育も課題の一つとなります。
新しい決済方法に対応できるよう、スタッフが正確に操作できるようトレーニングの実施が欠かせません。
特に、決済端末の使用方法やトラブル対応方法については、スタッフ全員が正しく理解する必要があります。
また、顧客対応の際にスムーズなサービスを提供できるよう、定期的な教育やフォローアップを行うことも効果的です。
また、顧客がスムーズに決済できるように、操作ガイドの設置や遠隔サポートの実施なども取り入れるとよいでしょう。
まとめ
キャッシュレス決済は、店舗側と顧客側の双方とってメリットの多い決済方法ですが、同時にいくつかのデメリットも存在します。
従来の現金払いとは異なり、キャッシュレス決済は新しいシステムを採用しているため、予期しないトラブルやリスクが発生する可能性もあります。
そのため、キャッシュレス決済を導入する際は、メリット・デメリットの両方を理解したうえで、導入を検討する必要があります。
キャッシュレス決済についてさらに知識を深めたい方は、概要から種類、導入方法まで詳しく解説している、以下の記事も参考にしてください。
関連記事▼
TTG-MONSTARは、クレジットカード決済や交通系IC、QR決済など幅広い決済方法に対応するセルフレジです。
キャッシュレス決済に対応する端末の導入をご検討中の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TTG-MONSTAR の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download1/