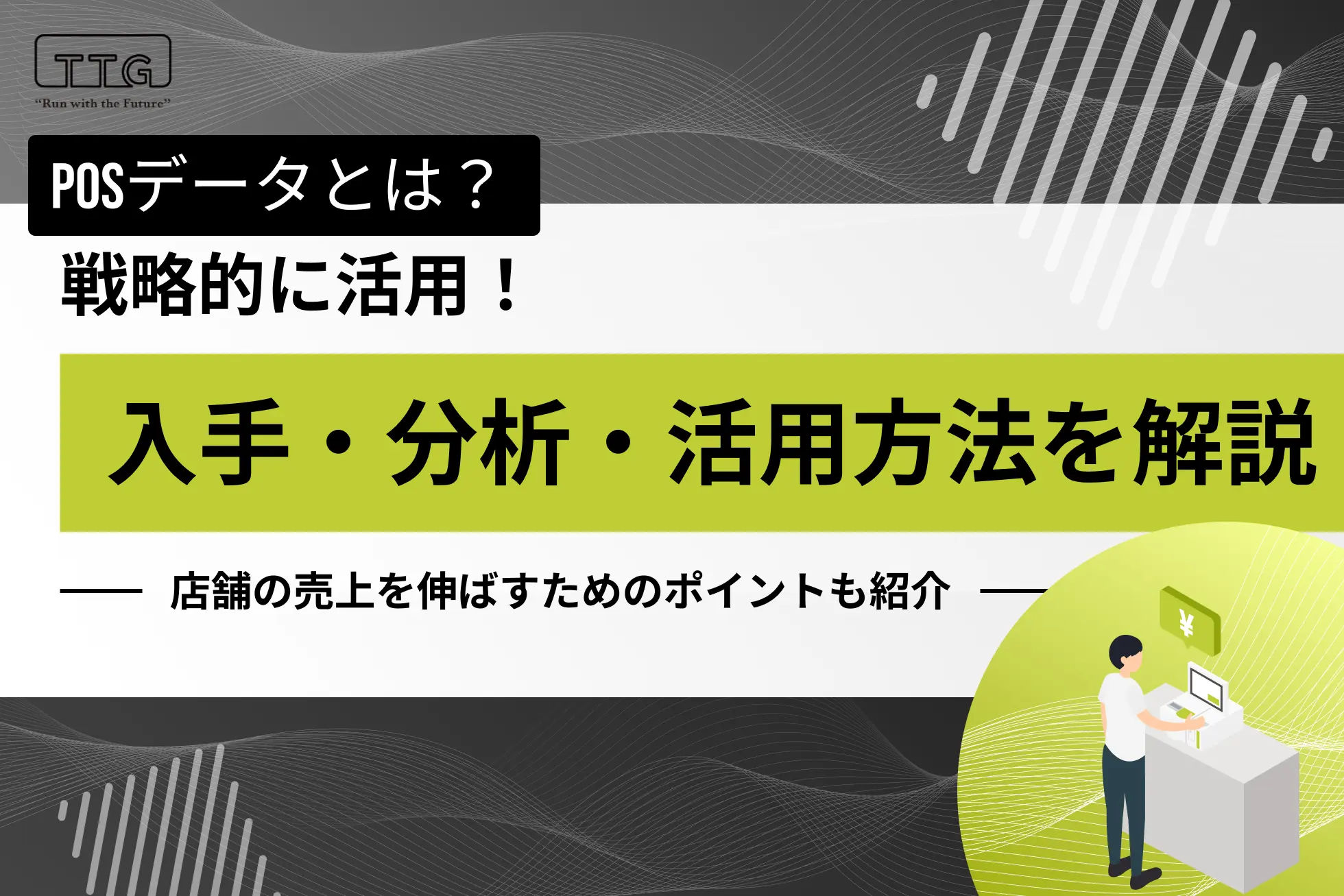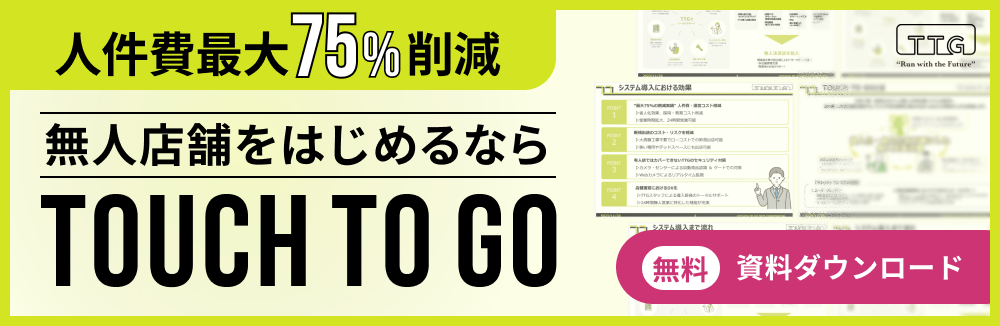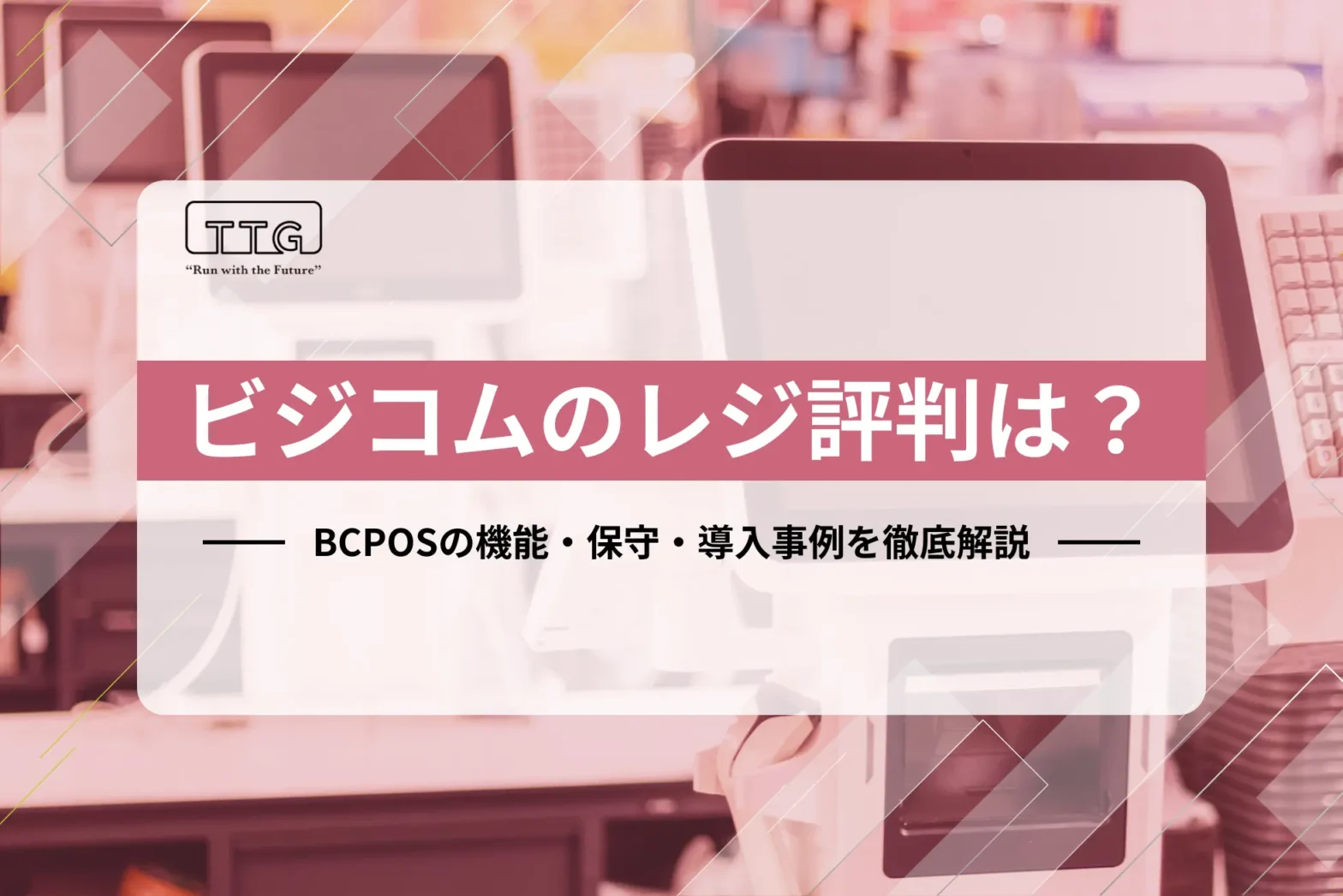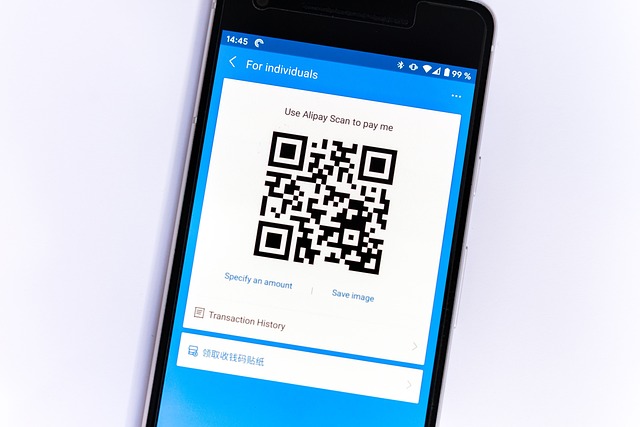Category
こんにちは。無人決済店舗システムを提供しているTOUCH TO GO 編集部です。
近年、店舗運営やマーケティングにおいて欠かせない存在となっているのが「POSデータ」です。
レジでの販売情報をもとに、売上や在庫の状況、顧客の購買傾向まで把握できるPOSデータは、売上アップや業務改善のための重要な判断材料となります。
しかし、具体的にどのような情報が得られ、どのように活用すれば効果を最大化できるのか、正確に理解している方は意外と多くありません。
本記事では、POSデータの基本的な仕組みから、入手方法・分析手法・活用方法を解説します。
さらに、店舗の売上を伸ばすための実践的なポイントも紹介しますので、POSデータを戦略的に活用したい方はぜひ参考にしてください。なお、セルフ/セミセルフレジによるPOSデータ活用をご検討の方には『TTG-MONSTAR』もご用意しています。ご興味のある方はぜひご確認ください。
関連記事▼
監修者プロフィール

2019年に株式会社TOUCH TO GOを設立。無人決済店舗システムを提供し、次世代型小売の拡大に取り組んでいる。
目次
POSデータとは
POSデータとは、「Point of Sale(販売時点情報管理)」の略称で、商品が販売された時点で記録されるさまざまな情報を指します。
店舗のレジや無人決済システムを通じて自動的に収集され、売上管理や在庫管理、販売戦略の立案などに活用されます。
近年では、従来の有人レジだけでなく、「TOUCH TO GO」のような無人決済システムやセルフレジでもリアルタイムにPOSデータを取得できるため、より迅速で正確な経営判断が可能になっています。
POSデータで集められる情報
POSデータには、以下のような情報が含まれます。
| 項目 | 内容 |
| 商品が購入された日時 | 購入日や購入時間帯 |
| 商品が購入された店舗 | 複数店舗を展開している場合の店舗名や店舗コード |
| 商品が購入された個数 | 1回の会計で購入された数量 |
| 購入された商品名 | 商品の名称や商品コード |
| 購入された商品の価格 | 税込・税抜の販売価格 |
| 商品を購入した方の性別※ | 顧客の性別(※条件付き) |
| 商品を購入した方の年齢層※ | 顧客の年代区分(※条件付き) |
※性別や年齢層のデータは、ポイントカードの利用やクレジットカード・QRコードなどキャッシュレス決済を通じてのみ取得できる場合があります。
POSデータとID-POSの違い
POSデータは販売時点での商品情報や取引内容を記録しますが、「誰が購入したのか」までは特定できません。
一方でID-POSは、POSデータに顧客IDを紐づけて管理する仕組みです。
ID-POSでは、顧客ごとの購買履歴や来店頻度、購買単価などを分析できるため、より精緻なマーケティング施策やパーソナライズ化された販促活動が可能になります。
たとえばPOSデータだけでは「A商品が100個売れた」という結果しかわかりませんが、ID-POSを使えば「30代女性が中心に購入している」「特定の曜日や時間帯に売れている」といった詳細な傾向を把握できます。
これにより、ターゲットを絞った販促や商品の最適配置など、効果的な施策に直結します。
TOUCH TO GO の無人決済店舗システム『TTG-SENSE』なら、POSデータだけでなく「商品を手に取ったか」「購入されたか」まで把握可能。購買行動を可視化することで、売上改善やマーケティング戦略に活かせます。
売上改善や効率的な店舗運営を目指したい方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/
POSデータを分析するメリット
POSデータを活用すると、店舗運営やマーケティング施策において多くのメリットが得られます。ここでは代表的な5つのメリットを解説します。
売上予測の正確性が高まる
過去の販売実績や季節ごとの売れ行き傾向をPOSデータから分析することで、将来の売上予測の精度を高められます。
たとえば、前年同月比や曜日ごとの売上変動を把握することで、仕入れや在庫の量を無駄なく調整できます。
精度の高い予測は、在庫切れや過剰在庫といったリスクの軽減にもつながります。
人気商品の傾向が把握できる
POSデータには、どの商品がどれだけ売れたかが明確に記録されています。
このデータを分析すれば、売れ筋商品の特徴や購買されやすい価格帯、季節ごとのトレンドを把握可能です。
人気商品の傾向を理解すれば、販売機会を逃さない品揃えやキャンペーンの企画につなげられます。
コスト改善につなげられる
POSデータは、原価・人件費・在庫・販促費など、店舗運営に必要なあらゆるコスト改善に活用できます。
たとえば、売上と仕入れコスト、販売数量を組み合わせれば原価率を把握でき、時間帯別の売上と人員配置を比較すれば人件費効率を見直せます。
また、在庫回転率を把握すれば過剰在庫や欠品を防ぎ、保管コストや廃棄ロスの削減が可能です。
発注の最適化で配送コストや仕入れ単価を抑え、販促効果の高い商品や時期を特定すれば、広告費も効果的に配分できます。
顧客の求める商品やサービスを理解できる
POSデータは、顧客が実際に購入した商品やその数量、価格帯を明確に示します。
これらの情報を分析すれば、顧客層ごとのニーズを把握でき、新商品の開発や既存商品の改良、販促メッセージの改善に活かせます。
「何を・いつ・どんな人が」購入しているのかを理解することは、顧客満足度向上の第一歩です。
効果的な販売タイミングを見極められる
POSデータを時系列で分析すると、商品の売れ行きが特定の曜日や時間帯に集中しているケースが見えてきます。
この傾向を把握すれば、需要が高まるタイミングに合わせて在庫を確保したり、販促イベントを仕掛けたりすることで、販売効率を最大化できます。
POSデータの入手方法
POSデータは、商品の販売時点で自動的に記録されるため、特別な作業をしなくても店舗のレジや販売システムから取得できます。
どのような方法で入手するかは、導入しているシステムや業態によって異なります。ここでは、POSデータの主な入手方法を紹介します。
POSレジシステムから取得する
多くの小売店や飲食店では、POS機能を備えたレジシステムを導入しています。
これらのPOSレジシステムは、販売と同時に以下のようなデータを自動で記録します。
- 商品名
- 数量
- 価格
- 決済方法
取得したデータは、管理画面上で確認したり、CSVファイルとしてエクスポートして分析ソフトに取り込んだりできます。
また、クラウド型を採用している場合は、インターネット経由で複数店舗の売上や在庫状況をリアルタイムに確認することが可能です。
売上推移や在庫回転率などの集計レポートを自動生成できる機能を備えたシステムも多く、日次・週次・月次での定期分析や本部による一括管理にも適しています。
以下の記事で、POSレジの導入方法やおすすめ製品を紹介しています。POSレジの導入を検討している方は、ぜひチェックしてみてください。
関連記事▼
無人決済システムやセルフレジから取得する
セルフレジや無人決済システムは、顧客自身が会計を行う仕組みですが、POSデータの収集機能も標準で備えているのが一般的です。
商品スキャンや決済のたびにデータが自動で反映され、有人レジと同様に販売実績や在庫の管理に利用できます。
また、多くのシステムでは管理画面や専用アプリを通じて、売上や購入履歴をリアルタイムで確認できます。
クラウド型の場合は、複数店舗や遠隔地からのアクセスも可能なため、店舗にいなくても売上状況や在庫変動を把握でき、迅速な経営判断につなげられます。
以下の記事で、セルフレジの導入事例やおすすめ製品を紹介しています。あわせてご覧ください。
関連記事▼
外部データ連携サービスを利用する
最近では、POSデータと会計ソフト、在庫管理システム、マーケティングツールなどを自動で連携できる外部サービスが普及しています。
こうしたサービスを活用すれば、売上や在庫といった販売データだけでなく、仕入れコスト・利益率・販促効果など経営全体の状況を一元的に把握できます。
連携はクラウド経由で行われることが多く、POSデータを自動で同期・更新できるため、手作業での入力やデータ移行の手間が省けます。
さらに、各ツールの分析機能を組み合わせれば、売上推移や在庫回転率、顧客層別の購買傾向といった高度な分析も可能です。
外部のデータ提供サービスから購入する
データ提供企業から、市場全体や特定カテゴリーのPOSデータを購入できる場合があります。
これらは複数の店舗や企業から集計されたパッケージ型データで、主に市場動向や競合分析に活用されます。
ただし、自社店舗の詳細な販売データを取得したい場合は、外部購入よりも自社のPOSシステムや連携サービスを活用する方が現実的です。
POSデータの問題点
POSデータは店舗運営に役立つ一方で、活用にはいくつかの注意点や制約があります。ここでは代表的な3つの問題点を解説します。
データの扱い方に注意が必要
POSデータには売上や顧客属性などの詳細な情報が含まれるため、適切な管理が欠かせません。
セキュリティ面では、不正アクセスや情報漏えいを防ぐために、アクセス権限の制限やデータの暗号化、定期的なセキュリティチェックといった対策を徹底しましょう。
また、分析面では誤った結論を避けるために、集計条件や分析手法を明確にし、データの前提や範囲を正しく理解して活用することが重要です。
インターネット環境が必須
クラウド型POSや無人決済システムの場合、リアルタイムでデータを取得・管理するには安定したインターネット接続が必要です。
通信環境が不安定だと、データの送信や同期が遅延し、在庫や売上の把握にズレが生じる可能性があります。
特に複数店舗を運営している場合は、すべての店舗で安定したネットワーク環境を整えることが重要です。
オフライン状態が長引いた場合の対処が必要
POSレジや無人決済システムは、短時間の通信障害であれば一時的にローカル保存し、復旧後にデータを同期できます。
しかし、長時間オフライン状態が続くと、データの欠損や同期漏れのリスクが高まります。
そのため、障害発生時の手順やバックアップ方法をあらかじめ決めておき、トラブル発生時に迅速に対応できる体制を構築しておくことが大切です。
関連記事▼
POSデータの代表的な分析手法4つ
POSデータを効果的に活用するためには、適切な分析手法を用いることが重要です。
ここでは、小売や飲食などさまざまな業態で広く使われている4つの代表的な分析方法を紹介します。
ABC分析
ABC分析は、売上や利益への貢献度によって商品をA・B・Cの3ランクに分類する手法です。
- Aランク:売上や利益の大部分を占める重要商品
- Bランク:中程度の貢献度を持つ商品
- Cランク:売上や利益への貢献が小さい商品
この分析により、重点的に管理・販促すべき商品を明確にできます。在庫管理や販売戦略の優先順位付けに役立ちます。
RFM分析
RFM分析は、顧客を以下の3つの指標で評価・分類する手法です。
- Recency:最終購入日
- Frequency:購入頻度
- Monetary:購入金額
この分析により、優良顧客・休眠顧客・新規顧客など、顧客の状態を把握できます。
たとえば、最近よく購入してくれる顧客は「ロイヤル顧客」、過去に購入実績があるものの最近は離れている顧客は「休眠顧客」といった具合に分類できます。
分類結果をもとに、それぞれの顧客に合ったマーケティング施策を打つことで、顧客維持やリピート率の向上に効果的です。
バスケット分析
「マーケットバスケット分析」や「アソシエーション分析」とも呼ばれるバスケット分析は、顧客が同時に購入した商品の組み合わせを抽出する手法です。
例えば「パンを買ったお客様はバターも一緒に買う傾向がある」といった関連性を明らかにできます。
この分析結果は、クロスセルやセット販売の提案、商品陳列や販促施策の改善などに活用できます。
トレンド分析
トレンド分析は、時系列でPOSデータを追い、売上や購買傾向の変化を把握する方法です。
季節性の強い商品や流行に左右されやすい商品を管理する際に特に有効で、仕入れや販促のタイミングを最適化できます。
売れ行きが下降傾向の商品を早期に察知し、在庫リスクを減らす効果もあります。
POSデータの店舗運営への活用方法
POSデータは、単に売上を記録するだけでなく、店舗運営全般の改善や戦略立案にも大きく役立ちます。ここでは代表的な5つの活用方法を紹介します。
活用方法① 在庫管理の最適化
POSデータを使えば、商品ごとの販売スピードや在庫回転率を正確に把握できます。
これにより、売れ筋商品の欠品を防ぎ、売れ行きの鈍い商品の在庫過多を回避できます。在庫管理の効率化は、資金繰りの改善や保管コストの削減にもつながります。
活用方法② 売上予測の精度向上
過去の販売実績を分析すれば、季節変動や曜日ごとの売上傾向を把握できます。
その結果、仕入れやスタッフ配置を最適化でき、販売機会を逃さない店舗運営が可能になります。特にイベントやキャンペーン時には、予測データをもとに事前準備が行える点が強みです。
活用方法③ 品揃えの見直し・新商品開発
POSデータは、どの商品が顧客に支持されているのかを明確に示します。売れ筋商品の特徴を分析することで、類似商品の拡充や不振商品の入れ替えが行えます。
また、購買傾向をもとに新商品を企画すれば、ヒットの可能性を高められます。
活用方法④ 販促施策・キャンペーン展開
購買データを分析することで、特定の商品が売れやすい時期や顧客層を把握できます。これにより、タイムセールやポイント倍付けなど、的確な販促施策を展開可能です。
顧客の購買行動に合わせたキャンペーンは、集客効果と売上向上の両方に役立ちます。
活用方法⑤ 店舗運営の効率化と改善
POSデータは、売上だけでなく時間帯別の来店数や商品別の販売動向なども把握できるため、スタッフの配置や作業スケジュールの最適化に役立ちます。
業務効率が向上すれば、人件費の削減やサービス品質の維持にもつながります。
POSデータで売上を伸ばすための3つのポイント
POSデータは収集するだけでは意味がなく、適切に分析し、改善につなげることで初めて成果が出ます。ここでは、売上向上に直結させるための3つのポイントを紹介します。
活用目的をはっきりさせる
POSデータを分析する前に、「何のために分析するのか」という目的を明確にすることが重要です。
たとえば、在庫管理の改善や売れ筋商品の強化、顧客満足度向上など、目的が具体的であればあるほど、必要なデータの抽出や分析手法を選びやすくなります。
複数のデータを掛け合わせて分析する
POSデータ単体では見えない傾向も、他のデータと組み合わせることで浮かび上がります。
たとえば、顧客属性データや天候データ、SNSのトレンド情報などを掛け合わせると、購買行動の背景や需要の変動要因をより正確に把握できます。多角的な分析は、施策の精度を高める鍵となります。
結果を検証・改善を繰り返す
分析結果をもとに施策を実行したら、その成果を必ず検証しましょう。売上の増減や在庫の動き、顧客の反応を追跡し、必要に応じて施策を修正します。
改善を繰り返すことで、POSデータ活用の効果を継続的に高められます。
まとめ
本記事では、POSデータの基本から分析のメリット、入手方法、具体的な活用方法、そして成果につなげるポイントまで紹介しました。POSデータは、販売実績や顧客の購買傾向を可視化し、店舗運営のあらゆる場面で活用できる重要な情報源です。
データは集めるだけではなく、目的を持って分析し、検証と改善を繰り返すことで初めて売上や業務効率の向上につながります。日々の店舗運営にPOSデータを積極的に取り入れ、戦略的な意思決定に活かしていきましょう。
なお、セルフ/セミセルフレジによるPOSデータ活用をご検討の方には『TTG-MONSTAR』もご用意しています。ご興味のある方はぜひご確認ください。
関連記事▼
TOUCH TO GO の無人決済店舗システム『TTG-SENSE』なら、POSデータだけでなく「商品を手に取ったか」「購入されたか」まで把握可能。購買行動を可視化することで、売上改善やマーケティング戦略に活かせます。
売上改善や効率的な店舗運営を目指したい方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/