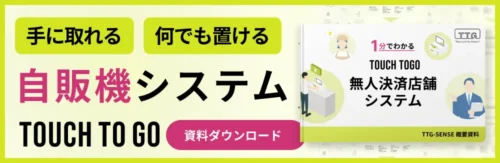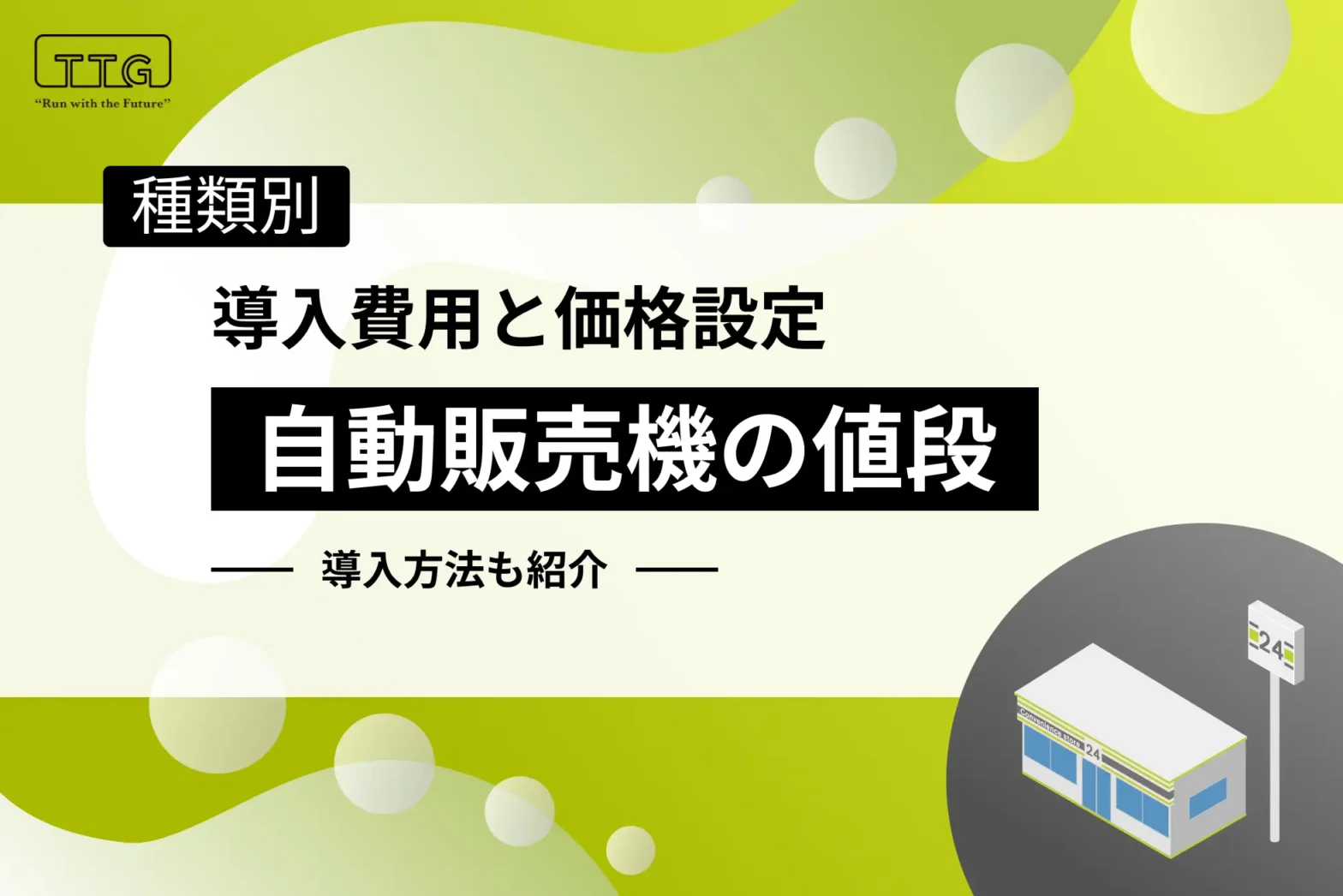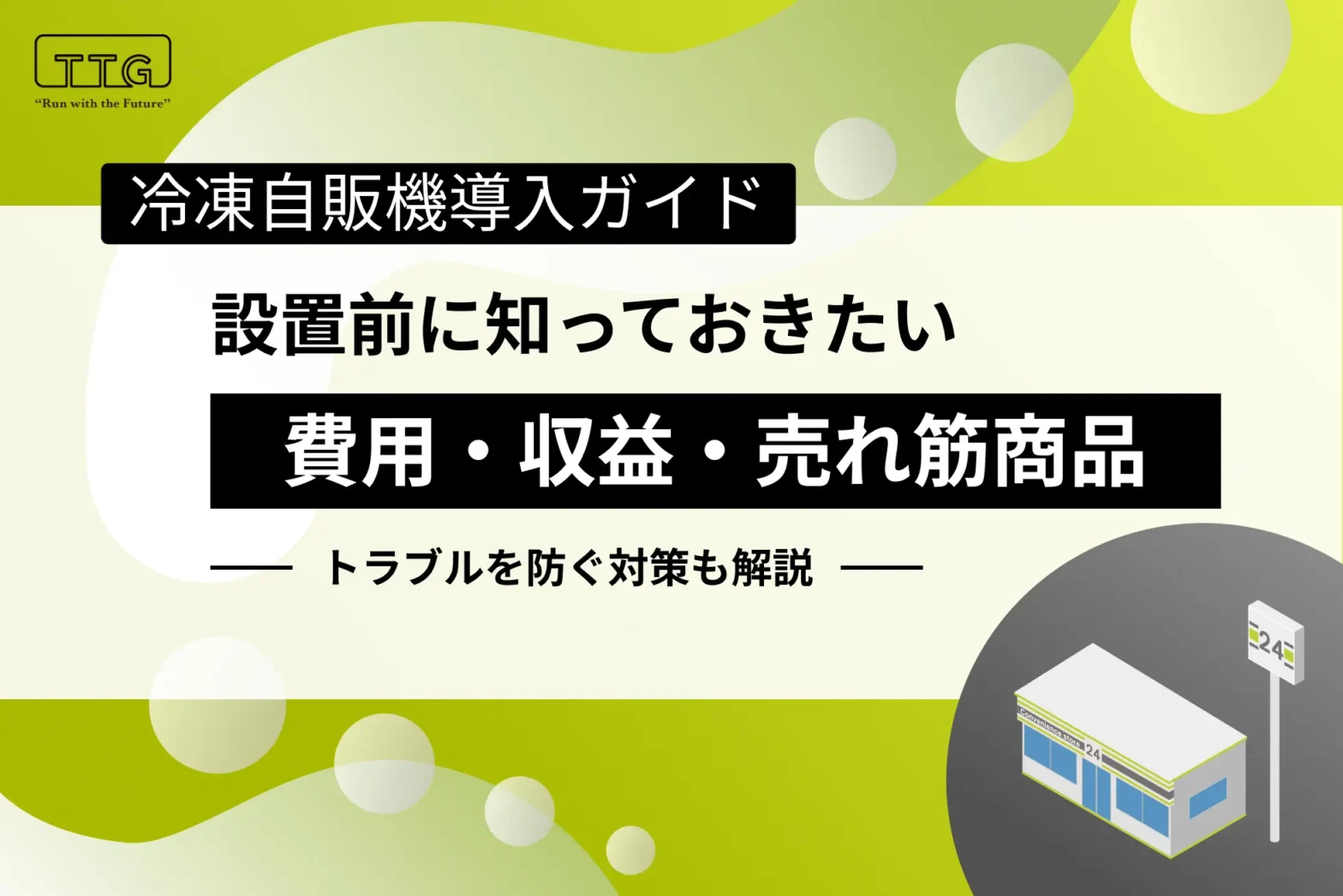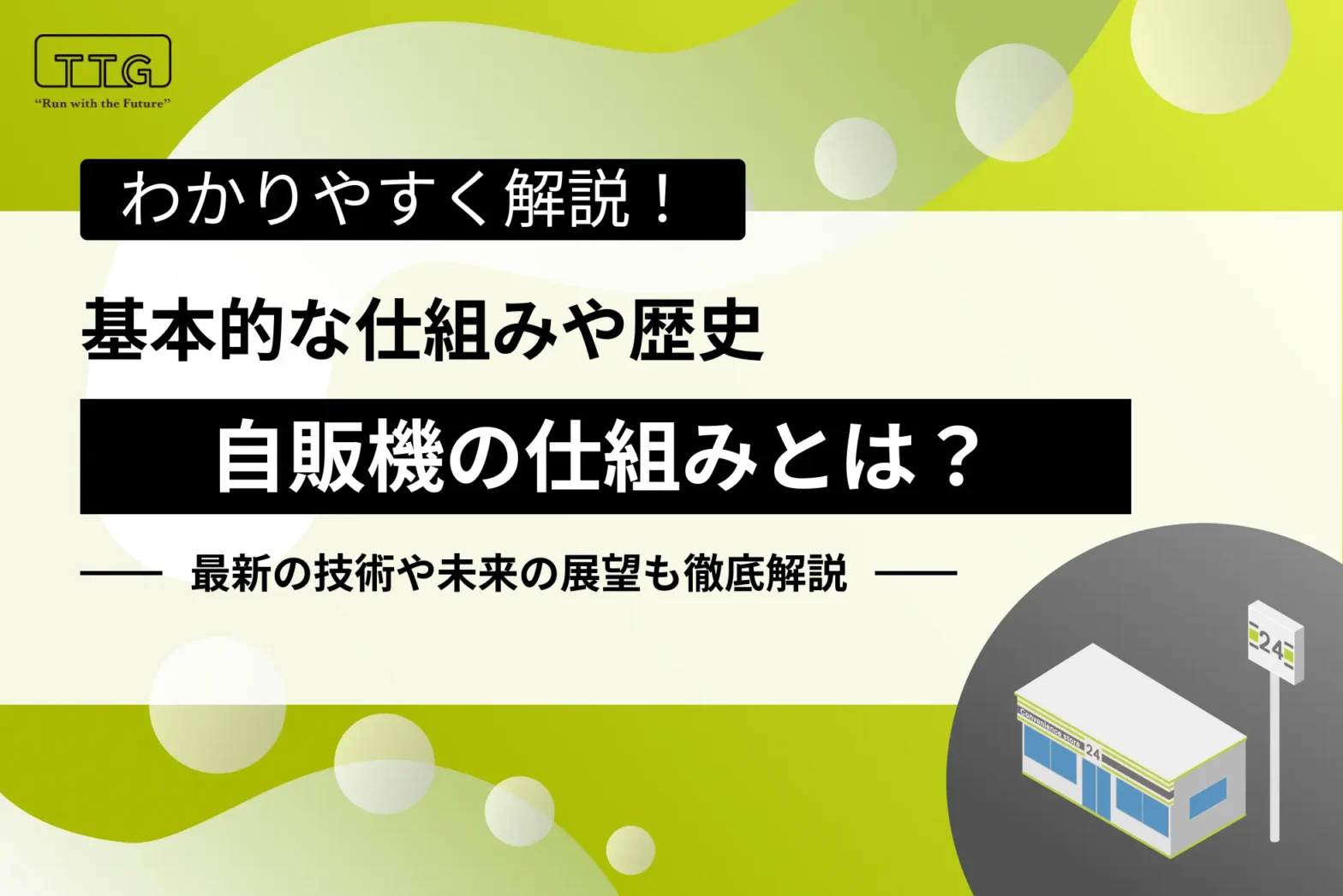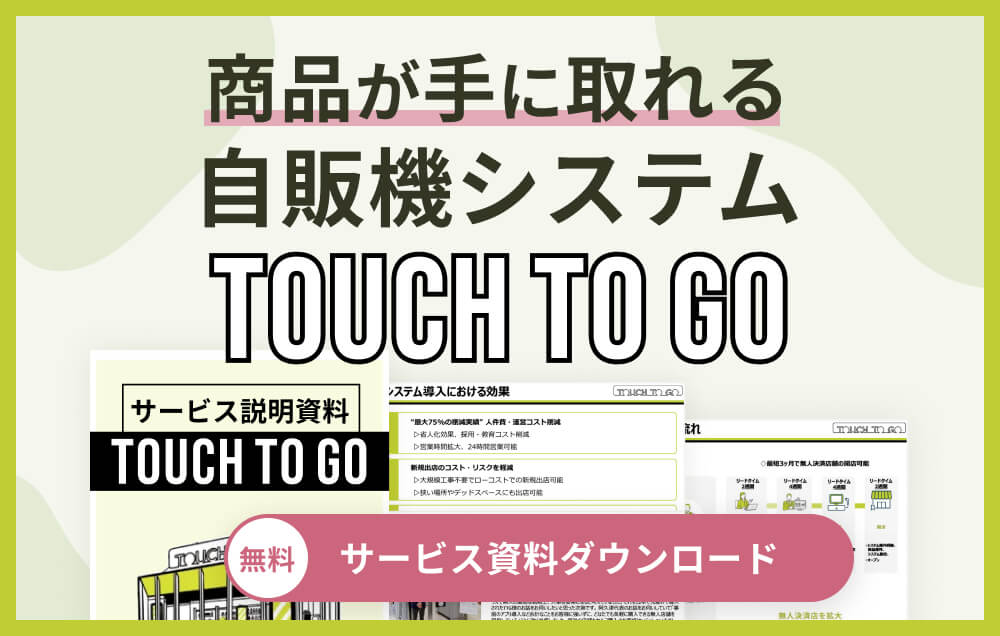Category
自販機システムの導入なら、無人決済店舗システムTOUCH TO GOにお任せください!プロダクト概要資料を下記のフォームよりダウンロードできます。
こんにちは。無人決済店舗システムを提供しているTOUCH TO GO 編集部です。
近年、街中で「ラーメン自販機」を目にする機会が増えてきました。
コロナ禍をきっかけに注目されるようになったラーメン自販機は、非対面で24時間いつでも本格ラーメンを購入できる利便性の高さから、新たな販売チャネルとして注目されています。
そこで、「自分のお店の前に置けるのでは?」「副業として始めてみたい」と、興味を持つ方も多いのではないでしょうか。
この記事では、ラーメン自販機の種類や人気ブランドの特徴、導入費用、設置方法まで初めての方にもわかりやすく解説します。
導入を検討している方はもちろん、「そもそもどんな仕組み?」という方も、ぜひ最後までご覧ください。
関連記事>>自販機設置に適している場所とは? | 無人決済・セルフレジならTOUCH TO GO
その他の関連記事
監修者プロフィール

2019年に株式会社TOUCH TO GOを設立。無人決済店舗システムを提供し、次世代型小売の拡大に取り組んでいる。
目次
ラーメン自販機とは
ラーメン自販機は、冷凍ラーメンを販売する自動販売機です。近年、その手軽さから設置台数が増加しており、全国各地でさまざまな種類のラーメンが販売されています。
とくに人気の「ヌードルツアーズ」は、2021年に丸山製麺が開発した冷凍ラーメン自販機で、全国の有名ラーメンを手軽に購入できます。
2025年5月時点で全国200ヶ所以上に展開されており、設置台数を着実に伸ばしています。
「ヌードルツアーズ」以外にも、ラーメン自販機を提供する企業は複数あり、それぞれ独自のラーメンを販売しています。
ラーメン自販機の種類
一口にラーメン自販機といっても、いくつかのタイプに分かれており、それぞれに特徴や導入の適性があります。ここでは代表的な「冷凍タイプ」「カップタイプ」「レトロタイプ」の3種類について解説します。
冷凍タイプ
現在主流となっているのが、冷凍ラーメンを販売する自販機です。有名ラーメン店監修の商品を自宅で簡単に楽しめることから人気が高まっています。
多くの製品では、麺・スープ・具材がそれぞれ冷凍パックされており、湯せんや電子レンジで調理が可能です。
味の再現度が非常に高く、二郎系や味噌・塩・魚介系など、ジャンルの幅広さも特長。商品ラインナップの柔軟性があるため、リピーター獲得にもつながりやすいのが強みです。
カップタイプ
カップタイプは、いわゆるインスタントラーメンを自販機で提供する形式です。お湯を注ぐだけで食べられるため、オフィスやサービスエリアなど「短時間で食べたい」というシーンに向いています。
価格帯は比較的安価に抑えられますが、冷凍タイプに比べると味の本格さではやや劣ります。導入コストやメンテナンスが比較的軽く、設置のしやすさがメリットといえます。
レトロタイプ
レトロタイプの自販機は、昭和時代に活躍していた紙コップ式や自動加熱式のラーメン自販機です。近年、SNS映えやノスタルジーの流行により、観光地や道の駅などで再注目されています。
ただし、機械自体が古いため、メンテナンスの難しさや部品の供給に課題があり、導入には専門知識や費用がかかるケースもあります。
「TOUCH TO GO」のプロダクトは、自販機を設置するように、工事不要でコンビニ区画を導入できます。
店舗の省人化・人件費削減をご検討中の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/
人気のラーメン自販機3つ
ここでは、代表的な3つのラーメン自販機を紹介します。
ヌードルツアーズ
「ヌードルツアーズ」は、老舗製麺所の丸山製麺が運営する冷凍ラーメン自販機ブランドです。全国の有名ラーメン店と提携し、店舗の味をそのまま冷凍して提供しています。
主な特徴としては、24時間非対面で購入可能であり、湯煎で簡単に調理できる点が挙げられます。また、ラーメン缶などの新商品も展開しており、幅広いラインナップが魅力です。
RAMEN STOCK 24
「RAMEN STOCK 24」は、凪スピリッツジャパンが運営する冷凍ラーメン自販機ブランドです。有名ラーメン店の味をそのまま冷凍し、24時間いつでも購入できる点が特徴です。
例えば、ラーメン凪の「すごい煮干ラーメン」や吉祥寺武蔵家の「家系MAX」など、人気店のメニューを取り扱っています。都内を中心に展開し、店舗の軒先や商業施設などに設置されています。
ウルトララーメン大集合
「ウルトララーメン大集合」は、ウルトラフーズ株式会社が展開する冷凍ラーメン自販機ブランドです。横浜家系ラーメンや濃厚な味噌ラーメンなど、こってり系からあっさり系まで、さまざまなラーメンを取り扱っています。
毎月1日と15日には全品550円で提供する「ウルトラの日」を実施。 東京や神奈川をはじめ、東北から九州まで幅広い地域で展開しています。
ラーメン自販機を設置するメリット
次に、ラーメン自販機を設置するメリットについて解説します。
全国の有名ラーメン店の味を24時間提供できる
ラーメン自販機の最大のメリットは、全国の有名ラーメン店の味を24時間いつでも販売できることです。
顧客は店舗の行列に並ぶ必要がなく、好きな時間に自宅で手軽に有名店の味を楽しめます。
多くのラーメン自販機では「冷凍自販機」が使用されており、店舗のラーメンに近い味をそのまま提供できます。
また、特定の地域に限定されず、全国のラーメンファンのニーズに応えられる点も魅力です。
非対面・非接触で安心して購入可能
ラーメン自販機は非対面・非接触で購入できるため、感染症対策としても有効です。
新型コロナウイルス感染症の流行以降、非接触型のサービスが求められるようになり、その需要が高まりました。
「人との接触を避けたい」というニーズにも応え、顧客は安心して好みのラーメンを購入できます。
販売・在庫管理が自動化できる
多くのラーメン自販機には、販売管理や在庫管理などのシステムが備わっています。
自動販売機本体に「売れ筋商品」「購入者の年齢・性別」「購入時間」などのデータが記録されることから、商品ラインナップの最適化が可能です。
また、在庫データも自動化できることから補充のタイミングがわかりやすく、在庫切れによる機会損失も最小限におさえられます。
自販機を広告媒体にできる
ラーメン自販機は、本体を広告媒体として活用できます。
ラッピング広告やデジタルサイネージを設置することで、自社ブランドや商品の宣伝も可能です。
また、地域密着型の広告媒体としても活用でき、特定のターゲット層にアプローチできます。
自販機自体を広告媒体にできることで、売上アップだけでなく認知度向上も期待できます。
ラーメン自販機を設置するデメリット
次に、ラーメン自販機を設置するデメリットについて解説します。
トラブル発生時に迅速な対応が必要
ラーメン自販機は電気で稼働するため、停電や電源トラブルが発生すると商品の冷凍状態が維持できなくなります。
特に長時間の停電では商品が著しく劣化し、最悪の場合は食中毒のリスクが高まるため、迅速な対応が欠かせません。
万が一のトラブルを防ぐために、日頃の点検やメンテナンスも必要です。
赤字の可能性もある
ラーメン自販機は、設置場所や商品ラインナップによって売上が大きく変わります。
人通りが少ない場所や需要が低いエリアでは売上が伸び悩み、思うように収益は上がらないでしょう。
導入前の市場調査や経営計画が不十分な場合、赤字経営に陥るリスクが高まります。
初期費用や運営コストが高くなりやすい
ラーメン自販機の導入には、自販機本体の購入費用や設置費用がかかります。
さらに、冷凍状態をキープするための電力が常に必要なため、冷蔵自販機に比べて電気代が高くなりやすい傾向があります。
運営コストが予想以上にかさむケースもあり、長期的な維持費を見据えた費用計算が欠かせません。
事前に初期費用や運営コストを把握し、収支計画を立てたうえで導入を検討しましょう。
自家製ラーメンを販売する際の許可・衛生管理の注意点
自家製のラーメンを自販機で販売する場合には、食品衛生法に基づいた複数の手続きや許可が必要になります。
とくに「製造する」「冷凍する」「自販機で販売する」という3つの工程が含まれるため、それぞれに応じた対応が求められます。
製造に必要な営業許可
まず、麺やスープなどを自社で製造する場合は、「麺類製造業」や「冷凍食品製造業」など、製造工程に応じた営業許可が必要です。
冷凍状態で販売する場合は、施設の冷凍保管能力や衛生管理体制も審査対象となります。
(出典)
営業許可業種の解説
食品の自動販売機に係る施設基準ガイドラインについて
自販機販売に必要な届出
製造した商品を自動販売機で販売するには、「自動販売機による販売業の届出」が必要です。
さらに、自販機に調理機能(加熱機能など)がついている場合は、「飲食店営業許可」が必要になるケースもあります。
販売形態が「自社製造・直販」なのか、「他社製造品の仕入れ販売」なのかによっても必要な届出が異なるため、注意が必要です。
保健所への相談が必須
必要な営業許可や届出の内容は、地域や施設の条件によって細かく異なる場合があります。導入前には必ず所管の保健所に相談し、自社の営業形態に合った必要手続きや施設基準を確認しておきましょう。
食品表示と衛生管理(HACCP)にも注意
ラーメン自販機で販売する商品には、食品表示法に基づいた適切な表示が求められます。具体的には、以下の情報の記載が必要です。
- 原材料名
- アレルゲン情報
- 消費期限
- 保存方法
- 製造者情報
なお、2020年の食品衛生法改正により、2021年以降すべての食品等事業者に対して「HACCPに沿った衛生管理」が義務付けられました。ラーメンの製造から自販機での販売に至るまで、一貫した衛生管理体制を整えることが求められます。
出典:食品衛生法の改正について
ラーメン自販機の導入費用
ラーメン自販機の導入には、さまざまな費用がかかります。ここでは、具体的な導入費用について解説します。
ラーメン自販機本体
ラーメン自販機を設置する際は、「本体を購入する」もしくは「パートナー契約を結ぶ」のどちらかになります。
多くのラーメン自販機提供会社は本体価格を公表しておらず、要問い合わせとなりますが、一般的な冷凍自販機の100〜200万円程度が相場のため、ラーメン自販機も同程度と考えられるでしょう。
また、パートナー契約の場合は提供元が定めた価格となりますが、10〜50万円程度と推測されます。
なお、パートナー契約は初期費用をおさえられますが、契約手数料や初月のレンタル料金が発生します。
関連記事>>冷凍自販機導入ガイド|設置費用・収益・売れ筋商品まで徹底解説
運営コスト
運営コストには、電気代・商品の仕入れ費用・メンテナンス費用などが含まれます。
冷凍ラーメンを販売するには、常に冷凍機能が必要です。特に夏場や気温が高い環境では電力消費が増え、電気代が高くなりやすい傾向があります。
また、ラーメン自販機で販売する商品の仕入れ費用も、運営コストの一つです。
商品単価は提供するラーメンの種類やブランドによって変わりますが、品質の高いラーメンを提供するほど原価も高くなります。
さらに、ラーメン自販機は機械であるため、定期的な点検やメンテナンスが必要です。
故障やトラブルが発生すれば修理費用が発生しますし、長時間の停電などで商品が劣化した場合は、損失コストも考慮しなければなりません。
関連記事▼
ラーメン自販機の保守・メンテナンスはどうする?
ラーメン自販機を安定的に運用するためには、設置後の保守・メンテナンスも重要なポイントです。
ここでは、ラーメン自販機の保守・メンテナンスについて解説します。
定期点検と清掃の重要性
自販機内部は冷凍環境が保たれているとはいえ、ホコリや汚れが蓄積しやすいため、定期的な清掃が必要です。
販売口やボタンまわりはとくに汚れが目立ちやすく、衛生面でも悪影響を及ぼします。
また、製品によってはメーカーや運営元による定期点検サービスが付いていることもあります。設置時にその有無を確認し、メンテナンス頻度や連絡体制を明確にしておきましょう。
温度管理とトラブル対策
冷凍機能が常に安定しているかを確認することも大切です。庫内温度が適切に保たれていないと、商品の品質が劣化し、食品事故につながる恐れがあります。
多くの自販機には温度センサーや異常通知機能が搭載されていますが、万が一の停電や機械故障に備えて、すぐに対応できる連絡先や予備電源の準備も検討しておくと安心です。
故障時の対応とサポート体制
故障した際に迅速な修理を受けられる体制が整っているかどうかも、導入前に確認しておくべきポイントです。とくに冷凍タイプは停止時間が長引くと、全商品が廃棄対象になる可能性もあります。
製造元や企業によっては24時間対応のサポート体制がある場合もあるため、サポートの内容や範囲は事前に把握しておきましょう。
ラーメン自販機の導入ステップ
ラーメン自販機の導入を検討する際は、いくつかのステップと事前準備が必要です。ここでは導入までの基本的な流れと、設置にあたって整えておきたい環境や体制について解説します。
利用するサービスによって異なりますが、一般的には以下の流れで導入します。
1.問い合わせ・相談
自販機を提供している企業に連絡し、商品の内容や契約形態、費用について相談します。
2.契約の締結
自販機の本体を購入するか、パートナー契約(リース・委託販売)を結ぶかを選び、条件に合ったプランで契約を交わします。
3.設置工事と搬入
電源やスペースの確認を経て、自販機の本体が現地に設置されます。場合によっては土台の整備や搬入経路の確保も必要です。
4.商品仕入れ・初期設定
自販機に販売するラーメンを仕入れ、価格設定や商品説明などの初期設定を行います。
5.販売開始・運用
商品を補充し、販売をスタートします。以降は在庫管理やメンテナンスなどの運用フェーズに入ります。
設置に必要な設備と環境
さらに、冷凍ラーメン自販機を設置するには、以下の設備・条件が必要になります。
- 100Vまたは200Vの電源(機種により異なる)
- 屋外対応機種の場合は屋根や日除けなどの保護措置
- 約1㎡程度の設置スペース
- 防犯対策としての監視カメラや照明
上記の設備は、設置場所の選定にも大きく関わるため、事前に現地の環境を確認しておくことが重要です。
仕入れ・補充体制の構築
自販機運用には、継続的な商品補充や在庫管理も欠かせません。販売するラーメンは、ブランド元から仕入れるのが一般的で、定期的な納品スケジュールに基づいて補充を行います。
冷凍商品のため保管・搬入時の温度管理にも注意が必要です。また、売れ行きデータをもとにラインナップを調整し、無駄なロスを防ぐことも収益性に直結します。
ラーメン自販機の設置場所を選ぶポイント
ラーメン自販機の設置場所は、売上を大きく左右する重要な要素となります。
これから紹介する選び方のポイントを参考に、売上が見込める場所を探してみましょう。
人通りの多い場所
ラーメン自販機は、人通りの多い場所に設置するのが基本です。駅前や商業施設、オフィス街などの人が多い場所であれば、安定した売上が見込めます。
とくに、若年層やビジネスマンが多い場所は、ラーメンの需要が高い傾向があり、リピーターの獲得も期待できます。
また、観光地やイベント会場も人通りが多く、ラーメン自販機に適した設置場所といえます。
立ち寄りやすい場所
ラーメン自販機の売上を最大化するには、気軽に立ち寄れる場所を選ぶことも大切です。
先ほど紹介した人通りの多い場所以外にも、日常的に利用されるエリアとして、コンビニエンスストアやスーパーマーケット前などが挙げられます。
また、住宅地周辺であれば、帰宅途中の購入や家族向けの需要も見込めます。
駐車場の有無
ラーメン自販機を設置する場所に、駐車スペースがあるかどうかも確認しましょう。
とくに郊外では車での移動が多いことから、駐車場がない場合は利用されづらくなります。
一方で、コインパーキングやショッピングモール内に設置すれば、車で訪れる顧客を取り込みやすく、集客力向上に期待できます。
競合の有無
設置予定のエリアに、ラーメン自販機や飲食店などの競合があるかどうかを事前に調査しておくことも重要です。
競合が少ない場所であれば新規顧客を取り込みやすくなりますが、競合が多い場合は、価格や商品ラインナップ、サービス面で差別化を図る必要があります。
他の冷凍食品や飲料の自販機が近くにある場合は、顧客が選びたくなるような魅力的なラーメンを取り扱いましょう。
ラーメン自販機で売上を上げるための工夫
ラーメン自販機で安定した売上を上げるためには、さまざまな工夫が必要です。
ここでは、売上を上げるためにおさえておきたいポイントを解説します。
商品ラインナップ
定番の人気ラーメンは欠かせませんが、それだけでは競合との差別化は困難です。
対策として、地域限定のご当地ラーメンや珍しいラーメンを取り入れ、顧客の興味関心を引きましょう。
また、季節ごとに冷やしラーメンや温かいラーメンを取り入れたり、期間限定メニューを提供したりすると、リピーターの獲得につながりやすくなります。
在庫管理
ラーメン自販機の品切れは機会損失につながるため、商品の売れ行きを常に把握し、適切に補充する必要があります。
また、廃棄ロスを防ぐために販売データを活用し、過剰在庫を避けながら最適な商品数を維持しましょう。
サービス強化
ラーメン自販機のサービス強化には、以下の3つのポイントが欠かせません。
- 品質管理
- 利便性向上
- 新しい価値の提供
まず、商品の品質を保つために適切な温度管理や定期メンテナンスを実施し、安心して購入できる環境を整えます。
また、キャッシュレス決済の導入や、調理方法・商品情報の表示で利便性を高めることも重要です。
さらに、季節限定商品やキャンペーンを展開し、顧客に新鮮さや楽しさを提供することでリピーターの獲得につなげます。
ラーメン自販機の設置でよくある質問(Q&A)
ラーメン自販機を初めて知る方や、導入・利用を検討している方に向けて、よくある疑問にQ&A形式でお答えします。
Q. ラーメン自販機ってどう使うの?
基本的な使い方はとても簡単です。タッチパネルやボタンで商品を選び、表示された案内に従って決済を行います。
商品は冷凍パックで出てくるため、家庭の電子レンジや湯せんで調理するだけで食べられます。
Q. どんな決済方法が使える?
自販機のタイプによって異なりますが、現金に加えてクレジットカード・交通系ICカード・電子マネー・QRコード決済などのキャッシュレス決済に対応している機種も増えています。
特に駅や商業施設にある機種は、非接触決済に対応していることが多く便利です。
Q. ラーメンの価格帯は?
商品の価格はおおむね800円〜1,200円が一般的です。ただし、有名店とのコラボ商品や具材が豪華なタイプになると、1,500円前後の商品も見られます。
高級志向の冷凍ラーメンとしては比較的リーズナブルな価格帯といえるでしょう。
Q. 衛生面は大丈夫?
ラーメン自販機は、冷凍保存を前提としており、衛生管理がしやすい設計になっています。製造元によってはHACCP対応の工場で製造されており、品質管理が徹底された商品が多く安心です。
また、多くの自販機には温度異常時のアラート機能も備わっており、万が一のトラブルにも対応できます。
Q. 子どもや高齢者でも使いやすい?
最新のラーメン自販機は、内容の写真がハッキリ表示されていたり、操作が直感的なタッチパネル式になっていたりと、誰にでも使いやすい仕様になっています。
特に画面の文字が大きく表示される機種であれば視認性に優れており、子どもや高齢者でも安心して操作できます。
まとめ
ラーメン自販機は手軽に始められるビジネスとして注目されていますが、成功には事前の準備と計画が欠かせません。
本記事で紹介したメリットとデメリットを理解し、適切な対策を講じることで安定した売上が期待できます。
また、市場調査や立地条件の選定、商品ラインナップの充実など、多角的な視点から戦略を立て、さらなる売上アップを目指しましょう。
関連記事▼
「TOUCH TO GO」のプロダクトは、自販機を設置するように、工事不要でコンビニ区画を導入できます。
店舗の省人化・人件費削減をご検討中の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/