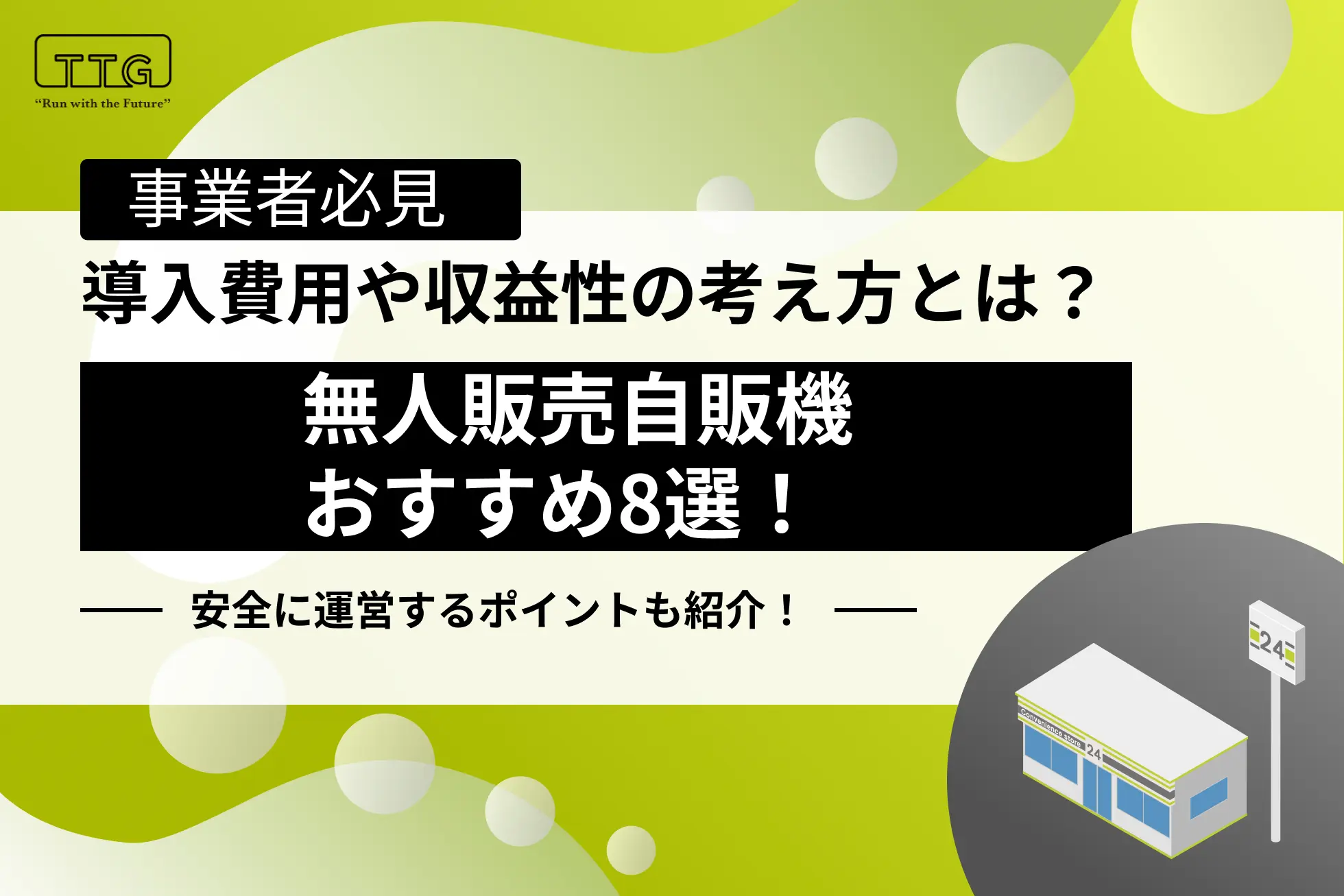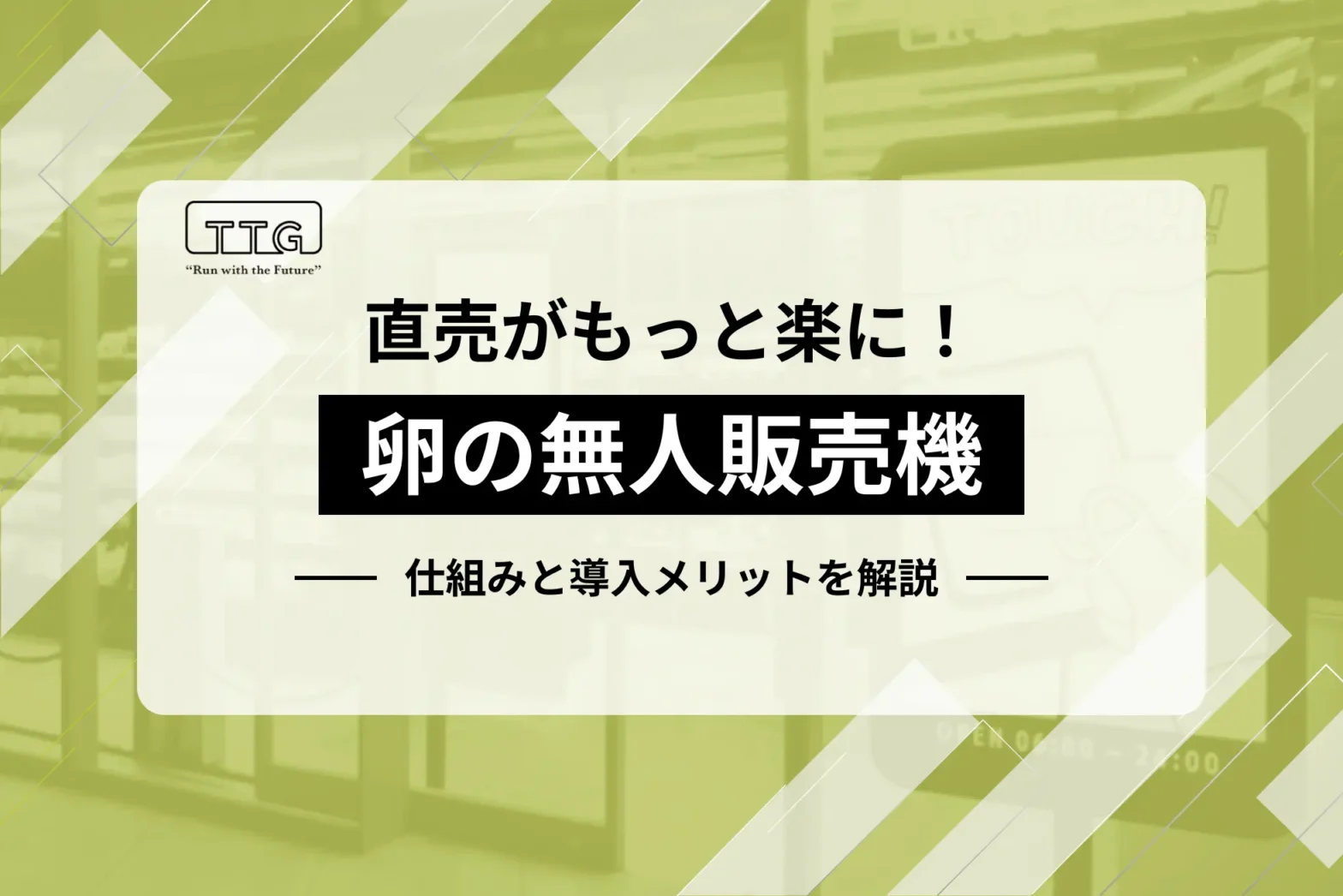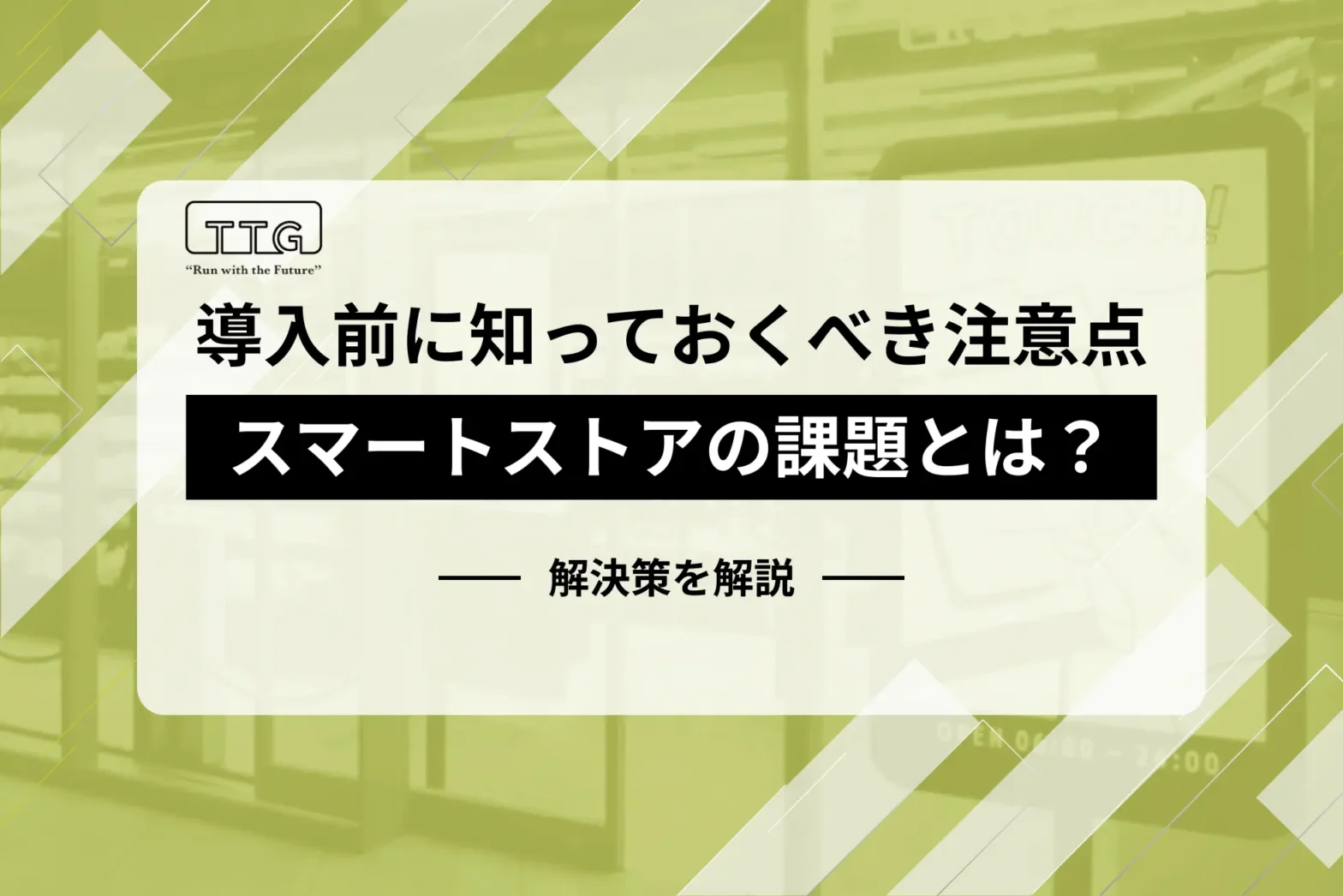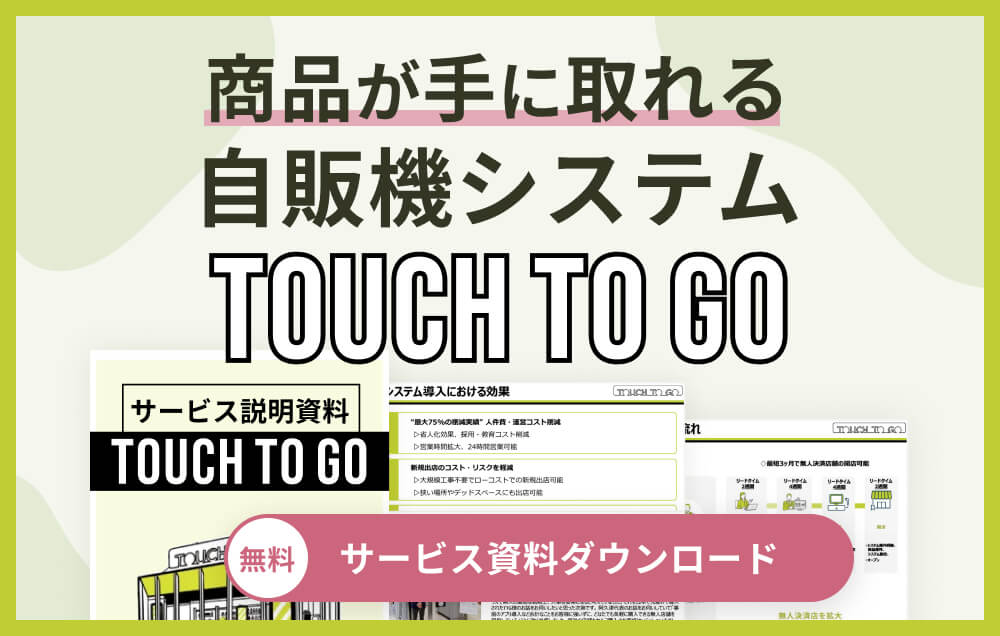Category
こんにちは。無人決済店舗システムを提供しているTOUCH TO GO 編集部です。
無人販売自販機は、人手不足への対応や省コスト化の手段として導入が広がっています。しかし、導入を検討する際には、「どんな種類の自販機があるのか」「初期費用やランニングコストはどのくらいか」「本当に収益が見込めるのか」などの疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
この記事では、おすすめの無人販売自販機8選や導入費用、収益性の考え方を解説します。さらに、無人販売自販機の安全に運営するポイントも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
▼関連記事
監修者プロフィール

2019年に株式会社TOUCH TO GOを設立。無人決済店舗システムを提供し、次世代型小売の拡大に取り組んでいる。
目次
無人販売自販機とは
無人販売自販機とは、販売員が常駐することなく商品を24時間自動で販売できる仕組みを備えた自動販売機のことです。従来の飲料やスナック菓子専用の自販機にとどまらず、近年では冷凍食品や生鮮野菜、スイーツ、日用品など幅広い商品を取り扱えるタイプが登場しています。
設置スペースさえあれば比較的容易に導入できるため、個人事業主から大手企業まで、さまざまな事業者が注目しています。
有人店舗を新たに開業するには、スタッフの採用や教育が必要となり、固定費がかさみます。一方で、無人販売自販機であれば初期投資は必要なものの、人件費をほぼかけずに継続的に販売できる点が大きな魅力です。
無人店舗との違い
無人販売自販機と混同されやすいのが「無人店舗」です。両者の最大の違いは、販売の自由度と設置形態にあります。無人販売自販機は、あくまで自動販売機の枠組みを利用するため、販売できる商品のサイズや種類には制約があります。
一方、無人店舗は店舗空間そのものを活用するため、レイアウトや商品構成の自由度が高く、幅広いラインナップを展開できます。また、導入コストや運営の手間にも違いがあります。
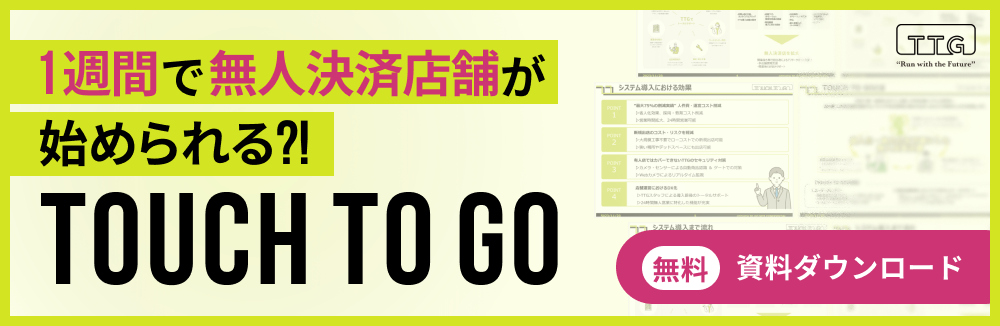
「TOUCH TO GO」のプロダクトは、自販機を設置するように、工事不要でコンビニ区画を導入できます。
店舗の省人化・人件費削減をご検討中の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/
おすすめの無人販売自販機8選
無人販売自販機といっても、販売する商品や目的によって選ぶべき機種は大きく異なります。野菜や果物などの農産物を販売できるタイプから、冷凍食品専用のモデル、スマートフォン連携で非接触販売を可能にするロッカー型まで、バリエーションは多彩です。
ここでは、無人販売自販機を8つ紹介します。
無人販売機セルフベンダー

画像引用:https://www.iseki-tls.co.jp/life_yasai.html
株式会社ISEKIトータルライフサービスが提供する「無人販売機セルフベンダー」は、農家が採れたての野菜や果物を直接販売できるロッカー型の無人販売機です。透明アクリル扉付きのボックスを備え、100円硬貨などを投入して利用するシンプルな仕組みが特徴です。常温モデルの一部は電源を必要とせず、設置場所の自由度が高い点も強みといえます。
比較的導入コストを抑えやすいことから、農家や地域の生産者にとって新しい収益源として活用しやすいのも魅力です。ただし、冷蔵・冷凍機能や防犯設備を備えたモデルでは初期費用や維持費が高くなるため、目的に応じた選択が重要です。
農産物コイン販売機 朝市くん

画像引用:https://www.yamamoto-ss.co.jp/product/nogyo/fvs.html
「朝市くん」は、山本製作所が製造するロッカー型の農産物コイン販売機です。常温で保存できる野菜や果物、加工品を対象としており、利用者はコインを投入して扉を開け、商品を受け取るシンプルな仕組みになっています。
ロッカーは複数区画に分かれており、100円・200円・300円・500円といった段階的な価格設定が可能です。奥行きのあるボックスを備えたモデルもあり、丈の長い野菜や大きめの加工品にも対応できます。
ロッカー型自動販売機 RVMシリーズ

画像引用:https://www.nakabayashi.co.jp/news/2021/release/854
RVMシリーズは、常温保存が可能な野菜・果物・雑貨などを販売できるロッカー型の自販機です。販売者は商品をロッカーに入れて鍵を施錠し、料金を設定します。購入者はコインを投入して鍵を回すだけで扉が開き、商品を取り出せる仕組みです。操作がシンプルなため、誰でも使いやすい無人販売自販機です。
さらに、サイズや扉数も複数の仕様が用意されており、ニーズに合わせたカスタマイズも可能です。
ど冷えもん

画像引用:https://www.sanden-rs.com/product/vending-machine/frozen.html
「ど冷えもん」は、サンデン・リテールシステム株式会社が展開する冷凍食品専用の自動販売機シリーズです。ラーメンや餃子、スイーツ、アイスなど、さまざまなサイズや形状の冷凍食品を一台で販売できるマルチストック方式を採用しており、商品の自由度が高い点が大きな特徴です。
ラインアップには、標準モデルのほか、冷凍・冷蔵の切替が可能な「ど冷えもん NEO」、省スペース設置に適した薄型の「ど冷えもん SLIM」、多種類の商品を収容できる大型の「ど冷えもん WIDE」などがあります。販売商品や設置環境に応じて最適な機種を選べるのも魅力です。
スマリテ

画像引用:https://www.smarite.co.jp/
「スマリテ」は、株式会社スマリテが提供する無人販売ロッカーシステムで、従来の自販機の枠を超えた先進的な機能を備えています。常温・冷蔵・冷凍の3つの温度帯に対応しており、商品の種類や季節に合わせて最適な温度管理ができるのが特徴です。
識別方式は「AIカメラ」「重量センサー」「RFID(ICタグ)」の3種類から選択でき、販売環境や商品に応じて組み合わせることで、誤認識を抑えつつ効率的に運用できます。キャッシュレス決済に対応しているため、利用者は非接触でスムーズに購入可能です。
FROZEN STATION Ⅱ

画像引用:https://www.fujielectric.co.jp/products/food/vending/product_series/c02_10.html
「FROZEN STATION Ⅱ」は、富士電機が展開する冷凍食品専用の自動販売機です。従来機と比べて収納力が約30%拡大しており、業界標準サイズのフードパック容器も収納可能な設計となっています。冷却温度は-23〜-19℃に設定されており、冷凍食品を安心して保管・販売できる仕様です。
7種類の商品を最大70個まで収納でき、視認性が高く使いやすいのが特徴です。さらに、オプションにて売上や売切、故障の遠隔管理や、キャッシュレス決済にも対応可能で、運営の効率化と利用者の利便性を両立できます。
ロッカー型IoT自販機

画像引用:https://bordstation.jp/lineup/coldplush/
「ロッカー型IoT自販機」は、通常の自販機に比べて柔軟性と機能性に優れた次世代型の無人販売機です。32インチの液晶タッチパネルを搭載し、商品説明や動画によるプロモーションが可能です。さらに、電子マネー・クレジットカード・QRコード決済など多彩なキャッシュレス決済にも対応。
さらに、外観のラッピングも可能なため、景観に合わせたデザインやブランド訴求にも活用できます。省人化と販促効果を両立できる、今注目の無人販売自販機といえるでしょう。
TOUCH TO GO
近年、無人販売のスタイルは自動販売機だけでなく、より進化した仕組みへと広がっています。その代表例が、無人決済システム『TOUCH TO GO』です。
『TOUCH TO GO』は、専用ゲートとカメラ、センサーを組み合わせたシステムにより、来店客は商品を手に取ってそのまま通過するだけで、自動的に会計が完了します。レジに並ぶ必要がなく、スムーズでストレスのない購買体験を実現できるのが大きな特徴です。
従来の無人販売自販機では商品のサイズや種類に制約がありますが、『TOUCH TO GO』なら食品や飲料から日用品まで幅広い商品に対応可能です。店舗空間を活用できるため、レイアウトや商品構成の自由度も高く、豊富な品揃えを維持しながら人件費を抑えられます。
また、売上や在庫をリアルタイムで把握できるシステムを備えており、運営の効率化にもつながります。複数のキャッシュレス決済にも対応しているため、利用者はスムーズに買い物でき、事業者にとっても現金管理の手間を大幅に削減できます。
ぜひチェックしてみてください。
「TOUCH TO GO」のプロダクトは、自販機を設置するように、工事不要でコンビニ区画を導入できます。
自社に最適なオフィスコンビニを導入したい方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/
無人販売自販機のメリット
無人販売自販機は、単なる販売設備にとどまらず、事業者にとって多くの利点をもたらす仕組みです。ここでは、無人販売自販機の代表的なメリットを6つ解説します。
24時間365日商品を販売できる
無人販売自販機の最大の魅力は、営業時間に縛られず24時間365日稼働できることです。人手を介さずに自動で商品を提供できるため、夜間や早朝など通常の店舗営業ではカバーしにくい時間帯でも売上を獲得できます。
特に住宅地や駅前、病院・学校周辺など、人の流れが途切れない場所に設置すれば、大きな収益機会につながります。
一般的な店舗よりコストを削減できる
有人店舗を運営する場合、家賃・光熱費に加えて人件費が大きな固定費として発生します。対して、無人販売自販機は本体導入費用は必要ですが、運営に必要なのは主に電気代と商品補充・清掃程度です。
人件費をほとんどかけずに事業を継続できるため、低コストで販売チャネルを拡大したい事業者に適しています。
中古での購入やリースも可能
新規導入でコストを抑えたい場合、中古機やリース契約を利用できるのもメリットです。中古市場では飲料用から冷凍食品対応までさまざまな機種が流通しており、初期投資を抑えながらスモールスタートが可能です。
また、リース契約なら分割払いにより資金負担を軽減できるうえ、最新機種への更新もしやすくなります。
幅広い商品を販売できる
従来の自販機は飲料やスナックが中心でしたが、近年は冷凍食品・生鮮野菜・スイーツ・日用品など、多彩な商品に対応できる機種が登場しています。
ロッカー型やIoT型を活用すれば、商品サイズや保存環境に合わせた販売が可能になり、販売アイテムの自由度が飛躍的に高まりました。そのため、無人販売自販機を活用することで、地域特産品やオリジナル商品の販売など、差別化戦略につなげることも可能です。
広告として商品や店舗をPRできる
無人販売自販機は、商品を販売する装置としてだけでなく、広告媒体としての役割も担います。例えば、ラッピングや液晶ディスプレイを活用することで、ブランドイメージの訴求や新商品のプロモーションが可能です。
また、設置場所によっては街のランドマーク的な存在となり、商品販売と同時に認知度アップにも貢献します。
無人販売自販機の導入費用
無人販売自販機を導入する際には、本体価格だけでなく、設置工事や電気代といったランニングコストも考慮する必要があります。
また、予算に応じてリース契約や中古機を選択する方法もあり、事業計画に合わせた柔軟な導入が可能です。ここでは、具体的な費用項目ごとにポイントを解説します。
本体価格と設置工事費用
無人販売自販機を導入する際、最も大きな初期投資となるのが本体価格です。一般的な飲料用自販機であれば数十万円から導入可能ですが、冷凍食品対応やIoT機能を備えた高機能モデルでは100万円を超えるケースもあります。
さらに設置にあたっては、基礎工事や電源工事などが必要となる場合があり、数万円から十数万円程度の追加費用が発生します。
電気代やランニングコスト
運営にかかる主なランニングコストは電気代です。冷蔵や冷凍機能を持つ機種では、1台あたり月に数千円から1万円前後の電気代がかかります。また、定期的な清掃や消耗部品の交換、補充や在庫管理にかかる人件費も見込む必要があります。
最新機種の中には省エネ性能を高めたモデルも多く、長期的な運用コストを抑えられる点も導入の判断材料となります。
リースや中古機の選択肢
初期費用を抑えたい事業者にとって有効なのが、リース契約や中古機の活用です。リースを利用すれば毎月の支払いを分散できるため、大きな資金を一度に用意する必要がありません。
さらに契約期間終了後には最新機種へ入れ替えることも可能です。一方、中古機は新品に比べて大幅に安価で導入できるのが魅力ですが、保証やサポート体制が限定的な場合もあるため、信頼できる業者からの購入が安心です。
以下の記事で、自販機の導入費用や本体価格の相場、ランニングコストを解説しています。あわせてご覧ください。
関連記事▼
無人販売自販機の収益性の考え方
無人販売自販機を設置しただけで利益が出るとは限りません。しっかりと利益を出すためには、コスト管理や設置場所の戦略、データ分析などの工夫が必要です。
ここでは、収益性を高めるために押さえておきたい3つのポイントを解説します。
仕入れコストを把握して利益率を計算する
収益性を考える上で欠かせないのが、仕入れコストの管理です。例えば、冷凍食品を1個200円で仕入れて500円で販売した場合、粗利は300円となります。
ここから電気代や補充・管理にかかる人件費を差し引くことで、実際の利益率を算出できます。商品の単価や仕入れルートによって利益構造は大きく変わるため、導入前にシミュレーションしておくことが大切です。
設置場所を選んで売上をシミュレーションする
自販機の売上を左右する最大の要因は「設置場所」です。駅前や商業施設の近くなど人通りが多い場所では、販売回転率が上がりやすくなります。
一方、住宅街やオフィス街では、特定の時間帯に売上が集中する傾向があります。候補地の通行量や利用者層を調査し、販売数を予測してシミュレーションを行うことで、より正確に収益を見込めます。
関連記事▼
季節や時間帯ごとの販売データを分析する
自販機の売れ行きは、季節や時間帯によって大きく変動します。夏場は冷たい飲料やアイスが売れやすく、冬場は温かい飲み物や惣菜系の需要が高まります。
また、通勤時間帯や昼休み、深夜帯なども売上の山場になりやすい時間帯です。最新のIoT自販機なら販売データを遠隔で収集できるため、これらの傾向を分析し、商品構成や補充頻度を最適化することで収益性を高められます。
関連記事▼
無人販売自販機を安全に運営するポイント
無人販売自販機は省人化や収益化に優れる一方で、盗難やイタズラといったリスクも伴います。安全に運営するためには、防犯対策や決済方法の工夫に加え、在庫や売上を遠隔で把握できる仕組みを取り入れることが大切です。
ここでは、無人販売自販機を安心して運営を続けるためのポイントを紹介します。
盗難やイタズラを防ぐ仕組みを導入する
無人販売自販機は人が常駐しないため、盗難やイタズラのリスクがあります。強化ガラスや頑丈なロッカー型構造を選ぶことで被害を軽減できます。また、防犯カメラを設置し、周辺を明るく保つことで犯罪の抑止力が高まります。
さらに、センサーやアラームを搭載した機種を利用すれば、不正開錠や衝撃を検知した際に通知を受けられるため安心です。
キャッシュレス決済でトラブルを減らす
現金の取り扱いは釣銭切れや誤作動などのトラブルにつながりやすい面があります。その点、キャッシュレス決済を導入すれば、利用者の利便性が高まるだけでなく、現金管理の負担を減らし、盗難リスクも抑えられます。
特にQRコード決済や電子マネーに対応した自販機は、若年層から高齢層まで幅広い顧客に受け入れられやすい傾向があります。
関連記事▼
在庫や売上を遠隔で管理できるようにする
最新のIoT自販機では、売上や在庫状況を遠隔から確認できる機能が搭載されています。この仕組みを活用すれば、補充のタイミングを最適化でき、品切れによる販売機会の損失を防げます。
また、異常検知やエラー通知も行えるため、万が一のトラブルにも迅速に対応可能です。運営の効率化と安全性の両面を考える上で、遠隔管理機能は欠かせない要素といえるでしょう。
関連記事▼
まとめ
無人販売自販機は、24時間365日稼働でき、人件費をかけずに商品を提供できる新しい販売方法として注目を集めています。野菜や冷凍食品、日用品など取り扱える商品も幅広く、設置環境に応じた多様なタイプが登場しています。
導入の際には費用や収益性、運営方法を見極めることが重要ですが、工夫次第で安定したビジネスモデルへと育てることができます。これからの時代に合った販売方法のひとつとして、無人販売自販機の導入を検討してみてください。
関連記事▼
「TOUCH TO GO」のプロダクトは、自販機を設置するように、工事不要でコンビニ区画を導入できます。
店舗の省人化・人件費削減をご検討中の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/