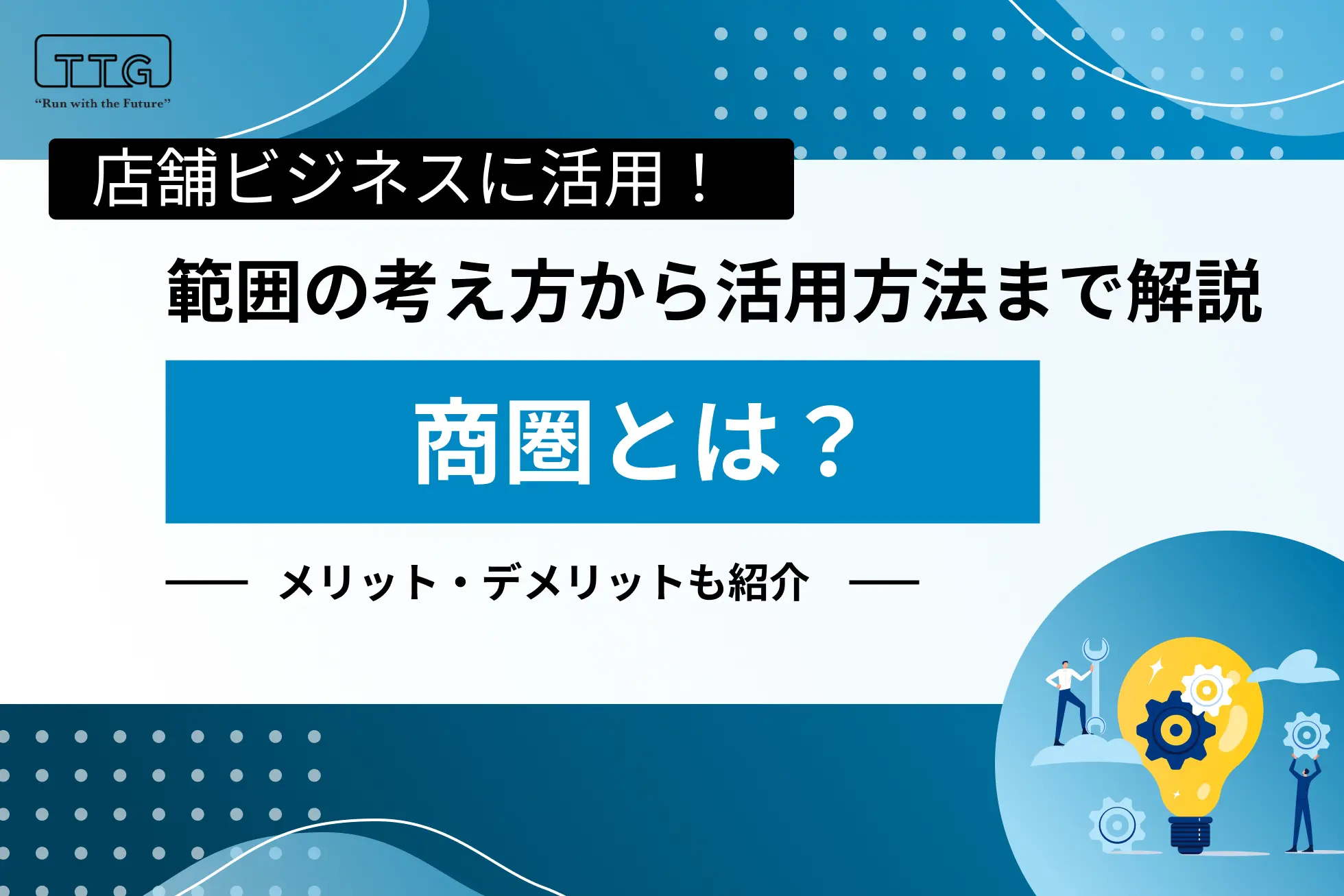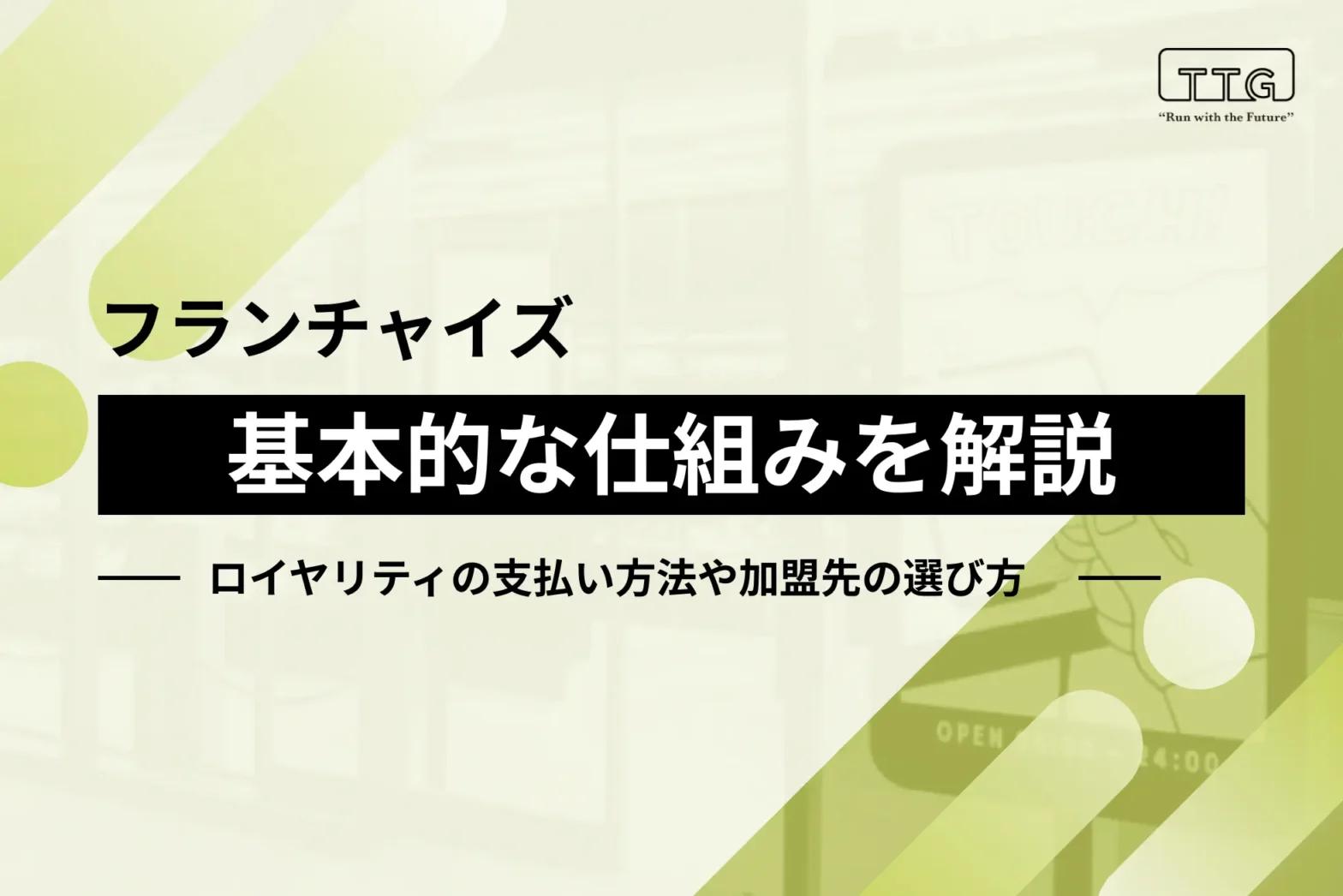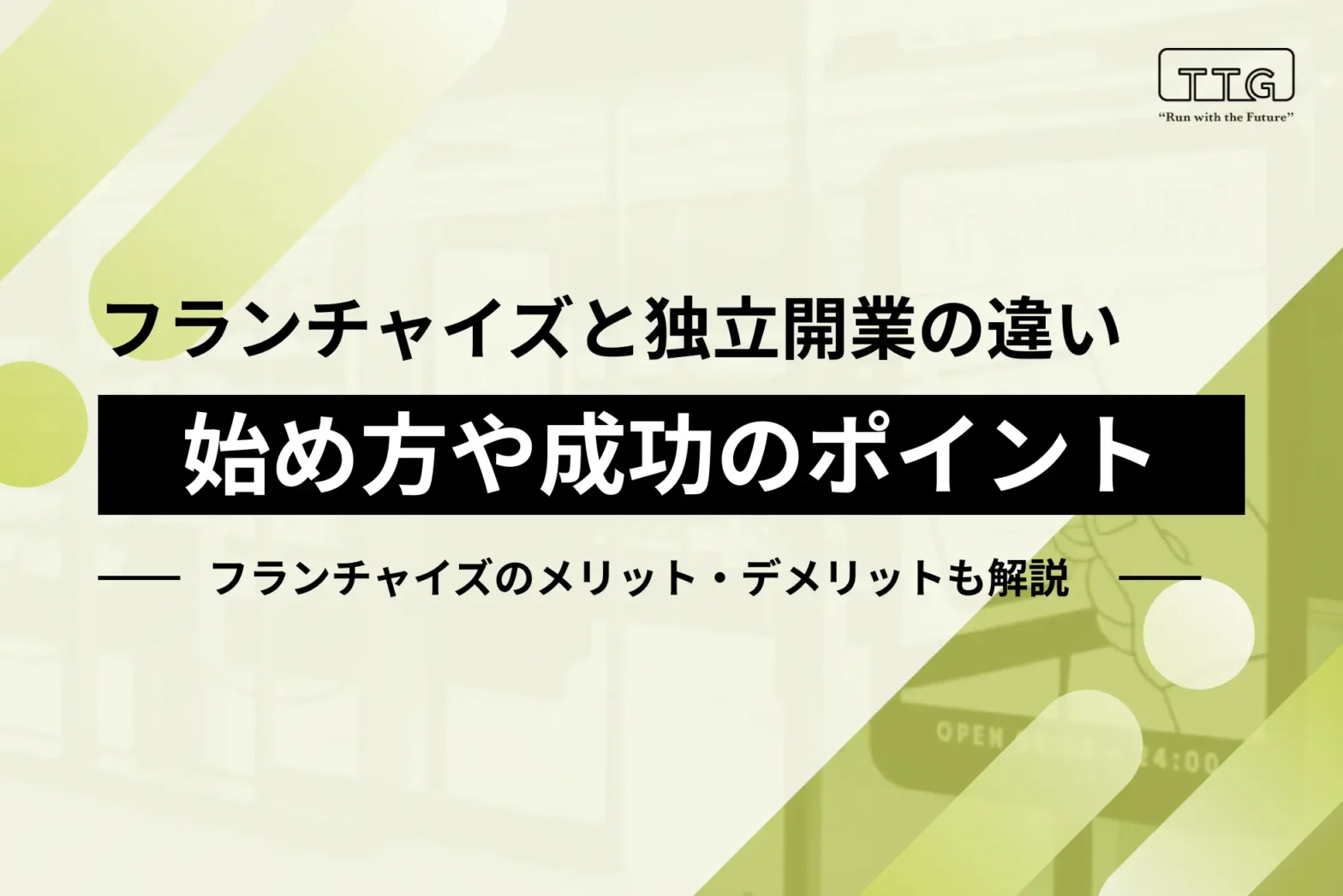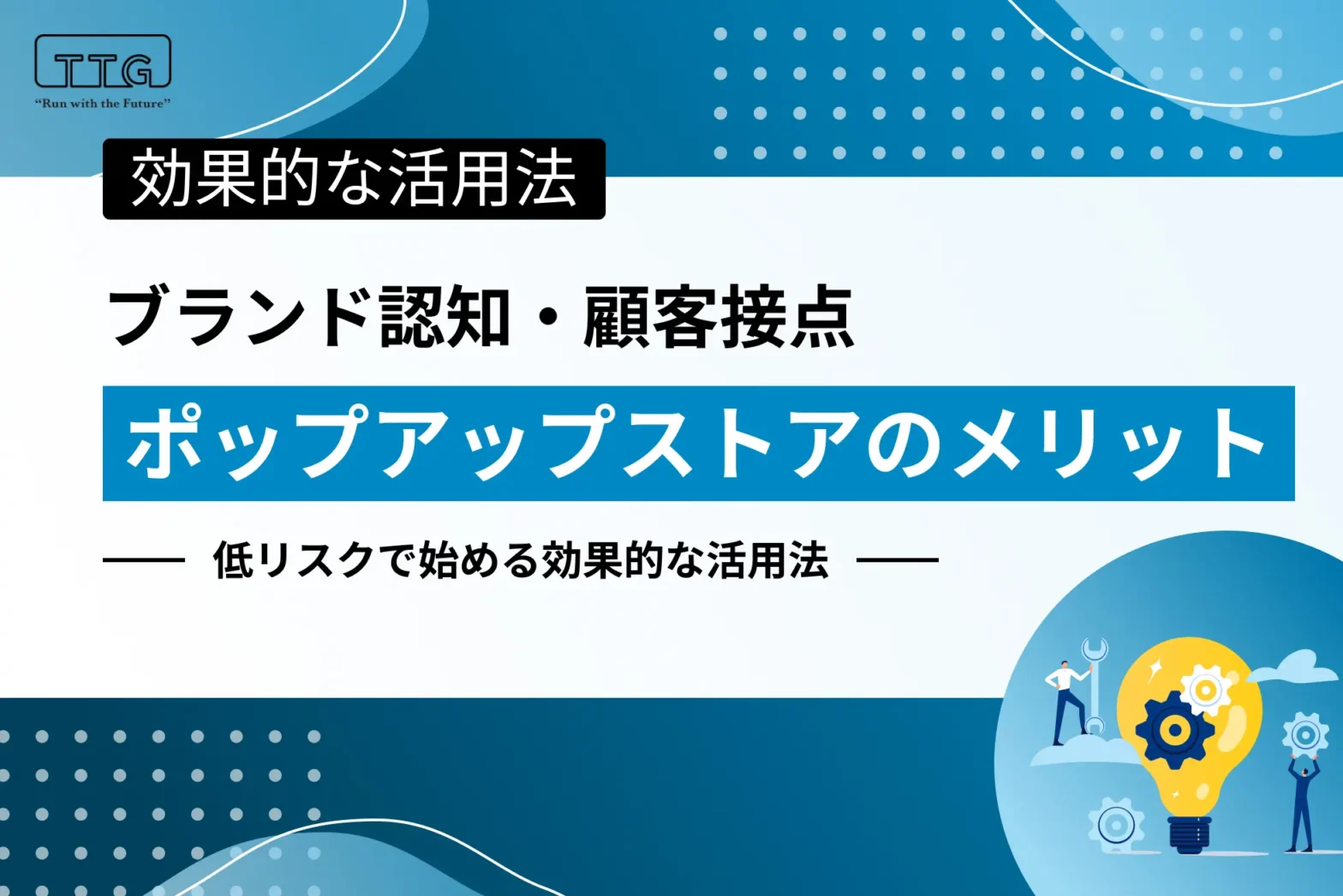Category
こんにちは。無人決済店舗システムを提供しているTOUCH TO GO 編集部です。
店舗ビジネスを成功させるうえで欠かせないのが「商圏」の考え方です。どれだけ魅力的な商品やサービスを提供していても、商圏の設定を誤れば十分な集客ができず、売上にも影響してしまいます。
一口に商圏といっても、その範囲は距離や時間、交通事情、業態などによって大きく変わります。また、商圏分析を行うことで、出店候補地の選定や販促エリアの最適化、将来の売上予測など、店舗運営の判断材料を得ることができます。
この記事では、商圏の基本的な定義から種類・範囲の違い、商圏を決める際のポイントを解説します。活用シーンやメリット・デメリットも紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
関連記事▼
監修者プロフィール

2019年に株式会社TOUCH TO GOを設立。無人決済店舗システムを提供し、次世代型小売の拡大に取り組んでいる。
目次
商圏とは?
商圏とは、店舗への来店が見込まれる顧客が居住・滞在している範囲を指します。言い換えると「商売が成立するエリア」のことです。小売店や飲食店、美容室など、業種を問わず商圏の広さは集客数や売上に直結する重要な要素となります。
商圏を考える際には「どこからどれくらいのお客様が来るのか」を具体的にイメージすることが大切です。一般的には自宅や職場からの距離や到達時間を基準にしますが、それだけでは十分ではありません。
交通機関の利便性や道路事情、地域の人口密度や特性、さらには競合店の存在など、複合的な条件によって実際の商圏は大きく変わります。したがって、単に距離を測るのではなく「顧客が現実的に来店できる環境かどうか」を見極める視点が求められます。
商圏の種類・範囲
商圏の種類を理解することは、自店の集客可能性を見極めるうえで欠かせないステップです。ここでは、代表的な分類方法や地域特性、業態ごとの違いについて解説します。
距離による商圏の分類
商圏を最もわかりやすく区切る方法が「距離による分類」です。店舗を中心に半径何km圏内を商圏とするかを設定し、その範囲ごとに顧客の来店頻度や購買行動が変わると考えられています。
以下の表は、一般的に使われる「足元商圏」「一次商圏」「二次商圏」「三次商圏」の目安を整理したものです。
| 商圏の種類 | 距離の目安 | 到達時間の目安 | 特徴 |
| 足元商圏 | 徒歩〜半径500m | 徒歩5分以内 | 常連客が中心で来店頻度が高い |
| 一次商圏 | 〜半径1km | 徒歩10〜15分、または自転車数分 | 日常利用者が中心、売上の主要エリア |
| 二次商圏 | 約2〜5km/場合によってはもっと広く | 自転車で15分程度 | 特別な来店目的が見込める範囲 |
| 三次商圏 | 5km以上(地域によって10km〜) | 車・公共交通で30分以上かかることも | 目的性が強く、来店頻度は低めだが広域から集客可能 |
このように、近い範囲ほど来店頻度が高く、遠くなるにつれて来店回数は減少します。ただし、イベントや特売など特別な要因があれば、三次商圏からの来店も十分に期待できます。それぞれの種類について、以下で詳しく見ていきましょう。
足元商圏
店舗から徒歩数分圏内にあたる最も近い範囲を指します。コンビニやクリーニング店のように日常的な利用が多い業態では、この足元商圏が売上の大半を支えることも少なくありません。
一次商圏
徒歩や自転車で気軽にアクセスできる範囲で、半径500m〜1km程度が目安です。スーパーやドラッグストアなど、生活必需品を扱う店舗は一次商圏の顧客が中心になります。
二次商圏
公共交通機関や車で来店するお客様が多く、半径2〜5km程度が目安です。ショッピングモールやファミリーレストランなど、目的を持って訪れる店舗は二次商圏の顧客が大きな割合を占めます。
三次商圏
5km以上の遠方から訪れる顧客層を指します。テーマパークや大型アウトレットモールなど、目的性の強い施設や店舗は広域から集客できるため、三次商圏の影響も無視できません。
地域特性による商圏の違い
商圏は同じ距離であっても、地域特性によって広さや集客力が大きく異なります。都市部と郊外では人口密度や交通手段が違うため、同じ1km圏内でも来店可能な顧客数は大きく変わります。
以下で、都市部と郊外それぞれの立地特性について見ていきましょう。
都市型立地
都市部は人口が密集しているため、比較的狭い範囲でも多くの顧客を取り込むことができます。徒歩や自転車での移動が中心となり、一次商圏や足元商圏が特に重要です。カフェや小売店など、立地条件によって売上が大きく左右されやすい特徴があります。
郊外型立地
郊外では人口密度が低いため、商圏の範囲が広がる傾向にあります。自動車での移動が前提となることが多く、二次商圏・三次商圏までを含めて顧客を見込む必要があります。ロードサイド店舗や大型専門店などは、郊外型商圏に合わせた戦略が不可欠です。
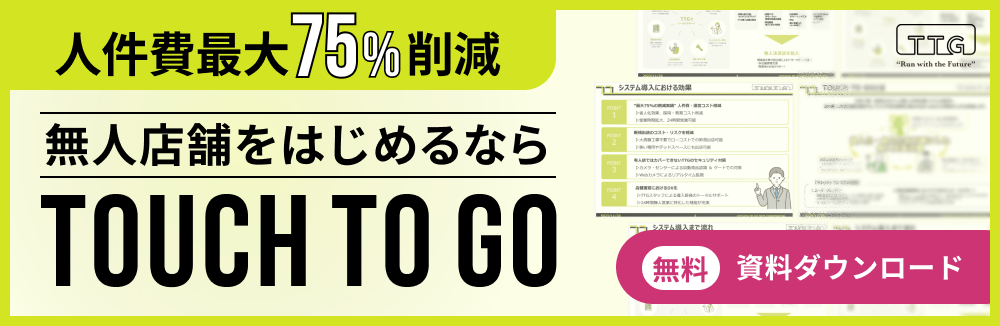
無人決済店舗システム「TOUCH TO GO」なら、限られたスペースにも出店が可能です。来店者の動きはカメラで自動的にトラッキングされ、手に取られた商品は棚のセンサーが検知。最小人数での店舗運営を実現できます。
店舗の省人化・人件費削減をご検討中の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/
商圏の決め方
商圏を決める際には、一つの基準だけに頼るのではなく、複数のアプローチを組み合わせることが大切です。大きく分けると「データに基づく分析」と「現地での観察(フィールドワーク)」の2つの方法があります。
以下で、それぞれの特徴と活用方法を解説します。
データ分析
データ分析は、商圏を客観的かつ効率的に把握するための方法です。国勢調査や自治体の統計データを活用することで、人口・世帯数・年齢層・所得水準など、潜在顧客の属性を数値で把握できます。
また、交通量データや通勤・通学の動線を調べると、実際に人の流れがどこに集中しているかも見えてきます。例えば、同じ1km圏内でも「高齢者が多い地域」と「若いファミリー層」が多い地域では、必要とされる店舗やサービスは大きく異なります。
データを使うことで「どんな顧客が、どのくらい存在するのか」を把握でき、出店や販促の判断をより精度高く行えるのです。ただし、データ分析だけでは数字に現れない地域の特性を見落とす可能性もあるため、次に紹介するフィールドワークと組み合わせることが重要です。
フィールドワーク
フィールドワークとは、実際に現地に足を運び、街の雰囲気や人の動きを直接確認する調査方法です。例えば、同じ「人通りの多いエリア」でも、平日と休日、昼と夜では客層や賑わい方が大きく変わることがあります。
データだけでは捉えきれない、リアルな生活感や利用動線を把握できるのがメリットです。具体的には、次のようなポイントを観察します。
- 時間帯ごとの人の流れ
- 歩行者と車の動線の違い
- 周辺施設(学校・病院・商業施設など)の利用状況
- 競合店舗の立地や客入り
上記のような項目を把握することで、「駅前は人通りが多いが、実際の買い物は駅から離れたスーパーで行われている」などの気付きを得られることがあります。こうした現地の実態を商圏設定に反映させ、より実効性のある戦略を立てることが大切です。
商圏分析の目的
商圏を理解すること自体は出発点にすぎません。実際の経営に役立てるには、商圏分析を通じて「どこに出店すべきか」「どの範囲に販促を打つか」「どれくらいの売上が見込めるか」などの判断材料を得る必要があります。
ここでは、商圏分析が店舗経営にどのような目的で活用されるのかについて、具体的に解説します。
出店候補地の選定
新規出店を検討する際、商圏分析は最も重要な判断基準のひとつです。商圏内の以下の要素を調べることで、その立地に十分な集客力があるかどうかを見極められます。
- 人口規模
- 世帯数
- 顧客層の属性
- 競合店の分布
たとえば、人口は多いものの競合店が密集しているエリアでは、差別化戦略が不可欠になります。一方で、周辺に競合が少なく交通の利便性も高いエリアであれば、新規出店の成功確率は高まります。
商圏分析を活用すれば、感覚や経験に頼らず、データに基づいた出店判断が可能になります。
販促エリアの最適化
商圏分析は、広告やチラシ、キャンペーンを展開する際にも役立ちます。来店が見込めるエリアを明確に把握すれば、無駄な範囲にコストをかける必要がなくなります。
例えば、新聞折込チラシを配布する場合、二次商圏の一部ではほとんど効果が見込めないケースもあります。その場合は一次商圏に限定して配布する方が効率的です。
逆に、車利用が多い地域では二次商圏まで含めて広告を展開した方が、成果につながることもあります。商圏ごとの特性を踏まえることで、販促活動の費用対効果を高めやすくなります。
売上・需要の予測
商圏分析を行うことで、将来的な売上や需要を予測することも可能です。商圏内の人口動態や購買力を調べれば、「どの程度の売上が期待できるのか」を見積もることができます。
特に、住宅地の開発や再開発、駅前の商業施設オープンなどは商圏に大きな変化をもたらします。こうした動きを先取りして需要予測を行えば、店舗運営のリスクを抑え、長期的に安定した売上を確保できるようになります。
顧客分布の可視化
商圏分析のもう一つの目的は、自店の顧客分布を「見える化」することです。顧客データを地図に落とし込めば、来店が多いエリアと少ないエリアが一目で分かり、店舗の強みと弱みを明確にできます。
その結果、販促を強化すべきエリアや、コストを抑えるべきエリアを的確に判断でき、売上改善や戦略の見直しにつながります。
以下の記事で、商圏分析の概要や進め方を解説しています。あわせてご覧ください。
関連記事>>商圏分析とは?新規店舗出店時に知っておくべき活用例や進め方を解説!
商圏分析に活用するデータ
商圏分析に使えるデータにはいくつかの種類があります。人口や世帯数などの基本的な情報から、競合店舗の立地や交通状況まで、多角的に確認することで精度の高い分析が可能になります。
以下の表に代表的なデータの種類を表にまとめました。
| データの種類 | 内容 |
| 基礎データ | 人口・世帯数 |
| 属性データ | 年齢・所得・家族構成 |
| 交通データ | 交通量・道路条件 |
| 競合データ | 競合店舗の立地・規模 |
このように、商圏分析では人口や属性、交通、競合といった多様なデータを組み合わせて考えることが重要です。それぞれのデータについて、具体的に見ていきましょう。
人口・世帯数などの基礎データ
商圏分析を行ううえで、まず確認すべき基本情報が「人口」と「世帯数」です。これらは潜在的な顧客規模を把握するための土台となり、どの程度の需要が見込めるかを測る出発点となります。
たとえば、同じ半径1km圏内であっても、都市部には数万世帯が集まっている場合がありますが、郊外では数千世帯にとどまるケースも少なくありません。この差が、そのまま潜在的な来店可能人数の違いにつながります。
人口・世帯数などは、国勢調査や自治体が公開する統計資料を見ることで把握できます。
年齢・所得などの属性データ
人口規模だけでは、商圏内の顧客像を十分に把握することはできません。実際の消費行動に影響を与えるのは、以下のような「属性データ」です。
- 年齢層
- 所得水準
- 家族構成
これらを分析することで、商圏に住む人々がどのような商品やサービスを求めているのかをより具体的にイメージできます。
例えば、子育て世帯が多い地域ではファミリー向けの飲食店や学用品の需要が高まります。一方、単身世帯や若年層が多い地域では、コンビニやテイクアウトなど、手軽に利用できる業態が支持されやすい傾向があります。
このように、年齢や所得などの属性データは、単に「どれだけ人が住んでいるか」を超えて、「どのようなニーズが存在するのか」を示してくれる重要な指標といえます。
交通量・道路条件に関するデータ
顧客が実際に来店できるかどうかは、交通の利便性が大きく影響します。主要道路沿いや幹線道路のアクセス、信号・踏切・渋滞状況などを調べると、実際の来店可能範囲をより現実的に予測できます。
たとえば、直線距離では近くても、川や線路などの物理的な障害があると来店しにくくなります。一方、交通アクセスが良好で駐車場も整っている幹線道路沿いの店舗であれば、10km以上の範囲から車で集客できる可能性もあります。
このような交通データの分析も、商圏を設定するうえでの重要な判断要素となります。
競合店舗や周辺施設のデータ
最後に欠かせないのが競合状況の把握です。同じ商圏内に強力な競合店がある場合、自店舗が取り込める顧客は限られます。一方で、飲食店街やショッピングセンターのように「集積効果」が働く立地では、競合が多いほど人が集まり、相乗効果で集客できることもあります。
また、競合だけでなく周辺施設の存在も重要です。学校や病院、オフィス街などの施設は顧客層の属性に直結し、購買行動を左右します。こうした情報をあわせて分析することで、商圏の強みとリスクを立体的に把握できます。
無人決済店舗システム「TOUCH TO GO」なら、限られたスペースにも出店が可能です。来店者の動きはカメラで自動的にトラッキングされ、手に取られた商品は棚のセンサーが検知。最小人数での店舗運営を実現できます。
店舗の省人化・人件費削減をご検討中の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/
商圏分析の活用シーン
商圏分析は単なる理論やデータ収集にとどまらず、実際の経営判断に直結します。ここでは、商圏分析がどのような場面で役立つのかを見ていきましょう。
新規出店計画での活用
商圏分析の最も代表的な活用シーンは、新規店舗の出店計画です。候補地ごとに人口規模や世帯数、顧客属性、競合状況を分析することで、そのエリアに出店する価値があるかどうかを客観的に判断できます。
たとえば「駅から徒歩5分の立地」と聞くと好条件に思えますが、周囲に同業態の店舗が集中していれば差別化が難しく、十分な売上が見込めない場合があります。逆に、郊外のロードサイドでも、交通量が多く駐車場を完備できる立地であれば、広域からの集客が期待できます。
商圏分析は、こうしたメリット・リスクを可視化し、投資判断の精度を高める役割を果たします。
販促・キャンペーン施策への応用
商圏分析は、販促活動やキャンペーンの効果を最大化するための有効な手段です。来店可能性が高いエリアを特定できれば、広告費を集中投下することで費用対効果を高められます。
例えば、新聞折込チラシを配布する際には、商圏全域に配布するのではなく、一次商圏を中心に限定的に配布した方が効果的な場合があります。また、SNS広告であれば、商圏データをもとに配信エリアを設定することで、来店確率の高い層に的確にアプローチできます。
このように、商圏の実態に合わせて販促施策を設計すれば、無駄なコストを抑えながら集客効果を高められます。
既存店舗の商圏見直し
商圏分析は新規出店だけでなく、既存店舗の改善にも大きな効果を発揮します。顧客データをもとに実際の来店エリアを把握すれば、想定していた商圏と実態にギャップがあることが明らかになるケースも少なくありません。
例えば「二次商圏からの来店を期待していたが、実際には一次商圏の顧客ばかりだった」という場合、広告戦略や商品構成を見直す必要があります。
逆に「意外と遠方からの来店が多い」と分かれば、その層に合わせたキャンペーンを展開することで新しい需要を掘り起こせます。既存店舗の商圏を定期的に見直すことは、安定的な売上を維持するために欠かせない取り組みの一つです。
商圏を理解するメリットと注意点
商圏分析にはメリットが多い一方で、いくつかの注意点や課題も存在します。ここでは、商圏分析を導入することで得られるメリットと、押さえておきたいリスク・解決策について解説します。
商圏分析のメリット
商圏を分析する最大のメリットは、経営判断をデータに基づいて行える点です。商圏分析を行うことで、出店や販促、商品構成の決定を「勘」や「経験」に頼らず、客観的に進められます。
また、顧客分布が見える化されることで、効率的に広告や販促を実施でき、無駄なコストを削減できます。さらに、競合の強さや周辺環境を把握することで、差別化戦略を考える材料にもなります。
商圏分析の課題・デメリット
一方で、商圏分析には課題もあります。第一に、データ収集や分析には手間とコストがかかります。国勢調査や統計データは誰でも入手できますが、情報が古かったり精度に限界があったりするケースも少なくありません。
また、商圏は固定されたものではなく、人口動態や交通インフラの変化によって常に動いています。そのため、一度分析しただけで安心してしまうと、実態とのズレが生じるリスクがあります。
さらに、専門知識がないとデータの解釈を誤り、誤った経営判断につながる恐れもあります。
課題を解決する方法
こうした課題を解決するためには、まず「データは最新のものを使う」ことが大前提です。自治体の公開統計に加え、商業データベースやマーケティング調査会社の情報を組み合わせることで精度を高められます。
さらに、商圏分析は一度きりではなく「定期的に見直す」ことが重要です。年に1回でも実施すれば、人口変動や競合状況の変化を把握でき、柔軟に戦略を修正できます。
必要に応じて、専門家や外部コンサルタントの力を借りるのも有効です。このような工夫を取り入れることで、商圏分析のメリットを最大限に活かしつつ、リスクを最小限に抑えることが可能になります。
まとめ
商圏は、店舗経営の基盤となる重要な概念です。商圏分析を活用することで、経営判断の精度を高められます。
データ収集や分析には手間がかかりますが、定期的に見直して最新の状況を反映させれば、成果は着実に積み重なります。
商圏を正しく把握することは、無駄のない投資と効率的な集客につながります。新規出店を検討している方も、既存店舗を強化したい方も、まずは自店の商圏を振り返ってみましょう。
関連記事▼
無人決済店舗システム「TOUCH TO GO」なら、限られたスペースにも出店が可能です。来店者の動きはカメラで自動的にトラッキングされ、手に取られた商品は棚のセンサーが検知。最小人数での店舗運営を実現できます。
店舗の省人化・人件費削減をご検討中の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/
RECOMMEND / この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます
-

フランチャイズの仕組み|ロイヤリティの支払い方法や加盟先の選び方も解説
こんにちは。無人決済店舗システムを提供しているTOUCH TO GO 編集部です。 フランチャイズは、独立してビジネスを始めたい人々にとって魅力的な選択肢の一つです。 既に確立され...
-

フランチャイズと独立開業の違いとは?始め方や成功のポイントも解説
こんにちは。無人決済店舗システムを提供しているTOUCH TO GO 編集部です。 起業を考える際、フランチャイズと独立開業のどちらを選ぶべきか迷う方も多いのではないでしょうか。 ...
-

ポップアップストアのメリットとは?ブランド認知・顧客接点・低リスクで始める効果的な活用法
こんにちは。無人決済店舗システムを提供しているTOUCH TO GO 編集部です。 ポップアップストアは短期間でブランド認知を高め、顧客とのリアルな接点を築ける効果的な手法です。 ...
-

アクセサリーのおすすめ陳列方法やポイントを紹介します
ここではアクセサリーの陳列方法に関する情報を、以下の項目にそって紹介します。 アクセサリーのおすすめ陳列方法 アクセサリーの陳列の注意点 「インテリアやコンセプトに悩んでしまい、セ...