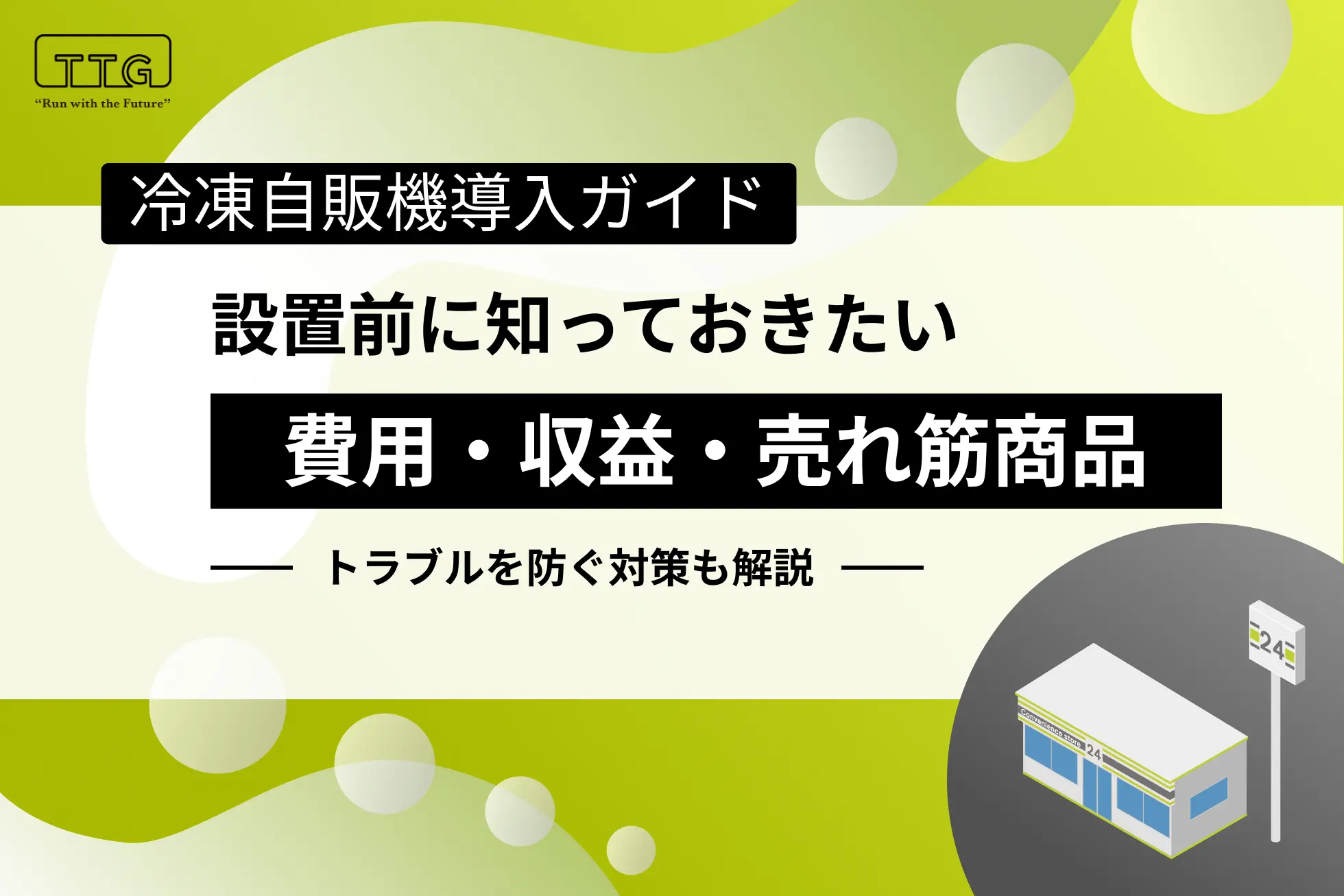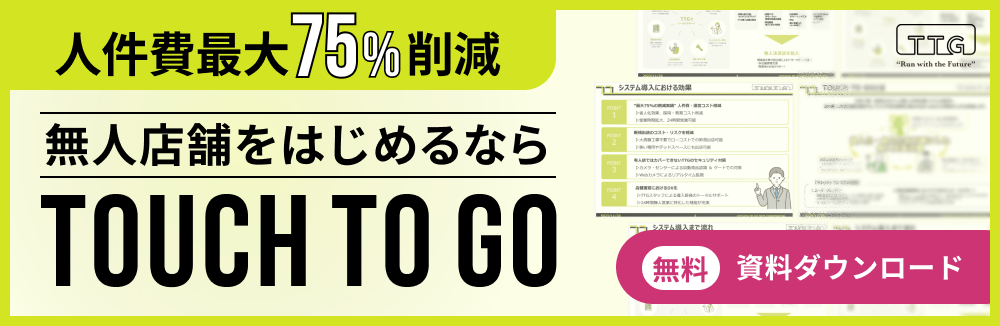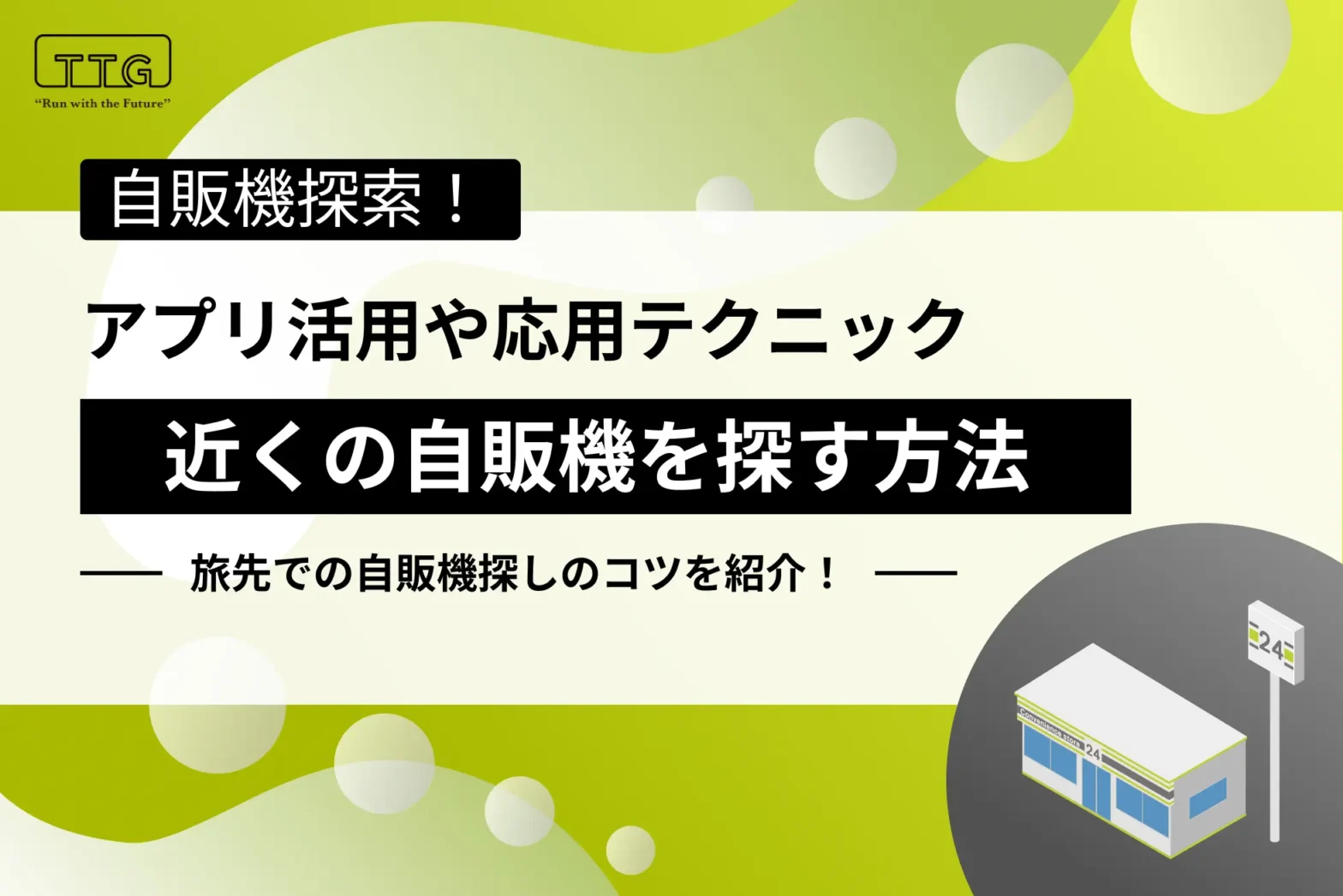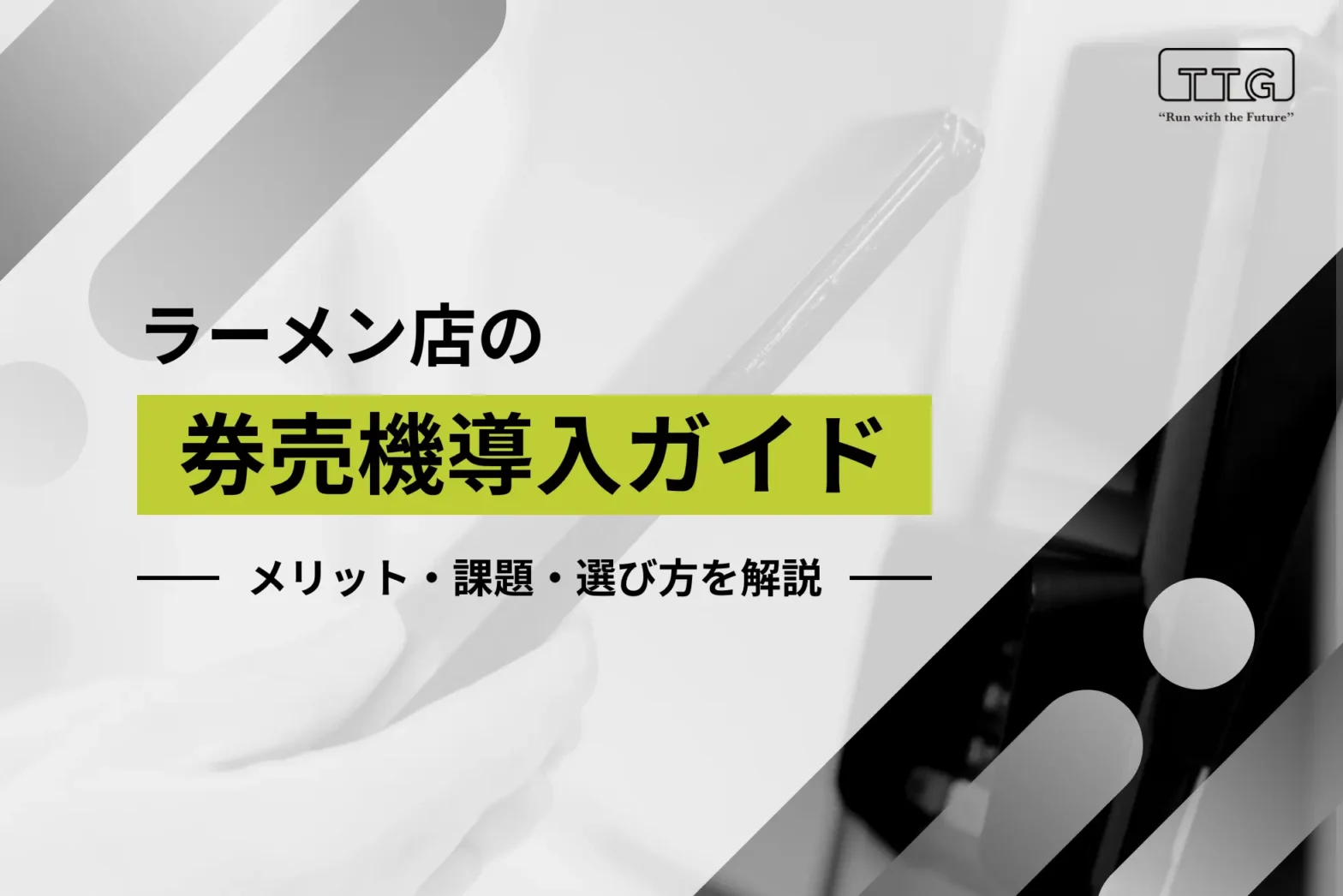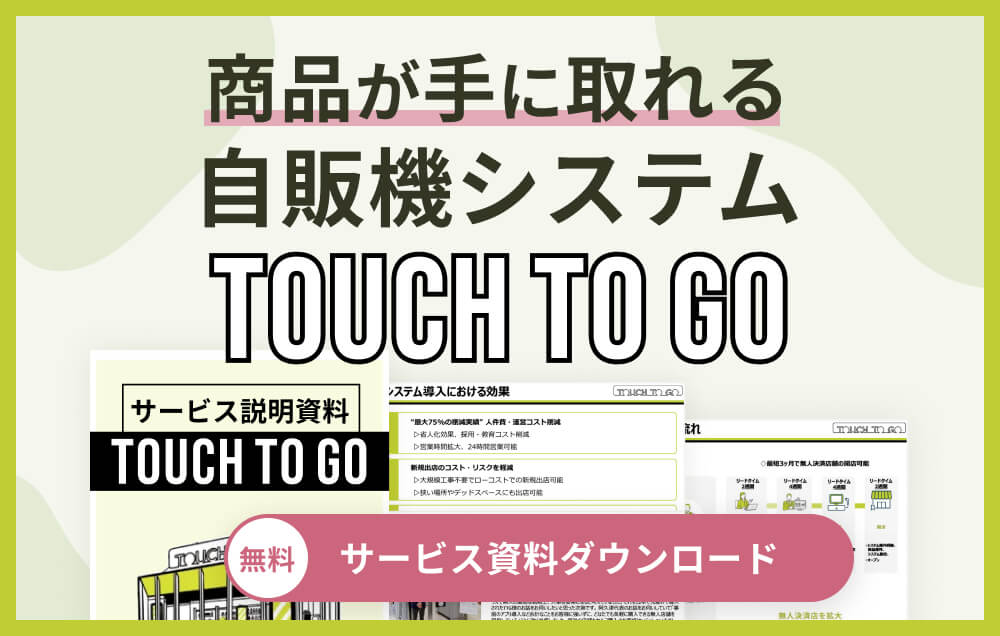Category
こんにちは。無人決済店舗システムを提供しているTOUCH TO GO 編集部です。
冷凍自販機は、便利で効率的な商品販売の方法として近年注目を集めています。
従来の冷蔵自販機では飲料やお菓子などを販売するのが一般的ですが、冷凍自販機はアイスクリームや餃子など、さまざまな冷凍食品の扱いが可能です。
さらに、冷凍自販機は無人で稼働できることから人件費削減や運営の効率化など、さまざまなメリットがあります。
今回の記事では、冷凍自販機の特長や活用例、そして人気商品の傾向を紹介します。
さらに、設置費用や収益シミュレーション、トラブルを防ぐための対策まで幅広く解説するので、ぜひ参考にしてください。
関連記事▼
監修者プロフィール

2019年に株式会社TOUCH TO GOを設立。無人決済店舗システムを提供し、次世代型小売の拡大に取り組んでいる。
目次
冷凍自販機とは?
冷凍自販機は、食品や飲料を冷凍状態で販売できる自動販売機です。
近年ではアイスクリームなどのスイーツ以外にも、冷凍食品・弁当・惣菜など、さまざまな冷凍自販機が登場しています。
冷凍自販機は無人で24時間営業が可能なため、利用者は時間に制約されることなく、いつでも冷凍食品を購入できます。
また、スタッフが常駐する「有人店舗」と比較すると、人件費や店舗賃料などのコスト削減効果があります。
冷凍自販機のビジネスモデルの具体例として、以下のような方法が挙げられます。
飲食店のテイクアウト販売
飲食店のメニューを冷凍して販売することで、新たな顧客層の獲得や、営業時間外の売上増加に期待できます。
地域特産品の販売
地元の特産品を冷凍して販売することで、地域活性化にも貢献できます。
イベントや催事での販売
冷凍食品やアイスクリームをイベント・催事で販売することで、売上増加を狙えます。
売れ筋の冷凍商品と人気ジャンル
冷凍自販機で安定した売上を得るには、「どんな商品を販売するか」がとても重要です。
導入する場所の特性や利用者層に合った商品ラインナップを選ぶことで、リピーターの獲得や口コミによる拡散も期待できます。
ここでは、冷凍自販機で人気のあるジャンルや、売れ筋商品を選ぶ際のポイントについて紹介します。
人気のジャンルと特徴
冷凍自販機では、次のようなジャンルの商品が特に人気を集めています。
冷凍ラーメン
ラーメン専門店の味をそのまま自宅で楽しめるとして、非常に人気の高いジャンルです。スープと麺が別々にパックされているものが多く、クオリティが高い商品が多いため、グルメ志向の消費者からの支持を集めています。
スイーツ
アイスやチーズケーキ、カヌレなどの冷凍スイーツは、手軽なおやつや手土産として需要があります。見た目の華やかさや「映え」を意識したパッケージも多く、女性や若年層をターゲットとするエリアでの設置に向いています。
餃子・唐揚げ・ハンバーグなどの家庭料理系
家庭で手軽に調理できるメニューは、忙しい共働き世帯や単身者層から人気です。中でも餃子や唐揚げは根強い定番人気があり、一度買った人が再度購入しやすいというメリットもあります。
ご当地グルメ
観光地や道の駅などでは、地元の名物や特産品を使った冷凍食品が人気です。「旅先の味をおみやげに」といったニーズにマッチし、地域活性化の一環として導入されるケースも増えています。
売れ筋商品を選ぶときのポイント
人気のジャンルを把握するだけでなく、実際にどの商品を選ぶかもとても重要です。
売れ行きを安定させたり、在庫管理をスムーズに行ったりするためには、次のようなポイントを意識するとよいでしょう。
賞味期限・保存性の高い商品を選ぶ
冷凍とはいえ、商品によって保存期間は異なります。できるだけ賞味期限が長く、劣化しにくい商品を選ぶことで、廃棄リスクを減らせます。
包装がシンプルで取り出しやすいもの
利用者が自販機から取り出す際に、かさばったり取りにくかったりするとストレスになります。
取り出しやすさや耐久性のある包装がされている商品は、ユーザー体験の向上にもつながります。
ターゲット層に合った価格帯・ボリューム感
学生が多いエリアでは、「安くてボリュームのある商品」が好まれます。一方、高所得層が多い住宅地では、「少量でも高品質で特別感のある商品」に需要が集まります。
このように、設置場所の客層に合わせて価格や内容量のバランスを考えることが、売れ行きを左右するポイントになります。
関連記事▼
「TOUCH TO GO」のプロダクトは、冷凍自販機を設置するように、工事不要でコンビニ区画を導入できます。
店舗の省人化・人件費削減をご検討中の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/
冷凍自販機を選ぶポイント
次に、冷凍自販機を選ぶポイントを3つ紹介します。
自販機のサイズ
冷凍自販機は、商品を一定の温度で保つための冷却機能が必要ですが、機能に応じて本体サイズや内部構造が異なります。
そのため、冷凍自販機を設置する際は、設置スペースにあわせて適切なサイズと容量の自販機を選ぶ必要があります。
たとえば、設置場所のスペースが狭い場合は、小型の機種を選ばなければなりません。
反対に広いスペースが確保できる場合は、大型の冷凍自販機を設置して、より多くの商品を取り扱うことも可能です。
商品にあわせた温度や容量
販売したい商品に適した機種を選ぶことも、重要なポイントの1つです。
たとえば、アイスクリームを販売する場合は-20℃前後の温度をキープできる冷凍自販機が必要です。
また、冷凍弁当や惣菜を扱う場合は、商品の取り出しやすさや収納スペースも考慮するべき要素となります。
冷凍自販機の価格とランニングコストについて
次に、冷凍自販機の価格とランニングコストについて紹介します。
購入・リース・レンタルの費用
冷凍自販機を導入する際は、購入・リース・レンタルのどれかを選択することになります。
冷凍自販機の価格は機種や機能によって異なり、どの方法で導入するかによってランニングコストも変わります。
購入・リース・レンタル、それぞれの費用目安は次のとおりです。
| 導入方法 | 価格目安 |
| 購入 | 200万円程度/台 |
| リース | 月額3〜5万円/台 |
| レンタル | 月額3〜5万円/台(設置費用・撤去費用は別途必要) |
月々の電気代やランニングコスト
冷凍自販機のランニングコストには、電気代やメンテナンス費用などが含まれます。
電気代は使用頻度や機種により異なりますが、毎月5,000〜8,000円程度となります。
また、メンテナンス費用は定期的な清掃や点検費用などが該当します。
本体の保証期間内であれば無料ですが、期間終了後、もしくは保証がない場合は修理代として1回あたり2〜3万円程度の費用が発生します。
関連記事▼
冷凍自販機ビジネスの収益モデルと儲けの目安
ここでは、冷凍自販機1台あたりの月間売上・利益のシミュレーションをもとに、冷凍自販機ビジネスの収益構造を解説します。
月間売上と利益シミュレーション
たとえば、以下のような販売条件を想定した場合の月間収支は次の通りです。
- 1日あたりの販売数:20個
- 商品単価:700円
- 原価率:65%(平均的な水準)
この条件で算出した場合の月間売上と利益は次の通りです。
月間売上:20個 × 700円 × 30日 = 42万円
商品原価:42万円 × 65% = 約27万3,000円
粗利益:約14万7,000円(粗利率:約35%)
さらに、以下のような運用コストを差し引くと、実質の営業利益が見えてきます。
- 電気代:月5,000〜8,000円
- メンテナンス費用(定期点検や簡易修理など):月3,000〜5,000円
- その他:通信費・消耗品など月1,000〜2,000円程度
実質営業利益(目安):約13万円〜13万5,000円
このように、安定した販売数と原価管理ができていれば、1台あたりでも十分な収益性が見込めるのが冷凍自販機の特徴です。
利益率を高めるための工夫
限られたスペースと商品点数の中で利益を最大化するには、次のような工夫が効果的です。
原価率の低い商品を選定する
たとえば、自社製造の商品や原材料の調達コストを抑えたメニューを導入することで、原価率を60%以下に抑えることも可能です。粗利の確保には、商品開発の工夫が重要です。
まとめ買い割引やポイント制の導入
「2個購入で100円引き」や「次回使える割引クーポン」などを導入することで、客単価やリピート率を向上させることができます。デジタル決済システムとの連動で柔軟な施策も展開可能です。
季節限定・数量限定などの販促策を活用
「冬季限定スープ」「ご当地グルメフェア」など、希少性のある商品や期間限定メニューは単価アップや話題性の向上につながります。SNSでの拡散とも相性が良く、集客効果も期待できます。
ランニングコストをおさえるためのポイント
ランニングコストをおさえるためのポイントは、次のとおりです。
【省エネ機能搭載の機種を選ぶ】
省エネ機能のある機種を選ぶことで、電気代を削減できます。
【適切な温度管理】
適切に温度管理することで、商品の品質を保ちながら無駄な電気消費をおさえられます。
【定期的な清掃とメンテナンス】
定期的な清掃やメンテナンスにより故障のリスクが下がり、修理費用を節約できます。
冷凍自販機の設置場所の選び方と注意点
冷凍自販機の売上は、設置する場所によって大きく左右されます。どれだけ良い商品を扱っていても、立地条件が悪ければなかなか売れません。
ここでは、冷凍自販機の設置場所の選び方と注意点を解説します。
屋外と屋内、どちらに設置すべきか
冷凍自販機は屋外・屋内のどちらにも設置できますが、それぞれに適した環境と注意点があります。
屋外に設置する場合は、直射日光や雨風、気温変化の影響を受けやすいため、屋根付きの場所や耐候性のある機種、防水・防塵対策が必要です。
屋内であれば天候の影響が少なく、補充や清掃もしやすくなりますが、スペースの確保や施設側の許可が必要になるケースもあります。
それぞれの特性をふまえて、設置場所の環境や目的に合った選択を行いましょう。
通行量と人目につきやすい場所を選ぶ
冷凍自販機は、通りすがりの購入が中心となるため、人目につきやすい場所に設置することが大切です。
駅前や商業施設の入口、観光地など、人通りの多い場所はそれだけ購入のチャンスも高まります。
また、時間帯によって利用者層は変わります。「昼は主婦や会社員」、「夜は帰宅途中の社会人や学生」など、想定するターゲットに合わせて設置場所を選びましょう。
さらに、近くに同じような冷凍自販機がある場合は、商品内容や価格で差別化できるかがポイントです。事前に競合の有無を確認しておくことをおすすめします。
電源・防犯面のチェックポイント
設置場所を選ぶ際は、安定した電源の確保と、防犯対策にも注意が必要です。
冷凍自販機には100Vまたは200Vの電源が必要なため、設置場所に十分な電力が供給できるか、延長コードが必要かなどを事前に確認しておきましょう。
屋外に設置する場合は、防犯カメラや照明の有無、死角の少なさなど、安全面のチェックも欠かせません。
さらに、補充やメンテナンスを考慮し、搬入しやすい導線や車の横付けが可能かどうかも確認しておくと、運用がスムーズになります。
関連記事>>自動販売機の設置ガイド|費用・条件・収益の仕組みまで徹底解説
冷凍自販機の導入に必要な許可・届出
冷凍自販機を設置して食品を販売する場合、事前に確認すべき法的手続きがあります。販売する商品によっては、営業許可や届出が必要になるケースもあるため、あらかじめチェックしておくことが大切です。
販売する商品によって必要な許可が異なる
冷凍自販機で食品を販売する際には、「食品衛生法」に基づく営業許可が必要になることがあります。
特に、冷凍弁当や惣菜などの加工食品や調理済み食品を製造・販売する場合は、「そうざい製造業」や「冷凍食品製造業」の営業許可が求められるケースが多いです。
一方で、未開封の冷凍スイーツや個包装された冷凍食品などは、許可が不要な場合もあります。ただし、食品表示や保存方法など、別の法令に基づくルールを守る必要があります。
どのような商品を取り扱うかによって対応が変わるため、導入前に商品の分類を明確にしておくことが重要です。
保健所での事前確認が重要
営業許可の要否や申請の手続きは、設置する地域を管轄する保健所が担当しています。
必要な許可や条件は自治体によって異なる場合があるため、事前に販売品目や設置予定場所の情報を用意し、保健所に相談するようにしましょう。
無許可での販売は、営業停止命令や罰則の対象となる可能性もあります。安心して運営をスタートするためにも、慎重な準備が欠かせません。
「TOUCH TO GO」のプロダクトは、冷凍自販機を設置するように、工事不要でコンビニ区画を導入できます。
店舗の省人化・人件費削減をご検討中の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/
冷凍自販機を設置するまでの流れ
冷凍自販機の設置までの流れは以下のとおりです。
1.自販機販売業者へ問い合わせ
冷凍自販機を導入する際は、販売業者にメールもしくは電話で問い合わせます。問い合わせ時には以下の点を伝えるとスムーズです。
- 取り扱いたい商品の種類(冷凍食品、弁当、スイーツなど)
- 予算
- 希望する機能(温度管理、省エネ機能など)
2.販売業者と打ち合わせ
販売業者との打ち合わせで、具体的な機種や仕様について確認します。また、冷凍自販機設置後の事業展開や、運用管理についてもすり合わせます。
場合によっては、運用開始前に販売商品の確認や搬入のテストが実施されることもあります。
3.注文手続き
導入する自販機が決まったら、正式に注文します。購入の場合は代金の支払い手続き、リースやレンタルの場合は契約手続きが必要です。
契約書の内容について、以下の点を確認しておきましょう。
- 自販機本体の価格またはリース・レンタル料
- 設置や配送の費用
- アフターサポートの有無や保証内容
- 納期
契約後、業者側で自販機の準備(製品の手配や設定)が開始されます。なお、補助金を利用する際は、採択通知書の到着後の注文となります。
4.設置場所と設置日程を決定
設置場所の詳細や日程を業者と最終確認します。この段階で確認するポイントは、次のとおりです。
- 電源の確保
- 設置スペースの広さ
- 必要な工事
- 自治体の許可の有無
なお、設置日程は、搬入作業の都合や周辺環境への配慮も踏まえて設定します。
5.搬入・設置・運用開始
設定したスケジュールに、契約者立会のもと業者による自販機の搬入・設置が実施されます。設置後の確認項目は以下のとおりです。
- 自販機が適切に稼働するか
- 商品に適した温度設定になっているか
- 機能の操作方法
- 商品の陳列や在庫の補充方法
設置後すぐに運用できるよう、操作方法や運用管理の手順について業者から説明を受けます。
運用開始後は、商品の売れ行きや稼働状況を確認しながら必要に応じて微調整します。
冷凍自販機導入後の運営管理について
冷凍自販機を導入した後は、適切な運営管理が必要です。ここでは、冷凍自販機の運営管理における重要なポイントを説明します。
商品管理
冷凍自販機の運営において、商品管理は基盤となる重要な作業です。次の3点をおさえておきましょう。
【在庫管理】
自販機内の商品の在庫を常に把握し、不足があれば補充します。また、過剰在庫にならないように適切なバランスを保つことも大切です。
【発注管理】
売れ筋商品や季節に応じた商品の需要を予測して、適切に発注します。販売データをもとに分析することで精度が向上します。
【品質管理】
商品の温度や保存状況を定期的に確認し、食品の劣化や異常を防ぎます。温度管理が行き届いてない場合、商品の品質低下や衛生面でのリスクが高まるため注意が必要です。
売上管理
売上管理は、利益向上のために欠かせない作業です。管理すべき具体的なポイントは次の2点です。
【売上データの分析】
自販機が記録する売上データを分析し、売れる時間帯や人気商品の傾向を把握します。
【販売戦略の立案】
分析結果をもとに、キャンペーンや商品ラインナップを見直します。季節限定商品の取り扱いや新規プロモーションを実施するなど、さらなる売上アップを目指しましょう。
メンテナンス
メンテナンスは、機器の長期的な運用と故障防止に直結します。気をつけたいポイントは、次のとおりです。
【清掃】
自販機の庫内や外側を定期的に清掃し、衛生管理を徹底します。とくに利用者が触れる部分は汚れやすいため、定期的に拭き掃除するなど、清潔な状態をキープしましょう。
【点検】
冷却装置や電源系統、制御システムの点検を定期的に実施します。定期的に点検することで、突然の故障や停止を未然に防ぎます。
【故障対応】
故障が発生した場合に備えて、迅速に対応できる体制を整えます。定期契約を結んでいる業者がいる場合は、スムーズに連携できる関係性の構築も大切です。
セキュリティ対策
セキュリティ対策を万全にして、トラブルを未然に防ぐことも大切です。ここでのポイントは、以下の2点です。
【盗難防止】
防犯カメラの設置・注意喚起のためのポスターの掲示などにより、盗難や破壊行為を防ぎます。
【不正利用対策】
支払い機能の安全性を確保するため、定期的にセンサーや支払いシステムの点検を実施します。
また、古い決済システムのままではセキュリティリスクが高まりやすいため、常に最新の状態にしておきましょう。
冷凍自販機の設置後によくあるトラブルと対策
冷凍自販機は無人で運営できる利便性の高い販売手段ですが、設置後に予想外のトラブルが起こることもあります。
ここでは、冷凍自販機の設置後によくある4つのトラブルと、その対策を紹介します。
霜がつきすぎて扉が開かなくなる
冷凍自販機は内部の温度管理が重要ですが、外気との温度差や湿度の影響で、扉周辺に霜が発生することもあります。
霜が多くなると、ドアの開閉に支障をきたすだけでなく、商品が取り出せなくなるケースもあります。
対策としては、「霜取り機能を備えた機種」を選ぶことや、庫内の温度・湿度の設定を定期的に見直すことが有効です。
売れ筋商品だけが集中して売り切れになる
特定の商品に人気が集中しすぎると、すぐに売り切れてしまうことがあります。他の商品が残っていても、利用者にとっては「買いたいものがない」状態になり、自販機としての役割を果たしにくくなります。
このような場合は、売れ行きデータをもとに商品のラインナップを見直すことが大切です。類似の人気商品を複数用意したり、需要の波に合わせた数量調整を行ったりすることで、バランスのよい販売が可能になります。
補充が間に合わずクレームにつながる
販売好調な反面、補充が追いつかないと「買えなかった」という不満が生まれ、ブランドイメージの低下にもつながります。とくに、週末や長期休暇中などの繁忙期は、補充体制の見直しが必要です。
あらかじめ売上の傾向を分析し、補充スケジュールを曜日や時間帯で最適化しておくことが効果的です。また、繁忙期には補充回数を増やす、在庫数を増やすなどの柔軟な対応も検討しましょう。
設置後の立地が期待外れだった
設置前は人通りが多いと判断しても、実際に運用を始めてみると「想定より利用者が少ない」というケースもあります。
たとえば、昼間は賑わっていても夜間は閑散とする場所では、24時間営業の冷凍自販機の強みを活かしきれません。
事前に、時間帯ごとの通行量や周辺環境の変化を調査しておくことが重要です。仮設置や短期間のテスト運用を行い、実際の売上データや人の流れを確認することで、失敗のリスクを抑えられます。
中古の冷凍自販機を購入するメリット・デメリット
冷凍自販機には、中古で販売されている製品もあります。ここでは、中古冷凍自販機を購入するメリットとデメリットについて詳しく紹介します。
メリット
中古の冷凍自販機を購入するメリットは、次の2つです。
【購入費用が安い】
中古品は新品よりも価格が安く、初期コストをおさえられます。
とくに初めての自販機ビジネスや試験的な運用の場合、中古冷凍自販機を購入することで、「低コストで事業を開始できる」というメリットがあります。
【すぐに導入できる】
新品の場合は納品までに時間がかかることがありますが、中古冷凍自販機は在庫があればすぐに購入・設置が可能です。
その理由は、中古冷凍自販機はすでに市場に出回っているため、在庫があれば短期間で入手できるからです。
計画から設置までのリードタイムが大幅に短縮されることは、中古冷凍自販機の大きなメリットの1つといえます。
デメリット
中古の冷凍自販機を購入するデメリットは、以下の3点です。
【故障のリスクが高い】
中古の冷凍自販機は、過去に使用されていた機械のため、内部部品の劣化が進んでいる可能性があります。
導入後に予期せぬ故障が発生し、修理費用や運用停止の影響を受けるリスクが高くなります。
【保証がない場合が多い】
中古の冷凍自販機は、保証が付いていない、もしくは保証期間が短いケースも少なくありません。
購入後に故障や不具合が発生した場合の修理費は自己負担となり、突発的な費用がかかる可能性があります。
【機能が限定される】
中古の冷凍自販機は販売から数年が経過しているため、最新の機能や技術が搭載されていないことがあります。
たとえば、最近の冷凍自販機には、遠隔で在庫や故障を管理できるシステムがありますが、古い機種にはこのような機能が備わっていないことも少なくありません。
そのため、商品の管理やメンテナンスを手動でおこなう必要があり、運営効率の低下が考えられます。
中古冷凍自販機を選ぶ際のチェックポイント
次に、中古冷凍自販機を購入する際に押さえておきたいポイントを解説します。
製造年式
製造年式が古い冷凍自販機は、部品の劣化や動作不良のリスクが高くなります。
また、最新の機能が搭載されていない場合も多く、運用効率に影響を及ぼす可能性があります。購入前に製造年式を確認し、導入後の運用に支障がないか検討しましょう。
使用時間
使用時間が長い中古冷凍自販機は、冷却システムやモーターなどが消耗している可能性があります。
部品の劣化が進行している場合、冷却性能の低下や予期せぬ故障が発生しやすくなります。購入前に、冷却性能や内部機能が正常に動作するか業者に確認しておきましょう。
外観や動作確認
自販機を稼働させたら、以下の点を確認しましょう。
- 冷却機能:商品が適切に冷却されているか
- ボタンや画面の反応:操作はスムーズか
- 外観の状態:傷や腐食が目立つ部分がないか
とくに外観の損傷が大きい場合は、耐久性や見た目の印象が損なわれる可能性があります。実際の運用環境にふさわしいかどうかを判断しましょう。
まとめ
冷凍自販機は「24時間無人で稼働できる便利な販売ツール」として、飲食店の拡販・イベント会場での活用・空きスペースの有効活用など、さまざまなシーンで採用されています。
導入時には、本体価格やランニングコストを十分に理解したうえで、設置スペースや取り扱う商品の特性に適した機種を選ぶことが大切です。
冷凍自販機のメリットとデメリットを正しく理解し、効率的な運用を目指しましょう。
関連記事▼
「TOUCH TO GO」のプロダクトは、冷凍自販機を設置するように、工事不要でコンビニ区画を導入できます。
店舗の省人化・人件費削減をご検討中の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TOUCH TO GO の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download4/