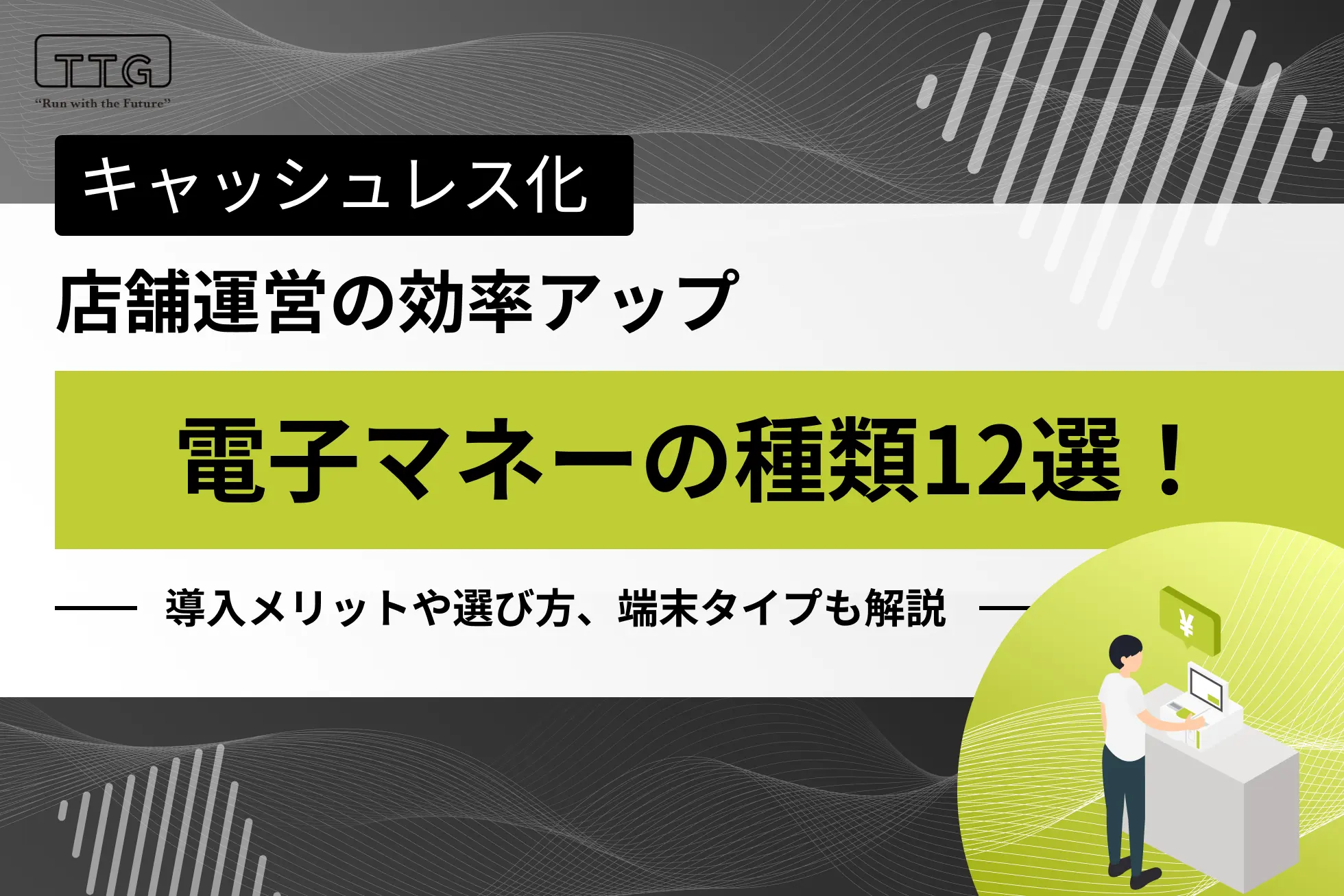Category
こんにちは。無人決済店舗システムを提供しているTOUCH TO GO 編集部です。
キャッシュレス化が急速に進む中、店舗運営において電子マネー決済の導入は欠かせない時代になっています。
現金払いだけでは取りこぼしてしまう顧客も多く、利便性を求める利用者に対応できなければ、競合に遅れをとる可能性もあります。
しかし「電子マネーにはどんな種類があるのか」「自店舗にはどれを導入すべきか」と悩むオーナーの方も多いのではないでしょうか。
本記事では、電子マネーの基本的な仕組みや支払い方式、代表的な種類12選を紹介します。
導入のメリット・デメリット、端末の種類や選び方、導入の流れも解説しているので、ぜひ参考にしてください。
関連記事▼
- キャッシュレス決済とは?種類や仕組み、人気ランキングも紹介
- 【店舗・顧客別】キャッシュレス決済のメリット|導入成功のポイントも解説
- 無人店舗のキャッシュレス決済とは?必要とされる理由や種類と仕組みについて解説
監修者プロフィール

2019年に株式会社TOUCH TO GOを設立。無人決済店舗システムを提供し、次世代型小売の拡大に取り組んでいる。
目次
電子マネーとは
電子マネーとは、現金を使わずにICカードやスマートフォンなどを介して支払いができる決済手段のことです。
利用者は事前にチャージを行ったり、クレジットカードや銀行口座と連携したりすることで、スムーズに買い物ができます。
小銭のやり取りが不要になり、スピーディーかつ簡単に決済できるため、消費者にとってはもちろん、店舗側にとっても業務効率化や売上向上につながる点が大きな魅力です。
電子マネーの仕組み
電子マネーは、利用者が持つICカードやスマートフォンに「支払い用の電子データ」を記録し、決済時に専用端末と通信して支払いを完了する仕組みです。
現金の受け渡しを省けるため、会計時間の短縮や釣銭ミス防止に役立ちます。電子マネーの方式は大きく以下の3つに分けられます。
【プリペイド型(前払い型)】
あらかじめチャージして使う方式。チャージ分しか利用できないため使いすぎを防げます。代表的なサービスにはSuica、nanaco、WAON、楽天Edyなどがあります。
【ポストペイ型(後払い型)】
クレジットカードと連携して利用し、後からまとめて精算する方式。チャージ不要で利便性が高いのが特徴で、iDやQUICPayが代表的です。
【デビット型(即時払い型)】
利用と同時に銀行口座から即時に引き落とされる方式。口座残高の範囲内でのみ使えるため、家計管理がしやすい点が特徴です。
クレジットカードとの違い
電子マネーとクレジットカードはどちらもキャッシュレス決済ですが、その利用シーンや仕組みには明確な違いがあります。特に店舗運営においては、どちらを導入するかによって会計スピードや客層の取り込みに差が出るため、特徴を理解しておくことが大切です。
以下の表に、電子マネーとクレジットカードの主な違いをまとめました。
| 比較項目 | クレジットカード | 電子マネー |
| 決済スピード | サインや暗証番号が必要な場合あり | 端末にタッチするだけで即時決済 |
| 利用金額の傾向 | 高額決済が中心 | 少額決済が中心 |
| 主な利用層 | 信用力のある成人層 | 若年層・訪日観光客を含む幅広い層 |
このように、電子マネーは「スピーディー」「少額決済に強い」「幅広い層に支持されやすい」という特徴があります。
特にコンビニや飲食店、ドラッグストアのように日常的な買い物が中心となる店舗では、導入することで顧客の利便性を高め、リピーター獲得や集客力向上につながるでしょう。
関連記事>>【完全ガイド】クレジットカード決済の導入方法|おすすめサービスや費用、流れまで解説

TOUCH TO GO の セルフ/セミセルフレジ『TTG-MONSTAR』なら、会計のスピード化によりレジ対応の人員を減らし、人件費削減を実現できます。
電子マネー決済が可能なセルフ/セミセルフレジの導入をご検討中の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TTG-MONSTAR の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download1/
電子マネーの支払い方式
電子マネーは、大きく「プリペイド型」「ポストペイ型」「デビット型」の3種類に分けられます。方式によって利用者の使い方や導入効果が異なるため、店舗側はそれぞれの特徴を理解しておくことが大切です。
ここでは、電子マネーの支払い方式ごとの仕組みと代表的なサービスを紹介します。
プリペイド型(先払い)
プリペイド型は、あらかじめチャージ(入金)してから利用する方式です。代表例にはSuicaやPASMOなどの交通系電子マネー、nanacoやWAONなどの流通系電子マネーがあります。
利用者は残高の範囲内でしか使えないため、使いすぎを防ぎやすいのが特徴です。一方、店舗側にとっては「未回収のリスクがない」という大きなメリットがあります。特にコンビニやドラッグストアのように少額決済が多い店舗では、決済スピードの速さとあわせてレジ回転率の向上につながります。
ポストペイ型(後払い)
ポストペイ型は、クレジットカードと紐づけて利用する後払い方式です。代表的なサービスにはiDやQUICPayがあります。事前にチャージする必要がないため、スムーズに決済できる点が利用者にとって大きな魅力です。
店舗側にとっては、残高不足による販売機会の損失を防げるため、高単価商品を扱う飲食店やアパレル、家電量販店では導入効果が特に大きいといえます。
デビット型(即時払い)
デビット型は、利用時に即座に銀行口座から引き落とされる方式です。代表的なものには銀行系のデビットカードと連携した電子マネーがあります。
利用者は口座残高の範囲内でしか利用できないため、使いすぎを防ぎたい層から支持されやすいのが特徴です。店舗にとっても支払いが即時に確定するため安心感があり、日常的に使いやすい決済手段として幅広い顧客層への対応に役立ちます。
電子マネーの種類12選
電子マネーと一口にいっても、その種類はさまざまで、利用者の生活スタイルや年代、地域によって選ばれるサービスが異なります。
店舗側にとって重要なのは、単に種類を知ることではなく「自店の顧客がどの電子マネーを日常的に使っているか」を理解することです。
ここでは、代表的な以下の電子マネー12種類の特徴と導入のポイントを解説します。
| サービス名 | 特徴 | 店舗導入のポイント |
| Suica | 首都圏を中心に利用者数が非常に多い | 幅広い顧客に使われており、導入で利便性を高めやすい |
| PASMO | 首都圏の私鉄・バスで利用される | 通勤・通学客の多いエリアでは利用頻度が高い |
| PiTaPa | 関西圏中心のポストペイ型 | 関西のビジネスパーソンを取り込みやすい |
| ICOCA | JR西日本エリアで利用される | 関西・中国地方や観光利用者に対応しやすい |
| nanaco | セブン&アイグループが展開 | 食品や日用品を扱う店舗で活用しやすい |
| WAON | イオングループが展開 | ファミリー層や郊外型店舗での利用が多い |
| 楽天Edy | 楽天ポイントと連携可能 | 若年層やネット利用者を取り込みやすい |
| iD | ドコモが提供するポストペイ型 | 高単価商品を扱う店舗やキャッシュレス志向層に対応できる |
| QUICPay | JCBが展開するポストペイ型 | 決済スピードを重視する小売や飲食店で役立ちやすい |
| PayPay | 国内で利用者数が多い | キャンペーンによる集客効果を期待できる |
| d払い | ドコモユーザーに強い | キャリア決済を利用する顧客層に適している |
| 楽天ペイ | 楽天カードや市場と連携 | 楽天経済圏の顧客にアプローチしやすい |
各電子マネーの種類や特徴について詳しくみていきましょう。
交通系電子マネー4選
交通系電子マネーは全国の公共交通機関で利用されており、日常生活に深く浸透しています。特にコンビニや飲食店などの少額決済で使われるケースが多く、幅広い顧客層に対応するためにも導入を検討しておきたい電子マネーです。
主な交通系電子マネーのサービスと特徴は次のとおりです。
Suica(スイカ)
Suica(スイカ)は、JR東日本が展開する交通系電子マネーで、首都圏を中心に圧倒的な普及率を誇ります。全国の交通系ICカードとの相互利用が可能で、日常の買い物から交通まで幅広く活用できるのが特徴です。
また、モバイルSuicaによるスマホ決済や定期券との一体利用、JRE POINTとの連携など、利便性を高める独自の機能も充実しています。
PASMO(パスモ)
PASMOは首都圏の私鉄やバスで広く使われている交通系電子マネーで、Suicaとの相互利用にも対応しています。そのため、首都圏の店舗においてはSuicaに加え、PASMOにも対応することが顧客利便性の面で望ましいといえるでしょう。通勤・通学客が多いエリアでは、日常的な利用に対応できる点が特に重要な要素になります。
PiTaPa(ピタパ)
PiTaPa(ピタパ)は、関西圏を中心に利用されている交通系電子マネーで、特徴的なのはポストペイ型(後払い方式)を採用している点です。利用者は事前にチャージする必要がなく、提携した銀行口座から利用額がまとめて引き落とされます。
そのため、日常的な移動や買い物の中でスムーズに利用でき、特に通勤や通学で交通機関を使う人にとって利便性の高い決済手段です。関西エリアでは、大阪・京都・神戸を中心にビジネスパーソンや学生の利用が多く、交通だけでなく加盟店での買い物にも幅広く使われています。
ICOCA(イコカ)
ICOCAはJR西日本が発行する代表的な交通系電子マネーで、関西・中国・北陸エリアを中心に利用されています。全国の交通系ICカードと相互利用が可能で、SuicaやPASMOを利用する関東の旅行者にとっても便利に使える仕組みです。
地域密着型の小売店や観光施設では、交通利便性と買い物を一体的に提供できるため、導入によって顧客の利便性を高めやすいのが特徴です。特に訪日観光客の増加を背景に、インバウンド対応策としても有効な選択肢といえるでしょう。
流通系電子マネー3選
大手流通グループが提供する電子マネーは、系列店舗との連携を活かして設計されており、スーパーやコンビニ、日用品店、ショッピングモールとの相性が良いのが特徴です。
ポイントプログラムとの統合も進んでおり、リピーター獲得にも効果的です。以下に代表的な3つの流通系電子マネーをまとめました。
nanaco(ナナコ)
nanacoは、セブン&アイ・ホールディングスが提供する代表的なプリペイド型電子マネーです。セブンイレブンやイトーヨーカドーなど系列店舗で広く使われており、導入初期から会員数や利用頻度が高く、全国規模で根強い普及を誇ります。
食品スーパーや日用品店といった業態とは特に相性が良く、ポイント還元もあるためリピーター育成にも効果的です。ブランド力が高く、顧客の信頼を集めやすいのも特徴です。
WAON(ワオン)
WAONはイオングループが提供するプリペイド型の電子マネーで、イオン系列のスーパーやモールを中心に広く導入されています。特に家族での買い物が多いファミリー層との相性が良く、郊外型店舗では出店当初からの導入効果も高いと考えられます。
さらに、WAONポイントやイオンカードとの連携により、ポイント還元を通じた顧客のリピーター化にも役立ちます。
楽天Edy
楽天Edyは楽天が提供するプリペイド型電子マネーで、楽天ポイントとの相互交換が可能な点が大きな特徴です。楽天市場や楽天カードとの連携により、ネット利用に慣れた層にとって使いやすい決済ツールとなっています。
若年層にも一定の人気があり、楽天関連サービスとの親和性の高さから、ポイントを通じたリピーター獲得にも役立つ仕組みです。
クレジットカード系電子マネー2選
クレジットカードをベースにした電子マネーは、チャージの手間なしで高い利便性を提供する点が最大の強みです。特に高単価商品を扱う店舗やキャッシュレス志向の顧客へ対応したい場合は、導入の価値が高いと言えます。
代表的なクレジット系電子マネーは、以下の2つです。
iD(アイディ)
iDはNTTドコモが提供する非接触決済サービスで、もともとポストペイ型(後払い)としてスタートしましたが、現在はプリペイド型やデビット型にも対応しています。スマートフォンや対応カードをかざすだけで支払いができ、全国の幅広い店舗で利用できるため、さまざまな業態で導入効果が期待できます。
QUICPay(クイックペイ)
QUICPayは、JCBが開発したポストペイ型の非接触決済サービスです。最大の特徴は「タッチするだけでサインや暗証番号が不要」というシンプルさとスピード感にあり、スムーズなレジ対応を可能にします。
また、後払い方式のため事前チャージが不要で、クレジットカードや銀行口座と連携してすぐに利用できる利便性も魅力です。さらに、Apple PayやGoogle Payといったスマホ決済サービスにも対応しており、利用者の幅広いニーズに応えられる点が他の電子マネーにはない強みといえます。
QRコード決済系電子マネー3選
スマートフォンアプリを利用するQRコード決済は、キャンペーンやポイント還元で若年層を中心に人気が広がっています。小規模店舗からチェーン店まで幅広い業態で導入されており、集客施策としても有効です。代表的なQRコード決済系電子マネーは、以下の3つです。
PayPay(ペイペイ)
PayPayは、日本で最も広く使われているQRコード決済ブランドの一つで、2025年には登録ユーザーが7,000万人を突破しました。全国の多様な店舗で導入が進んでおり、小規模店舗から大手チェーンまで幅広い業態で活用されています。
さらに、インパクトのあるキャンペーン展開で話題を集め、新規顧客の獲得や来店促進にも効果を発揮しています。
d払い
d払いはNTTドコモが提供するQRコード決済サービスで、ドコモユーザーを中心に広く利用が進んでいます。支払い方法として「電話料金合算払い(キャリア決済)」が利用できるため、月々の携帯料金と支払いを一括管理できる点も強みです。
さらに、dポイント還元プログラムやdカードとの連携によって、効率的にポイントを貯められる点が利用の後押しになっています。
楽天ペイ
楽天ペイは、楽天市場や楽天カードと連携して支払いやポイント獲得が可能な、楽天グループのQRコード決済です。
楽天IDがあればスマホ一つでオンライン・実店舗ともにスムーズな決済体験ができるため、楽天経済圏に親しんでいるユーザー層との関連性が強く、導入による集客効果が期待できます。
関連記事▼
電子マネーを導入するメリット
電子マネーを導入することで、店舗運営にさまざまな効果が期待できます。ここでは代表的な4つのメリットを紹介します。
レジ業務の効率化
電子マネー決済は端末にタッチするだけで支払いが完了するため、現金の受け渡しや釣銭計算が不要になり、会計スピードが向上します。その結果、待ち時間の短縮や混雑時の対応力強化につながります。
さらに、釣銭準備やレジ締めなどの現金管理の作業も減り、スタッフの業務負担やヒューマンエラーの削減にも効果的です。キャッシュレス比率が一定以上に高まることで、こうした効率化のメリットをより強く実感できるようになります。
未回収リスクの低減
電子マネーは支払いが即時に確定するため、売上が未回収になるリスクを防ぐことができます。特にプリペイド型の電子マネーであれば利用者が事前にチャージしているため、確実に入金が担保される点が安心材料になります。
さらに、会計データが電子化されることで売上管理が自動化され、資金管理が安定し、事業計画にも柔軟に対応しやすくなります。
集客力アップ
電子マネーを導入すると店舗の利便性が高まり、結果として集客力の強化につながります。現代の消費者は支払い手段の多様性を重視しており、現金以外の決済方法が用意されているかどうかで来店先を決めることも少なくありません。
特に交通系ICカードや流通系電子マネーなど、日常的に使われる決済に対応していれば「ついで買い」や立ち寄り需要の獲得に効果的です。さらに、各電子マネーのキャンペーンやポイント還元も、来店の動機を強めるきっかけとなります。
電子マネーはセルフレジやセミセルフレジとの相性も抜群です。詳しくは、以下の関連記事をご覧ください。
関連記事▼
電子マネーを導入するデメリット
一方で、電子マネーの導入には注意点もあります。デメリットとなる部分を事前に把握しておくことで、導入後のトラブルを防ぐことができます。
初期費用や手数料がかかる
電子マネー決済を導入する際には、専用の端末やシステムを準備する必要があり、その分初期費用がかかります。
さらに、利用ごとに決済手数料も発生します。現金決済に比べるとコストの負担は大きくなるため、売上規模や客単価に合わせて、費用対効果をしっかりと検討することが重要です。
関連記事▼
- キャッシュレス決済の手数料とは?決済方法別の手数料相場・安く抑える方法を徹底解説!
- セルフレジ導入価格を徹底解説|具体例や初期費用のおさえ方も紹介
- セミセルフレジの価格相場と費用の内訳|導入コストのおさえ方も解説!
入金までにタイムラグがある
電子マネー決済では、売上金がすぐに入金されるわけではありません。決済事業者を経由するため、数日から数週間といった一定のサイクルで振り込まれるのが一般的です。
入金までのタイムラグは、仕入れ代金や人件費などの支払いに直結するため、資金繰りに影響を及ぼす可能性があります。とくに運転資金に余裕のない小規模店舗では、「売上があるのに資金が手元にない」という状況に陥りやすく注意が必要です。
ネット環境に依存する
電子マネーはオンライン通信を前提とした仕組みであるため、ネットワークが不安定な環境や停電・災害時には利用できない場合があります。とくに大規模災害の際には、通信インフラそのものが停止することもあり、決済手段としての電子マネーが一時的に機能しなくなるリスクは無視できません。
このような状況では、支払いができずに販売機会を逃す可能性や、店舗側で混乱が生じるリスクが生じます。そのため、電子決済の利便性を活かしつつも、緊急時には現金で対応できる環境を残しておくことが大切です。
TOUCH TO GO の セルフ/セミセルフレジ『TTG-MONSTAR』なら、会計のスピード化によりレジ対応の人員を減らし、人件費削減を実現できます。
電子マネー決済が可能なセルフ/セミセルフレジの導入をご検討中の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TTG-MONSTAR の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download1/
電子マネー決済端末の種類3つ
電子マネーを導入する際には、店舗の規模や業態に合わせて決済端末を選ぶ必要があります。端末の種類によってコストや利便性が異なるため、自店のオペレーションに最も合うものを検討しましょう。
ここでは、電子マネー決済端末の種類を3つ紹介します。
据え置きタイプ
据え置きタイプは、カウンターやレジ横に設置して使う固定型の決済端末です。安定した通信環境で操作もしやすく、決済スピードが速いのが特徴です。そのため、スーパーマーケットや飲食店など、来客数が多くレジ対応に追われる店舗で広く導入されています。
一方で、設置場所が固定されるため、移動販売やイベント出店など「持ち運びが必要なシーン」には適していません。
モバイルタイプ
モバイルタイプは、タブレットやスマートフォンと接続して使う小型端末です。持ち運びができるため、キッチンカーやイベント出店、訪問販売など移動を伴う事業に適しています。
比較的導入コストも低く抑えられるため、初めて電子マネー決済を導入する小規模店舗にも導入しやすい端末です。ただし、バッテリーや通信環境に依存するため、長時間利用する場合は運用面で注意が必要です。
関連記事▼
マルチタイプ
マルチタイプは、電子マネーだけでなくクレジットカードやQRコード決済など、複数の決済手段に対応できる端末です。幅広い顧客層に対応できるため、ショッピングモール内の店舗や観光地の飲食店など、多様な顧客が訪れる業態に向いています。
将来的にキャッシュレス決済の利用率がさらに高まることを考えると、長期的な投資として有効な選択肢といえますが、導入費用や月額コストは他の端末より高めになる傾向があります。
関連記事▼
- キャッシュレス端末とは?種類別の特徴・導入費用・補助金まで徹底解説
- POSシステム(POSレジ)とは?機能や種類、費用・補助金制度も紹介
- おすすめのPOSレジ15選!対応できる業種別に各製品のおすすめポイントを徹底解説
電子マネーを選ぶ際のポイント
店舗が電子マネーを導入する際は、数ある種類の中から自店に合ったものを選ぶことが重要です。計画性なく導入すると、本来の効果が十分に発揮されない可能性が高まります。
そこで、電子マネーの導入を検討する際は、次のポイントを抑えておきましょう。
- 利用者のニーズに合っているか
- 導入コストや手数料はいくらか
- ポイント還元やキャンペーンが充実しているか
- スマホ決済やオートチャージに対応しているか
電子マネーの導入には、端末費用や決済手数料といったランニングコストが発生します。そのため、売上規模や取扱商品に対してコスト負担が適切かどうかの見極めが欠かせません。複数の事業者の料金体系を比較し、自店にとって費用対効果の高い方法を選ぶことが成功につながります。
電子マネー導入方法
電子マネーを導入する際には、契約方法から端末準備、初期設定までいくつかのステップがあります。ここでは代表的な流れを解説します。
契約方法の選択
電子マネーの導入は「決済代行サービスを利用する」か「決済事業者と直接契約する」かの2つの方法があります。
代行サービスを利用すれば、複数の電子マネーやクレジットカード決済を一括で導入でき、手続きや管理がシンプルになります。
一方で直接契約の場合は、個別の条件交渉や費用調整ができる反面、事務手続きが煩雑になることがあります。自店の規模やリソースを踏まえて、どちらが効率的かを判断することが大切です。
必要な端末やシステムの準備
契約が決まったら、電子マネー決済に対応できる端末やPOSレジの準備を行います。据え置き型・モバイル型・マルチ対応型などの端末の中から、自店の業態に合ったものを選びましょう。
また、「既存のPOSレジと連動させるか」や、「独立した決済端末を利用するか」も検討ポイントになります。端末やシステムの選択が業務効率に直結するため、慎重に比較検討することが大切です。
初期設定と運用開始
端末が導入されたら、電子マネーの初期設定を行います。導入直後はトラブルが起こりやすいため、スタッフ全員が操作に慣れるまでサポート体制を整えておくと安心です。
運用が軌道に乗れば、顧客にとっても利便性の高い決済環境となり、店舗全体のサービス品質向上につながります。
まとめ
電子マネーは、交通系・流通系・クレジットカード系・QRコード系と多様な種類があり、利用者の生活スタイルや世代によって選ばれる手段が変わります。
店舗にとっては単に決済手段を増やすだけでなく、顧客層に合った電子マネーを導入することで利便性を高め、集客や売上アップにつなげられることが大きなポイントです。
キャッシュレス化が進む今、電子マネー決済に対応することは競合との差別化や顧客満足度向上にも直結します。自店に合わせたキャッシュレス環境を整備し、より多くの顧客に選ばれる店舗づくりを進めていきましょう。
関連記事▼
TOUCH TO GO の セルフ/セミセルフレジ『TTG-MONSTAR』なら、会計のスピード化によりレジ対応の人員を減らし、人件費削減を実現できます。
電子マネー決済が可能なセルフ/セミセルフレジの導入をご検討中の方は、以下のリンクよりプロダクト概要資料をご確認ください。
▼【無料】TTG-MONSTAR の概要資料をダウンロード
https://ttg.co.jp/download/download1/